ハイブリッドワークとは?
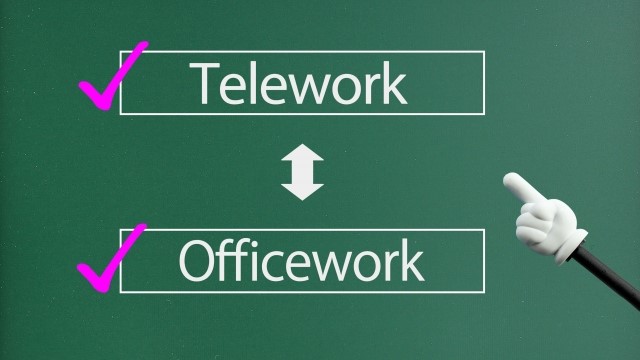
ハイブリッドワークとは、テレワークとオフィスワークを組み合わせる勤務スタイルです。たとえば、週に2日間はオフィスに出社し、残りの3日間は在宅といった働き方を指します。テレワークと比べて本質的に何が違うのか、また、なぜここまで浸透してきたのかなど、基本知識としてまずはおさえておきましょう。
テレワークとの本質的な違い
自宅やコワーキングスペース、サテライトオフィスなど自社オフィス以外の場所での勤務が含まれます。
◆ハイブリッドワーク・・・テレワークと固定オフィスでの勤務を柔軟に組み合わせる勤務スタイル。
ある日は自宅で仕事をし、別の日にはオフィスに出勤するなど、日によって勤務地を選択できます。
テレワークは、時間や場所にとらわれず働くリモートワークの一種(あるいは総称)です。もっともポピュラーな例では、在宅勤務が挙げられます。一方、ハイブリッドワークは繰り返しお伝えしているとおりテレワークとオフィスワークを組み合わせた働き方です。企業によって実施状況は異なりますが、従業員が両者を能動的に選択できます。そしてハイブリッドワークの典型的な活用シーンからは、本質的な違いが浮かび上がってきます。集中して作業をしたい時にはテレワーク、コミュニケーションを密に取りたければオフィスに出社といった具合です。当然、業務内容によっては、どちらが適しているかが変わります。したがって、導入するにあたっては、従業員にとっての最適解をどう見極めるかがポイント(企業側が求められること)です。
ハイブリッドワークが浸透してきた背景
ハイブリッドワークが注目され浸透してきた背景には、遡るとやはり新型コロナウイルスの蔓延が挙げられます。それに伴い、(そうせざるを得ない状況下で)リモートワークが急速に広まりました。
実際に取り入れることで多くの企業が気づきを得られたのではないかと思います。業務効率化、生産性向上といったメリットを感じる一方でオフィス勤務の重要性も再確認されたはずです。フルリモートによる弊害も少なからずあったでしょう。そうしたなかでパンデミックが徐々に落ち着きをみせると、オフィスワークとリモートワークを組み合わせたハイブリッドワークが注目されはじめます。先んじて取り入れたGoogleなどの有名企業は、まさにロールモデルとして機能。いまや規模を問わず多くの会社で導入されています。
ハイブリッドワークのメリット

ハイブリッドワークの核心は、従業員の個々のニーズや生活様式にあわせた働き方の多様性にあります。もちろん、従来の勤務スタイルを選択することも可能です。そうやってオフィス内外問わず主体的に動けることでメリットが得られるわけです。以下、いくつか取り上げます。
オフィススペースが活用しやすい
ハイブリッドワークを導入することで、オフィススペースの効率的な利用が可能です。たとえば、オフィスに出社する従業員が減った分、ミーティングルームに空きが出やすくなり、そこを業務に集中できる個別ブースやリフレッシュできる休憩室に使えます。このように、生産的で快適に働ける空間のサポートにつながるはずです。
緊急時も柔軟に対応しやすい
ハイブリッドワークは、オフィスに固執せず自宅で作業できる選択もあるため、災害時や公共交通機関の停止、それこそ新型コロナウイルス感染症拡大のような場合でも、継続して業務を行えます(その逆で自宅に固執する必要もありません)。業務停止のリスクを極力軽減し、企業活動の持続につなげられる点は、やはり大きなメリットです。
従業員のモチベーションが上がりやすい
ハイブリッドワークは、テレワーク派もいればオフィスワーク派もいるなかで両方のニーズを満たします。テレワークの頻度を上げることで通勤時間の短縮やストレスの軽減につながり、オフィスに出向くことで作業環境が安定するといった具合にいわゆる“いいとこ取り”ができるからです。この働き方により、従業員はライフワークバランスの実現が図れます。結果、満足度そしてモチベーションの向上に期待が持てるでしょう。従業員がエネルギッシュに仕事に取り組むことを促せる点は、紛うことなきメリットです。
組織の生産性が上がりやすい
ハイブリッドワークによって柔軟な働き方ができれば、作業効率改善のベストプラクティスが見つかるかもしれません。集中が必要な業務にはリモートワークを、コミュニケーションが欠かせない時にはオフィス勤務を選ぶなどして各々が生産性を最大化できれば、おのずと組織の成果にもつながるでしょう。
タレントプールが広がりやすい
ハイブリッドワークの導入は、優秀な人材を引き寄せるきっかけになり得ます。というのも、働きやすさを求める求職者にとって、環境を選べる点は少なからず魅力的だからです。結果、自由な働き方の訴求によって、採用範囲が広がるものと思われます。そう、いわゆるタレントプールの拡大です。これは、育児や介護など私生活と仕事(における責任)の両立を可能にする働き方のため、離職防止につながる期待も持てます。
ハイブリッドワークのデメリットや課題

ハイブリッドワークは、柔軟な働き方を実現し、従業員のワークライフバランスの向上や企業の人材確保に貢献する一方で、いくつかのデメリットや課題も伴います。以下取り上げるのは、勤怠管理の煩雑化、コミュニケーションの希薄化、人事考課の難易度アップ、セキュリティ面でのリスクについてです。導入後に困惑することのないよう、あらかじめ把握しておきましょう。
勤怠管理が煩雑になりやすい
ハイブリッドワークの導入にあたって、勤怠管理や労務手続きをスムーズに行うことは、多くの企業が直面する課題です。オフィス出社と在宅勤務が混在すれば、従業員の出勤状況や体調などの確認はしづらくなるでしょう。そのため、管理を徹底あるいは工夫していく必要があります。これまでどおりではやはり、給与計算なども煩雑化してくるはずです。
コミュニケーションが希薄になりやすい
勤務スタイルの変化により、従業員同士で対話する機会が減るかもしれません。フルリモートだとなおさらでしょう。チーム内のコミュニケーション不足が発生すれば、それがそのままタスク進捗など業務上で影響を及ぼす可能性があります。
人事考課が難しくなりやすい
ハイブリッドワークにより従業員の働き方が多様化すれば、個々の成果や勤務状況を公平に評価することが難しくなるかもしれません。ただでさえ、勤務状況の可視化しづらい状況下では、勤務態度や貢献度を測りにくくなります。そのため、従業員一人ひとりの業務内容や成果に応じた柔軟な評価基準の設定、見直しが必要です。
▶関連記事:パートに人事考課を導入するメリットやコツ、評価シートの書き方など解説
セキュリティ面でリスクを抱えやすい
ハイブリッドワークを導入する場合は、セキュリティ対策の再考が不可欠です。とりわけ、フリーWi-FiやVPN接続機器は、その脆弱性によって不正アクセスや情報漏洩など大きなトラブルの温床はたまた直接的な要因になり得ます。もちろん、システムの強化は大事ですが、それだけでなく従業員一人ひとりに対するセキュリティ意識の啓発と指導の徹底が重要です。
ハイブリッドワークをうまく機能させるには?

ハイブリッドワークを効果的に機能させるには、いくつかステップを踏む必要があります。まず、基盤となる勤務ポリシーの設計です。そのうえで、セキュリティ教育の実施は欠かせません。また、コミュニケーション促進のために、ビデオ会議システムやプロジェクト管理ツールなどの導入も有効です。加えて、オフィス環境も整備しましょう。出社する従業員が柔軟に働けるように、フリーアドレス制の導入や、コラボレーションスペースの設置などを考えるのも一つの方法です。
以下、これらについてそれぞれ詳述します。
勤務ポリシーの設計
ハイブリッドワークを成功させるためには、従業員がどこで働くかにかかわらず、明確な勤務ポリシーの設計が必要です。具体的な項目としては、勤怠報告やコミュニケーションの手段などが挙げられます。
セキュリティ教育の実施
セキュリティ面でのリスクに対する従業員の意識向上と理解促進のために、セキュリティ教育は定期的に行いましょう。セキュリティ対策の基本から最新の脅威に対する防御方法まで、教育を通じて安全な働き方を実践できるよう支援することが企業側の課題です。
ゼロトラストセキュリティ
セキュリティ教育のなかで重宝されている考え方がゼロトラストセキュリティです。これは、日本語に直訳してもわかるように「何も信用しない」という前提に基づいています。ネットワークの内外は問いません。すべてのユーザー、デバイス、アプリケーションへのアクセスを厳密に検証していくものです。リモートワークやクラウドサービスの利用増加に伴い、その重要性は如実に高まっているのがわかります。このアプローチにより、サイバー攻撃に対する防御が強化され、企業資産の保護が可能です。
便利なコミュニケーションツールの導入
ハイブリッドワークをサポートするコミュニケーションツールには、「Slack」でのリアルタイムメッセージング、「Zoom」によるビデオ会議、「Trello」でのプロジェクト管理などがあります。これらは、チームメンバーが情報を簡単に共有し、物理的な距離に関係なく協力して作業を進めることを可能にします。そのほか、「Microsoft Teams」「Google Workspace」なども便利です。前者はチャット、会議、コラボレーションを一つのプラットフォームで提供でき、後者はドキュメント共有やメール通信の効率化が図れます。
オフィス環境の整備
ハイブリッドワーク導入に際しては、オフィス環境の整備もセットで考えたいところです。働くのに快適な職場でなければ、従業員が出社を選択しなくなるかもしれません。例を2つ挙げます。一つはフリーアドレス制度です。個々の専用デスクを廃止し、その日の作業場所を自由に決められるのは気分を整えるのにも効果的でしょう。ただし、一度に全席をフリーアドレスに変えるのは難しいのも確か。出社率とテレワークのバランスをみながら、段階的に導入することをおすすめします。
そしてもう一つは、コラボレーションスペースの設置です。従業員同士がオフィス内で肩肘張らずに交流を図れるよう、休憩中やちょっとしたミーティング時に利用できる小部屋を用意してみてください。こうした場があれば、懸念されるコミュニケーション不足は生じにくくなるはずです。
ハイブリッドワークの活用事例

ハイブリッドワークは、大手を中心に広く浸透してきています。会社規模問わず今後取り入れていこうと検討されているなら、ぜひ、導入済みの企業を参考にしてみてください。
たとえば、株式会社ぐるなびは、ハイブリッドワークのためにフリースペースを拡張。打ち合わせやイベントに使えるフレシキブルスペースに加えて、集中して作業するのにもってこいの個室ブースなども設置したといいます。
また、NECはビジネス・教育用にパソコン(「Mate&VersaPro」)を開発。自社ならではのユニークなアクションです。
富士通の場合、保有するサテライトオフィスを一部開放し、生体認証をはじめとする社内外テクノロジーの導入を行っています。これは、オフィスでのコラボレーション推進が目的です。対して社内交流を深めようとしたのがベネッセコーポレーションです。コミュニケーション活性化を狙った茶室が設けられています。
なお、ハイブリッドワークを先んじて導入していたGoogleはオフィスへの出勤を業績評価の一部として考慮するなど勤務ポリシーを厳格化。週に3日以上オフィスで過ごすことで、従業員同士のつながりが強固になるといった定性情報も加味しているようです。こうした動きもまた、新たな指針になる予感がします。
結局、ハイブリッドワークは導入した方がよい?
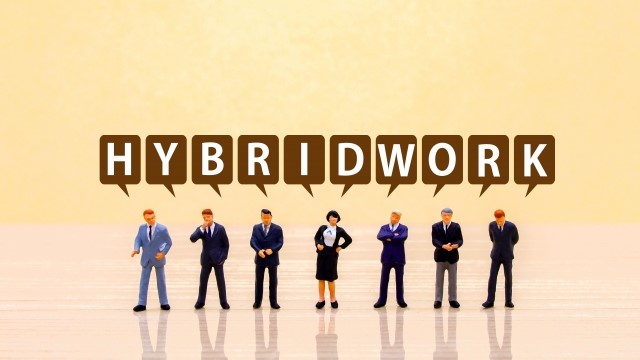
再三述べているとおり、昨今は多くの企業がハイブリッドワークを活用するようになっています。もちろん、その背景には期待できるメリットがあるからでしょう。それらを把握すれば、これまで取り入れてこなかった企業や組織の方々も、前向きに検討するようになるかもしれません。しかし、判断材料として大事なのは、むしろデメリットや課題(対策・対応の可否)です。そこに向き合う前に短絡的に導入してしまうと、トラブルを招く恐れさえあります。セキュリティリスクなどは最たる例です。
したがって、まこの制度の仕組み、そしてネガティブなポイントをしっかり認識するところからはじめましょう。目先のおいしい話に飛びつく前にやれることは意外と少なくありません。たとえば、業務効率化や生産性向上が一つのゴールだとして、そこに向けては、コツコツと地道に採用活動に力を入れ、欲しい人材を獲得していくことの方が、急がば回れで実現しやすいケースもあります(dipのサービスでは、求人掲載後すぐに応募が来るスピード採用が強みです)。状況判断を見誤らないよう、特に人事関連では、適宜然るべきサービスの利用や相談も視野に入れて動くとよいでしょう。
求人掲載・採用業務のサポートや料金についてなど、ぜひ気軽にお問い合わせください。
また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談も無料で承っております!
▶アルバイト・パート採用に強い「バイトル」のサービス資料はこちらからダウンロード(無料)
▶社員採用に強い「バイトルNEXT」(ネクスト)のサービス資料はこちらからダウンロード(無料)

