求人・採用ブログとは?

一口に求人・採用ブログといっても、その種類、目的はさまざまです。まずはそれらについて言及します。
求人・採用ブログの種類
求人・採用ブログの主な種類は次のとおりです。
- 新卒入社に該当する方に向けたブログ
- 中途入社に該当する方に向けたブログ
- 社内の従業員に向けたブログ
以下、それぞれ詳述します。
新卒入社に該当する方に向けたブログ
新卒入社に該当する方に向けたブログは、一般的に、彼・彼女らが入社前に知っておくべきルールやマナーに加え、入社後の研修、各部署の紹介といった情報が中心です。これにより、自社に対する解像度が上がり、入社に対する不安も少しずつ軽減される期待が持てます。つまるところ、右も左もわからないと思われる新卒者をガイドする役割を担います。
中途入社に該当する方に向けたブログ
中途入社に該当する方に向けたブログでは、現在、転職活動中の方はもちろん、そうでなくともビジネスパーソン全般を対象に届けるものです。自社の魅力が伝われば、当面、転職の意思がなくともいずれ縁を生むかもしれません。そうした狙いもどこかでありながら、基本的には自社のことをもっと知ってもらうためのブログです。そのため、事務的なお知らせに終始せず、社内の様子、キャリアパス、ロールモデル、トレンド、ノウハウ……等々を織り交ぜた自社ならではのコンテンツを発信している企業も珍しくありません。
社内の従業員に向けたブログ
社内の従業員に向けたブログでは、情報共有がメインです。自社の取り組み、制度、経営方針の変更……等々をなるべくタイムリーに伝えていきます。また、一人、あるいは一つの部署にフォーカスした特集も社内ブログならではのコンテンツです。いうなれば社内報と捉えてよいでしょう。
とりわけ、全国に拠点がある規模の会社では、距離が離れた従業員同士をつなぐ架け橋としても機能します。そのなかで意見交換も促進できれば、活発なコミュニケーションが取り交わされる企業風土の醸成にもつながります。
求人・採用ブログの主な目的
求人・採用ブログの主な目的は次のとおりです。
- 求職者との接点構築
- 自社の認知度向上
- 自社に対する求職者の関心度向上
- 自社に対する従業員のエンゲージメント向上
以下、それぞれ詳述します。
求職者との接点構築
自社の存在を知らない求職者との接点構築に、求人・採用ブログは一役買ってくれます。そこで興味・関心を持ってもらえたなら、今すぐではなくとも、いずれ(一緒に働く)ご縁が生まれるかもしれません。
自社の認知度向上
求職者との接点が広がれば、その分、自社の認知度も向上します。一つの記事が拡散され、応募数も一気に増えるケースも決して珍しくありません。そのため、認知施策として戦略的に運用する企業も多く見受けられます。
自社に対する求職者の関心度向上
求人・採用ブログによって求職者は企業について、リアルタイムで理解を深めていくことができます。ユニークな取り組みなどが話題に上れば、少なからず関心を寄せる求職者も出てくるでしょう。自社の強みを継続的に伝える意味でも、ブログの更新は効果的です。
自社に対する従業員のエンゲージメント向上
採用ブログは外部の求職者だけでなく、自社の従業員に対しても影響を与えることがあります。たとえばブログ内で従業員の成果やプロジェクトを取り上げれば、(頑張りが認められた実感も伴い)大なり小なりモチベーションにつながるはずです。また、それは決して個人だけに限りません。自組織の取り組みが面白いと外から評価されれば、同じように(むしろそれ以上に)誇りを持つことができるでしょう。
求人・採用ブログの書き方

種類、目的に続いては書き方の基本です。求人・採用ブログに限らず、記事コンテンツを作成し、運用していくには相応の手順があります。
以下、一般的な流れに沿って、求人・採用ブログの書き方について説明します。
求人・採用ブログを書き始めるまで
求人・採用ブログは、思い立ってすぐに書けるものでもありません。まずは、書き始めまでの準備・計画が大事です。具体的には、最適なメディアの選定、運用チームの構築、テーマやカテゴリーの決定、そして公開スケジュールの策定が行われます。というわけで各フェーズについて、それぞれ詳述します。
メディアの選定
まずはメディアの選定です。自社サイトのなかで作成するのもよいですが、外部サービスを利用する方法もあります。どちらにするかは目的、予算などによって答えは変わってくるでしょう。
仮に自社サイト内にブログを設置する場合、掲載内容に制限がないため、独自性を強く打ち出すことができます。が、ノウハウやリソースがないと効果的、継続的な運用は難しいかもしれません。これは外部のブログホスティングサービスでも同様です。無料で立ち上げることもできますが、デザインの自由などがなくなり、また社内リソースが足りなければ、更新も滞ってしまうため思うような運用にならない可能性が高い確率で考えられます。
こうした懸念点を解消するためにも、次ステップの運用責任者、ライターの選定が肝心です。
運用責任者、ライターの選定
前項を踏まえて、ブログを効果的に運営するための責任者を決める必要があります。求人・採用ブログは、広報と人事の役割を兼ね備えたメディアです。したがって、これらを理解し、適切に管理できる人物が求められます。
ライターについては、部署ごとに持ち回りで行うか、特定の担当者で進めるか、選定方針で変わります。前者の場合、部署特有の視点や情報が反映され、多様な内容の提供が可能です。が、質や情報量などムラがあるブログになることも考えられます。一方で後者だと、多様性を重視するなら(一人の担当者が)意識的に視野を広げなければならず、当然、難しいケースも出てくるはずです。一長一短を考慮し、どのように運用していくかは、慎重に決めましょう。
テーマ、カテゴリーの選定
どのテーマやカテゴリーで運用するかも重要です。社内制度や働き方の紹介、新サービスや製品の開発秘話、業界トレンド、スタッフインタビュー……等々、大きなテーマから細かいトピックまでうまく整理し、構造化していくことが求められます。
スケジュールの設定
求人・採用ブログは更新頻度も大事です。なるべく日を空けずに運用するのが理想的ですが、企業によっては通常業務との兼ね合いで困難なことも当然、考えられます。無理はせず、とはいえ極力更新できるスケジュールを模索し、設定しましょう。
求人・採用ブログには何を書く?
書くまでの準備が整ったなら、次に内容を洗い出していきましょう。ここで気を付けたいのは、決して何でもアリというわけではないことです。先に選定したテーマ、カテゴリーに紐づけていく必要があります。その前提のうえ、よくあるコンテンツをここでは紹介します。
社内イベント情報
社内イベント情報の掲出は、内外問わず、関心を引きやすいコンテンツです。準備期間、当日、その後と一連の流れを伝えてあげられると、ストーリー性も加わり、より興味深いものとなるでしょう。
従業員インタビュー
従業員へのインタビューも求人・採用ブログの定番です。入社したきっかけ、具体的な仕事内容、やりがいを感じる瞬間、経験した困難や挑戦、将来の目標……等々によって読者(求職者)は「自身が働く未来」をイメージしてくれるかもしれません。また、従業員自身もあらためて自社を知る機会になるでしょう。
従業員の一日
従業員の一日をタイムテーブル形式で見せるのもよくあるコンテンツの一つです。お仕事だけでなくお昼休憩の時間など何気ない一コマまで切り取れると、従業員のリアルな姿が描写され、記事はよりリアルで魅力的なものになるでしょう。
職場の様子
オフィス環境、設備、朝礼、チームミーティング……等々、職場の様子は定期的にアップデートしながら求人・採用ブログにも落とし込んでいけると望ましいでしょう。ポジティブな印象を与える内容であれば、エンゲージメントアップに、より効果的です。
自社商品・サービス
自社商品やサービスも、定期的に紹介できるとよいでしょう。商品に込められた情熱やこだわり、技術的な詳細まで記載すれば、理解促進にもつながります。専門スキルを持った求職者の方の興味を引くこともできるでしょう。
応募・面接ノウハウ
応募プロセスや面接に関する具体的なアドバイスを提供するのも、一つのコンテンツになり得ます。一般的なものに限らず自社向けの対策法まで明示すれば、独自性も加わるでしょう。何より自社を志望する求職者にとっては、選考通過のヒントになるため非常にありがたい情報です。
業界ノウハウ
特定の業界における専門知識や技能を深掘りする記事も、(対象の読者にとっては特に)価値あるコンテンツです。当然、自社への信頼にもつながります。さらには、それらが拡散されれば、権威性まで帯びるようになり、(内外問わず)エンゲージメントは飛躍的に向上するでしょう。
業務ノウハウ
具体的な業務遂行に役立つ知識や技能に関する情報もまた、業界ノウハウ同様、ニーズに応えた信頼性を高めてくれるコンテンツです。効率的なワークフローの構築、時間管理のテクニック、チーム内コミュニケーションの改善方法……等々、実践的なアドバイスは、現職の従業員だけでなく、求職者の方にもきっと刺さることでしょう。
求人・採用ブログはどのように書く?
書く内容が決まれば、次に考えるべきはどのように伝えるかです。手法や工夫次第で反響は大きく変わるといっても過言ではありません。そしてそれは、決して抜本的でなくてもよく、意識一つでも十分効果は生まれます。
以下、具体的に取り上げます。
写真や動画を使う
テキストだけの説明ではどうしても伝わる情報は限られます。一方で、写真や動画を駆使したコンテンツは、やはりわかりやすく、そしてありがたいものだと考えます。もちろん、テキストだけで表現できる世界観もありますが、ビジュアル訴求も加われば、より魅力的なブログになるはずです。
自社ならではのコンテンツにする
せっかく自社で運用するなら(自社の)色をしっかり出せるブログにしたいものです。多少な制約も出てくるかもしれませんが、従業員の声、自社独自の取り組みや制度、一次情報は積極的に打ち出せることが望ましいと考えます。
引用してもらいやすいデータを載せる
たとえば、前述した一次情報などは、他のメディアや読者に引用してもらいやすいデータの典型です。これは拡散を意味し、ひいては自社ブログの影響力、価値を上げることにもつながります。認知度を高める目的で運用するのであればなおさらです。
内容によっては監修者を付ける
特に専門性が高いテーマや法律、信ぴょう性が求められる内容を扱う場合は、その記事に対し監修者を付けましょう。誤情報の回避はもちろん、自社に対する評判(or信頼性)にも関わるため、非常に重要です。
読者の視点や期待を意識する(自分事化してもらう)
求職者の視点や期待、ニーズをなるべく深く理解し、それに応じた情報を提供することは、求人・採用ブログを書くうえでの基本であり理想です。決して独りよがりにならず、自分事化してもらう意識で取り組みましょう。それでこそ目指すべきコミュニケーションの形です。どういった内容を書くにせよ、常に念頭におけることが望ましいと考えます。
求人・採用ブログを書く際の注意点
求人・採用ブログを書く際は、いくつかある注意点も把握しておきましょう。具体的には次のとおりです。
- テーマ・カテゴリーとは無関係の内容にしない
- 裏付けのない情報を安易に載せない
- 更新を疎かにしない
それぞれ、詳述します。
テーマ・カテゴリーとは無関係の内容にしない
ブログのテーマあるいはカテゴリーのなかで、それとは逸脱した内容を書いてしまうと、読者の混乱を招きかねません。そうなると、自社に対する信頼やブランドイメージにも影響する可能性が出てきます。自社内でも方針がぶれてしまうのは問題です。挙句の果てには求人・採用ブログとして成り立たなくなるでしょう。
裏付けのない情報を安易に載せない
ブログに掲載する情報は、いわずもがな正確でなければなりません。明らかな誤情報はもちろん、裏付けのない(あるいは検証されていない)データを安易に公開するのも危険です。読者に誤解を与え、企業の信用度が下がるだけでなく、最悪、法に抵触する恐れもあります。
更新を疎かにしない
ブログの更新が途絶えてしまうと、閲覧者は徐々に減っていきます。これまで築いてきた読者との良好な関係が、求人・採用活動においてもよい影響を及ぼしていたなら、なおさら勿体ないことでしょう。もちろん、更新頻度を意識しすぎて、質が落ちるのは考えものです。が、事前に決めた更新頻度は極力守れるようにしましょう。または軌道修正するなどして、継続できる運用を図っていくことが大事です。
求人・採用ブログのメリット
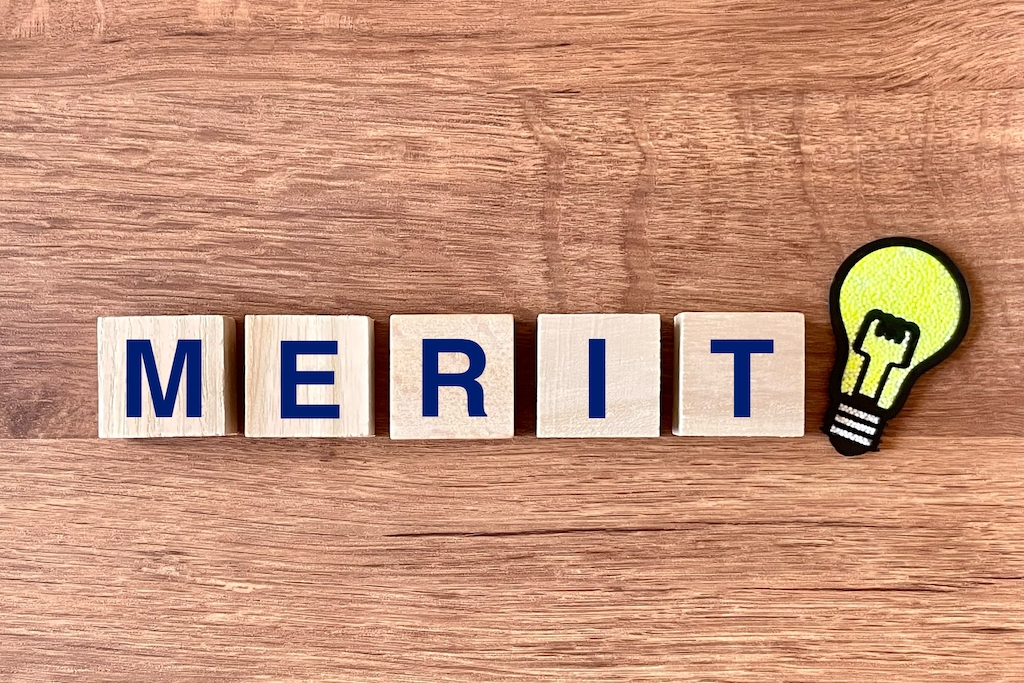
前章からも、求人・採用ブログの運用そして書き方は、思いのほか一筋縄でいかないことがおわかりでしょう。そうはいってもやはり、得られるものや期待できることを考えると、取り組む意義は十分にあります。というわけでは、本章ではそうしたメリットを紹介します。主に次のとおりです。
- 自社情報を広く発信できる
- 母集団形成につながる
- ミスマッチの回避が期待できる
以下、それぞれ詳述します。
自社情報を広く発信できる
その特性上、ブログ記事は文字数やスペースに縛られることなく広い範囲に届けられます。タイムリーな情報も同様です。大事なお知らせを、いち早く多くの方に伝えられることは、ブログの柔軟性があるからこそだと考えます。
母集団形成につながる
求職者にとって役に立つ情報を更新頻度を上げて提供できれば、一定数ファンが付く期待が持てるでしょう。うまくいけば、求人広告の掲載や会社説明会を実施したとき以上に、母集団形成の(費用対)効果が出るかもしれません。
ミスマッチの回避が期待できる
日常の風景としてオフィスのなかを、ブログを介し伝えることで、企業理解を促進できます。そうなるとミスマッチにつながる安易な応募は減っていくでしょう。一方で、不透明ゆえに躊躇っていた向きも減るため(応募するのに背中を押されるため)、結果的に、自社に合った人材が集まる期待が持てます。
採用ブランディングや採用戦略に使える
継続的に自社のあれこれを紹介し、ユニークなコンテンツを発信できていれば、その魅力は、そのまま採用ブランディングや採用戦略として昇華することも可能です。そうやって求める人材にアプローチしやすくなる点は、まさに求人・採用ブログのメリットだといえるでしょう。
求人・採用ブログをうまく活用するコツ

求人・採用ブログについて、書き方、メリットだけでなく、うまく活用するコツまで把握できれば、より効果的な運用につながるはずです。具体的には次の方法が挙げられます。
- 求人情報をあわせて紹介する
- メルマガやSNSでも取り上げる
- 従業員に向けても発信する
- アクセス解析を基に改善を図る
以下、それぞれ詳述します。
求人情報をあわせて紹介する
職場の魅力とセットで求人情報を紹介することで、応募を促進できるかもしれません。あくまでメインコンテンツはそれでなくても、自然な流れで人材募集できれば、気に留めてくれる方は一定数出てくるものと思われます。
メルマガやSNSでも取り上げる
求職者に役立つブログ記事は、メールマガジンやSNSと連携させることで、多くの人にリーチできる期待が高まります。配信頻度も工夫しながら、SNSユーザーと良好な関係を築けたなら、拡散性も相まって、一気に認知度が向上するかもしれません。
従業員に向けても発信する
求人・採用ブログは、意外と自社の従業員にも読まれているものです。そのため、内容によっては社内エンゲージメントの向上につながる可能性があります。一人ひとりあるいは各部署を主役にし、尊重し、激励することで、モチベーションはぐんと高まるはずです。
アクセス解析を基に改善を図る
求人・採用ブログの運用に欠かせないのが効果検証とそれに基づく改善施策の実行です。訪問者データを分析し、どのタイプのコンテンツに反響があるかなど理解が深まれば、効率的かつ効果的な運用に向けて動けます。あわせて採用戦略の精度も上げられるため、相乗的・総合的に成果へとつながる期待が持てるでしょう。
求人・採用ブログから応募に発展することもある!
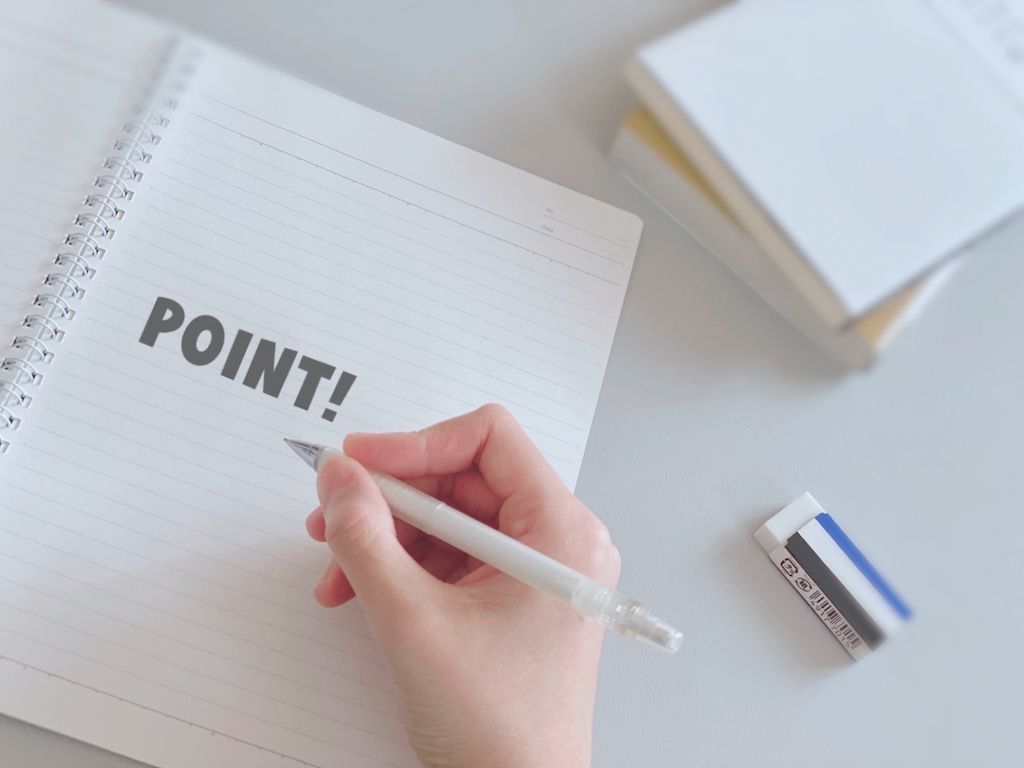
求人・採用ブログは、単なる日常の記録ではありません。求職者との接点構築にはじまりブランドイメージの向上、そこから応募・採用に至る期待さえ持てる、可能性に満ちたメディアツールです。運用していくにあたっては(もしくは再開する際は)、拙稿で述べた注意点を含む書き方やコツをあらためて参照してみてください。人材募集における手札の一枚として確立されれば、採用活動がよりスムーズになるはずです。
求人掲載・採用業務のサポートや料金についてなど、ぜひ気軽にお問い合わせください。
また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談も無料で承っております!
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。
▶【公式】面接コボット – 応募者対応の自動化で面接管理が楽に!
┗求人サイトからの応募対応を自動化できるサービス。チャットボットを通じ、日程調整まで効率よく進めてくれます。
▶【公式】採用ページコボット – 費用・実績も紹介!採用サイト制作サービス
┗採用ページ作成サービス。求人まとめサイトとの自動連携や求人検索エンジンへの対応により外部集客を強化します。

