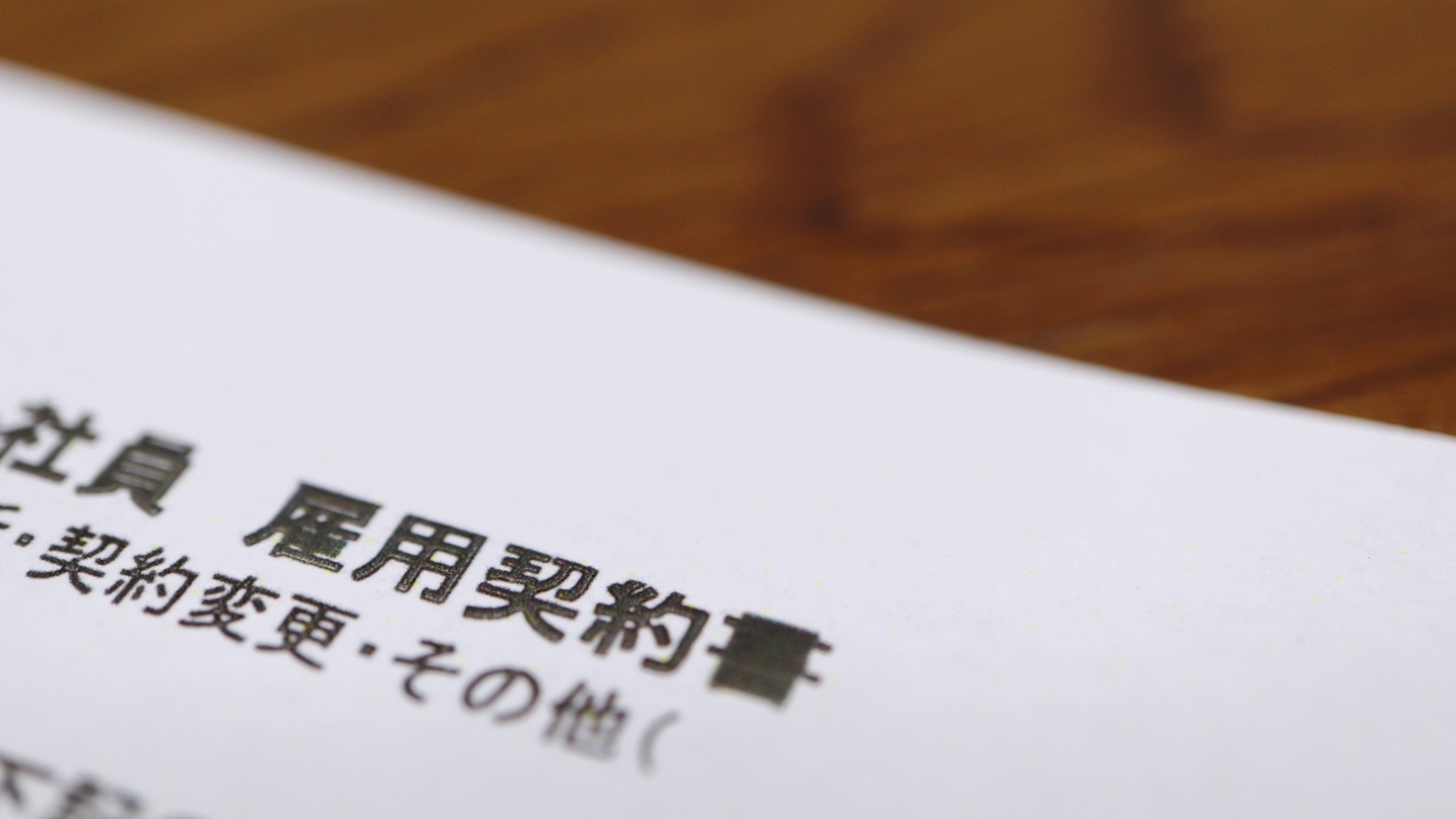直接雇用とは?

直接雇用とは、企業が従業員と文字どおり直接、雇用契約を結ぶ形態を指します。これには正社員、契約社員、アルバイト、パートなどが含まれます。以下、それぞれ簡単に説明します。なお、派遣社員は該当しません。
正社員とは?
正社員とは、企業と期間の定めのない雇用契約を結び、フルタイムで勤務する従業員を指します。昇進や昇給、社会保険、福利厚生などの待遇が整っているところも少なくないでしょう。賞与も企業によって区々とはいえ、支払われるケースの方が多いと思われます。
契約社員とは?
契約社員とは、企業と期間の定めのある労働契約を結び、(特定の期間内で)勤務する従業員を指します。一般的には1年でしょうか。更新も可能です。正社員と同様にフルタイムで働く場合も多い一方で、昇進や昇給、賞与、退職金などの待遇面では企業によって異なり、支給されないケースも見られます。また、同一の企業で有期労働契約が通算5年を超えた場合、労働者の申し出により無期労働契約へ転換できる「無期転換ルール」が適用されます。
▶関連記事:契約社員とは?アルバイトとの違いやボーナス、雇う際の注意点など解説
アルバイト・パートとは?
アルバイト・パートとは、企業と雇用契約を結び、主に時給制で働く従業員を指します。短時間勤務のケースもあればフルタイムで働く方も珍しくありません(前者を指して“パート”と呼ぶことが一般的です)。正社員や契約社員と比べて賞与の機会は少ないように見受けられます。また、昇給や福利厚生の適用範囲も企業の規定や勤務時間によって区々です。
間接雇用とは?

間接雇用とは、企業が労働者を直接雇用せず、派遣会社や請負会社を通じて労働力を確保する雇用形態です。この方式では、労働者は派遣元や請負会社と雇用契約を結び、実際の業務は派遣先企業や依頼企業で行います。企業からすると人事管理や社会保険の負担を軽減でき、人員の柔軟な配置が可能です。一方で、労働者目線では雇用の不安定さや待遇面での課題が指摘されています。いずれにしても、間接雇用の増加は労働市場に大きな影響を与えているわけです。以下、派遣社員や請負社員について説明します。これらを確実におさえることは、直接雇用が派遣とどう違うかを知るうえでも大切です。
派遣社員とは?
派遣社員とは、派遣会社(派遣元)と雇用契約を結び、別の企業(派遣先)で働く労働者を指します。したがって、給与の支払いなどは雇用主である派遣会社の管轄です。一方、派遣先企業は業務上の指示や指導を行います。派遣の形態は大きく2つ。派遣先が決まった時点で雇用契約を結ぶ「登録型派遣」と、派遣会社と無期限の雇用契約を結ぶ「無期雇用派遣(常用型派遣)」があります。
▶関連記事:無期雇用派遣とは?メリット・デメリットや戦略、注意点を解説
また、一定期間の派遣就業後、派遣先企業と直接雇用契約を結ぶことを前提とした「紹介予定派遣」も存在します。
▶関連記事:紹介予定派遣社員を雇うには?辞める理由や正社員登用のポイントも解説
請負社員とは?
請負社員とは、請負会社と雇用契約を結び、他企業から受託した業務を遂行する労働者を指します。派遣社員とは異なり、勤務先企業から直接の指揮命令を受けず、あくまで請負会社の管理下で業務を行います。
派遣社員を直接雇用にできるのか?

派遣社員を直接雇用にできるかどうか、法的に不安を覚える向きも一定数あるようです。先にいうと、これは問題ありません。ただし切り替えるタイミングは、基本的に派遣会社と契約を終了した後です。しかしながら、契約期間中に実行しようと動く企業も稀に見られます。以下、各ケースについて補足します。
派遣会社と契約を終了した後
派遣会社との契約が終了した後に派遣社員と派遣先企業が雇用契約を結ぶことは、労働者派遣法にて、禁止してはいけないと定められています。つまり、このタイミングでは問題なく直接雇用に切り替えられるわけです。
(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)
第三十三条 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
派遣労働者に係る雇用制限の禁止
派遣会社との契約期間中
契約期間中に直接雇用を打診する場合は、派遣会社との契約内容を確認し、適切な手続きを踏むことが重要です。十分に協議し、派遣会社の合意を得ることは必須。紹介料については交渉に及ぶケースもあるでしょう。逆にもしも身勝手に事を運んだ場合、トラブルや法的なリスクを伴う可能性が大いに考えられます。
推進される派遣先の直接雇用

派遣労働者の直接雇用への切り替えは、派遣会社にとっては痛手や弊害が想定される一方で、国からは推進されているのも確かです。以下、具体的に説明します。
雇入れ努力義務の対象
次のシチュエーションに該当する派遣労働者を受け入れるよう、派遣先企業は努力しなければなりません。
- 有期雇用の派遣労働者が同一の組織単位の同一業務で1年以上継続して従事している
- 派遣期間終了後に業務を継続する目的で新たに社員を雇用する予定がある
- 派遣労働者が引き続き就業を希望され、派遣元からも直接雇用の依頼がある
上記は俗にいう「雇入れ努力義務」の対象です。直接雇用が推進されています。
派遣先での正社員登用
派遣先企業が派遣社員を正社員登用することは、国が推奨しています。正社員化だけでなく、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対しては、助成制度があるほどです。このように、非正規雇用労働者は派遣先企業内でのキャリアアップが促進されています。
雇用安定措置
雇用安定措置は、派遣社員がより長期的に安定した職場環境を得られるようにするための取り組みです。具体的には、派遣就業見込みが3年であり、継続就業を希望する有期雇用派遣労働者については、派遣会社が次のいずれかの雇用安定措置を講じる義務があります。
- 派遣先への直接雇用の依頼
- 新たな派遣先の提供
- 派遣元での無期雇用
- その他、安定した雇用の継続を図るために必要な措置
これらの措置は、派遣労働者の雇用の安定とキャリア形成を支援することが目的です。なお、派遣労働者が同一の組織単位で1年以上3年未満就業した場合も、派遣会社には上記のいずれかの措置を講じる努力義務があります。
参照:雇用安定措置について
直接雇用に切り替えるメリット

直接雇用への切り替えは、派遣社員のための措置とはいえ、企業側にもメリットはあります。ざっと挙げると次のとおりです。
- 業務範囲を広げられる
- コストを抑えられる
- 3年以上働いてもらえる
以下、それぞれ解説します。
業務範囲を広げられる
派遣契約では、業務内容が限定されることが多く、派遣社員はその範囲内でしか働けません。これが直接雇用になれば、お願いできる仕事の領域を広げられます。優秀な方であれば、組織として生産性もぐっと上がっていく期待が持てるでしょう。
コストを抑えられる
派遣社員を利用する場合、派遣会社への手数料や管理費用が発生します。しかし、直接雇用に切り替えることで、これらの費用を削減でき、実質的な人件費の低減が可能です。長期的な視点で人材育成も図れるため、教育や研修にかかるコストも同様に抑えられます。
3年以上働いてもらえる
派遣社員の場合、原則、同じ派遣先で働ける期間は3年に限られます。これが直接雇用だと縛りがなくなるため、長期間働いてもらえることが期待できるでしょう。ただし、直接雇用にした途端、辞められてしまうケースもあります。そうならないように、環境づくりも重要です。給与や働きやすさ、成長の機会……等々、定着のためにしっかりと考えていかなければなりません。
直接雇用に切り替える方法
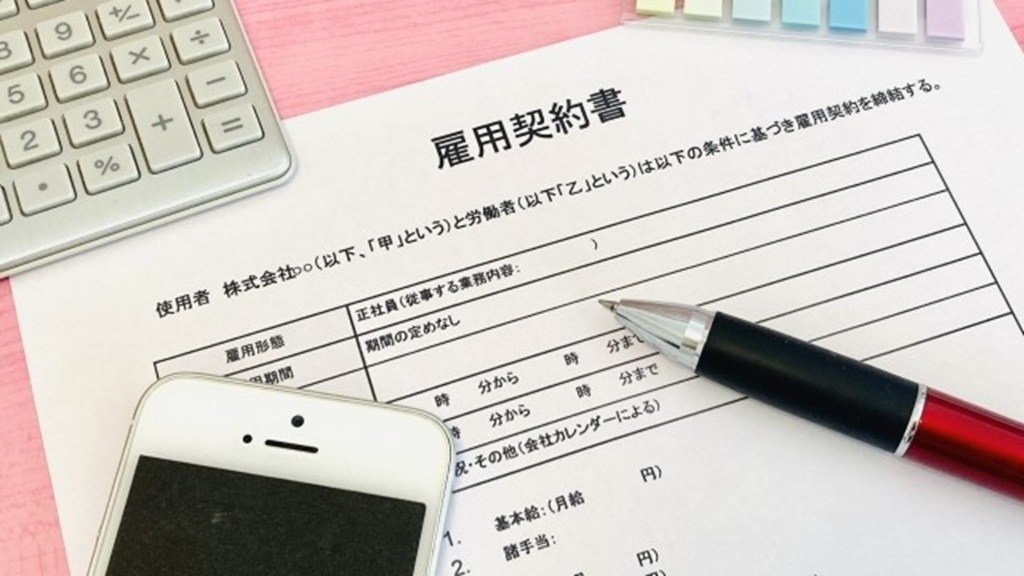
直接雇用に切り替える方法は、そう複雑ではありません。実際に派遣社員を直接雇用に切り替える場合、次の手順で進めるとスムーズです。
- 派遣契約の確認
- 派遣会社への連絡
- 派遣社員との交渉
- 社会保険等の手続き
以下、それぞれ解説します。
派遣契約の確認
期間や業務内容、派遣料金、業務遂行に関する条件などが記載されている派遣契約書には、必ず目を通しましょう。なるべく入念に確認しなければ、後で困るのは自分たちです。特に直接雇用に関する項目がないかどうかは、細心の注意を払う必要があります。
派遣会社への連絡
派遣契約の内容を十分に確認できたら、派遣会社に対して直接雇用の意向を伝えます。派遣会社との連絡は、書面による通知だけでなく、担当者と直接会話を通じて行えるとよいでしょう。合意形成も必要です。双方が納得できるよう協議しましょう。状況に応じて、法務部門や外部の専門家に相談するのも一つのやり方です。
派遣社員との交渉
直接雇用への切り替えは、派遣会社だけでなく派遣社員本人との交渉も必要です。場を設けて、直接雇用への意向や条件について率直に話し合いましょう。その際、給料や職務内容、福利厚生などの条件は明確に提示することが大事です。ここでも双方が納得できる合意形成が求められます。
社会保険等の手続き
直接雇用に切り替わるタイミングで、社会保険(健康保険や厚生年金保険、雇用保険)は派遣会社から自社にシフトします。忘れないよう、そして不備がないよう、手続きは慎重に行いましょう。
直接雇用の注意点
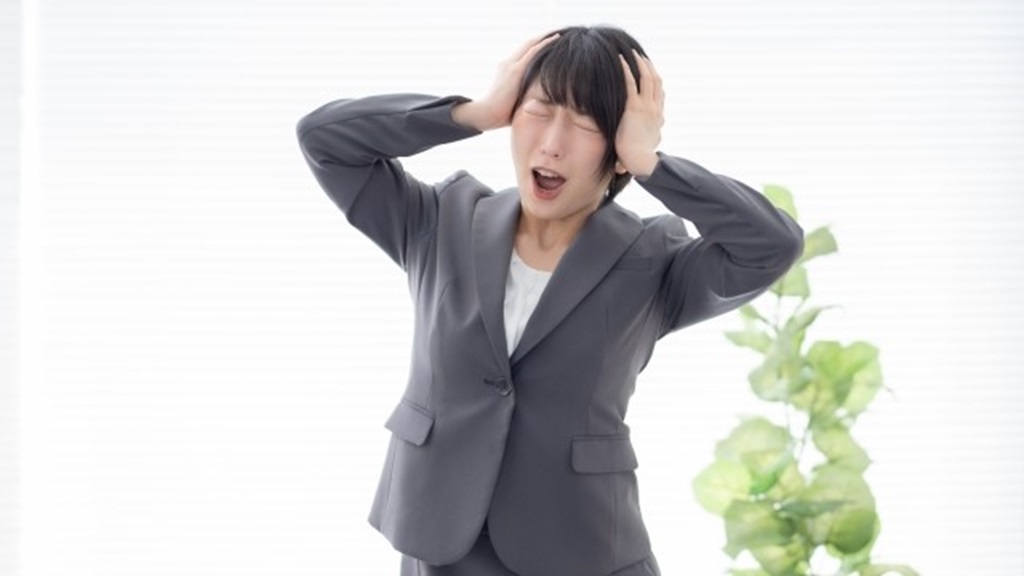
メリットや方法だけでなく、直接雇用に潜む注意点も把握しなければ足をすくわれるかもしれません。大きくは次の2点です。
- 管理コストが嵩む可能性
- 派遣雇用時とのギャップ
以下、それぞれ解説します。
管理コストが嵩む可能性
直接雇用では、給与や社会保険、福利厚生に関する支払いなどは企業が行います。また、研修をあらためてしっかりと行う必要も出てくるでしょう。そうなると当然、その分のコストが発生するわけです。ほかにも、事務手続きなどの業務負担の増加やそれらに伴う人件費の増加も考えられます。いずれにしても工数管理は必須。現状と直接雇用に切り替えた場合できちんと比較し、調整を図ることが大事です。
派遣雇用時とのギャップ
正社員と派遣社員では、業務範囲が異なります。それゆえ直接雇用後、そのギャップに苛まれる従業員も少なくありません。以前の業務であれば問題なく遂行できていたとしても、新たな業務や責任の重さに苦労されるケースはそこかしこで見られます。これが起きないよう対策は必須。事前の入念なコミュニケーションと、入社後のフォローはどうしたって欠かせません。
直接雇用におけるスポットワーカーの採用について

直接雇用であってもスポットワーカーの採用なら、派遣のように一時的な人員確保が可能です。実際、短時間やスキマ時間を埋めたい労働者は少なくありません。そうしたポジティブな理由でいわゆる「スキマバイト」に応募する人は増得ている印象です。そのニーズに応えるように市場には特化したサービスが続々と出てきています。dipが提供する『スポットバイトル』もその一つ。無料掲載、即日マッチング可能、ボーナス制度(dip負担)でワーカーのモチベーションにも寄与。人手不足や急な欠員にお困りならぜひ、『スポットバイトル』の活用も検討してみてください。
詳細は、以下のご案内ページや資料(さらにくわしく!)でご確認できます。
▶【公式】スキマ時間のスポット募集ならスポットバイトル|求人掲載はこちら
人材確保には直接雇用とは何かを網羅的に知ることが大事!

人手不足が深刻化する現代では、欲しい人材を確保することは簡単なことではありません。そのため、自社で働く派遣社員が優秀であれば、直接雇用に切り替えることも視野に入れたいところです。ただそれを安易に実行するのではなく、まずは直接雇用とは何かを網羅的に把握したうえで、自社のケースに当てはめるとよいでしょう。法的リスクやトラブルに対しても目配りが十分にできたなら、安心して進められるはずです。
求人掲載・採用業務のサポートや料金についてなど、ぜひ気軽にお問い合わせください。
また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談も無料で承っております!
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【公式】スキマ時間のスポットワーカー募集ならスポットバイトル
┗スキマ時間で「働きたい」と「働いてほしい」をつなぐ求人マッチングサービス。求人は無料で掲載できます。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。
▶【公式】面接コボット – 応募者対応の自動化で面接管理が楽に!
┗求人サイトからの応募対応を自動化できるサービス。チャットボットを通じ、日程調整まで効率よく進めてくれます。
▶【公式】採用ページコボット – 費用・実績も紹介!採用サイト制作サービス
┗採用ページ作成サービス。求人まとめサイトとの自動連携や求人検索エンジンへの対応により外部集客を強化します。