計画年休とは
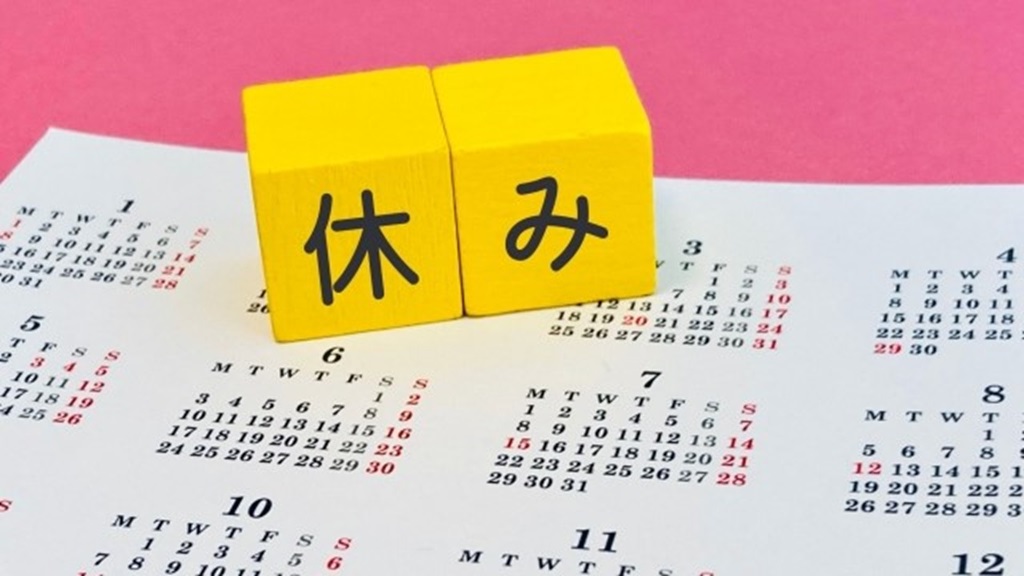
計画年休とは、従業員の休暇取得日をあらかじめ決めておける制度です。これによって企業は、従業員の有給休暇を文字どおり計画的に消化できます。本章ではまず、この取り組みが導入された経緯や主な目的、適用対象者、そして有給休暇との違いといった基本中の基本について解説します。計画年休を理解するうえで確実におさえておきましょう。
導入の経緯、目的
遡ること1947年、労働基準法第39条で年次有給休暇が定められました。そしてこの取得率を上げようと、1987年に計画的付与制度が設けられます。そう、これが計画年休です。具体的には、事業場の労働者の過半数を組織する労働組合もしくは労働者の過半数代表者と使用者が労使協定を締結すれば、付与された有給休暇から5日を超える分について計画的に休暇取得日を割り振れるようになります。しかしながら、なかなか浸透せず、有給休暇の取得率はさほど伸びないまま年月は経過。と、ようやく抜本的に状況が変わったのが、記憶に新しい2019年です。このとき、年5日の年次有給休暇の確実な取得が施行されます(「働き方改革関連法」の一環として労働基準法が改正)。年間10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、年間5日の取得が義務化されるようになったのです(違反した場合は罰則あり)。有給休暇の取得率を向上させるための(政府の)相当な覚悟が見て取れます。また、企業としても、労働時間を是正するために(あるいは労務管理を適切に行うために)いまはこうした制度を積極的に用いているといえそうです。
計画年休が適用される対象者
前述のとおり、計画年休は付与された有給休暇のうち5日を超える部分に対して設定できます。つまり、計画年休の対象者は、有給休暇が6日以上付与されている労働者です。したがって、付与される有給休暇に計画年休の余地がない方は適用されません。なお、付与対象の時季であっても、退職がすでに決まっている方やあらかじめ育児休業や産前産後休業に入ることがわかっている場合は、除外せざるを得ないのが一般的です。
有給休暇との違い
計画年休は、有給休暇の取得を促し、企業の業務運営を円滑にするための制度です。ゆえに、あくまで有給休暇を取得させる方法の一つと位置付けられます。こう捉えていくと、そもそも両者は並べて比較するものでもないことがわかるはずです。また、基本的に有給休暇をいつ取得するかは、従業員本人に委ねられます。が、計画年休は労使協定を結んだうえで企業が指定可能です。
計画年休の活用方式

計画年休の設定方法は、大きく3つのパターンに分けられます。ずばり、次のとおりです。
- 一斉付与方式
- 交替制付与方式
- 個人別付与方式
以下、それぞれ解説します。活用の際は、各特徴と自社の業務特性を照らし合わせて選べるとよいでしょう。
一斉付与方式
計画年休を対象者全員、同じ日に付与するのが一斉付与方式です。全員を休ませても支障をきたさない職種、職場に向いています。なお、よく見られるのが、ゴールデンウィークやお盆の時期、年末年始などの長期休暇につなげて付与するケースです。
交替制付与方式
業務を止めないようグループやチームごとに時期をずらして計画年休を割り振るのが、交替制付与方式です。一斉付与方式が難しい業界や企業規模の組織におすすめします。
個人別付与方式
計画年休の取得日を、従業員一人ひとりの希望やタスク進捗の状況を踏まえて個別に決めるのが、個人別付与方式です。文字どおり個々の事情に配慮しやすく、シフト調整や繁忙期を避ける対応もしやすい一方、全体のスケジュール管理が煩雑になりやすいデメリットもあります。従業員数が少なく、個別調整がしやすい組織に向いているといえるでしょう。
計画年休で期待できるメリット
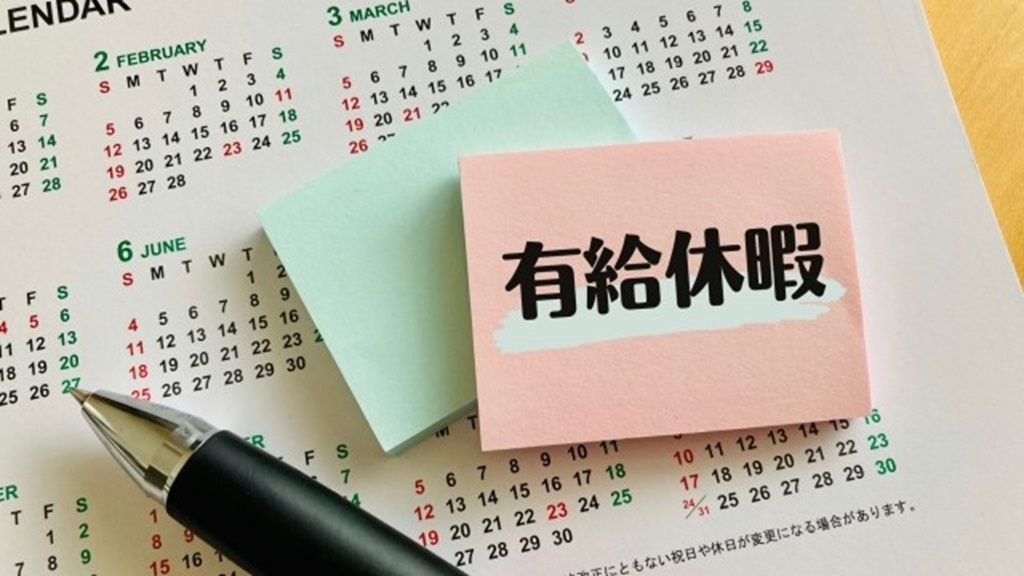
計画年休を活用することで、いくつかメリットが見込めます。ざっと挙げると次のとおりです。
- 有給休暇の取得義務を果たしやすい
- 労務管理がしやすくなる
- 繁忙期に備えることができる
これらを期待し、導入する企業も少なくないでしょう。以下、それぞれ解説します。
有給休暇の取得義務を果たしやすい
計画年休によって年5日必要な取得の穴を埋めることができます。義務化されたいま、管理面も含めて企業としてはどうクリアしていくか頭を悩ますところでしょう。従業員任せではどうしてもコントロールできない部分もあり、結果、義務を果たせないケースも考えられます。だからこそ、企業主導で取得を促すことが必要です。そのお膳立てとして、(取得日を設定できる)計画年休は便利かつ安心だといえます。
労務管理がしやすくなる
計画年休は取得日をあらかじめ設定しておけるため、活用方式によっては労務管理の把握が容易になると思われます。シフトや業務量の調整も同様です。一人ひとりの作業負担は少なからず軽減されるでしょう。
繁忙期に備えることができる
計画年休を一斉付与方式で閑散期にまとめて設定できると、繁忙期に向けた人員調整も目途がつきやすく安心でしょう。備えあれば憂いなし。繁閑の時期がはっきりしているならなおさらメリットとして感じられるはずです。同時に、上述した有給休暇の取得義務も果たせ、なおかつ労務管理も煩雑にならずに済みます。使わない手はないかもしれません。
計画年休で懸念されるデメリット

メリットにばかり目がいったからか、計画年休を導入した後で思わぬ落とし穴にハマることも決して珍しくありません。たとえば、しばしば見受けられる問題として従業員から不評を買うケースが挙げられます。実際、計画年休に対して窮屈に感じる人も多いようです。そしてもう一つ。導入するまでのプロセスに手間がかかる点も無視できません。メリットに続いては以下、これらの懸念されるデメリットについて解説していきます。
不自由に感じる従業員も少なくない
仮に一斉付与方式の計画年休を導入した場合、「休みたいときに休めない」と感じる従業員が出てきてもおかしくありません。家庭の都合やタスク進捗など個々の事情如何では、せっかくの休みとはいえ計画年休が「ありがた迷惑」になってしまいます。他方、個人別方式なら調整の余地がある分、柔軟な対応は可能です。しかし、大なり小なり動きを封じられてしまうなら、結局はストレスを禁じ得ないでしょう。
規則設計や労使協定に手間がかかる
計画年休をどの方式で運用するのか、誰を対象とするのか、適用ルールを明確にしておかなければ、後々トラブルになりかねません。そのため、就業規則にはしっかりと明記する必要があります(労働基準監督署へ届けます)。そして実際に導入するためには、労使協定の締結が必須です。くわしくは後述しますが、これらの手間が負担に感じられることも、ある程度は想定しておいた方がよいでしょう。
計画年休の導入フロー

メリット・デメリットを踏まえて実際に計画年休を導入する場合、手続きをどう進めるかお伝えします。大きくは次の3ステップです。
- 就業規則に明記する
- 活用方式を決める
- 労使協定を締結する
手順どおり、それぞれについて解説します。
就業規則に明記する
計画年休を導入する際は、就業規則に自社の方針を正式に書き加えます。確認するのは「年次有給休暇」の項目です。その際、労使協定に基づき、会社があらかじめ指定する日を有給休暇として取得させるといった旨を追記します。(追記例:前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。)
活用方式を決める
続けて、活用方式も決めましょう。先述した3つの方式(一斉付与方式、交替制付与方式、個人別付与方式)のうち自社にとってどれが最適解かを探り、具体的に付与日を定めます。
労使協定を締結する
計画付与の対象者、方式、付与日変更の場合の手続き……等々、労使(事業場の労働者の過半数を組織する労働組合もしくは労働者の過半数代表者と使用者)双方が話し合い、協定書を作成・締結します。これが、導入に必要な正式な手続きです。締結後はあらためて計画年休の内容を、(対象日は絶対に休まなければならないことも含めて)周知しましょう。
計画年休に関するよくある質問

計画年休について概要や導入の流れが一とおりわかってもなお、疑問に思うところは出てくるかもしれません。本章では、よくある質問を抜粋します。ぜひ、参考にしてみてください。
有給休暇の付与日数が5日を超えない従業員に対してはどう扱えばよいですか?
新入社員や非正規雇用労働者など、年次有給休暇が5日を超えない従業員に対しては、「一斉の休業日を有給の特別休暇とする」あるいは「一斉の休業日に対して、休業手当として平均賃金の60%以上を支払う」といった措置を取ります。ただし、これはあくまで一斉付与方式または部門別の交替制付与方式の場合に限っての話です(個人別付与方式の場合は従業員の年次有給休暇取得率向上が目的のため、付与日数が5日を超えない労働者は計画年休の対象外です)。
計画年休は変更できますか?
計画年休は労使協定に変更を認める条項がある場合や、労使双方が協定を再締結すれば変更可能です。また、個別に労働者の同意を得た場合もこの限りではありません。ただし、労働者に不利益となる一方的な変更は避けなければなりません。
導入企業の特性に向き不向きはありますか?
向いているのは、明らかに閑散期がある企業です。その時期、休暇日をまとめて設定することで業務の効率化が図れます。反対に不向きなのは、日々の業務量や人員が変動しやすく、休暇日を固定しにくい企業です。方式問わず、影響は受けやすいといえます。そのため、事前の運用設計が重要です。
計画年休によるシフトの空きが不安な事業主様へ

一斉付与方式以外で計画年休を実施する場合、どうしてもシフトには空きが生まれます。一時的であってもそれを痛手に感じる事業主の方も多いでしょう。空いたシフトをどう埋めて凌ぐか。ずばり、スポットバイトの募集に特化したサービス『スポットバイトル』の導入をおすすめします。
『スポットバイトル』は、当日掲載、即日採用を実現する求人サイトです。昨今は空いた時間に働きたいスポットワーカーがますます増えてきています。ニーズの高まりはいざ活用すると驚くほどに実感できるでしょう(▶初回でスピードマッチングを体感 レギュラーバイトのきっかけとなることにも期待)。 出色は、給与に加えてdipから支給される「Good Job ボーナス」の制度です。単発バイトでありがちなモチベーションの低いワーカー問題も、このボーナス制度によりある程度、回避できると考えます。うまく活用できればリピーターひいては長期雇用への期待も広がるサービスです。
▶無料でダウンロードできるスポットバイトルの資料はこちらから
計画年休の導入は慎重に検討しよう!

計画年休は、有給休暇取得の義務化をクリアしやすくする一方、従業員の不満や運用負担といったデメリットもはらんでいます。だからこそ、導入ありきで進めるのではなく、自社の業務特性や現場の声にしっかり耳を傾け、慎重に検討していくことが大事です。実施するなら事前に制度設計や周知を丁寧に行い、納得感を持ってもらえる運用を目指しましょう。そのうえで、シフトの空きを柔軟に埋める仕組みとして『スポットバイトル』のようなサービスを取り入れるのも一つの安全策です。 つまるところ、計画年休は、体制整備と運用管理のどちらも現実的なバランス感覚が問われるテーマだといえます。
求人掲載・採用業務のサポートや料金についてなど、ぜひ気軽にお問い合わせください。
また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談も無料で承っております!
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【公式】空いた時間のスポットワーカー募集ならスポットバイトル
┗空いた時間で「働きたい」と「働いてほしい」をつなぐ求人マッチングサービス。求人は無料で掲載できます。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。
▶【公式】面接コボット – 応募者対応の自動化で面接管理が楽に!
┗求人サイトからの応募対応を自動化できるサービス。チャットボットを通じ、日程調整まで効率よく進めてくれます。
▶【公式】採用ページコボット – 費用・実績も紹介!採用サイト制作サービス
┗採用ページ作成サービス。求人まとめサイトとの自動連携や求人検索エンジンへの対応により外部集客を強化します。

