契約社員の5年ルールとは
契約社員の5年ルールとは、労働契約法に基づき、契約社員やアルバイト・パートなどの有期契約労働者と企業の間で有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者が無期労働契約への転換を申し込むことができる制度を指します。2013年に施行された改正労働契約法によって導入され、契約社員の雇用の安定を図ることを目的としています。
適用条件
契約社員の5年ルールが適用される条件は、主に次の2点です。
- 同一の企業のもとで5年以上継続して有期契約を更新し続けている
- 労働者が無期転換を申し出る
このルールは自動的に適用されるものではなく、労働者本人からの申込みがあって初めて効力を持つ点に注意が必要です。
クーリング期間とは
クーリング期間とは、契約社員の雇用において、同一の企業での契約期間が5年に達する前に一定期間を空けることで、再び新たな契約を開始できるようにする制度です。具体的には、契約社員が5年を超えて同一企業で働き続けた場合、無期労働契約へ転換する権利が発生しますが、クーリング期間を設けることで、カウントをリセットできます。
クーリング期間の長さには法的な規定はなく、実質的に労働者と企業との間での合意や、企業の就業規則により決定されます。ただし、クーリング期間が短すぎる場合、労働者が実質的に同じ職務を継続していると見なされる可能性があるため、注意が必要です。
参照:厚生労働省「通算契約期間の計算について(クーリングとは)」
契約社員の5年ルールがもたらすメリット
契約社員の5年ルールは、社員側に大きなメリットがあるように思われますが、実は企業側にも様々なメリットがあります。ここでは、契約社員の5年ルールがもたらすメリットを解説します。
経験者の定着
企業にとって、自社で働いた経験がある社員や専門的なスキルやノウハウを持つ社員が長期間にわたって定着することは、競争力を維持・向上させるうえで欠かせません。契約社員の5年ルールが適用されることで、企業側としても貴重な人材を長期的に保持できます。
社員のモチベーションアップ
契約社員の5年ルールを設けることで、契約社員が正社員への登用の可能性を見据えることができ、長期的なキャリア形成の視点を持つことができます。キャリアの明確な道筋が見えることで、社員はより高い目標を持ち、日々の業務に対する意欲が自然と高まります。
企業のイメージアップ
契約社員の5年ルールは、社員に安定した雇用環を提供することになるため、企業が従業員を大切にしているというメッセージを社会に発信できます。特に、企業の社会的責任が重視される現代において、従業員の安定的な雇用をサポートする姿勢は、企業の信頼性を高められます。
契約社員を5年超えて更新しない場合
契約社員の5年ルールの基本的な内容と合わせておさえておきたいのが、契約社員を5年超えて更新しない場合です。以下の内容は、注意事項としてしっかりと理解しておきましょう。
雇止め法理に注意が必要
雇止め法理とは、契約社員や有期雇用契約の労働者に対して、契約更新をしないことを決定する際に適用される法的な原則を指します。雇止め法理は、企業が契約の更新を拒否する際に不当な扱いを防ぐために存在し、労働者の雇用安定を図る重要な役割を果たしています。仮に契約の更新が長期間にわたって繰り返されている場合、または更新が期待される状況が生じているなら、企業が合理的な理由なしに契約を終了させることは難しいでしょう。
したがって、契約社員を5年超えて更新しない場合、企業は契約終了の際に、合理的な理由を持つことが求められます。契約社員が契約更新を期待する合理的な理由があるかどうか、過去の更新回数や期間、企業側の説明責任などから、雇止めが適法であるか否かが判断されるため、注意が必要です。
事前の明示が大事
契約社員を5年超えて更新しない場合、契約期間が終了する前に、企業としては契約社員に対して雇用の継続や終了に関する意図を明確に伝えなければなりません。特に、5年を超えて契約を更新しない場合、企業はその理由や状況を契約社員に納得のいく形で説明する必要があります。説明を怠ると、前述した雇止め法理に基づいて不当な雇止めと判断される可能性もあるため、企業にとって法的リスクが増大します。
契約社員の5年ルールについてのよくある質問
契約社員の5年ルールの概要を理解できたとしても、企業の様々な状況によって疑問や不安が出てくるでしょう。ここでは、契約社員の5年ルールについてのよくある質問とその回答を紹介します。
契約社員からの申し入れがなければどうなるか?
契約社員から5年ルールに基づく無期転換の申し入れがない場合、企業と契約社員の関係は基本的に現行の有期契約のまま継続されます。ただし、企業側は契約更新の際に、あらかじめ契約社員に無期転換の権利があることを明示しましょう。契約社員が申し入れを行わないまま5年を超えて勤務を続けた場合、企業側は特別な措置を取る必要はありませんが、契約更新時には条件変更や契約内容の確認を行うことが一般的です。
満期直前で雇止めは可能か?
満期直前での雇止めは、法律上可能ですが、いくつかの条件を考慮する必要があります。まず、契約社員は通常、契約期間の終了時に雇用の終了が想定されていますが、契約更新を繰り返している場合には、その雇止めが不当とみなされかねません。
また、労働契約法に基づく雇止め法理により、雇止めの際には正当な理由が必要とされます。強引に契約を終了することはできません。したがって企業側は、満期直前で雇止めを行う際には、その理由を明確にし、労働者に対して十分な説明を行うことが求められます。
5年ルールが施行された以降の労働条件はどう変える?
5年ルールが施行され、契約社員を正社員として迎える際には、給与や福利厚生、労働時間などの労働条件を正社員と同等またはそれに見合った形で調整することが求められます。また、労働条件の見直しには、社員の職務内容や責任範囲を考慮し、能力や実績に応じた評価制度の導入も欠かせません。
ほかにも、契約社員のスキルアップを支援するための研修制度を充実させることも社員にとってはもちろん、企業としての在り方を示すうえで大事な取り組みです。
契約社員の5年ルールを把握したうえで大事なコツ
契約社員の5年ルールは、基本理解はもちろん、おさえておきたいコツもいくつか存在します。以下、具体的に取り上げます。
社内周知の徹底
契約社員の5年ルールは、企業が契約社員と適切に契約を結ぶために重要です。経営陣や人事部門がルールの具体的な内容を正確に理解するのは当然ですが、全社員に対して分かりやすく説明する必要もあります。
具体的には、定期的な研修や説明会の実施が効果的です。契約社員を管理するラインマネージャーや現場のリーダーが、5年ルールについて誤解なく把握し、ルールに基づいた適切な処遇を行うのに効果的でしょう。
また、社員に対する情報提供は、メールや社内イントラネットを活用して、いつでも確認できる状態にしておくことで、社員一人ひとりが契約の更新や雇用継続に関する不安を軽減できます。
処遇、評価体系の調整
契約社員が無期契約への転換を希望した場合に備えて、評価基準も明確に設定しておきましょう。これがはっきりしていると、契約社員が自分の役割や成果をどのように評価されるかを理解し、キャリアパスを描きやすくなるはずです。
また、正社員と契約社員の間で不公平感を生まないよう、処遇面でもバランスを取る必要があります。特に給与や福利厚生といった報酬面を調整することで、契約社員が長期間働くモチベーションにもつながるでしょう。
契約社員の採用におすすめのサービス
契約社員の5年ルールはありますが、実際は5年未満でやめてしまう契約社員も少なくありません。そのため、求人サービスの活用も視野に入れることが必要です。具体的には、dipが提供する『バイトルNEXT』をおすすめします。正社員はもちろん契約社員の募集に特化しているため、大なり小なりスムーズな採用が期待できるでしょう。
▶無料でダウンロードできるバイトルNEXTの資料はこちらから
契約社員の5年ルールに関するポイントまとめ
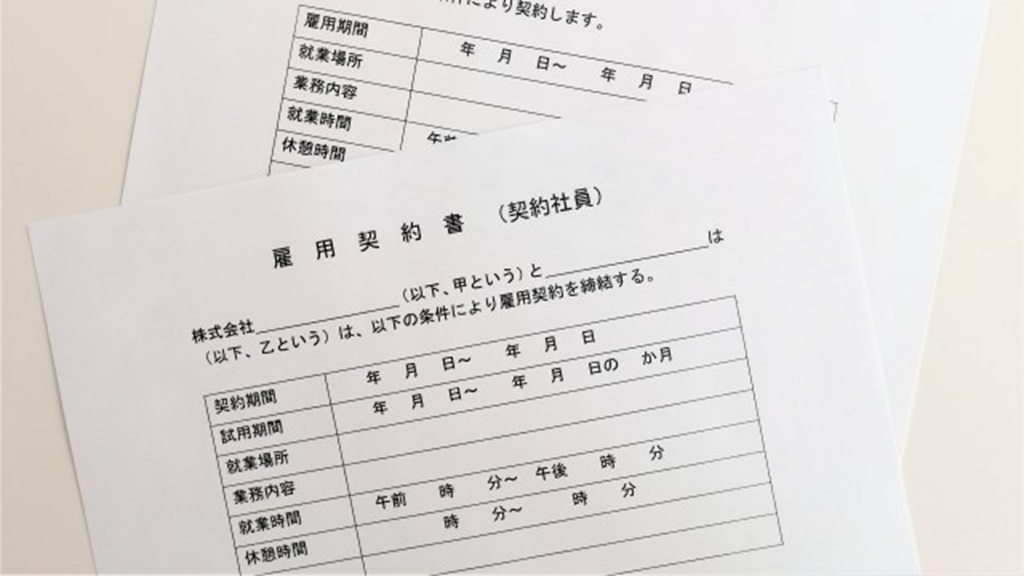
契約社員の5年ルールは、「5年を超える有期契約の反復更新があった場合、本人の申し出により無期契約へ転換できる」というシンプルな仕組みですが、実務では判断が分かれる場面も少なくありません。クーリング期間の扱い、雇止めの妥当性、無期転換後の処遇設計など、企業側には多面的な配慮が求められます。制度への理解不足や曖昧な運用は、法的リスクや職場の不信感につながる恐れもあります。人事担当者としては、形式的な契約更新だけでなく、社員との対話や社内での情報共有を重ねることで、ルールを単なる義務で終わらせず、組織づくりに生かす視点が重要です。
▶関連記事:契約社員とは?アルバイトとの違いやボーナス、雇う際の注意点など解説
求人掲載・採用業務のサポートや料金についてなど、ぜひ気軽にお問い合わせください。
また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談も無料で承っております!
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【公式】空いた時間のスポットワーカー募集ならスポットバイトル
┗空いた時間で「働きたい」と「働いてほしい」をつなぐ求人マッチングサービス。求人は無料で掲載できます。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。
▶【公式】面接コボット – 応募者対応の自動化で面接管理が楽に!
┗求人サイトからの応募対応を自動化できるサービス。チャットボットを通じ、日程調整まで効率よく進めてくれます。
▶【公式】採用ページコボット – 費用・実績も紹介!採用サイト制作サービス
┗採用ページ作成サービス。求人まとめサイトとの自動連携や求人検索エンジンへの対応により外部集客を強化します。

