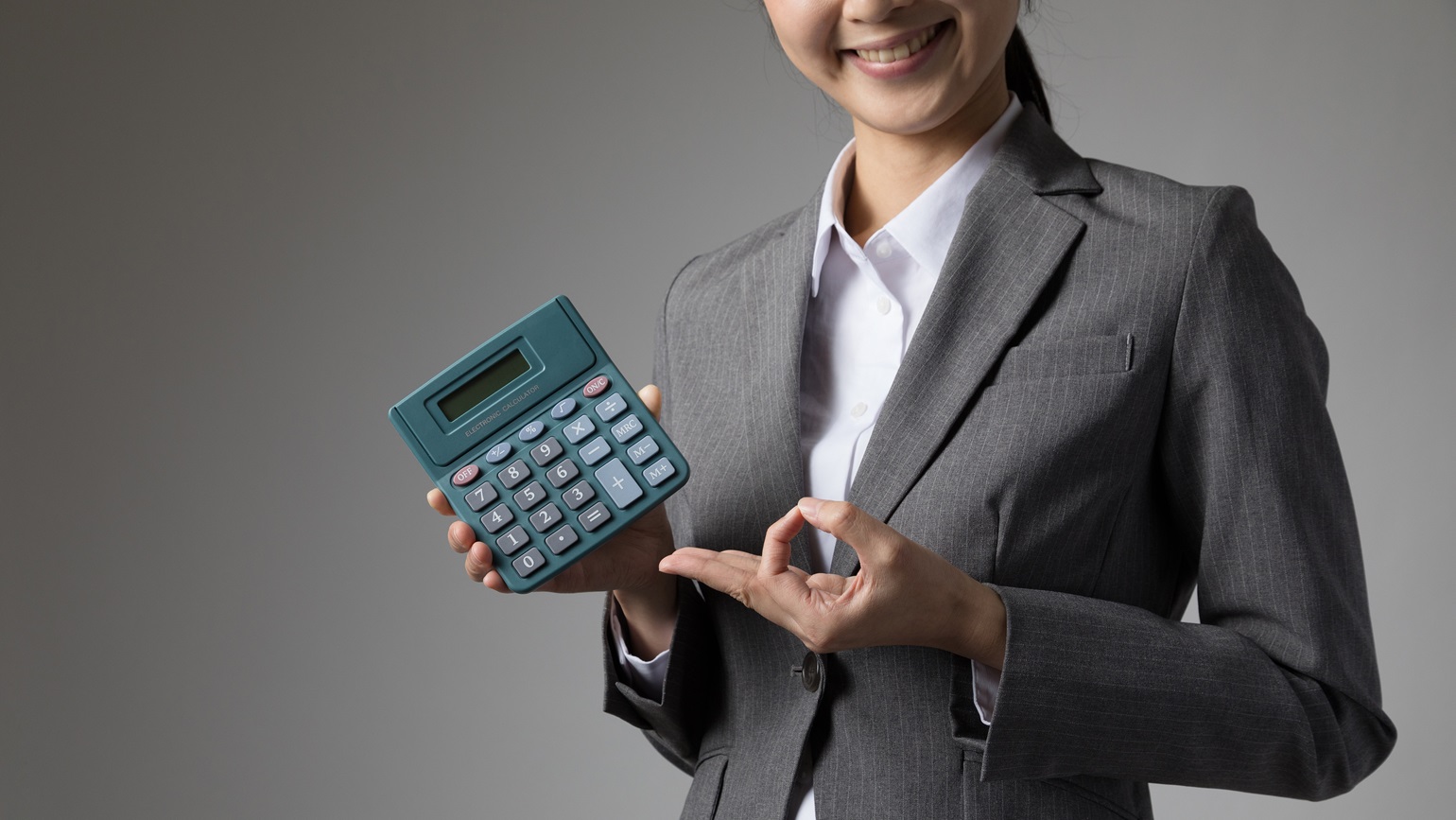費用を計上するとは?

費用を計上するとは、端的に述べるならば、企業が日々の経済活動において発生するコストを財務諸表に反映させることです。他方、似たような言葉として「出金」や「仕訳」、「記帳」なども挙げられます。費用計上に対する解像度を上げる意味でも、これらとの違いは知っておくべきでしょう。以下、それぞれ簡単に説明します。
出金との違い
出金とは、企業が実際に現金や預金を支払うことを指し、主に現金の流れにフォーカスしています。他方、費用の計上は、発生した費用を会計帳簿に記録することです。これは、必ずしも現金の動きと一致するわけではないことを意味します。たとえば、特定の月に商品やサービスの提供を受けた場合、その費用はその月に計上されるべきですが、実際の支払いが翌月になることもあります。
仕訳との違い
仕訳とは、会計帳簿に取引を記録する具体的な行動を指します。仕訳の目的は、発生した取引をデビット(借方)とクレジット(貸方)に分けて明確に記録し、勘定科目に基づいて正確な帳簿を作成することです。一方で、費用計上は対象期間の損益を正確に反映させることが狙いにあります。とはいえ、仕訳もまた費用計上を行うプロセスの一つです。
記帳との違い
記帳とは、実際に行われた取引を一定の形式に基づいて帳簿に記録する作業を指します。対して、費用計上は特定の会計期間において発生した費用を財務諸表に反映することです。会計期間全体の財務情報を正確に反映するためには、その基礎となる取引データを詳細に記録する必要があります。つまり、費用計上は記帳によって成り立つわけです。そう、両者は、相互に補完的な役割を果たします。
費用を計上するタイミング

費用を計上するタイミングは、企業によって区々です。主に「発生主義」「実現主義」「現金主義」で分かれます。以下、それぞれについて説明します。
発生主義
発生主義とは、取引が発生した時点で費用や収益を計上する考え方です。支払いの有無に関係なく、経済的実態が生じた時点で会計処理が行われます。
実現主義
実現主義とは、現実に取引が実現し、対価を受け取る権利が確定した際にその費用を計上する考え方です。たとえば、商品を引き渡して相手に債権が発生した時点(販売が成立した時点)でそれは認識されます。
現金主義
現金主義とは、実際に現金の支出や収入があったタイミングで費用や収益を計上する考え方です。まさにお金が動いた時点を基準に会計処理を行うため、現金の流れを明確に掴めます。小規模事業者や個人事業主の一部では、(国税庁が特例として定めているため)この方式が使われますが、法人会計では原則認められません。
費用を計上する基準

費用の計上をいつと見なすかは、業種や契約内容によって基準が異なります。以下、主に「仕入れ」と「請負」に関する費用計上の考え方を紹介します。
仕入れ計上とは
仕入れ計上とは、商品や原材料などを仕入れた際に、どの時点で費用として計上するかを定めたものです。具体的には、「発送基準」「入荷基準」「検収基準」が挙げられます。
発送基準
発送基準では、仕入先から商品が発送された時点で費用が計上されます。実際の到着を待たずに処理するため、物流に時間がかかる場合に適用されがちです。
入荷基準
入荷基準では、実際に商品が倉庫に到着した時点で費用が計上されます。納品書や受領記録などで到着を確認したうえで処理するため、現物の受領に即した会計処理が可能です。
検収基準
検収基準では、商品やサービスの内容を確認し、受け入れに問題がないと判断された時点で費用が計上されます。(買い手側にとって)法人税法上の原則とされ、多くの企業で採用されています。
請負の計上基準
請負の計上基準とは、工事や業務委託などの請負契約において、費用や収益をどのタイミングで計上するかを定めたルールです。一般的には、引渡しや検収が完了した時点で計上される「工事完成基準」が用いられます。ただし、長期にわたる工事などでは、進捗に応じて段階的に計上する「工事進行基準(進行基準)」が認められることも少なくありません。なお、後者を採用するには、進捗の信頼性を示す合理的な基準(出来高、原価比例法など)が必要です。
費用を計上する主な流れ

企業が外部に業務を依頼したり物を購入したりする場合、発注から支払いまでにはいくつかの段階があります。会計上「費用を計上する」とは、請求内容が確定し、その金額を帳簿に記録することを指しますが、実際の業務フローでは、その前後のやりとりや支払いまで含めて、一連のプロセスとして扱われることが一般的です。たとえば、次の流れが挙げられます。
- 見積書の受領
- 発注書の作成
- 商品の検収
- 請求書の受領
- 代金の支払い
以下、これらについて補足します。
見積書の受領
業務を外部に依頼する際、最初に必要となるのが見積書です。ただ金額だけを確認するのではなく、数量、納期、単価の内訳、手数料、消費税の扱いなど、細かい条件を一通り確認する必要があります。過去にやり取りがあった取引先であっても、今回の内容がそれと同じとは限りません。見積書に記載されていない条件については、その都度確認を入れるのが基本です。社内の決裁を通す資料としても使うため、曖昧な記載がある場合はそのまま提出せず、補足や説明を添えることもよくあります。
発注書の作成
見積書の内容が確定し、社内の承認が得られたら、次は発注書を作成します。単なる金額の転記では済まないことが多く、見積書に記載されていない納品場所や支払条件など、細かい点まで自社側で明文化する必要があります。発注書は正式な依頼の証拠となる書類であるため、作成時の文言や記載漏れには注意が必要です。場合によっては、取引先と合意したやり取りをメールなどから拾い直し、文書に落とし込む作業が発生することもあります。特に不具合や納期遅延などが起きた場合、発注書の内容が基準になるため、曖昧な表現を避けるよう心がけましょう。
商品の検収
納品された商品やサービスが、発注内容と合致しているかを確認する工程です。品目や数量、仕様が正確であるかはもちろん、破損や不良がないかといった点も含めて確認します。検収作業を担当するのが自分でない場合でも、誰がチェックし、どのように記録を残したかは把握しておくべきです。検収が完了したということは、請求内容に異議がないと示すことにもつながるため、不備があった場合はこの段階で指摘しておかなければなりません。特にサービス系の取引では、「完了」の判断基準が曖昧になりがちなため、検収の範囲と責任の所在を事前に確認しておくことが重要です。
請求書の受領
取引先から請求書が届いたら、見積書・発注書・検収内容と突き合わせて、金額や条件に差異がないかを確認します。書類上で不明点が見つかった場合は、速やかに取引先へ問い合わせましょう。その際、請求書を再発行してもらう必要もあります。消費税の端数処理や、請求書に書かれている案件名・品目名が自社の管理と異なるケースは、意外と多く発生するものです。そしてこれらの不備を放置したまま支払い処理に進めば、会計記録とのズレが生じます。差し戻しの手間も含めて、やはり確認は疎かにしないようにしましょう。
代金の支払い
支払いは会計上「資金の移動」として処理されますが、このタイミングで費用を計上する場合もあります。請求書の内容に問題がなければ、最終的に社内の承認フローを経て、支払い処理に移りましょう。支払い方法や期日は取引先との取り決めに基づきますが、実務では社内の支払い日程や決裁者のスケジュールも影響するため、余裕をもって手続きを進めることが肝要です。特に月末や四半期末など、社内の処理が集中する時期は、想定以上に時間がかかるものと思って動いた方がよいでしょう。
費用計上の注意点
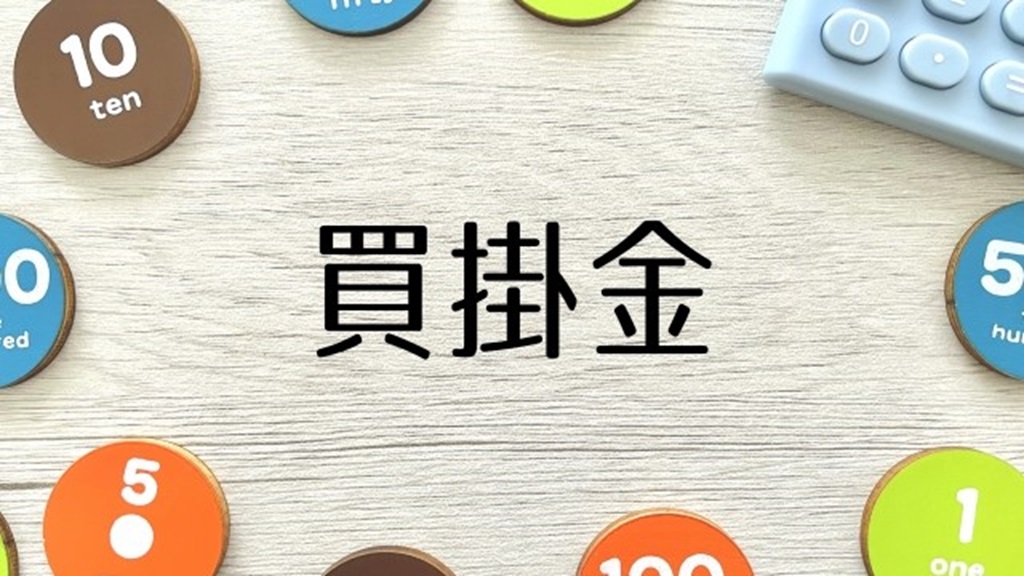
費用計上の注意点として、特に次の3つはおさえておきたいところです。
- 支払い期日
- 買掛金の残高
- 在庫の扱い
以下、それぞれ説明します。
支払い期日
支払い期日は、企業が取引先に対して代金を支払うべき日を指します。支払い期日を守ることは、取引先との信頼関係を維持する意味でも当然のことです。逆にいうと、遅延が続けば取引条件の悪化や信用低下につながる可能性があります。
支払い期日を管理するためには、請求書を受領した際に期日を確認し、スケジュールに組み込めるとよいでしょう。また、期日を見落とさないよう、会計ソフトやカレンダーアプリを活用してリマインダーを設定することも有効です。さらに、支払い期日が近づいた際には資金繰りを確認するのもおすすめします。必要に応じて事前に資金を確保できれば、遅延防止につながります。
買掛金の残高
買掛金とは、企業が仕入れた商品やサービスに対して、まだ支払いが済んでいない金額です。この残高が大きい場合は、多くの未払い債務を抱えていることを意味します。適切な管理が行われていないと、キャッシュフローの悪化や信用の低下につながるでしょう。
買掛金の残高を管理する際には、支払い期日や取引先との条件をしっかりと把握する必要があります。買掛金の増加が一時的なものなのか、長期的な傾向なのかを分析することも大事です。前者は突発的な仕入れの増加が考えられますが、後者なら、経営戦略自体、見直さなければならないでしょう。
在庫の扱い
費用計上において在庫の扱いも要注意です。というのも、仕入れた商品や原材料はすぐに消費・販売されるとは限らないため、「購入した=費用が発生した」とカウントされないケースがあります。会計上では、そういったまだ使われていない在庫は「棚卸資産」として資産に計上されるため、費用にはならないのです。たとえば、期末時点で大量の在庫を保有していた場合、それを費用として全額計上してしまうと、実際よりも当期の利益が小さく見えてしまう恐れは否めません。これは、本来あるべき会計期間と異なるタイミングで費用や収益が計上されてしまう問題につながります。そう、いわゆる「期ずれ」です。
そのため、費用を正しく計上するには、仕入と消費(または売上)のタイミングを分けて考えなければなりません。期末には棚卸を行い、使われなかった在庫を資産に振り替える処理が必要です。これにより、費用の計上が実際の消費や販売と対応し、会計上の整合性が保たれます。 実務においても、仕入伝票や請求書の内容だけを見て費用処理を行うのではなく、それが「すぐに費用化してよいものかどうか」確認を挟みましょう。在庫がある取引では、金額よりもタイミングが重要になる場面も少なくありません。
経費精算の基本
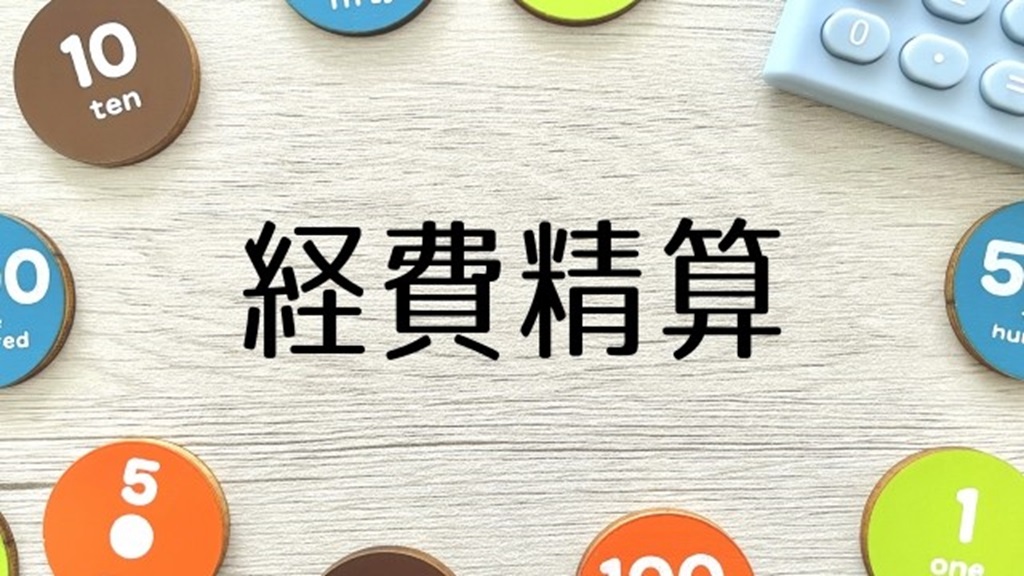
費用計上において、経費精算への理解も大切です。以下、基本中心に説明します。
経費とは
経費とは、事業活動において生じる会社の支出です。事務用品や通信費、交通費、接待費などが含まれます。なお、所得税の計算では、これらの経費を収益から差し引いて課税所得を算出します。
経費で落とすとは
“経費で落とす”とは、前述したような業務上の支出を、実際に会社の経費として処理することを指します。税務調査の際には、その支出が本当に仕事に必要だったのかを確認されることもあるため、領収書や記録を日頃からしっかり残しておくことが大切です。
経費で計上するメリット・デメリット
経費を計上するメリットは、税負担を軽くできる点です。経費として認められた支出は課税所得から差し引かれるため、法人税や所得税の軽減につながります。さらに、収益と費用を正確に把握することで、経営判断や資金のやりくりにも役立てられるでしょう。一方で、経費の処理には手間もかかります。証拠書類の管理や仕訳の記録など、日々の業務が煩雑になりがちです。特に人手の限られた中小企業では負担が大きく、うっかりした記載ミスでも税務調査で指摘されれば、追徴課税の対象になる可能性もあります。
経費で計上できるもの、できないもの
基本的に経費として計上できるのは、業務に関わる支出です。たとえば交通費、事務用品の購入、従業員の研修費用など、いずれも事業活動に必要な支出として認められやすいでしょう。そのほか、人件費やオフィスの賃料、店舗や駐車場の使用料、水道光熱費、電話・インターネットの通信費なども、通常は経費として扱えます。一方で、家族旅行の費用や趣味に関する支出、個人の住宅ローン返済など、業務と無関係な出費は経費対象外です。また、経費にできる項目でも、税務上の扱いには制限があります。たとえば接待交際費は、一定の上限を超えると損金として扱われません。事務用品なども、期末に使っていない在庫が大量にある場合は、資産処理を余儀なくされます。
経費計上で知っておくべき主なルール
経費計上にはいくつかルールが存在します。とりわけ下記3つは必須で知っておきたいことです。
- 一度決めた勘定項目は継続して使い続ける
- 計上可能な固定資産税は事業用の部分に限られる
- 家族を対象に支払う給与は原則経費計上できない
以下、それぞれ説明します。
一度決めた勘定項目は継続して使い続ける
勘定項目とは、企業の財務活動を整理し、記録するために使われるカテゴリーです。大きくは、資産、負債、資本、収益、費用の5つに分類されます。これらによって企業の財務状況を包括的に表現することが可能です。
そのうえで、一度決めた勘定項目は継続して使用しなければなりません。これは、会計処理の一貫性を保ち、財務データの比較可能性を高めるための基本原則です。特に、同じ取引が異なる期間に発生する場合、同一の勘定項目を用いることは、財務諸表の信頼性と透明性を確保します。また、属人性に依存せずに済む点も無視できません。複数人が担当する場合は特に安心です。そうやって、内部統制の強化にも寄与しています。
計上可能な固定資産税は事業用の部分に限られる
固定資産税は、所有する資産の評価額に基づきます。一般的には土地や建物などの不動産に対して課されるものです。
ただし、費用として計上可能な固定資産税は、事業用として使用している部分に限られます。自宅の一部を事業所としている場合などは、これが当てはまるわけです。なお、経費として計上する際は、事業用部分の面積比率や使用割合を正確に計算し、それに基づいて税金を按分する必要があります。税務調査時に適正か否かを問われるケースも想定しておきましょう(すなわち、間違わないよう慎重に計算しましょう)。
家族を対象に支払う給与は原則経費計上できない
一般的に、事業主が家族に対して支払う給与は、原則経費計上できません。というのも、その家族が実際に事業に従事し、かつ業務内容に見合った対価であることが条件だからです。それが明確でない限り、経費としての計上は難しいでしょう。
これを可能にするには、具体的に、家族が実際にどのような業務を行っているのかを詳細に記録し、その給与が市場相場と比較して妥当であるかを証明しなければなりません。業務内容の説明や、類似の業務に従事する一般労働者の給与水準と比較した資料なども求められます。
経理や会計担当者の採用におすすめのサービス

費用計上は、高い専門性が求められる業務です。些細なミスと思えても、実際は組織全体に大きく影響することもざらにあります。
だからこそ、費用計上の経験が豊富な経理のプロフェッショナルを採用することも対策の一つです。かといって漠然と求人サービスを選ぶわけにもいきません。せっかくなら有資格者やスキルフルな人材が集まるサイトを選びたいものです。
なお、dipが提供する『バイトルPRO』は、まさにそうした即戦力人材が集まりやすい傾向にあります。ミスマッチを避ける機能も十分に搭載されているため、安心してお使いできるはずです。
費用計上の理解と適切な人材の採用が業務を円滑にする!

費用計上は、単なる帳簿作業ではなく、企業の経営や税務にも直結する重要な会計処理です。そのため、適切なタイミング、基準に沿って取り組むことが、財務の健全性を保つうえでは欠かせません。また、その前提である経費精算や在庫の管理、帳簿処理の整合性を含め、全体としての流れやルールを理解しておくことも求められます。さらに、実務を支えるには、会計処理に精通した人材をいかに確保できるかも課題になってくるでしょう。いずれにしても、業務を円滑にすべく、広い視野で捉えることが大事です。
求人掲載・採用業務のサポートや料金についてなど、ぜひ気軽にお問い合わせください。
また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談も無料で承っております!
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【公式】空いた時間のスポットワーカー募集ならスポットバイトル
┗空いた時間で「働きたい」と「働いてほしい」をつなぐ求人マッチングサービス。求人は無料で掲載できます。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。
▶【公式】面接コボット – 応募者対応の自動化で面接管理が楽に!
┗求人サイトからの応募対応を自動化できるサービス。チャットボットを通じ、日程調整まで効率よく進めてくれます。
▶【公式】採用ページコボット – 費用・実績も紹介!採用サイト制作サービス
┗採用ページ作成サービス。求人まとめサイトとの自動連携や求人検索エンジンへの対応により外部集客を強化します。
【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所
代表 荒武 慎一
同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。