パートでも産休制度は適用される

まずは産休取得の対象者や条件、育休との違いについて説明します。
雇用形態を問わず産休は取得できる
労働基準法では、正社員に限らず、条件を満たしていれば派遣社員、パート、アルバイトも産休・育休制度を取得できると定められています。そのなかで企業は産後8週間を経過していない女性を就業させてはいけない決まりです。
産休・育休の権利は労働者を守るために法律で認められています。子供を安心して産んで育てるためにも、こうした制度は積極的に利用することが大切です。
社員以外の産休の取得率
産休には「戻る場所があるという精神的な安心感」「保育園の入所の申し込みの際、働いていない場合よりパートのほうが断然有利になる」など、さまざまなメリットがあります。
しかし、労働政策研究・研修機構が2015年に実施した、企業と非正規社員に対して行ったアンケートによると、「産休・育休を実施している企業」は、契約社員などのフルタイム雇用労働者で3割、パートタイマーで約4割と、いずれも半数以下という結果が出ています。社員以外の産休・育休は多くの企業で浸透していないのが現実です。
産休と育休の違い
産休は、正式名称を「産前産後休業」といい、出産する本人であれば誰でも取得することができます。産前休業は、出産予定日の6週間前から取得可能です(双子以上の場合は産前14週間前から取得可能)。一方で産後休業は文字どおり出産後に取得できます。出産の翌日から8週間経過するまで就業できませんが、本人が希望し、医師が認めた場合は産後6週間から出勤が可能です。
一方、育休は「育児休業」を指します。就業先に申し出ることで、子どもが1歳になるまでの間、育児のために休業できる制度です。保育園が見つからないなど特別な理由があれば、2歳まで延長することもできます。産休と違い、男女ともに取得可能です。
従業員の産休中に企業がすべきこと

企業は従業員から妊娠の報告を受け出産が終わるまでに、いろいろと手続きを行わなければなりません。そのため、タイミングを見計らい、申請漏れがないよう注意する必要があります。
産休に関わる各手続きをスムーズに進めるためには、以下の流れを参考にしてください。
産休取得のための必要事項の確認
従業員から妊娠の報告を受けたら、まずはしっかりと妊娠・出産・育児に関して利用できる制度や給付金などについて説明します。
また、男女雇用機会均等法により、妊娠や出産などを理由に解雇その他不利益な扱いをしてはいけないことはもちろん妊娠中の働き方についても女性従業員の希望を尊重しなければなりません。たとえば、産後6週間こそ必ず休業する必要がありますが、産前6週間は従業員が希望すれば働くことを許可することになります。そのうえで以下の内容を従業員に確認します。
- 出産予定日
- 最終出社日
- 産休取得の有無
- 復帰予定日(復帰する場合)
さらには、里帰りして出産する従業員もいるため、手続きが遅れないようあらかじめ書類の届け先や給与振込先についても確認しておきましょう。 加えて、従業員が「産前産後休業取得者申出書」を用意しているか否かも聞いてください。これによって従業員は、健康保険や厚生年金保険などの社会保険料免除を受けることができます。 提出先は日本年金機構です。出産前もしくは出産後に提出します。社会保険料の免除期間は、産休開始月から終了月の前月まで(産休終了日が月末日の場合はその月まで)です。原則、企業側が届けます。書類は郵送のほか電子申請も可能です。
なお、産休における休業期間の割り出しは出産予定日を起点にします。そのため、出産前に提出すると、予定日を過ぎて出産した場合に「産前産後休業取得者変更届」の提出が必要です。この手間と予定日に確実に出産できるケースが稀なことを考えると、特別な事情でもない限り、出産後の休業中に提出する方が良いかもしれません。
扶養追加の申請を行う
従業員が会社の健康保険に加入している場合、出産後に出生届を提出して戸籍を取得してもらい、会社経由で「扶養追加の申請」を行ってください。生まれた子どもを従業員の扶養親族にすることで保険証が発行されるため、病院で受診した際など従業員個人の負担額を減らせます。
国民健康保険は手続き後から発行まですぐですが、健康保険の場合は扶養追加の手続きから保険証の発行まで2~3週間かかります。従業員を思えば、子どもの1カ月検診に間に合わせるように、生後5日以内には日本年金機構に書類を提出しておきましょう。
産休後の育児休暇手当について
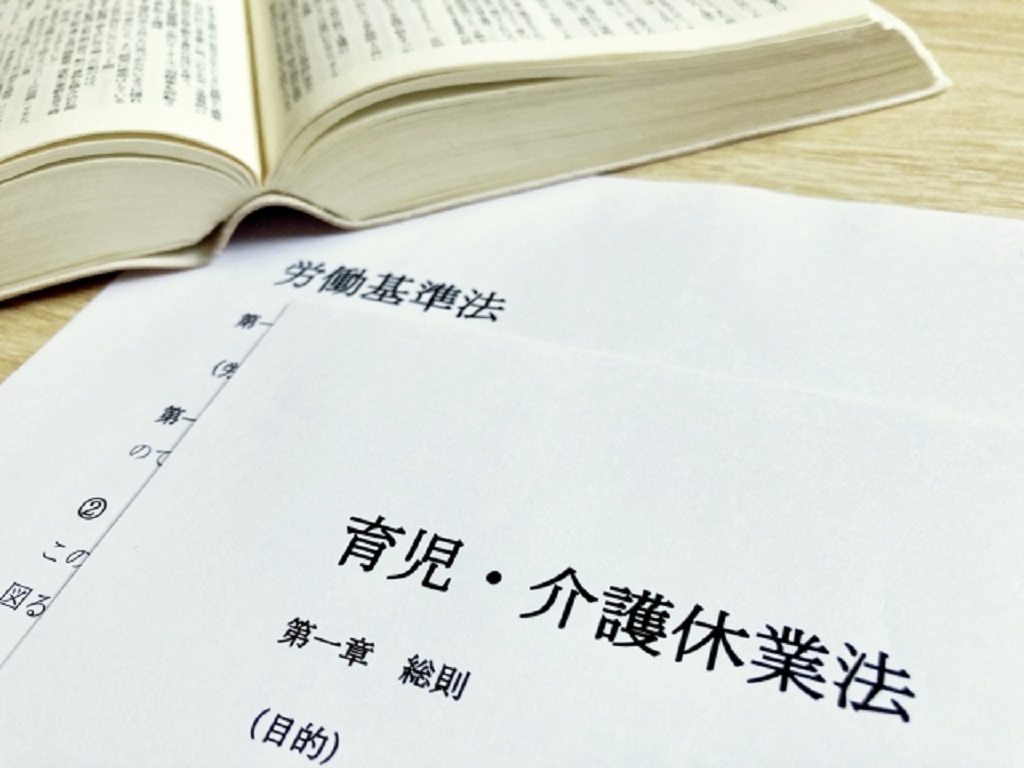
一般的に産休が終了すると、ほとんどの女性が育児休業に入ることが考えられます。そのとき大切な収入源になるのが育児休暇手当です。 以下、くわしく解説します。
育児休暇手当とは?
育児休暇手当(育児休業給付金)とは、育休を取得した従業員が給与を受け取っていない期間、収入面を安定させるために支給される手当のことです。育児休暇手当は、働いている企業ではなく国からの給付金で雇用保険に一定期間加入していれば、派遣社員やパート、アルバイトでも受給することができます。そう、雇用形態に関係なく受け取れるわけです。
また、受給対象は出産した女性だけに限りません。配偶者に当たる男性も受け取ることが可能です。
育児休暇手当の条件
育児休暇手当が支給されるための条件は次のとおりです。
- 休業前に雇用保険に加入している
- 育児休業中の就労日数が1カ月で10日以下(10日を超える場合は勤務時間が月80時間以下)
- 育児休業前の80%以上の賃金が支払われていないこと
- 育児休業を開始する時点で育児休業終了後に退職予定がないこと
特に注意したいのが、退職の予定がある場合、育休を取得すると支給対象から外れてしまう点です。育児休暇手当は育児休業終了後に職場復帰することが前提にあります。そのため、原則として「育休終わりで退職してしまうのは対象外です。
育児休暇手当で支給される金額
育児休暇手当は休業する前の給料全額が補償されるわけではありません。支給される金額は、育休開始からの日数によって異なります。
育児休業開始から180日目までは「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」が計算式です。一方、181日目以降は「休業開始時賃金日額×支給日数×50%」で算出されます。
ちなみに、休業開始時賃金日額の計算式は「育児休業開始前の6ヶ月間の給料 ÷ 180日」です。
育児休暇の期間
育児休暇手当は、育休を取得して給与をもらっていない期間で、基本的には育児休業開始日から子どもの1歳の誕生日の前日までが支給対象(期間)です。
ただし、保育園に申請しているにもかかわらず、1歳になろうとする子どもがいまだ入所待ちの状態といった特別な理由がある場合には、2歳になるまで延長することができます。
パートの産休についてよく理解し、働きやすい環境づくりを!

パートの産休に伴う手当は、従業員とその家族の今後の生活に関わります。企業側は産休についてよく理解し、各手続きを適切なタイミングでスムーズに行うことが大切です。
日頃より常に女性従業員が働きやすい環境づくりを意識しながら、手続きミスなどがないように、手順をマニュアル化したり、状況に応じては効率化を図れる専用ソフトやシステムの導入も検討してみましょう。
そうしたなか、産休中の従業員の代わりとして、有期雇用を考えている企業も多いと考えます。そこでおすすめしたいのが、アルバイト・パート採用向け求人サイトの「バイトル」です。
また、社員志向の求職者にアプローチするなら「バイトルNEXT(ネクスト)」の利用がうってつけ。 ドライバー、飲食をはじめ幅広い業種で社員採用の実績を持つサイトです。多くの求職者へアプローチできる点は大きなメリットだと考えます。採用活動を効率的かつ有意義に進めてくれるはずです。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら

