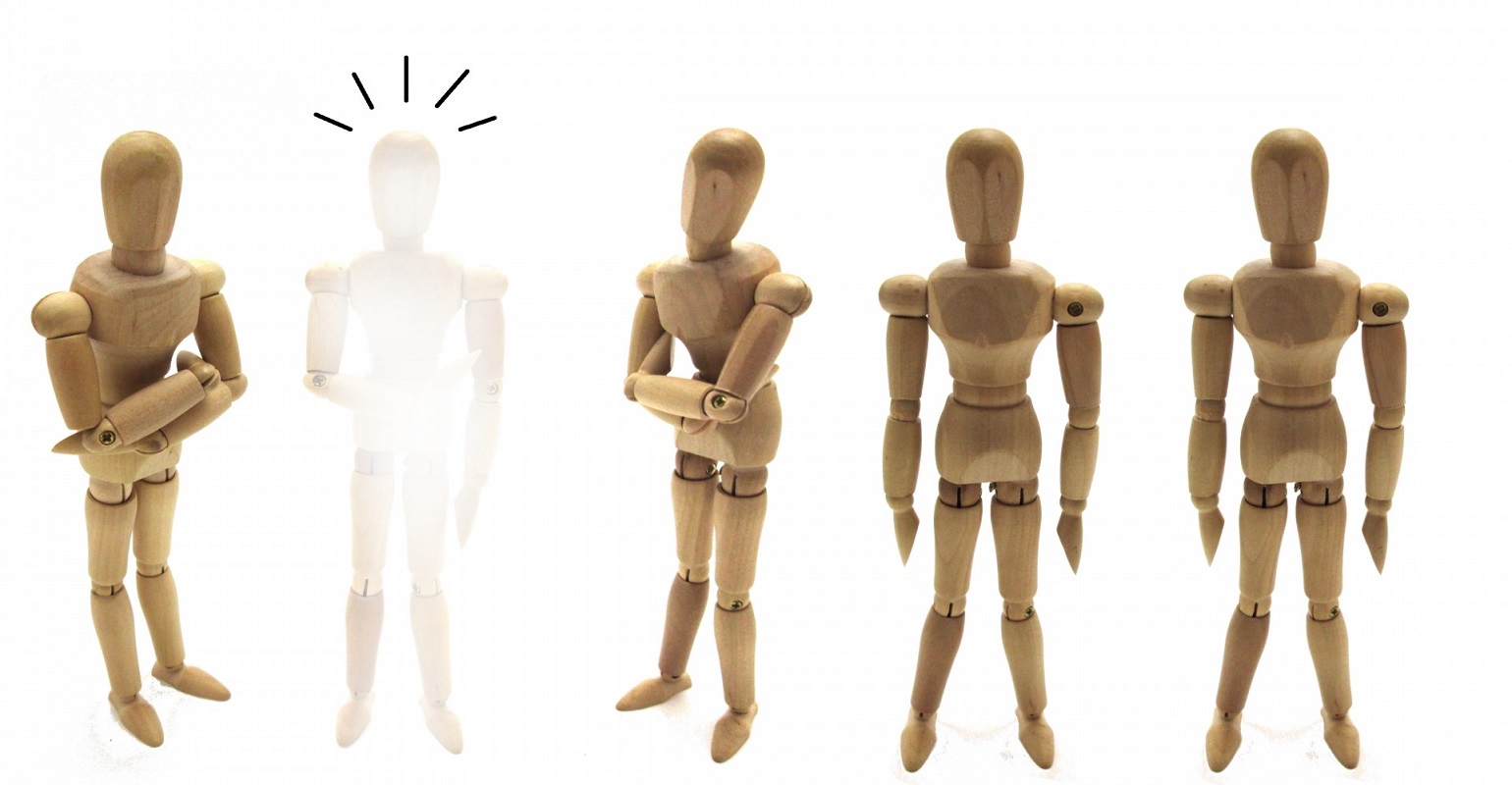アルバイトが無断欠勤した際の対応

「アルバイトが何も連絡せずに休んでいる」
「出勤していないアルバイトから電話がこない」
バイトに限らずですが、従業員の無断欠勤は一緒に働く方々にとって大変迷惑です。
このとき、彼・彼女らを管理する側はどのように対応すればよいのでしょうか。
管理登録している電話番号やメールアドレス宛てに連絡を入れる
まずは、とりあえず連絡するという選択があります。無断欠勤をする理由は、人それぞれです。なかにはうっかり寝過ごしてしまったり、シフト変更の連絡ミスなどで出勤日を忘れてしまったりといったケースも考えられます。そのため、1本の電話で解決するケースも少なくありません。
アルバイトが無断欠勤をするには何らかの原因が存在し、特に、今まできちんと出勤していたアルバイトの場合は、何か深い事情があるかもしれません。また、通勤中の事故や急病により連絡が取れないことも想定できます。安否確認を兼ねて、まずは企業側からメールや電話で連絡をとり、その際は決して相手を責め立てるのではなく、対話あるいは返信しやすい状況を作りましょう。
仮に連絡が取れた場合は、無断欠勤の理由とあわせて何時からだと出社できるのかなど聞き出し調整を行います。もちろん、当日すぐの出勤が難しいことも考慮しましょう。そのため、並行して代わりのアルバイトを探しておくことも必要です。
一方で、無断欠勤した本人から連絡があった場合は、まず相手の話にじっくり耳を傾けます。一とおり経緯を把握したうえで前向きな話ができそうなら、上述同様、無断欠勤の理由とあわせて出社できる時間帯などを聞き出し調整を図ってください。
緊急連絡先とコンタクトをとる
無断欠勤をしたアルバイトといつまでも連絡がとれない場合、緊急連絡先へとコンタクトをとる必要が出てきます。そう、家族などの身元保証人への連絡です。万が一事件や事故に巻き込まれている可能性もあります。無断欠勤している状況を伝えたうえで、ひとまず安否確認を優先しましょう。一とおり話を終えたなら、最後に本人から職場に連絡することをお願いしてください。
どうしても連絡をとりたいなら自宅への訪問も検討
では、緊急連絡先にも連絡がつかない場合、一体どうすればよいのでしょうか。ここからはやや踏み込むすぎる内容のため安易に推奨できませんが、どうしても連絡をとりたければ強行するのも一つの手だと考えます。それはずばり、そのアルバイト従業員の自宅を訪問することです。さらには、自宅を訪れインターホンを鳴らしても反応がなければ、管理会社に確認してもらうこともできなくはないです。(何より安否確認が大事ですが、それはそれで問題になるおそれがあるため)状況に応じて判断してください。
無断欠勤した翌日以降もアルバイトから電話がこないときは?

無断欠勤したアルバイトに対しては、可能な限り連絡を取り続けることが大事ですが、それでもまったくリアクションがなかったり、督促に応じてくれなかったりといった場合もあります。
にっちもさっちもいかないなか、しかるべき行動を何か?以下、お答えします。
内容証明郵便を送る
無断欠勤した翌日以降も相変わらず音沙汰なければ、内容証明郵便を送るという手も一つです。具体的には指定の期日までに連絡がない場合、出社の意思がないものとみなし、自己都合退職として扱う趣旨の文言を相手に送ります。
最低限譲歩しつつ、確実に問題解消へと進めるにはもってこいの方法です。そうした記録が残れば証拠としても機能します。少なからずトラブルのリスクを軽減あるいは回避できるものと思われます。
備品回収の連絡
携帯、パソコン、タブレット、鍵、制服など従業員に貸与している備品があれば当然、回収する必要があります。それゆえ「本人と連絡がとれない」「会社からの督促に応じない」場合は、こうした大義名分(返却依頼)を盾に留守番電話やメールで記録を残し、相手の動向をうかがうのも有効です。その際、貸与物の内容と返却されていない事実、返却期限を伝えるようにしてください。
いずれにせよ、社用の携帯電話やパソコンなど個人情報を含んだものであれば、未返却によって企業側も重大な損害が生じる可能性があります。事件に巻き込まれるリスクも想定し得ることです。半ば強引にでも返却してもらう姿勢で対応しましょう。
退職・解雇手続き
無断欠勤が続くアルバイトとどうしても連絡がつかない場合は、退職もしくは解雇手続きを実行することもやむを得ません。しかし、決して安易に行えるものではないため注意も必要です。できれば、あらかじめ自然退職として扱う(無断欠勤の)日数を自社の就業規則内の条文に記載することを推奨します。加えて、社会保険と雇用保険の喪失手続きも進めておきましょう。
ばっくれたアルバイトの対処における注意点

無断欠勤が続くアルバイト従業員の対処としては、前述のとおり最終的には退職してもらうことがほとんどです。一方でいくつか注意点があることもおさえておきましょう。
以下、具体的に挙げます。
割に合わない損害賠償請求
アルバイトが無断欠勤したことによって、急遽新たな従業員を雇わなければならないケースも少なくないでしょう。当然、そのために手間や費用、とりもなおさずコストが掛かってきます。単純に企業にとっては予定外の負担です。それゆえ渦中のアルバイトに対して損害賠償の請求を検討することもあるかもしれません。しかし、これが思いのほか一筋縄ではいかないのです。というのも、損害と無断欠勤の因果関係を立証するのは難しく、実際に(損害が)認められた場合でも企業側が期待するような賠償金額を得られるケースはほとんどありません。したがって、無断欠勤だけで企業がアルバイトに損害賠償を請求することは得策とはいえないでしょう。
就業規則はあくまで企業ルール
アルバイトの無断欠勤が続く場合の対応については、就業規則に定めている規則をしっかりと確認しましょう。「無断欠勤が〇日以上続いた場合には、本人の意思に関係なく退職扱いとする」などが一般的です。
ただし、それはあくまで自社の就業規則で決めたことであり、法律で定まっているわけではありません。そのため、従業員が入社するタイミングで無断欠勤に対する処置への認識をしっかり浸透させるまたは教育することが大切です。
解雇手続きの際は不当解雇などに留意する
アルバイトを不当解雇すると、損害賠償を請求される可能性があります(民法709条)。これは、会社の不法行為に基づくもので、慰謝料などを請求されるのが一般的です。
そのため、無断欠勤をしたアルバイトに対して就業規則に則り対応する際、いきなり“解雇”ではなくまずは“指導”を行い、その後は 以下のような段階的処分に移るというプロセスを踏む必要があります。
| <解雇にいたるまでの対処フェーズ> 指導→出勤命令→軽い懲戒処分→重い懲戒処分(解雇) |
手順を誤ると、処分の違法性を問われるおそれがあります。解雇後のトラブルも十分に考慮し、不当解雇にあたらないよう注意しましょう。
バイトの無断欠勤や無断退職を防ぐ方法

そもそもアルバイトの無断欠勤や無断退職を防ぐにはどうすればよいのでしょうか。
以下、企業側のアクションについて言及します。
就業規則を設け、明確に説明する
あらかじめ就業規則に、無断欠勤した場合の対応を記載しておくことは、もはや必須といってもいいほど基本的な対策です。ただし、それだけでは効果は薄いでしょう。あくまで大事なのは認識してもらうことです。入社オリエンテーションや面談など従業員と接点を作れる場でしっかりと説明しておきましょう。当たり前のこととはいえ、無断欠勤を禁じる職場であることを強く訴えかける努力が必要です。
決めた規則を反故にしない
前項のように就業規則内でルールを設けしっかり把握してもらうことはもちろん大事ですが、実際に無断欠勤を行った従業員に対して適用できていなければ説得力がありません。曖昧な状況が一たび目に入れば、アルバイト一人ひとりの意識は傾き、どんどん無法地帯が広がります。そうならないためにも、決めた規則は反故にせず毅然とした態度で対処するようにしましょう。
積極的にコミュニケーションを図る
アルバイトが無断欠勤や無断退職する背景には、職場環境に対する不満が原因の可能性もあります。これらを防止するためには、アルバイトとコミュニケーションがとりやすい職場づくりが肝要です。
アルバイト一人ひとりに対し、不満がないかを定期的に確認する場を設けることはもちろん、そこで感謝を伝えるなどモチベーションアップに寄与するアクションを心がけましょう。
バイトの無断欠勤は丁寧かつ適切に対処しよう
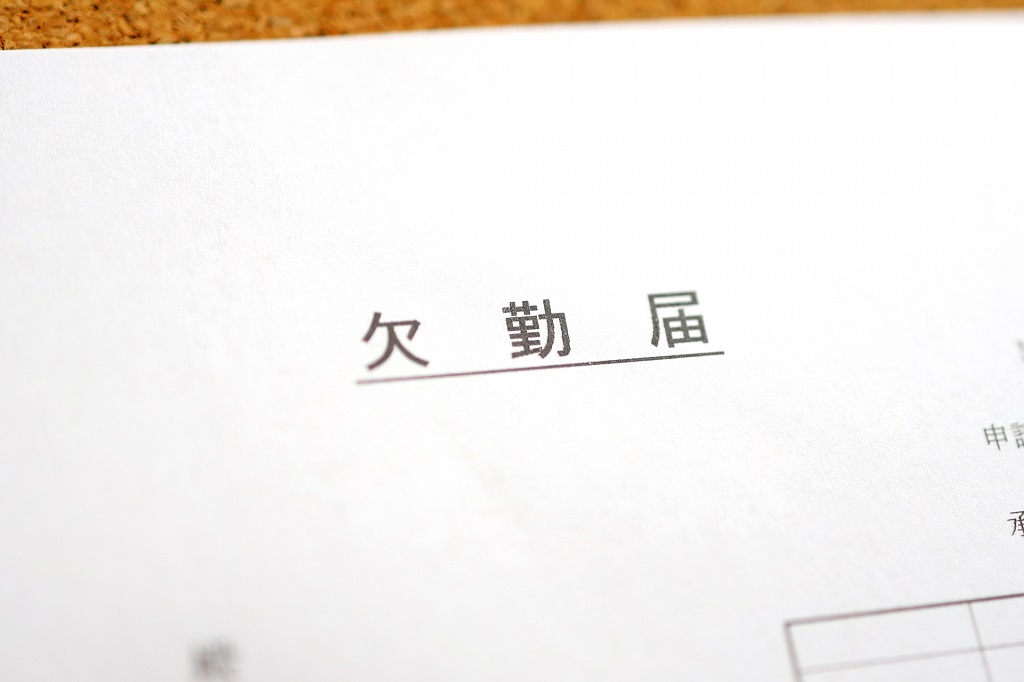
無断欠勤は決して社会人として認められる行為ではありませんが、企業側も対処の仕方によっては事を穏便にすませることもできるため、意識的な取り組みが大事だといえます。労務管理や職場環境の見直しなどは最たる例かもしれません。まずはアルバイトの無断欠勤を防ぐ努力から進め、そのうえで発生した場合には連絡先の範囲を広げるなどできることから実行し、それでも埒が明かないのであれば、退職や解雇の方向へと舵切りするようにステップを踏んで対処することが大切です。また、解雇に関しては、まさしく段階的処分がを後々トラブルにならないためにも有効なやり方だと考えます。当然、就業規則のなかで無断欠勤に対する処分の明記も必要です。組織内での認識の浸透も欠かせません。
結論、こうした一つひとつを丁寧に対処することが企業側には求められます。
上記踏まえてアルバイトの募集をお考えの担当者の方には、求人掲載サービスのバイトルをおすすめします。内容はもちろん、選べる料金プランなど、まずはご希望に適ったサービスかどうかを確認してみてください。なお、お問い合わせは無料で承っています。ぜひ、ご検討ください。