賞与とは?
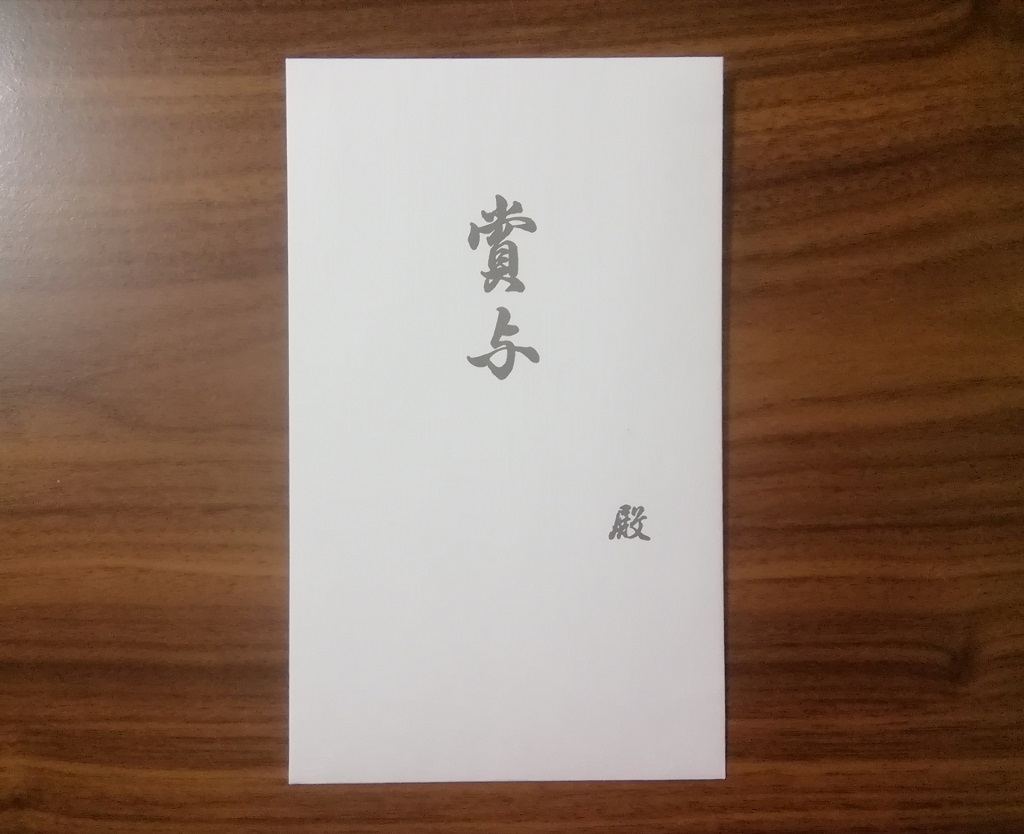
賞与とは、毎月の支払いが義務づけられている給与とは別に支払う、特別な報酬を指します。「ボーナス」「特別手当」など呼び方はさまざまですが、一応、健康保険法・厚生年金保険法において定義づけられている概念は「3ヶ月を超える期間ごとに支払われるもの」です。そのため、年4回以上支払われる場合は賞与に該当しません。これは月次給与として扱われます。
また、賞与は決して現金に限られたものではありません。自社製品などで支給するケースもあります。
賞与の対象者は基本的に企業側の裁量で決められます。そのうえで現状、該当するのは、正社員のみがほとんどのように見受けられます。契約社員やアルバイト・パートタイマーなど非正規雇用の従業員は、大抵、賞与対象外です。稀に少額で支給されるケースもみられますが、国内企業における賞与の有無に関してはやはり、雇用形態で明確に線引きされています。
賞与に掛かる社会保険料について

さて、ここからは本題でもある賞与と社会保険料の関係について言及していきます。
賞与に社会保険料が掛かるようになった背景
かつてはそうでありませんでしたが、平成15年度以降、総報酬制の成立によって、月給以外、すなわち賞与からも社会保険料は徴収されるようになりました。法律上、控除の対象になってしまったわけです。もちろん現在も、賞与に社会保険料は掛かります。
退職した従業員の賞与に社会保険料は掛かるのか?
加入していた健康保険や厚生年金から抜けることを「資格喪失」といいます。それぞれ手放したその日が「資格喪失日」、該当月が「資格喪失月」です。
仮に賞与支給月に退職予定の従業員がいたとしましょう。なんとこの場合、「資格喪失月」と重なるため社会保険料は掛かりません。
たとえば、12月上旬に冬の賞与の支給を受け、12月20日付けで退職する従業員は、「賞与支給月」が12月で社会保険の「資格喪失月」も12月として扱われます。まさに上述したケースです。それゆえお察しのとおり、社会保険料の徴収対象には当たりません。
賞与支給時に必要な手続き

賞与支給の際には書類の提出など、事業主は別途、手続きが発生します。それらに対して、つい不要だと思い込んでいるものもあるかもしれません。以下、くまなくチェックしてみてください。
被保険者賞与支払届の提出は必須!
通常、賞与を支給すると、5日以内に健康保険組合および日本年金機構へ「被保険者賞与支払届」を提出する義務があります。そこで保険料を計算する根拠に当たる標準賞与額が決まる流れです。知っておきたいポイントとしては、賞与が社会保険料の徴収対象にならない場合でも上記の書類(被保険者賞与支払届)は提出しなければならないこと。これは、健康保険の標準賞与額が「資格喪失日」の前日までに支給されたすべての賞与で計算されるからです。
賞与支払届と賞与支払届総括表
賞与を支給した際、事業主は5日以内に「賞与支払届」と「賞与支払届総括表」を管轄の年金事務所と健康保険組合に提出しなければなりません。気を付けたいのは後者に関してでしょう。仮に賞与の支給がなかった場合でも「不支給」と記載して届ける必要があります。
賞与引当金の処理
賞与は「賞与引当金」として会計処理を行わなければなりません。「賞与引当金」とは、将来的に発生する可能性のある費用や損失に対する備えです。決算時において、翌期に支給する予定の賞与や、当期に属する金額を見積り計上するための負債科目を指します。
賞与明細書の発行
賞与明細書の発行も忘れてはいけません。事業主は、厚生年金保険法と健康保険法の規定により、賞与の支給に伴って発生する社会保険料と所得税の控除額を、対象の従業員へ通知する義務があります。そこで発行するのが、控除額を記した明細書(賞与明細書)です。
社会保険料を左右する標準賞与額とその上限

賞与には健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料の4つの社会保険料が掛かりますが、そのうち雇用保険料を除く3つに関しては、計算する際、根拠に置くのが標準賞与額です。標準賞与額は、賞与額(支給合計)から1,000円未満の端数を切り捨てた数字が該当します。
また、社会保険料には掛かる額に一部上限があることも把握しておきましょう。健康保険料の場合、年度単位で上限が設けられています。その額は、毎年4月1日~翌年3月31日までの累計で573万円です。そして、厚生年金保険料に関しては「1ヶ月あたり150万円」が上限として定められています。それぞれオーバーした分の保険料は、掛かりません。なお、標準賞与額が関わる社会保険料の計算方法については、次章で、よりくわしく解説しています。
賞与に掛かる社会保険料の計算方法

賞与の総支給額から控除される社会保険料の計算式は、次のとおりです。
| (標準賞与額×健康保険の保険料率÷2)+(標準賞与額×介護保険の保険料率÷2)+(標準賞与額×厚生年金保険の保険料率÷2)+(賞与額×雇用保険の保険料率) |
保険料ごとに計算方法は異なります。算出するにあたって以下、それぞれご参照ください。
健康保険料の計算方法
健康保険料は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額(標準賞与額)に健康保険料率を掛けて算出します。その際、健康保険料率は都道府県で異なり、毎年更新される点に注意しましょう。
健康保険料は、企業と従業員が半分ずつを負担します。つまり、標準賞与額に健康保険料率を乗じた額を2で割った数が個人の健康保険料です。
| <健康保険料の計算例> 標準賞与額×健康保険料率=健康保険料(総額) 令和4年4月にAさん(40歳、扶養親族なし)に賞与50万円を支払う場合。 ・50万円×9.81%÷2=24,525円(Aさんの健康保険料※東京都の例) |
厚生年金保険料の計算方法
健康保険料と同様に、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額(標準賞与額)に厚生年金保険料率を掛けて算出します。また、負担額も健康保険料と同じく企業と従業員が半分ずつです。したがって個人の分は、標準賞与額に厚生年金料率を乗じた額を2で割って算出します。
| <厚生年金保険料の計算例> ※厚生年金保険料率は2017年9月以降、一律「18.3%」です。 標準賞与額×厚生年金保険料率=厚生年金保険料(総額) 令和4年4月に、Aさん(40歳、扶養親族なし)に賞与50万円を支払う場合。 ・50万円×18,3%÷2=45,750円(Aさんの厚生年金保険料) |
介護保険料の計算方法
介護保険料もまた、上述した2種類と同じく、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額(標準賞与額)に介護保険料率を掛ける計算です。そして健康保険料同様、その割合は都道府県別に設けられ、毎年更新されます。
介護保険料の徴収対象となるのは、40歳以上65歳未満の従業員です。
企業と従業員が半分ずつ負担するため、標準賞与額に介護保険料率を乗じた額を、2で割って算出します。
| <介護保険料の計算例> 標準賞与額×介護保険料率=介護保険料(総額) 令和4年4月に、Aさん(40歳、扶養親族なし)に賞与50万円を支払う場合。 ・50万円×1,64%÷2=4,100円(Aさんの介護保険料※東京都の例) |
雇用保険料の計算方法
雇用保険料は、ほかの3つの社会保険料の計算とは異なり、賞与額(1,000円未満を切り捨てない値)に保険料率を掛けて算出します。特筆すべきは、保険料率が事業の種類や、労働者か事業主かで変わる点です。ちなみに、一般事業がもっとも低く、建設事業がもっとも高く設定されています。加えて、毎年見直されていることも把握しておきましょう。
| <雇用保険料の計算例> ※雇用保険料率は、令和4年10月以降に0.5%へ引き上げられました。 賞与額×保険料率=雇用保険料(総額) 令和4年10月に、Aさん(40歳、扶養親族なし)に賞与50万円を支払う場合。 ・50万円×0.5%(一般事業の労働者負担)=2,500円(Aさんの雇用保険料) |
賞与に掛かる社会保険料への理解を深め管理ミスを未然に防ごう

賞与に関する社会保険料の計算は、扱い慣れていない人には難しいと感じるかもしれません。しかし、本記事で紹介したように、順を追って公式に照らし合わせていけば、意外と苦にならず済むかと考えます。まずは賞与の概念、そして社会保険料の構成などをしっかりと理解して、あとはミスのないよう正確に計算していきましょう。
さて、本記事は経理に関する内容をお届けしましたが、実際のところ、一つの分野に限らず人事業務全般で負担を軽減をしたいとお考えの企業担当者の方は、多くいらっしゃるかと存じます。そこでおすすめしたいのが AI・RPAを活用したDXサービス「コボット」です。内容ご確認のうえ、導入ご検討、はたまた気になる方はぜひお問い合わせください(お問い合わせは無料です)。
【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所
代表 荒武 慎一
同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。

