パートとは?アルバイトとは?

パートとアルバイト。まずは、それぞれについて定義や特徴を確認していきます。
パートとは?
パートとは、英語の「part time」または「part timer」が語源の、短時間労働者を指します。正社員なら(あるいはアルバイトとして働く場合でも)、フルタイム勤務が一般的であるのに対して、パートは日・週・月単位で稼働時間を減らし従事される方がほとんどです。それは、上述した定義どおりのまさしく最たる特徴でしょう。
そもそもの経緯は1954年、大丸百貨店が新聞広告で3時間だけ働ける女性を「パートタイム」として募集したことに端を発します。以降、定着したこの労働スタイルは、主婦や主夫が家事の合間を縫って行うイメージとも結びつき、現在、一つの雇用形態として確立されています。
アルバイトとは?
アルバイトは、ドイツ語で労働を意味する「Arbeit」が語源です。生来的には仕事や働きを示す言葉ですが、日本では本業や生活の目的が別にあり、そのかたわらで働く形が一般的かもしれません。
パート同様、短時間勤務も多く、主に学生が家庭教師のお仕事や飲食店のお手伝いなどを行うイメージが(アルバイトに対しては)特に根強いように見受けられます。
パートとアルバイトの違いは法的に明示されている?
「パートタイム労働法」では、パートもアルバイトも“1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の、1週間の所定労働時間に比べて短い労働者”と定義されています。裏を返せば、法的に違いは確認できません。他方、企業の扱いをみていると、いくばくか線引きできるポイントも浮かび上がってきます。
たとえばパートの場合、1日2~4時間程度、週2~3回、比較的長期間働ける主婦あるいは主夫に向けたものが多い傾向にあります。アルバイトだと、在職期間にかかわらず3~8時間程度、週3~5回は働いてくれる方に向けた印象が強いです。なかには、週5日・8時間のフルタイム相当働ける方に向けたアルバイト求人の広告や募集要項なども散見されます。
パートとアルバイトで社会保険の加入条件に違いはある?
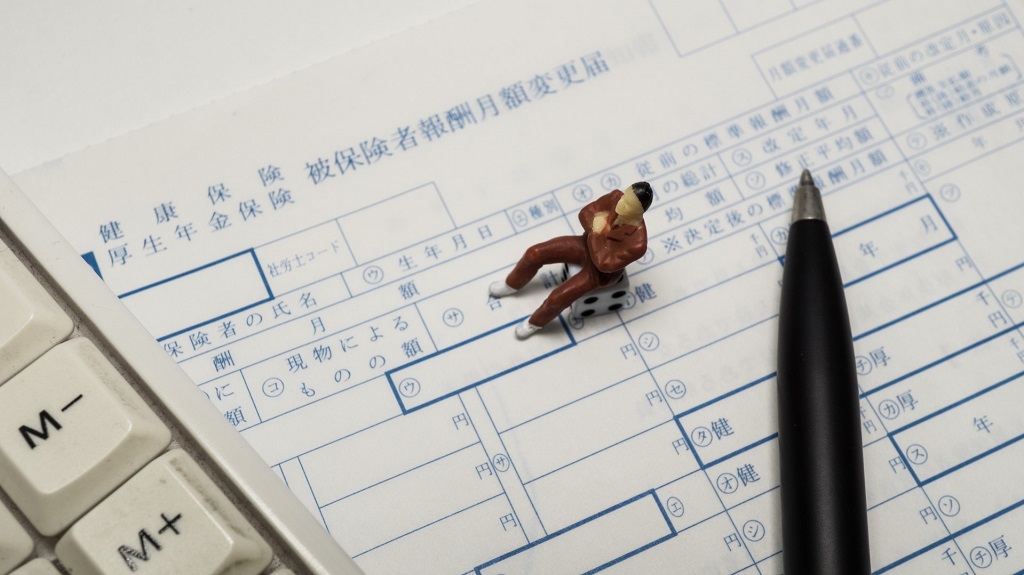
パートとアルバイトの違いについてよくある質問が、社会保険に関することです。以下、それぞれの加入条件を取り上げ説明します。
パートとアルバイトの社会保険加入条件
ときおり見かけるのですが、社会保険の加入を正社員の特権だと思われる方がいらっしゃいます。実際のところ、パートやアルバイトであっても勤務状況によっては社会保険への加入が可能です。
そしてその条件は、パートもアルバイトも変わりません。具体的には、次のとおりです。
- 所定労働時間が週30時間以上、または所定労働時間が週20時間以上で、以下の条件に当てはまる
- 月額賃金が8.8万円以上
- 勤務期間が1年以上見込まれる
- 従業員数が500人以上、または従業員数が500人以下でも(社会保険の加入を)労使で合意済み
ただし、学生は除外されます。
また、下記のケースでは家族の扶養から外れ、自ら保険に加入しなければなりません。
- 年収が130万円を超える(交通費などの手当も含む)
- 雇用形態にかかわらず、フルタイムで週3.75日以上定期的に勤務する
- 企業規模が100名以下の場合、正社員の労働日数・時間のうち3/4以上勤務する
106万円の壁
パートやアルバイトは、年収がある一定の額を超えると、配偶者の扶養から外れ、勤務先の社会保険へ加入しなければならなくなるケースが生まれます。ずばり、その額は106万円です。いわゆる106万円の壁が立ちはだかります。
年収106万円を超え、なおかつ次の条件に当てはまれば対象です。もちろん、これらは雇用形態を問いません。
- 週の労働時間が20時間以上
- 賃金の月収が88,000円以上
- 雇用期間が2ヶ月を超えることが見込まれる
- 従業員(厚生年金の被保険者)が101人以上いる企業(※2024年からは51人以上に緩和される予定 )
- 学生ではない(定時制は除く)
なお、パートとアルバイトの社会保険加入については以下の記事でもくわしく解説しています。あわせて確認することでより理解は深まるでしょう。
▶関連記事:アルバイトの社会保険加入について、条件や義務化の流れなどくわしく解説
パートとアルバイトで税金控除に違いはある?
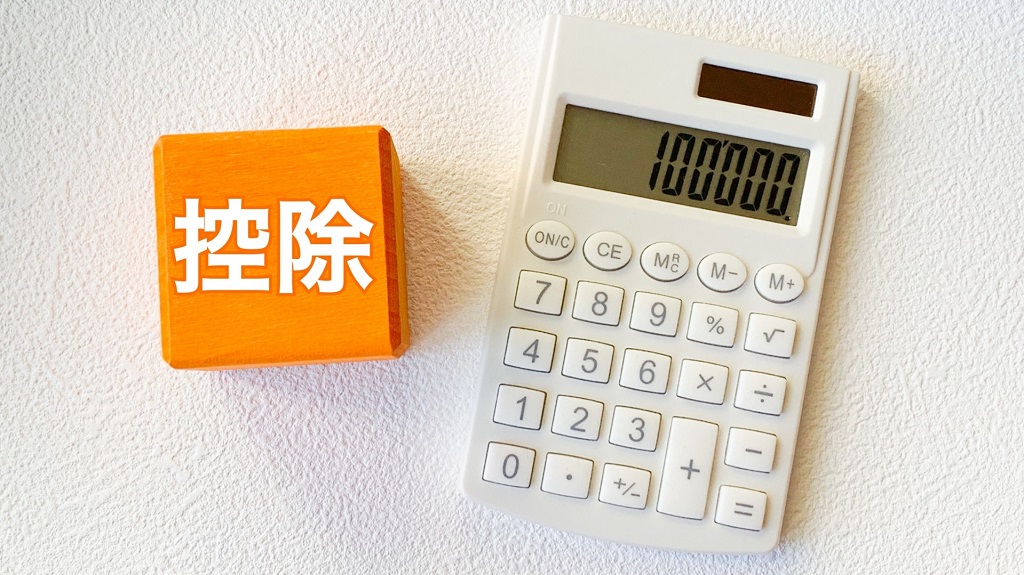
社会保険同様、税金控除に関してもパートとアルバイトに違いがあるのか把握しておきたいところです。以下、基礎知識とあわせて言及します。
あくまで影響するのは給与の総額や年齢含む環境属性
結論を伝えると、税金の控除に関しても、パートとアルバイトによる違いはありません。影響するのは年間収入の総額、そして環境です。後者について具体的に述べると、学生であるか、親や配偶者などに扶養してもらっているかなど、年齢も含めて当事者の置かれている状況によって異なります。
所得税と住民税控除
パートにせよアルバイトにせよ、関わる税金のうち所得税は年収103万円以下であればかかりません。なお、住民税には、所得に応じた負担を求める所得割と、所得にかかわらず定額の負担を求める均等割が存在します。
学生の場合の税金控除
16歳以上のパートやアルバイトが年収103万円を超えると、扶養者の所得税や住民税の負担が増えることになります。この扶養控除は、パートもアルバイトも変わりません。また、学生であってもフリーターであっても、同様に適用されます。とはいえ学生の場合、所得が130万円以下であれば、勤労学生控除によって自身の所得税はかからない仕組みです。
配偶者特別控除
主婦あるいは主夫がパートでもアルバイトでも収入を得たうえで、配偶者が扶養者である場合には「配偶者特別控除」を受けられます。たとえそのパートやアルバイトの方の年収が103万円以上あったとしても、201万6千円未満なら扶養者(配偶者)側の収入が1,220万円を下回った時点で一定額の所得控除が受けられる仕組みです。
パートとアルバイトで有給休暇の取得に違いはある?
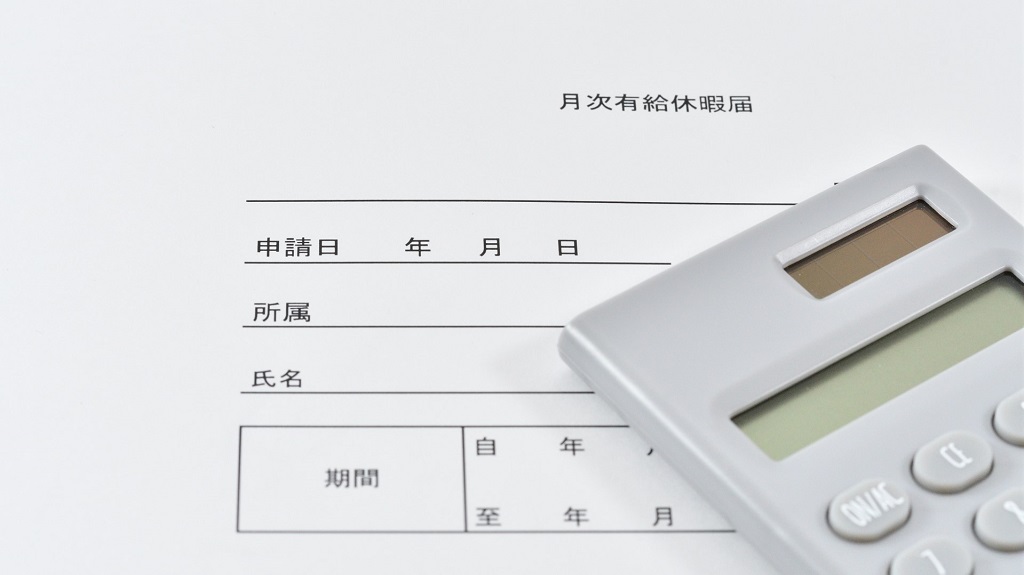
パートもアルバイトも有給休暇は取得可能です。仮に週1日の勤務であったとしても、次の条件に当てはまれば付与されます。
- 半年以上勤務している
- 契約労働日数の8割以上の勤務が認められる
と、正社員の場合、半年勤務した時点で10日の有給休暇が付与されその後勤務年数に応じて増えるのが一般的ですが、パートやアルバイトの場合は勤務年数と週の所定労働日数をもとに付与されます。
たとえば、週2日半年勤務したパートの場合は、3日間。週4日1年半勤務したアルバイトの場合は8日間といった具合です。
なお、パート・アルバイトに支払う有給休暇分の賃金(1日分)は、次のいずれかで算出されます。
| ①平均賃金:過去3ヶ月の合計賃金÷過去3ヶ月の日数 もしくは過去3ヶ月の合計賃金÷過去3ヶ月の労働日数×0.6 ②所定労働時間働いた際の賃金:時給×所定労働時間 ③健康保険の標準報酬日額:保険料の金額を決定する際に使われる標準報酬額÷30 ※ただし、標準報酬日額を用いる場合は、労使協定の締結が必要 |
なお、働き方改革関連法の成立により、パート・アルバイトであっても年間10日以上の有給休暇を付与されている労働者に対しては、1年間に5日以上の有給を取得させなければなりません。違反した場合には罰則を受ける可能性もあるため、注意が必要です。
違いの有無も含めて、パートとアルバイトに対する理解を深めよう

ここまで述べてきたとおり、パートとアルバイトは、同じように扱われることがほとんどです。社会保険、税金控除、有給休暇の取得に関してこれといった違いはありません。一方で企業の希望する人材や労働条件によっては、臨機応変に区分けられています。求人広告の募集要項など、その辺りのニュアンスを踏まえて記載することが大事です。
そうしたなか、パートやアルバイト採用をお考えの人事担当者の方におすすめのサービスが「バイトル」です。80,000件以上の求人掲載数を誇り、知名度の高さも特徴として挙げられます。また、利用者には10~20代が多く、求職者のターゲティングも可能です。お問い合わせは無料。気になる方はぜひ、サービス内容を確認したうえで導入をご検討ください。

