休業や欠勤と比較して浮かび上がる休職の定義
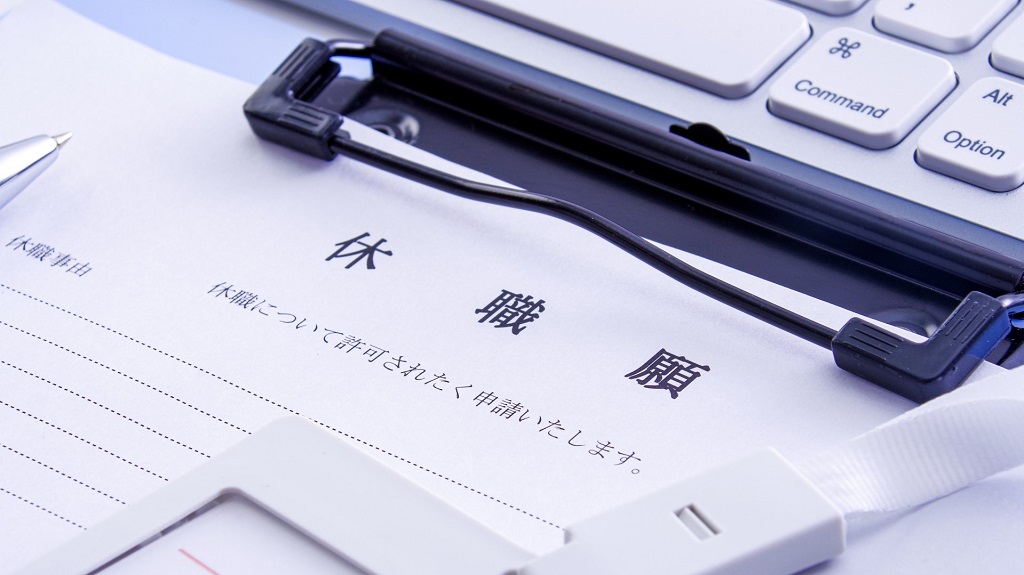
休み自体は、休職含めて大まかに3種類あります。それぞれ定義するなら、具体的に次のとおりです。
| 休業…会社都合の休み、または法律に定められた休み 欠勤…勤務予定日に自己都合で休むこと 休職…自己都合により会社から許可をもらい長期的に休むこと |
育児や介護、労災による怪我・病気の療養といった理由が当てはまる場合、すなわち休業であれば、企業側は休みをとることを拒否できません。
他方、自己都合による欠勤や休職に対しては、厳密にいえば認めない判断も可能です。とはいえ、よほどのことがなければ認可されるでしょう。なかには、ボランティアや留学のための休職制度を設けている企業もあります。
自己都合で単に会社を休むだけなら欠勤です。1日だけ、あるいは数日休む場合、ここに区分されます。有給休暇をすべて消化した従業員がさらに休みを取った場合も欠勤扱いです。当然、その分の賃金は支払われません。
ちなみに、会社への連絡なしに勝手に休むと、いわゆる無断欠勤です。休職であれば事前に企業との話し合いを行い、了承を得たうえで長期的に休むため、近いようで実は明らかに違うものだとわかります。
▶関連記事:アルバイトが無断欠勤!電話がこない!ばっくれ時の対処法を解説
休職の主な種類
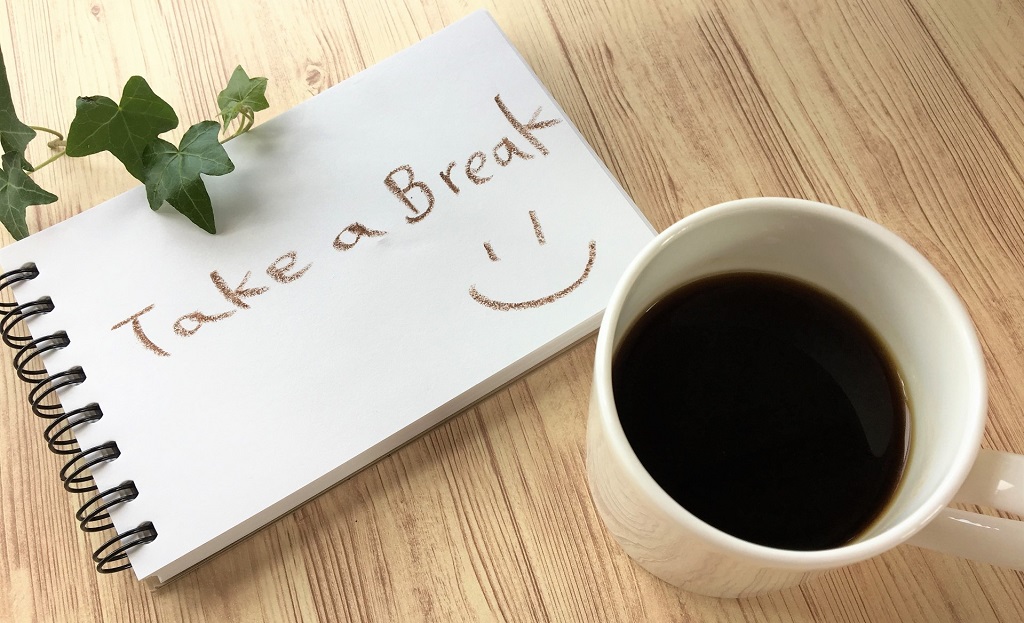
休職そのものにもいくつか種類が存在します。主に、以下のとおりです。
傷病休職
労災のケースに限らず、病気や怪我を理由に休職を認める企業は少なくありません。これは、傷病休職に含まれます。医師から「仕事を休み療養する必要がある」と判断されれば、その時点で対象です。
事故欠勤休職
従業員が刑事事件に関与し、逮捕や拘留などに見舞われた際、休職の打診を受けた企業がそれを許可すれば、自己欠勤休職として扱われます。
警察や検察に容疑をかけられたからといって、直ちに本人が犯罪者といえるわけではありません。休職期間終了までに(容疑が晴れ)放免されれば、職場にも復帰可能です。
自己都合休職
ボランティアや青年海外協力隊への参加を理由に長期休暇をとることは、自己都合休職に該当します。内容によっては、社会福祉活動に貢献していると評価され、一定額の報酬が別途発生することもあります。
出向休職
在職する会社のグループ企業や関連企業などに出向する際、現職からは出向休職として扱われます。
休職は基本的には自己都合によるものですが、出向休職の場合は例外的に会社都合です。また、出向先では働いているため、当然、給与も支払われます。このとき考えられるのは、出向元、出向先、はたまた両者が負担しあうといった3パターンです。
留学休職
従業員自身の希望で、キャリア形成などを目的に海外へ生活を移した場合の休職が、留学休職です。本人のキャリアップだけでなく、組織への利益還元につながることさえ期待できるため、制度として取り入れている企業も少なからず見受けられます。
組合専従休職
組合専従休職は、労働組合専従者が勤務時間内に組合の業務を行うために取得するものです。本来、労働組合の業務は勤務時間外に行いますが、大きな企業の場合は仕事も嵩むため、会社を休職し対応を図ることがあります。なお、組合専従者の給与を企業が支払うことは法律で禁止されています(給与は組合からの支給です)。
公職就任休職
従業員が地方議員や首長などの公職に就き、会社の業務との両立が困難になった際に利用できる制度が公職就任休職です。
たとえば、在職中に裁判員に選ばれた場合、労働基準法の定めにより、従業員は(裁判員としての)職務に必要な休暇を取得できます。ただし、その分を有給とするか無給とするかは、企業側の判断です。とはいえ国は、あくまで有給のうえ裁判員休暇制度の導入を推進しています。
起訴休職
刑事事件の被告人として起訴された場合は、判決が確定するまで一定の期間、企業側が休職させるケースもあります。事故欠勤休職の一例とも重なりますが、起訴休職の場合、企業側の意思を起点に扱われるものです。企業の信用毀損、職場内での混乱などが想定されれば、その権利を行使させることができます。もちろん、無罪判決が出ることも考えられるため、後々トラブルにならないよう、制度の適用は慎重な判断が必要です。
従業員の休職の際に企業が行うこと
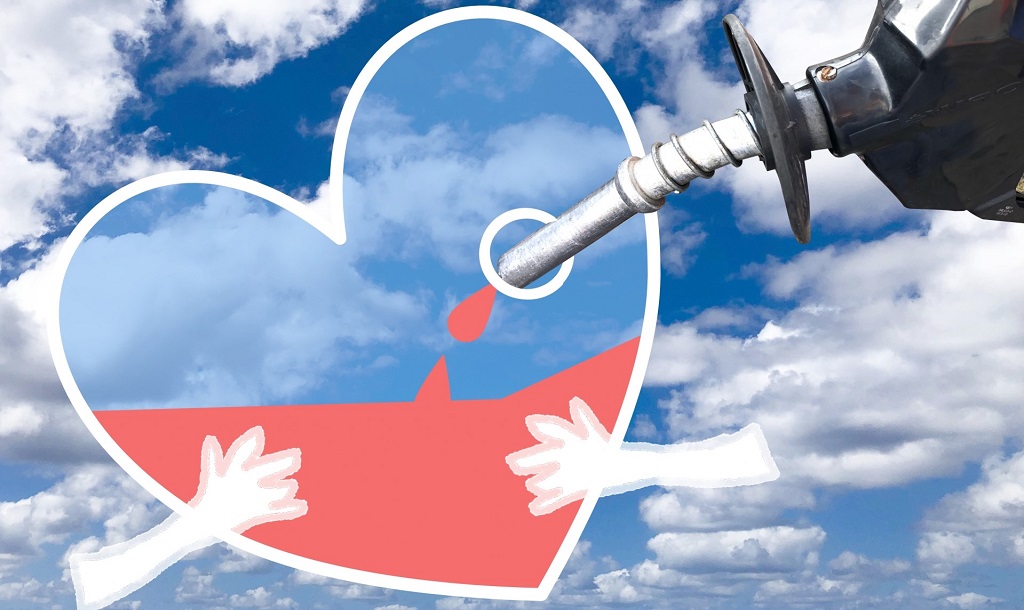
従業員の休職に関して、当然、企業側には行うべき手続きがあります。具体的なステップは次のとおりです。
休職対象かどうか確認する
休職に該当するか否かは、原則、企業ごとの規定をもとに判断されます。ただし原因や理由によっては、その限りではありません。状況を把握したうえで、一人ひとりに向き合う姿勢で対応しましょう。
心身の不調が理由であれば診断書を提出してもらう
心身の不調を伴う休職には医師による診断書の提出をもらうようにしましょう。受け取った際は、理由および必要な期間など記載事項をくまなく確認してください。
本人と面談を行う
トラブルなく休職するためにも、本人との面談は必須です。そのなかで次の項目は確実に確認しましょう。
- (あらためて)なぜ休職を希望するのか
- 休職期間の後に復帰できそうな見込みはあるのか
- そもそも復職したい意思はあるのか
- 別の部署や職種に異動することで、休職せずに済む可能性はあるのか
実際に事情を聞くと、この先復職が難しい状況であったり、配置転換によって休職の必要がなくなったりと、本質的な課題や解決策がみえてくることは多々あります。休職という選択が果たして最適かどうかは、企業側もじっくり見極めなければなりません。
休職の決定、延長に関する共有
診断書や面談の情報を吟味し、休職の可否を決定します。そこで正式に休職が決まれば期間もあらためて確認しましょう。一般的には長くて3ヶ月程度ですが、その後長引くことも想定できるため、延長のタイミングなど更新時期まで含めて共有する必要があります。
書類を作成
休職辞令および確認書を文書で発行します。法的に決まった形式や記載事項こそありませんが、後々トラブルの火種にならないよう気を付けましょう。ゆえに下記内容は必須の情報といってもよいかもしれません。
| 【休職辞令】 ・休職の起算日と終了日 ・休職命令発令日 【確認書】 ・ 休職中の企業側の連絡先および担当者 ・ 休職者へ連絡する際の方法 ・月毎の経過報告(診断書も添付) ・ 社会保険料の取り扱いについて ・ (該当すれば)傷病手当金の手続きについて ・ 職場に復帰する際の取り決め |
休職辞令交付および確認書の取り交わし後、決められた日程で休職が施行されます。
休職期間の終了後について
心身の不調を伴う休職に関しては、期間中に本人が回復すれば、あらためて医師からの診断書や面談をもとに職場復帰を承諾する流れへと進めていきます。反対に、病状が相変わらず思わしくなければ延長も視野に入れなければならないでしょう。または、総合的に判断して職場復帰が困難な場合、休職辞令に記載されている期間満了日をもって退職してもらうことになります(解雇ではなく、期間の定めによる自己都合退職の扱いです)。
休職に対して企業が意識すべきポイント

休職制度の構築は法的義務ではありませんが、離職率の低下や従業員の生産性向上、企業のイメージアップのためには、もはや不可欠なものといっても過言ではありません。実際に、休職に関する制度を設けている企業は数多く見られます。
採用活動において求職者から選ばれる企業になるためにも、たとえば以下に挙げるポイントは確実に意識しておきたいところです。
就業規則への明記
休職の条件、期間、適用範囲、待遇などを就業規則に明記しておくことで、従業員を困惑させずトラブル防止にもつながります。期間中の制限事項や禁止事項もはっきりと共有しておくことが大事です。休職を希望する方は突然出てきます。咄嗟の出来事にもあたふたせず、手続きもスムーズに行えるよう、休職に関するマニュアルは就業規則でしっかり構築しておきましょう。
休職者や所属部署に対するケア、フォロー
休職者に対しては、1ヶ月、いやできれば1週間に1度は必ず連絡をとるようにしてください。特に長期に及ぶ場合、休職者の不安は募る一方かもしれません。彼・彼女らが職場に再びなじめるように復帰支援の環境づくりは必須です。また、休職者が抜けた部署に対しても、ほかの従業員の負担をおさえるべくケア、フォローを怠らないようにしましょう。さらには、必要に応じて新たに従業員を募集するなど採用活動における施策も講じる必要があります。
職場環境の改善
前項でも触れましたが、環境改善は不可欠です。うつ病や過労、各種のハラスメントなどが原因で発生した休職については、同じようなことが起こらないよう対策を用意しておかなければなりません。事実の調査や無記名によるアンケートの実施などで原因を把握し、従業員が安心して働ける仕組みづくりを目指しましょう。定期的な健康診断はもちろん、外部の専門家を招くなどしてメンタルヘルスに向き合うことも重要です。
新たな人材の確保
休職者が出ることで何かしら業務に影響を及ぼすことは容易に考えられます。企業によって動き方は変わってくるとはいえ、やはり少なからず手を打つ必要はあるでしょう。休職を申し出た従業員をただ悠長に待っているだけでなく、空いた穴を埋めるべく、特に採用活動を視野に入れるのは半ば避けられないといえます。このことは、休職される方に無理せず安心してもらうためにもしっかりと念頭に置かなければなりません。なお、スピーディーかつほしい人材を的確に獲得するためには、専門性と信頼性湛える求人サービスの活用が有効です。ゆえに手前味噌ながら好評の声をいただくことが多いdipのサービスをおすすめします。
| サービスのご案内についてはこちら▼ 求人広告掲載、採用業務サービスの総合窓口 サービスの導入事例をピックアップ▼ これまでに無いスピード感で理想の経験者を採用! |
休職中の社会保険料について
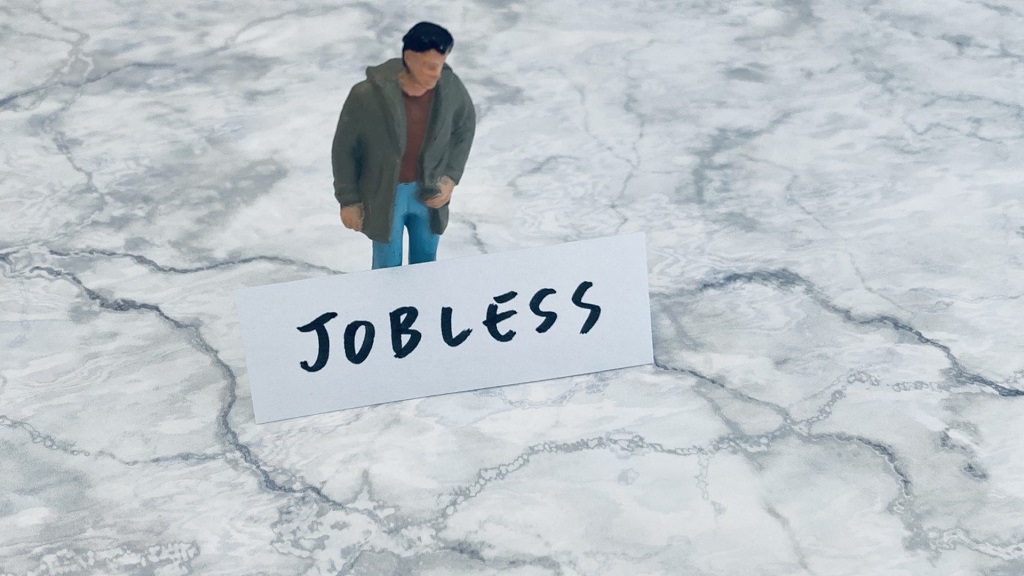
休職中の従業員に対して、仮に社会保険料を企業側が立て替えた場合、いくつか懸念点が生まれます。もしもその従業員が復帰できないまま退職してしまうとどうでしょう。立て替えたお金が戻ってこないケースも考えられます。だからこそ休職中の社会保険料についても事前に取り決めておくことが大事です。以下、お伝えする知識を踏まえて、企業側は用意周到に動くようにしましょう。
休職中も払い続けなければならない
休職中、対象の従業員が無給であっても、社会保険料の負担金額について、本人、企業側ともに変動はありません。これは、標準報酬月額をもとに社会保険料が計算されているからです。
標準報酬月額は、毎年1回7月に、4月~6月に支払われた3ヶ月分の給与の平均額から社会保険料を割り出すために用いられます。これを引き下げるには条件がありますが、休職はそれに含まれません。したがって、社会保険料の負担は休職中も変わらないのです。
そこで上述したとおり、企業側が休職者の経済面をケアしようと社会保険料を立て替えるケースが出てくるわけですが、そうなると対象の従業員の去就次第ではただただ一方的に負担するだけになってしまう可能性もあります。
休職者に支払ってもらいたいなら
通常、企業が負担する社会保険料については給料から天引きを行います。しかし、休職期間中は、無給になるため天引きが行えません。そのため、休職者にも負担してもらうためには直接振り込んでもらうといった対応が必要です。
または、心身の不調を伴う休職であれば、傷病手当から支払ってもらってもよいでしょう。
傷病手当の支給要件
傷病手当とは、病気や怪我の療養のため、一時的に働くことが困難な労働者に対して、企業が加入している保険(協会けんぽまたは健康保険組合)から支給されるお金です。
休職前の「継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額」の3分の2に相当する金額が支給されます(健康保険法99条2項)。
傷病手当の支給要件は以下のとおりです。
勤務先の健康保険の被保険者であること
扶養家族や国民健康保険に加入している方については、対象外です。
病気や怪我により仕事に就けないこと
業務外の原因で病気や怪我をして、医者から労務不能と診断されたケースが当てはまります。
傷病により連続する3日間を含み4日以上仕事に就けないこと
医者から労務不能と診断された後、3日間連続で会社を休まなければなりません。この期間は「待機期間」と呼ばれます。傷病手当が支給されるのは、待機期間経過後、4日目以降です。
給与が支払われないこと
会社を休んだ期間に無給であることも条件です。また、給与の支払いがあっても、傷病手当の金額より少ない場合は、差額分が支給対象に当たります。
なお、傷病手当の支給期間は、支給開始日から最長で1年6ヶ月です。
休職についての要点まとめ
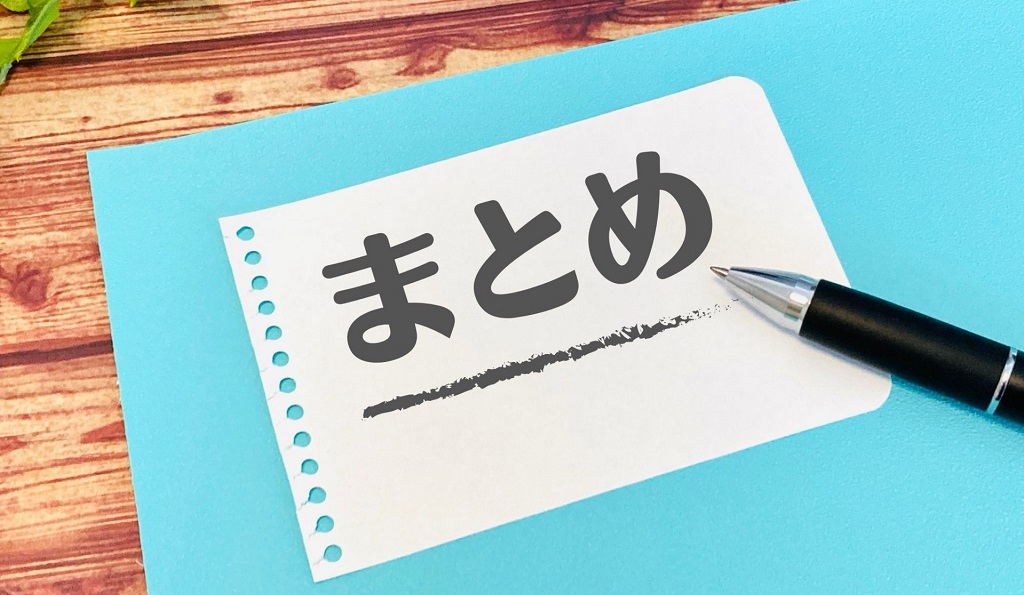
人事担当者に限らず、全社員が休職について理解を深めた方がよいと筆者は考えます。混同しやすい休業や欠勤との違い、種類や手続き、社会保険料のことなど、拙稿でお伝えしてきた内容はどれも大事です。
いずれにしても、従業員が休職する事態に備えて、あらかじめ(休職の)ルールをわかりやすく定めておけば、トラブルを未然に防止でき、一人ひとりが安心して働ける環境づくりにもつながります。
以前に比べて、休職が当たり前に浸透している時代です。企業側はできることを最大限尽くしてください。
さて、休職した従業員の業務をカバーするために、新たな人材確保に向けて動く企業も多いでしょう。dipのサービスを利用すれば、短期雇用からでも新たな仲間の採用に一役買ってくれるはずです。サービスの問い合わせは無料。ぜひ、導入をご検討いただけますと幸いです。
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。

