契約社員とは?

一般的に契約社員といわれれば、有期雇用契約のもと勤務先に直接雇用され、かつフルタイムで働く社員を指します。本章では、そのほか法律上での扱いや更新期間、退職金に関する知識について説明。いずれも基本概要として確実におさえておきましょう。
雇用区分について
働き方そのものは正社員と同じでも、契約社員の場合、基本、雇用期間に定めがあります。すなわち彼・彼女らを端的に定義するならば、前述のとおり、有期雇用契約で働く社員です。ただし、法律上では“契約社員”と称される雇用区分の記載はありません。そのため一口に有期雇用契約といっても、件の「契約社員」だけでなく、「非常勤」「臨時社員」「準社員」「非常勤」「嘱託」など、企業によってさまざまな呼称、扱われ方が存在します。
契約更新について
契約期間の満了に際しては、更新するか否かを決めなければなりません。上限は原則として最長3年です。ただし、「高度な専門技術を持っている」「満60歳以上の労働者」など条件によっては、最長5年まで引き延ばすことができます。
なお、「有期労働契約が3回以上更新されている」もしくは「1年を超えて継続している」従業員に対しては、契約終了する場合、その旨を30日前までに伝える必要があります。
退職金について
更新せずに契約終了となった場合は、当然、退職扱いになります。その際、退職金を支払う必要があるかは、就業規則によって決まります。というのも退職金支給の有無は、企業が独自に定めても問題ない制度です。実際のところ、制度自体を設けていても、正社員のみが対象の企業は少なくありません。もちろん、契約社員に支給する企業もあるとはいえ、その額が正社員と同等のケースは稀だといえるでしょう。
| 契約社員の募集を検討中の方は、バイトルNEXT(ネクスト)をご利用ください。 ▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら |
契約社員はアルバイトやパート、正社員とは何が違う?

法的に雇用区分があるわけではないにせよ、契約社員を深く理解するためには、アルバイトやパート、正社員についての差分や違いを知ることも必要です。以下、要点を中心にそれぞれの雇用形態と比較します。
アルバイトとの違い
既述のとおり、契約社員とは有期雇用契約を結んでいるとはいえ、労働時間や日数は基本的に正社員と同じ条件です。一方、アルバイトの場合、「1日3時間」「1週間で20時間」など、大抵は短時間労働も含まれます。従業員からすると、彼・彼女らの都合で曜日や労働期間を決めていくケースも少なくないため、契約社員と比べると自由度の高い働き方が実現可能です。
パートタイマーとの違い
契約社員であっても厳密にはアルバイト・パートの方々と同じ非正規雇用に分類されます。呼称こそ違えどその形態はアルバイトとほぼ同義といってもよいかもしれません。そのなかで、より短時間単位で働いてもらう場合、パートタイマーの区分で募集されることがほとんどです。また、アルバイトは学生やフリーター、パートタイマーは主婦・主夫がターゲットにされるなど、細かく整理すると、両者の傾向には違いがあります。
▶関連記事:パートとアルバイトに違いはあるの?社会保険や扶養の観点からも解説
正社員との違い
繰り返し述べているとおり、契約社員と正社員の大きな違いは雇用期間の定めの部分です。そして正社員は、(期間の定めが)ありません。いわゆる無期雇用契約に該当します。契約更新する必要はなく、基本的に、退職しない限り定年を迎えるまで働き続けることが可能です。また、福利厚生の内容でも違いが生まれることがあります。企業によって規定は異なるとはいえ、契約社員の場合、適用条件が制限されるケースも見受けられます。
なお、休日や休暇については、両者に差分はありません。有給休暇に関しても所定労働日の一定条件を満たせば、どちらも平等に付与されます。
▶関連記事:雇用期間とは?バイトやパートへの設定ルールや注意点など解説
契約社員にボーナスを与える必要はある?

契約社員を雇うにあたって、よくある疑問点として挙げられるのがボーナス(賞与)の問題です。以下、与える必要性に加え、現状の風潮についても言及します。
ボーナスどうする!?
労働基準法では、ボーナスについての規定は特にありません。これは、契約社員に限っての話ではなく、正社員に対しても支給する必要はないことを示します。ただし、就業規則に記載していれば話は別です。その場合、契約社員に対してもそこで定められたルールに基づきボーナスを支払わなければなりません。
また、仮に契約社員がボーナス対象外であれば、従業員に誤解されないようその旨(正社員に限るなど)も就業規則にはきちんと明示しておくことをおすすめします。
契約社員にボーナスを支給する企業は多い?
契約社員に対してボーナスを支給する企業の数は、現状日本では非常に少ないと認識してよいでしょう。そもそも企業が契約社員を雇う理由の一つには人件費を抑えることが挙げられます。そのため、仮にボーナスが支給されたとしても、退職金同様に、正社員同等の額が与えられることは極めて稀なケースです。
また、ボーナスの支給は業績にも左右されます。業績が悪化すれば、本来支給対象であったとしても、(就業規則で“賞与支給は業績による”との記載があれば)契約社員はじめ非正規雇用の従業員に対して、カットや削減する方針に切り替わることは当然考えられます。
契約社員を雇うメリット

ここまで述べてきた定義や管理上の基礎知識に加え、契約社員を理解するうえで欠かせないのが雇用するにあたってのメリットとデメリットの把握です。まずはメリットからお伝えします。
長期雇用を避けた効率的な人材確保
人材の確保が必要だとしても、無期雇用となると少なからず採用の判断には慎重にならざるを得ない、あるいは躊躇が生まれやすくなります。それゆえ、期間をある程度絞りジョインしてもらいたいのが大方の企業の本音かもしれません。
たとえば「期間限定プロジェクトへの追加募集」「繁忙期の対処」「産休に入った社員の穴埋め」など、ある一定の時期だけ人員を強化、補填したいシチュエーションに出くわすことは当然あり得ます。その際、ひとまず契約期間を定めて募集できれば、無期限で働いてもらう価値まで考える労力は省けるでしょう。そうやって長期雇用を視野に入れずとも人手不足の解消につなげられるのなら、その効率の良さは、やはりメリットだといえます。
人件費を抑えられる
多くの企業がそうであるように、ボーナスや退職金支給の対象に契約社員を含めていない場合、(求職者を正社員ではなく契約社員として雇うことで)支払う賃金は抑えられます。
人手は必要。と同時に、膨れ上がる人件費はケアしたい。そうした要望を叶えるべく、新たな仲間を契約社員として招き入れることは、理に適ったやり方だといえます。
教育コストの削減
契約社員として雇うからこそ削減できるコストは、何も給与だけではありません。教育や研修などに要する手間や時間においても同様です。それは、前提としてキャリア構築が長期に及ばないことを意味します。また、帰属意識を養うことにもそこまで注力する必要はないでしょう。自社の企業文化や価値観とのマッチングよりもスキルや経験重視で採用できる分、コストパフォーマンスも計算しやすい傾向にあります。
| 契約社員の採用なら、バイトルNEXT(ネクスト)をご利用ください。 ▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら |
契約社員を雇うデメリット
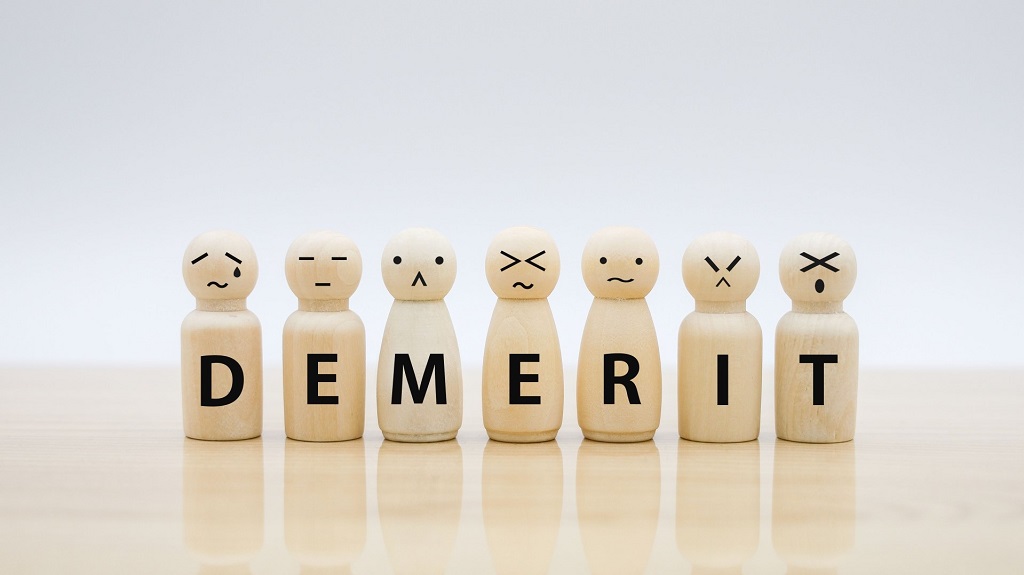
前述のメリットに続いて、本章ではデメリットを取り上げます。
契約社員を採用することで主にコストダウンにつなげられる反面、マイナス要素も無視できません。募集の際は、メリットだけでなくデメリットもしっかり念頭に置くようにしましょう。
即戦力人材をタイムリーに見つけられない
期間に定めがあるからこそ、カルチャーフィットよりも即戦力重視で探せるのは一見、効率的に思えますが、実際のところ、契約社員志向で技術力の高い求職者は、そうそうタイムリーには探せないものです。結局は、正社員として経験を積んだ方々が、希望するスキルを持っていることは往々にしてあります。したがって、短期間のプロジェクトにおける追加募集や人員補填であっても、すぐに優秀な人材を獲得したい場合は、契約社員の採用に固執しない方がよいかもしれません。
責任のある仕事を任せづらい
契約社員が自社に在籍するのは、基本的に期間満了までです。そのため、責任の大きな仕事を安易に任せてしまうのは気を付けた方がよいでしょう。契約社員が責任を負うのは、契約によって定められた業務の範疇だけです。そのため、契約期間が終わりに差しかかる時期の依頼や、重要な任務が本人にとって想定外の仕事であった場合、認識の齟齬も含めて軽率な仕上がりになる可能性があります。また、突発的なトラブルなど起きた際も同様です。それらが契約外の内容であれば、その分、正社員の方々の負担が大きくなるかもしれません。さらには、案件が重なり忙しい時期にも、残業はできないと断られることさえ十分に考えられます。
契約更新してもらえないことも少なくない
雇い入れた契約社員に期間満了後も働き続けてほしいと思った場合、企業は契約期間の延長や正社員としての雇用をあらためて打診することがあります。しかし、それには本人の同意が必要であり、本人が希望しなければ企業は引き止めることができません。その場合、必要に応じてまた一から新たな人材を探すことになります。
契約社員はあくまで有期雇用契約であり、また、期間中に馴染んでいたからといって無条件に更新してもらえるわけではないことをしっかり念頭に置きましょう。加えて、採用活動への目配りも大事です。
| 契約社員の採用なら、バイトルNEXT(ネクスト)をご利用ください。 ▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら |
契約社員を雇用する際の注意点

メリット、デメリットも踏まえたうえで、いざ契約社員を雇用する際、どのような点に注意すればよいのでしょうか?具体的には次の3つが挙げられます。
- 業務内容を曖昧にしない
- 正当な理由なしに解雇しない
- 有期雇用のままにしない
それぞれ、以下、補足します。
業務内容を曖昧にしない
契約社員を雇い入れる際、担当業務を契約書で明確に示すことで、曖昧な状態を作らず、無用なトラブルの回避につなげられます。だからこそ、業務内容は慎重に決めましょう。定められた期間のなかで、どの業務を割り当てればパフォーマンスの最大化が図れるのか、求めるレベルや責任の度合いなど含めて細かく調整することが大事です。加えて注意したいのが、安易に正社員と同じ業務を与えてしまうことは避けるべきかと考えます。重要な決断、進行はあくまで正規雇用である人間に任せるのが無難です。
正当な理由なしに解雇しない
契約社員の解雇についても注意が必要です。労働基準法により、期間途中での解雇は「やむを得ない事由」がある場合でなければ違法とされています。
なお、やむを得ない事由としては、「経歴や年齢を詐称していた」「無断欠勤が続いた」「会社に損害を与える問題を起こした」などが該当します。
有期雇用のままにしない
労働基準法で定められている1回の有期雇用契約の上限は3年ですが、その後の更新を経て、雇用契約期間が通算5年を超えた場合、本人の希望により、以降は無期雇用契約に転換できます。にもかかわらず、契約社員本人からの申し出を企業側で拒むのはご法度です。メリットがあるからこそ、契約社員としていつまでも重用したい気持ちもわかります。が、法律上、該当する従業員を有期雇用のままにしておくことはできないのです。
契約社員への理解を深め適切な雇用管理、採用活動に努めよう

雇用区分が実は曖昧な契約社員ですが、アルバイトやパート、正社員の働き方と比較すると、おのずと特徴が浮かび上がってきます。また、ボーナスや退職金制度の適用についても拙稿で述べたとおりです。ただし、あくまで一般的な見解として伝えたものの、この先、世相がどう変わっていくのかはわかりません。随時追跡しなければ世間とずれたまま取り残されてしまう可能性もあるでしょう。メリット、デメリットも同様です。あくまで現時点での価値観であり、今後、雇用側、労働者側、両方で契約社員の捉え方が刷新されることも大いに考えられます。
採用活動を行う際は、ぜひこうした観点で以て注意事項にも気を配り進めてください。
| 契約社員の採用なら、バイトルNEXT(ネクスト)をご利用ください。 ▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら |

