無期雇用派遣とは?
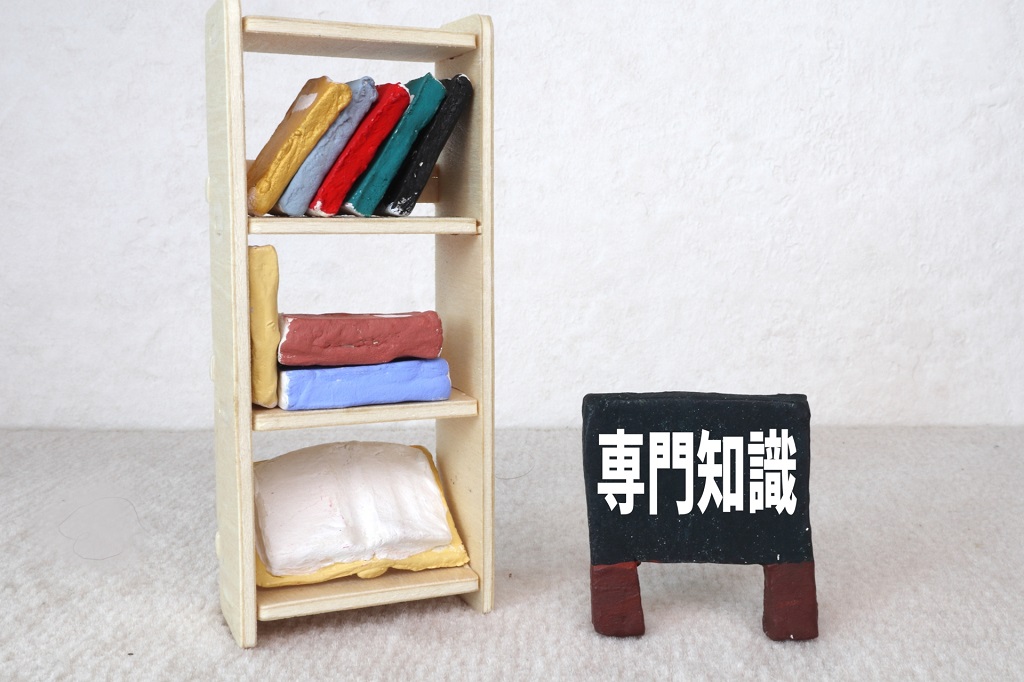
「無期雇用派遣とは何か?」
この問いに対する答えは、単なる用語の意味だけでは完結しません。それは、現代の労働市場の変化と深く結びつき、人材雇用のあり方に新しい風を吹き込んでいます。本セクションでは、(無期雇用派遣の)厳密な定義から、生まれた背景、そして重要な無期転換ルールについてピックアップ。それぞれ順を追って説明します。
無期雇用派遣の定義
無期雇用派遣とは、派遣会社と労働者との間で派遣先の企業が変わっても雇用契約を継続する雇用形態です。他方、派遣先ごとに契約期間が定められる形態は「有期雇用派遣」と呼ばれます。
ちなみに「登録型派遣」と「常用型派遣」の2つの用語についても知っておきましょう。前者は、派遣先での就業期間終了とともに契約が終了する形態です。一方で後者の場合、派遣先での就業期間終了後もなお派遣会社との雇用契約が継続されます。もうお気づきでしょうか。そう、(お察しのとおり)この常用型派遣こそ無期雇用派遣を指します(つまり別名です)。
無期雇用派遣が生まれた背景
無期雇用派遣が生まれた背景には、労働市場の変化と法制度の改正があります。少子高齢化や経済のグローバル化が雇用形態の多様化を促進した結果、労働者の選択肢は広がり、企業側は雇用に柔軟性が求められるようになりました。そのなかで派遣社員に対しても、彼・彼女らの権利保護と待遇改善を望む機運が高まります。そしてまさに、無期雇用派遣が、この課題・命題を解決するための一手となったわけです。無期雇用派遣は2015年、労働者派遣法の改正によって正式に導入。派遣社員の雇用安定とキャリア形成の支援が目的である一方で、人員配置など企業の人材戦略が問われる制度だといえます。
▶関連記事:労働者派遣法とは?改正の歴史を通じて内容をわかりやすく解説
無期転換ルールについて
2013年に施行された労働契約法の改正により無期転換ルールが導入。これは、同じ労働者を通算5年以上有期契約で雇用し続けた場合、労働者の希望に基づいて無期契約への転換を認めるというものです。このルールを利用すると、派遣社員は同じ事業所で3年を超えて働けるようになります。
無期雇用派遣と正社員の違い

前項で述べた内容kあら、もしかすると無期雇用派遣を正社員と混同される方がいらっしゃるかもしれません。確かに一見、両者は似ているように感じられます。しかし、実際にはそれぞれ別です。契約や待遇などその特性は異なります。そしてそれらの違いを具体的に把握することは、採用戦略や人材管理において非常に大切です。以下、主な違いを説明します。
雇用契約の締結形態
正社員との契約は、企業が直接労働者と締結します。一方で無期雇用派遣の場合、派遣会社と派遣先の間で業務委託契約、労働者と派遣会社が雇用契約を結びます。
待遇面
正社員は、企業の経営方針や業績に応じて、給与、ボーナス、昇進の機会、各種保険、退職金、休暇制度などの福利厚生が設定されるのが一般的です。また、研修や教育制度を通じてのキャリアアップのサポートが期待されます。一方で無期雇用派遣の場合、給与や福利厚生を決めるのは派遣会社です。派遣先のそれとは異なり、研修や教育の機会も同様に派遣会社の規定や方針に基づきます。そのため、派遣先での活躍を反映していないケースも多々見受けられます。
企業側が無期雇用派遣を受け入れるメリット

企業が無期雇用派遣を受け入れることで得られるメリットはいくつか挙げられます。たとえば、安定した労働力や高いスキルを持つ人材の確保です。後者であれば、専門的あるいは重要な業務を任せることも可能にしてくれます。そのうえでコスト削減も無視できません。短期の派遣を頻繁に求人する企業であれば、より実感できるはずです。少なからず採用活動の手間は省けるでしょう。こうしたポイントの認識は、すなわち無期雇用派遣の価値理解です。以下、補足説明します。
長期的に就業してもらえる
無期雇用派遣であれば、3年ルールを超えて長期的に就業してもらえます。それだけでも人材確保の観点ではありがたいものでしょう。時間を経て専門性が高まりスキルが身につけば、いうまでもなく貴重な戦力です。彼・彼女らを期間の縛りによって強制的に手放さずに済むのは、一つ安心できるポイントだと考えます。
重要な業務を任せられる
優秀、はたまた長く働いてくれるなかで育ってきた人材には、任せられる仕事の幅も変わります。長期的なプロジェクトであればなおさらです。ややこしいミッションも無期雇用派遣だからこそアサインできるケースもあるでしょう。
コストの削減
派遣社員の期間満了に際して慌ただしく後任を探し、また一から教育をしていくことを非効率に感じている方は、多少なりともいらっしゃると思われます。実際、無期雇用派遣の社員として長く勤めてもらえれば、上記のコストは削減可能です。ただし、採用時にそうした人材をうまく見極める、さらに述べると応募してもらう必要があります。肝は、エンゲージメントの高い求職者とのマッチングです。
求人広告の掲載をお考えの企業様へ
「はたらこねっと」は派遣から直雇用案件までお仕事情報の掲載が可能です。
| ▶【公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり!派遣、直接雇用、即戦力多数 「はたらこねっと」が、株式会社oricon MEの発表する「2023年 オリコン顧客満足度®調査の派遣情報サイトランキング」で、顧客満足度第1位を獲得いたしました。 2023年 オリコン顧客満足度®調査 派遣情報サイトランキング で「はたらこねっと」が第1位を獲得~4つの評価項目全てで第1位に~ |
無期雇用派遣を戦略的に活用する方法

無期雇用派遣を受け入れるメリットが分かったところで、それをいかに活用するかが大事です。戦略的に扱うにはどうすればよいのか、以下、参考にしてみてください。
中長期的なプロジェクトとの整合性を視野に!
無期雇用派遣の活用は、企業のビジネス戦略や目標もセットで考えていきたいところです。新事業領域への進出や業務拡大など長期に渡り、かつ責任重大なプロジェクトを予定しているのであれば、人員配置とあわせてうまく計画を立てられるようにしましょう。
業務プロセスの最適化が大事!
いざ無期雇用派遣として活用する際に、適材適所の采配ができるよう、派遣社員に対して特定の専門スキルや経験を持っているか否か把握しておくことが大事です。結果、業務の効率化や品質向上を図ることができます。
人材の多様性に期待!
無期雇用派遣の社員のなかには、正社員とは異なる背景やスキルセットを持つ人材もいるかもしれません。その辺も目配りしながらうまく融合できれば、企業のイノベーションや新しいアイディアの創出を促進できる期待が持てます。経済状況の変動や業界の変化に対して企業は柔軟性が求められる昨今、意識したいポイントです。
派遣会社とのパートナーシップが肝要!
無期雇用派遣を成功させるためには、派遣会社との強固なパートナーシップを築くことが肝要です。定期的にコミュニケーションをとり、ニーズや期待値を共有することで、最適な人材を派遣してもらうことも期待できます。
継続的な評価とフィードバックも忘れずに!
無期雇用派遣を希望する派遣社員が増えれば、組織としての厚みが加わります。そのためにも派遣社員に対しては、業務遂行状況を定期的に評価しフィードバックを提供するとよいでしょう。業務の質の維持・向上にもつながります。
求人広告の掲載をお考えの企業様へ
「はたらこねっと」は派遣から直雇用案件までお仕事情報の掲載が可能です。
| ▶【公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり!派遣、直接雇用、即戦力多数 「はたらこねっと」が、株式会社oricon MEの発表する「2023年 オリコン顧客満足度®調査の派遣情報サイトランキング」で、顧客満足度第1位を獲得いたしました。 2023年 オリコン顧客満足度®調査 派遣情報サイトランキング で「はたらこねっと」が第1位を獲得~4つの評価項目全てで第1位に~ |
無期雇用派遣で考えられる企業側のデメリット
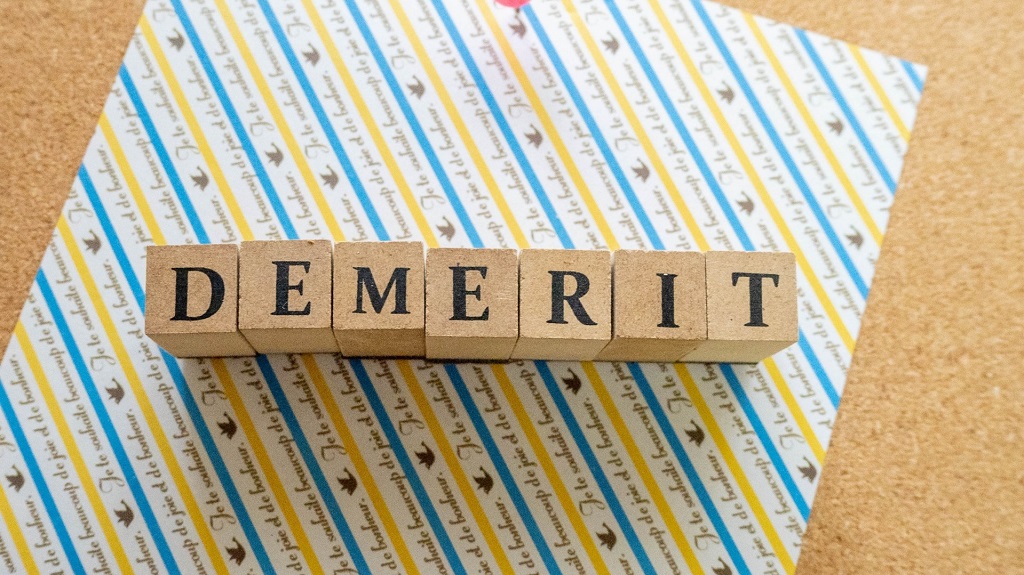
無期雇用派遣は、前述のとおりメリットがいくつかあり、企業が柔軟に人材を確保する手段の一つになり得ます。が、その一方でデメリットが存在するのも確かです。企業が無期雇用派遣を受け入れるなら、これらについてもまた十分に理解し、適切な対策を講じることが求められます。では、一つずつ確認していきましょう。
人件費が掛かる
無期雇用派遣の制度では、派遣会社は待機期間中も派遣社員に給与を支払う義務があります。このコストは最終的に派遣先のいわゆる派遣料金に反映されることが多く、結果的に人件費が高くなる可能性があります。
解雇が難しい
無期雇用派遣の特性上、簡単に解雇することは難しいというデメリットが考えられます。特定の契約期間を設けずに雇用された派遣社員は、派遣先での業務が終了しただけでは解雇することができません。
解雇が認められるケースとしては、「派遣会社の就業規則に違反した場合(業務上の重大な過失など)」や「派遣会社からの仕事の紹介を受けることができない長期の休業状態」が挙げられます。しかし、これらの条件を満たさない限り、企業側の一方的な都合での解雇は困難です。
モチベーションが低い人も出てきやすい
既述のとおり、無期雇用派遣だと(派遣会社の規則や契約内容次第で)正社員とは異なり昇給や昇進の機会に恵まれない人が出てきます。有期雇用派遣に比べて勤務の自由度が低いと感じる向きも然り。こうしたことを理由に、派遣社員のモチベーションが低下するケースは決して珍しくありません。
帰属意識が低くなりがち
無期雇用派遣の従業員は、派遣会社の雇用下にあるため、派遣先の企業に対する帰属意識が弱まることが考えられます。この帰属意識の低さは、組織へのコミットメントの減少や、職場の人間関係への関心の低下を引き起こす可能性があります。さらに、情報の取り扱いに関する不注意や、企業の目標達成に対する熱意の欠如などの問題も生じる恐れがあります。これらの問題を回避するためには、派遣先の企業がコミュニケーションを強化し、派遣社員のインクルージョンを促進する取り組みが必要です。
無期雇用派遣を採用する際の注意点

無期雇用派遣の採用には、法的な観点も含めて注意が必要です。具体的には、正社員募集情報提供義務、派遣社員への意向確認などが挙げられます。以下、これらについての説明です。
正社員募集情報提供義務
自社で継続して1年以上働いている無期雇用派遣の労働者がいる場合、自社で正社員を募集する際にはその情報を当事者に周知しなければなりません。これは労働者派遣法第40条において定められているため、抵触しないよう注意が必要です。情報提供(周知)の方法としては次のようなものがあります。
- 対象となる派遣労働者に直接メールなどで通知する
- 事業所の掲示板に求人票を貼り出す
- 派遣会社に募集情報を提供し、(派遣会社を通じて)対象となる派遣労働者に伝えてもらう
派遣労働者に周知した内容については、派遣先において記録および保存することが望ましいでしょう。作為的に正社員募集の事実を隠すことがあると疑われれば、違反行為として処罰される可能性もあります。情報提供は必ず行うようにしましょう。
▶関連記事:派遣雇用の違反事項~禁止業務や契約ルール、罰則、対策交えて解説~
派遣社員への意思確認
有期雇用期間が3年を迎える、または派遣会社との雇用契約が通算5年を迎えるタイミングでは、無期雇用派遣へ移行する意志があるか確認する必要があります。なかには無期雇用派遣での契約を申し出たとき、それを望まない派遣労働者もいるため、本人の意思と派遣会社の意向は早めに確認しておくことが無難です。
▶関連記事:派遣の抵触日とは?リセットルールや延長手続きなど交えて解説
台帳での明確な管理
派遣会社が派遣労働者の雇用状況や派遣先情報などを記録・管理するのに派遣元台帳があります。これは、労働基準監督署などの行政機関が監査を行う際に重要な資料です。当然ながら正確かつ詳細な記載が求められます。
そのうえで無期雇用派遣労働者と有期雇用派遣労働者の違いについても、明確に区別しなければなりません。労働者の権利や待遇、雇用の更新・終了に関する手続きが異なる両者です。不正確な記録や混同があると、たちまちトラブルや行政からの指導・是正勧告を受ける可能性が高くなります。
そして、派遣雇用における重要書類としてもう一つ、「派遣先管理台帳」があります。これは、派遣社員の労働日や労働時間などの就労実態を記載する台帳です。その名のとおり、派遣先が作成しなければなりません。派遣元管理台帳同様、記載内容は多岐に渡り、スタッフ一人ひとりに対して記録していくものです。
▶関連記事:派遣先管理台帳とは?記載事項やフォーマット、保管期間などくわしく解説
求人への記載が必須
人材募集の際は、求人情報に無期雇用派遣の旨はしっかり記載しましょう。雇用形態はじめ給与、勤務地、勤務時間、休日・休暇、福利厚生などの基本的な労働条件が明記されていない場合、求職者との間で誤解やトラブルが生じるリスクが高まります。
▶関連記事:求人広告の書き方を例・テンプレートを交えて解説。応募を集める求人とは?
無期雇用派遣についてのポイントまとめ

ここまでお伝えしてきたとおり、無期雇用派遣を活用すれば、長期で働き続けてくれる人材を確保できるうえ、コスト削減にもつながる期待が持てます。長期的なプロジェクトや重要な業務を任せることもでき、正社員と同等の重要な働き手として活躍が計算できるでしょう。一方で、人件費の高騰や対象派遣社員のモチベーション低下など危惧される要素もあります。法律についても気を付けなければトラブルを見舞う羽目になりかねません。したがって、無期雇用派遣を活用する際には、戦略的に進めることや注意点を念頭に置くことが大切です。拙稿で述べてきたことを、あらためてご参照ください。
なお、派遣の求人掲載なら「はたらこねっと」がおすすめです。サービスの内容や料金など気軽にお問い合わせください。
求人広告の掲載をお考えの企業様へ
「はたらこねっと」は派遣から直雇用案件までお仕事情報の掲載が可能です。
| ▶【公式】はたらこねっと – 派遣、直接雇用案件の掲載可能!料金プランも豊富 「はたらこねっと」が、株式会社oricon MEの発表する「2023年 オリコン顧客満足度®調査の派遣情報サイトランキング」で、顧客満足度第1位を獲得いたしました。 2023年 オリコン顧客満足度®調査 派遣情報サイトランキング で「はたらこねっと」が第1位を獲得~4つの評価項目全てで第1位に~ |
【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所
代表 荒武 慎一
同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。

