正社員登用について

冒頭でも述べたように、正社員登用制度は多くの企業で取り入れている制度の一つです。しかしながら、その詳細について理解されている方は、人事担当者であっても実はそう多くないように見受けられます。具体的には、無期転換ルールとの違いや企業の導入状況などです。あるいは正社員になることを望まない従業員の存在も無視できません。本章では、正社員登用制度を知るのにおさえておきたい基本概要に加え、データを交えた実態についても言及します。
正社員登用制度とは?
正社員登用制度とは、アルバイトやパート、契約社員といった非正規雇用者を、(規定の条件を満たしてもらったうえで)文字どおり正社員として登用していく制度を指します。
希望する従業員には企業独自の試験や面接を実施し、正社員としての適性を判断するのが一般的なやり方です。正社員登用後は給与や待遇の見直し、研修の提供など、さまざまな手続き、サポートを行っていきます。
なお、正社員登用制度を積極的に取り入れることはパートタイム労働者、パートタイム労働法 においても推進されています。
無期転換ルールとの違い
無期転換ルールとは、有期雇用契約で通算5年以上働いた方が自身の希望で無期雇用契約に変更できる制度です。労働契約法18条では、有期労働契約を結び5年経過した労働者が無期労働契約を申し込んだ場合、使用者はそれを承諾したとみなされます。
そうしたなか、正社員登用制度との一番の違いは、やはり雇用形態の扱いでしょう。無期転換ルールが非正規のまま変わらないのに対して、正社員登用制度は(“正社員”として登用するわけで)正規雇用へと切り替わります。
▶関連記事:無期雇用派遣とは?~無期転換ルールについて
正社員登用制度の導入状況
企業が制度を導入しているかを含めて正社員登用の状況については、厚生労働省が発表している「労働経済動向調査(令和5年2月)の概況」から確認できます。以下、特筆すべきポイントを整理しました。
正社員登用制度がある企業の割合
調査産業計では、正社員登用制度があると答えた企業は77%でした。
業種別では卸売業・小売業が84%と最も多く、金融業・保険業が83%と続きます。生活関連サービス業・娯楽業、医療・福祉も81%と高い数値です。人手不足が深刻な業界が、正社員登用制度をより多く活用していることがうかがえます。
▶人手不足解消に向けて正社員採用をお考えなら「バイトルNEXT」
正社員登用を実施した企業の割合
前項で述べたデータは、制度を設けている企業すべてを含んでいますが、実際に正社員へ登用した割合だとまた変わってきます。まず全体平均は39%でした。業種でみていきましょう。もっとも多いのは金融業・保険業の45%。次いで、医療・福祉、運輸業・郵便業が43%です。このことから、専門スキルを持った人材が求められている傾向にあるとわかります。
制度はあるが登用実績まではない企業の割合
登用制度こそあるものの実績がない企業は39%でした。そのなかで卸売業・小売業は、48%ともっとも多い割合を占めています。
そもそもなぜ制度があるにもかかわらず活用しなかったのでしょう。理由はいくつか挙げられます。そして、そのなかで特に多かったのが「正社員を募集あるいは必要としなかった」「正社員以外の労働者から応募がなかった」です。つまり、こうした企業はアルバイト・パートの採用に軸足を置いていたあるいは課題があったということがわかります。
正社員登用に対して意欲的な企業の割合
正社員登用制度がある企業では「登用していきたい」と答えた割合が62%ともっとも多く、他方、制度を設けていない企業は「現在のところ未定」と答える割合が一番で、56%を占めていました。
加えて、実績ありの企業の場合「今後も登用していきたい」が72%。実績なしでは「現在のところ未定」が44%という結果でした。
正社員になりたくない人もいる
アルバイトやパートとして働く人のなかには、正社員への転換を望まない方も少なくありません。その背景にはライフスタイルが挙げられます。子育てなど優先すべきものがあれば、固定されたフルタイム勤務が難しくなるのは当然です。また、責任やプレッシャーが増すことを懸念して、正社員を選択しない向きも少なからず見受けられます。
アルバイト・パートを正社員登用するメリット

アルバイトやパートを正社員登用することは、企業にとって少なからずメリットがあります。たとえば、すでに業務を熟知している従業員を正社員として迎え入れることで、教育コストの削減が可能です。また、従業員のモチベーション向上や離職率の低下なども考えられます。人材育成に力を入れているあるいは力を入れていきたい企業なら、有効活用しない手はありません。ということで以下、そうしたメリットについて具体的に説明します。
即戦力の働きが見込める
求人広告を使って期待の新人を獲得するのと同じように、今いる優秀な従業員にさらなる活躍の場を与えることも、組織力をアップさせるには有効な方法だといえます。つまり、能力も高く現場での適正もわかっているアルバイト・パートの方を正社員登用すれば、即戦力の働きが見込めるというわけです。もちろん、そうスムーズにいくとは限りませんが、求人がうまくいっていない企業であれば、一度は検討してみてもよいかもしれません。
アルバイト従業員のモチベーションが上がる
正社員登用制度があることで、アルバイト・パートにはモチベーション高く業務に取り組んでもらえるでしょう。というのも非正規雇用という自身の境遇に不安を覚えている方は少なくないと思われます。が、正社員への道が明確にあることがわかれば中長期的にキャリアパスを設計できるため、彼・彼女たちは日々の業務にもやりがいを感じやすくなるかもしれません。そうなれば、制度の存在だけでも生産性の向上につながる期待が持てそうです。
人材が定着しやすい
入社後のミスマッチは従業員の離職に直結します。一方で、正社員登用した方々は職場の雰囲気に慣れている方がほとんどです。これだけでもアドバンテージだといえます。したがって、少なくともミスマッチを理由に離職される心配は不要でしょう。結果的に定着率向上が期待できます。
コスト効率を高められる
正社員の採用には、当然、費用と手間がかかります。求人広告の出稿、応募者の選考、面接(複数回)、雇用契約の締結など、各フェイズを設けるなかで少なからずリソースが発生し、さらには入社してもらった後も教育コストが必要です。他方、アルバイト・パートを正社員登用する場合、上記のプロセスをばっさり省略できます。加えて、厚生労働省が提供するキャリアアップ助成金の受給も視野に入れれば、よりコストの効率化が図れます。
正社員登用で生じやすいデメリット

正社員登用を考える際、メリットだけでなくデメリットもまた念頭に置く必要があります。人件費の増加や水面下で起きがちな人間関係の変化など、経営者や人事担当者はこれら潜在的なリスクをしっかりと認識しておきましょう。
給与アップや退職金の支払い
正社員登用は給与体系の変更を伴います。アルバイトや契約社員と比べて、高くなるケースがほとんどです。これは、役割や責任、期待される業績に応じて、給与が設定されるからだといえます。加えて、正社員に退職金制度を設けている企業の場合は、当然のことながら人件費は嵩みます。したがって、あらかじめ支出額の変化(増加分)を把握、そして管理しておくことが大切です。
福利厚生関連の経費負担
正社員登用による福利厚生関連の経費も無視できません。具体的には、健康保険、厚生年金、雇用保険などの社会保険料に加え、住宅手当や子育て支援、社員旅行など、企業独自の制度があれば、その分の費用も当然掛かってきます。
これらは、確かに従業員のモチベーション向上やリテンションの強化に寄与しますが、一方で負担額としては決して小さくありません。特に中小企業やスタートアップの場合、経営に大きな影響を及ぼすことも考えられます。
解雇に対するハードル
労働者を解雇するにはいくつかの制約があります。もちろん、それは正社員のみならずアルバイト・パートに対してもいえることですが、有期契約労働者に対しては、契約期間の終了をもって雇用関係が自動的に終了するため、無期契約の労働者と比べて解雇のハードルは低くなります。当然、正社員は後者のため、上述したいくつかの制約をクリアすることが必要です。
▶関連記事:アルバイトを解雇するには?妥当な理由、方法、流れについて解説
アルバイト同士の人間関係
正社員登用は、アルバイト同士の人間関係にも大なり小なり作用します。当然、それは悪影響も含めてです。たとえば1人のアルバイトが正社員に登用されると、その方と他のパート従業員との間にギクシャクした関係が生まれることが考えられます。特に昇進したアルバイトの方が「自分は認められた」と下手に自信を持つと厄介です。態度が大きくなり周囲に嫌な印象を与えかねません。かつ正社員でない方々が自身が登用されないことに不満を持ち、もっとひどいと正社員登用された方に嫌がらせを行うケースも存在します。結果的に、正社員登用者を巡って多くの方が離職に至ることも珍しくありません。
このようなトラブルを避けるためには、正社員登用の明確な基準や条件を設け、それを従業員全員にしっかりと伝えることが大切です。公平性を保ちつつ、透明な評価とコミュニケーションを心掛けることで、健全な職場環境の維持につながります。
正社員登用までの流れ
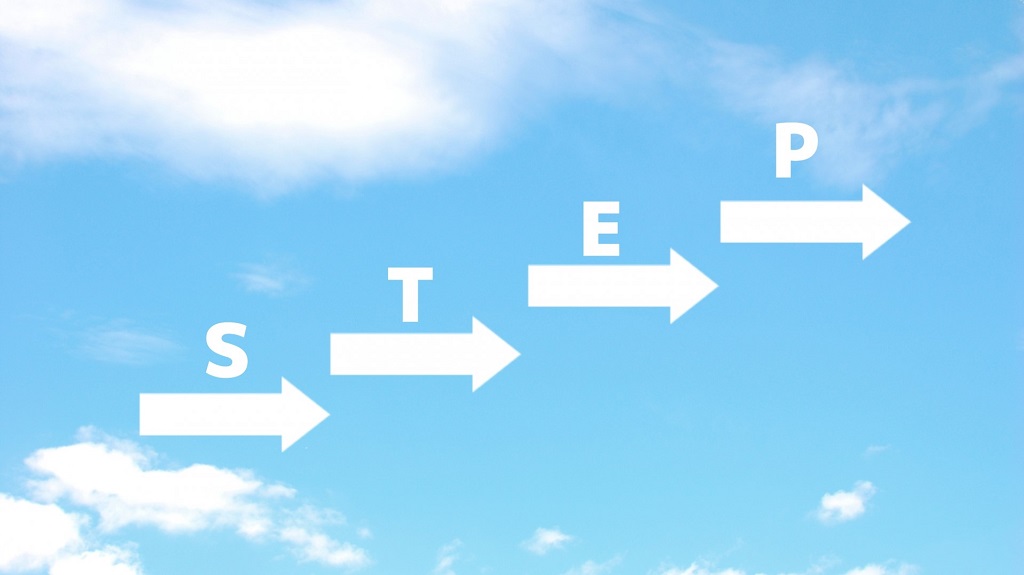
多くの企業がアルバイト・パート、契約社員を正社員として登用する際、(人事戦略や組織のニーズに応じて)一定の手順やプロセスを設けています。具体的には、制度自体の導入にはじまり、対象者を選定したうえで適性試験を実施する流れです。適性試験に関しては、大抵が採用選考さながらに面接とセットで行われます。そしてそれは、上司のみならず人事部、役員を交えた面談になることもしばしば(実際のところ、ほとんどがこのパターンに当てはまります)。これらのステップを経て、正社員としての採用が決定されるわけですが、一連の流れについては当然、企業側の理解が必須です。なおかつ従業員側にもしっかり認識してもらう必要があります。以下、各プロセスについての詳細です。
制度自体の導入
まずは正社員登用制度自体を、きちんと会社の規則の一つに組み込まなければはじまりません。そして踏み入れる第一歩は、企業の経営方針や人事戦略との整合性を確認することです。企業の成長やビジョン、目標に合わせて、正社員登用が必要な背景や理由を明確にしておきましょう。そのうえで内容設計に着手します。具体的には、登用対象の職種や部署、条件や基準に対する詳細な定義です。その際、登用後の待遇や福利厚生、キャリアパスの設定も検討できると望ましいでしょう。
上記を踏まえて、関連する部署やステークホルダーとの調整を行います。特に、人事部や経営層、現場のリーダーやマネージャーとの連携は欠かせません。その後の面談(くわしくは後述)をスムーズにするためにも、しっかりと準備しておくことが大事です。もちろん、彼・彼女らの意見やフィードバックを取り入れ、制度そのものをブラッシュアップする目的もあります(費用対効果の算出や試験運用……等々含みます)。
と、ここまで整えたなら、いざ制度の導入を全従業員にアナウンス。正確な情報の共有を通じ、従業員の理解と協力を得てようやく正社員登用制度が成立します。
候補者をピックアップ
続いて正社員登用の候補者をピックアップします。もちろん、企業によって選出方法はまちまちですが、主に取り入れられているのが「推薦」と「本人希望」の2つのやり方です。それぞれ説明します。
上司やマネージャーからの推薦
一つは上司やマネージャー、配属部署のリーダーなどによる推薦です。実績はもちろん、近くで見ている人間の審美眼を頼りに、潜在能力を加味した成長への期待も含めて正社員にふさわしい人材を選んでいきます。と、同時に意識したいのは(選ばれたかったと思われるものの)選ばなかった従業員に対するケアです。彼・彼女らのモチベーションが低下しないよう、選出されるメンバーは極力皆が納得できる人間でなければなりません。
本人希望
アルバイト・パート、契約社員の方々で本人が正社員登用を希望する場合、その意向は申し出可能です。企業としては、その意欲やモチベーションを尊重したうえで、慎重なジャッジが求められます。いうまでもなく、彼・彼女たちの期待に応えられない結果を突きつけなければならないこともあるため、状況に応じてフォローは不可欠です。
登用試験の実施
前項で繰り返し述べた納得感がたいせつであることともつながる意味ではやはり、客観的な判断に試験の実施は欠かせないでしょう。ただし、どのように進めるかはこれまた企業によりけりです。たとえば、筆記試験では一般常識、業界知識などを確認するのに使われます。より専門的なスキルを見たい場合は実技も加わるでしょう。また、グループディスカッションなどでコミュニケーション能力を測るケースも定番になりつつあります。さらには、持っているビジョンや展望を探りたいなら、その想いを小論文で表現してもらう試験方式も効果的です。
面接・面談
面接あるいは面談は、候補者の人物像や適性、モチベーションを深く探るための場です。
ゆえに正社員登用においてもっとも重要なプロセスといっても過言ではないでしょう。事実、上司だけでなく人事部、果ては取締役員さえも同席し行われることも珍しくありません。
では具体的にどのような質問が交わされているのでしょうか。
まずはやはり“なぜ正社員になりたいのか”、希望する理由の把握です。また、アルバイトや契約社員の業務においてどう貢献してきたかも、自身の言葉で伝えてもらうとよいでしょう。成功体験や困難を乗り越えた経験が正社員としての戦力につながるのなら、大いに前向きに捉えることができます。あわせて、問題解決のために取った手段や対処法、周りのメンバーをどう巻き込んでいったかも確認しておきましょう。さらには将来のビジョンです。正社員になって5年後、10年後の姿をどうイメージしているかを聞き出すことで、本人の気概はもちろん、組織の展望としても参考になり得る要素が見えてくるかもしれません。
上記を踏まえて、何より、企業文化にフィットするかどうかを評価していきます。
正社員登用する際の注意点

ここまで述べてきたメリット・デメリットそして一連の流れを踏まえて、アルバイトやパートを正社員登用していく方針が固まったなら、以下お伝えする注意点もぜひ念押しで確認できるとよいでしょう。いくつか具体的に説明します。
明確な基準の設定
明確に基準を設定することの必要性はすでにお伝えしているとおりです。実際に正社員登用を導入するなら、あらためて不可欠だと念頭におくようにしましょう。具体的には評価する項目をどれにするのか、そしてそれぞれどこまで求めるのか。たとえば業績やスキル、あるいはスタンスやアティチュード、これらに対して閾値など用意できると望ましいでしょう。
期待値の調整
正社員登用を検討する際、候補者と企業側の期待値のギャップが生じることは避けたいものです。従業員が望む業務内容や待遇、キャリアパスと、企業側が正社員として求める役割や責任、成果には必ずしも一致しない部分があります。これを最小限に抑えるためには、事前のコミュニケーションが不可欠です。そこで期待値の調整を怠ると、後になってミスマッチが生じ、離職の原因となることも考えられます。
選考後のフィードバック
結果はどうあれ、フィードバックは必要です。と、選考後もコミュニケーションは定期的に取るようにしましょう。とりわけ、今後のキャリアパスなど従業員が気になる情報は、折に触れ伝えたいところです。引き続き従業員一人ひとりのモチベーションやスキル向上につながる管理体制が求められます。
企業の成長には正社員登用制度も有効!

人材不足が叫ばれる昨今、正社員登用制度の活用は、一つの手札として持っておいて損はないかと考えます。それでも心配なら、あらためて拙稿で取り上げたメリット・デメリットを把握し自社の状況と照らし合わせるとよいでしょう。加えて、リスクや注意点も念頭におく必要があります。
仮に導入する場合は、正社員登用の意義、込めた期待についてもしっかり共有することが大切です。 効果的な人材の確保と育成を目指すべく、うまく取り入れてみてください。
なお、求職者、従業員目線で解説されている記事はこちらです。
▶正社員登用制度とは?試験内容や制度利用の実態や正社員になるメリットなどを解説!
よくある質問がまさにそうですが、彼・彼女たちが正社員登用に関して不安を抱いていることなどストレートに書かれています。
さて、正社員登用制度に直結するサービスとして紹介したいのが「バイトルNEXT」です。掲載すると、ステップを踏みながら正社員を目指す方々に自社の求人を訴求できます。制度以上に、企業を魅力的に映してくれるはずです。
▶バイトルNEXTは求職者のネクストを応援する社員募集サイト
【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所
代表 荒武 慎一
同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。

