まずは基本概要を学ぼう!年末調整とは?
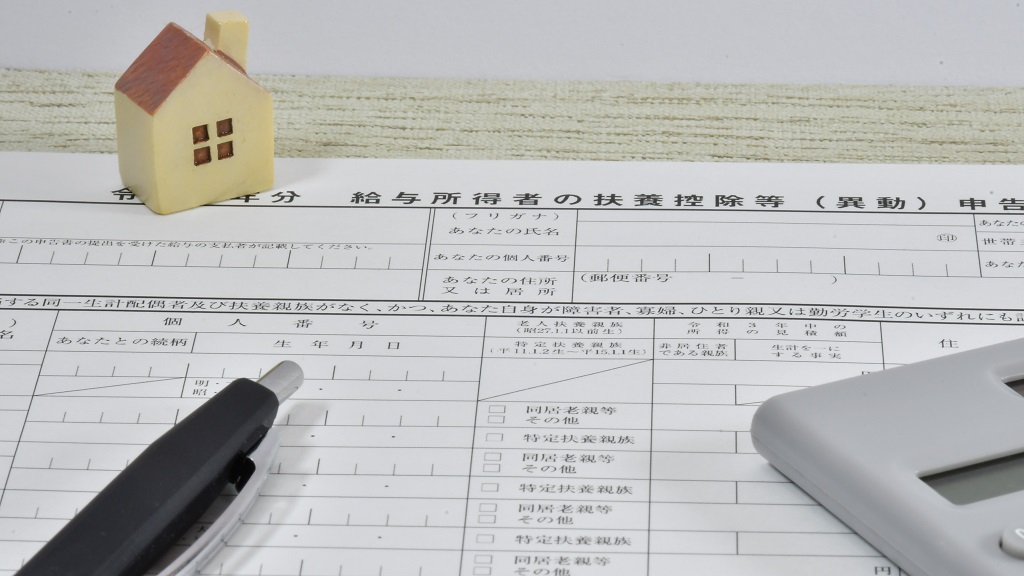
年末調整とは、給与所得者の一年間の所得税額を精算する手続きです。企業は従業員の給与から予定どおりに税金を天引きし、年末に所得状況を再計算して適切な額を出していきます。このプロセスを通じて、従業員が過剰または不足して支払った税金を調整し、最終的な正しい税額を確定させます。
以下、対象や目的、全体的な流れについてフォーカス。いずれも基礎的な知識ですが、だからこそしっかり把握しておく必要があります。
年末調整の対象になる人、ならない人
年末調整の対象になる従業員はざっと次のとおりです。
- 1年間勤務している人
- その年の途中で勤務開始し、年末まで勤務している人
- その年の途中で海外転勤などにより非居住者となった人
- 12月中に給与を受け、その後退職した人
- 心身の障害により退職し、再就職の見込みがない人
- 死亡により退職した人
一方で、日雇い労働者やその年の給与所得が2,000万円以上の方、(12月以前に転職された場合を含めて)自社とは別の勤務先で年末調整を行う人などは対象外です。また、災害減免法により源泉所得税および復興特別所得税の徴収猶予または還付を受けた人にも年末調整は行われません。
年末調整の目的
年末調整は、サラリーマンや給与所得者にとって重要な税務処理です。基本原則は「申告納税」ですが、これは(納税者が)自身の所得と税額を計算し、所定の期日までに税金を納めるという考え方を指します。そう、いわゆる「確定申告」です。しかし、このような個々の対応は、納税者と行政の両者にとって大きな負担を強いるのも事実。そこで設けられた制度が年末調整というわけです。 勤務先が納税者に代わって、上述のように正確な税金の精算を行います。この効率化こそいわば年末調整の目的です。従業員は適正な税額を支払い、企業は税務上の責任を果たすための重要な手続きとなっています。
年末調整の大まかな流れ
年末調整は、大きく3つのステップに分けられます。まず、1つ目のステップとしては、従業員による各種申告書の提出です。大抵は11月下旬を目安に始まります。
各種申告書の回収が完了すれば、2つ目のステップに突入です。時期は12月に差し掛かり、ここではずばり、年末調整の計算を行います。あわせて源泉徴収票にまとめる作業も必要です。
そして最後のステップには、法定調書合計表などの作成・提出が挙げられます(源泉徴収票も含まれます)。これを期限内に提出できればひとまず完了というわけです。
年末調整は複雑な手続きですが、明確なステップに分けて計画的に進めることで、スムーズな実施が可能です。なお、具体的なスケジュールに関しては次章でくわしく説明します。
事前計画が肝要!年末調整のスケジュールは?

本章では、前項でも取り上げた年末調整の流れについて、より体系的にお伝えします。
以下、一般的なスケジュールです。準備、そして実施するタイミングは企業によって区々とは思います。そうはいってもやはり、ここで記載する内容は大体の基準にはなるはずです。各月の詳細も含めてぜひ、ご参照ください。
| 月 | 企業の主な対応 | 従業員の主な対応 |
|---|---|---|
| 11月 | 年末調整の通知、案内 書類の回収 給与データの整理、修正依頼などの個別対応 | 申告書や証明証などの提出 書類不備の修正、再提出 |
| 12月 | 税額計算 給与と税額の調整 年末調整の最終処理 | |
| 翌年1月 | 年末調整関係書類の提出 住民税関係書類の提出 源泉徴収票の提出 |
11月初旬:年末調整の案内
企業は従業員に対して年末調整の通知を発行します。これは、年末調整の目的、必要書類、提出方法、期限などを記載するものです。また、従業員が書類を正確に記入できるよう取り計らう必要があります。そのため、記入ガイドやヘルプデスクの情報提供も極力行うことが望ましいでしょう。
11月中旬:書類の回収
従業員に提出を求めた申告書や証明書等々を回収していきます。この時点で、書類が正確か否かをきちんと確認し、不備があれば(従業員ごとに修正・再提出依頼など)迅速な対応が必要です。
11月下旬:年末調整の実施準備
提出された書類を基に、企業はいよいよ年末調整の準備を開始します。これには、従業員の所得と控除情報の確認、給与データの整理が含まれ、その正確性を担保すべく(データの)整合性チェックも行います。
12月初旬:税額計算
控除額がわかれば、従業員の所得税額を計算します。このとき、給与計算システムを活用すると効率的に進められるでしょう。
12月中旬:給与と税額の調整
給与から源泉徴収している所得税と、年間所得に応じた正しい所得税の差額を調整します。これぞまさしく年末調整です。上乗せあるいは差し引いた税額は12月の給与に反映します。あわせてこのタイミングで、源泉徴収票を作成し従業員に渡します。なお過不足があった場合は、給与からの控除または追加支給が必要です。
12月下旬(年末):最終確認
年末調整の最終確認を行い、必要に応じて追加処理を実施。算出した数値が正確だったか否かを、くまなくチェックします。
翌年1月:関連書類(法定調書合計表など)の作成と提出
1月は、提出しなければならない書類の締め切り時期です。まず税務署には、徴収した所得税額や企業が支払った給与、報酬金額などをまとめて作成した法定調書合計表を提出しなければなりません。このなかには支払調書や源泉徴収票で記載する情報も含まれます。また、所轄の自治体(市区町村)からは、従業員の住民税を計算するために必要な給与支払報告書が求められます。
どれも1月末までです。くれぐれも期限を過ぎないよう気を付けましょう。
しっかり準備!年末調整に必要な書類は?
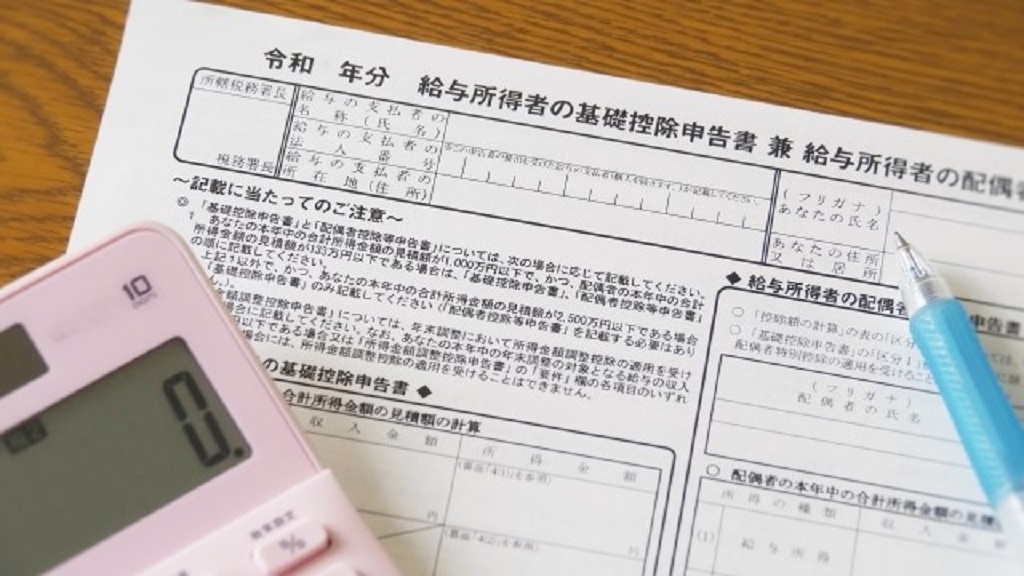
年末調整を実施する際にはいくつか書類が必要です。前述したとおり、申告書や証明書を従業員から回収するだけでなく、年末調整の計算後に作成する文書を税務署や市区町村へ提出することも求められます。細かく見てみると取り扱うそれらは思いのほか多く感じられるかもしれません。なおかつ関連書類は7年間保管しておくように定められています。(給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間-国税庁)
こうした知識をあらかじめ念頭におけるよう、さらには関連書類への理解を深めるべく、本章で説明するそれぞれの概要をぜひ、ご参照ください。
従業員から受け取る書類
従業員へ提出を求め、回収しなければならない書類には具体的に次の4つが挙げられます。
- (給与所得者の)扶養控除等(異動)申告書
- (給与所得者の)基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- (給与所得者の)保険料控除申告書
- 住宅借入金等特別控除申告書
各詳細を整理すると以下のとおりです。
扶養控除等(異動)申告書
扶養控除等(異動)申告書とは、従業員がその年の12月31日時点で扶養している親族についての情報を記入するためのものです。扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除などが対象に含まれます。勤労学生控除の適用を受ける場合や、非居住者である親族に対して扶養控除、障害者控除、源泉控除対象配偶者の控除を受ける場合には、各々指定された添付書類が必要です。
基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「所得金額調整控除申告書」それぞれが一枚の用紙に組み込まれています。各欄については次のとおりです。
参照:令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書 – 国税庁
基礎控除申告書の欄
一律38万円だった基礎控除額は2020年度から最大48万円に改正。対象者は所得が2,500万円(給与収入が2,695万円)以下の人が該当します。つまり、2,500万円(給与収入が2,695万円)を超えた場合の基礎控除は0円です。なお、所得は2,400万円(給与収入が2,595万円)を超えると減額します。 上記踏まえて2020年度からは、控除適用に基礎控除申告書の提出が必須です。この申告書では、従業員が自身の収入額から所得金額を算出(確認)できるようになっています。
配偶者控除等申告書の欄
配偶者がいる方で本人の所得が1,000万円以下(給与収入が1,195万円以下)の人が対象です。配偶者の所得が48万円以下の場合は、配偶者控除が適用されます。他方、配偶者の所得が48万円超〜133万円以下(給与収入が103万円超〜201.6万円未満)なら、適用されるのは配偶者特別控除です。つまりこれらは、本人や配偶者の所得に応じて適用の有無や金額が異なります。実際に配偶者控除もしくは配偶者特別控除の額は、配偶者控除等申告書の欄に配偶者の情報を記入し、従業員本人の所得金額と照合して算出します。従業員には正確な情報で提出してもらうようしっかり伝えることが大切です。
所得金額調整控除申告書の欄
23歳未満の扶養親族がいる方、あるいは本人か同一生計配偶者か扶養親族が特別障害者である人が対象です。かつ給与収入は850万円を超えていなければなりません。2020年度から給与所得控除が改正されたことにより(850万円を超えている方々は)所得税が増えるようになったわけですが、そのなかで子どもや障害者を扶養している人の負担を減らすことを目的に導入された控除です。したがってこの欄に記入があれば、増税分を調整する必要があります。
保険料控除申告書
保険料控除申告書には、「生命保険料」「地震保険料」「社会保険料」「小規模企業共済等掛金」について記入してもらいます。生命保険料の控除は、契約した時期によって取り扱い方が異なるため注意が必要です(2011年12月31日以前か2012年1月1日以降かで変わります)。したがって控除額は、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」に分類し、それぞれ契約時期を確認したうえで算出します。また、地震保険料控除は、従業員本人またはその本人と生計をともにする親族が所持している家屋・家財で、特定の損害保険契約などによって地震等損害部分の保険料を支払ったものに限られます。と、社会保険料控除は、国民健康保険や国民年金など、従業員が直接支払った保険料や掛金が対象です。そして小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済法に則った共済契約や確定拠出年金(iDeCo)などに支払った掛金が該当します。
住宅借入金等特別控除申告書
住宅借入金等特別控除申告書では、住宅ローン控除に関する情報を記入してもらいます。これは、住宅ローンなどを利用してマイホームを購入、新築、増改築した場合、一定の要件を満たせば「住宅借入金等特別控除」または「特定増改築等住宅借入金等特別控除」が受けられます。
| <新築住宅の適用要件> ○床面積50平方メートル以上のマイホーム ○床面積の2分の1以上が居住用 ○新築・取得から6ヵ月以内に居住を開始し、適用開始年の12月31日まで継続して居住 ○親族・知人以外の金融機関・勤務先等から借入期間10年以上、金利0.2%以上の住宅ローンを利用 ○該当マイホーム居住開始年から前後2年間ずつ(合計5年間)に居住用財産を譲渡した場合に「長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けていない ○住宅借入金等特別控除を受ける従業員のその年の合計所得が3,000万円以下 |
(対象の従業員は)初年度こそ確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で対応可能です。その際、「住宅借入金等特別控除申告書」に加え、住宅金融支援機構が発行する「融資額残高証明書」、ローンを利用した金融機関などが発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」もあわせて提出してもらうよう案内してください。
税務署に提出する書類
税務署に提出する書類には、次の3つが挙げられます。
- 支払調書
- 源泉徴収票
- 法定調書合計表
以下、各詳細です。
支払調書
従業員への給与支払いに加え、弁護士や税理士といった専門家への報酬、ライターやデザイナーへの外注費、広告宣伝費、社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬などについても詳細を申告する必要があります。これらを書類に落とし込んだものが支払調書です。年間の支払いがすべて終わった時点で作成し、翌年の1月31日までに税務署へ提出します。
源泉徴収票
源泉徴収票には、従業員ごとに年間所得額や控除額の合計を記載します。従業員用と税務署提出用があり、前者は12月中で、後者は支払調書同様、翌年の1月31日までに提出する必要があります。
▶関連記事:源泉徴収票はアルバイトにも必要!発行時期や書き方について徹底解説
法定調書合計表
給与所得そして退職所得の源泉徴収票、報酬や料金そして不動産の使用料などの支払調書の情報(人員数や支払い額、源泉徴収税の各合計)を記載するのが法定調書合計表です。つまり、前術した二つの書類、源泉徴収票や支払調書の内容をまとめることになります。税務署への提出期限は、こちらも例にもれず翌年の1月31日までです。
市区町村には給与支払報告書を提出
所轄する自治体、すなわち市区町村には給与支払報告書を提出します。期限は年末調整の翌年1月31日までです。市区町村は企業が提出する給与支払報告書を基に、次年度の住民税の額を決定します。
給与支払報告書は2種類存在します。それぞれ「個⼈別明細書」「総括表」です。以下、各概要をお伝えします。
個人別明細書
個人別明細書は、従業員ごとに給与をまとめたもので、基本的に源泉徴収票と同じ内容です。通常は給与システムで給与支払報告書と源泉徴収票が同時に作成されます。なお、紙で作成する場合、源泉徴収票の複写になっている用紙が便利です。
総括表
総括表は、事業所全体の個⼈別明細書をまとめたものです。従業員が居住する市区町村ごとに分類して作成する必要があります。具体的に記載される内容は、その市区町村に提出する個人別明細書(人数)や、報告人員の中に含まれている退職者の数などです。
最後におさらい!年末調整に関するポイントまとめ

年末調整を適切かつ正確に行うためには、つまるところ念入りにチェックすることが大事だと考えます。たとえば次のような要点は、チェックリストとしておさえておいてもよいかもしれません。
| ○従業員に提出してもらう申告書類は証明書も含めて通知できたか、期限内に収集できるか。(扶養控除等申告書、基礎控除申告書、住宅ローンや保険料控除など) ○提出された書類の内容、特に詳細なデータはダブルチェックなどでミスのないよう対処できているか。(扶養家族の情報や保険料の額など) ○所得金額に応じて基礎控除額を調整できているか。 ○年末調整を通じて、源泉徴収税額の過不足を調整できているか。 ○税務署や市区町村向けに作成する書類の提出が期限内に間に合うか(法定調書合計表や給与支払報告書など) |
保管も必要です。紙だとどうしても紛失や破損といったトラブルへの不安が出てくるでしょう。そのため近年はクラウドサービスを利用する企業も増えています。実際、Webを介することによって効率よく管理できる点は大きなメリットです。
そのほか所得税法や関連する税制の変更に対しては、常に目配りしておきましょう。また、個人情報や金融情報を扱う分、プライバシー保護とデータセキュリティには細心の注意を払わなければなりません。もちろん、データを正確に記載することも大切です。
年末調整は、従業員と企業双方にとって重要なプロセスであり、その正確かつ効率的な実施は、企業の責任と信頼性を示します。従業員の税負担が適正に管理され、企業の法的義務が適切に履行されるよう、細部まで見落とさず対応することが肝要です。
▶関連記事:甲欄、乙欄、丙欄とは?違いなどわかりやすく解説
求人掲載・採用業務のサポートや料金についてなど、ぜひ気軽にお問い合わせください。
また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談も無料で承っております!
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。ユーザーの55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。

