社内公募制度に関する基礎知識
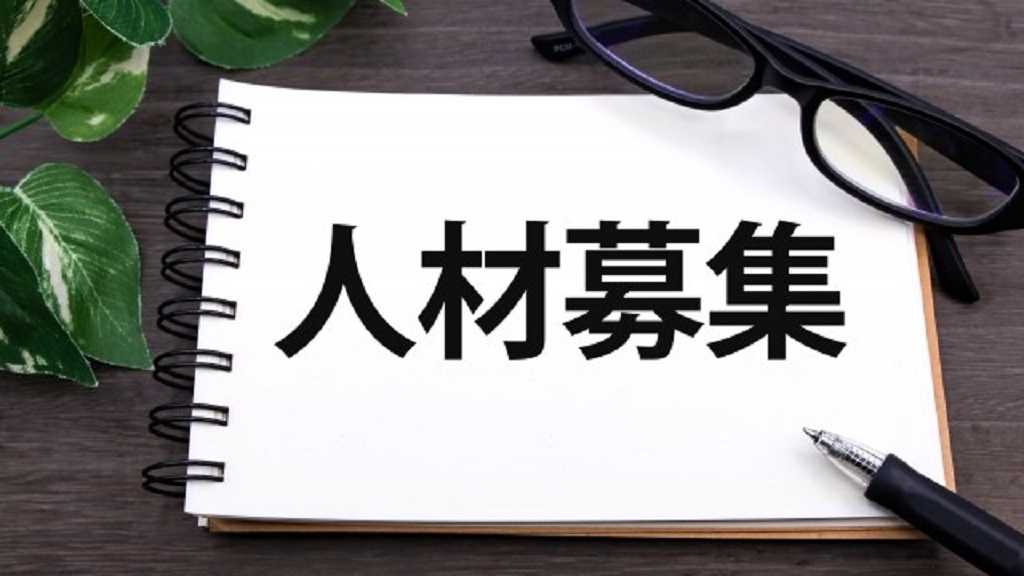
社内公募制度は、従業員にキャリアアップの機会を提供すると同時に、組織の人材活用を効率化するための重要な仕組みです。この制度によって、従業員は自らの意思でキャリアパスを選択し、企業は適材適所で人員配置することが可能になります。が、うまく運用するには前提として基礎知識をおさえておくことが必要です。社内公募の明確な定義や混同されやすい類似の人事制度との違いなど、まずはしっかり把握しておきましょう。
社内公募制度とは
社内公募制度とは、人材を必要とする部署が社内で募集をかけ、従業員が自分の意思で応募する制度です。これは「ジョブ・ポスティング」とも呼ばれ、定期的または必要に応じて行われます。従業員の自主性を促進し、キャリア自律を支援する一方で、企業にとっても、優秀な人材を適切なポジションに配置できるための効果的な手段です。
混同されやすい他の人事制度
社内公募制度は、自己申告制度や社内FA制度としばしば混同されるように見受けられます。まず、自己申告制度では従業員が異動希望などを人事部に申告し、それが異動案作成の参考情報として用いられます。ただし、実際の異動が行われるかどうかは不透明です。他方、社内FA制度は、従業員が希望する部署に自分を売り込む形で異動が行われます。これらに対して社内公募制度は、応募する従業員にはしっかりと選考試験や面接を受けてもらいます。そのうえで、採用・不採用の結果通知までを一貫して実施するものです。こうした特徴の違いからか、求人型の社内公募、求職型のFA制度と表現されることもあります。
あわせて知っておきたいリファラル採用とは?
近年、浸透しつつある人事制度としては、リファラル採用についても知っておきたいところです。これは、従業員が自身のネットワークから企業が求める人材に見合う方を紹介し、入社につなげていく採用手法です。あくまで外部の人間を募る点は社内公募制度と大きく異なりますが、自社の従業員に頼って活性化を図る意味では、実はそこまで掛け離れたものでもないように思います。
くわしくはこちらの記事をご参照ください。
▶リファラル採用とは?報酬の決め方や違法性、トラブル回避策など解説
企業が社内公募制度の導入を検討する理由

企業が社内公募制度を検討する背景には、現代の労働市場における人材採用の難しさがあります。昨今は人手不足に悩むなか、離職が相次ぐ企業も少なくない状況です。加えてこの先も、若年層の人口減から労働力低下が危ぶまれています。
と、そうした事態への対応策の一つとして社内公募制度があるのも確か。企業はそこに何を期待し、従業員がそれをどう思っているのか、以下簡単に言及します。
社内公募制度に企業が期待すること
社内公募制度で従業員を適材適所に配置することで、少なからずモチベーションひいては生産性の向上が期待できるはずです。また、組織の最適化を、今あるリソースで図ってくことも同様です。後述する採用コストの削減などのメリットにつなげるべく、実施へと舵を切る企業は決して珍しくないように思われます。
社内公募制度に対する従業員の見方
では、従業員の方々は社内公募制度をどのように見ているのでしょうか。これもまた容易に想定できることとはいえ、大なり小なりポジティブに捉えているはずです。社内公募制度の場合、あくまで自身の決断で応募します。現状の環境に対して不満を持っているケースやキャリアチェンジで人生を変えたい向きもおそらくあるでしょう。いずれにせよ、自身の意思で応募されている時点で彼・彼女たちの意欲は十分だと考えます。また、今はまだ検討しなくとも、キャリアの選択肢が自社内で残されていること自体、安心材料になっているかもしれません。
社内公募制度の一般的な流れ

社内公募制度は、募集要項の公開、告知に始まり、応募の受付、書類選考、面接選考、最終的な採用通知までの一連のプロセスを含みます。適切な人材を選出するためにも、この流れを理解することは大事です。以下、各ステップについて詳述します。
公募内容の策定
社内公募を行うにあたってまずは公募内容を策定します。すなわち募集要項の作成です。巷のそれと特段違いがあるわけではありません。具体的には、募集の背景、各部署の説明、職務内容、必要な応募資格などを含みます。無論、これらの情報は応募者が自分に適したポジションかどうかを判断するのに役立つものです。
社内広報
公募内容はイントラネットで公開されるなど社内広報を通じて従業員に伝えられます。とりわけ、応募期限や応募方法(例:専用フォームやメールアドレスへの送信など)は混乱を招かないよう明確に示しましょう。また、選考プロセスについて説明するのも、親切です。こうした配慮は、従業員を安心させると同時に、応募を促すことにもつながります。
応募の受付
従業員からの応募書類を整理すべく、窓口(担当部署)を設ける必要があります。提出された書類を収集した後は管理が大切です。加えて、応募者のプライバシー保護や情報のセキュリティにも気を配らなければなりません。
書類選考の実施
書類選考では、提出された応募書類を基に、職務要件として定めている経験やスキル、資格などと照らし合わせて判断します。過去のプロジェクトでの成果、リーダーシップといった強みも、事前に把握されていれば評価に反映させてもよいでしょう。
面接選考の実施
書類選考後は、一般採用同様、面接選考を実施します。業務遂行に関する部分はある程度計算できる前提で、重視すべきはその部署との適合性です。具体的には、コミュニケーション能力、課題解決力、チームワーク力などを見ていくとよいでしょう。社内公募であっても、(一般採用同様)結局はそこに行き着きます。また、今後のキャリアパスに対する展望や、仕事への価値観、姿勢なども限られた時間のなかで引き出せるよう意識しましょう。
内定通知
一とおり選考をクリアした応募者には内定の旨を上長と本人へ連絡します。一方で不採用者にも当然、結果をお伝えしなければなりません。この場合、本人のみへ連絡することが一般的です。
社内公募制度のメリット

実施もしくは検討される企業が増えてきている現状からも、社内公募制度にメリットがあることは容易に想定できるでしょう。具体的には、社員のエンゲージメント向上に伴う離職防止や、採用業務におけるコスト削減、社内キャリアの機会創出、組織内でのスキルセット最適化などが挙げられます。以下、それぞれの詳細です。
離職防止と社員エンゲージメント向上
社内公募制度によって、従業員が希望する環境へとシフトした場合、彼・彼女らは心機一転、仕事へのモチベーションが高まることでしょう。キャリアパスを自らの手で選択することは、やはり帰属意識や満足感の向上につながるものと思われます。また、キャリアの岐路に立つ従業員が他社への転職を模索せずとも希望を叶える機会があるのなら、結果的に、離職者を減らすことにも寄与するはずです。
研修・採用コストの削減
社内公募制度は、スムーズに進行できれば採用プロセス全般においてコスト削減が期待できます。求人媒体に出稿する費用や、ある程度人となりを知った状態で選考できること、そのうえで要件を満たしていれば、一から手取り足取り教える必要はなく、採用後の研修にもさほど時間を掛けずにすむでしょう。
社内キャリアの選択機会拡大
社内公募制度は従業員に多様なキャリアパスを提供するものです。選択肢が広がる分、各人のポテンシャルを最大限に生かせるチャンスが増えます。キャリア自律の支援にもなり、相乗的に成果への還元も期待できるはずです。
組織内におけるスキルセットの最適化
社内公募制度は、組織内のスキルセットを最適化する役割もあります。前述のとおり、従業員が個々の強みを最大限に活用できれば、組織全体の生産性向上につながるでしょう。それは、異なる部門間での人材交流という意味でも有効です。新しいアイデアや視点がシームレスに組織内で浸透すれば、少なからず企業の成長が期待できます。
社内公募制度のデメリット

社内公募制度は前述のとおり、いくつかのメリットが考えられますが、一方でデメリットがあるのも確かです。導入に際しては当然、後者へも目を向ける必要があります。以下、主なデメリットについてです。
人事業務の負担増
社内公募制度を実施するにあたっては、多少なりとも人事担当への負担が嵩むことになるでしょう。募集計画、応募書類の受理と整理、面接の調整など、選考プロセスに関わる業務は一般採用のそれとさほど変わらないように思います。むしろ勝手がわからないうちは、不安な心境とあわせて余計に手間が掛かるように感じられるかもしれません。
育成計画への影響
社内公募を通じて従業員が頻繁にキャリアチェンジしてしまうと、長期的な育成計画には大なり小なり影響を及ぼす可能性があります。もちろん、スキルの習得や経験を積んだこと自体は貴重な財産であり、何かしら活きてくることでしょう。が、せっかく戦力として育っても、そのタイミングで別の部署へと離れてしまえば、再び一から教育し直す必要が出てきます。
社内政治と不公平感の問題
社内公募制度は、社内での政治的な動きや不公平感を引き起こす可能性があります。とりわけ、ポストや昇進機会の分配に関して透明性の欠如が感じられる場合、従業員間で不平・不満や気まずい雰囲気を生む原因になり得ます。
適性が不確実
社内公募制度によって新たに就いたポストが、必ずしもその応募者に適合するわけではありません。そもそも、必要なスキルや経験が得られる土壌がこれまでの配属のなかで特になければ、闇雲に社内で人を探しても、最適な候補者を見つけることはなかなか困難でしょう。
選考プロセスの長期化
社内公募制度に固執するあまり、選考プロセスが滞ることはしばしば見受けられます。特に応募者が続々と出てきた場合は顕著です。採用決定まで長引くことは容易に想定できます。非効率に進めばタスク管理も煩雑になり、状況によっては一般採用や通常業務にまで支障をきたすことも考えられるでしょう。
社内公募を成功させるコツ

社内公募を成功させるために意識したいことは、前述したデメリットをいかに回避していくかです。そのコツを大まかにお伝えすると、透明かつ公正な採用基準を設け、適切なコミュニケーションとフィードバックの実施がカギを握ります。うまくいけば、社内公募制度自体の信頼性が上がり、自身のポテンシャルやキャリアビジョンと真摯に対峙する従業員が増えるようにもなるはずです。以下、具体的に言及します。
透明かつ公正な採用基準の設定
社内公募制度の信頼性を保つうえで、選考プロセスの透明性や公正性は、最も肝心な要素といっても過言ではありません。プロセスについては、募集背景や求めるスキルセットも含めて選考プロセスの全体像を従業員に明示することが大事です。事前に策定した詳細は、全社員がアクセスできるように公開する点も重要。そうやって透明性を持たせることで、応募者が自身のキャリアを見直し、可能性を見出す機会の創出につながります。また、採用基準が公正であるとわかれば、従業員も懐疑的にならずにすむでしょう。その結果、社内公募をチャンスと捉える向きが増え、積極的な応募が促進されるのではないかと考えます。
▶関連記事:採用条件、採用基準について決め方や注意点など解説
適切なコミュニケーションとフィードバック
社内公募を円滑に進めるためには、適切なコミュニケーションとフィードバックが欠かせません。したがって、応募者に選考状況をタイムリーに伝えることや、建設的なフィードバックの提供が求められます。特に不採用の場合には、少なからずわだかまりが残る可能性があるため、しっかりと対話することが大事です。従業員の成長をサポートし、この先のモチベーションへとつなげられれば、あらためてチャレンジしてもらうことも十分に考えられます。そうしたユースケースあるいはサイクルが生まれることで、制度としての強度も増していくはずです。
社内公募が失敗に終わるパターン

社内公募制度がうまく機能しない原因としては、選考プロセスや評価基準が曖昧であったり、コミュニケーションが十分に取れなかったりといった問題が挙げられます。そう、つまるところ、前述した成功術が必須というわけです。
せっかく導入するなら、失敗は避けたいところ。ゆえにこれらのパターンについてはあらかじめ認識しておくことが重要です。以下、詳述します。
曖昧な選考プロセスと評価基準
プロセスや評価軸が曖昧であれば、いざ応募したところで納得感を持てないまま選考に臨むことになります。いやはやその不透明性から、選考を受けたい気持ちさえ起きないかもしれません。一貫性を欠いた選考プロセスや不明瞭な評価基準によって、従業員の不信感を買うようであれば、社内公募制度は無効に化します。それどころか、実施しない方がまだよいようにも思えます。
不十分なコミュニケーション
コミュニケーションが不十分であれば、従業員(あるいは応募者)と企業(あるいは一組織)のあいだで誤解や期待値のズレが生じてしまう恐れがあります。これは社内公募制度において大きな問題です。たとえば、選考結果に対してフィードバックを行わないなどは言語道断。制度にだけでなく会社に対する信頼を損ねかねません。選考段階問わず、不要な不安を抱かせないよう、人事担当者は常日頃、従業員への目配りが必要です。
社内公募は自社の風土と目的を見失わないことが大事!

昨今は、採用難易度が上がってきたと(特に中小企業の)人事担当者が口々に漏らしているのを見聞きしますが、そうした人手あるいは労働力不足の悩みに対する策として、社内公募制度が重用されてきているのもまた確かです。当然、それはいくつかのメリットを見込んでのことでしょうが、一方でデメリットにも気を付けなければなりません。業務に対する負担が嵩まないために、育成計画が頓挫しないために、従業員に不信感を抱かせないために……等々、あらゆる側面でケアする必要があります。加えて、選考が長期化していくことも懸念材料です。
社内公募制度は、単に人材を効率的に配置する手段ではなく、従業員のキャリア支援や組織発展への促進が主たる目的だと考えます。そのためのいわば戦略的システムです。そして、うまく機能させるには、企業文化や目指す組織像に合わせた運用計画が求められます。つまるところ、自社の風土や目的を見失わないことが何より肝心です。社内公募が企業の目指す方向性と合致しているか、従業員のモチベーションやエンゲージメントにどう影響するかを常に考慮しながら、選考プロセスや評価基準には透明性と公正性を担保させ、全社員に平等な機会が提供されるよう努めましょう。
もちろん、社内公募制度に固執しなくても構いません。これまでとは異なる求人媒体を活用するなどして、状況を好転させることもできるでしょう。
以下、dip(ディップ)が提供する求人掲載サービスです。興味・関心が少しでもありましたら、料金や特徴などまずは気軽にご相談ください。お問い合わせは無料です。
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。

