職務分掌とは?

職務分掌は、冒頭でもお伝えしたとおり、組織運営の健全化に欠かせない取り組みとして、多くの企業で浸透しつつある状況です。一方で、導入したくとも理解が漠然であるがゆえに検討段階で止まっているケースも見受けられます。「なぜ必要とされるのか」「どのようなメリットをもたらすのか」「注意しなければならないことは何か」等々も、当然おさえるべき内容ですが、それらは後ほど詳述するとして、まずは用語定義など大前提把握しておきたい基礎知識から説明します。
職務分掌の定義
職務分掌(読み方は“しょくむぶんしょう”)とは、(役職も含めて)担当者の行うべき職務を整理・配分したうえで、責任の所在と業務の詳細や領域を明確にすることです。変化するビジネス環境や組織のニーズに適応すべく、一度きりではなく定期的に見直しを図る必要があります。もちろん、企業規模によって柔軟に設定することが大切です。
業務分掌との違い
業務分掌と職務分掌は、組織運営の効率化と明確化を目的としている点こそ共通しますが、その対象とする範囲に違いがあります。前者は、ずばりチーム単位です。これにより部署間での協力や連携が促進されます。一方で、後者は、個々の従業員が担うべき職務の整理です。個人レベルでの役割と責任を明確にする職務分掌に対して、業務分掌では組織レベルでの業務と権限の配置を重視します。
職務分離との違い
職務分離は、不正やミスを減らすべく、特定の業務やプロセスで各人の職務を分けるものです。つまり、業務効率化を図る職務分掌とは目的が異なります。一例として、財務関連の業務で支出の承認と実際の支払い担当者を別にすることなどが挙げられます。
セグリゲーションとの違い
セグリゲーションという言葉も聞いたことがあるかもしれません。これは職務分離と同義です。つまり、職務分掌とは目的が異なります。そう、セグリゲーションもまた不正やミスの発生を防ぐための手段です。主に、特定のプロセスにおけるリスク管理の文脈で用いられます。
ジョブディスクリプションとの違い
ジョブディスクリプションとは、各職務についての必要なスキルや資格、素質や特性を詳細にまとめた文書を指します。一方で、職務分掌は部署や役職などの個人が担う業務を整理するものです。つまり、明確化する対象が異なります(前者はスキル、後者は業務)。
内部統制における職務分掌の重要性

職務分掌によって内部統制が図れます。これは、業務の有効性や財務報告の信頼性などを高めるために重要です。そのうえで内部監査や上場審査において問われることも無視できません。以下、内部統制とは何か、目的や基本的要素なども具体的に記すとともに、職務分掌が必要な場面についても詳述します。
内部統制について
金融庁が公表している財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)では、内部統制とは、上述した業務の有効性や財務報告の信頼性といった目的達成に対して合理的な保証を得るために組み込まれているものであり、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスだと定義されています。
規定、システム、経営計画など社内管理体制が整合性を伴い機能することで、組織の健全な運営へとつながっていく仕組みです。
内部統制の目的
内部統制の目的は次の4つです。
- 業務の有効性及び効率性
- 財務報告の信頼性
- 事業活動に関わる法令等の遵守
- 資産の保全
業務の有効性及び効率性は、日々の業務において時間・人員・コストなどの組織内のリソースを合理的に使用することを意味します。その先にあるのは当然、事業の成功です。
また、財務報告の信頼性も問われます。具体的には、金融商品取引法上の開示書類(有価証券報告書及び有価証券届出書)で記載される内容の正確さ・精度です。財務諸表及び財務諸表に大きな影響を及ぼす可能性のある情報に不備があれば、たちまち組織への信頼は失われます。投資家をはじめ利害関係を有する人たちに不利益・損害を被らせないよう細心の注意を払わなければなりません。
そして事業活動に関わる法令ですが、これを遵守しなければ、しかるべき罰則が科されます。パブリックイメージも底に落ちるでしょう。逆にいうと、誠実に向き合うことで社会的信用につながります。
さらには、資産の保全も重要です。事業活動は資産あってのもの。ゆえに取得、使用、処分……等々は、正当な手続き、承認のもと行われます。有形資産に限らず、知的財産や顧客情報といった無形資産も同様です。いずれも適切な管理・活用が求められます。
これらは決してそれぞれ独立したものではありません。たとえ一つの目的を成し遂げようとする場合でも、おそらく相互に補完することの必要性が感じられるはずです。
内部統制の基本的要素
上記の目的を実現するためには、内部統制を構成する要素の整備・運用が欠かせません。
内部統制の基本的要素とは具体的に次の6つです。
- 統制環境
- リスクの評価と対応
- 統制活動
- 情報と伝達
- モニタリング
- ITへの対応
一つ目の統制環境は、組織の気風が決定すると同時に、全員の意識そして他の基本的要素にも影響を及ぼすものです。その基盤を構成するのに「誠実性及び倫理観」「経営者の意向及び姿勢」「経営方針及び経営戦略」「取締役会及び監査役又は監査委員会の有する機能」「組織構造及び慣行」「権限及び職責」「人的資源に対する方針と管理」などが挙げられます。
二つ目、リスクの評価と対応とは、組織目標の達成を阻む要因を識別、評価し、適切な対応を行っていく一連のプロセスです。そのリスクは全体レベルか業務別か、どれぐらいの頻度で発生するのかなど分類したうえで評価し、その結果をもとに適切な対応を選択します。
続いて、統制活動。これは、経営者の命令や指示が適切に実行されることを確保するために定められる方針、手続きを指します。たとえば、不正または誤謬などのリスクヘッジには、各担当者の権限、職責を明確にしていく点はまさしく職務分掌そのものです。そうやって内部統制を可視化させることで、円滑に業務が回る組織体制ができあがります。
そして、情報と伝達。いうまでもなく、内部統制に関する情報は、タイムリーかつ正確に伝えられなければなりません。組織にいる全員、さらには株主や監査機関の方々などの関係者にも共有が必要です。
内部統制が有効に機能しているかのモニタリングも基本的要素の一つです。取締役会や監査役、監査委員会、内部監査部門からも別の角度でチェックが入ります(独立的評価)。
最後にITへの対応です。これは、組織の内外どちらに対しても当てはまります。特に業務との関わりが深い場合や、高度な情報システムを取り入れているのであれば必須です。紛うことなく、内部統制の目的達成に欠かせない要素だといえるでしょう。
内部監査にあたって
内部監査にあたっては、内部監査人が職務分掌を確認します。そこできちんと内部統制が取れているかどうか、判断されるわけです。責任の所在がはっきりしなければミスや不正につながりやすくなります。それを回避するためにも、職務分掌が必要です。仮に用意できなければ、その旨指摘が入り、作成するよう促されるでしょう。
上場審査にあたって
上場する際の審査でも職務分掌が必要です。適切な権限と責任の委譲が行われているかどうか、法令は遵守されているかなどは、職務分掌規定と照合しながらチェックされます。
職務分掌のメリット

職務分掌は、ここまでお伝えしてきたように内部統制の強化や組織運営の効率化を促進する点において有用です。たとえば、職務ごとに明確な役割と責任を設けることで、円滑な業務進行が図れます。また、従業員が自身のやるべきことに集中できる環境は、人材育成にも効果的に作用するはずです。加えて、リスクマネジメントにおいても重要な役割を果たします。職務ごとに明確化された責任範囲は、業務上の問題が発生した際に責任者を迅速に特定できるため、対応が後手に回らずに済むでしょう。
以下、こうしたメリットについて、より具体的に掘り下げて言及します。
円滑な業務進行
職務分掌は、タスク過多や無駄な重複を回避するため、従業員の日常業務を効率よく進行させてくれます。また、そのプロセスが透明性を帯びる点も管理する側にとってはありがたいことでしょう。プロジェクトが円滑に回り、結果、生産性の向上まで期待できます。
人材育成の最適化
職務分掌により、従業員が自身の役割と責任を明確に理解できれば、同時に自主性も生まれやすくなるでしょう。もちろん、前提として各自のスキルセットに応じたトレーニングやフィードバックなど成長機会の提供こそ必要ですが、従業員が描くキャリアパスと組織が望む姿が重なれば、前者は充実感を得やすく、後者はポテンシャルの引き出しにつながる期待が持てます。つまりは、人材育成の最適化が図れるわけです。企業によってはその時々で部署異動を行うなど試行錯誤を繰り返すところも少なくありません。それも踏まえて効率的に最適解を出すのであれば、職務分掌はやはり、役に立つ取り組みだと考えます。
▶関連記事:人材育成とは?目的、課題、目標設計の方法など主要ポイントを解説
リスクマネジメントの効果的な実践
職務の明確化は、リスクの早期識別と対処を容易にし、業務プロセス全体の安全性と信頼性を高めます。その結果、内部統制がより強固になれば、不正やミスも最小限に抑えるあるいは事前に防ぎやすくなるかもしれません。このように、職務分掌は組織の運営を安定させる基盤として機能させることができます。
職務分掌の注意点

前述のとおり、職務分掌は組織にいくつかメリットをもたらしますが、同時に注意すべきデメリットも存在します。それらを認識せず実践した場合、想定していた成果がみられないどころか組織の成長に暗雲が立ち込める事態を招きかねません。そうならないよう以下取り上げる注意点を把握することが大事です。対策も含めてご確認ください。
従業員のモチベーション低下
職務分掌で業務が決められることに窮屈さを覚える従業員も少なからずいらっしゃいます。与えた役割に不満を持たれてしまえば、モチベーションの低下につながるでしょう。無理やりミッションやキャリアパスを指定されたと捉える向きもあります。加えて、とりあえず指示を待てばよいと解釈されるケースも見受けられます。そうなると本来、自主性を育むものであるはずが、まったくもって逆効果です。
したがって、いたずらに職務分掌が行われないよう、常日頃からコミュニケーションを疎かにせず、適性の見極めや従業員の意向を慮る必要があります。そのうえで慎重に実施しましょう。
業務範囲外への対応
職務分掌の規定が絶対視されてしまうと、イレギュラーに発生した業務には誰も手をつけなくなることが考えられます。もちろん、責任の所在が明確になっていないからといってその仕事を無視するわけにはいきません。最悪、従業員同士で押し付け合うなど軋轢が生じる恐れもあります。そうしたケースまで想定し、規程とは別にルールを設けることが必要です。あわせて、職務分掌の範囲外に及ぶ場合は、その働きを評価制度に反映させてもよいでしょう。
規程に対する向き合い方
職務分掌によって、各業務の担当あるいは責任者が本当にその人でよいのかどうかは慎重に判断しなければなりません。必要なスキルとの適性はもちろん、権限が一人に集中しすぎないようにも目配りしましょう。が、そうやって苦労して作り上げたとしてもなお、有効に作用しないことはあります。大事なのは柔軟性。決して固執せず、定期的に見直しを図ることが大切です。組織や役職の定義、業務内容自体が変化(時に進化)していく局面で既存の規定に縛られるのは得策ではありません。また、業務担当を横断し複数の部署が連携した方が、そのプロジェクトを効率的に進められるケースは往々にして見受けられます。そうした側面も念頭におきながら臨機応変に行動できるよう、規定作成にはぜひとも工夫を凝らしたいところです。
職務分掌の規程を作成するまで
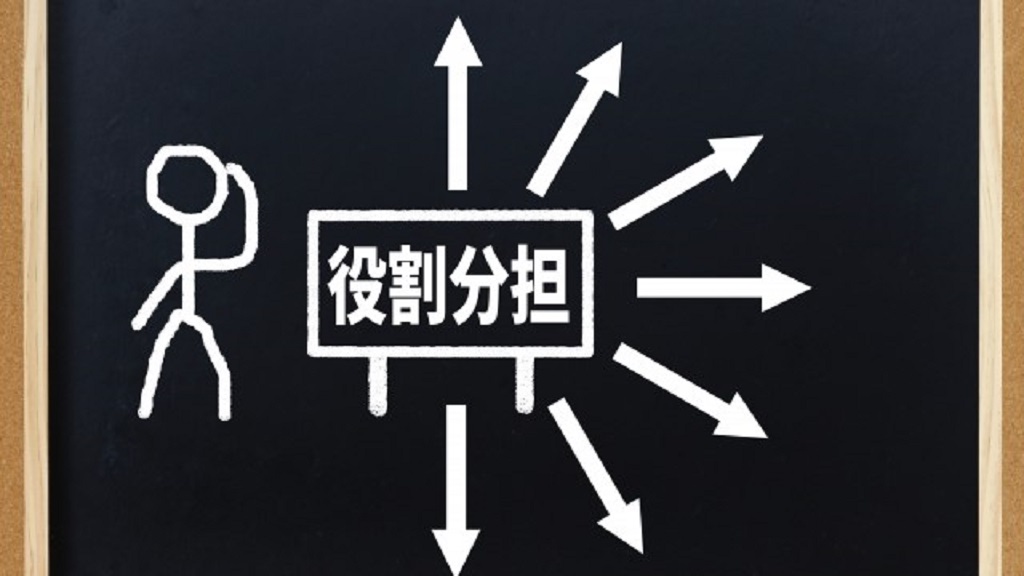
さて、それでは実際に職務分掌規程を作るまでにはどのような手順を踏めばよいのかお伝えします。大きくは以下のステップです。
- 組織の現状を把握
- 職務内容の細分化
- 責任範囲、権限領域の明確化
- 関連する書類の用意
- 職務分掌を整理、定めた内容の文書化
それぞれ解説します。
組織の現状を把握
職務分掌規程を作成するにあたってまずは、組織の現状を正確に把握することが必要です。そこで、経営陣はじめ各部署の従業員から直接情報を収集します。やはり、現場の実態や業務の特性を理解していなければ、意味のある職務分掌の作成は困難です。課題、改善点も含めて詳細な聞き取りのもと、全体像を描いていきます。
職務内容の細分化
ヒアリングで得られた情報のなかには当然、職務内容が含まれています。次のステップとして行うことはずばり、それらに対する細かな整理です。こうしたプロセスを蔑ろにしてしまうと業務の重複などが生じやすくなります。無自覚のまま生産性にも悪影響を及ぼしかねません。適材適所で円滑に仕事を回していくためにも、職務内容の細分化は必須です。
責任範囲、権限領域の明確化
職務を細分化したあとは、責任範囲や権限領域まで明確にしましょう。
前者は各業務に対して誰が責任を負うかを決めます。まさに責任転嫁しやすい状況が生まれないよう複数の部署が関わるプロジェクトに対してはどうするのかなど、はっきりルールを定めることが不可欠です。状況によっては一般社員、従業員では対応しきないこともあるでしょう。したがって、上司あるいは会社が責任を持つケースの線引きもはっきりさせておかなければなりません。責任範囲が定まれば、業務遂行に必要な権限も決めていきます。データ閲覧などは部署を横断することも考えられます。協業も視野に入れて検討しましょう。
関連する書類の用意
いよいよ書類の作成に着手します。が、すぐに職務分掌規程に取り掛かるわけではありません。先に関連書類から用意しましょう。具体的には次のとおりです。
第一ステップの段階で組織の体系化が図れたと思いますが、それをあらためて図に落とし込みます。このとき、部署ごとに作るのがポイントです。煩雑にならないよう丁寧に扱いましょう。
そのうえで、各職務の担当者や重要度をまとめた「職務分担一覧表」。仕事内容そして難易度を抽出、目標・成果までを記す「職務基準書」。さらにそこから責任の所在や必要スキルの要件を明確にする「職能基準書」。この二つの基準書を統一した「職務・職能基準表」を作成していきます。
職務分掌を整理、定めた内容の文書化
ここまで設定してきた内容に則り、職務分掌規程を作成します。企業によって区々とはいえ、目的、組織や部署、職務や責任、実施期日などは漏れなく盛り込みたいところです。また、テンプレートや支援ツールを使うのも一つでしょう。一方で、自社での作成が難しい場合は、トラブル防止のためにも社会保険労務士に依頼することをおすすめします。専門家に相談することで少なからず安心できるはずです。
職務分掌を成功に導くために

職務分掌は、組織運営の健全化や業務の効率化、さらには人材育成にもつながる側面があります。そうはいってもやはり、ただ漠然と行えばよいわけではありません。メリットばかりに目がいってしまわないよう注意点も念頭におくようにしましょう。なおかつ適切なステップのもと規程の作成には取り組んでいただきたいです。もちろん、適宜見直しを図ることも大切。曖昧な方はぜひ、あらためて拙稿を参考にしてみてください。
求人掲載・採用業務のサポートや料金についてなど、ぜひ気軽にお問い合わせください。
また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談も無料で承っております!
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーの55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。

