春闘とは
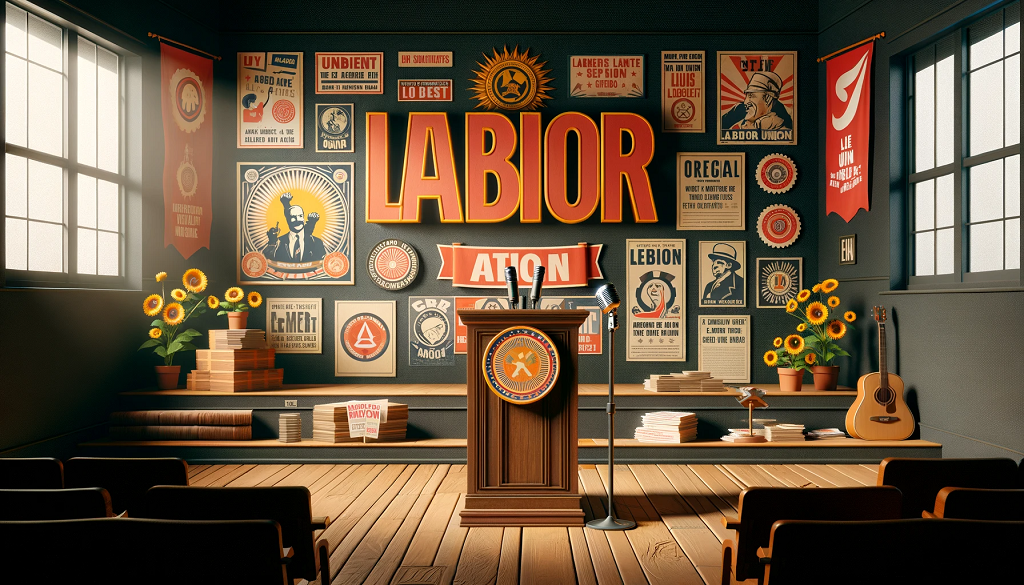
春闘(読み方は“しゅんとう”)とは、毎年2月から3月にかけて行われる日本の労働運動の一環です。正式名称は「春季生活闘争」ですが、一般的には、件のとおり「春闘」の呼称が浸透しています。
内容は、冒頭でもお伝えしたように、労働組合が使用者側に対して賃上げをはじめ労働条件や環境の改善を要求するものです。過去には労使交渉が決裂した際、労働組合がストライキに発展したこともあります。以降、アプローチの仕方が段階的に変わったことも手伝ってか、そこまでの事態には至っていませんが、一方で昨今問題視されている人手不足を理由に、企業の多くがその要求を受けざるを得ない状況になっている可能性は否めません。記憶に新しいところでは2023年、満額回答という形で交渉が速やかに決着するケースが続出したのは象徴的な動きだったと考えます。
さて、上記の定義に加え、労働組合の種類、目的や企業への影響、一連の流れなども前提知識としておさえておきたいところです。以下、具体的にお伝えします。
春闘を行う組合組織
春闘を行う労働組合は、全国規模のものから産業別、企業別と分類されます。とはいえ、いずれも労働者の権利を守るために活動している点は変わりません。
日本全国の労働者を代表する労働組合組織には、主に「日本労働組合総連合会(連合)」「全国労働組合総連合(全労連)」「全国労働組合連絡協議会(全労協)」などが挙げられます。そして、それらの傘下にある自動車産業や電気産業など各産業固有の労働組合が産業別組織です。さらに、そこに(一部が)従属する企業別労働組合が、企業内の労働条件の改善に向けて奔走。その会社の経営陣と直接交渉を行います。
つまるところ、全国的な労働組合組織である連合・全労連・全労協が、産業別、企業別の労働組合を統制し、一斉に労使交渉するのが春闘というわけです。
春闘の目的と企業への影響
春闘の主な目的は、待遇や労働条件の改善、加えてその先にある一人ひとりの生活水準の向上です。個々の声では届かなかったことを、組合組織でもって実現を図ります。
加えて、これは決して労働者だけのためではありません。企業側にとっても結果的にプラスに作用する期待が持てます。人手不足が深刻化する昨今、やはり賃金水準や人事制度の見直しは経営戦略上、欠かせません。もちろん、そこには労働時間の短縮や安全な職場環境の確保なども含まれます。これらは少なからず労働者からすると魅力的な要素です。よりよくすることで求人・採用にもよい影響をもたらすでしょう。
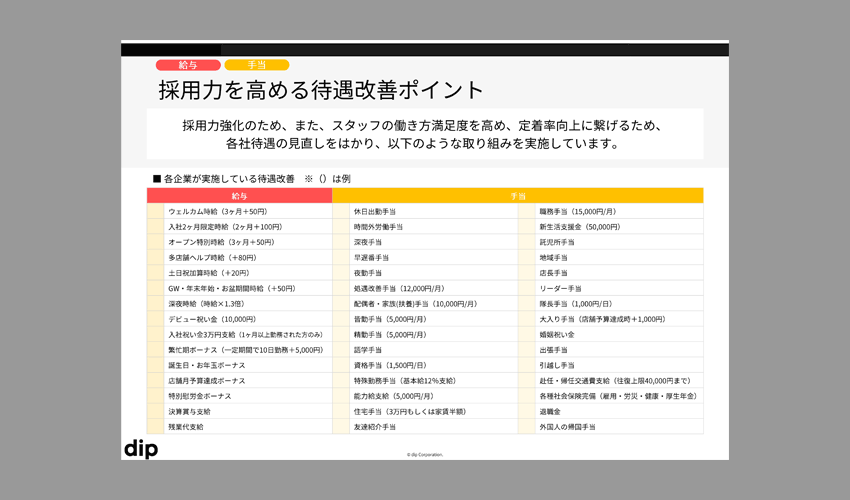
2022.06.22
採用力を高める待遇改善ポイント
待遇改善の取組み事例を一覧化しました。採用力を高める待遇改善チェックリストとしてご活用ください。 こんな方にオススメです 採用力を強化したい スタッフの満足度を高めたい 定着率を向上させたい ダウンロードフォーム hbspt.forms.create({ p...
春闘の流れ
春闘は、準備を含めると厳密には労働組合組織が基本的な方針をまとめるところから始まります。前年末を目途にそれが終えられると、続けて1月、発表された全体方針を基に産業別、企業別で要求水準、要求内容が決定し、2月に入り交渉が行われます。重大な局面が訪れる時期は、例年3月中旬頃です。そのタイミングでは、とりわけ大手企業からの回答が集中する傾向にあります。以降は中小企業も続々と対応していき、3月末までには、すべての春闘が終結していく流れです。これによって労使間の新たな合意が形成されることになります。以下、詳細なステップです。
- 全体方針の発表
- 要求水準の決定
- 要求内容の決定
- 労使交渉
- 妥結
それぞれ説明します。
全体方針の発表
春闘の準備段階として、(全国的な)労働組合組織が集まり検討を重ねていきます。そのうえで前年12月から1月にかけて全体方針を発表。これは、産業別組織が要求水準を決める際の重要なガイドラインです。
要求水準の決定
産業別組織における要求水準の決定は、先に発表された全体方針に基づいて行われます。仮に賃金に関する要求であれば「ベースは3%、ボーナスを含めた総額では5%の引き上げ」といった明確な数値が定められることが一般的です。これは、企業別労働組合が要求内容を決めるうえでの重要なドキュメントであり、個別交渉を行う際の基準になります。
要求内容の決定
要求水準を基に、企業別労働組合が要求する内容は決まります。当然、企業によってさまざまです。現実的なものに落とし込めるよう財務状況や業績、過去の交渉結果、および労働市場の動向などが考慮されます。
労使交渉
要求内容が決まれば、いよいよ労使交渉の始まりです。すなわち、春闘のハイライト。労働者、使用者双方にとって重要な意思決定の場です。当然、難航するケースも考えられます。企業によっては扱う事項が多岐にわたることもあるでしょう。とはいえ団体交渉を正当な理由なしに拒むことはできません。山場は大体3月頃です。
妥結
交渉成立後は、詳細を記した合意書を作成します。以降、その内容が新たな約束事です。
今後の労働条件に反映していくことになります。
官製春闘とは?
春闘に先駆けて行う、政府が経団連に対する賃上げ要請を「官製春闘」という言葉で表現(揶揄)することがあります。これは、経済の活性化や消費促進が主な目的です。原則として労働条件は労使間で決めるものとはいえ、政府が介入することで結果的に(労使間の)力関係に均衡が図れるケースも少なくありません。いずれにしても、労働市場全体の賃金水準に影響を与えるものです。
春闘で要求されること

先述したように、春闘で要求される内容は企業によってさまざまです。状況いかんでは多岐にわたることもあります。具体的には次のとおりです。
- 賃金の引き上げ
- 長時間労働の是正
- 育児や介護に関する制度の充実化
- 企業間の格差是正
- ダイバーシティの推進
それぞれ説明します。
賃金の引き上げ
賃金の引き上げは、春闘においてもっともポピュラーな要求といっても過言ではありません。2023年は物価上昇への対応がフォーカスされ、ベースアップが強く求められました。一方で、年齢や勤務年数などに配慮した定期昇給も春闘の重要な議題です。ここについては、昨今、年功序列制度が崩れはじめたこともあり、能力主義や成果主義に基づく賃金制度への移行が進んでいます。そのため、(そうした時代背景に合わせて)交渉内容も多角的になっている印象です。
長時間労働の是正
春闘では、働き方改革の一環として長時間労働の是正、ひいてはワークライフバランスの実現が要求されることも少なくありません。一部の企業では当たり前のように労働基準法で定められた勤務時間を超えて残業が行われていたり、また、残業代が適切に支払われなかったりといった問題が取り沙汰されているのも確かです。春闘は、こうした由々しき状況に対峙します。そしてこれは、決して労働者を守るためのものだけではありません。労働環境の改善による組織の生産性向上、さらには、従業員の余暇時間を増やし消費活動の活性化につなげる狙いもあります。
育児や介護に関する制度の充実化
育児や介護を行う労働者の支援強化も、近年、浸透しつつある要求内容です。前者に対しては男女共同参画の進展、後者については高齢化率の上昇、それぞれ社会を取り巻く現象や問題が背景にあります。実際のところ、2022年より施行されている育児・介護休業法の改正は、男女ともに仕事と育児の両立を促し、高齢化社会における介護支援を後押しする取り組みです。とりわけ、産後パパ育休制度を取得しやすい雇用環境の整備が義務化されたことは象徴的だと思われます。こうした制度の拡充を企業単位で行うために、春闘が一役買うわけです。企業側からすると、女性労働者の職場復帰やキャリア継続などにもつながる期待が持てます。
▶関連記事:パパ休暇が廃止!産後パパ育休って?違いもあわせて解説
企業間の格差是正
春闘では、企業間の格差是正も要求事項に挙げられることがあります。典型的なのは、大企業と中小企業の賃金、労働条件の差です。そうはいってもやはり、中小企業が賃上げを行うことにはそれなりに高いハードルが立ちはだかります。たとえば、人件費の増加が企業の利益減少や設備投資の抑制につながることは当然ながら無視できません。が、今後の人手不足の深刻化を考慮すると、賃上げが避けられないのも確かです。加えて、日本経済の健全な発展につなげるべく公正で均衡のとれた労働市場を創り出す必要があります。したがって、全体最適の観点からも(中小企業の労働条件改善など通じて)企業間格差を縮小することがミッションとなり、春闘が行われる(春闘で要求される)わけです。
ダイバーシティの推進
近年、そこかしこで叫ばれている多様性のある社会の実現は、春闘においても然り。そう、ダイバーシティの推進です。
▶関連記事:ダイバーシティ採用とは?企業の取り組み事例やアンケート調査の結果も交えて解説
性別、年齢、国籍、障がいの有無などにかかわらず、すべての労働者が平等に扱われ、その能力を最大限に発揮できる環境の実現が求められます。
▶関連記事:障がい者雇用とは?メリット・デメリット、助成金の話など
春闘賃上げ率
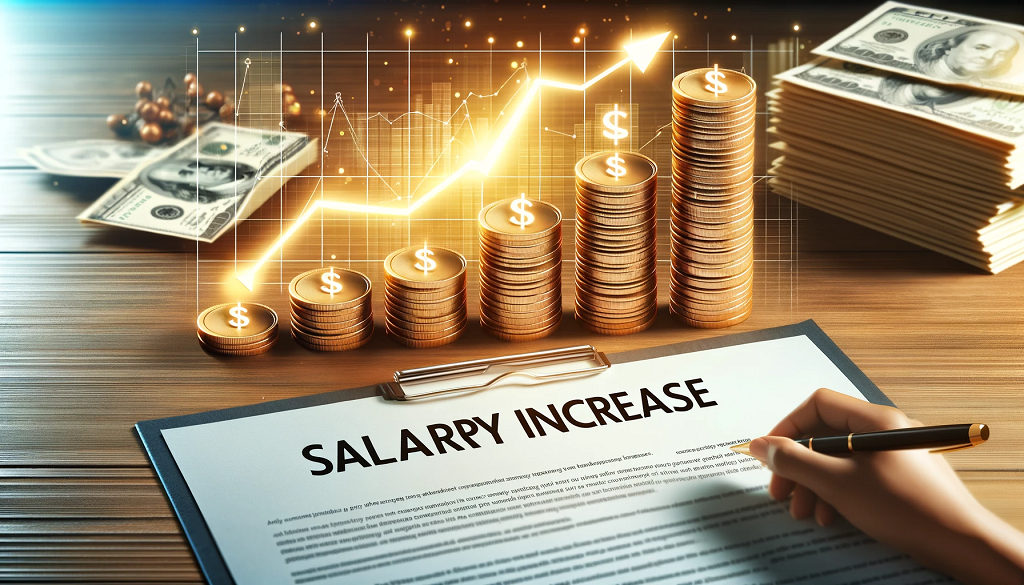
物価高の背景もあり、連合は昨年同様、持続的な賃上げの実現を目標に掲げていました。そうしたなか、2024年も全体の方針が決定。ずばり次のとおりです。
- ベースアップ相当分として「3%以上」の賃上げ
- 定期昇給分を含めて「5%以上」の賃上げ
参照元:春闘2024要求は? 賃上げ5%以上 定期昇給分含む 連合が方針固める
定期昇給分も含めると5%以上の引き上げが要求されています。2023年は5%“程度”だったところが“以上”と表記されている点に強気な姿勢がうかがえます。
方針含めた賃上げ率の推移
賃上げ率がどのように推移してきたかを知ることで、予測も立てやすくなります。過去から現在に至るまで、春闘での方針、実際の結果両方あわせて表にまとめると次のとおりです。
| 年度 | 方針(要求) | 最終結果(賃上げ率) |
|---|---|---|
| 2015 | 4%以上 | 2.38% |
| 2016 | 4%以上 | 2.14% |
| 2017 | 4%以上 | 2.11% |
| 2018 | 4%以上 | 2.26% |
| 2019 | 4%以上 | 2.18% |
| 2020 | 4%以上 | 2.00% |
| 2021 | 4%以上 | 1.86% |
| 2022 | 4%以上 | 2.20% |
| 2023 | 5%程度 | 3.60% |
| 2024 | 5%以上 | ?% |
賃上げ率の最新予測
日本経済研究センターによると、2024年の春闘賃上げ率(厚生労働省「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」ベース)は3.85%と予想されています。これは、予測を行ったエコノミスト36人の平均値です(最高は5.0%、最低は3.2%だった模様)。
なお、内訳は基本給の引き上げ分が2.15%、定期昇給分が1.70%です。
非正規春闘とは

いまや春闘は正社員だけで行われるものではありません。従来のそれとは異なり、非正規社員の賃上げに寄与しようとする気運は確実に高まっています。2023年以降に最低賃金が大きく引き上げられたことは、まさにその流れを汲んだ重大なトピックだったといえるでしょう。
▶関連記事:2023年度の最低賃金決定!引き上げ額は?いつから?【全国一覧】
▶関連記事:2024年度の最低賃金(地域別、全国平均)~引き上げ額は?いつから適用?~
同じ年、これまで交渉に含まれていなかった非正規労働者からの声が上がり、この「非正規春闘」が公に宣言されました。2024年以降は、物価高も相まって活発化される見込みです。すでに非正規春闘実行委員会は、インフレに賃金が反映されないことを課題に挙げ、本格始動する旨の声明を出しています。もちろん、賃上げだけでなく育児や介護に対する目配り、ワークライフバランスの実現なども例にもれず要求事項の対象です。
2023年の結果
2023年の非正規春闘では、全国の労働組合に参加する非正規雇用の方々が集まり、勤務先の企業36社に対して「一律10%」の賃上げを要求。そのうち16社で実現されています。
2024年の方針
2024年の非正規春闘については、非正規春闘実行委員会が、非正規雇用で働く人たちの勤務先に対して10%以上の賃上げを要求することを発表しています。“以上”が示すことからも、あくまで昨年要求した10%は閾値にすぎないことがわかります。
春闘を受けて企業が取り組むべきこと

春闘で賃上げを行うことに対し、つい負担と捉えてしまいがちですが、結果的に功を奏す形で人材獲得や定着につながるケースもあります。とりわけ中小企業は、人手不足の問題が年々深刻化している状況です。
以下、採用・育成・定着の観点から、春闘を受けて企業が取り組むべきことをお伝えします。
柔軟な採用
人手不足に悩む企業が数多存在するなか、アルバイト・パート含めて採用は年々難しくなっています。一方で求職者は、現在の社会情勢も味方にしつつ、自身が納得する形で入社することを望む方がほとんどです。したがって、待遇面や職場環境など選ばれる求人のために工夫を凝らす必要があります。なかでも昇給、時給アップは最たる例です。
▶関連記事:アルバイト・パートの昇給について時給アップの事例も交えて解説
なおかつタイミングも大事。毎年10月には全国的に最低賃金の引き上げが行われます。が、給与の見直しはその時で問題ないと高を括ってしまうと、結局のところ他社と比べて横並び、あるいは後れをとり、採用に手こずる恐れがあります。逆にいうと、なるべく早いうちに賃上げを実施できると給与面で他社よりも魅力的な求人になり、採用を優位に進められる期待が持てるでしょう。人手不足を解消していくには、そうした柔軟な採用がどうしても不可欠です。もちろん、人件費は嵩みます。そのため、生産性の面でカバーできるよう工数が掛かっている業務の見直しもセットで取り組むことが大事です。
解像度の高い人材育成
春闘を経て人件費が嵩むことになっても、育成強化によってコストパフォーマンスを高めることは可能です。労働力人口が減っていくなかで、組織の持続的な成長を“採用”だけに依存するのはどうしても無理があります。やはり、従業員の能力向上は欠かせません。それは彼・彼女たちの自己実現、ひいては育ててくれた組織への信頼にもつながるでしょう。春闘が労働組合の団結で成り立つように、自社内でも一体感のあるチーム作りが肝要です。
▶関連記事:人材育成とは?目的、課題、目標設計の方法など主要ポイントを解説
従業員の定着促進
人材獲得後は、当然、定着してもらうよう努めなければなりません。疎かにしてしまえば、たちまち人は離れていきます。前述した待遇改善や育成プログラム、そのほか職場環境などで見直せることがあれば、積極的に取り組んでいきましょう。
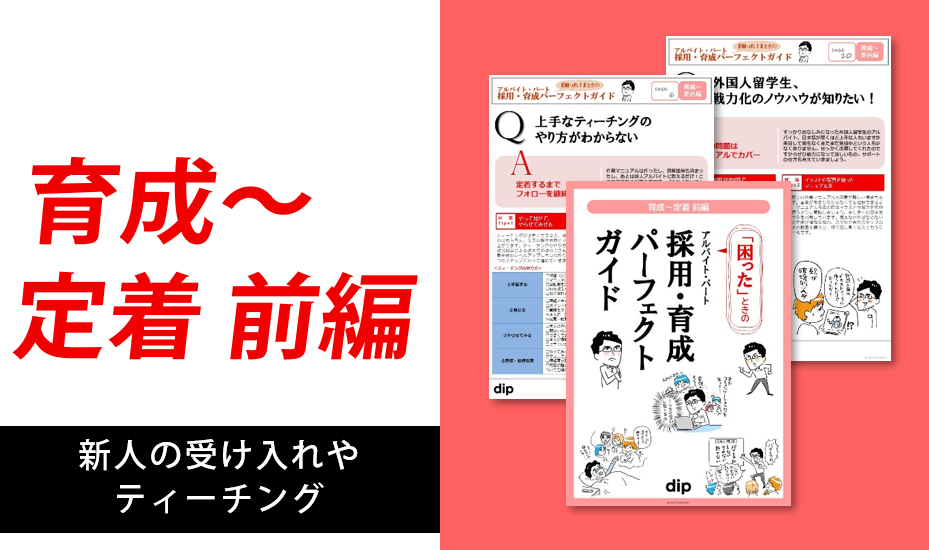
2022.07.13
採用•育成パーフェクトガイド 育成~定着編(前編)
アルバイト・パート採用時のアルバイト募集の掲載に関するノウハウを徹底解説!毎月1万社以上の採用活動のサポートを行っているバイトルのメソッドが集約。 こんな方にオススメです 採用した人が長く続かない ずっと働いてもらうためにやるべきことって何? ダウンロードフォーム hb...
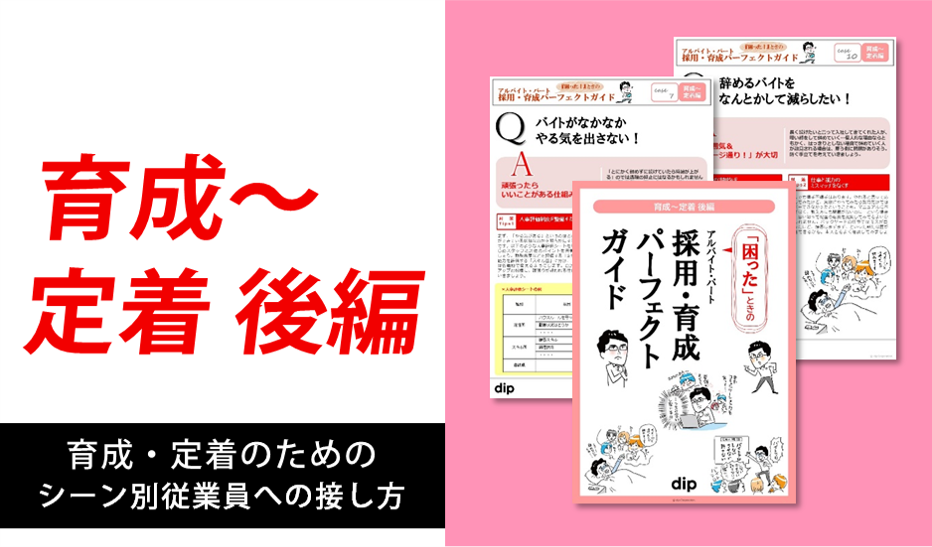
2022.07.13
採用•育成パーフェクトガイド 育成~定着編(後編)
アルバイト・パート採用時の育成~定着までのノウハウを徹底解説!毎月1万社以上の採用活動のサポートを行っているバイトルのメソッドが集約。 こんな方にオススメです スタッフの褒め方・叱り方が分からない バイトテロを防ぐ方法が知りたい 退職手続きの方法が知りたい ダウンロードフォーム ...
春闘を受けて企業が注意すべきこと

春闘に際して企業は、交渉以前に法的な観点や長期的な視点を持つ必要があります。労使関係の健全な発展と持続可能な成長は、どのみち目指さなければならない企業の命題です。もちろん、交渉過程においては透明性や公正性を保ちつつ、現実的で建設的な対応が求められます。そうした点を踏まえて、以下、企業が注意すべきことについて取り上げます。
不当労働行為
労働組合法第7条2号に基づき、使用者は労働組合からの団体交渉申し入れを「正当な理由」がない限り拒否することができません。この規定に従わなければ、いわゆる不当労働行為に当たります。また、たとえ団体交渉に応じた場合でも、春闘の参加者に対して不利益な取り扱いを行うのはご法度です。そのほか、労働組合の結成あるいは運営を支配しこれに介入することや、運営費について経理上の援助(※)を行ってもいけません。
※基金に対する寄附および最小限の広さの事務所の供与を除く
対応の持続性
春闘での交渉は、短期的な利益に終始せず、組織の長期的な成長を考慮しなければなりません。特に経済的余裕の少ない企業が無理な賃上げを行う場合、あるいは毎年のようにそれが続くことで、財務的に困窮し、競合と戦えなくなってしまう可能性もあります。結果、雇用の不安定化を招けば、従業員が離れていくのも無理はないでしょう。だからといって、まったく要求に応えないわけにはいきません。大事なのは、採用同様、柔軟な姿勢です。賃上げ要求を額面どおりで呑むことに固執せず、福利厚生や会社独自の制度などを新たに設け、働きやすい環境の構築もぜひ視野に入れてみてください。もちろん、待遇面で改善できるポイントがあれば前向きに検討していくのが望ましいと考えます。いずれにしても対応の持続性を思案し、経済的な現実と将来の展望を踏まえ交渉することが重要です。
業績の透明性
業績の透明性もまた、春闘において気を付けなければならないポイントです。これは、企業の経営状況を労働組合に対して正確に伝えることを指し、結果、信頼につなげる意味があります。労働組合側に現実的かつ合理的な要求をしてもらうためにも、蔑ろにせず誠実に対応しましょう。
春闘で困らないために

近年の春闘ではあまり目立たないものの、雇用形態問わず誰もが参加者になれる今、労働者側がストライキを起こすことも十分に考えられます。実際のところ非正規春闘実行委員会は、企業側が要求に応じない場合、そうした行動を辞さない姿勢です。したがって、今後の春闘の行方としては、アルバイト・パートの方々が中心となっていくようにも思います。
そのうえで、企業が目指すべきは定着する人材の確保です。
採用プロセスにおいては、ミスマッチを防ぐために、職場の様子を動画や写真でリアルに伝えるなどし、面接時にも業務内容について具体的な話をすることが必要だと考えます。応募者に仕事内容や職場環境を事前に理解してもらうことは、労使双方にとってメリットです。
▶関連サービス:【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
また、採用後は育成のための研修を定期的に実施できるとよいでしょう。従業員一人ひとりのスキルアップを図れることはもちろん、業務の効率化や新たなアイデアの創出も促進できます。
さらには、キャリアパス制度の明示も重要です。これによって、従業員は自身の成長を見据え、目標に向かって努力する意欲が芽生えやすくなるでしょう。
そして当然ながら、賃上げについてもポジティブに捉え、対応することが大事です。やはりモチベーション、満足度に直結しやすい待遇面での計らいは、人手不足問題における筆頭格の解決策であり、離職者増加の抑止力にもなり得ます。
春闘を通じて企業が従業員の採用、育成、キャリアパスの明示、そして賃上げに積極的に取り組むことは、総じて、企業の持続可能な発展へとつながるはずです。
求人掲載・採用業務のサポートや料金についてなど、ぜひ気軽にお問い合わせください。
また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談も無料で承っております!
▶アルバイト・パート採用に強い「バイトル」のサービス資料はこちらからダウンロード(無料)
▶社員採用に強い「バイトルNEXT」(ネクスト)のサービス資料はこちらからダウンロード(無料)

