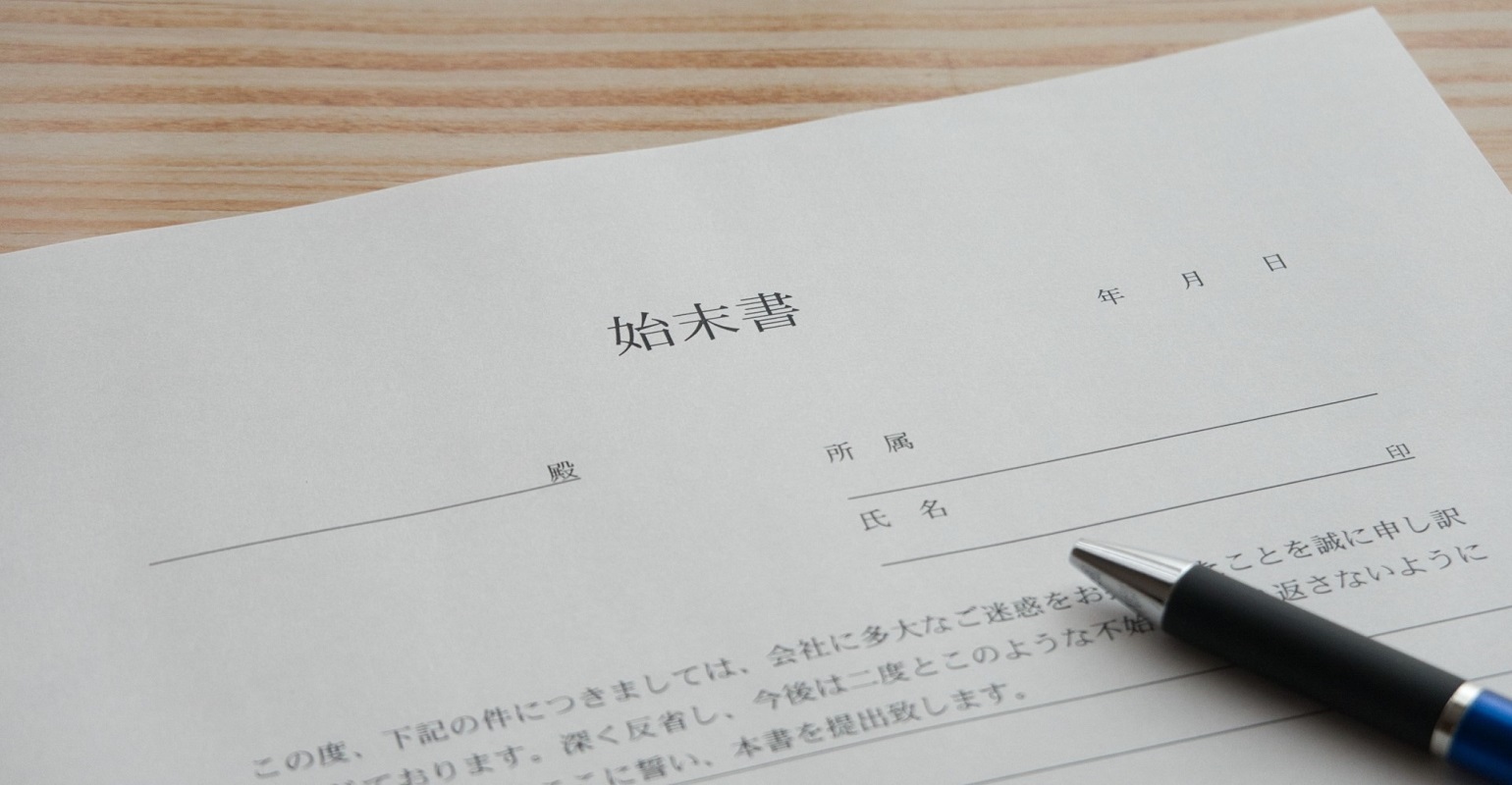始末書とは?顛末書や反省文との違い

始末書とは何か。まずは、大まかに把握するうえで知っておきたい基本的な概要や混同しやすい他の文書との違いを説明します。
始末書の概要
始末書とは、従業員が大きなミスやトラブルを起こした際に謝罪、反省の弁を記すとともに一部始終を報告し、以後繰り返さないことを会社に対して誓約する文書です。冒頭でも述べたとおり懲戒処分の一つに該当します。自省する機会を与えるとともに再発防止の意識を促すことが目的です。
あらためて後述しますが、作成が必要なケースとしては「会社が所有する備品の紛失・破損」「度重なる寝坊・遅刻」「過失による甚大な損害」「就業規則を守れていない」などが挙げられます。
顛末書との違い
顛末書も始末書と同様に、従業員が勤務中に起こした大きな問題に対して会社に提出する文書です。ただし、重視するポイントは異なります。顛末書は、事実と経緯を詳細に報告することが主な目的です。第三者による客観的な視点が求められるのもそのためだといえます。一方、始末書の場合は、反省の気持ちと再発防止を約束することに力点が置かれる傾向にあります。
▶関連記事:【例文付き】顛末書とは?書き方、注意点を企業向けに解説
反省文との違い
反省文は、始末書同様、文字どおり反省の意を示すものですが、もはやそれ(反省)に終始するといっても過言ではありません。始末書はあくまで今後の行動改善につなげる文書ですが、反省文は本人の行いを振り返って生じるお詫びの気持ちに焦点が当たります。本人が起こした行動を自ら見直す、いわば個人的な報告書です。
始末書を作成する手順と望ましい書き方や対応

始末書の作成を指示する際、あわせて手順とコツまで伝えられると、効率的かつ内容にも深みが出るでしょう。加えて、フォーマットまで共有できれば、各人の書式がバラバラで確認しづらい事態を防ぐこともできるはずです。上記踏まえて、以下、参考にしてみてください。
全体構成を決める
始末書は大きく分けて次の3つの要素で構成することをおすすめします。
「ミスやトラブル、違反した内容に関する説明(被害や損害についての具体的な情報、状況含む)」
「自らの責任を認めたうえでの謝罪の言葉」
「再発防止策及び再発させないことの誓約」
裏を返せばこれらは、最低限必要な項目です。いっそのこと社内で必須事項として共有するのもよいでしょう。
事実を整理する
いざ始末書の作成に取り掛かる前には、構成決めに加え、事実の整理も行っておきましょう。ここで気を付けたいのは、下手に体裁を取り繕わないことです。すなわち、起きた問題をぼかしたり、濁したりせず明確に伝える意識で、事実をまとめます。また、言い訳や責任転嫁と受け取られかねない表現も避けましょう。反省の気持ちがないと判断されることがあります。実際に記載する際、小細工を弄する真似はご法度です。
コンパクトにまとめる
さて、いよいよ記載するとき、まず意識したいのがコンパクトにまとめることです。どの項目においても長々しく述べるのはやはり、内容が分かりづらく(読みづらく)なるため避けたいと考えます。もちろん、必要な情報はあますことなく伝えるべきです。どうしても多くを説明したい場合は、一文を短く切る、箇条書きにするなど一工夫入れて表現してください。
再発防止策は具体的に記載する
再発防止策は具体性が高いほど、当然、読み手には伝わりやすくなります。そして、それによって分かることは決して対策内容に限りません。反省の度合いも測れるものだと考えます。再発させないようどこまで深掘りしたかは、解像度を高く上げる作業に比例するはずです。すなわち、再発防止策の具体性を高めれば高めるほど、真摯に向き合っていくことになるといえます。裏を返せば、企業側もそうした観点を持つことが大切です。
適切なタイミングで提出する
始末書は作成することがすべてではありません。いうまでもなく、提出して成り立ちます。ここで気を付けたいのが提出のタイミングです。トラブルの内容によっては、即座に始末書の提出が必要な場合もあれば、事態の収束を待ってからの方がよいこともあります。したがって、企業側が提出を指示する際は、状況判断が不可欠です。ただし、一般的には早ければ早い方が望ましいでしょう。
始末書が必要なケースと例文の一部を紹介
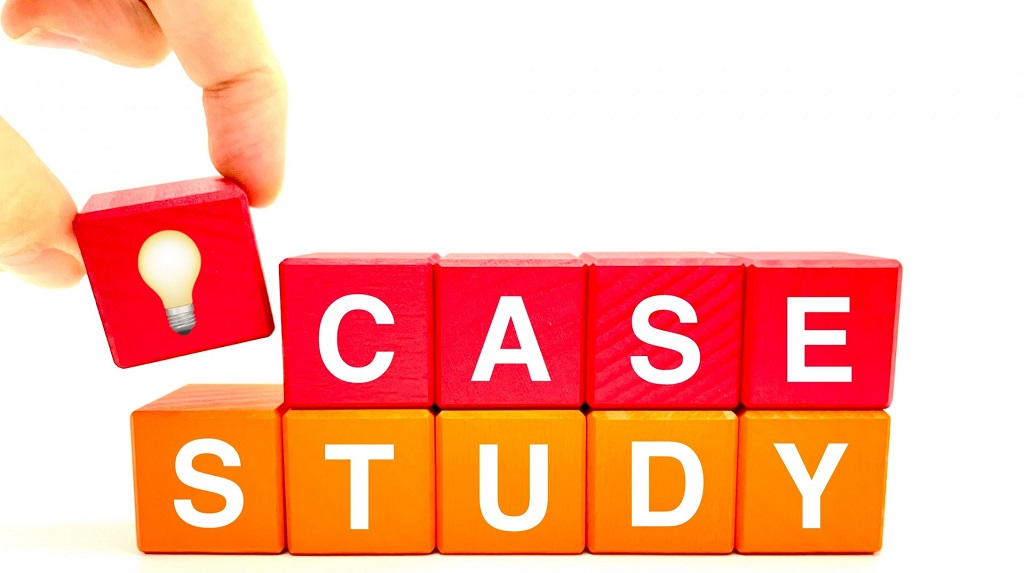
本章では、始末書が必要なケースに加え、実際に書くうえで参考にしたい例文の一部や注意点を紹介します。
始末書が必要なケース
始末書の提出を要するのは、主に次のようなケースです。
- 社内外に金銭的損失を負わせた
- 社内規定や就業規則に違反した場合
- 企業の社会的イメージを著しく傷つけた
- 法律に違反した場合
企業ごとにその尺度や判断基準は異なるとはいえ、概ね上記が事例として挙げられます。とりわけ法に触れた場合は、あらゆる手続きが必要です。始末書レベルで済まないことを、組織のなかでしっかり認識させましょう。
例文の一部と注意点
度重なる遅刻を繰り返した従業員のとある始末書の一部がこちらです。
| 私は再三の注意を受けたにも関わらず、令和4年11月1日からの1ヶ月間、正当な理由のない遅刻をくり返し、業務に支障をきたし、部署の皆様に多大なご迷惑をおかけしてしまいました。 すべては、自己管理能力の欠如が原因であり、弁解の余地もございません。 深く反省し、心からお詫び申し上げます。 今後は自己管理を徹底し、二度とこのようなことがないよう細心の注意を払い、与えられた業務に全力で取り組むことをお誓いいたします。 誠に申し訳ございませんでした。 |
ざっくり簡潔にまとめている点に関しては、一定の評価ができるでしょう。しかし、上記の文面だと再発防止策に具体性が欠けているともいえます。たとえば、前日は何時までに就寝し、家を出る時間もこれまでより何分早くするといった内容が加わるとまた印象は変わるはずです。受け取る側、すなわち企業側は曖昧に感じた点があれば蔑ろにせずフィードバックしてください。
と、例文を扱う際は注意点もあります。業務効率化を図るべく企業側でフォーマットを用意するのは有効ですが、あくまで内容は対象従業員一人ひとりの気持ちがこもっているかどうかを軸に評価しなければ本末転倒です。少し手直しした程度の文章で提出させては始末書の本来の意義が損なわれます。従業員の反省を促すためにも、自らの不始末を振り返り、自分の言葉で書くことを絶対としたうえで、共有(場合によっては指導)しましょう。
始末書提出後の処分対応について

始末書の作成後に企業側はさらに処分を下す必要はあるのでしょうか。以下、法律に基づき言及します。
二重処罰について
繰り返しお伝えしてるとおり、始末書を提出することは、それ自体が会社の就業規則に則った処分の一つです。それ以上の罰則を科すことは、二重処罰に該当します(一事不再理の原則に反するといった考え方もできるでしょう)。
また、始末書の不提出を理由に出勤停止処分など、別の処分を行った場合も同様です。先に始末書の提出を求めた時点で、問題の行為に対する懲戒処分は終了します。ただし、後述しますが、始末書の提出とセットで扱われる処分があるのもまた事実です。
懲戒処分の種類
該当する懲戒処分によっては、始末書だけでは済まないこともあります。これは二重処罰ではなく、そもそも始末書込みで科されるものだからです。いずれにせよ、懲戒処分にはどのようなケースがあるのか知っておく必要があります。以下、懲戒処分の種類です。
訓戒
口頭もしくは文書による厳重注意を指します。原則、始末書の提出はありません。ただし、反省文や報告書を作ってもらうことは要求できます。懲戒処分のなかでは最も軽い処分です。
譴責(けんせき)
始末書の提出が必要です。が、それ以上は特に科すものはありません。仮に、追加して処分を下してしまうと二重処罰に該当するため注意しましょう。
減給
厚生労働省のモデル就業規則にあるように減給は始末書とセットで科しても構いません。ただし、ある程度大きな失態でない限りはむやみに適用するのは憚れます。訓誡や譴責を経ても改善がみられない場合などに与えらるのが一般的でしょう。
出勤停止や降格降職
これらも、始末書を提出させたうえで、下される処分です。出勤停止は一定期間の出勤の停止を命じられ、その間の賃金は支払われません。降格降職は等級の引き下げや役職を解くことです。
論旨解雇や懲戒解雇
論旨解雇は退職届を提出すように勧告するもので、懲戒解雇は予告期間を設けずに即時解雇することをいいます。始末書どころでは済まない、まさに最も重たい処分です。
始末書をもっと有意義なものに!
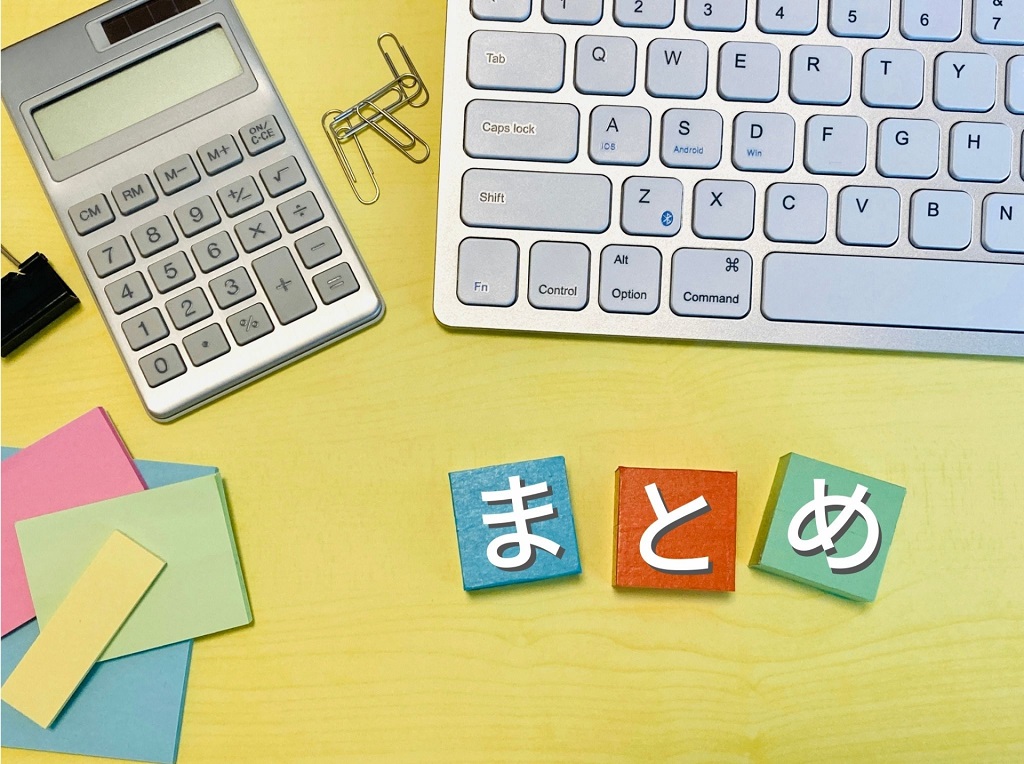
始末書は一人の従業員だけでなく組織全体にとって重要な文書です。意味のないものにならないようルールや方針をしっかり定めておく必要があります。仮に該当する従業員が出てきても、真摯に向き合う姿勢を当たり前に意識させることができていれば、当の本人含めて、士気は下がらずに済むでしょう。いわば挽回のチャンスとして位置づけられると、理想的かもしれません。
さて、そうやって組織改革あるいは強固なチーム体制構築に欠かせないのが採用活動です。それはアルバイト雇用でも同様に期待が持てます。たとえば派遣も直接雇用案件も掲載できる「はたらこねっと」のサービスは、実績はもちろん、求職者の層が幅広い分、これまでマッチングが難しかった企業様でも欲しい人材に辿りつきやすい傾向にあります。気になる方は、無料でのお問い合わせ登録からはじめてみるのもおすすめです。ぜひ、ご検討ください。