ボーナス(賞与)の定義

ボーナス(賞与)とは、従業員に対して定期的な給与とは別の扱いで支給される報酬を指します。毎月の給料は、労働基準法第24条2項で支払いが義務付けられていますが、ボーナスは法律上、明確なルールが決められているわけではありません。企業ごとに支給の有無や金額、時期は区々です。よく見られるケースとしては、たとえば、業績や個人評価に基づき夏と冬でそれぞれ支給されるといったパターンが挙げられます。
ボーナスの減額が違法に当たるケース

前述のとおり、ボーナスは支給に義務はなく企業が任意で設定するものです。そうはいっても、就業規則や契約上の定め、もしくは過去の運用実績次第では、安易な減額がトラブルを引き起こしかねません。事実、法に抵触する恐れさえあります。理不尽な真似によって従業員に訴訟を起こされる可能性も否めないでしょう。本章ではこうした懸念を禁じ得ない違法に当たるケースについて解説します。
就業規則や契約に反した減額
ボーナスの支給条件が就業規則や雇用契約書に明記されている場合、原則としてそれを守らなければなりません。仮に「全従業員〇ヶ月分支給」と明文化されているにもかかわらず、恣意的に金額を下げることは、契約違反と見なされるわけです。たとえやむを得ない事情が出てきたとしても、定められたルールとの整合性が重視されます。
団体交渉義務に反した減額
労働協約でボーナスの支給条件が取り決められている場合、企業側が一方的に変更することはできません。団体交渉を経ずに減額を強行すれば、不当労働行為に該当する恐れがあります。減額の対象や理由にかかわらず、組合との協議なしに進めることは避けるべきです。
差別的な取り扱いによる減額
同じ等級・職務内容で働く従業員のうち、特定の年齢層や国籍の社員だけを減額対象とするような差別的な扱いは到底許されるものではありません。また、育児休業や介護休業から復帰した社員に対し、不当に低い支給額を設定することも問題視されかねない理不尽な対応です。これらは労働基準法や男女雇用機会均等法などに抵触します。
労使慣行から外れた減額
就業規則や契約書に明記されていなくても、過去に継続的かつ一貫してボーナスが支給されていた場合、その実績は労使慣行として扱われます。そのため、突如一方的に減額を行うと、黙示の合意を無視したものと見なされ、違法と判断されるかもしれません。
ボーナスの減額が可能なケース
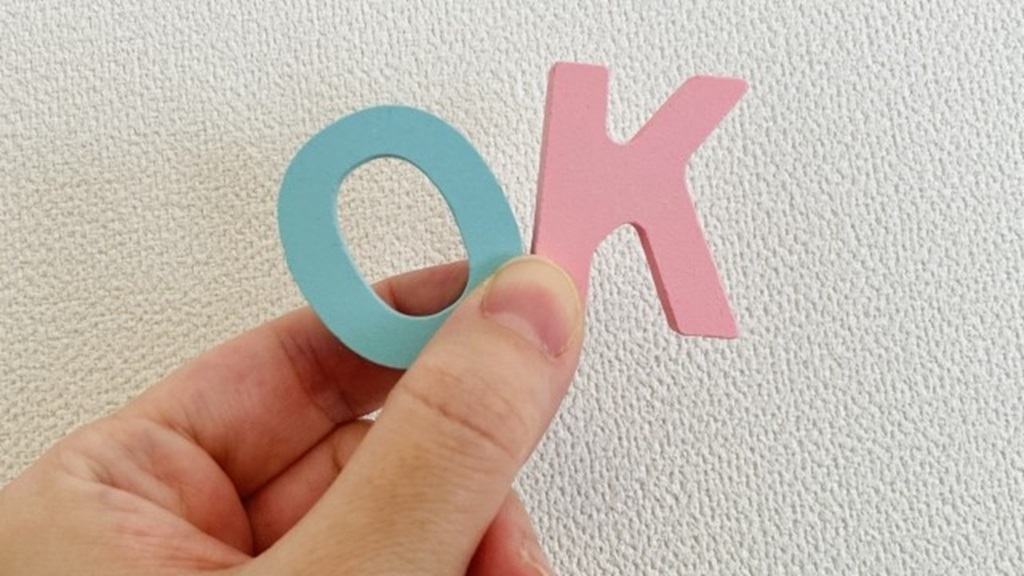
違法か否かの判断は、前提として就業規則や契約のなかで(倫理規範や法的観点も含めて)どう定められているかがカギを握ります。本章では、減額が許容される代表的なケースをいくつかピックアップ。ざっと次のとおりです。
- 支給が業績連動型の場合
- 従業員の勤務態度に問題があった場合
- 在籍条件を満たさない場合
- 従業員が休業中の場合
これらの状況を加味することで、合理的に対応できるでしょう。
支給が業績連動型の場合
あらかじめ業績に応じて支給額を決定するといった方針が就業規則や契約書に明記されている場合、その基準に従った減額は原則として問題ありません。たとえば、営業利益や売上高が一定水準に届かなかった場合に支給額を抑える、といった取り扱いは、合理性のある運用と見なされます。ただし、基準が不透明なケースや後出しで変更されたように見える場合は、不信感を与えトラブルにつながることもあるため、条件設定や従業員への周知には注意が必要です。
従業員の勤務態度に問題があった場合
賞与の支給に関して勤務態度や業務成績を評価の対象とする旨が就業規則にて定められている場合、著しく規律を乱す行為や極端に成果が下がった従業員に対して減額を行うことは一定の合理性があります。ただし、問題と見なす評価が主観的すぎると、後に不当と受け取られる恐れもあるため、減額の根拠を客観的に示せる状態にしておくことが重要です。指導記録や人事考課の内容がその裏づけになります。
在籍条件を満たさない場合
「支給日現在で在籍していること」などの条件があらかじめ就業規則や雇用契約に明記されているなら、該当するケースでは減額も正当です。退職予定者についても、納得できる形で共有されているのであれば問題ないでしょう。無論、条件は明瞭に、そして運用にも一貫性を持たすように気を付けましょう。これが疎かになると不利益変更や差別的取り扱いと見なされることも考えられます。
従業員が休業中の場合
産前産後休業や育児休業、介護休業などで一定期間就労していない従業員に対しては、在籍中であってもボーナスを満額支給しないケースがあります。が、これが直ちに違法となるわけではなく、支給対象期間の労務提供実績をもとに按分するなど、合理的な算定方法が取られていれば減額は可能です。ただし、休業を理由に一律で不支給とする場合や、復帰後の扱いに偏りがある場合は、育児・介護休業法などに抵触する可能性もあるため、判断には慎重さが求められます。
ボーナスを減額するのに必要な手続きや対応
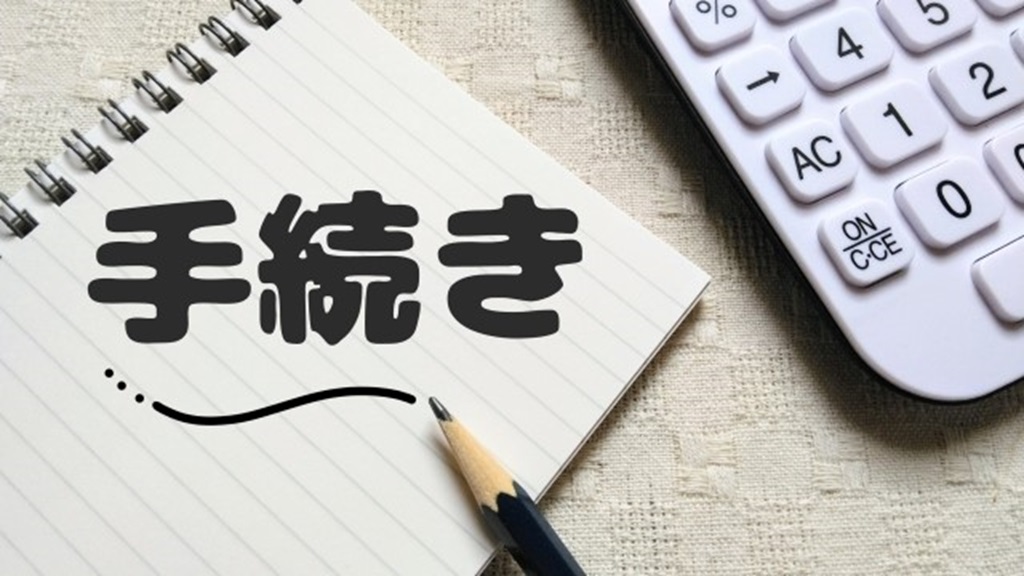
違法性を避け、かつ減額が合理的であったとしても、減額を実行に移すには一定の手続きを経る必要があります。具体的な流れは次のとおりです。
- 就業規則に記載
- 対象従業員への通知、説明
- 賞与不支払届の提出
以下、それぞれ説明します。
就業規則に記載
ボーナスの支給条件や減額の基準を明確にするためには、就業規則にその内容をあらかじめ記載しておく必要があります。たとえば、「業績に応じて支給額を調整する」「懲戒処分があった場合は減額の対象とする」といった規定が前提として共有されれば、減額が妥当かどうかも客観的に判断できるはずです。不合理かつ不利益変更にならないよう、まずは文面上の整備を怠らないようにしましょう。
対象従業員への通知、説明
ボーナスの減額をいざ実施する際には、対象従業員へ事前にその理由を伝えることが望ましいでしょう。たとえ制度上の正当性があったとしても、説明が不十分であれば不満や誤解を招きかねません。職場全体の信頼関係にもひびが入る恐れがあります。どのような事情で、どのような基準により減額が生じたのかを丁寧に説明し、納得してもらえるよう(納得せざるを得ないと思ってもらえるよう)真摯な姿勢で向き合いましょう。
賞与不支給報告書の提出
ボーナスの支給を減額のみならず実施すら取りやめる場合は、日本年金機構への「賞与不支給報告書」の提出が必要です。これは、従業員の生活保護を目的とした行政手続きであり、企業本位の判断を牽制する意味も含まれます。なお、提出しないまま一定期間経った場合は、督促状が送られてくるでしょう。それでも放置してしまうと、年金記録に誤りや延滞金が発生する恐れがあります。
参照:5-1:賞与を支給したとき、賞与支払予定月に賞与が不支給のとき|日本年金機構
ボーナスの減額に上限はあるのか?

ボーナスは法的に支給が義務づけられた賃金ではないため、「何割までしか減額してはならない」といった明確な上限規定は存在しません。しかしながら、著しい減額は労務トラブルの火種になりやすいため慎重に検討すべきでしょう。過去の支給実績や社内の説明責任の果たし方によっては、事実上、ここまでが限度というラインが生まれることもあります。金額の問題ではなく、背景や手続きも含めて妥当性を判断する姿勢が肝要です。
ボーナス減額後の人材流出リスクに備えて

ボーナスの減額は大なり小なり従業員にとってはネガティブな要素です。モチベーションの低下から転職の検討につながる可能性も大いに考えられます。そのようなリスクを見据えたとき、具体的にどういった対策が必要なのでしょうか。本章では、人材の定着、そして採用の観点から、効果的だと考えるアクションについてお伝えします。
従業員のモチベーションを下げないための工夫
ボーナス減額後、特に何もフォローせずにいると、上述したようにモチベーションが低下し帰属意識も失った挙句、転職活動に踏み切る向きもあるでしょう。最悪、連鎖退職を引き起こしかねません。これを少しでも緩和するにはやはり減額の理由や背景を丁寧に伝えることが大事だと考えます。ただそれだけで納得させるのも難しいかもしれません。だからこそ、希望を見出してもらえるよう前向きな言葉が必要です。たとえば、業績が改善すればそれなりにボーナスが増え、場合によってはこれまでを上回る可能性があることや、評価制度を従業員がもっと報われるものにできないか検討している旨など、信頼をつなぎとめるためのアクションが求められます。
人員を新たに確保するための手段
ボーナスの減額がきっかけで従業員が離職した場合、欠員補充は避けられません。ただでさえ人手不足が深刻化するなか、即戦力を見つけるのは容易ではなく、採用活動そのものの工夫が問われます。特に短期間で人員を確保したい場合は、それなりに認知度の高いサービスを選定する必要があるでしょう。もしくはスポット的に募集していくのも一つの手です。これもまた特化したサービスを利用するなど実は(媒体の)見極めが求められます。経験者が欲しい場合もそう。ミスマッチを避けつつ母集団形成を図っていくことが肝要です。
なお、dipが提供する求人サービスはあらゆるニーズに対応しています。アルバイト・パートの応募を安定的に集めたいなら『バイトル』、スポットワーカーを即日採用するなら『スポットバイトル』、社員採用に注力したいなら『バイトルNEXT』、プロフェッショナル人材と出会うなら『バイトルPRO』といった具合です。ぜひ、ご利用のほど検討ください。
▶【公式】求人広告を掲載、採用業務を支援-dip(ディップ)
ボーナスの減額と柔軟に向き合うために

ボーナスの減額は、企業にとっても心苦しく難しい判断だと思います。が、ときに経営判断として避けがたい局面があるのも確かです。そのうえで一方的な対応にならないよう配慮しなければ、たちまち従業員を失っていくことになるでしょう。法的なトラブル回避はもちろん、人材定着にも目配りできなければ、ボーナスの支給、ひいては事業継続も危ぶまれます。したがって、減額せざるを得ない状況のなかでいかに柔軟な対応ができるかが肝になるわけです。従業員との対話や納得形成を丁寧に積み重ねること。そして採用にも注力すること。こうした愚直なアクションが結果的に、組織の成長につながると考えます。
求人掲載・採用業務のサポートや料金についてなど、ぜひ気軽にお問い合わせください。
また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談も無料で承っております!
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【公式】スキマ時間のスポットワーカー募集ならスポットバイトル
┗スキマ時間で「働きたい」と「働いてほしい」をつなぐ求人マッチングサービス。求人は無料で掲載できます。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。
▶【公式】面接コボット – 応募者対応の自動化で面接管理が楽に!
┗求人サイトからの応募対応を自動化できるサービス。チャットボットを通じ、日程調整まで効率よく進めてくれます。
▶【公式】採用ページコボット – 費用・実績も紹介!採用サイト制作サービス
┗採用ページ作成サービス。求人まとめサイトとの自動連携や求人検索エンジンへの対応により外部集客を強化します。
【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所
代表 荒武 慎一
同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。

