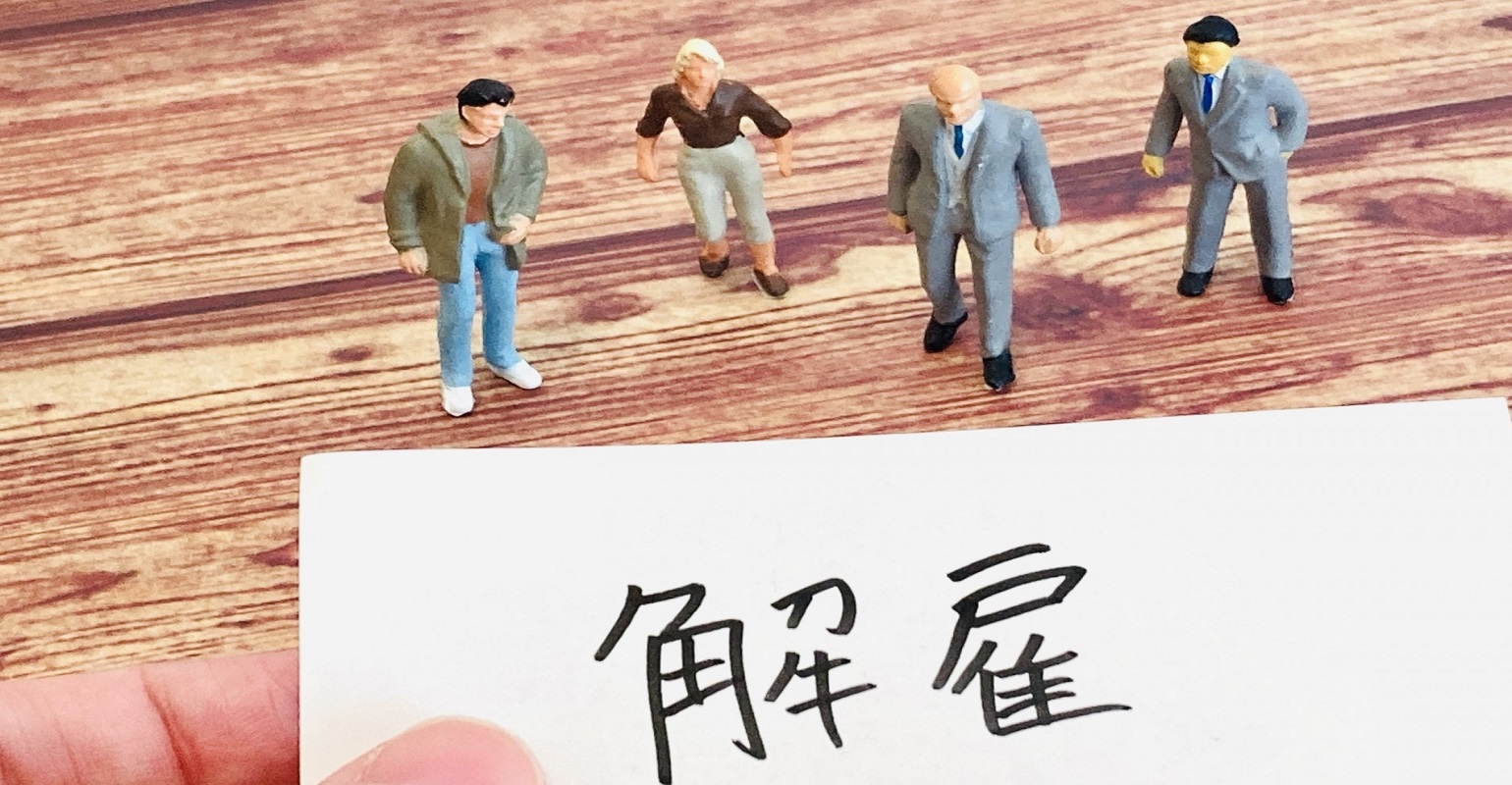解雇予告手当とは?
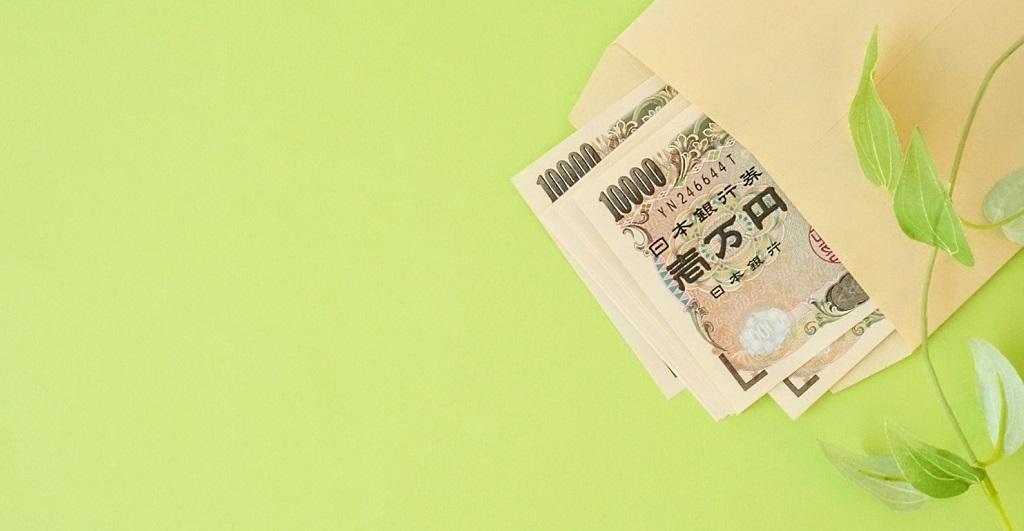
業績の悪化など、やむをえない事情により企業が従業員を解雇する場合、30日以上前にはその旨を(当該従業員に)告げなければなりません。これができないと、解雇予告手当支払いの対象になります。では、そもそも解雇予告手当とは何でしょう?以下、詳細をお伝えします。
解雇予告手当の基本概要
解雇予告手当とは、企業が解雇予告(従業員に解雇を事前に通知すること)をしないまま従業員を解雇した際に支払うべきお金です。原則、従業員の解雇は30日前に通知が必要だと労働基準法20条1項で定められています。
もちろん、急な事情でやむを得ず解雇に踏み切ることもあるでしょう。この場合、労働基準法20条2項により、30日に不足する残日数分に応じた金額を支払わなければなりません。たとえば、従業員を解雇する2週間前(14日前)に告げたなら、計算上、16日分(30日-14日)の金額です。
解雇予告除外認定
従業員に非がある旨を労働基準監督署に届け出て、解雇予告除外認定を受けられれば、解雇予告手当の支払いは免れます。
除外認定される主なケースは、次のとおりです。
- 従業員が企業のお金を盗んだ、横領した
- 賭博行為などで職場の風紀を著しく乱した
- 経歴を詐称した
- 2週間以上無断欠勤して出勤の督促にも応じなかった
- 遅刻が多く、数回にわたって注意しても応じなかった
また、地震や豪雨などの自然災害を被り、やむを得ない事由で事業の継続が不可能となった場合も、従業員に対する解雇予告や解雇予告手当の支払い義務は免除されます。
解雇予告手当の計算方法

解雇予告手当はどのように算出するのでしょうか。基本的には当該従業員の賃金が基準です。以下、具体的な計算方法をお伝えします。
解雇予告手当の計算式
解雇予告手当は次のように算出されます。
| 平均賃金1日分×解雇までの日数 |
“平均賃金一日分”の計算式は、労働基準法12条1項にて「直前3ヶ月に支払われた賃金の総額÷3ヶ月の総日数」と定義されています。
直前3ヶ月は、原則、解雇日の前日からさかのぼって数えられますが、労働基準法12条2項により賃金の締め日があれば、基点はその日です。
したがって、仮に平均賃金1日分が6,000円だった場合、10日分の賃金である6万円を支払えば、締め日から20日前に解雇することが可能です。
なお、計算上の端数は、銭未満が切り捨てられます。
解雇予告手当を計算するうえでの注意点
前項だけをみれば、シンプルに思える解雇予告手当の計算ですが、いくつか注意すべきポイントも存在します。
ミスを回避すべく、以下の内容をしっかり念頭に置くようにしましょう。
平均賃金の計算に含まない期間
平均賃金のうち、計算上、直前3ヶ月に含まない期間があります。
具体的には以下のとおりです。
- 業務上のケガや病気で休んだ期間
- 産前産後休業をとっていた期間
- 企業側の都合で休んだ期間
- 育児休業や介護休業をとった期間
- 試用期間(14日未満)
平均賃金の主な内訳
平均賃金として扱われる額の主な内訳も確実におさえておきたいポイントです。
- 基本給
- 通勤手当
- 精皆勤手当
- 年次有給休暇の賃金
- 昼食代
- 確定したベースアップの賃金
- 未払い賃金
賃金の総額から除外される対象
臨時手当やボーナスは平均賃金の計算から除外されます。
- 退職金や結婚手当、お見舞い金など
- 賞与をはじめ3ヶ月を超える期間ごとに支払われる手当
- 現物支給
解雇予告手当の最低保障額
解雇予告手当には最低保障額のルールが定められています。賃金の全部または一部が日給制、時給制、請負制の場合、最低保障額を下回ってはいけません。
最低保障額を出す計算式は次のとおりです。
| 過去3ヶ月分の賃金総額÷過去3ヶ月分の実労働日数×0.6 |
有期雇用に対する解雇予告手当
以下、有期雇用に対する解雇予告手当です。正社員と比較して説明します。
アルバイト・パート
アルバイトやパートは、月給制の従業員と同様に不足日数分の解雇予告手当を支払う義務があります。計算方法も変わらず、平均賃金が著しく低くなった場合は最低保障額を基準にします。
契約社員
3ヶ月以上の契約期間を定めて従業員を雇った場合、契約期間中の解雇であれば解雇予告手当を支払う必要があります。計算方法は正社員と同じですが、契約期間が2ヶ月以内の場合や、農業・林業など季節的業務に従事し4ヶ月以内の期間を定めて契約している方に対しては、解雇予告手当の規定は適用されません。
日雇い労働者
日雇い労働者は契約が1日ごとになっているため、原則、解雇予告手当は発生しません。ただし継続の末、1ヶ月を超えて雇用した場合は、一転して必要になります。
解雇予告手当の支払日

解雇予告手当を支給するタイミングについてはいくつかケースが考えられます。
まず、即日解雇した場合は、解雇したその日に30日分の平均賃金を支払わなくてはなりません。それ以外は、解雇日までに支払うのが厚生労働省の見解において適切とみなされています。が、実際のところ、最後の給料日に解雇予告手当をあわせて支払う企業も少なくないようです。ただしこれだと、解雇予告手当の支払日までは実質解雇されていないものとして扱われます。たとえば即日解雇で即日支払いできない場合、解雇通知から手当支払いまでの期間、対象の従業員は休業しているにすぎません。また、企業側は休業手当(平均賃金の60%以上)を支払う必要が別途出てきます。
支払日を解雇日にする理由は、感情面においても重要です。
解雇予告手当が発生する場合、急であればあるほど相手の怒りを喚起しトラブルを招きやすくなります。なかには裁判に発展するケースもあるため、企業側は落ち度がないよう、隅々まで細かく丁寧に対処することが大事です。それゆえ、できる限り厚生労働省の見解にしたがうこと(解雇日までに解雇予告手当を支払うこと)が望ましいといえます。
有給休暇がある場合や試用期間での解雇予告手当の扱い

有給休暇は、基本、雇用契約が続く限り消滅しません(労働基準法第39条)。
そのため、解雇を言い渡された従業員は、解雇日までに有給休暇を消化することができます。
しかし、即日解雇の場合は別です。残りの有休がその場で消滅します。企業によっては、従業員の希望により、有給の残日数を買い取る対応を行うこともありますが、その場合、事前の相談が必要です。
試用期間の場合はどうでしょう。14日未満であれば、解雇予告手当は発生しません。他方、14日間を超えて継続雇用されている場合は、支払う義務が出てきます。
また、契約社員など期間の定めのある従業員に対しては、「契約が3回以上更新されている場合」と「1年を超えて継続雇用されている場合」以外なら、期間満了で契約を終えた際いわゆる雇止めにあたるため解雇として扱われません。労働基準法の解雇予告に関する規定は適用されないことから、解雇予告手当を支払わずに済みます。
なお、解雇予告は、契約期間の満了日を基準にするのではなく、あくまで解雇日から数えて30日前までに行わなければならないものです。
解雇予告手当の源泉徴収

解雇予告手当は「退職所得」の一種です。そのため、源泉徴収を行わなければなりません。
退職所得とは、退職金など、一時的およびこれらの性質を有する給与のことを指します。原則、翌月の10日までに納めるものです。
そして、解雇予告手当の課税対象額は次のように算出されます。
| (解雇予告手当−退職所得控除額)×1/2 |
ただし、退職所得控除額の最低金額は80万円となっているため、実質、源泉徴収される金額が発生しないことも多いでしょう。
なお、所得税法226条2項により、解雇予告手当を支給する場合は、解雇後から1ヶ月以内に「退職所得の源泉徴収票」を作成し、税務署長と解雇した元従業員あてに一通ずつ送付する必要があります。こちらの知識もあわせておさえておきましょう。
解雇予告手当の扱いに違反があった場合

企業側が、解雇予告手当のルールに違反、すなわち解雇予告手当を支払うべきケースで支払わなかった場合は、労働基準法に抵触します。
そのほかのいざこざも含めて、リスクは膨大です。以下、違反によって考えられるペナルティ、トラブルを紹介します。
訴訟の可能性
解雇予告手当の支払い義務を怠った場合、解雇した従業員から訴訟を起こされる可能性があります。いうまでもなく、訴訟で争うことは企業側にとって大きな時間的・精神的負担です。敗訴すれば、当然、支払いを余儀なくされますが、それ以上に会社の内外問わず、信頼を失うことになるでしょう。
付加金の可能性
前述した敗訴によって強制的に支払う額は、解雇予告手当だけとは限りません。相手から付加金を請求されることも想定できます。これは、労働基準法114条によるもので、付加金は基本、解雇予告手当の2倍の額です。解雇された従業員が訴訟を起こした場合のみ適用されます。これを避けるには、訴訟外の和解や労働審判などで解決を図ることが必要です。
刑事罰の可能性
解雇予告手当のルールに反したとき、懲役6ヶ月以下または罰金30万円以下の刑が科せられる可能性もあります。
このように、刑事罰に相当する重いペナルティも考えられるため、従業員を解雇する場合は細心の注意が必要です。あらかじめ労働法にくわしい弁護士へ相談しておくことも一つの手でしょう。
従業員を解雇した後の手続きについて

従業員を解雇したあとは、ハローワークと年金事務所で所定の手続きを行わなければなりません。また、従業員から「解雇理由証明書」を求められるケースもあり、請求に対して交付が必要になります。手続きの期限が限られている点も要注意です。遅滞がないよう早めの手続きを心がけましょう。
離職票の交付、送付
解雇日の翌日から10日以内に、ハローワークへ「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」を提出します。これらと引き換えに交付された離職票は、すぐに解雇した従業員へ送りましょう。離職票の送付遅延は従業員との間でトラブルになりやすい要素の一つです。その元従業員の方が雇用保険から失業保険の給付を受けられるよう迅速に対応しましょう。
社会保険に関する手続き
社会保険に関する手続きとして、従業員を解雇した翌日から5日以内に、年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出します。期間を過ぎてしまうと、その従業員の保険料を請求されることも考えられるため、注意が必要です。加えて、「資格喪失証明書」も送付します。これは元従業員が健康保険に入るための書類です。トラブルを招かないよう直ちに発送しましょう。
解雇理由証明書について
先述した「解雇理由証明書」について、これは、企業が従業員を解雇した理由を記した書面です。法律上、企業は従業員から解雇理由証明書を求められれば、遅滞なく交付しなければなりません。その際、適切に記載するためにも弁護士への相談をおすすめします。
なお、従業員からの請求がなければ、解雇理由証明書を交付する必要はありません。
解雇予告手当についておさえておきたいポイントまとめ
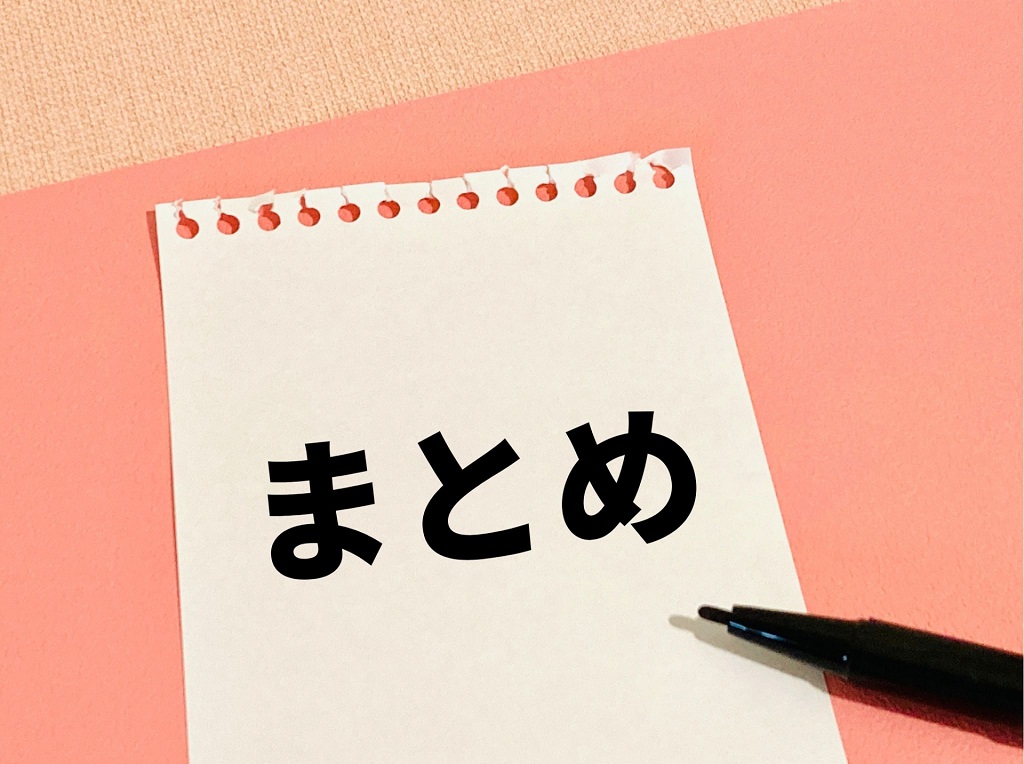
繰り返し述べてきたとおり、従業員を解雇する際は、労働基準法のルールに基づき慎重に対処していく必要があります。とりわけ解雇予告手当に関しては、周辺知識も含めて把握すべきポイントが実に多い制度です。理解を深めたうえで扱わなければ、すぐにトラブルへと発展します。曖昧なまま施行せず、不安であればあらためて拙稿を参照していただけると幸いです。
さて、従業員の解雇問題と同じく採用活動の停滞に頭を悩ます人事担当者の方も少なからずいらっしゃるでしょう。そこでおすすめしたいのが、掲載料金プランも選べるアルバイト募集向け求人サイト「バイトル」の利用です。求職者とのマッチング精度も高いと好評。気軽に無料でお問い合わせできます。ぜひ、この機会に導入をご検討ください。
【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所
代表 荒武 慎一
同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。