同一労働同一賃金の基本概要

まずは、同一労働同一賃金を理解するうえで把握しておきたい基本的なことを取り上げます。意味、経緯、対象者。いずれも確実におさえておきましょう。
同一労働同一賃金とは?
同一労働同一賃金を端的に述べるならば、「同じ業務内容であれば属性問わず同じ報酬でなければ理不尽ではないか」という考え方です。実際に非正規労働者(パートタイマー、アルバイト、契約社員)と正社員の間に不合理な待遇差が生じている場合は、その状況を改善しなければなりません。この取り組みは、かつての「パートタイム労働法」、そして現在に至る「パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)」にてまさしく形作られています。
同一労働同一賃金は、働き方改革の柱の一つです。今日、その推進を後押しするように議論されていることからも、社会全体で注目度の高さがうかがえます。
同一労働同一賃金でフォーカスされる対象者
同一労働同一賃金の取り組みによって大きく影響するのは、アルバイト・パート、契約社員や嘱託社員、派遣社員の方々です。彼・彼女らを大きく分類すると、次のタイプが該当します。
| パートタイム労働者 | 一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される正社員よりも短い労働者。パートタイマーや短時間労働者と呼ばれることもある。 ▶関連記事:パートタイム労働者、パートタイム労働法とは?【パート雇用の前提知識】 |
| 有期雇用労働者 | 事業主と期間を定めた労働契約(有期労働契約)を締結している労働者。契約社員や嘱託社員と呼ばれることもある。 |
| 派遣労働者 | 雇用契約を結んだ派遣会社から送り出された会社(派遣先)の指揮命令にしたがい業務を行う労働者。 |
※パートタイム労働者と有期雇用労働者は、パートタイム・有期雇用労働法8条(※P7を参照)、派遣労働者に関しては労働者派遣法30条の3以下において、それぞれ同一労働同一賃金の原則が規定されています。
なお、dip(ディップ)では雇用形態問わずさまざまな求人広告の掲載が可能です。特に、間口の広さでおすすめしたい「はたらこねっと」の場合、いわゆる直雇用も派遣案件も扱っております。採用についてお悩みなら、些細なことでも構いませんので、まずは気軽にお問い合わせください。ご相談は無料で承ります。
| サービスのご案内についてはこちら▼ 直接雇用も派遣掲載も可能な「はたらこねっと」 サービスの導入事例をピックアップ▼ 安定の応募数!面談設定率も高い! |
同一労働同一賃金の適用が必要な待遇面の問題

同一労働同一賃金の適用については、いくつかのシチュエーションが考えられます。同時にそれらは、待遇面に問題があることを示しています。企業側(人事担当者)としては、どの項目をどのようなポイントで見定めていけるとよいのでしょうか。合理的かそうでないかの境界線が曖昧な方もいらっしゃるかもしれません。以下、具体的にピックアップします。
基本給
まずは基本給です。企業によって設定方法が異なるとはいえ、大抵は次の要素を基に決められています。
- 労働者の勤続年数(勤続給)
- 労働者の能力または経験(職能給)
- 労働者の業績または成果(成果給・年俸給
仮に正社員と非正規社員で賃金のルールや決定基準が異なる場合、その違いについて企業はきちんと説明する必要があります。“将来に対する期待度が異なるため”など、抽象的な弁明では通用しないでしょう。
| 合理的とされるケース | ある非正規労働者と正社員の方を比べたとき、如実にスキル差があるため、前者は後者よりも基本給が低く設定されている |
| 不合理とされるケース | 非正規労働者よりも多くの業務経験を有する正社員の基本給を高く設定しているが、実際の業務にその経験は関連性がない |
昇給、賞与、各種手当
たとえばスキルアップに応じて適用される昇給制度が、正社員の特権になってはいけません。非正規社員も平等に対象です。もちろん、ただ上げればよいわけでもなく、仮にその額や割合に差が出るようなことがあれば、合理的な説明が求められます。賞与についても同様です。雇用形態ではなく会社への貢献度合いを基準に支給しなければ、不合理な待遇差とみなされても仕方ありません。そして、各種手当。こちらも、対象の業務に違いがなければ、雇用形態を理由に差分が生まれないようにしましょう。
| 合理的とされるケース | 正社員と非正規労働者を比較して、勤続による能力の向上に一定の相違があるため、非正規労働者の昇給を行わない |
| 不合理とされるケース | 勤続によって正社員と同等の能力向上が見られたにもかかわらず、正社員と同一の昇給を行わない |
| 合理的とされるケース | 業務上の責任が重く、ミスに対してペナルティが課されるなどの環境下で働く正社員には満額の賞与を支給する一方、業務上の責任が軽いことを理由に非正規労働者に対しては正社員よりも少ない支給額にする |
| 不合理とされるケース | 会社への貢献度が正社員と遜色ないにもかかわらず、非正規労働者には、正社員よりも少ない額の賞与を支給している |
| 合理的とされるケース | 同じ役職を肩書として与えているとはいえ、非正規労働者の方は所定労働時間が正社員よりも短いため、その分、(役職)手当は減額して支給する |
| 不合理とされるケース | 同じ役職にもかかわらず、非正規労働者だからという理由のみで、正社員よりも少ない額の役職手当を支給する |
福利厚生
社会保険や労働保険、医療関連、住宅関連、休憩室・更衣室・給食施設の利用、病気や怪我による休職や法定外の有給休暇……とりもなおさず福利厚生全般、たとえ非正規社員であっても、正社員と同等に受ける権利があります。そう、同一労働ならば賃金以外の報酬も同一なのです。
| 合理的とされるケース | 長期勤続者を対象としたリフレッシュ休暇を、非正規労働者には所定労働時間に比例した日数分だけ付与する |
| 不合理とされるケース | 同じ事業所で働いているにもかかわらず、非正規労働者に対しては正社員と異なり、マッサージルームなど社内でリフレッシュできる施設の利用を禁止している |
教育研修
前項に続き、賃金以外の項目では教育研修も挙げられます。そもそもこれは、従業員が職務を遂行するうえで必要な能力を身につけてもらうために行うものです。企業の戦力強化につなげる意味でも、同じ内容で実施するようにしましょう。
| 合理的とされるケース | 正社員と非正規労働者では業務内容が異なるため、それぞれに適した教育訓練を実施する |
| 不合理とされるケース | 業務内容および環境やそのほかの事情に相違がないにもかかわらず、非正規労働者には正社員と同じ教育研修を受けさせない |
退職金
厚生労働省が発表している『「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要』の冒頭では、“このガイドラインに記載がない退職手当、住宅手当、家族手当等の待遇や、具体例に該当しない場合についても、不合理な待遇差の解消等が求められる”と記載されています。つまり、くわしくは言及されていないとはいえ、退職金の有無や額の差についても、正社員とそのほかの非正規労働者で安易に線引きしてはならないということです。
| 合理的とされるケース | 正社員と非正規労働者の間で勤続年数や業務内容、責任の程度に差があったため、後者の退職金は前者より少ない額で支給する |
| 不合理とされるケース | 非正規労働者の勤続年数が10年を超えていたにもかかわらず、退職金を一切支給しない |
同一労働同一賃金を実現するパートタイム・有期雇用労働法

同一労働同一賃金の考え方と切っても切り離せないのが「パートタイム・有期雇用労働法」です。本章では次のポイントを軸に説明します。
- 法成立までの経緯
- 説明義務
- 前身にあたるパートタイム労働法との違い
- 行政による自主的解決・紛争解決の援助
なお、(パートタイム・有期雇用労働法を)くわしく知りたい方は以下の記事でも確認できます。
▶パートタイム・有期雇用労働法とは?
法成立までの経緯
以前の日本の企業文化では、非正規労働者よりも正社員のほうが待遇面で優遇されることは当然だと考えられてきました。給与や賞与の額、福利厚生など正社員と非正規労働者との間で大きな差が生じていたのです。責任の重さや業務内容に大きな違いがあればまだしも、単に雇用形態だけを理由にそう扱われてしまっては、解せない、納得できない向きがあるのも当然といえば当然だといえます。
この状態を是正すべく生まれた同一労働同一賃金。定義や概念、概要はすでに述べたとおりです。そしてそのルール(あるいは理念)を浸透させようと働き方改革関連法案の改正の一環として、2020年4月には「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されます。当時は大企業中心に適用されましたが、それから1年後、2021年4月には中小企業も対象に。いまや“同一労働同一賃金”は当たり前にそうあるべきものとして掲げられています(取り組みが本格化しています)。
説明義務
パートタイム・有期雇用労働法により、非正規労働者は正社員との待遇の違いや理由について、事業主に説明を求めることができます。裏を返せば、待遇格差について非正規労働者から説明を求められた場合、企業側は対応の義務が生じるわけです。たとえば「なぜ正社員と待遇差が生じているのか」「待遇を決定する際に考慮したポイントは何か」などは、弁明するのに必須要素でしょう。それらを踏まえて決して不合理ではないことを示さなければなりません。なお、説明を求められたことを理由に(不本意であったからといって)、解雇や減給などその従業員が不利益を被るよう処置することは、法律で禁止されています。
パートタイム労働法との違い
パートタイム労働法はいわばパートタイム・有期雇用労働法の前身です。遡ること1993年12月に施行され、その後2008年の改正などを経て、前述のとおり2020年、2021年と更新の末、現行の法律に至ります。その名称からもうかがえるように有期雇用労働者が法の対象に含まれたことも重要ですが、事業所レベルではなく企業単位に及ぶようになった点も無視できない変化です。
行政による自主的解決・紛争解決の援助
パートタイム・有期雇用労働法によって、労働者と事業主の間で労使トラブルが発生した場合は、都道府県労働局の紛争解決援助制度を利用できます。その際、当事者の一方または双方の申し出が必要です。なお、無料かつ非公開で対応してもらえます。
こうした手続きは、いわゆる行政ADRの対象です。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」なども含まれます。
同一労働同一賃金が企業にもたらすメリット

同一労働同一賃金は、非正規労働者側にとっての救済措置のように捉えられがちですが、企業側にも少なからずメリットをもたらしてくれるものです。以下、それらを列挙します。
採用活動へのポジティブな影響
少子高齢化が社会問題となっているなかで、多くの企業が人材不足に陥っています。ゆえに、非正規労働者を戦力化していくことは一つの命題です。にもかかわらず正社員と不合理な待遇格差があってしまっては、どうにもこの逆境に打ち勝つのは難しいでしょう。だからこそ、同一労働同一賃金が担う役割の重要性がわかります。いうまでもなく、理に適った労働条件を示すことは非常に大切です。そしてパートタイム・有期雇用労働法が新たに適用された現在、少なくとも従来よりは非正規雇用への応募にポジティブに向き合える求職者の方々が増えているものと思われます。実際のところ世相を鑑みるに、有期雇用労働者が増加傾向にあるのは、まさしくそうした背景も大きく手伝っているでしょう。
非正規労働者のモチベーション向上
同一労働同一賃金の実現によって、「仕事を頑張っているのに評価されない」「実績を残して会社に貢献しているのに給与アップも賞与もない」といった非正規労働者が抱く不満の解消が期待できます。たかだか査定に対する方針の一つにすぎないと思ってはいけません。正当な評価によって、業務や組織に対して愛着が湧くことは至極当然です。すなわち、やりがいやモチベーションの向上につながります。
チームワークが高まる
非正規労働者のモチベーション向上はそのままチームの意識やパフォーマンスにも寄与すると考えられます。また、これまで正社員だけしか利用できなかった食堂や休憩室などの福利厚生施設が雇用形態を問わず使えるとなれば、新たなコミュニケーションの場として機能するはずです。結果、アイデアの創出はもちろん、チームとしての一体感が増すことになるでしょう。
非正規労働者の戦力アップ
同一労働同一賃金は研修機会をも平等に是正するものです。これまでさして非正規労働者のスキル向上に力を入れてこなかった企業からすると、教育コストが掛かることに二の足を踏むかもしれません。が、企業内での競争を生むことも含めて非正規労働者の戦力アップによって生産性が改善するなら、まさしく全体最適といえるでしょう。
同一労働同一賃金で懸念されるデメリット

続いて、同一労働同一賃金を実施する際に、懸念される企業側のデメリットについてピックアップします。いずれも無視できません。が、あらかじめ認識しておくことで対策も打てるはずです。
人件費のアップ
同一労働同一賃金の導入は、人件費が嵩むことも意味します。労働契約法第9条により就業規則に記載がない場合には、本人の同意なしに正社員の給与を引き下げることはできません。そのため、正社員と非正規労働者の待遇差を解消するには、原則として後者の給与を引き上げることになります。
また、基本給や各種手当の引き上げに限らず、福利厚生や研修面でのコストに対しても考慮が必要です。
配属や任される仕事に対して生まれる不満
同一労働同一賃金は、雇用形態ではなく、任される職務内容や配置変更の範囲などで給与を決めるものです。そのため、非正規労働者内で待遇格差が生じる可能性はあります。もちろん、それが不合理でなければ本来は問題ないのですが、そうはいってもやはり他人と比べたときに差があること自体、不満を持つ向きは少なからずあります。かといって、皆が納得する公平な制度を構築することは容易でありません。むしろ不可能といっても過言ではないでしょう。いずれにせよ、従業員には丁寧な説明はじめ真摯な対応・運用が根気よく必要です。
正社員から生まれる不満
同一労働同一賃金を施行するために、やむを得ず正社員の給与で調整を図らねばならない企業が存在するのも確かです。これはこれで正社員にとっては納得できないでしょう。減給や賞与カットによって正社員と非正規労働者の待遇を均等化した場合、大抵は前者の満足度低下につながります。そうなると、就業規則にもとづき泣き寝入りする正社員、あるいはその会社から離れる方が出てきそうです。
同一労働同一賃金を実施する流れと注意点
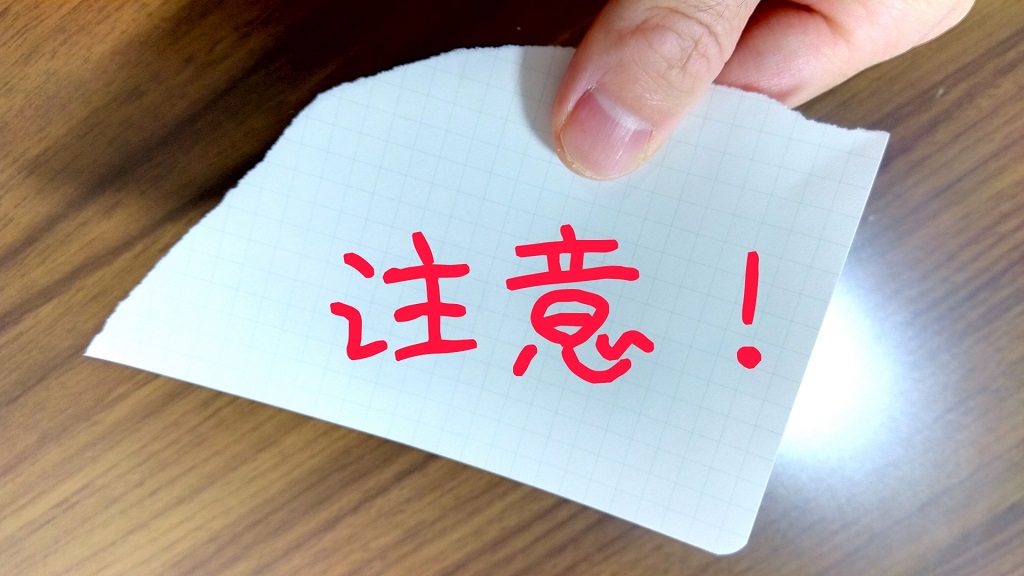
実際に同一労働同一賃金を行うにあたって、どのような手順で進めるとよいのでしょうか。必要なアクションはずばり、しかるべき確認(を怠らないこと)です。と同時に、前項で取り上げたデメリットをケアする意味でも注意点に敏感にならなければなりません。以下、具体的な内容をステップに沿ってお伝えします。
雇用形態や契約内容の確認
まずは、雇用形態と契約内容を確認します。従業員管理は基本中の基本です。しかし、意外と疎かにしている企業も少なくないように見受けられます。労働者名簿なのか賃金台帳なのか。給与・賞与・各種手当・福利厚生など正社員と非正規労働者の間で待遇格差が生じていないか照合できる状態に整えることが最初のアクションです。
待遇差の確認と不合理か否かの判断
確認していくなかで待遇差があった場合、その合理性を精査します。焦点になるのは、待遇に差をつけたポイントが果たして従業員に納得してもらえる理由によるものかどうか。説明を求められた際、スムーズに対応するためにも、あらかじめ要点を整理しておくことが大事です。
不合理な待遇差を生まないための処置
精査した結果、待遇差の妥当性が疑わしい場合、しかるべき処置が必要です。その際、いくつか方法があります。ひとつは正社員と非正規労働者それぞれの職務(業務内容、責任の程度、配置転換の範囲)の差を明確にすることです。非正規労働者の業務内容や責任の程度を正社員よりも軽くするなどして、第三者に説明しやすい状況に変えましょう。そして、もっともシンプルに改善を図るなら、待遇差をなくすことが手っ取り早いといえます。賞与、退職金などの支給について、両者同じ扱いにすれば、そもそも俎上にあげられることはありません。が、待遇差をつけていることは何かしらの理由があったはずです。その場しのぎで短絡的に待遇差を埋めることは、正社員も含めて誰かしらの反感を買うかもしれません。
同一労働同一賃金に関するポイントまとめ
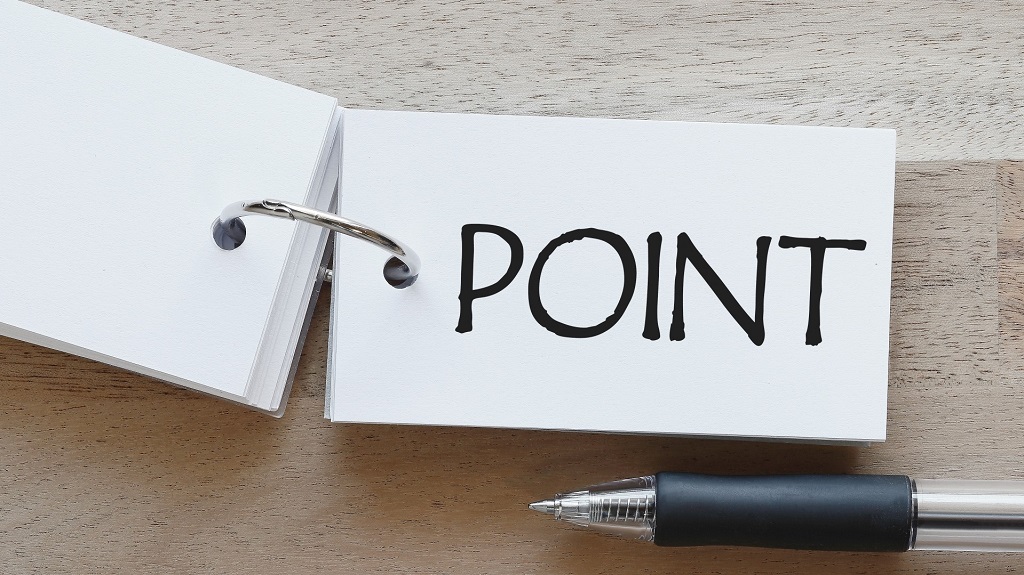
同一労働同一賃金の導入は、社会的格差の解消にダイレクトに影響する施策です。まさしく働き方改革の柱の一つといえます。近年の有期雇用労働者の増加傾向からもうかがえるように、パートタイム・有期雇用労働法が少なからず波紋を呼び人材の動きに作用するなか、企業にとっては非正規労働者の待遇を改善することが、生産性向上や組織活性化の糸口になっているわけです。正しく実践することはもちろん、同時に採用活動にも積極的に取り組むことをおすすめします。
求人掲載・採用業務のサポートや料金についてなど、ぜひ気軽にお問い合わせください。
また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談も無料で承っております!
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。
【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所
代表 荒武 慎一
同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。

