固定就労とは?

固定就労とは、端的にいうと労働日や労働時間があらかじめ決められている勤務形態です。業務の特性や従業員のライフスタイルに応じて、大きくは「固定労働時間制」「固定シフト」「パートタイム固定勤務」に分けられます。以下、それぞれ解説します。
固定労働時間制
固定労働時間制では、日々の労働時間が固定され、勤務時間の開始と終了が明確です。たとえば、「9:00~18:00(休憩1時間)」といった具合に定められています。対象は、フルタイムで働く方が一般的です。特に製造業などにおいては、決められた時間内での業務遂行が求められるため、多くの職場はこれに該当します。
固定シフト
固定シフトとは、勤務時間や曜日が固定されているものです。週や月ごとに同じシフトが繰り返されます。たとえば、「毎週月曜、水曜、金曜の13:00~18:00」といった具合です。アルバイトやパートでよく見られます。
パートタイム固定勤務
パートタイム固定勤務も固定シフト同様、原則、勤務時間や曜日は決まっています。違いは文字どおり、パートタイムに限定される点です。わかりやすくいうと固定シフトよりも短く、具体的には「毎週火曜、木曜の9:00~12:00」などが挙げられます。変則就労ほどではないにせよ、家事や育児、学業との両立を図るのに重用される働き方です。
変則就労とは?

変則就労とは、業務の繁閑や従業員のライフスタイルに合わせて臨機応変に働く時間を設定する勤務形態です。基本的に1週間、1ヶ月、1年単位で調整できます。また、フレックスタイム制も定番です。以下、それぞれ解説します。
1週間単位の(非定型的)変形労働時間制
1週間単位の(非定型的)変形労働時間制では、1日10時間、1週間で40時間を超えない範囲で労働時間を設定できます。授業員数が30人未満の事業所で導入可能です。主に小売業、旅館、飲食店などで見られます。
1ヶ月単位の変形労働時間制
1ヶ月単位の変形労働時間制は、1ヶ月以内の労働時間を1週間あたりの労働時間に換算したときに法定労働時間(通常40時間)を超えない範囲であれば、労使協定の締結、所轄労働基準監督署への届け出を条件に、一定の限度を超えて柔軟に時間調整が図れる制度です。たとえば、月末に業務が集中しがちな経理など、月の前半と後半で繁閑状況が変わる職種に適しています。
1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制は、1年以内の期間で労働時間を調整できます。1ヶ月を超え1年以内の一定期間を平均した1週間あたりの労働時間が、法定労働時間を超えず、なおかつ労使協定の締結を所轄の労働基準監督署に届け出れば、取り入れることは可能です。季節による業務量の変動が大きい仕事や繁閑の差がはっきりしている業種に適しています。
フレックスタイム制
フレックスタイム制は、始業時刻や終業時刻を従業員が選べる働き方です。一般的にコアタイム(必ず勤務しなければならない時間帯)とフレキシブルタイム(自由に出勤・退勤できる時間帯)で構成されています。いわば1日単位の変形労働時間制です。
固定就労で期待できるメリット

固定就労と変則就労のどちらを選べばよいのか悩んだなら、それぞれのメリット・デメリットを整理してみてください。本章ではまず、固定就労で期待できるメリットをお伝えします。大きくは二つ。勤怠管理のしやすさ、コミュニケーションの取りやすさです。以下、補足します。
勤怠管理がしやすい
出勤・退勤時間が一定であるため、勤怠管理にそう手間をかけることもないでしょう。労働時間の集計はもちろん、給与計算も同様です。これが大規模な組織になるとなおさら如実に差が出てきます。労務管理を必要以上に煩わしくしたくないなら、固定就労が無難かもしれません。
コミュニケーションが取りやすい
固定就労では、従業員が基本、同じ時間を共有し働けるため、コミュニケーションが取りやすく情報共有もスムーズでしょう。業務の進捗確認や問題点の早期発見にもつながり、おのずとチームの連携も強化されていくはずです。新人や経験の浅い従業員にとっても声をかけやすかったり、教育の時間も割きやすかったりすると思われます。これらが積み重なっていき、組織全体の成長が促進されるわけです。
固定就労で懸念されるデメリット
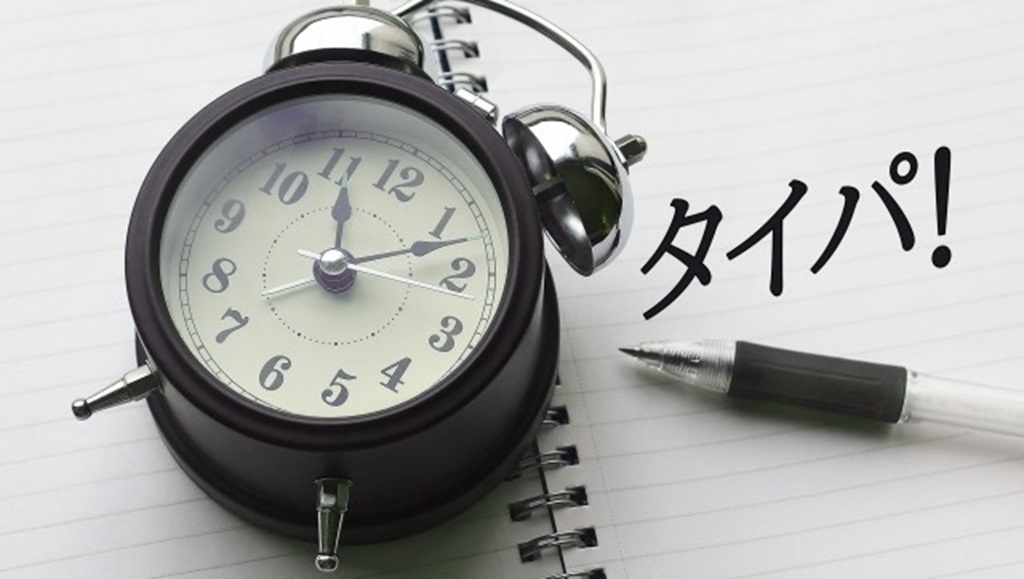
続けて固定就労で懸念されるデメリットについてです。安易に導入して後悔しないためにも、メリット以上に把握しておいた方がよいかもしれません。こちらも2つをピックアップ。業務量の変動に対応しにくい点と、働き方に融通が利かない部分を取り上げます。
業務量の変動に対応しにくい
勤務時間やシフトが固定されていることで、業務量の増減に振り回される企業やお店も見られます。たとえば、繁忙期はどうしてもリソース確保が課題です。人員を新たに獲得するのか、はたまた従業員に残業を依頼するのか。やはり悩みどころです。コストの負担、モチベーション低下などマイナスの影響も当然考えられます。方や閑散期も、同じ条件での時間雇用・労働が生産性の側面で無駄に思えるかもしれません。
働き方の融通を利かすのが難しい
従業員のライフスタイルや事情を理由に離職されるケースは、しばしば見受けられます。ただこれは、シフト体系が柔軟であれば防げたことかもしれません。たとえば、育児や介護が必要な家庭では、決まった労働時間に縛られてしまうことは、不安でしかないでしょう。また、通院しながら働いている方も同様です。彼・彼女たちがフレックスタイム制度の導入など働き方に融通が利く職場を望むのは、至極当然のことだと考えます。
変則就労で期待できるメリット

さて、次に変則就労についてお伝えします。先にメリットです。ざっと3つ挙げましょう。
- 業務の繁閑に対応しやすい
- コストを調整しやすい
- 個々のライフスタイルや家庭事情に合わせやすい
これらは、固定就労ではなかなか難しかったポイントともいえそうです。以下、それぞれ解説します。
業務の繁閑に対応しやすい
変則就労の場合、人員リソースやシフトの調整が図りやすいため、勤務時間を繁忙期と閑散期で適切に割り当てるといったことも可能です。また、想定外の残業を半ば無理にお願いするようなことも、従業員管理を計画的に行っていれば、そう頻繁には起きないと思われます。
コストを調整しやすい
変則就労は、コスト調整しやすい働き方です。とりわけ人件費を抑えやすく、不要な残業や稼働状況に対する固定費の無駄遣いを減らせる点は大きなメリットといえるでしょう。
個々のライフスタイルや家庭事情に合わせやすい
変則就労は、何か大事な急用や事情が生じたときにも臨機応変に対応できる安心感があります。これは従業員だけでなく求職者にとってもそう。私生活とのバランスを求める彼・彼女らに柔軟な働き方を提供することは、人材獲得や定着率向上において、もはや欠かせない施策といえるでしょう。
変則就労で懸念されるデメリット

では、変則就労ではどのようなデメリットが懸念されるのでしょうか。ざっと挙げると次のとおりです。
- 労務管理が複雑になる
- 従業員の健康や生活リズムに影響する
- 働き方に対する公平性が損なわれる
以下、それぞれ解説します。
労務管理が複雑になる
変則就労では、勤務時間やシフトが従業員ごとに異なるため、勤怠管理、加えて給与計算も煩雑になりやすい側面があります。状況が複雑になれば、定期的に改正される法に抵触する恐れも出てきやすく、なおかつそれらに対する目配りがつい疎かになってしまうことも懸念事項です。
従業員の健康や生活リズムに影響する
変則就労により生活のリズムが不規則な従業員も少なくありません。睡眠不足や疲労の蓄積から健康状態が悪化すれば組織にとって大きな問題です。特に夜勤や長時間労働が頻繁に発生する職場では、くれぐれも体調管理を徹底するよう注意が必要でしょう。
働き方に対する公平性が損なわれる
変則就労を導入すると、従業員の勤務時間や待遇にばらつきが生じるため、不満も出やすくなります。たとえば、働く時間が同じでも繁忙期と閑散期では負担が違うといった声などです。このような問題を防ぐためには、透明性のあるルールを設け、公正な評価制度を導入などが考えられます。加えて、誤解や軋轢を無くすためにも、従業員間のコミュニケーション促進や1on1ミーティングの実施なども必要でしょう。
裁量労働制とは?

裁量労働制とは、業務の進め方や時間配分を労働者の裁量に委ね、実際の労働時間に関係なく、あらかじめ定めた時間を働いたものとみなす制度です。 これは、専門業務型と企画業務型の2種類があり、適用される業務は法律で限定されています。また、労使協定の締結や所轄労働基準監督署への届け出など、法定の手続きが必要です。本章ではこれらに加え、 裁量労働制と混同しやすい「事業場外みなし労働時間制」についても解説します。
専門業務型裁量労働制
専門業務型裁量労働制が適用されるのは、研究開発やデザイン、プロジェクトマネジメントなど、高度な専門知識やスキルを必要とする業務においてです。これらは、性質上、労働時間の管理が難しいと判断されています。したがって、労働者が自らの裁量で仕事の進め方を決めることが可能です。
企画業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制は、企業の経営戦略や事業計画の立案など、企画業務に従事する労働者を対象とした制度です。創造的な発想や迅速な意思決定が求められる分、時間の制約を受けずに柔軟に働けます。
事業場外みなし労働時間制
事業場外みなし労働時間制は、営業職や出張の多い職種など、主に事業場外で働く労働者に適用される制度です。業務の特性上、実際の労働時間を正確に把握するのが難しい場合に、所定労働時間働いたとみなされます。そのため、混同されやすいとはいえ、特定の業務が適用対象であり、労使協定で定めた時間が労働時間にみなされる裁量労働制とは別の扱いです(裁量労働制には含まれません)。
適切な勤務形態を決めるコツ

固定就労と変則就労のどちらの勤務形態を選択するか、はたまた裁量労働制にした方がよいのかの判断は、ここまで述べてきたなかにもヒントはあったはずです。
そのうえで、「管理を煩雑にしたくない」「時期に応じて柔軟に人員を配置したい」といった要望だけで決めるのではなく、 業務特性の合致や生産性、従業員の定着率向上まで考えていけるとよいでしょう。たとえば、製造業やコールセンターなど稼働に安定性が求められるのであれば、固定就労が適しています。一方、小売・物流・観光など繁閑の差が大きい業界では、変則就労の方が効率的に業務を回せるでしょう。また、IT・クリエイティブ業界などは裁量労働制の親和性が高く、実際、ほとんどの企業が取り入れています。
そしてこれらを当てはめたときに、定着率も含めた従業員エンゲージメントがどう変わっていくかも調査できると、最適解を見つけるのになお有効です。
働き方はさまざま!柔軟な採用にうってつけのサービス

人材確保において、求職者の多様な働き方に対応できる採用手法を持つことは、今の時代、ますますアドバンテージとして機能するはずです。
たとえば、dipが提供するサービスには、アルバイト・パート採用だけでみても、レギュラーバイトの応募が多く集まる『バイトル』もあれば、スキマバイトの募集に適した『スポットバイトル』も最近は需要が高まっています。前者は、幅広い求職者へリーチできます。他方、後者は今すぐ人がほしいときにもってこいのサービスです。どちらもスピード採用がウリですが、『スポットバイトル』はまさに今、一時のニーズに対応しているため、最短で即日マッチングが期待できます。
また、捉えようによってはスキマバイトとして採用したワーカーを、レギュラーアルバイトへと育成(ナーチャリング)することも可能です。長期的な人材確保へとつながります。とにもかくにも、働き方の多様化同様、採用も柔軟さが大事です。
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
▶【公式】スキマ時間のスポット募集ならスポットバイトル|求人掲載はこちら
固定就労と変則就労の違いを自社の人材管理に生かそう!
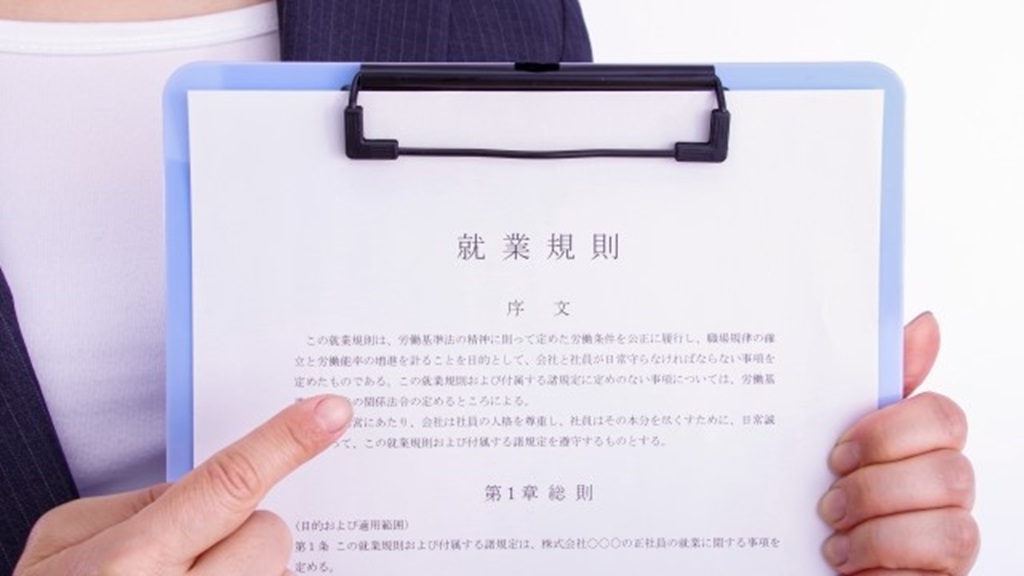
労働時間の管理は業務の生産性や従業員の働きやすさに直結します。だからこそ、固定就労と変則就労の違いを理解することは非常に大事です。両者ともに一長一短あります。そうはいってもやはり、自社の業務、環境、従業員にとっての最適解は、突き詰めればきっと見つかるはずです。たとえば、フレックスタイム制と裁量労働制を両方導入するといった組み合わせ方式も選択肢にいかがでしょう。いずれにしても試行錯誤は必要かもしれませんが、固定就労と変則就労に関する知見を自社の人材管理に生かせるよう、ぜひ拙稿をお役立ていただけますと幸いです。
求人掲載・採用業務のサポートや料金についてなど、ぜひ気軽にお問い合わせください。
また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談も無料で承っております!
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【公式】スキマ時間のスポットワーカー募集ならスポットバイトル
┗スキマ時間で「働きたい」と「働いてほしい」をつなぐ求人マッチングサービス。求人は無料で掲載できます。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。
▶【公式】面接コボット – 応募者対応の自動化で面接管理が楽に!
┗求人サイトからの応募対応を自動化できるサービス。チャットボットを通じ、日程調整まで効率よく進めてくれます。
▶【公式】採用ページコボット – 費用・実績も紹介!採用サイト制作サービス
┗採用ページ作成サービス。求人まとめサイトとの自動連携や求人検索エンジンへの対応により外部集客を強化します。
【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所
代表 荒武 慎一
同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。

