期間の定めのある労働契約(有期労働契約)とは?

期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という)とは、あらかじめ使用者と労働者が合意して契約期間が定められている雇用契約です。これを深く理解するためにも、前提としておさえておきたい知識があります。それは主に、「契約の種類」「1回あたりの契約期間」そして「無期労働契約との違い」です。本章ではまず、基本に当たるこれらについて言及します。
有期労働契約の種類
一口に有期労働契約といっても、法的にはいくつか種類が存在します。具体的に該当するのは、次の雇用形態です。
- 契約社員
- パートタイム・アルバイト
- 高度専門職型契約社員
- 定年後に再雇用される嘱託型契約社員
以下、それぞれ簡単に説明します。
契約社員
契約社員は、嘱託以外のフルタイムで働く方及び、職務、勤務地、労働時間などを限定している有期の社員を指します。会社によっては準社員という呼称で無期契約する場合もありますが、定義は区々です。
▶関連記事:契約社員とは?アルバイトとの違いやボーナス、雇う際の注意点など解説
パートタイム・アルバイト
パートタイム・アルバイトは、短時間勤務を基本としつつ、契約満了日まで従事する雇用形態です。企業側はうまく活用できれば、シフトにスキマが空かないよう調整が図れます。人数をかけて業務をカバーする場合にも有効です。家事や育児などプライベートと両立できる環境を求める人材は一定数いらっしゃいます。期間こそ限られますが、そうした方々のニーズに応えられる契約といえるでしょう。
高度専門職型契約社員
高度専門職型契約社員とは、その分野に精通した高度な知識やスキルを有する契約社員を指します。即戦力、そして技術力を求める局面やプロジェクト遂行には、彼・彼女らのようなプロフェッショナル人材の獲得は非常に有効です。報酬や待遇面では一般的な契約社員よりも高めに設定されることがほとんどとはいえ、企業が契約更新を打診するケースも決して珍しくありません。
定年後に再雇用される嘱託型契約社員
定年後に再雇用される嘱託型契約社員は、文字どおり、定年を迎えた従業員が、一定期間の契約で引き続き勤務する雇用形態です。定年後、無理のない働き方で現場に携わる方は少なくありません。企業からしても、彼・彼女らが培ってきた長年の知識やノウハウを、そう簡単には手放したくないでしょう。つまるところ、企業と従業員の双方にとってメリットのある契約です。
有期労働契約1回あたりの期間について
労働基準法第十四条では、“雇用契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年を超える期間の契約をすることはできない”と記載されています。※高度専門職型契約社員、満六十歳以上の労働者は例外として5年まで契約可能。
なお、労働契約法第十七条では、契約期間を短くし何度も契約更新を行うような真似は避けるべきだと注意喚起されています。
期間の定めのない労働契約(無期労働契約)との違い
期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という)は、従業員を長期間にわたって雇うことを前提にしたものです(一般的には正社員を指します)。定年や従業員からの退職申し出がない限り、雇用は続きます。また、仮に解雇を検討するにも、正当な理由が求められます。一時的に人材を確保したい有期労働契約に対して、無期労働契約は中長期的に活躍するメンバーを招き入れるイメージといったところでしょうか。いずれにしても、目的に応じて戦略的に選択することが肝要です。
有期労働契約で義務付けられていること

有期労働契約に際しては、守るべきことが法的に定められています。具体的には次のとおりです。
- 募集対象が“有期契約社員”だとわかるように明示する
- 締結時は「契約期間」と「契約更新の有無」を明示する
- 更新有りの場合は判断の基準を明示する
- 賃金や労働時間なども明示する
- 雇止めの場合は更新無しの旨を予告する
- 原則、契約期間途中の解雇はできない
- 雇止めの理由を要求された場合は遅滞なく交付する
- 更新の際は契約期間をなるべく長くする
以下、これらの義務について、簡単に説明します。
募集対象が“有期契約社員”だとわかるように明示する
採用要件における雇用形態が有期労働契約であれば、その旨をはっきりと示す必要があります。求職者が無期雇用と勘違いしないよう、求人票には“有期契約社員”を募集していることをわかりやすく記載しましょう。
締結時は「契約期間」と「契約更新の有無」を明示する
晴れて契約を結ぶ際、取り交わす書面には「契約期間」と「契約更新の有無」を記載しなければなりません。前者は、開始日と終了日を具体的に示す必要があります。また、後者について更新がある場合は、後述のとおりその条件や基準の追記もセットです。誤解を生まないよう丁寧に補足しましょう。
更新有りの場合は判断の基準を明示する
前項で触れたように、契約更新の可能性がある場合は、その判断基準を明示しなければなりません。具体的には、勤怠含状況を含めた業務態度、契約期間満了時の業務量、進捗具合がその材料に挙げられます。仮に能力が高い方であれば、むしろこちらから更新を打診することもあるでしょう。とはいえ、会社の経営状況いかんではこれらの基準が覆る可能性も考えられます。したがって、認識の齟齬を生まないためには、業績などの社内都合も条件に加わる旨を伝えておけると安心です。
賃金や労働時間なども明示する
上述した記載ルールは、いずれもパートタイム・有期雇用労働法で義務付けられています。そのほか、賃金や労働時間も雇い入れ時には明示しなければなりません。ざっと、対象の項目を挙げましょう。
- 契約期間
- 有期労働契約を更新する場合の基準
- 仕事をする場所
- 業務内容
- 始業・終業の時刻
- 所定時間外労働の有無
- 休憩時間
- 休日、休暇
- 賃金の決定・計算・支払い方法
- 昇給の有無
- 賞与の有無
- 退職に関する事項
- 退職手当の有無
- 相談窓口(労働者の相談に対応するための体制整備)
これらは、労働者の希望があれば電子メールやFAXで伝えてもかまいません。なお、違反した場合は、罰金が科される可能性があります。
▶関連記事:パートタイム労働者、パートタイム労働法とは?【パート雇用の前提知識】
▶関連記事:同一労働同一賃金とは?パートタイム・有期雇用労働法の解説交えて言及!
雇止めの場合は更新無しの旨を予告する
以下に挙げられる条件で雇止めとなる場合、企業は労働者に対して更新無しの旨を予告する義務があります。
- 有期労働契約を3回以上更新している場合
- 1年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新され、最初に労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合
- 1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合
この予告は、原則、契約期間が終了する30日前までに行わなければなりません(30日を切った場合は、その日数に応じて平均賃金を掛けた額を支払わなければなりません)。
原則、契約期間途中の解雇はできない
有期労働契約において、期間の途中で労働者を解雇することは原則として禁止されています。ただし、企業の経営状況の急激な悪化や労働者の重大な不正行為といった、やむを得ない事由がある場合は例外です(それでも、該当する従業員に対しては、解雇に至る適切な説明が必要です)。
雇止めの理由を要求された場合は遅滞なく交付する
前述したやむを得ない事由には次のような例が挙げられます。
- 前回の契約更新時に、(本契約を更新しないことの)合意があったため
- 更新回数が契約締結時に設けた上限に達したため
- 事業縮小のため
- 業務を遂行する能力が十分でないと認められるため
- 違反行為や無断欠勤など勤務態度に問題があるため
これらは、雇止めに際して労働者から理由を要求されたとき、速やかに交付しなければなりません。
更新の際は契約期間をなるべく長くする
契約をすでに1回以上更新し、なおかつ1年を超えて雇用している方に対しては、新たに更新する場合、その契約期間はできるかぎり長くするよう努めなければなりません。これは、まさに先述した労働契約法第十七条(二項)に当たります。
法改正によって生まれた有期労働契約に関するルール

遡ること10年以上前にはもう、無期労働契約への転換や「雇止め法理」の法定化、不合理な労働条件の禁止といったルールは法改正のなかで公布されていました。これらについての見識もまた、期間の定めのある労働契約を深く理解するうえでは、いまなお必要なことと考えます。以下、それぞれ簡単に説明します。
無期労働契約への転換
同一の使用者(企業)との間で有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合、労働者は無期労働契約への転換を申し込むことができます。これは、改正労働契約法第十八条に定められているルールです。なお、そのタイミングは、5年を超えたすぐの更新時でなくてもかまいません。通算5年を経過した次の1年も、一旦、有期労働契約を結び、翌年に無期労働契約に転換することも可能です。
「雇止め法理」の法定化
「雇止め法理」の法定化とは、いうなれば、すでに確立されていた一定の場合に雇止めを無効としていたルールの条文化です。これは、改正労働契約法第十九条にて定められています。対象は次のとおりです。
- 過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの
- 有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるもの
- 有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約の更新を期待することについて合理的な理由があると認められるもの
上記のいずれかに該当し、使用者の雇止めが、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は、(雇止めは)認められません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されます。
不合理な労働条件の禁止
不合理な労働条件の禁止とは、改正労働契約法第二十条で定められている、有期契約労働者と無期契約労働者の間で(労働条件に)不公平な相違が生じることを禁止するルールです。※同一の使用者と労働条件を締結している場合の話です。
賃金や労働時間等の狭義のものから、災害補償、服務規律、教育訓練、付随義務、福利厚生など、労働者に対する一切の待遇が含まれます。労働条件が不公平かどうかを判断する際に考慮するポイントは次のとおりです。
- 職務の内容(業務の内容および当該業務に伴う責任の程度)
- 当該職務の内容および配置の変更の範囲
- その他の事情
たとえば、通勤手当、食堂の利用、安全管理などで違いが生じる場合は特に、余程の理由がない限り、合理的と認められないでしょう。
2024年に追加された4つの労働条件明示事項
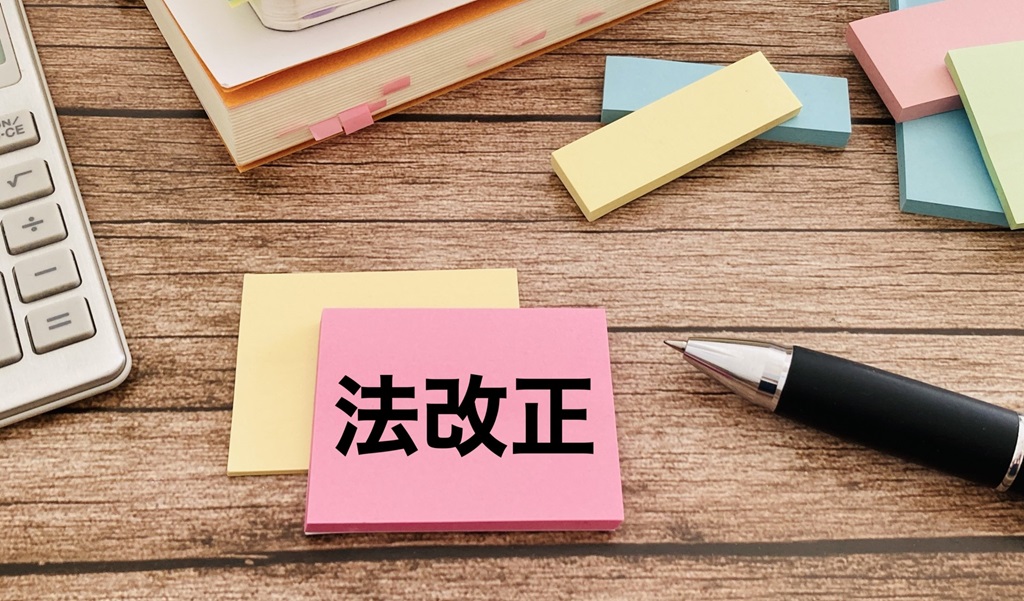
2024年の法改正では、有期労働契約に関する労働条件の明示事項が新たに追加されました。ずばり、次のとおりです。
- 就業場所・業務の変更の範囲
- 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
- 無期転換申込機会
- 無期転換後の労働条件
以下、それぞれ簡単に説明します。
▶関連記事:労働条件の明示義務について、ルールの改正とあわせて解説
就業場所・業務の変更の範囲
すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新時には、雇用直後の就業場所および従事すべき業務内容に加え、“変更の範囲”まで明示することが義務付けられました。これは、将来的に配置転換の可能性がある就業場所や業務内容を指します。
更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
有期労働契約の締結と契約更新時は、更新上限の有無とその内容の明示も義務付けられるようになりました。また、労働契約をはじめて締結した後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を事前に労働者に説明しなければなりません。あわせておさえておきましょう。こうした追加変更には、契約更新時の条件設定に対して労働者が同意を余儀なくされることがないよう牽制する意味があります。
無期転換申込機会
企業は「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)を明示する必要があります。これもまた、2024年に追加で義務付けられたことです。その背景には、先述した無期労働契約への転換に対する認知度の低さがあります。無期転換申込権を行使しない労働者が多いのは、そもそもそのルールを知らないからではないかといった声が、今回の追加変更へと押し上げたわけです。
無期転換後の労働条件
「無期転換申込権」が発生するタイミングでは、毎度、(無期転換後の)労働条件を明示しなければならなくなっています。いうなれば、無期転換をためらう労働者を減らすため、透明性を担保していこうとする取り組みです。あるいは、不合理な労働条件の禁止をさらに強化したルールとも捉えることができそうです。
有期労働契約の理解を深めて、トラブルのない職場に!
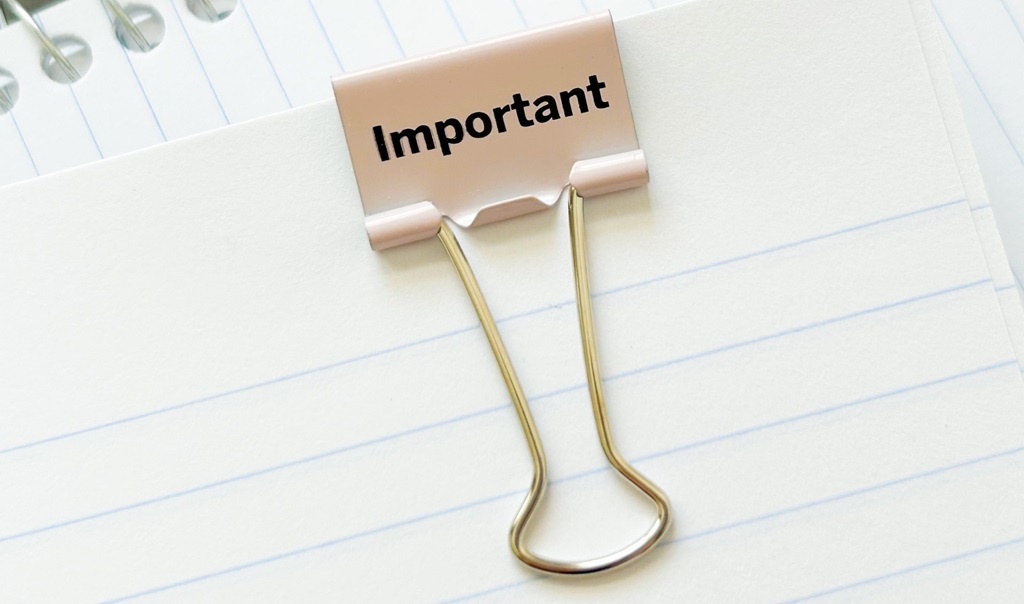
有期労働契約を巡っては、「雇止め」や「無期転換ルール」に関することなど、大なり小なりトラブルが散見されます。たとえば、事前の説明もなく契約の更新を断ち切ることや、無期転換ルールを適用させないよう契約満了前に雇止めを行うといった行為は、法に抵触する問題です。訴訟を起こされても無理はありません。
期間の定めがあるにせよ、ないにせよ、契約上のルールには労働者を保護する観点が含まれます。明示義務も然り。おそらく、この先の改正においてもまず焦点が当たるところでしょう。したがって、極端な話、働く人への配慮があれば、果たすべき義務について失念することはそうないと思われます。まさに、有期労働契約に対する理解を深めるうえでも核となる志向です。 そうやって、人事管理に真摯に向き合い続ける企業の姿勢は、トラブルのない職場づくりはもちろん、総じて採用力、定着力を強化する一因にもなると考えます。
求人掲載・採用業務のサポートや料金についてなど、ぜひ気軽にお問い合わせください。
また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談も無料で承っております!
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【公式】スキマ時間のスポットワーカー募集ならスポットバイトル
┗スキマ時間で「働きたい」と「働いてほしい」をつなぐ求人マッチングサービス。求人は無料で掲載できます。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。
▶【公式】面接コボット – 応募者対応の自動化で面接管理が楽に!
┗求人サイトからの応募対応を自動化できるサービス。チャットボットを通じ、日程調整まで効率よく進めてくれます。
▶【公式】採用ページコボット – 費用・実績も紹介!採用サイト制作サービス
┗採用ページ作成サービス。求人まとめサイトとの自動連携や求人検索エンジンへの対応により外部集客を強化します。
【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所
代表 荒武 慎一
同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。

