時間休とは?まずは成り立ちを紹介

冒頭でも述べたとおり、時間単位で有給休暇を取得できる制度が時間休です。時間単位年休や稀に時間有給などとも呼ばれています。
まずは時間休の成り立ちについて紹介しましょう。
従来の年次有給休暇は、原則1日単位、もしくは半日での利用が一般的でした。しかし、業種・業態や仕事内容によっては、誰もが簡単に有給休暇を取得できるわけではなかったのも事実。そこで2010年4月に労働基準法が改正されます。そう、有給休暇が取得しやすくなるようにとこの時間単位休の制度が導入されたわけです(労働基準法第39条第4項)。
時間休は、これまでちょっとした時間の通院や育児・介護でやむを得ず1日単位で有給休暇を取得していた人たち(なかには働きづらさから退職や休職の選択に踏み切った方もいたことでしょう)にとってありがたい制度だといえます。休みを細かく設定できるため、少なからず柔軟に働けるようになったはずです。
と、注意したいのは、時間休制度は決して企業への義務ではありません。導入の有無は各社の方針に委ねられます。しかしながら、離職防止や福利厚生の観点から、取り入れている企業は確実に増加傾向にあります。
時間休制度の導入手続きと計算方法
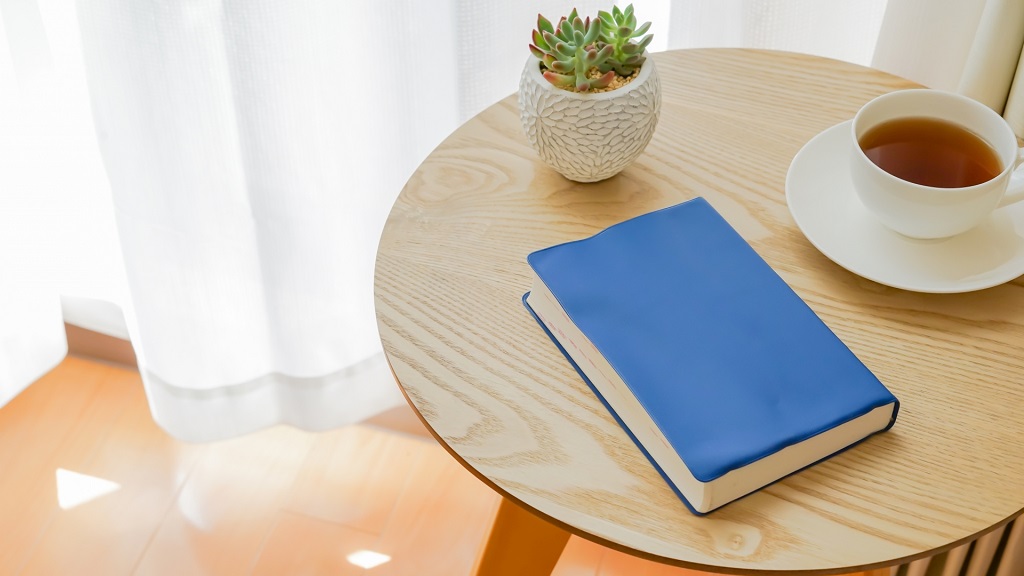
時間休制度を導入するためには、就業規則への記載と労使協定の締結が必要です。そのうえで、何時間刻みで設定するかも考えなければなりません。以下、具体的に説明します。
時間休制度を就業規則へ記載する
常時10人以上の労働者を使用している事業場では、時間休制度を取り入れるために、就業規則への記載が必要です。
モデル就業規則(第23条)では、次のように書かれています。
労働者代表との書面による協定に基づき、前条の年次有給休暇のうち、1年について5日の範囲で次により時間単位の年次有給休暇(以下「時間単位年休」という。)を付与する。
(1)時間単位年休付与の対象者は、すべての労働者とする。
(2)時間単位年休を取得する場合の、1日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとする。
① 所定労働時間が5時間を超え6時間以下の者…6時間
② 所定労働時間が6時間を超え7時間以下の者…7時間
③ 所定労働時間が7時間を超え8時間以下の者…8時間
(3)時間単位年休は1時間単位で付与する。
(4)本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の1時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。
(5)上記以外の事項については、前条(注※前条では年次有給休暇の付与日数等が規定)の年次有給休暇と同様とする。
引用元:モデル就業規則(第23条)
労使協定を締結する
実際に時間休制度を導入する際は、労働者の過半数で組織する労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者との間で、書面による労使協定を締結しなければなりません(労働基準監督署への届け出は不要)。
取り決め内容については次の項目を記載します。
時間休を取得できる従業員の範囲
時間休を取得できる従業員の対象範囲を定めます。仮に一部の労働者だけを対象にする場合は、(対象から外れる方々が時間休を取得することで)事業の正常な運営が妨げられるなどの正当な理由が必要です。また、「通院中の方」「育児中の方」といった具合に取得目的によって限定することもできません。そのため、基本、すべての従業員が対象に当たると捉えてよいかもしれません。
時間休の計算方法
時間休は、1年につき5日以内と定められています。取得できるのは、最低1時間です。1時間未満では取れません。また、企業と労働者間で交わした労働契約書に記載されている所定労働時間で換算されます。
たとえば1日の所定労働時間が8時間の場合、1時間の休暇を8回取れば1日分を消化した計算です。もちろん、7時間30分など労働時間が分刻みの企業も存在します。この場合、適用するのは切り上げです。7時間30分であれば1日分は8時間と扱われます。そのため、計算上、1日分を消化するなら1時間単位で8回、2時間単位で4回の時間休取得が必要です。
時間休導入のメリットとデメリット
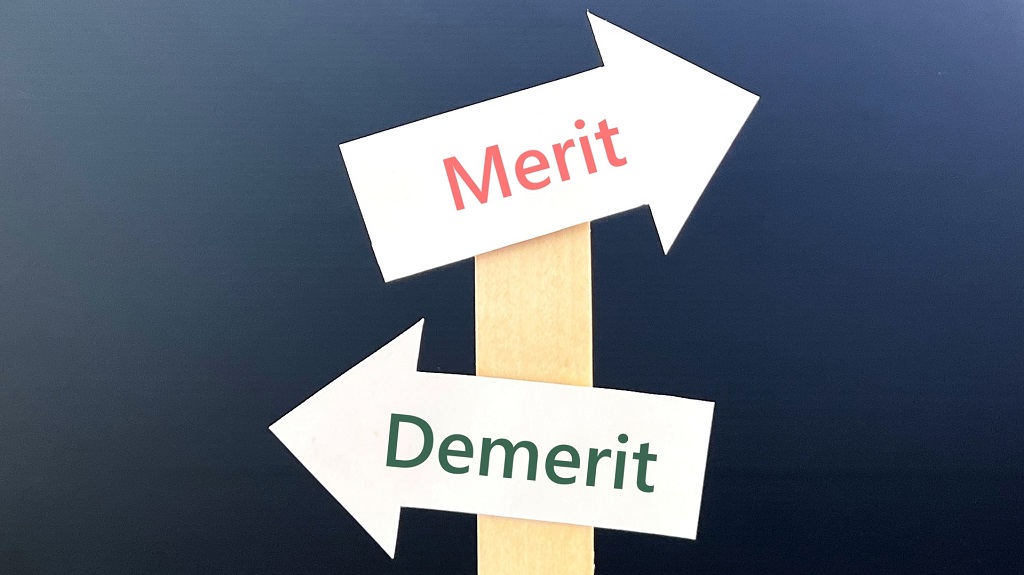
何とはなしに時間休の導入が気になっている人事担当者の方は、メリットとデメリットをしっかり把握しておくことが大切です。一見、従業員にはメリットをもたらし、企業側にはデメリットを及ぼすと短絡されがちですが、実は双方、それぞれ存在します。以下、正しく認識しましょう。
企業側のメリット
時間休が企業側にもたらすメリットは大きく2点です。ずばり、有給取得率の向上と採用活動でのアピールポイントが挙げられます。
有給取得率が向上する
企業は従業員に有給休暇をきちんと取ってもらう必要があります。しかし、たとえ取得を促したとしても、従業員たちが休暇を取ってくれないケースも少なくありません。「仕事が終わらない」「人が足りない」など、下手に休めない状況が蔓延していると、どうしても簡単には有給休暇を取ってもらえないわけです。が、そこで時間休を導入するとどうでしょう。1時間単位であれば、そう後ろめたさも感じることなく、有給休暇の取得に踏み切れるはずです。結果的に有給取得率の向上が期待できれば、それは紛れもなくメリットだと考えます。
採用活動でのアピールポイントになる
労働環境の改善をしている姿勢を見せることは、求人に注力するうえで非常に重要です。時間休でフレキシブルに働くことができる点は、まさに採用活動でのアピールポイントになり得ます。とりわけ福利厚生やライフワークバランスに重きを置く層には、魅力的でしょう。求人応募者数を増やすなら、このメリットはうまく活用したいものです。
企業側のデメリット
冒頭でも触れたとおり、管理が複雑化する点は確かにデメリットです。また、果たして従業員の疲労回復につながるのかどうかは甚だ疑わしい向きもあるでしょう。
有給の管理が複雑になる
時間休は1日を時間単位に分けて付与するため、実際にその従業員がトータル何日の有給休暇を取得したか、管理が煩わしく思えるかもしれません。もちろん最近はデジタルを駆使しながら労務管理を行う企業も増えているため、手間は大きく省かれるようになっていますが、それでも多くの企業がいまだにそうしたサービスを扱えずにいるのもまた事実です。複雑になったせいで業務の生産性が落ちるようなことがあれば、本末転倒だといえます。したがって、むやみやたらに導入することはおすすめしません。
時季変更権を行使しづらくなる
時季変更権とは、従業員が希望する休暇の日程が事業の正常な運営を妨げると判断した場合、企業側から変更を求めることができる権利のことです。これは時間休にも認められます。ただし、実際のところ時間休を取得する従業員に対しては行使しづらいのが慣例です。基本、従業員側の都合が優先される権利であるがゆえに、時間休となると、調整をお願いするのはより難しい傾向にあります。
有給休暇の本来の目的から外れる
有給休暇取得の本来の目的は、心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障することにあります。しかし、時間休を取得する従業員の場合、その理由は、育児や介護あるいは(ちょっとした合間で立ち寄れる)市役所など公的機関への用事といった疲労回復以外がほとんどです。それは決してデメリットとも言い切れませんが、休みを取った従業員には心身ともにリフレッシュしてもらい、その分のエネルギーをまた仕事に費やしてほしいと考える企業からすると、思惑と現実には少なからず乖離が存在します。
従業員にとってのメリット
人事担当者であれば、時間休が与える従業員への影響についても知っておいた方がよいでしょう。まずは、メリットからお伝えします。
タスク管理がしやすい
有給休暇の取得によって、自分の仕事がたまってしまうことはもちろん、上司を含めた同僚に負担を掛けてしまうことに罪悪感を覚える方がいらっしゃいます。1日あるいは半日の貴重な時間をなるべく無駄にせず、普段からつい無理をしてしまう人によくある傾向です。正直、そうした働き方は、推奨できるものではありません。そうしたなか、時間休であれば、タスク管理がグッとしやすくなるはずです。
ちょっとした用事を済ませるのに便利
市役所、病院、銀行、学校など平日にしかできない用事を済ませるためだけに、これまでは半日あるいは1日単位で有休を取得する必要があったところ、時間休を使えば、おそらく中抜けで対応できます。効率よく動ける点は、心情的にも楽にしてくれるため大きなメリットだといえるでしょう。
ワークライフバランスが実践できる
働き方改革により、これまでは長時間働くことが良いこととされてきた企業でも、次第にワークライフバランスの改善を重視するようになっています。ゆえに時間休は、まさしく企業の狙いに応えるように、従業員自身が日々の暮らしを充実させることにもうってつけの制度です。育児・介護だけでなく趣味や自分磨きのためにも使える貴重な時間。生活に張りが出る方も、きっと少なくないはずです。
従業員にとってのデメリット
それでは、従業員側のデメリットは何でしょう。メリット尽くしに思えますが、意外と落とし穴があります。
1日単位の有給休暇が取得しにくくなる
時間休が導入されたことで、これまで半日あるいは1日単位で取っていた有給休暇を時間休で取れないかと打診されるケースがあるようです。もちろん、法的に考えても従業員側の希望は問題なくとおります。が、そうした思わぬ角度からの指摘によって、時間休の弊害を覚える向きも出ないとは限りません。実際、1日単位の有給休暇を取る際にどこか後ろめたさが残るようになったとの声も見聞きします。
有給休暇の残数がわかりにくい
企業がそうであったように、有給管理の複雑化は、従業員にとっても当てはまります。たとえば、残日数(残時間)を確認する際、時間単位だとどうでしょう。細かい分、以前よりも煩わしく思えるはずです。だからこそ、企業側は労務管理サービスを用いるなど(時間休制度にあわせた)環境を整備していく必要があります。
時間休を導入するうえでの注意点

時間休制度は、厚生労働省が制定した指針に従って導入しなければなりません。いくつか注意事項をご紹介します。
1年の上限は5日まで
繰り返しお伝えしますが、有給休暇は本来、「心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障する」ために導入されたものです。そのため、“心身の疲労を回復”する以外の用途で使われやすい時間休は、1年間で5日までの上限が設けられています。例えば8時間勤務の場合、40時間までの時間休が上限です。
なお、5日を超えてしまったからといって有給休暇自体が取れなくなるわけではありません。時間休が使えなくなるだけで1日あるいは半日単位であれば有給は取得できます。
翌年への繰り越しが可能
時間休も通常の有給休暇と同様に翌年への繰り越しが可能です。
ただし、前述のとおり、1年間に取得できる時間休は上限が5時間と決まっています。そのため、前年度分を繰り越した場合であっても、これを超える時間休を取得することはできません(たとえば10時間繰り越した場合、翌年に「5日+10時間」が取得できることにはなりません)。
取得義務のある有給休暇以外が対象
労働基準法第39条により、企業は10日以上の有給休暇がある者に対して、1年間に5日間は必ず有給休暇を取得させる義務があります。対して時間休は、この取得義務のある有給休暇から控除できません(平成30年12月28日基発1228第15号)。つまり、時間休は義務とされている5日間以外で取得する必要があります。
企業側の時季変更権は認められる
時間休の場合も、時季変更権は認められています。ただし、時間単位の有給休暇に対して日単位に変更してもらう、もしくは日単位の有給休暇に対して時間休にしてもらうといった変更はできません。
時間休制度の導入に助成金を活用しよう

時間休制度の導入に二の足を踏む企業は少なくありません。それは特に中小企業で顕著です。理由はいたってシンプルだといえます。おそらく人手不足の問題で、従業員には時間単位で安易に休まれたくないと考えているのでしょう。
が、そうした懸念を払しょくしてくれる制度があることはご存じでしょうか。そう、助成金です。現在、時間休制度の導入した企業に対して助成金が支給される制度が整っています。ずばり、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)です。
導入に伴う労務管理用ソフトウェアや機器の購入、研修や人材確保に向けた取り組みなどに対し、補助金が支払われる制度で、支給対象は以下のすべてに該当する中小企業の事業主です。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 交付の申請時、すべての対象事業場において以下の「成果目標」設定に向けた条件を満たしていること
- 時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、または月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行う
- 年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入する
- 時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入する
- 特別休暇(病気休暇・教育訓練休暇・ボランティア休暇・新型コロナウイルス感染症対応休暇・不妊治療休暇)の規定をいずれか1つ以上新たに導入する
- 交付申請時、すべての対象事業場で年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則などを整備していること
申請が受理されると、成果目標の達成状況に応じて、取り組みに要した経費の一部の内、下記の低い方が支給されます。
| ①成果目標の1~4の上限額と賃金加算額の合計金額 ②対象経費の合計金額×補助率3/4(※労働者が30名以下かつ労務系の取り組みに対する経費の申請に対しては、所要額が30万円以上の場合、補助率は4/5で計算されます) |
残念ながら、2022年は利用申請が多数寄せられたため、10月にいったん受付中止となりました。再開は未定ですが、決まり次第、厚生労働省のHPで発表されるとのことです。
時間休をうまく導入して働き方改革を実現!

ライフワークバランスの改善が叫ばれる昨今、時間休制度は労働者とって良い影響を与える制度です。一方でデメリットが存在することも無視できません。それらを解消していくにはどのような環境や体制を構築していくべきか、慎重に検討していくことが大事だとえいます。そのうえでうまくいけば、離職率の低下や魅力的な求人につながる期待も持てるでしょう。
さて、時間休制度をPRして新しい従業員を採用したい人事担当の方には、求人広告の掲載や採用業務を支援するdipのサービスをおすすめします。「バイトル」「バイトルNEXT」「バイトルPRO」「はたらこねっと」「コボット」と、バリエーションは実に豊富です。それぞれの内容を確認したうえで、自社の求人・採用における課題解消に応えてくれるサービスの導入を、どうぞご検討ください。なお、お問い合わせは無料です。不明点や気になる点があれば、気軽にご連絡いただけますと幸いです。
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。

