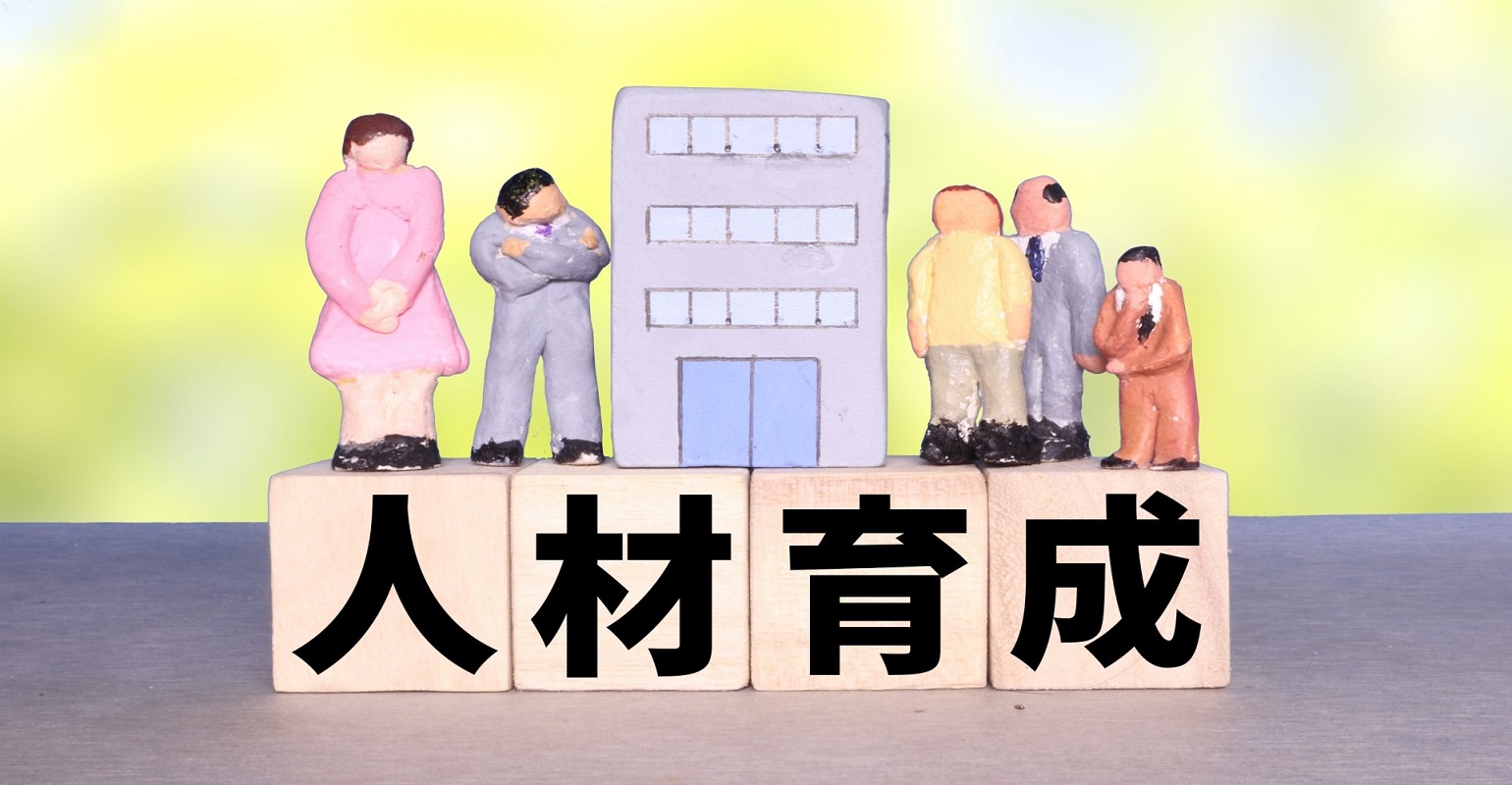人材育成とは?

人材育成とは、組織や企業が持つ人的資源を最大限に活用し、その能力やスキルを高めるための取り組みを指します。ビジネス環境が日々変化する現代において、企業が競争力を保持し続けるためには、従業員一人ひとりの成長が不可欠です。これは人材育成が個人のキャリアアップだけでなく、組織全体の発展にも寄与することを意味します。
さて、本章でまずお伝えするのは前提としておさえておきたい基礎知識です。基本概念を説明したうえで、混同しやすい「人材教育」や「人材開発」との違いについて明確にします。
人材育成の基本概念
人材育成の本懐を端的に捉えるならば、企業の発展に貢献できる従業員の成長を促進することです。これは、単に「仕事ができる人を育てる」という短期的な視点にとどまりません。本質的に求めたいのは、受け身にならず働ける自立したヒューマンスキルの向上です。企業が目指す将来の姿を見据え、そのビジョンに合わせて従業員一人ひとりが自身が必要とする能力を身につけていくことこそ、人材育成の肝といってよいでしょう。結果的に業績アップも期待できます。つまるところ、人材育成が基本とする概念は、従業員そして企業両方の成長です。
人材教育との違い
人材育成と人材教育は、しばしば同じ意味として使われることがあります。しかし実際のところ、両者のニュアンスは異なります。人材教育はあくまで育成手段の一つです。業務に必要な技術や知識を得るための研修、トレーニングを指すことが多く(ツールやシステムの活用方法の把握などもここに含まれます)、期間を設けて集中的に指南していくものだといえます。
一方、人材育成は、従業員の長期的な成長やキャリアの形成をサポートする取り組み全般です。これは、ヒューマンスキルの向上や、組織のビジョンやミッションに合わせたマインドセットの醸成など、より広範な視点での成長を促す要素が含まれます。あえて乱暴にいうならば、人材教育は「今、必要なスキルや知識を身につける」ことが重視され、人材育成は「将来を見据えた総合的な成長の促進」が目的です。
人材開発との違い
人材開発とは、従業員の潜在能力を最大限に引き出し、それらを組織の成果に結びつけるための取り組みです。具体的には、新しい役職や業務への配置転換、リーダーシップ強化、専門的なスキルの研鑽などが挙げられます。
他方、人材育成は、繰り返しお伝えしているように従業員の長期的なキャリアの成長をサポートするものです。そうやって持続的に育んだ人的資源も含めて、いかに活用していけるかが、人材開発の肝だといえます。
組織の成長には人材育成はもちろん、人材獲得も大切です。
求人・採用を検討中の方は、とりあえず気軽にお問い合わせください(ご相談は無料です)。
人材育成の目的

前述の内容からもわかるとおり、人材育成は組織の持続的な成長を支えるための戦略的な取り組みとして位置づけられています。そしてそこには当然、目的が存在します。主に挙げられるのは、次のとおりです。
- 従業員の能力や生産性の向上
- 従業員の自己実現とエンゲージメント向上
- 離職防止
- 将来に向けた経営戦略
上記はいわば人材育成の意義であり、期待する成果です。以下、それぞれ説明します。
従業員の能力や生産性の向上
業界・職種問わず人手不足に悩む企業は枚挙にいとまがない状況です。この傾向は今後も続くとみられ2030年には、なんと約1,000万人の労働力が不足するといわれています。そうしたなか、やはり必要なのは従業員の能力向上です。それはアルバイト・パートも例外ではありません(むしろ彼女・彼らにこそ必要)。一人ひとりがこれまで以上に高いパフォーマンスを発揮できれば、当然、生産性にもつながるでしょう。したがって、人材確保と同じように人材育成もまた急務だといえます。
人手不足にお困りの方は、ぜひこちらの記事もご覧ください。決してアルバイト・パートに限った話ではなく、ご参照いただきたいポイントを網羅的に取り上げています。
▶関連記事:アルバイトの人手不足でお困りの企業様へ。原因と対策を紹介
従業員の自己実現とエンゲージメント向上
従業員のキャリアにおいて成長や学びの機会を提供することは、(従業員自ら)己の価値や役割を再認識し、積極性をもたらす期待が持てます。うまく軌道にのせることができればエンゲージメントの向上、すなわち従業員が組織に対して持つ信頼やコミットメントの度合いも強まるでしょう。
高いエンゲージメントを持つ従業員は、組織の目標やビジョンに共感し、その実現のために自発的に行動します。人材育成を通じて従業員の自己実現をサポートすることは、エンゲージメントの向上にも寄与するわけです。そしてそれは、結果的に組織の生産性や業績、さらにはイノベーションの源泉へとなる可能性をもはらみます。
離職防止
早期離職の主な理由の一つには、自身のキャリアパスへの停滞感が挙げられます。「これ以上ここで働いても成長が見込めない」。いわゆるこうした心情は優秀な人ほど顕著です。当然、アルバイトの方にも当てはまります。なかには、「アルバイトだから期待されていない」と思い込む方も少なからずいらっしゃいます。
このような状況を回避するためにも、人材育成は必要です。従業員の成長をサポートしモチベーションを高い状態で保持することは、組織のミッションとして欠かせません。なおかつ、あらかじめそのビジョンを伝えておくのが望ましいでしょう。
将来に向けた経営戦略
経営戦略の策定において、企業の将来のビジョンや目標を明確にすることは不可欠ですが、それを実現するためのもっとも重要な資源は「人」です。
人材育成を通じて、従業員の能力や知識、そして価値観やビジョンに対する理解を深めることで、組織全体としての方向性や一体感が強化されます。これは、組織が目指すべき未来が作られることを意味し、同時に実現への大きな一歩です。アルバイト・パートを経て会社のキーマンに育っていくケースをみても、人材育成がいかに経営戦略のキーファクターか、如実にわかります。
▶関連記事:人的資本経営とは?有期雇用でも必要?背景から取り組み事例まで解説
人材育成における課題

ここまでお伝えしてきたとおり、人材育成は組織の成長と発展の鍵を握る大事な要素です。その一方で、取り組みには少なからず課題が伴います。とはいえ、これらを理解し適切に対応できれば、人材育成は効果的に作用するはずです。以下、人材育成において直面しやすい課題についてくわしく解説します。
適切なフィードバック
従業員の成長をサポートするうえでフィードバックは必須です。逆にいうと具体的かつ建設的なフィードバックが提示されない場合、従業員は自身の弱点や改善点を把握できないまま、結果、モチベーションの低下や成長の停滞を招く可能性があります。解決策として、定期的な1on1の面談が有効でしょう。コミュニケーションを強化し、まずは従業員を知ることが大切です。
キャリアパスの設計
従業員が自身のキャリアの方向性を明確に持てなければ、少なからず不安を抱えたまま日々の業務に取り組むことになります。だからこそ、人材育成が必要です。しかし、企業側が従業員に対して成長の道筋を示すことができていないケースも散見されます。したがって、前項で述べたことの繰り返しになりますが、まずは従業員を理解することに注力しなければなりません。
研修内容の組み立て
人材育成の一環として研修を組むとき、その内容次第では、従業員の混乱や不満につながる可能性があります。そのため、研修内容は慎重に精査することが必要です。仮に研修内容と実務が大きく乖離していれば、上述したようなトラブルを招きやすくなります。また、成長フェーズを見極め、状況に応じて適したプログラムを用意することも大事です。したがって、研修を実施する際は、現場でのオンジョブトレーニングの強化など、なるべく実務に即した内容かつ一人ひとりの進度にあわせて組み立てることが望ましいでしょう。
多様性への適応
企業文化や価値観は、人材育成の基盤です。しかし、それをすべての従業員に浸透させることは、そう容易くありません。多様性の時代といわれる昨今、一人ひとりの背景や属性を受け入れることは当然のこととはいえ、体制が構築されていないうちはそれなりに時間が掛かるでしょう。また、皆の意見を取り入れようとしたがために混乱を招くことも多々あります。したがって、どのように適応していくかが肝要です。
人材育成に必要なこと

本章では、人材育成において必要なポイントを取り上げます。具体的には、次のとおりです。
- 継続的な教育の機会
- メンターシッププログラムの実施
- 実践的な経験
- フィードバック文化の確立
実際、これらをどう行うのか、そして従業員の成長にどうつなげるのか。以下、それぞれ詳細を説明します。
継続的な教育の機会
教育は継続が大事です。それは、従業員が常に最新の知識とスキルを身につけるために欠かせません。卑近な例を挙げると、ツールやシステム、テクノロジーなど、時代についていけなくなると退化の一途を辿るばかりです。人材育成は社内だけでなく、外にも目を向けて行います。一時的な研修では点が線にはならないでしょう。さらには面になることを視野に入れて、すなわち業界の最前線で活躍できるよう支援することが大切です。
メンターシッププログラムの実施
人材育成においては経験豊富な社員が指導を行うことがほとんどです。しかし、教える側と学ぶ側両者のあいだに信頼関係が築かれなければ、なかなかスムーズにはいきません。そこで必要なのがメンターシッププログラムの実施です。メンターの選定も問われます。できる限り従業員の感情に寄り添い、尊重し、臨機応変に状況を見極められるような方に就いてもらうのが鉄則。内容も仕事関連に終始せず、柔軟にサポートしていくことが肝心です。
実践的な経験
座学による知識だけでなく実践的な経験を通じて学ぶこともまた、人材育成には不可欠です。インターンシップやプロジェクトベースの任務を通じて、従業員は実際のビジネスシナリオでの問題解決やチームワークの重要性を学びます。理論だけでなく実務に役立つスキルも身につけられることは、まさに人材育成の本懐です。
フィードバックの確立
先に課題の項で列挙しましたが、適切なフィードバックは人材育成において大変重要です。そのため、企業は文化としてこれを確立する必要があります。当然、どのように行うのか、仕組みづくりも大切です。従業員が自身の強みと弱みを理解し、改善へと意識を向けられるよう具体的かつ建設的なシステムが求められます。また定期面談だけでなく、普段から柔軟にそうした場を作ることが大事です。一方通行にならず、従業員からの意見も積極的に取り入れましょう。理想は、立場問わず皆がお互いの成長と組織の改善に貢献できる環境を構築していくことです。
組織の成長には人材育成だけでなく、人材獲得も必要です。
求人・採用を検討中の方は、とりあえず気軽にお問い合わせください(ご相談は無料です)。
人材育成の目標設計に便利なスキルマップ

人材育成を行ううえで便利なものの一つがスキルマップです。これによって、従業員の能力における進捗を体系的に把握できます。以下、この便利なツールについての解説です。
スキルマップとは
そもそもスキルマップとは何でしょう。これは、従業員ごとに求められるスキルを時系列にしてまとめた表です。人材育成における各ステップ、フェーズを一覧にしているため、全体像の把握がスムーズになります。同様に教育制度も組み立てやすくなるでしょう。というのも、スキルマップを確認すれば、いつまでにどれだけのスキルを身につければいいかという目安がわかりやすく、そこから逆算することで、カリキュラムも組みやすいのです。つまり、このスキルマップによって人材育成を効率的に行えます。
もちろん、スキルマップは人事評価にも使えます。従業員の能力をスキルマップに当てはめることで、そのポジションに相応しい人材かどうかの判断にも有用です。時期尚早な抜擢を避け、リーダー候補者を計画的に育てていくためにも、ぜひスキルマップを活用してみてください。
| 種類 | 3ヶ月以内 | 1年以内 | 3年以内 | 5年以内 |
|---|---|---|---|---|
| 共通スキル | 資料作成 電話応対 | タスク管理 課題の把握 | クレーム対応 新人指導 | 会議の司会・進行 プロジェクトの牽引 |
| 専門スキル | 伝票作成 | 自社システムの説明 | マニュアル作成 | イベント立案 |
スキルマップの作成手順
スキルマップは、以下の手順で作成します。
- 必要スキルの洗い出し
- スキルを分野ごとに分類
- 見直しと修正
- スキルマップ完成
まずは、必要なスキルを洗い出します。各部署で求められるスキル(部下・後輩に身につけてほしいスキル)をなるべく多く書き出していきましょう(労務管理やメンタルヘルスに関する知識など専門的なものは精通する部署や担当者に要確認)。次に、洗い出したスキルを、分野ごとに振り分けます。分類の基準になる項目は、「社会的スキル(ビジネススキル・対人スキル)」や「専門的スキル」などです。
さらに、分類したスキルを成長ステップに当てはめていきます。従業員のキャリアを時系列で見て、どの段階でどれだけのスキルを身につける必要があるかを整理していく作業です。ひとまず形になった時点で人事部はじめ関係各所に共有します。そのうえで適宜見直し・修正を行い完成です。
人材育成の主な手法

人材育成にはいくつか手法が存在します。本章で具体的にピックアップするのは、職場内での直接指導による「OJT」、より広範な知識を得てもらう「Off-JT」、自己主導の学びを促す「自己啓発」、柔軟な学習環境を提供する「e-ラーニング」、多様な業務経験を積む「ジョブローテーション」、そして目標に基づいた成果を追求する「MBO」です。以下、これらが従業員一人ひとりのスキルアップとキャリアの発展にどのように寄与するのか掘り下げていきます。
OJT (職場内研修)
OJTは「On-the-Job Training」の略称で、人材育成の代表的な手法の一つです。一般的には、実務を通じて経験を積ませていきます。上司から部下へ直接仕事を教えることで、実務能力の向上を図るものです。同時に、従業員の主体性や自律性も促します。いずれにしても、一人ひとりに合わせた指導やサポートが必要です。
Off-JT (職場外研修/集合研修)
Off-JTは「Off-the-Job Training」の略称で、主に職場以外の場所で行う集合研修を指します。普段、従事している環境から離れて行うことや集中的に取り組んでもらう点が特徴です。また、OJTのような実務的なスキルの習得を目指すやり方とは異なり、Off-JTの場合、汎用性の高いスキルや知識を身につけてもらうようにします。ビジネスマナー研修やキャリア自立研修などは、まさに典型といえるでしょう。
自己啓発
自己啓発とは、カリキュラムを従業員自身が決めて自発的に受講する教育研修方法です。企業としては、職務に必要な知識や教養、個人のキャリア形成のための資格取得をサポートします。具体的には、セミナーへの参加費用の負担や、学習時間を確保するための休暇制度導入などが挙げられます。
e-ラーニング
e-ラーニングは、デジタルプラットフォームを介した人材育成手法です。オンライン上で完結するため、従業員が自身のペースで学習を進めることができます。コースの内容は企業の特定の要件に合わせてカスタマイズが可能です。また、管理システム上では進捗の追跡と評価が容易に行えるため、従業員の成長を記録しやすいといえます。
ジョブローテーション
ジョブローテーションとは、さまざまな経験を積ませるために、ある一定の配属期間を設けて職場や職種を異動してもらう制度を指します。従業員の能力が多岐にわたることで組織に対する理解が深まり、なおかつ長期にわたって活躍できる人材へと成長が期待できる方法です。広い視野を持てることで、将来的には重要なポストに就いてもらうキャリアパスも生まれます。
MBO (目標管理制度)
MBOは「Management by Objectives」の略称で、従業員個人が(あるいは各部署が)自身で目標を設定し、その達成に向けて成長を図るやり方です。このアプローチでは、適宜サポートすることはあっても、基本は従業員が自発的に動いていくことを促します。目標の設定にとどまらず、行動計画の策定、進捗のモニタリング、最後に評価とフィードバックの構成で行うのが一般的です。
人材育成が会社の未来を創る!

人材育成は企業が競争力を長期的に向上・維持できるかどうかを左右します。もちろん手間こそ掛かりますが、アルバイトも含めて、従業員の成長をきっかけに会社の業績が好転することは決して珍しくありません。ただし、適切な対応が必要です。たとえば、目標を曖昧にすることやフィードバックを疎かにしてしまっては、むしろ人は離れていく一方でしょう。
人材育成を通して企業のさらなる成長につなげるためにも、研修や現場経験から学べる仕組みを整えていくことが肝心です。そこに加えて、そもそも欲しい人材をいかに獲得していくか。採用、そして人材育成に成功するサイクルを作れたとき、おのずと企業は発展していくことになります。
そういうわけで、自社の未来をより明るくするため、拙稿が人材育成の重要性を今一度考える機会になれば幸いです。
求人掲載・採用業務のサポートや料金についてなど、ぜひ気軽にお問い合わせください。
また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談も無料で承っております!
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーの55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。