人材とはずばり何?

人材とは、企業や社会にとって価値を持ち、何らかの役割を果たすことができる人物を指します。単に“人がいる”という状態ではなく、彼・彼女たちが持つスキルや知識、経験、あるいは可能性を含めて、組織にとって有益であると見なされる存在です。採用や人事の現場では、「求める人材」という言葉が頻繁に使われますが、そこには「自社にとって活躍が期待できる人物像」という意味合いが含まれています。つまり、人材は単なる労働力として扱われるのではなく、“戦力になり得る人”という前提で求められるわけです。なお、辞書のなかでも“才能があり、役に立つ人”、“有能な人物”などと定義されています。
人材と人財の違い

経営者、事業主のなかには人材を“人財”と表現される方がいらっしゃいます。ちょっとしたユーモアやレトリックとしてこの言い回しが使われることもありますが、明確に両者の違いは把握しておいた方がよいでしょう。同音異義というよりは、使い手の意図や視点がにじみ出る分、良くも悪くも受け手の印象が変わってくる言葉です。以下、それぞれがどのような文脈で用いられるかを紹介。「材」と「財」をどう選ぶか、あるいは控えるか、どうぞ参考にしてみてください。
表現としての“人材”の使われ方
“人材”という言葉は、採用、育成、配置、登用……等々、人事領域全般で広く使われています。たとえば、求人票や企業の採用ページでは「新たな人材を募集」「即戦力となる人材を歓迎」といった表現が一般的です。また、「人材育成制度」「人材開発プログラム」のように施策や取り組みを表す場合もしばしば用いられています。加えて、自治体の運動や新聞記事、官公庁の報告書でも使われている場面は多く、たとえば「地域産業を支える人材の確保」「女性人材の活躍推進」など一度は目にしたことがあるはずです。(“人材”は)総じて、特に対象を選ばない汎用性の高い言葉、表現だといえるでしょう。
表現としての“人財”の使われ方
人材ではなく“人財”と使われるケースも決して珍しくありません。たとえば、次のようにあえて人材ではないことを強調した理念や惹句は、ある意味典型的な使われ方だと考えます。
- 当社は、人材ではなく人財を育てます。
- 組織の発展に必要なのは人材ではなく人財です。
- 次世代のリーダー育成のために人材ではなく「人財プログラム」を実施しています。
もちろん、“人財”単体で使われることもあります。
- 多くの人財がイノベーションを生む!
- 従業員は人財だ!
- 貴重な人財として組織の成長に欠かせません。
字面からもわかるように、企業の経営資源としての価値を見出すその表現には、思いの強さがうかがえます。
人材を人財と表現する理由

人材の“材”に“財”の字を当てるのは、文字どおり財宝、財産の意味が込められているのが一般的な解釈でしょう。実際、従業員は企業にとって宝でありいわば資本だという考え方が浸透している背景には、少子高齢化に伴う労働力の減少や急速なグローバル化があり、さらには従業員への投資で利益の最大化を図る「人的資本経営」が注目を集めていることも無関係ではないはずです。そうした世相の影響が現況に、つまり人材から人財へと捉える向きに拍車をかけているのだと考えます。
人材を人財と表現する場合の注意点

従業員は企業の経営資源という考え方を大切にされているとポジティブに捉えることもできれば、“財”の字にお金の意味合いを強く覚える向きもあるかもしれません。たとえば、従業員が自身の存在を利益のための道具だと受け取る可能性もあります。「人を大事にしている」という言葉さえ、結果として“都合よく扱いたい”という本音の隠れ蓑のように映ることもあるでしょう。
そもそも「人財」という言い回しそのものがやや堅苦しく、企業目線の表現であることから、受け手との距離を広げてしまうリスクも懸念されます。どれほど前向きな意味を込めていたとしても、言葉が一方的に響いてしまえば、本来伝えたかった「敬意」や「感謝」がうまく届かないわけです。 結局のところ、大切なのは言葉よりも行動であり、扱われ方そのものです。「人財」と表現するからには、実際にその人の価値を認め、育て、報いようとしていることが伝わらなければ、かえって空回りすることになりかねません。
人材と混同しやすい人財以外の言葉
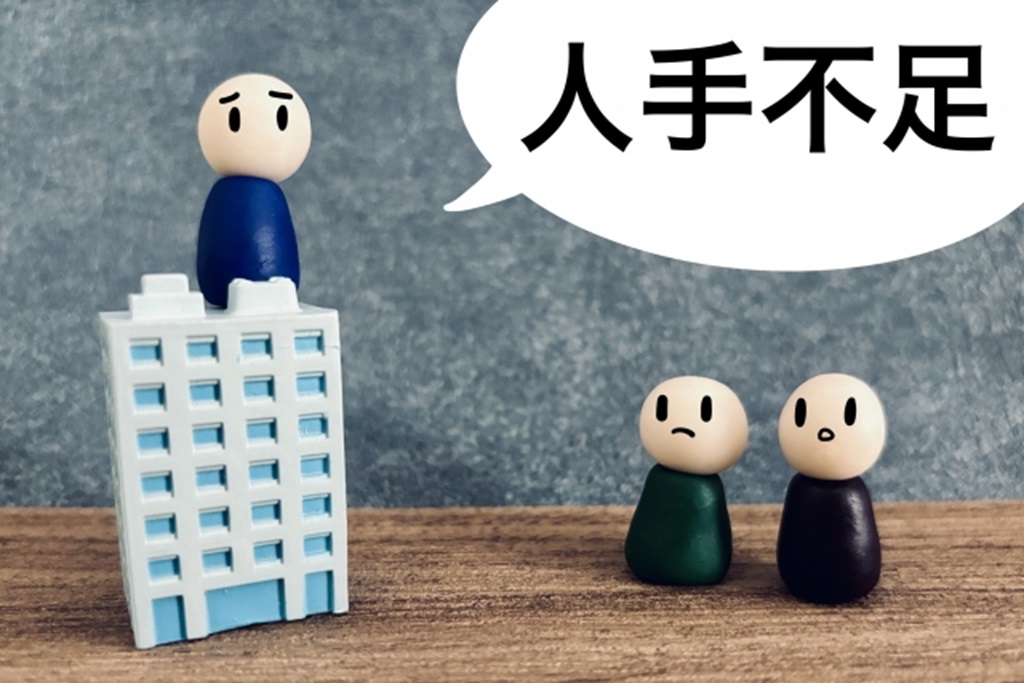
人材の使われ方と似ているのが人手や人員でしょう。また、人財と誤表記するのはまだしも“人罪”や“人在”と間違ってしまうのはやはり避けたいところです。本章ではこうした混同しやすい言葉にフォーカスします。
人手
“人手”と“人材”は同じように使われることも少なくありませんが、厳密には微妙な違いがあります。前者は主に“労働力の数”を指し、現場を回すために必要な「作業をこなす人」のニュアンスが強いでしょう。方や後者は、スキルや経験がある即戦力と見なされる方が多く、その言葉には単なる作業要員以上の期待が込められているはずです。現場レベルでは両者の境界が曖昧になることもありますが、人手は“今足りない手数”、人材は“先を見据えて迎え入れる人”といった認識の違いで使い分けられるものだと考えます。
人員
“人材”と“人員”もまた、似た文脈で使われることはありますが、意図している対象はやはり異なります。“人員”は、ある業務や組織に必要な人数や配置上の枠を意味する言葉です。誰がどのような能力を持っているかはさほど重視されません。たとえば「人員を補充する」という場合、それは数的な調整の話であり、その人物の適性や将来性に対する期待とは切り離されています。一方“人材”には、組織にとっての価値や成長の可能性などが前提として含まれていることがほとんどです。人員が「枠を埋める人」であるなら、人材は「将来を担う人」といえるかもしれません。数を整えるのか、力を育てるのか。その違いが両者の使い分けに表れます。
絶対に避けたい“人罪”や“人在”との間違い
人材の変換ミスで避けたいのが“人罪”や“人在”です。これらの誤表記によってその意味は一変し、極めてネガティブな印象を与えてしまいます。“人罪”は字のとおり罪をもたらす人のことです。つまり、迷惑な存在や厄介者といった否定的なニュアンスを含みます。また“人在”は一見それらしく見えるものの、そこに“ただいるだけ”の人と定義される言葉です。無気力・無関心を連想させるため、受け手に冷たい印象を与えかねません。特に社内資料や採用広報などでこのような誤記が生じると、従業員当人たちにとって屈辱的であるだけでなく、企業としての配慮のなさや言葉の軽さが疑われることにもつながります。ほんの一字の違いが、信頼や評価を大きく損なうことがあるため、変換時には細心の注意が必要です。
求める人材、育つ人財を確保するために必要なこと

前項までにお伝えしてきた言葉の定義から、企業は要件に合った人材を求め、入社後は人財として活躍してもらうことを期待していると解釈できそうです。では、そうした方々を確保するためには何が必要なのでしょうか。一連の流れとして順序立てて挙げると次のとおりです。
- 適切な採用ターゲットの設定
- 採用媒体や手法の見直し
- 成長できる環境の整備
- モチベーションが高まる仕組みの構築
以下、それぞれの概要を端的に説明します。
適切な採用ターゲットの設定
求める人材を確保するにはやはり、適切な採用ターゲットの設定が欠かせません。どのような人物を迎え入れたいのかという視点が曖昧なままでは、採用活動そのものが場当たり的になりがちです。結果として、応募者の側にも「この会社が何を求めているのか」が伝わらず、互いに期待のずれが生じるリスクが高まります。逆に、ターゲットが定まっていれば、発信する言葉のトーンや情報の取捨選択にも一貫性が生まれます。すなわち、採用の質を高めるためにもまずは、人材要件を明確に設定していくことが重要です。
採用媒体や手法の見直し
ターゲットが決まれば、採用媒体や手法も当然ながら見直していく必要があります。届けたい相手が明確になった以上、それに適した対応が肝心です。場合によっては馴染みのあるやり方を捨てなければならないでしょう。そうやって試行錯誤していくことが採用活動には求められます。
成長できる環境の整備
採用した人材を人財として育てていくには、環境整備は必須です。教育体制が杜撰、相談できる雰囲気がないといった組織では、どれだけ有望な方を招き入れても力を発揮させることは難しいでしょう。加えて、早期離職も懸念されます。これらを回避し、人財として確保するためにも成長につながる環境づくりが求められます。
モチベーションが高まる仕組みの構築
働くなかで生まれる意欲や充実感は偶然に任せるものではなく、何らかの形で後押しされる仕組みが求められます。人材から人財へ育ち、定着していくうえでも欠かせない要素です。すなわち、モチベーションのアップ(構造化)が継続的な活躍のカギを握ります。
人材要件を設定するコツ

前述した適切な採用ターゲットの設定とは、人材要件の定義を指します。コツは次のとおりです。
- 業務に直結するスキル・経験を洗い出す
- 現場で活躍する人たちの共通点を見つける
- 組織の現状や方針と照らし合わせる
- 優先順位を明確にする
以下、それぞれ解説します。
業務に直結するスキル・経験を洗い出す
つい漠然と理想像を追いかけてしまうと、要件が現場と乖離することが多々起こります。そのため、まずは日々の業務の中で実際に求められることを明らかにすることが大事です。知識、経験、柔軟な思考など一つずつ丁寧に拾い上げていくことで、「活躍できる人」の輪郭が自然と浮かび上がり、結果として採用のミスマッチも減らせる期待が持てます。
現場で活躍する人たちの共通点を見つける
人材要件を一から組み立てようとすると抽象的になりがちですが、すでに自社で成果を上げている人たちを観察すれば、彼・彼女らの特徴から帰納法的に具体的なスキルセットや人物像を導き出せると考えます。行動パターンや習慣なども組み込めると、欲しい人材の解像度はより高まることでしょう。
組織の現状や方針と照らし合わせる
どれだけ優秀な人であっても、組織の現状や方針とずれていれば、力を発揮できなかったり、早期に離職してしまったりと、ミスマッチを起こす可能性は高くなるはずです。そもそも人材要件は、自組織の何を支え、何を変えていく人が必要かを見極める作業ともいえます。変化のフェーズにあるのか、安定を求める時期なのか。トップダウンなのか、自走型を求めているのか。そうした方向性との整合性が取れるように調整を図ることが大事です。現場の要望だけでなく、経営やチームの方向性と丁寧にすり合わせることが、自社に合う人材獲得の肝になります。
優先順位を明確にする
人材要件を挙げていくと、どうしても「あれもこれも必要」となりがちですが、すべてを満たす人など現実にはほとんどいません。そのため、何が絶対に外せないのか、何は後からの習得で補えるのか、優先順位を明確にすることが不可欠です。求める要素に順序をつけておくことで、採用の判断軸がぶれにくくなり選考段階でも迷いが減ります。また、優先度の低い要件にこだわりすぎて本当に必要な人を見逃してしまうといった失態を招かずに済むでしょう。
求める人材を採用するコツ

求める人材を採用するためには、前述した採用媒体や手法の見直しなども含めて取り組んでいく必要があります。その際、いくつかコツを意識すると結果もまた変わってくるでしょう。ざっと挙げると次のとおりです。
- 定した人材要件に合わせて求人サービスを選ぶ
- 求人原稿を求職者目線で考える
- 選考プロセス上の問題を解消する
以下、それぞれ解説します。
設定した人材要件に合わせて求人サービスを選ぶ
人材要件が独り歩きしないよう、求人サービスの選定にも慎重に向き合いましょう。たとえば、「経験者が集まりやすい」「募集業種に特化している」といった強みを持つメディアが要件に合致し、求める人材との接点創出につながりやすい場合、それは適切なサービスと捉えることができます。そうやって照合かつ比較しながら最適解を見つけていくわけです。
求人原稿を求職者目線で考える
求人原稿に多くの情報を詰め込んだとしても、あくまで受け手に意図したとおりに伝わらなければ意味を成しません。つまりは、求職者目線で考えることが大事です。彼・彼女たちがいざ働くとなったとき、何に不安を覚え、何を期待するのか、そうした視点を持ち合わせていないと、一方的な発信に留まってしまいます。そのため、写真や動画うまく使ったり、言い回しを工夫したりといった計らいが必要です。ここに配慮するかどうかで、他社求人とも差別化を図ることができます。
選考プロセス上の問題を解消する
適切なサービスで、魅力的な求人原稿を出しても、選考プロセスに見直しの余地があった場合、それが理由で採用を逃す羽目になるケースも存在します。たとえば、次の選考の案内が遅かったり、内容が不透明だったりすると応募者は不安や不信感を覚えるものです。また、面接官の態度も印象を大きく左右します。たった一人の面接担当の軽率な姿勢が選考辞退につながることも決して珍しくありません。いずれにしても、選考プロセスや社員に対するイメージに無頓着にならないよう、問題があれば早急に改善、解消が必要です。
採用した人材を育成するコツ
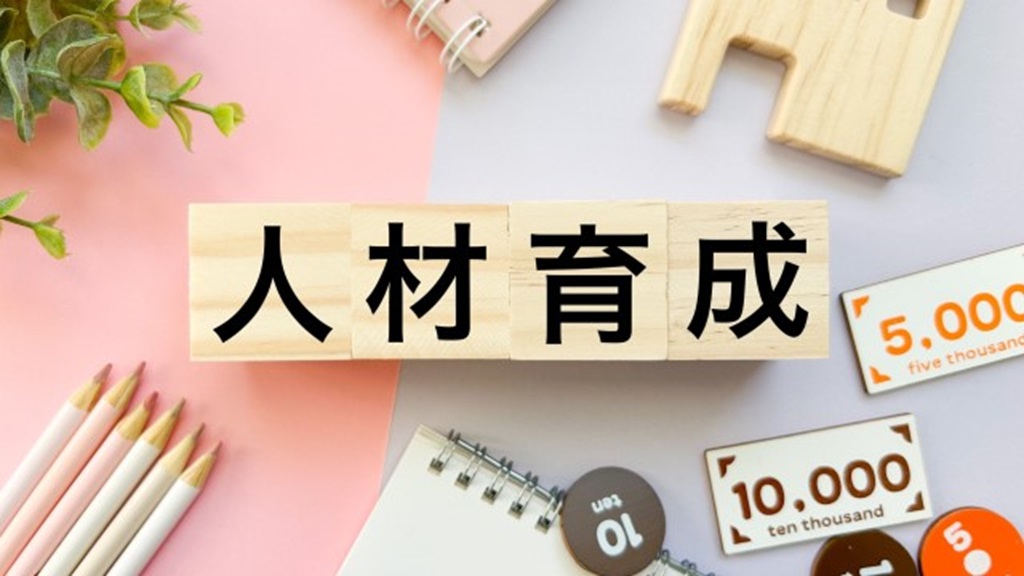
求める人材を採用できたとしても、すぐに辞められてしまっては意味がありません。また、一向に職場に慣れない、なかなか成長が見られないといった事態が続くことも問題です。では、どのようにして育成を行えばよいのでしょう。大事なコツは次の3つです。
- 各人の得意分野や苦手な領域を把握する
- 仕事の背景や目的を伝える
- 段階的に裁量を増やす
以下、それぞれ解説します。
▶関連記事:人材育成とは?目的、課題、目標設計の方法など主要ポイントを解説
各人の得意分野や苦手な領域を把握する
人材育成は、均一化したメニューでは効果にバラツキが生まれます。それはいうまでもなく、一人ひとり、得手不得手があるからです。したがって、まずは各人の得意分野や苦手な領域を把握するところからはじめましょう。得意なことを伸ばす方向で自信を持たせ、苦手な部分には過剰なプレッシャーを与えず段階的に取り組めるよう調整する。加えて、本人の性格にも目を向けながら、どうすれば持っている力をうまく発揮できるか配慮を重ねていくことが大事です。
仕事の背景や目的を伝える
仕事を任せる際、その背景や目的を伝えることで、取り組み方や意欲に大きな違いが生まれます。単に作業内容だけを伝えられた場合、指示待ちや表面的な対応に留まりがちですが、「なぜそれをやるのか」「どのような意味があるのか」といった文脈が共有されていれば、自ら考え、工夫しようとする姿勢が培われることにもなるでしょう。背景を知ることは、業務への納得感や当事者意識にもつながります。伝え手にとっては当たり前のことでも、受け手には説明の有無で理解の深さが段違いに変わるといっても過言ではありません。そしてそれは成長スピードにも大きな影響を及ぼします。
段階的に裁量を増やす
人材育成に有効なものの一つとして裁量を持たせることが挙げられます。これ自体、コツといえばコツなのですが、端からすべてを任せるのは現実的ではありません。無理な負荷は失敗体験や不安感を強め、成長の妨げになることも考えられます。だからこそ、慣れとともに少しずつ責任領域を広げていくことが大切です。段階的に裁量を増やすことで当人に合った育成が図れます。
人材育成から定着につながるコツ

人材育成に力を入れるだけでは定着につながらないことも往々にしてあります。大切なのは、一人ひとりに向き合う姿勢です。まさに人材を人財(宝)と捉えるように、各人の価値を承認してあげることが求められます。具体的なコツは次のとおりです。
- 働きやすい環境を作る
- 1on1や雑談の場を意識的に設ける
- 成長を評価し待遇面にも反映する
以下、それぞれ解説します。
働きやすい環境を作る
スキルの習得や経験の蓄積も重要ですが、それを積み重ねるには、安心して日々を過ごせる土台が必要です。企業側はまさにそれを提供することが求められます。たとえば、無理のない業務量や、相談しやすい雰囲気、過度なストレスのない人間関係といった要素は、表立って語られにくいものの、大なり小なり定着に影響するものです。逆に、いくら育成に力を入れても、環境そのものに負担や違和感があれば、そこに居続けたいとは思えません。育成にばかり目を向けず、働きやすいか否か、常々目配りすることが大事です。
1on1や雑談の場を意識的に設ける
業務以外のコミュニケーションがあるかどうかで、帰属意識に差が生まれるといっても過言ではありません。特に1on1やちょっとした雑談のように、形式にとらわれず相手に目を向ける場があると、「見てもらえている」「話せる相手がいる」といった安心感を覚えるものです。それは、離職のきっかけを未然に減らすことにもつながります。人材が定着していくには制度や待遇だけではないわけです。むしろ、人間関係や会話の積み重ねに支えられています。だからこそ、こうした場を“自然に生まれるもの”ではなく、“意識してつくるもの”として捉えることが重要です。
成長を評価し待遇面にも反映する
日々の努力や成長が正当に評価され、待遇に反映される実感があるかどうかで、働く意欲も変わってきます。無意識に定着の意志にも影響を及ぼしているでしょう。一方でどれだけやりがいのある仕事でも、成果が見過ごされたままでは、報われなさや不公平感につながりかねません。ゆえに小さな成長も見逃さず称え、少しでも報酬などに上乗せできると、従業員エンゲージメントはわかりやすく上がっていくと思われます(定着率も然り)。いずれにしても定着を促すには、彼・彼女たちへの労いを形にしてあげることが大事です。
人材・人財確保に役立つdipのサービス

求める人材そして育つ人財を確保していくにはサービスの選定が肝になるのは既述のとおりです。本章では、dipのサービスをご紹介。それぞれの特長を理解したうえで、ときに組み合わせることなども視野に入れつつ、ご利用のほど検討いただけますと幸いです。
アルバイト・パートの人材募集なら『バイトル』
『バイトル』は、アルバイト・パートの人材採用におすすめの求人サイトです。TVCMなどの広告効果もあり認知度も高く若年層を中心に幅広い年代の求職者にリーチできる期待が持てます。原稿作成の対応、多彩な検索、細かな条件の絞り込み……等々、サポート面、機能面、ともに充実しているため安心です。そのほか、掲載から応募までのスピーディーに進められる点も特長に挙げられます。
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
今すぐ人材が必要なら『スポットバイトル』
『スポットバイトル』は、急な欠勤やピンポイントでシフトを埋めたいときに使えるサービスです。公式LINEアカウントから簡単に求人を掲載できる点や送客が見込める『バイトル』とのお得な連携、ワーカーのモチベーションにつなげる「Good Job ボーナス」制度……等々、市場のスポットサービスとは一線を画しています。初期費用や求人掲載費用が不要な点もありがたいところ。費用対効果に優れ、柔軟に人材を獲得できます。
▶【公式】空いた時間のスポット募集ならスポットバイトル|求人掲載はこちら
社員・契約社員の人材募集なら『バイトルNEXT』
『バイトルNEXT』は、正社員・契約社員を目指す人のための求人サイトです。特に20~30代の若年層、なかでも未経験からキャリアを築きたい層の応募が集まりやすい傾向にあります。とりわけ物流業界に強く、不足しがちなドライバー採用での実績が豊富です。職場の雰囲気を動画で伝えるオプションやしごと体験、職場見学といった機能もあるため、求職者からすると応募前に現場の空気を知ることができ、結果としてミスマッチの防止策としても作用しています。そのほか、求人掲載と同時に『バイトル』にも無料で情報が出るため、求職者へのリーチも広く採用効率の面でも魅力的です。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
プロフェッショナル人材の採用なら『バイトルPRO』
『バイトルPRO』は、有資格者や業界経験者が多く集まる求人サイトです。医療、介護、保育、美容、Web/IT、飲食、物流、販売、サービス……等々、各業界のプロフェッショナル人材を採用するのにおすすめします。職種ごとに最適化された求人原稿のテンプレートやスカウトメールなどの機能、各業界に精通したコンサルタントによる専任サポート……等々、安心して採用が行えるプラットフォームです。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
派遣も含めて雇用形態問わず人材が必要なら『はたらこねっと』
『はたらこねっと』は、派遣求人を中心に、正社員、契約社員、パート・アルバイトなど多様な雇用形態の求人情報を提供する総合求人サイトです。特に派遣求人においては、掲載企業数が業界トップクラスを誇ります。機能もユニーク。たとえば、職場の特徴を(バロメーターで)示す「ねこバロメーター」により、求職者は応募前に職場の詳細を把握しやすくなり、企業側はミスマッチの回避が期待できます。また、求職者が匿名で興味を示すことができる「キニナル」機能では、文字どおり気になる人材へのアプローチが(応募前の段階で)可能です。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
人材と人財の理解を深めて採用、育成、定着を図ろう

人材とは何かを考え、“人財”と表現するケースを見極めることは、採用や育成、定着にも影響を及ぼすポイントです。それは自社の価値観を定義することはもちろん、従業員だけでなく、今後仲間になり得る求職者も含めて、どう個々と向き合っていくかを意味します。だからこそ、数を揃えるだけの採用ではなく、各人の可能性を引き出す関わり方が問われます。長く活躍できる人材を確保していくためにも大事な意識です。
求人掲載・採用業務のサポートや料金についてなど、ぜひ気軽にお問い合わせください。
また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談も無料で承っております!
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【公式】空いた時間のスポットワーカー募集ならスポットバイトル
┗空いた時間で「働きたい」と「働いてほしい」をつなぐ求人マッチングサービス。求人は無料で掲載できます。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。
▶【公式】面接コボット – 応募者対応の自動化で面接管理が楽に!
┗求人サイトからの応募対応を自動化できるサービス。チャットボットを通じ、日程調整まで効率よく進めてくれます。
▶【公式】採用ページコボット – 費用・実績も紹介!採用サイト制作サービス
┗採用ページ作成サービス。求人まとめサイトとの自動連携や求人検索エンジンへの対応により外部集客を強化します。

