仕事が長続きせず辞める人にみられる特徴

仕事が長続きしない人には、いくつかの共通した特徴があります。これらを理解することで、採用時や日々の業務のなかで潜在的なリスクを早期に発見し、適切な対応を取ることができます。
具体的な特徴は次のとおりです。
- そもそも転職回数が多い
- 人間関係で悩みやすい
- 他責思考が強い
- 真面目過ぎる
- こだわりが強い
- 野望・行動力がある
以下、それぞれ詳述します。
そもそも転職回数が多い
転職回数の多さは、その人の職場適応力や忍耐力を示す指標の一つです。頻繁に職場を変える人は、相性の問題や不運が重なるケースも考えられますが、困難に直面すると逃避しやすいといった傾向が少なからずあるように見受けられます。
企業風土や仕事の内容に対する期待と現実には、多少なりともギャップは出てくるものです。が、そこに対して学習せずにコロコロ職場を変えている可能性は大なり小なり考えられます。
人間関係で悩みやすい
職場の人間関係をうまく構築することが苦手な人は、悩んだ挙句、その環境を離れるケースがほとんどでしょう。これは、コミュニケーションスキルや協調性といった要素が顕著に関係します。対話する姿勢や感情のコントロールも含めて、面接選考時にしっかり見極めたいところです。
他責思考が強い
問題が発生したとき、その原因を他人や環境に求める「他責思考」が強い人は、自己成長の機会を逃しやすく、結果として仕事が行き詰まりやすくなります。自分自身の行動を見直すことが少ないがゆえに、同じような問題を繰り返してしまいがちです。
真面目過ぎる
「真面目過ぎる」ことは決して悪い特徴ではありません。が、過度に完璧を求めるあまり、ストレスが溜まりやすく、バーンアウトする可能性も考えられます。高い基準を自分に課し続ける人の転職理由にそうした背景が見え隠れするようなら、注意が必要です。
こだわりが強い
こだわりを持つことも、当然、ポジティブに捉えてよいでしょう。しかし、自身の理想と現実のギャップに苦しみやすく、職場に適応できない人もなかにはいます。自分のやり方や価値観に固執し、他人の意見や新しい方法を受け入れることをしてこなかった人は、チームでの協働はやはり厳しいでしょう。長続きせず辞めてしまうのも、容易に頷けます。
野望・行動力がある
大きな野望や行動力を持つ人材は、頼もしい存在です。現状に満足せず、より高いレベルを目指して日々奮闘する姿は、既存の従業員に対してもお手本になるでしょう。が、彼・彼女らが果たしてどの職場でも機能するかというと、実はそうでもありません。こうした方々は、常に新しい挑戦を求め、自分のキャリアを積極的に切り開こうとするため、ある程度の経験を積んだなら別の環境に活躍の場を移そうとします。また、企業文化によっては和を乱すリスクも考えられ、一筋縄でいかないのが現実です。
要注意!仕事を辞める人に見られる前兆

仕事を辞める決断は、多くの場合、突然下されるものではありません。そこには、いくつかの前兆が見られます。具体的には次のとおりです。
- 欠勤が増える
- 退社時間が早い
- 社内イベントに参加しなくなる
- 会話が減る
- 仕事が雑になる
- 新規プロジェクトに対して消極的
- タスク整理に着手している
- 辞める人に対して敏感に反応する
これらを早期に察知することで、貴重な人材の流出が防げるかもしれません。以下、それぞれ詳述します。
欠勤が増える
欠勤が急に増え始めた従業員には注意が必要です。現在の職場に不満を抱き、辞める準備を進めているサインかもしれません。仕事に対するモチベーション低下のあらわれ、あるいは他社の採用選考を受けている可能性があります。
退社時間が早い
以前と比べて早く退社する場合も警戒が必要です。これまで残業時間が長かった従業員がこの変化を見せた場合、心身のケアも当然考えられますが、仕事または職場に対する関心、モチベーションの低下を示唆している可能性もあります。
社内イベントに参加しなくなる
忘年会や社員旅行、そのほかのイベント等々、社内行事への参加を突然拒むようになった場合、企業への帰属意識に変化が生じているかもしれません。職場から距離を置くのはわかりやすい態度変容です。転職を視野に入れている可能性も考えられます。
会話が減る
これまで活発にコミュニケーションを取っていた従業員の口数が極端に減った場合も要注意です。モチベーション、帰属意識が薄れたのでしょうか。人間関係で何かしら問題があったのかもしれません。はたまた転職を考え、後ろめたさがそうさせた可能性もあります。
仕事が雑になる
これまでの丁寧な対応とは打って変わって急に仕事ぶりが雑になることも、辞める人の前兆としてよくあるケースです。そこには開き直りや無責任な姿勢がうかがえます。これは、離職を考えているからこその行動(原理)だといえます。
新規プロジェクトに対して消極的
長期的な視点が求められる新規プロジェクトへの参加を渋ったり、積極的に関わろうとしない姿勢が見られたりした場合、その従業員が近い将来の退職を考えている可能性があります。新規プロジェクトに対して消極的であることは、現在の職場に将来を見据えていないサインであり、転職を検討していることを示唆しています。
タスク整理に着手している
突然、長期的なプロジェクトの進捗状況をまとめたり、担当業務に関するフローや資料を作成したりするなど、必要以上にタスクの整理を行う様子が見られた場合、それは離職に向けた準備かもしれません。かつ通常業務を疎かにしていたなら、よりその可能性は高いと考えます。
辞める人に対して敏感に反応する
同僚や上司の退職に対して、強い関心を示したり、詳細な情報を求めたりする様子もまた、離職の前兆といえるかもしれません。そのように敏感になるのは、おそらく自身も退職を考えているからでしょう。と同時に、普段から職場の状況や将来に対して不安を抱いていることも、(そうした行動から)垣間見えます。
仕事を辞める人が表立って伝えないネガティブな理由

従業員が退職を決意する背景には、表面上は語られないネガティブな理由が隠れていることもあります。考えられるのは、たとえば次のとおりです。
- 自身への評価や待遇に不満があるから
- 嫌いな人間と仕事をするのが辛いから
- 勤務形態に融通が利かないから
- 日々の業務を非効率に感じているから
- 自社のレベルが低いと感じているから
以下、それぞれ詳述します。
自身への評価や待遇に不満があるから
多くの従業員は、自身の努力や成果が適切に評価されていないと感じると、モチベーションを失い退職を考え始めます。これは給与面だけでなく、昇進や権限の付与など、総合的な待遇に対する不満を含みます。しかし、こうした不満は直接的には伝えにくい方がほとんどです。そのため、従業員は(この不満を)心に抱えたまま辞めていきます。
嫌いな人間と仕事をするのが辛いから
職場の人間関係(特に直属の上司や頻繁に協働する同僚との関係)は、仕事の継続を左右する大きな要素です。しかし、これがこじれて辞めることになった場合、そのまま退職理由として表明するのは、ネガティブゆえに心理的に容易ではありません。結果、別の理由が建前上、告げられるわけです。
勤務形態に融通が利かないから
ワークライフバランスを重視する傾向は年々、目に見えて高まっています。そうなると、硬直的な勤務形態が従業員の不満を招きやすいことは当然です。特に、育児や介護といった家庭の事情を抱える従業員にとっては、柔軟なシフトで働けるかどうかが仕事を続けるカギを握ります。しかし、これは捉え方によっては勤務形態に対する不満です。したがって、そのまま伝えて角が立つぐらいなら自己都合で無難な理由を選ぶという人も、一定数いらっしゃるように考えます。
日々の業務を非効率に感じているから
業務プロセスの非効率さや、不要な会議の多さに不満を感じる従業員は少なくありません。このような職場環境は、従業員の時間とエネルギーを無駄に消耗させ、仕事への意欲を低下させます。しかし、これもまた退職理由にした場合、会社批判と捉えかねません。結局のところ、ありきたりな話をして穏便に済ませる従業員が多いように考えます。
自社のレベルが低いと感じているから
優秀な従業員ほど、自社の技術力や経営方針に対して高い目線を持っています。彼・彼女らは、会社の成長スピードや業界内でのポジション、そして同僚のスキル、成果に対して敏感です。一度懐疑的になると、不安が膨らみ転職を考えだすことも珍しくありません。しかしながら、いざ辞めるとなると、その理由として自社のレベルに言及することは憚られると思う方がほとんどでしょう。
長く貢献してくれた人が突然辞める理由
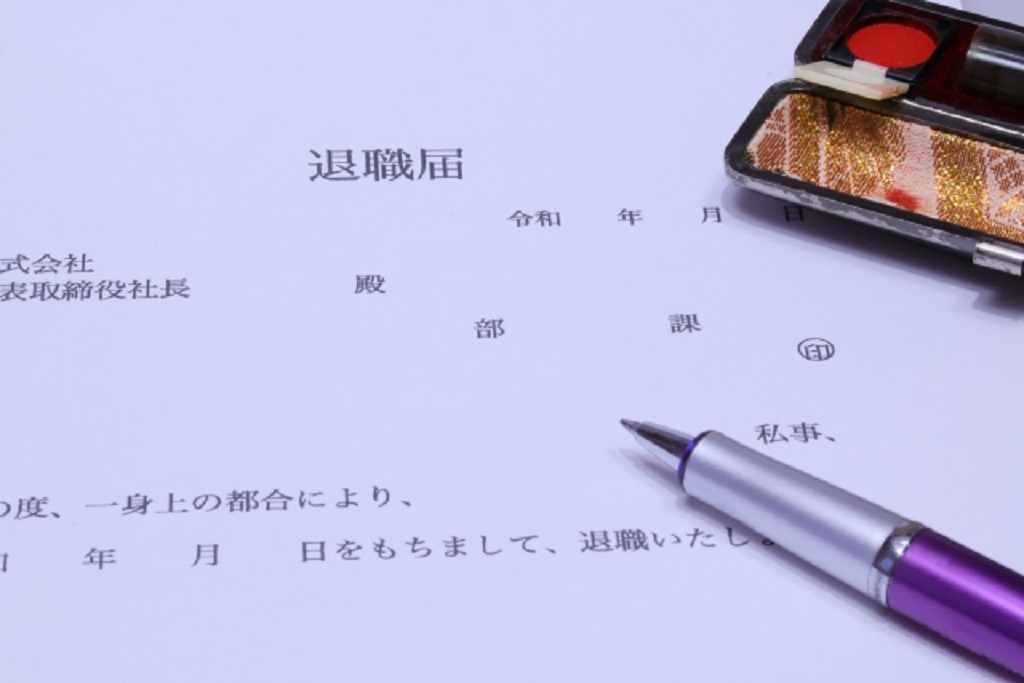
長年勤務してきた従業員から突然、退職の申し出があった際には、驚きと残念な思いでいっぱいでしょう。しかし、こうなることにも明確な理由はあります。決して、想定外の事態ではないのです。これを事前にケアすべく、長く貢献してきた人が突然辞める理由もしっかりと把握しておきましょう。具体的には次のとおりです。
- ライフステージの変化が会社の方針と合わなくなったから
- 会社の方針変更と自身の働き方が合わなくなったから
- 急な配置転換に納得いかなかったから
- 他社から魅力的なオファーを受けたから
以下、それぞれ詳述します。
ライフステージの変化が会社の方針と合わなくなったから
結婚、出産、介護……等々、従業員のライフステージの変化に対して、会社の制度や取り組み、方針が追いついていない企業も少なくありません。子育て中の従業員に対する支援制度や、柔軟にシフトを組める勤務体系などは最たる例でしょう。これらの整備がいつまでたっても進まなければ、長らく貢献してきた従業員であっても、しびれを切らして辞めることになるのは、至極自然だと考えます。
会社の方針変更と自身の働き方が合わなくなったから
前項とは逆に、会社の方針が変わることで辞められるケースもあります。組織の成長や市場の動向に伴い、方向転換が余儀なくされることは当然考えられます。しかし、長く働いてきたからこそ価値観や働き方にズレが生まれ離職に発展することも、決して珍しくはないのです。
急な配置転換に納得いかなかったから
組織の再編や業務の効率化を目的とした配置転換は、時として長年勤続してきた従業員の離職につながります。とりわけ、本人の希望や適性を考慮せずに行われた場合は、なおさら危険です。仮に引き留めることができたとしても、その理不尽さも相まって、モチベーションの低下や職場不適応を引き起こす可能性は高いでしょう。
他社から魅力的なオファーを受けたから
優秀な人材ほど、他社からの誘いを受けやすいものです。特に、長年の経験とスキルを持つ従業員に対しては、市場価値も高いゆえ、採用ターゲットとして同業他社がスカウトの目を光らせています。仮に他社のオファーが、現職以上の好待遇やチャレンジできる機会提供など魅力的な条件だった場合、(長らく愛着を持って働いてきた場所からそちらへ)気持ちが揺れるのも無理はないでしょう。
仕事を辞める前兆がみえないうちにやっておきたい対策
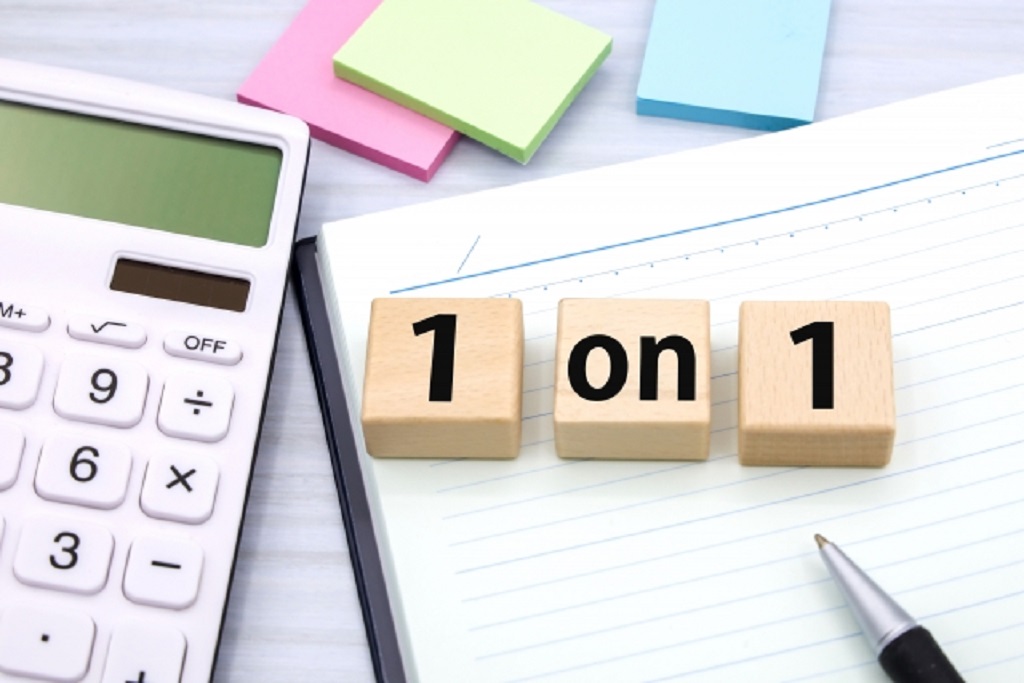
従業員の離職を防ぐには、前兆が現れる前から適切な対策を講じておくことが重要です。主に次のような取り組みが挙げられます。
- 従業員の本音を収集
- 定期的な1on1ミーティング
- メンタルヘルスサポート
- キャリアパスの明確化
- 外部研修も含めたスキルアップの機会
以下、それぞれ詳述します。
従業員の本音を収集
従業員の本音を把握しておくことは、離職を未然に防ぐうえで非常に大切です。先述のとおり、多くの従業員が直接的に不満を表明することを躊躇します。そのため、定着率改善に向けた取り組みも、本質とはずれてしまいがちです。
したがって、匿名のアンケート調査や第三者機関によるヒアリングなど、従業員が本音を語りやすい環境を整えることが求められます。加えて、定期的に自組織に対する満足度調査も実施できると望ましいでしょう。さらには、退職者に対する出口調査も貴重な情報源です。耳が痛いこともあるかもしれませんが、自組織への不信感を募らせないためには必要不可欠だと考えます。
定期的な1on1ミーティング
上司と部下が定期的に1対1で対話する機会を設けることは、従業員の不満や不安の早期発見に有効です。この場では、業務上の課題だけでなく、キャリアの展望や個人的な悩みについても話し合えるとよいでしょう。
無論、1on1ミーティングの質を上げることも大切です。それには上司のコミュニケーションスキルがカギを握ります。傾聴力や共感力を高めるための研修を実施するなど、管理職の育成にも注力していくことが必要です。
メンタルヘルスサポート
メンタルヘルスの重要性が年々高まるなか、サポート体制を整えることは、離職防止に不可欠だといえます。ストレスチェックの実施や、産業医との面談機会の提供、外部のカウンセリングサービスの導入など、できることは積極的に取り入れましょう。あまねく人は感情で動く生き物です。メンタルヘルスケアを徹底する企業文化が醸成できれば、不満や不安の火種を生まずに済む期待が持てます。
キャリアパスの明確化
自社でのキャリアパスが曖昧なことに不安を覚える方は思いのほか多くいるものです。これを未然に解消できていれば、入社してから早い段階で転職を考えることもないでしょう。
具体的には、各職位や職種ごとのキャリアパスを明確に示すだけでなく、定期的にキャリア面談も実施し、各人の希望や適性に合わせたキャリア形成支援を行えるのが望ましいと考えます。それによって従業員は自身の将来像を描きやすく、長きにわたって働く気持ちが生まれてくるはずです。
外部研修も含めたスキルアップの機会
キャリアパスの明確化と同様に、スキルアップの機会を求める従業員も少なくありません。彼・彼女らの成長意欲に応えることは、モチベーション向上につながり、離職へと心が揺れるきっかけを未然に潰す効果をもたらします。学びの機会を通じて、帰属意識を高められるはずです。
なお、研修は社内に終始するだけでなく、外部のセミナーや資格取得支援など、できる限り多様なスキルアップの機会を提供できるとよいでしょう。
仕事を辞める前兆が見えてからの対処法

前兆が見えてからでも、退職を思いとどまらせることは可能です。無論、適切に対処する必要があります。主な方法としては、次のとおりです。
- 早期のヒアリング
- 昇給、再評価
- 求める成果の再考
- 割り当てる業務の再考
- キャリアパスの再構築を提案
- 職場環境の再整備
以下、それぞれ詳述します。
早期のヒアリング
退職の兆候が見られた場合、まずは該当する従業員と対話の機会を設けましょう。このとき、高圧的な態度はご法度です。あくまでも従業員の話に耳を傾ける(傾聴する)ことを念頭においてください。そこから、不満や悩みの根本原因を探ることに注力します。その背景にこそ本質的な問題があるはずです。それらを把握したうえで改善を図っていきます。
昇給、再評価
給与面での不満が退職の理由である場合、適切な昇給や待遇の見直しを検討する必要があります。もちろん、単に給与を上げるだけでなく、従業員の貢献度や市場価値を適切に評価し、(ほかの従業員から不満を持たれないためにも)公平性を保つことも大切です。一方で、給与アップが難しいこともあるでしょう。そのときは金銭的な報酬に固執せず、(できる範囲で)新たな責任や権限の付与、称賛・感謝を表明してください。それなりに効果があると考えます。いずれにしても、モチベーションの回復が図るべく、従業員の努力や成果を正当に評価し、それを明確に伝えることが大事です。
求める成果の再考
退職を考えている従業員に対して、これまでとは異なる視点で成果を評価することも一つの方法です。たとえば、短期的な数値目標だけでなく、長期的な視点での貢献度やチームへの影響力なども評価の対象とすることで、その従業員も自身の新たな可能性を見出してくれるかもしれません。それを承認してあげることで、従業員は気持ちの面でもリスタートでき、以前のように頑張ってくれる期待が持てます。
割り当てる業務の再考
現在の業務内容が従業員の適性や希望と合っていない場合、業務の割り当てを再検討した方がよいかもしれません。その従業員の強みを生かせる新たなプロジェクトへの配置、方や負担の大きい業務は減らしてあげるなど柔軟な対応を取ることで、モチベーションの回復を図れるでしょう。
キャリアパスの再構築を提案
長期的な視点でのキャリア形成に不安を感じている従業員に対しては、一度、キャリアパスをリセットすることも効果的です。最たる例では、スペシャリストかゼネラリストか、今後の方向性を選び直すことなどが挙げられます。あるいは管理職への登用や新規事業への参画なども、まさに心機一転で、ポジティブな気持ちを引き起こすのに役立つはずです。
職場環境の再整備
人間関係や職場の雰囲気に問題がある場合、離職を考えている方が潜在的に多くいる可能性が考えられます。そうなると、職場環境の改善は急務です。コミュニケーションを活性化するためのチームビルディングの実施やワークショップの開催など職場全体で取り組む必要があるでしょう。
すぐに仕事を辞める人を採用してしまわないためのコツ

優秀な人材を確保し、長期的に活躍してもらうためには、採用段階から慎重に選考を行うことが大事です。具体的には、次のようなアクションが必要でしょう。
- 採用目的と人材要件を明確にして求人を出す
- 求人では動画などを通じてなるべくリアルな様子を伝える
- 面接時は応募者の本音を引き出せるようにする
- 事前に職場見学などを実施する
- 試用期間中に特徴を見極める
いわば、これらは定着率向上のコツです。以下、それぞれ詳述します。
採用目的と人材要件を明確にして求人を出す
まずは採用目的、そして募集するポジションに求める役割と責任、必要なスキルや経験を明確に定義することが重要です。これにより、応募する段階から、求職者が自身に合った職場かどうかを判断しやすくなり、ミスマッチを減らすことができます。したがって、求人票には募集に至った背景、具体的な業務内容、求める人物像……等々、詳細に記載しましょう。入社後のキャリアパスについても言及できるとなお望ましいと考えます。
求人では動画などを通じてなるべくリアルな様子を伝える
職場の雰囲気や実際の業務の様子をあらかじめ知ってもらうこともミスマッチ防止につながります。その際、ポイントは、テキスト情報だけで伝えないことです。写真そして可能であれば動画も使えると、見る人にリアルな職場のイメージを持ってもらいやすいでしょう。コンテンツも、従業員へのインタビューや業務の流れをタイムテーブルにして紹介するなど工夫を凝らすことで、入社後のギャップ軽減が図れます。
面接時は応募者の本音を引き出せるようにする
面接では、経歴やスキルの確認だけでなく、応募者の価値観や仕事に対する姿勢、長期的なキャリアビジョンなどを深掘りすることが重要です。オープンエンドな質問を多用し、応募者の本音を引き出していきましょう。なお、よくある質問としては「理想の職場環境はどのようなものですか?」「これまでの職場でもっとも困難だった経験は何ですか?それにどう対処しましたか?」などが挙げられます。応募者の適性や潜在的な離職リスクを評価するのに、ぜひお役立てください。
事前に職場見学などを実施する
可能であれば、内定前に職場見学や半日体験などの機会を設けることをおすすめします。実際の職場環境や雰囲気を体感することで、応募者はより現実的な判断を下せるはずです。一緒に働くメンバーやチームとの相性も確認できるように計画を組めれば、なおよろしいかと考えます。
試用期間中に特徴を見極める
新入社員の適性や能力を見極めるには、試用期間を有効に活用することも大事です。期間中は適宜、フィードバックを行い、双方向のコミュニケーションを密に取れるとよいでしょう。その際、気になる点があれば、早めに指摘し改善の機会を与えることで、本採用後の離職リスクを軽減できるかもしれません。もちろん、新入社員の声を企業側が受け入れる姿勢も大切です。試用期間でなるべく多くの(問題解消など)収穫を得るべく、不安や疑問を気軽に相談できる環境は、事前に整えておきましょう。
仕事を辞めると申し出があった場合は?
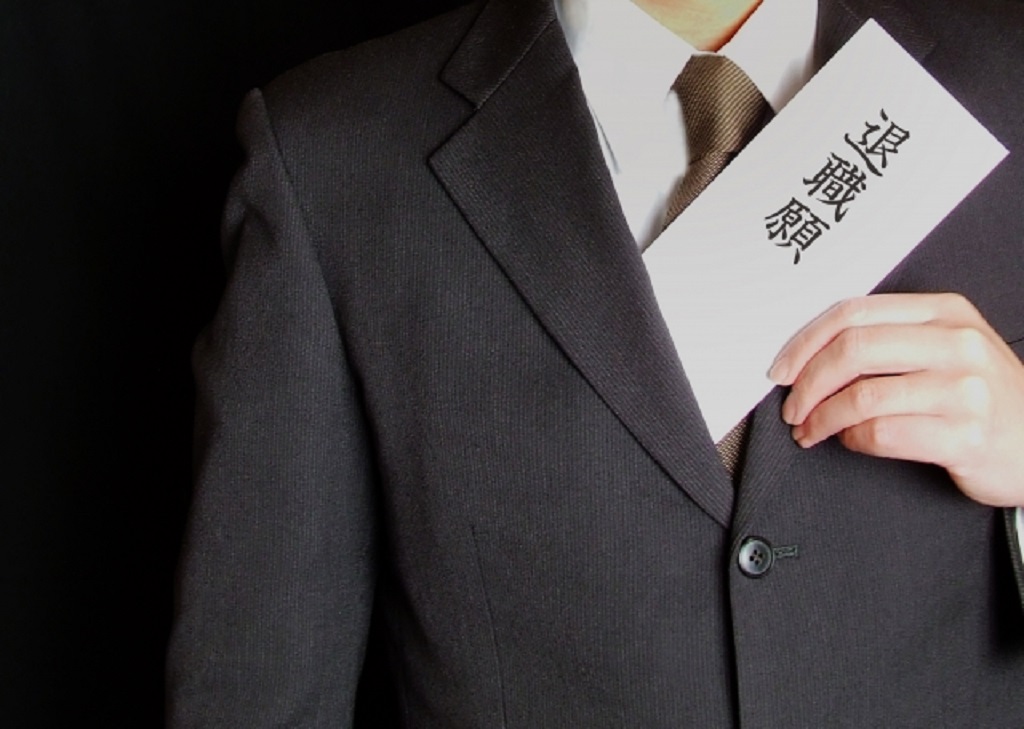
ここまで主に、あらかじめできることとして対策をお伝えしてきましたが、実際に従業員から退職の申し出があった場合にはどう対応するのがよいのでしょう。以下、望ましいアクションを具体的に列挙します。
- 辞めてほしくないことはしっかり伝える
- 悩みや不満に対して改善の余地があれば検討する
- 配置転換など代案を提示する
それぞれ詳述します。
辞めてほしくないことはしっかり伝える
まず、その従業員への普段の仕事ぶりに対する感謝、そして価値を認めたうえで、会社として引き続き貢献してほしい思いを率直に述べましょう。このとき、感情的になってはいけません。冷静に対話を進めることはもちろん、退職しようと思った経緯について話しやすい雰囲気づくりも大切です。そのうえでこちらからは、従業員のこれまでの貢献や今後期待される役割について具体的に伝えます。思いとどまってくれるのが理想ですが、(印象悪化につながるため)くれぐれも無理に引き留めることのないよう気を付けましょう。
悩みや不満に対して改善の余地があれば検討する
退職理由として挙げられた問題点に対し、改善の余地がある場合は、具体的な対策を提案しましょう。たとえば、給与面での不満であれば昇給を、業務内容に対する不満であれば担当業務の変更を、可能性があるなら伝えてみてください。ただし、安易に条件を飲むことは避けるべきです。会社全体のことを考えたうえで、柔軟な対応が求められます。
配置転換など代案を提示する
前項の内容とも重なりますが、現在の部署や職務に問題がある場合、配置転換や職務変更などの代替案を提示することも有効です。部署あるいは拠点異動、新規プロジェクトへの抜擢など、その従業員が求めていることで、かつ組織にとっても有益なのであれば、(代替案の提示に)躊躇することもないでしょう。実際に、適性や希望に合わせた新たなチャレンジの機会を提案することで、モチベーションの回復を図ることができるかもしれません。
なお、こうした提案・交渉を行う際は、単なる引き止めではなく、その従業員にとってもメリットがある話だと伝えるのがポイントです(考え直してもらうのに納得が得やすいと思われます)。
仕事を辞める人の特徴・前兆にすぐ気付けるかが定着率向上の鍵!

従業員の離職は、単に人材の損失だけでなく、残されたスタッフのモチベーション低下や、採用・育成コストの増加など、企業にとって大きな影響をもたらします。そのため、早期に離職リスクを察知しなければなりません。もちろん、そのうえで適切な対策を講じることが必要です。
また、求人募集においてもテコ入れできる余地は大いにあるでしょう。たとえば、価値や求める要件は、自社の特性(今後変革していくのであればそこも加味して)に応じて定めることが大切です。天井知らずに優秀な方を追い求めても、人材確保どころか人材獲得にすらつながらないでしょう。ゆえにミスマッチのない採用も求められます。そのうえで、期待に応える組織づくりが肝心です。特徴・前兆にすぐ気付けるかどうかは、どうしたって定着率向上の鍵だといえます。
仕事を辞める人の特徴や前兆に気を配ることは、すなわち従業員とのコミュニケーション強化です。日頃からこれを大切にすることで、多くの離職を未然に防げる期待が持てます。そしていつか、愚直に組織の育成に励んだ先に、真の理想すなわち「特徴・前兆がない世界」を築けるときがくるかもしれません。
▶関連記事:突然またはすぐ辞める人(アルバイト含む)の特徴や対策方法を解説
▶関連記事:人がすぐ辞める職場の特徴とは?起き得る弊害、原因と対策にも言及!
求人掲載・採用業務のサポートや料金についてなど、ぜひ気軽にお問い合わせください。
また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談も無料で承っております!
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。
▶【公式】面接コボット – 応募者対応の自動化で面接管理が楽に!
┗求人サイトからの応募対応を自動化できるサービス。チャットボットを通じ、日程調整まで効率よく進めてくれます。
▶【公式】採用ページコボット – 費用・実績も紹介!採用サイト制作サービス
┗採用ページ作成サービス。求人まとめサイトとの自動連携や求人検索エンジンへの対応により外部集客を強化します。

