連続夜勤は違法?

連日の夜勤は法的に問題があるのでしょうか?
ずばり、法律上、可能です。もちろん、休日の付与や割増賃金などは労働基準法に沿って守らなければなりませんが、夜勤に関してもその点にさえ抵触しなければ、雇用する側が罰せられることはありません。
上記踏まえて制限はまったくないのでしょうか。強いていうならば、法定休日のルールで連勤は12日までと定められています。そのため、夜勤も12連勤が上限です。
ちなみに、夜勤から日勤あるいは日勤から夜勤をさせる場合はどうでしょう?
途中、休憩時間を挟むにせよ確かに労働時間は長くなってしまいます。が、違法には当たりません。なおこのとき、ポイントは始業開始時刻です。勤務時間が0時を跨がなければ法定労働時間(8時間)を超えた分の割増賃金が発生します(0時を超えると、一旦別日として扱われます)。
ちなみに上記について厳密には労働基準法で定めがなく、行政通達(※)で「一日とは午前0時から午後12時まで」と記載されています。これによって「深夜0時以降の夜勤でも始業した日付を労働日として扱う」わけです。
| (※)行政通達:昭和63年1月1日基発第一号 【一日は、午前〇時から午後一二時までのいわゆる曜日をいうものであり、継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取扱い、当該勤務は始業時間の属する日の労働として、当該日の「一日」の労働とするものである。】 |
なお、この通達の解釈をめぐって議論が勃発することは往々にしてあるといいます。さまざまな見解が飛び交うなか、社労士側はどのように対応するかというと、(国会でも論戦になるほどで、埒もあかないため)その会社が管轄している労基署の釈義を正に据えるようです。
求人掲載・採用業務のサポートについて知りたいことは、ぜひ気軽にお問い合わせください。
また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談なども無料で承っております!
▶サービスのご案内:【公式】バイトルPRO – 即戦力・専門職の人材募集に特化
連続夜勤の注意点
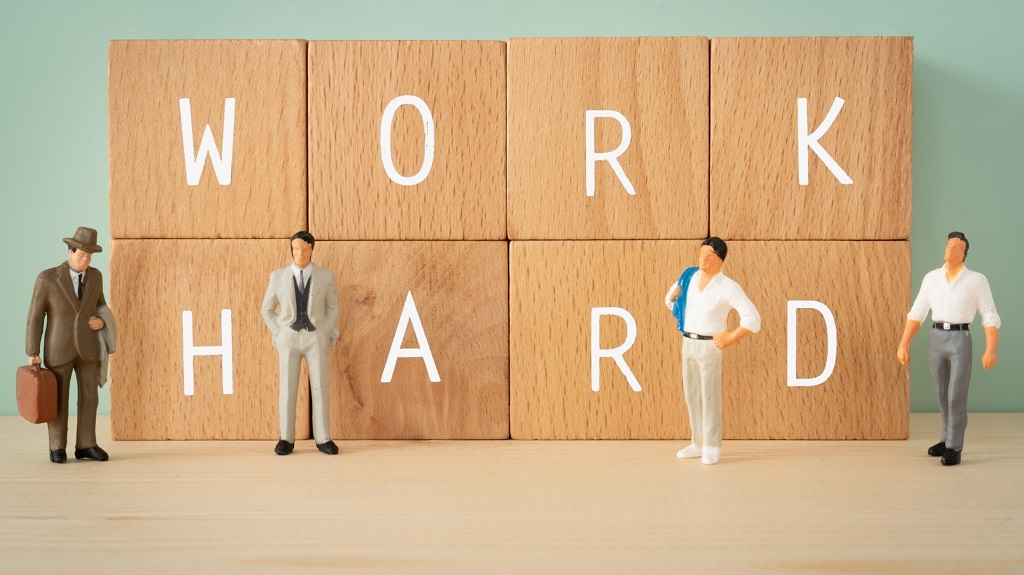
前項でも触れていますが、連勤が夜勤に限って制限されることはありません。しかし法律上、守るべきルールがあるのも事実です。それらについては、もちろん注意しなければなりません。以下、具体的に取り上げます。
法定休日の規定を再確認!
前述の通り、法定休日として従業員には1週間に1日もしくは4週間に4日の休みを与えることが労働基準法で定められています。夜勤に関わる部分では、明けた日を基本、休日として扱えないことも知っておきましょう。休日の条件は暦日です。すなわち午前0時から午後12時までの24時間が該当します。たとえば午前5時まで仕事をして、翌朝午前8時まで27時間休憩を取ったとしても、暦日と夜勤中の時間帯(0時~5時)が重なるため、この時点で公休のルールから外れてしまうのです。
▶関連記事:法定休日とは?所定休日(法定外休日)との違いや法改正による変更点など解説
しかし、企業が三交代勤務の制度を導入している場合は話が変わります。
三交代勤務とは1日24時間を8時間ずつ3つのグループ(日勤・準夜勤・夜勤など)に分ける働き方です。企業側でこうしたシフト制を敷くことによって夜勤明けからの24時間を休日として扱えます。ただしこれは、あくまで特例です。
割増賃金の規定を再確認!
労働基準法では1日8時間もしくは週40時間の勤務を法定労働時間として定めています。超えた時間に対して払うのが割増賃金です。また、午後10時から午前5時の深夜帯に働く場合にも発生します。両方重なった場合は、それぞれ掛かる計算です。
なお、以下の記事で詳細を確認できます。ぜひ、ご参照ください。
残業した際の賃金についてくわしくはこちら
▶アルバイトの労働時間について、上限など労働基準法に則り解説
深夜の割増賃金についてくわしくはこちら
▶アルバイトの深夜手当は何時から?計算方法は?法律を基に解説!
安全や健康面への配慮の徹底
従業員が安全かつ健康に働けるよう企業は徹底した配慮が必要です。大きくは作業環境と健康管理に気を配らなければなりません。
前者は、安全に作業できる労働環境の整備です。具体的には、機器のメンテナンスや設備の導入、従業員に対する指導・レクチャー(機械の操作方法など)が挙げられます。
一方で後者は、従業員の心身に不調をきたすことのないようマネジメントしなければなりません。その際、長時間労働の防止、健康診断の実施、メンタルヘルスのチェックや改善などの対策が考えられます。
夜勤の連続や次のシフトまでに十分な休息を取れない状況が常態化すると少なからず疲労は蓄積するものです。異変をすぐ察知できるよう普段から周囲を見渡せる体制づくりにも力を入れましょう。
36協定の締結と管理
従業員に時間外労働させる場合、または休日出勤させる場合、必ず従業員代表もしくは労働組合と「時間外・休日労働に関する協定」すなわち36協定を締結(その後労働基準監督署へ提出)する必要があります。ただし、36協定を結んでいても原則、月45時間、年360時間が上限です。また、1ヶ月の残業と休日出勤の合計は、100時間未満でなければなりません。夜勤においても当然、連日続いた場合にこのラインを超えてしまう恐れが出てきます。厳守すべく管理を怠らないよう目配りが不可欠です。
求人掲載・採用業務のサポートについて知りたいことは、ぜひ気軽にお問い合わせください。
また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談なども無料で承っております!
▶サービスのご案内:【公式】バイトルなら掲載料金プランを選んでアルバイト求人募集が可能
過度な連続夜勤が与える影響

連続夜勤が法律で認められているからといって、従業員に無理をさせてはいけません。それは、注意点でお伝えした内容はもちろん、表面的に見えにくい部分でも悪影響を及ぼす可能性が高いといえます。以下、労働者、企業、両者に与えるマイナス要素について整理します。
労働者に及ぼす影響
連続夜勤は、いうまでもなく身体への負担がかかります。たとえ体力に自信のある方でも、睡眠不足や疲れが溜まり、少なからず体力は削られていくでしょう。加えて、精神面でも、ストレスが蓄積されていくはずです。
いずれにせよ毎日、夜勤が続くようであればそれはもう過労だといえ、脳梗塞やくも膜下出血、心筋梗塞などを発症する可能性が出てきます。また、うつ病などの精神疾患を患うケースも珍しくありません。業務中にトラブルが起きることも容易に想定できます。居眠り運転などは最たる例です。このように、命の危険と隣り合わせだということは強く認識してしかるべきです。
企業に及ぼす影響
従業員を疲弊させることによって、企業の生産性もダウンします。集中力やモチベーションを低下させないためには、適度な休日、休憩は不可欠です。そのうえで万が一従業員の健康に著しい悪影響を及ぼし、労災が認められたなら、貴重な人員を書くだけでなく、多額の慰謝料を払う羽目にもなります。事故も同様です。損害賠償(の請求)が発生します。
過度な勤務はトラブルの温床です。ニュースになれば外部からの評判にも影響します。ひとたびブラック企業と思われてしまえば、汚名返上は簡単ではありません。したがって、無理のないシフトを組む、業務量を見直すなどの定期的なアクション、対策は必須だといえます。
人事業務を自動化・効率化するサービスなどもご用意できます。どうぞ気軽にお問い合わせください!
夜勤の連続に対する限度は今後も考えるべき命題

業種によっては夜勤なくして成立しない仕事も少なくありません。従業員にとっては割増賃金の支払いを加味すれば効率よく稼げるともいえます。しかしながら、働きやすさの観点ではどうでしょう?決して手放しで推奨できるものではないと思われます。たとえ一日だけの夜勤であっても、疲労の感じ具合は日勤のそれを上回るはずです。そして連続となると、肉体的にも精神的にもやはり苦しくなるのは否めません。働き方改革が進められている昨今、夜勤についても社会全体で改善に取り組むべきでしょう。そのうえで企業は限度を具体的にどう設けるかなど考えていく必要があります。同じく、従業員のパフォーマンスを保つべく、「定期健診の結果を十分に活用する」「適正なシフト管理を行う」「仮眠室を整備する」……等々あらゆる視点で対策を講じることも大切です。
【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所
代表 荒武 慎一
同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。

