介護のための短時間勤務制度等の措置とは

介護のための短時間勤務等の措置とは、家族のなかに要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態※、介護休業と同じ)の方がいる労働者が、所定労働時間の短縮等を申請できる制度です。ただし、労働者にせよ家族にせよ対象は限られます。また、利用できる期間や回数も同様です。以下、それぞれ説明します。
対象に当たる労働者
短時間勤務制度等の措置を利用できる労働者は、原則として要介護状態の家族を介護する日々雇用者を除くすべての男女が対象です。事業主は、彼・彼女らが希望すれば、利用できる短時間勤務制度その他の措置(短時間勤務制度等の措置)を講じなければなりません。ただし、勤続1年未満や週の所定労働日数が2日以下の労働者については、労使協定を締結している場合、対象外です。
対象家族
対象家族に含まれるのは、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。なお、介護関係の「子」の範囲は、法律上の親子関係がある子(養子含む)のみを指します。
利用期間と回数
対象家族一人につき、利用開始日から連続する3年以上の期間で2回以上適用することができます。介護の状況は長期化や変化を伴うことが多いため、分割取得により柔軟に対応できる仕組みです。そのため、3年まるまる利用することもあれば、介護休業を途中挟んで2回取得するケースも見られます。
措置が必要な制度
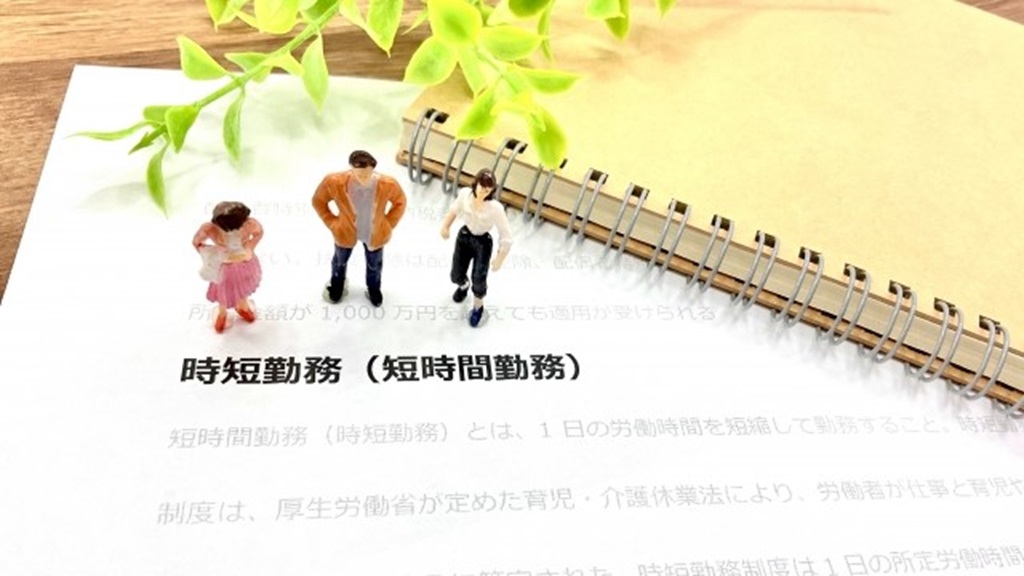
短時間勤務制度等の措置として、事業主は次のなかから一つ以上を設ける必要があります。
- 短時間勤務
- フレックスタイム
- 時差出勤
- 介護費用の助成
以下、それぞれ説明します。
短時間勤務
短時間勤務制度で所定労働時間を短縮する場合は、それぞれ日や週、月単位で調整ができるものとして扱われます。また、隔日勤務や、特定の曜日のみといったように日数も同様です。そのため事業主は、労働者が個々に勤務しない日や時間も請求されれば認めなければなりません。
フレックスタイム
フレックスタイム制度を設けた場合、1日の始業・終業時刻を労働者自身でずらす(出退勤時間を変動させる)ことができます。一定の清算期間内で所定労働時間を満たせばよいという考え方です。
時差出勤
時差出勤制度も、フレックスタイムと同様に通常の勤務時間帯をずらせるものです。大きく異なるのは、時差出勤では1日の所定労働時間を変更することはできません。あくまで、勤務する時間帯を前後にスライドする制度です。
介護費用の助成
介護費用の助成は、労働協約や就業規則のもと、企業が介護サービス利用料などの一部を負担することを指します。
企業にとって期待できる短時間勤務制度等のメリット

短時間勤務制度等の措置は、労働者の介護と仕事の両立を支援するものですが、企業側にも一定のポジティブな効果が見込めます。ざっとメリットを挙げると次のとおりです。
- 人材流出のリスク回避
- 人材採用で有効な打ち出し
- 企業イメージの向上
以下、それぞれ説明します。
人材流出のリスク回避
短時間勤務制度等の措置によって、介護の都合で労働者が仕方なく離職することを未然に防げる期待が持てます。なかにはスキルが高い人材でありながら、両立が図れないばっかりに辞められてしまった苦い経験のある事業主の方からすると、大きなメリットでしょう。定着につながれば再採用や育成にかかるコストを抑えることもできます。うまくいけば、社内のノウハウも継続的に蓄積され、生産性にも良い影響をもたらすはずです。
人材採用で有効な打ち出し
短時間勤務制度等の措置は、求人時に企業の柔軟性や働きやすさを具体的に示す材料になり得ます。特に中途採用市場では、仕事と家庭の両立を重視する求職者が案外多く、制度の有無が応募判断に影響することも決してないとは言い切れないでしょう。募集要項や採用ページ、面接時においてもうまく訴求できると有効な打ち出し、アピールになると考えます。そのほか広報・CSR活動の一部としても活用できるはずです。
企業イメージの向上
従業員のライフステージに配慮した働き方を提供する企業は、前述した働きやすさはもちろん、社会的責任を果たす組織としても外からのイメージアップにつながることがあります。短時間勤務制度等の措置、導入も例にもれず、認知されれば、企業としての社会的信用力に影響を与える期待が持てるはずです。
企業にとって懸念される短時間勤務制度等のデメリット

短時間勤務制度等の措置は、従業員の働きやすさ向上などのメリットが目立つ一方で、問題点として浮き彫りになる側面も無視できません。ざっとデメリットを挙げると次のとおりです。
- 業務負担の偏り
- シフト管理の煩雑化
- 生産性への影響
以下、それぞれ対策とセットで説明します。
業務負担の偏り
短時間勤務制度を導入することで、一人当たりの業務量が増える可能性があります。時短勤務者がいない時間、残されたメンバーに業務が集中すれば、疲労や不満が溜まっていくかもしれません。
これを回避する対策としては、業務の棚卸しと再分配が効果的です。各業務の優先度を再確認し、短時間勤務者には比較的重要なタスクを時間内で担当してもらうなど、フルタイム勤務者の業務量も含めて調整を図れるとよいでしょう。
シフト管理の煩雑化
短時間勤務制度等の措置は、各社員の勤務時間や出勤日数がバラバラになるため、シフト管理が難しくなる懸念も出てきます。
こうしたシフト管理の煩雑化を解決するには、勤怠管理システムの導入が有効です。特に、就業規則や法令に基づいた自動チェック(労働時間・休憩・残業など)を行う機能が付いていたり、勤務実績と予定の差異が管理できたりすると望ましいでしょう。
生産性への影響
短時間勤務制度等の措置によって、生み出せる量や磨ける質を減らしたり下げたりしないといけなくなることもあるでしょう。納期の遅延やチームでの連携不足が起きてしまうことも考えられます。
このような生産性への影響を極力抑えるには、業務の見直しや効率化は必須です。タスクの一部を自動化したり、定型業務は外注したりといった調整で、限られた時間でも成果が出せる体制を構築していく必要があります。
短時間勤務制度等の流れ

基本的に就業規則等の定めによるとはいえ、短時間勤務制度の適用を受けるための手続きには大まかな流れが存在します。ざっと各ステップを挙げると次のとおりです。
- 申請を受ける
- 短時間勤務の期間や労働条件について通知する
- 他の従業員の理解を得る
- 短時間勤務を実施する
以下、それぞれ説明します。
申請を受ける
まずは、従業員から「介護短時間勤務申請書」の提出を受けます。書式こそ任意とはいえ、取得する期間や実際の勤務時間などは必ず記載してもらいましょう。なお、申請期限は企業側でも決められますが、開始予定日の2週間前までが一般的です。
短時間勤務の期間や労働条件について通知する
申請内容の確認と社内調整が済んだ段階で、労働者に対して短時間勤務の期間および具体的な労働条件を文書で通知します。このとき、給与の変更についても曖昧にせず明確に伝えましょう。
他の従業員の理解を得る
短時間勤務制度は、職場全体の理解と協力が不可欠です。プライバシーの配慮は前提のうえ、制度利用者の勤務形態変更について関係者に説明します。「〇〇さんが短時間勤務になる」とだけ伝えるだけでなく、「チームとしてどう対応するか」という前向きな方向で話し合いを進めるのがメンバーのモチベーションを保つためには大切です。業務の分担についてもメンバーに負担を押し付けるのではなく、優先順位付けや不要なタスクの廃止など、一人ひとりが無理せずに済むことを意識しましょう。
短時間勤務を実施する
周知後は、実施に移行します。いざ始まったら終わりということではなく、問題なく適用できているか定期的な確認が大切です。特に初月は何が起きるかわかりません。その取り組みに慣れるまでは、組織全体、一人ひとりを細かくフォローできることが望ましいと考えます。
短時間勤務制度等で生じる労務管理についての注意点
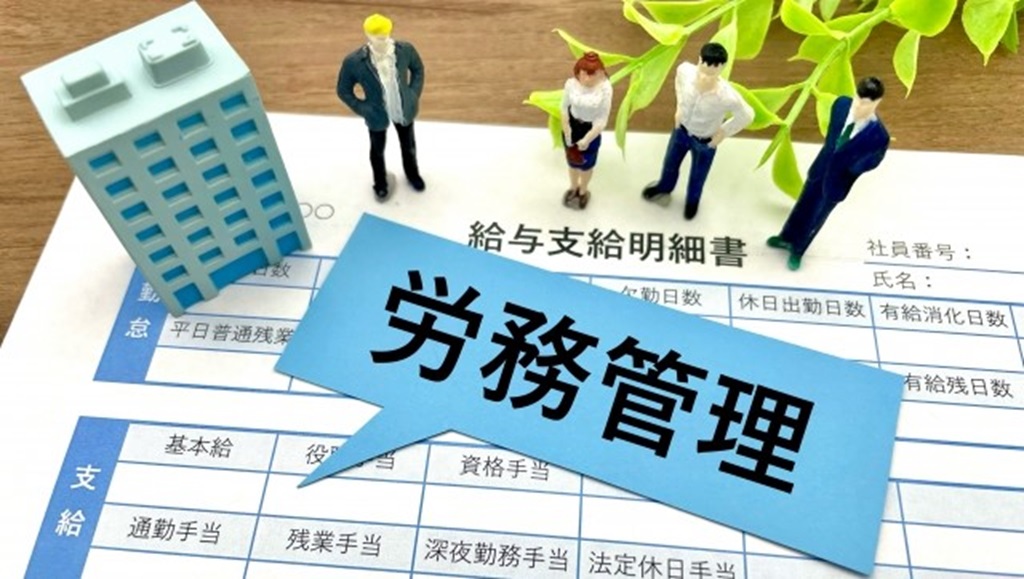
短時間勤務制度を導入する際は、労務管理にも細心の注意を払いましょう。ざっとポイントを挙げると次のとおりです。
- 有給休暇の扱い
- 賃金の扱い
- 社会保険の扱い
- 所定外労働の制限
- 時間外労働の制限
- 深夜業の制限
- 短時間勤務制度等の利用を理由にした不利益な取扱い
以下、それぞれ説明します。
有給休暇の扱い
短時間勤務者の年次有給休暇は、全労働日の8割以上出勤していれば、通常の従業員と同じように付与されます。このとき、労働者が取得を申請したときの労働時間が基準です(付与した時点ではありません)。
賃金の扱い
前述した有給休暇の取得時は賃金計算にも注意が必要です。これは取得申請時が基準になっているように短縮後の労働時間に換算されます。たとえば、6時間勤務の従業員が1日休暇を取得した場合は、賃金も6時間分というわけです。
そして基本給、加えて職務手当や精勤手当などの各種手当についてもそうですが、基本は就業規則に沿って支払います。特に歩合給や成果報酬制度を採用している場合、評価対象期間や業績目標への影響を考慮した調整が求められるため、事前に明確な基準を設けることが必要です。
社会保険の扱い
短時間勤務により支払う賃金が下がった場合は、社会保険料の負担額が変更できます。その際、申請が必要です。具体的には、事業主が「月額変更届」を日本年金機構へ提出することが求められます。なお、保険料の適正化とあわせて年金についても標準報酬月額が下がることによる変更が可能です(「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」)。このときも事業主は手続きが求められます(日本年金機構に「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出します)。
所定外労働の制限
短時間勤務制度の利用者は、原則として所定労働時間を超える労働を拒否できる権利があります。そのため、該当する従業員に業務都合で所定外労働を命じることはできません。それでも突発的な対応が生じることはあるでしょう。だからこそ、普段から皆でカバーする体制づくりが必要なのです。
時間外労働の制限
要介護状態の家族がいる従業員には、時間外労働を月24時間、年150時間を超えて行わせることはできません。なお、この制限は「36協定」で定めた時間外労働の上限とは別に適用されているものです。
そもそも、時間外労働の依頼は強制であってもいけません。あくまで従業員の同意が前提です。介護と仕事の両立支援の観点からも、時間外労働はできるだけ発生させない工夫が求められます。
深夜業の制限
育児・介護休業法では、介護中の従業員を深夜(午後10時から午前5時まで)に労働させてはならないと定められています。深夜業制限は介護の状況が継続する限り適用されます。
短時間勤務制度等の利用を理由にした不利益な取扱い
短時間勤務制度等の利用を理由とした従業員への不利益な取扱いは法律で明確に禁止されています。不利益な取扱いの例としては以下のような行為です。
- 解雇
- 降格
- 不当な配置転換
- 賞与や昇給における差別的取扱い
- 人事評価における低評価など
いうまでもなく、企業は制度利用者に対して公平な評価を行い、キャリア形成の機会を奪わないように配慮しなければなりません。また、短時間勤務者に対するハラスメントも信じ難いことに決してないわけではなく、組織全体で徹底して防止に取り組む必要があります。
短時間勤務制度等に伴う人員調整におすすめのサービス

短時間勤務制度等の措置を行った場合、人員配置や業務分担の見直しを余儀なくされることもあるでしょう。先述した業務負担の偏りや生産性への影響を抑える手段としてもやはり、人員補強を視野に入れることは必要です。そこで手っ取り早い方法として求人サービスの活用が挙げられます。
もちろん、状況に応じて適切なものは区々です。ただ組み合わせも含めて選択肢が広がれば安定的な人材確保が期待できます。おすすめしたいのはずばりdipが提供する採用支援サービスです。
▶【公式】求人広告を掲載、採用業務を支援-dip(ディップ)
CMや広告などでも認知度が高い『バイトル』。今話題のスポットワーカーに特化した『スポットバイトル』。正社員・契約社員の採用に強い『バイトルNEXT』。有資格者や業界経験者が集まる『バイトルPRO』。社員・派遣・パートと幅広く求職者と接点が持てる総合求人情報サイト『はたらこねっと』。DXで労働力不足を解消したくとも資金・運用面で導入が難しかった中小企業向けに開発された『コボット』。
これらを駆使して採用を強化できたなら短期間勤務制度等の措置もひとまず安心して行えるはずです。
短時間勤務制度等の措置は企業側にとっても安心要素

短時間勤務制度等の措置は、家族の介護を抱える従業員が心身の負担を軽減しながら、仕事と両立できるように設けられた制度です。企業側もうまく活用することで、人員確保はもちろん、スキルや経験値が高い人材の流出を減らせる期待が持てるでしょう。安易な離職を防げるなら制度自体が安心要素といっても過言ではありません。もちろん、拙稿でもお伝えしたデメリットや注意点を念頭におくことは必要です。そのうえで、短時間勤務制度はじめ従業員の働きやすさをサポートすることを、単なる義務と捉えるのではなく、組織の継続的な成長につなげてほしいと考えます。前述した求人サービスも後ろ盾になってくれるはずです。
求人掲載・採用業務のサポートや料金についてなど、ぜひ気軽にお問い合わせください。
また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談も無料で承っております!
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【公式】空いた時間のスポットワーカー募集ならスポットバイトル
┗空いた時間で「働きたい」と「働いてほしい」をつなぐ求人マッチングサービス。求人は無料で掲載できます。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。
▶【公式】面接コボット – 応募者対応の自動化で面接管理が楽に!
┗求人サイトからの応募対応を自動化できるサービス。チャットボットを通じ、日程調整まで効率よく進めてくれます。
▶【公式】採用ページコボット – 費用・実績も紹介!採用サイト制作サービス
┗採用ページ作成サービス。求人まとめサイトとの自動連携や求人検索エンジンへの対応により外部集客を強化します。

