パパ・ママ育休プラス制度の概要ならびに取得条件

パパ・ママ育休プラス制度は、文字どおり、母親だけでなく父親も育休を取得するよう促す制度です。まずは基本概要から説明しましょう。
パパ・ママ育休プラスの基本概要
パパ・ママ育休プラスは、夫婦が協力して育児を行うことを目的に、2010年のタイミングでスタートしました。
通常の育休では、子どもが1歳の誕生日を迎える前日までが期日ですが、パパ・ママ育休プラスの場合は条件次第で、そこから2ヶ月先の日まで選択できます。つまり、期間こそ1年ですが、子どもが1歳2ヶ月になるまでのあいだで育児休暇を取れるわけです。そして、母親の場合は産後8週間の産後休業を含みます。
また、1歳2ヶ月の育休が終わるタイミングで待機児童になったなど、止むを得ない事情に見舞われた際は、認可が下りれば通常の育休制度がそうであったように、パパ・ママ育休プラスでも延長が可能です(最長で子どもが2歳になるまで)。
パパ・ママ育休プラスの取得条件
パパ・ママ育休プラスの取得にはいくつかの条件があります。
具体的には次のとおりです。
- 夫婦ともに育児休業を取得すること
- 配偶者が子どもの1歳の誕生日前日までに育児休業を取得していること
- 育児休業開始予定日が子どもの1歳の誕生日より前であること
- パパ・ママ育休プラス取得者の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業開始の初日以降であること
取得中は、本人も企業もともに社会保険料が免除されます。このとき、企業側の手続きが必要です。企業側は、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を管轄の年金事務所と健康組合に不備なく提出しましょう。
また、本人たちはパパ・ママ育休プラスの取得中、(通常の育休同様)育児休業給付金を受け取ることが可能です。その額は、ひと月の給与に対して育休開始日から180日間は67%、181日目から支給終了日までは50%で算出されます。
パパ・ママ育休プラスを社員に取ってもらうことで得られるメリット

パパ・ママ育休プラスは取得者にはもちろん、自社の従業員にこの制度を取得してもらうことで企業側もさまざまなメリットを得られます。
以下、いくつか列挙します。
企業イメージの向上
パパ・ママ育休プラスを従業員が取得している事実は、子育てを会社として積極的に応援していることを指します。これは少なからず周囲あるいは外部の人間に対しても好印象を与えるでしょう。
また、厚生労働省は、仕事と育児・介護の両立が可能な体制を構築している企業を「ファミリー・フレンドリー企業」として表彰する取り組みを実施しています。イメージアップを図るのであれば、やはり選ばれたいところです。
離職率の低下
育児が大変なことを理由に離職される方は少なくありません。だからこそ、夫婦で取れて柔軟に活用できるパパママ育休プラスは、貴重な制度です。働きやすい環境を従業員に提供するのに使わない手はないといえます。
子育て時間を確保でき、余裕をもって仕事にも取り組められる従業員を増やせば、生産性、そしてモチベーションも高まるでしょう。結果、会社に対する満足度や幸福度にもつながってくるはずです。これらを上げられれば、離職率の低下も大いに期待できます。
パパ・ママ育休プラスと混同しやすい産後パパ育休について

パパ・ママ育休プラスと似て非なる制度に産後パパ育休があります。人事担当者であれば、混同しやすいとはいえ、両者を確実に区別できるようにしましょう。
さて、産後パパ育休は、2022年10月に創設された育休制度です。父親の育児取得促進の一環として、さかのぼること2021年6月に改正された育児・介護休業法から頻度高く更新を経て現状にいたります。
一応、正式名称は「出生時育児休業」です。子どもの出生後8週間以内に取得する点から、男性版の産休ともいわれています。
また、産後パパ育休の場合、(育休を)2回に分けて取得することも可能です。
通常の育休は1人の子どもにつき1回が原則でした。そのため、夫婦で分割すれば子どもが1歳になるまでに合計4回も取得できます。このように柔軟な制度が設けられていることは、確実に父親の育休取得に寄与しているといえるでしょう。
そのほか取得条件については、原則として2週間前までに申し出る必要があります。加えて、労使協定を締結している場合、上限こそありますが、休業中の就業も可能です。
なお、こちらの記事でもくわしく解説しています。ぜひ、ご参照ください。
▶関連記事:パパ休暇が廃止!産後パパ育休って?違いもあわせて解説
給付金などパパ・ママ育休プラスで人事が知っておきたいポイント
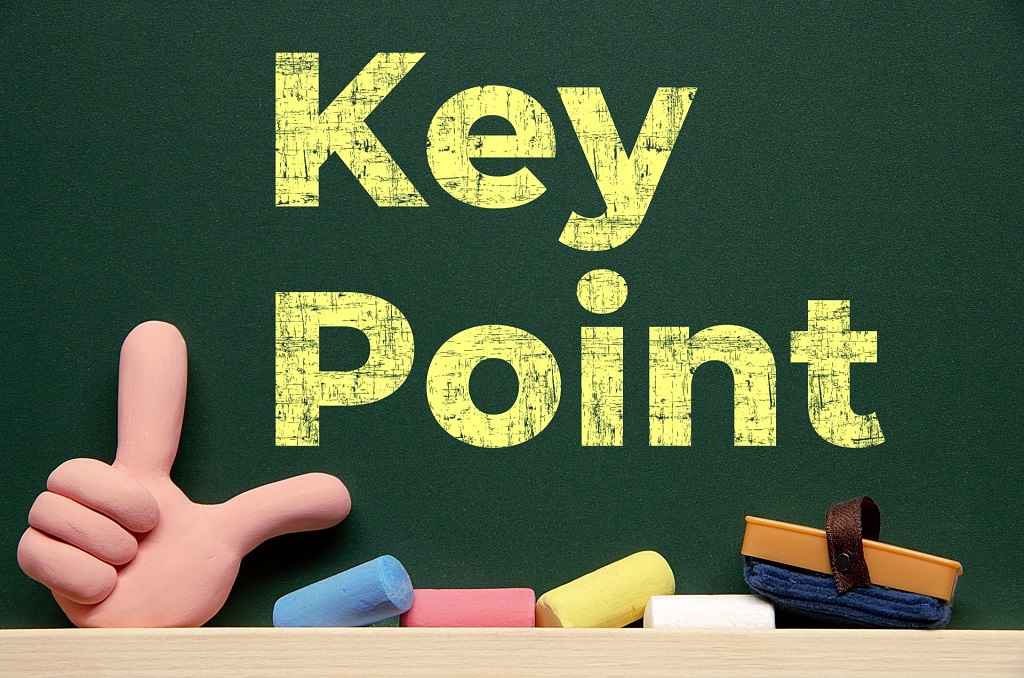
育休制度の活用により、社員のモチベーションアップや企業のイメージアップを図れることは前述のとおりです。加えて、給付金や助成金についても知っておくと、育休導入に対してなおさら積極的になれるかもしれません。以下、おさえておきたいポイントを紹介します。
育児休業給付金で会社の負担が軽減
育休取得者が雇用保険に加入しており、かつ一定の要件を満たしている場合は「育児休業給付金」が支給されます。この給付金は雇用保険から賄われるため、企業側が負担することはありません。
助成金がもらえる
育休取得に関する助成金はバリエーションも豊富です。中身も充実し、特に中小企業に手厚い点など、知っておいて損はないでしょう。これらのお膳立てのもと、自社内でもパパ・ママ育休制度を推奨しやすくなっているといえます。
両立支援等助成金・出生時両立支援コース
両立支援等助成金・出生時両立支援コースは、育休を取得しやすい職場の風土づくりを推進、重視している制度です。男性労働者に育休を利用させることで一定額の助成金が支給されます。
両立支援等助成金・育児休業等支援コース
両立支援等助成金・育児休業等支援コースは、育休取得や職場復帰を支援する取り組みを行った企業に助成金が支給される制度です。
それぞれのシチュエーションにおいて支給要件は変わります。
育休取得時・職場復帰時
育休復帰支援プランに沿って、円滑な育休取得・職場復帰に取り組んだ企業に支給されます。
代替要員確保時
育休取得者に代わる労働者を確保し、かつ育休取得者を原職に復帰させた企業に支給されます。
職場復帰後支援に該当
育休から復帰した労働者支援のための取り組み(制度導入など)に対して利用者が生まれた企業に支給されます。
新型コロナウイルス感染症対応特例に該当
小学校の臨時休業などで子どもの世話が必要になると、親はどうしても仕事を休まざるをえません。そうした労働者のために整備した有給休暇制度や両立支援制度に対して、利用者が生まれた企業に支給されます。
働くパパママ育休取得応援奨励金
上記2つのコースは国の制度でしたが、働くパパ・ママ育休取得応援奨励金については、東京都によるものです。
都内の企業を対象に「働くママコース」と「働くパパコース」があります。所定の要件を満たすことで助成金が支給される仕組みです。
働くママコース
1年以上の育休から、復帰後3ヶ月以上継続して雇用されている従業員がいる企業に対して、次の2つの取り組みを実施している場合に奨励金が支給されます。
- 育児・介護休業法の範疇を上回る取り組みを就業規則に定めていること
- 育休中の従業員に対して、復帰支援の面談を1回以上実施および復帰に向けた社内情報・資料を定期的に提供していること
働くパパコース
連続15日以上の育休を取得し、原職に復帰後3ヶ月以上継続して雇用されている男性従業員がいる企業に対して奨励金が支給されます。
従業員数は問われず、企業規模に関係ないコースです。
パパ・ママ育休プラスは企業にとってもプラス!

パパ・ママ育休プラスはじめ育休制度を従業員にうまく活用してもらうことで、今後はますます、企業の価値も向上していくのではないかと考える次第です。
もちろん、貴重な戦力が抜けた穴を埋める必要はあります。そこでおすすめしたいのが、求人広告の掲載や採用業務を支援するdipのサービスです。バイトルシリーズやはたらこねっとなど従業員を新たに雇いたい方はぜひ、導入をご検討ください。
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。
【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所
代表 荒武 慎一
同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。

