社会保険とは何か?簡単におさらい

社会保険は公的な保険制度のひとつです。日本に住む20歳以上の人は国民年金や医療保険などに加入するわけですが、これらが社会保険に該当します。
とりわけ健康保険と厚生年金保険は主要な項目といえるでしょう。前者を適用すると、病院で健康保険証を提示することで自己負担額が少なく受けられます。一方で後者は、老後に受け取れる年金のための保険です。
いずれも安心して生きていくためには欠かせません。
加入できる年齢については、健康保険の場合、最長74歳(75歳以降は後期高齢者医療制度に移行)です。また、厚生年金保険は最長70歳までに制限されています。
代表取締役や役員も含めて、正社員は全員、社会保険に加入します。と、現在は冒頭でも述べたとおり、一定の条件を満たせばアルバイト・パートも社会保険の加入が義務化されている状況です。
以上、ひとまずおさえておきたい社会保険に関する基礎知識を紹介しました。
次章より、アルバイト・パートに特化し詳細を紐解きます。
加入の義務化が進むアルバイトの社会保険

2022年10月からの法改正により、一部のアルバイトやパートの方に対しては社会保険の加入が義務化されました。以前までは従業員数501人以上の企業が対象だったところ、このタイミングで101人以上に変更されています。そして2024年10月。対象範囲は広がり、51人以上の企業が適用されます(この条件によって、加入対象者は約20万人増えるといわれています)。
参照: 被用者保険の適用拡大
この背景には、少子高齢化による高齢者の割合増加があります。年金制度の運営は現役世代が納めた保険料が原資になっているため、いうなれば適用範囲を拡大せざるを得ないのです。
もちろん、変化に対して各人思うところはあるでしょう。
たとえばアルバイトやパートからすると負担額の軽減や将来もらえる年金の増加につながるため、好都合だといえます。他方、企業にとっては標準報酬月額に基づいた毎月の保険料の徴収など管理範囲が広がるため、やや煩わしい印象を覚えているかもしれません。
そしてこの流れは、今後もさらに続きます。任意とはいえ労使合意に基づく場合は50人以下でも適用される予定です。と、そもそも要件自体を外す方向に議論は進んでいます。厚生労働省の被用者保険に関する有識者懇談会がまとめた論点整理では、(会社員らが加入する)厚生年金を適用し、老後の所得保障を厚くする狙いがあるようです。
参照:働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会議論の取りまとめ(案)
各所、影響を及ぼすことは容易に想像できます。引き続き、追跡していく必要があるでしょう。
アルバイトの具体的な社会保険加入条件

アルバイト・パートの社会保険加入条件は、勤務時間や日数、企業規模、賃金などによって定められています。従業員が以下に示すいずれかの条件に該当する場合は、社会保険に加入させなければなりません。義務であるゆえ、しっかりと把握しておきましょう。
勤務時間や日数が正社員の4分の3以上
アルバイト・パートが勤務する時間あるいは日数がフルタイム勤務の正社員(常時雇用者)のそれに対して4分の3以上の場合、企業側はその従業員を社会保険に加入させる義務があります。この条件は、社会保険完備の企業であれば、会社の規模や年収額、学生または社会人といった属性を問わず(加入が)必要です。
満たすべき5ヶ条
アルバイト・パートが以下の条件を満たした場合も、社会保険の加入は必要です。
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 月額賃金が8.8万円以上(年約106万以上)
- 2ヶ月を超えて雇用の見込みがある
- 学生ではない
- (2024年10月からは)厚生年金の被保険者数が51人以上の企業 ※2024年9月までは101人以上
認識に齟齬が生じやすい従業員数の定義
従業員数は、その企業が雇っている労働者の数ではなく、あくまで厚生年金の被保険者(正社員やフルタイムに対して4分の3以上働くアルバイト・パートなど)の数で算出します。
気を付けたいのは、短期間に人が入れ替わっていく雇用体制の場合です。当ルールは、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数(※1)が、直近1年のうち6ヶ月で51人以上(※2)となることが見込まれる企業に適用されます。と、仮にその後、従業員数が下回ったとしても、ルール継続が原則です。あわせて認識しておきましょう。
また、厚生年金の被保険者数が51人(※2)に満たない企業でも、次の条件に当てはまる場合は社会保険加入の義務が発生します。
- 組織の半分以上の労働者と事業主が社会保険加入を認め、かつ労使合意に基づき(事業主が)管轄の年金事務所に申し出ている
- 地方公共団体に属する事業所
(※1)法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者の総数、個人事業所の場合は適用事業所単位の被保険者数が該当します。
(※2)2024年10月以降
アルバイトが社会保険に加入できないケース

対象範囲が広がっているとはいえ、パートやアルバイトのなかで社会保険に加入できないケースも確かに存在します。具体的には以下のとおりです。
日雇いアルバイト
基本的に日雇いアルバイトは区分として社会保険加入の対象外です。ただし、日雇いでスタートしたアルバイト業務を結果的に1ヶ月以上続けたなら話は変わります。この場合、条件を満たした翌日以降、加入の対象になります。
労働契約2ヶ月以内のアルバイト
契約上、勤務期間が2ヶ月以内のアルバイトも、基本、社会保険には加入できません。しかし、この場合も日雇いアルバイト同様、期間終了後も引き続き働くことになれば、延長当日から社会保険加入の対象に含まれます。
臨時的事業の事業所で6ヶ月以内の契約を結んだアルバイト
工事現場の作業員などに当てはまる方が多い傾向にあります。ここでのポイントはあくまで期間です。当初から6ヶ月を超える契約を結んでいたならば、社会保険の加入対象に含まれます。
4ヶ月以内の契約で季節的業務に従事するアルバイト
農業や漁業など、特定のシーズンのみ雇用されるアルバイトが当てはまります。ここでもやはりポイントは期間です。当初から4ヶ月以上働く契約であれば、社会保険の加入対象に含まれます。
アルバイトが社会保険に加入する際の手続き

アルバイトやパートが社会保険の加入条件に該当した場合、企業側は手続きを行わなければなりません。手続きには電子申請と郵送による2つの方法があります。以下、それぞれ説明します。
電子申請
社会保険の加入手続きは2020年4月から、一部の特定企業に対して電子申請が義務化されています。具体的には、次のとおりです。
- 資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
- 相互会社
- 投資法人
- 特定目的会社
また、申請自体は主に下記の3つの方法から可能です。
- e-Govの利用
- 届書作成プログラムの利用
- 労務管理ソフトと届書作成プログラムの併用
e-Govの利用
e-Govは電子政府とも呼ばれる、各省庁提供のインターネットサービスの窓口です。
専用アカウントを作成しログインした先で申請書を発行します。その際、電子証明書の添付も必要です。
届書作成プログラムの利用
GBizIDを専用ページより取得したうえで、日本年金機構のホームページから「届書作成プログラム」をダウンロード。そこで必要事項を入力し画面の指示に従って申請していきます。
労務管理ソフトと届書作成プログラムの併用
労務管理ソフトごとにマニュアルこそ異なりますが、届書作成プログラムと連携して申請できる点は共通です。
郵送
アルバイト・パートの健康保険、厚生年金、介護保険の加入手続きは資格取得届が一つあれば同時に行うことができます。
まずは事実発生から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を、会社の所在地を管轄する年金事務所へ提出します。
企業が健康保険組合に入っている場合は、その組合との手続きも必要です。
添付書類は原則として必要ありませんが、健康保険証を発行するために、企業側の担当者が加入者のマイナンバーと本人確認を行います。本人確認は、マイナンバーカードはもちろん、運転免許証などの身分証明書などでも構いません。
社会保険の適用範囲拡大による企業への影響

社会保険の適用範囲拡大は、当然、企業側にも影響を及ぼします。 以下、いくつか列挙します。
社会保険料の負担
社会保険の適用範囲が拡大すれば、加入する従業員は増えるわけですが、その分、企業が負担する社会保険料も嵩むことになります。特にこれまで対象外だったアルバイトを多く抱えていた企業の場合、その差は顕著でしょう。
従業員の不満につながる扶養範囲の問題
社会保険の加入によって扶養範囲から外れるアルバイトやパートの方が出てきます。そうなると彼・彼女らが懸念すべきこととして挙げられるのが給料の手取り額です。保険料が天引きされてしまうため、可能であれば扶養の範囲内で働きたい方もいらっしゃるでしょう。そしてこの問題は、何も従業員側だけの話だけではありません。企業側もそうした方々のために配慮していかなければ、たちまち信頼関係にヒビが入る恐れがあります。
そのうえでどう取り組んでいくべきか。もちろん、社会保険加入の要件に当てはまらないように勤務体系を組みなおすことも一つのやり方です。
が、そもそも社会保険加入の仕組みについて今一度、説明することも大事でしょう。保険料を会社と折半できて家計全体の負担軽減につながることや、年金が増えるといったメリットを知らない方も思いのほか見受けられます。そういった点も踏まえて、どの雇用形態・条件が最適か、新たに社会保険の加入対象となったアルバイトに判断してもらうことが大切です。
労務管理に関わる税額の変動
新たに社会保険加入対象となったあるバイトに対しても、正社員と同じように毎月、標準報酬月額に基づいた保険料を徴収しなければなりません。
所得税についても計算上、注意が必要です。社会保険料控除後の額に対して課税されることから、仮に適用前後で総支給額が変わらなければ、所得税が低くなる可能性も考えられます。これに関しては、最終的に年末調整で適正な納税額が決定するとはいえ、いずれにせよ、税額が変動することはあらかじめ認識しておくべきでしょう。
社会保険の加入手続きを怠った場合の罰則やリスク

社会保険の適用範囲が拡大し、加入条件を満たすようになったアルバイトやパートに対して、何も手続きを進めないままで放置しているとどうなるのでしょう。
ずばり、未加入が発覚した場合にはペナルティが科されます。以下、具体的な罰則やリスクです。
6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
健康保険法208条で、事業主が正当な理由なく社会保険に加入すべき従業員を未加入のままにしておくと、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。直ちに罰則を受ける可能性こそ低いとはいえ、行政指導を受けても改善されない場合はしかるべき処置として適用されることになるでしょう。
過去分の保険料を支払う可能性
社会保険未加入のまま雇用を継続していた場合、ほかの罰則とは別に、未加入期間分の社会保険料を過去2年分までさかのぼって負担しなければならない可能性が出てきます。その際、総額に10%を乗じた追徴金もあわせて支払う羽目になるでしょう。
退職者分の未納金を支払う可能性
社会保険未加入だった従業員がすでに退職していた場合、未納金に当たる全額を会社が負担しなければならない可能性もあります。
ハローワークに求人を申し込めない
社会保険の加入手続きが遅れている企業は、ハローワークへの求人申し込みができなくなります。こうしたリスクもまた採用困難の時代には大きな痛手です。
社会保険の適用範囲拡大に伴う助成金制度について
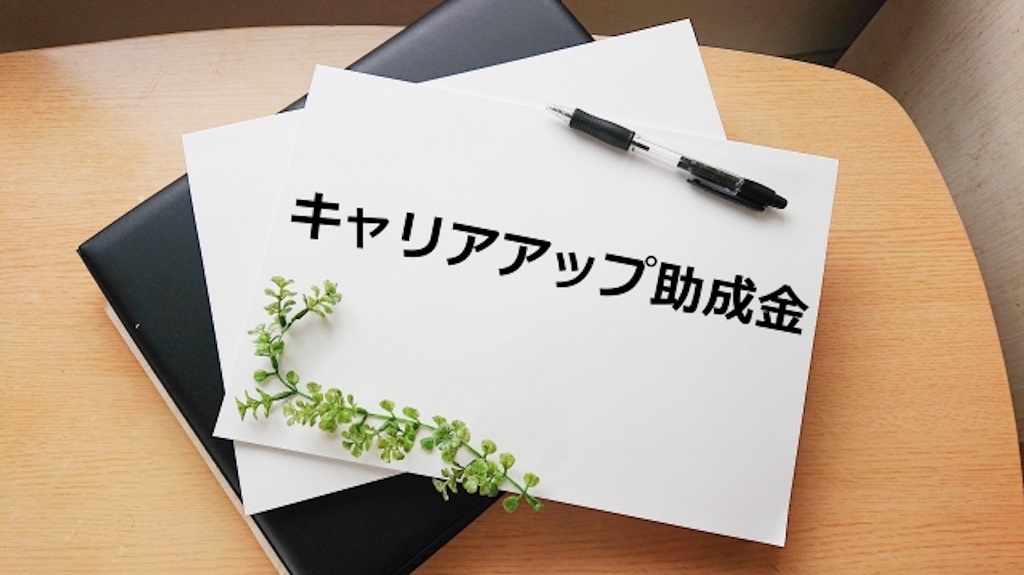
社会保険の適用範囲拡大を国は円滑に進めたいと考えているため、企業向けに支援制度を実施しています。その一つが、アルバイトやパートとのコミュニケーション活性化や賃金の引き上げ、働く時間の延長などを後押しする「キャリアアップ助成金」です。
キャリアアップ計画の作成・提出にはじまり、賃金規定などの増額改定の実施、増額改定後の賃金に基づいた半年分の賃金の支給申請、審査といった流れを経て助成金は発生します。
以下、主な取り組みです。
賃金の引き上げに対する助成金
まずは、賃金の引き上げに特化した助成金制度の内容について紹介します。
賃金規定等改定コース
アルバイトに限らずですが、基本給について賃金規定を2%以上増額改定し、実際に昇給した場合に助成金が支給されます。
賃金規定等共通化コース
アルバイトやパートが正社員と共通の職務に応じた場合の賃金規定などを新たに作成し、それを適用した場合に助成金が支給されます。
労働時間延長に対する助成金
続いて紹介するのは、労働時間の延長に関する助成金制度の内容です。
短時間労働者労働時間延長コース
待遇改善を図りつつ、アルバイトやパートの週所定労働時間の延長を促進し、結果、社会保険に加入してもらった場合、助成金が支給されます。
アルバイトの社会保険加入条件の緩和や義務化に思うこと

社会保険制度の拡大により、企業側は手続きや社会保険料の納付などの業務は増えますが、それ以上にアルバイトやパートとのコミュニケーションが今後より大事になってくると思われます。採用活動においても、欲しい人材を獲得するうえで、こうした制度と柔軟につきあっていくことの重要性がどんどん増していくはずです。当たり前のように変化が訪れる時代に、企業は先手を打ち、そして周囲への配慮を忘れずに、雇用の可能性を見出していかねばならないのでしょう。
そうしたなか、アルバイトの募集をお考えの方にぜひ検討していただきたいのがディップの求人広告サービスです。「社会保険制度あり」や「扶養控除内(扶養範囲内)相談」といった求職者のニーズにピンポイントで訴求できます。まずは、内容をご確認ください。
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。
▶【公式】面接コボット – 応募者対応の自動化で面接管理が楽に!
┗求人サイトからの応募対応を自動化できるサービス。チャットボットを通じ、日程調整まで効率よく進めてくれます。
▶【公式】採用ページコボット – 費用・実績も紹介!採用サイト制作サービス
┗採用ページ作成サービス。求人まとめサイトとの自動連携や求人検索エンジンへの対応により外部集客を強化します。
【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所
代表 荒武 慎一
同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。

