有給休暇の取得が義務化!退職前の取り扱いはやや複雑?
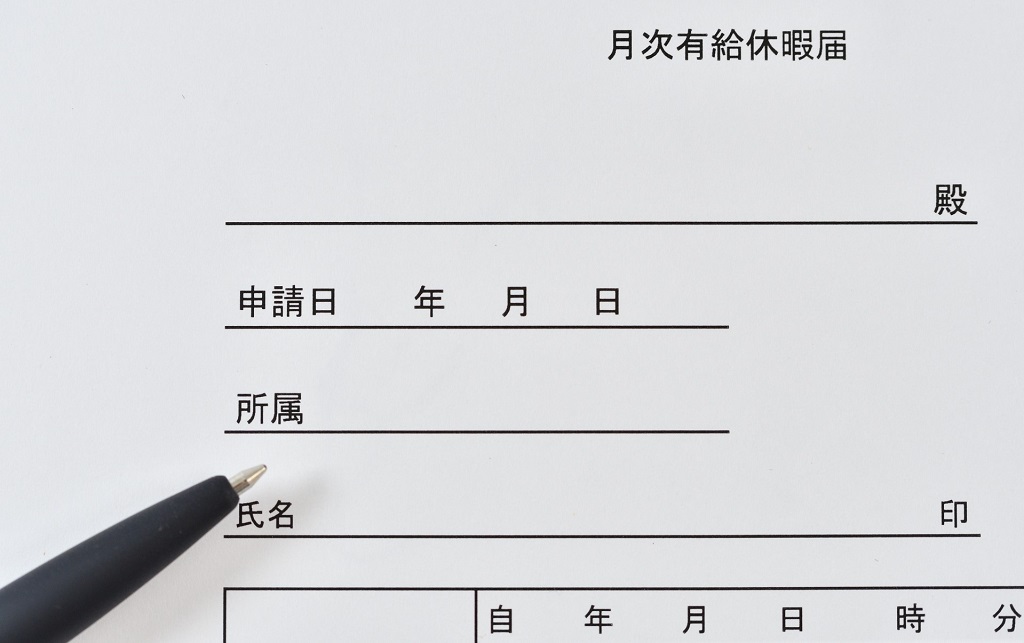
有給休暇は、一定期間勤続した労働者に対して、ゆとりある生活を保障するために付与される賃金を伴う休みです。実にシンプルな定義ですが、本記事で取り上げる従業員退職時のシチュエーションにおいてはやや特殊性を帯びます。
以下、基本的な仕組みとあわせて有給休暇取得の義務化の流れやアルバイト・パートに対する正しい認識を説明しつつ、退職時の取り扱いについてもピックアップ。人事業務では、いずれも重要な知識です。確実におさえておきましょう。
有給休暇の仕組み
有給休暇を取得する権利(年休権)は、以下の2つの条件を満たす従業員が行使できます。
- 雇い入れの日から6ヶ月経過していること
- 全労働日の8割以上出勤していること
上記をクリアすれば、その労働者には10日の有給休暇が付与されます。
また、(有給休暇を付与された)労働者は使用者に対して取得時期を指定することも可能です。
有給休暇の年次5日取得が義務化
働き方改革法の成立に伴い2019年4月1日以降、企業は従業員に対して年5日の有給休暇を取得させる義務が課されました。
前述の10日以上の有給休暇が付与された従業員は、企業規模にかかわらず一律で対象です(1年間の起点は10日以上の有給休暇が付与されたタイミングです)。
アルバイト・パートも有給休暇を取得できる!
有給休暇の取得義務は正社員に限ったものではありません。アルバイトやパートにも適用されます。なお、取得条件はじめ詳細については、こちらの記事で徹底的に解説しています。
▶関連記事: パートの有給休暇取得の条件、付与する日数、賃金の計算方法など解説
退職時の有給消化の特殊性について
退職時の有給消化に関しては、覚えておくべき特殊な点があります。
それは、時季変更権の行使についてです。従業員が退職時の有給消化の時期を指定して申し入れた際、企業側は無条件に拒否することはできません。無論、例外はあり、それが時季変更権です。条件としては、事業の正常な運営を妨げる場合が当てはまります。ただし、退職予定者に日程調整の余地がなければ、優先されるのは従業員の都合です。つまり、このケースでは企業は時季変更権を行使できなくなります。退職を控えた従業員に対しては、本人の希望に沿って有給休暇を消化してもらうのが基本原則というわけです。
従業員退職時の有給消化で企業が気をつけること

従業員から退職にあたって有給消化の申し入れがあったとき、企業側の対応次第ではトラブルになりかねません。そうならないよう、以下、企業が気をつけるべきポイントを紹介します。
有給消化を拒否してはいけない
有給休暇の取得は労働者の権利です。原則、企業側はそれを拒めません。にもかかわらず、認めようとしない方(企業)が稀に見受けられます。仮に断固として拒否し続けたなら、どうなるでしょう。法的に遵守すべきことに対して違反をおかしているのは企業側です。当然、罰則を受ける羽目になります。
有給休暇の残日数に対して、退職日までに取得すると退職者から申請された場合は、不毛なトラブルを招かないよう速やかに認めるようにしましょう。
業務をしっかり引き継いでもらう
退職が決まった従業員には、有給を消化してもらいつつも、業務の引き継ぎはしっかり行ってもらいたいものです。が、仕事に対する熱意が冷めてしまってか、あるいはただただ面倒に感じられてか、なかには、引き継ぎを怠る従業員もいます。そうなると、企業にとってこの先の業務や体制に支障をきたすことが、容易に想像できます。したがって、限られたスケジュールのなかでも従業員にしかるべき対応を促さなければなりません。場合によっては企業側が退職日から逆算して、引き継ぎの計画・進行を細かく指示した方がよいかもしれません。極端な例とはいえ、有給休暇を1ヶ月以上取得している従業員から「有給休暇を消化するために明日から出社しません」と1ヶ月前に言われてしまえば、企業側は基本、拒否できないわけです。そうした状況を考慮したとき、下手(したて)に出ながらでも粘り強く引き継ぎをお願いしていく必要があるでしょう。
事前に人員補充の手を打っておく
退職が決まった従業員の穴埋めが後手に回ってしまうと悪循環を引き起こしかねません。もちろん、企業あるいは部署の規模によってその影響度は異なりますが、いずれにしても一人が抜けた分、何かしら負担が生じるのは明らかです。忙しいなかでは正常な判断が難しいことも考えられます。ゆえに人員補充をスムーズに行うべく、採用活動への目配りは必須です。が、頭ではわかっていても(特に組織単位では)なかなかすぐには動けないケースが出てくることも想定できます。そこでおすすめしたいのがdip(ディップ)のサービスです。アルバイト・パートから契約社員、正社員と雇用形態はもちろん、そのほかの細かい属性に関してもニーズに合わせて訴求の引き出しがあるため、幅広くアプローチできます。何よりスピーディーである点が特長。企業と求職者を素早くマッチングしてくれます。
以下、先に問い合わせても良し、サービスの詳細を確認しても良し、よりイメージを高めるために実績を確認するのも良し。気になる方はぜひ、導入をご検討ください。
| サービスのご案内についてはこちら▼ 求人広告掲載、採用業務サービスの総合窓口 サービスの導入事例をピックアップ▼ 応募頻度が上がり、スピード採用が実現! |
従業員退職時の有給消化でよくある対処例

従業員が退職時に有給消化を申し出る際、単にその旨を伝えるだけでなく、付随する要望やそれに代わる条件の提示など、イレギュラー的に色々と一筋縄でいかないことも想定できます。これらに対して事前に対策方法を用意しておかなければ(あるいは心構えとして持っていなければ)、いざ直面したときには困惑してしまうことでしょう。以下紹介するのは、イレギュラー対応といっても、実際には頻繁に生じているケースです。スムーズに、そしてスマートに対処すべく、確実に把握しておいてください。
有給休暇の買い取りを求められたなら?
有給休暇は、休むことによって心身の疲労を回復させることが目的です。そのため、企業がその分をお金で買い取り、働かせることはできません。従業員から買い取りを求められた場合でもそれは同じです。
ただし、退職時の有給休暇の買い取りは例外的に認められることがあります。それは、(退職時の有給休暇の買い取りが)あらかじめ就業規則に規定されている場合です。したがって、従業員から買い取りを希望されたなら、認める認めないにかかわらず、就業規則に基づき、説明(後者に関しては納得してもらうように)してください。
消化期間中に追加される新たな有給休暇の取り扱いは?
退職までの期間で、その年度の新たな有給休暇が付与されるケースがあります。果たして、この追加分は加算できるのでしょうか。ずばり、ポイントは、退職日が確定しているか否かです。
有給休暇は、退職の効力が発生するまでの期間のみ取得できます。そのため、従業員がそのすべてを取得する前に退職した場合、権利はなくなります。つまり、退職日直前に有給休暇の日数が増えたとしても、それらをすべて消化させるために、退職予定日を先延ばしにする必要はありません。
他方、退職日がまだ確定していないのであれば、従業員の希望に沿って付与した分も消化対象に含まれます。繰り返しお伝えしますが、企業側は従業員からの有給休暇の申請を拒否できないため、(希望がそうであれば)追加分もあわせて消化してもらうのが原則です。
有給休暇消化期間中に転職先へ入社したいと頼まれたなら?
就業規則には「二重就労禁止規定」が盛り込まれている場合があります。二重就労とは、文字どおり、現在の職場を含む複数の企業で就労することです。仮にこの規定に抵触した場合は、退職金の減額や懲戒解雇といった罰則が考えられます。
ただし、有給休暇の消化期間中に転職先へ入社すること自体を禁じる法律はありません。そのため、上述した処分が法的に有効であるかどうかは別問題です。
従業員からすると、おそらく「次の職場には早く行きたいが、現職からの給料(有給分)もしっかりもらいたい」といった意図でしょうか。いずれにしても退職を前提とした有給休暇消化期間中の転職が可能か否かは、在職中の企業と転職先両方の就業規則によります。したがって、どちらの就業規則でも二重就労が認められていれば、従業員の希望に沿って対応してください。
ボーナスの支給と重なったらどうする?
ボーナス(賞与)の支給は法律で義務づけられているわけではありません。それでも企業がボーナスを支給するのは、就業規則で定めているからです。たとえば、受け取る対象者の条件として、支払い日までに在職中の者とはっきり記載されているならば、当然、企業側は支給する義務があります。
と、仮に金額について特に決めごとがない場合、有給期間の消化中やすでに退職が決まっている従業員に対して、(おそらく通常より)少ない額で支給するやり方ももよくあるケースの一つです。ボーナスの解釈として、大別すると「将来に対する期待」「成果配分」「過去の勤務状態や成績を評価」が挙げられますが、退職者に関してはすべからく例外になるため、決して減額がアンフェアとはいえません。ただし、こうした部分も就業規則で明記しておかなければ、その曖昧さから従業員といざこざが生じることも大いに考えられます。
したがって企業がすべきことは、ボーナスの定義を会社全体で共有できる体制づくりです(就業規則に関してもその効力含めて皆が一様の認識を持てることが望ましい)。
従業員退職時の有給消化は丁寧かつ適切に取り扱おう

再三述べてきましたが、まず、有給休暇の取得は労働者の立派な権利です。申請があれば、原則、企業側は拒否できません。もちろん、業務の引き継ぎはきちんと並行してもらわなければ、ドタバタしたまま業務の負担や会社内での混乱を招く恐れがあります。双方のやり取り次第では大きなトラブルを招く恐れも考えられるでしょう。だからこそ企業は、有給休暇の取得を普段から推奨するなど、各従業員が退職にいたる場合に備える必要があります。定期的に有給休暇を消化してもらえていれば、上述したまとめて取得することのデメリットは少なからず軽減されるはずです。あわせて、退職決定後に付与される分や、転職先への入社日、ボーナスの支給等々の想定し得るケースについては就業規則ではっきりと方針を定めておきましょう。もちろん、それらを全社員と共有できる体制、環境づくりに尽力することも大事です。
記事でも触れましたが、社員やアルバイトが退職した際はどうしても慌ただしくなります。場合によっては新しい従業員も見つけなければならないでしょう。したがって、繰り返しになりますが、求人広告の掲載や採用活動を支援するdipのサービスをおすすめします。「バイトル」「バイトルNEXT」「バイトルPRO」「はたらこねっと」「コボット」といった幅広いサービスでもって、求人・採用に関するお悩み解決を図ります。まさに今(あるいは今後)、そうした課題に直面しているのであれば(考える必要があれば)、ぜひ導入をご検討ください。お問い合わせは無料です。
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。
【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所
代表 荒武 慎一
同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。

