短期雇用契約とは

短期雇用契約は、一定の期間を定めて労働者を雇用する契約形態です。通常、数日から数ヶ月程度の比較的短い期間で設定され、企業の繁忙期や季節労働、プロジェクト単位の業務などに対応するために活用されます。人件費のコントロールや柔軟な人材確保を可能とし、労働者側にとっても短期間の就業機会を提供するメリットがあるため、重宝するお店や企業も多いのが実状です。本章ではまず、期間に焦点を当て、雇用契約の種類、そして似た働き方について取り上げます。
雇用期間(契約)の種類
雇用契約には、主に「有期労働契約」と「無期労働契約」の2つが存在します。それぞれの特徴を理解することで、おのずと違いは浮き彫りになるでしょう。以下、両者について説明します。
有期労働契約(期間の定めのある労働契約)
有期労働契約と一口にいっても、「契約社員」「アルバイト・パート」「高度専門職型契約社員」「定年後に再雇用される嘱託型契約社員」など複数該当します。特徴、活用シーンは下表のとおりです。
| 契約種類 | 特徴 | 主な活用シーン |
|---|---|---|
| 契約社員 | フルタイムで働く、または職務・勤務地・労働時間などが限定された有期雇用の社員です。 | 正社員に準じた業務や、特定のプロジェクト遂行時に活用されます。 |
| アルバイト・パート | 契約社員同様の働き方、あるいは短時間勤務で、契約満了日まで従事する雇用形態です。 | 繁忙期の人員補強や、シフト制の業務に適しています。 |
| 高度専門職型契約社員 | 特定分野に精通した高度な知識やスキルを有する契約社員です。 | 専門性の高いプロジェクトや研究開発などに活用されます。 |
| 定年後に再雇用される嘱託型契約社員 | 定年退職後、一定期間の契約で引き続き勤務する雇用形態です。 | 豊富な経験やノウハウを持つ人材の継続的活用に適しています。 |
これらは、企業の人材ニーズと労働者の多様な働き方を両立させる重要な役割を果たしています。前者は、業務の特性や必要な専門性に応じて、適切な雇用形態を選択することが求められ、後者は、たとえば自身のライフスタイルやキャリア目標に合わせて動くわけです。
▶関連記事:期間の定めのある労働契約(有期労働契約)とは?無期雇用との違いや新ルール(2024年)など解説
無期労働契約
無期労働契約は、雇用期間を定めず継続的に働くことを前提としています。主に適用されるのは正社員です。とはいえ有期契約社員も契約が更新され、通算5年を超えた場合、希望があれば無期契約に転換できます(労働契約法18条)。その際、業務内容や待遇は必ずしも変わるわけではありません。契約内容に対する認識に両者で齟齬が出ないようにすることが重要です。
短期雇用と似た働き方
短期雇用と似た働き方として「ギグワーク」や「単発アルバイト」があります。ほぼ同義として捉える向きも多いかもしれませんが、細かい部分では相違点もあるため、しっかり把握しておいて損はないでしょう。以下、それぞれ簡単に説明します。
ギグワーク
ギグワークは、短期的かつスポット的な業務を請け負う働き方です。主にオンラインプラットフォームを通じてマッチングされることが多く、「雇用契約」ではなく業務委託契約として行われる場合があります。
主にオンラインで完結する業務が多く、データ入力、デザイン、ライティング、プログラミングなど、幅広い分野で活用されています。ギグワークの特徴をざっと挙げると、「契約期間が短いこと」「成果報酬制であること」、そして「働く時間や場所の自由度が高いこと」です。フリーランスよりも短期的な案件が多い傾向にあるでしょう。
▶関連記事:ギグワークとは?意味や種類、メリット・デメリットなど簡単に解説
単発アルバイト
単発アルバイトは、1日や数日間のみ就労する形態です。宿泊業や建設業など特定の業界では、しばしば見受けられます。短期雇用契約に該当する場合も少なくありません。その際は、当然「雇用契約書」を取り交わします。内容が曖昧だと労務トラブルにもなりかねないため、注意が必要です。
短期雇用契約における社会保険の加入について
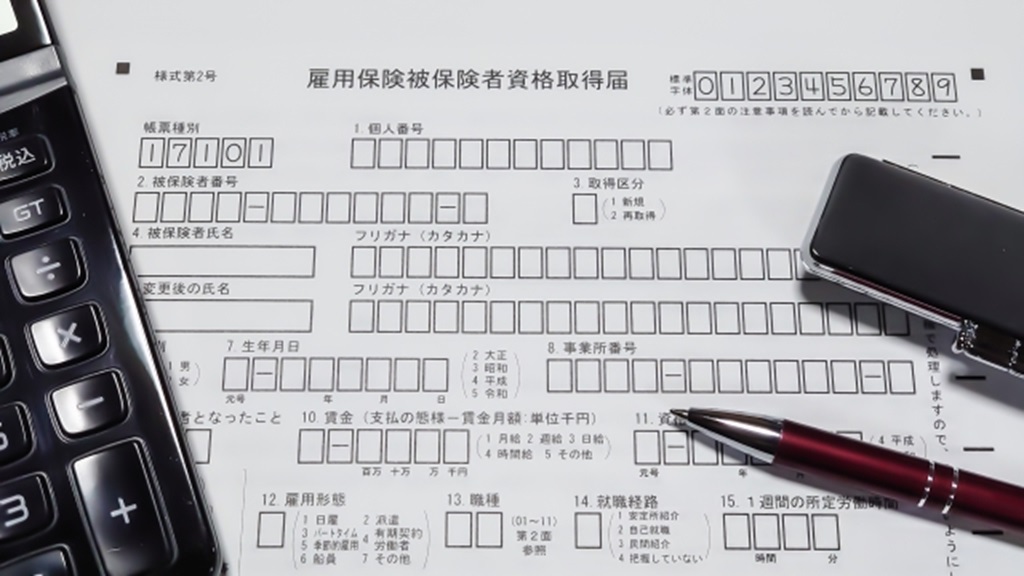
短期雇用契約を結ぶ場合、社会保険の加入が必要かどうかは、雇用契約期間や契約内容により異なります。適切な手続きを怠ると、労働基準法違反やトラブルの原因になるため、条件そして法改正の最新情報を把握することが重要です。以下、具体的なケースごとに社会保険の加入条件を説明します。
新規採用で雇用契約期間が2ヶ月以内なら
短期雇用契約のなかでも、初回の雇用契約期間が2ヶ月以内の場合は、社会保険の加入対象外となるケースが一般的です。ただし、雇用契約書には、契約期間を明確に記載し「雇用期間の定めあり」の状態であることを示す必要があります。また、労働時間が週20時間以上であれば、雇用保険の加入が求められます。採用時に社会保険対象か否かを確認することで、手続きの効率化を図れるでしょう。
契約更新の条件が変わったなら
短期雇用契約を更新する際、契約期間や労働条件に変更がある場合は、社会保険加入の有無も見直しが必要です。たとえば、契約期間が2ヶ月を超える、または週20時間以上働く条件が追加された場合、雇用保険や社会保険の加入義務が発生する可能性があります。契約更新時には、労働基準法に基づいた契約内容の確認と手続きを怠らないようにしましょう。労務トラブルや法的問題に対するリスクヘッジの意味でも大切です。
契約期間終了後に数日経ってから再び契約を結ぶなら
短期雇用契約が終了し、一定期間空いた後、再度契約を締結する場合も注意が必要です。というのも、新たな契約が過去の契約と連続しているとみなされるケースがあります。そうなると、社会保険の加入条件を満たすわけです。そのため、契約に関しては丁寧に確認、管理することが求められます。望ましいのは双方での認識共有です。雇用契約書には、新たな契約期間や条件を詳細に記載しておきましょう。
短期雇用契約における社会保険の加入可否は、契約期間や条件に大きく左右されます。法令遵守はもちろん、労務管理の効率化のためにも適切な運用を心掛けることが大事です。
短期雇用契約書について

短期雇用契約書は、雇用主と労働者の間で締結される契約内容を明確にする重要な文書です。労働基準法の規定に基づき、記載すべき事項が厳格に定められています。不備がある場合は、労務トラブルや法的問題に発展しかねません。以下、契約書を適切に作成すべく必要な情報をお伝えします。
▶関連記事:短期雇用契約書の作成~社会保険の加入条件やひな形利用の注意点など交えて解説~
記載必須事項
短期雇用契約書には、法律で定められた必須事項を漏れなく記載する必要があります。これらの項目は、雇用関係の基本的な枠組みを定義するものです。同時に労働者の権利を保護する役割を果たします。
具体的には下表のとおりです。
| 必須事項 | 内容詳細 |
|---|---|
| 雇用契約期間 | 契約開始日と終了日を明記。更新の可能性がある場合は、その旨も記載する。 |
| 労働条件 | 賃金、労働時間、休憩時間、休日、時間外労働の有無を具体的に記載する。 |
| 業務内容と勤務地 | 従事する具体的な業務内容と、勤務地を特定し記載する。 |
| 社会保険・雇用保険 | 労働条件に応じた説明も含めて加入の要否を記載する。 |
| 解雇・退職の規定 | 解雇理由や退職手続きについて詳細を記載する。 |
参照:厚生労働省「パートタイム労働者、有期雇用労働者の雇用管理の改善のために」
記載が望ましい事項
必須ではないものの、契約運用の円滑化に役立つ事項を記載することも推奨されます。主に下表のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 試用期間 | 期間と条件を明記する |
| 休日・休暇 | 法定休日、有給休暇の付与条件を明記する |
| 残業・休日出勤 | 時間外労働の取り扱いや割増賃金について明記する |
| 服務規律 | 遵守すべき規則や禁止事項を明記する |
| 機密保持 | 業務上知り得た情報の取り扱いについて明記する |
| 副業・兼業 | 他の仕事との兼務に関する方針を明記する |
| 教育訓練 | 研修や技能向上のための機会提供について明記する |
| 表彰・懲戒 | 評価制度や懲戒処分の基準を明記する |
記載が望ましい事項を盛り込むことで、契約書の内容がより実務に即したものとなるでしょう。しからば、スムーズな業務遂行にも役立てられるはずです。
短期雇用契約の注意点
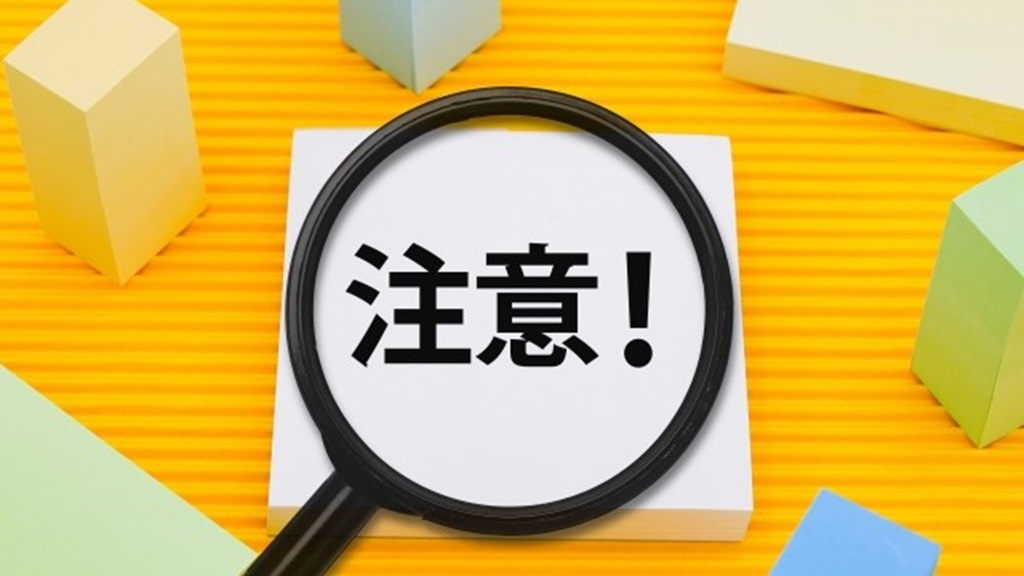
短期雇用契約も例にもれず労働法規に基づいた適切な対応が求められます。特に、改正労働契約法によって設けられたルールはつい見落としがちです。労働者の権利を保護し、公正な雇用環境を整備する目的に沿うよう、必ず把握しましょう。以下、こうした注意点をいくつか取り上げます。
改正労働契約法で設けられたルールに違反しない
改正労働契約法では、有期雇用労働者の保護を強化するためにいくつかの重要なルールが定められています。法的リスクを回避するためにも確実におさえておきましょう。具体的には次のとおりです。
- 無期雇用への転換
- 雇止め法理の法定化
- 不合理な労働条件の禁止
- 就業場所・業務における変更範囲の明示
- 更新上限の有無と内容の明示
- 無期転換申込機会の明示
- 無期転換後の労働条件の明示
以下、それぞれ簡単に説明します。
無期雇用への転換
短期雇用契約のつもりが、結果的に長期間雇うことになった場合、無期雇用への転換が必要になる可能性があります。その条件は次のとおりです。
- 契約期間の通算が5年を超える場合
- 労働者が無期転換を希望する場合
有期であっても必ずこのケースも想定しておきましょう。
雇止め法理の法定化
雇止め法理とは、短期雇用契約の更新を繰り返した場合、解雇に準じる扱いが発生するルールです。
反復更新された有期労働契約で、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、雇止めは無効となります。この規定は、労働者の雇用の安定性を確保するためのものです。雇用主は、契約更新や雇止めの判断に際して、十分な根拠と説明を用意する必要があります。
不合理な労働条件の禁止
有期雇用労働者と無期雇用労働者の間で、不合理な労働条件の相違を設けることは禁止されています。この規定は、同一労働同一賃金の原則に基づくものです。雇用主は、職務内容や責任の程度、人材活用の仕組みなどを考慮し、公平な労働条件を設定する必要があります。
就業場所・業務における変更範囲の明示
雇用契約時に、就業場所や業務内容の変更可能性についても明確に示す必要があります。雇用主は、契約書や就業規則に変更の範囲を明記し、労働者に説明することが求められるのです。これにより、労働者は自身の就業条件を正確に理解し、将来的な変更にも備えることができます。
更新上限の有無と内容の明示
契約更新の上限回数や期間がある場合、その内容を明示しなければなりません。この規定は、労働者が自身の雇用の見通しを立てやすくするためのものです。したがって雇用主は、更新上限を設ける場合、その理由と内容を労働者にはっきりと伝える必要があります。
無期転換申込機会の明示
雇用主は、無期転換の権利について労働者にわかりやすく説明し、転換申込の手続きを整備することが求められます。そのため、無期雇用への転換申込権が発生する時期や条件についても、労働者に明示しなければなりません。これにより、労働者は自身の権利を適切に行使することができます。
無期転換後の労働条件の明示
雇用主は、無期雇用へと転換した後の賃金、勤務時間、職務内容などの条件を具体的に提示しなければなりません。これにより、労働者は転換後の待遇を理解したうえで、無期雇用を選択することができます。
雇用契約の内容変更は慎重に行う
雇用契約の内容変更は、労働条件の変更を伴うため、労働者の同意が不可欠です。特に短期雇用契約の場合、契約期間中の変更は労働者に不利益を与える可能性が高いため、より慎重な対応が求められます。なお、変更手続きは、労働基準法や労働契約法に基づき行いましょう。
労働者との十分な協議
雇用契約の内容を変更する際の労働者との協議では、変更理由や必要性を明確に説明し、労働者の理解を得ることが必要です。また、労働者からの意見や要望にも耳を傾け、可能な限り配慮することが求められます。協議の過程を記録に残せば、後々のトラブル防止にも役立つでしょう。
変更内容の文書化、署名
雇用契約の内容変更が決定した場合、その内容を文書化し、労働者の署名を得ることが必要です。文書には変更前後の条件や適用日も明記し、その後は労働条件通知書や雇用契約書の変更覚書として保管します。これを疎かにすると労働基準監督署からの指導や解釈相違によるトラブルなども起きかねません。細心の注意を払いましょう。
短期雇用の求人が多い主な業種

特定の業種や職種では、短期雇用の需要が高く、求人も多く見られます。おそらくそれは、季節変動や繁忙期の対応、プロジェクトベースの業務など、一時的に人材を必要とするからでしょう。本章では、そうした短期雇用の求人が多い業種をいくつか取り上げます。
事務作業関連のお仕事
データ入力、書類整理、電話対応などの事務作業関連の業務では、専門的なスキルよりも正確性と効率性が求められるため、短期雇用が重用されがちです。特に、年度末や税務申告期間などには需要が高まります。
クリエイティブ関連のお仕事
デザイン、ライティング、そのほかWeb制作などのクリエイティブな業務に対して、プロジェクトベースで短期人材を雇う企業は少なくありません。そのうえで、スキルが高い方であれば継続的に従事してもらうケースもしばしば見受けられます。仮に自社とマッチする方であれば(もちろん労働者側の立場でも)、長期人材として社員雇用につながることも決して珍しくないのです。
配送系のお仕事
物流業界では、繁忙期に合わせて短期雇用の求人が増加します。特に年末年始やセール時期には、宅配便やネット通販の配送需要が急増するため、短期的に多くの人材を必要とします。これらの仕事は、体力と正確性が求められますが、特別な資格がなくても始められることが多いため、短期雇用のなかでも人気の求人です。それに応える形で採用に踏み切る会社も多く見受けられます。
代行系のお仕事
家事や運転、買い物などを代行するサービスも短期雇用求人の定番です。特に、イベントシーズンや長期休暇期間中には需要が増す傾向にあります。それを見据えて採用活動を行う企業も少なくありません。
専門資格を要するお仕事
医療、介護、教育などの分野では、専門的な資格が問われる業界では、正社員の産休や育休の代替、繁忙期の人員補強などで短期雇用が活用されます。とりわけ看護師、介護士、保育士などの資格保持者はニーズが高く、魅力的な報酬を提示し雇う企業も少なくありません。
短期バイトの募集なら『スポットバイトル』がおすすめ

実際に短期バイトを募集するなら求人サービスの選定は非常に大事です。特に昨今は、スポットワーカーを募集するサイトも増えてきています。
そうしたなか、おすすめしたいのが『スポットバイトル』です。スキマ時間で「働きたい」ワーカーと「働いてほしい」事業主をつなぐサービスとしてディップ株式会社が提供しています。急な欠員補充、効率的なシフト調整を図るのにもってこい。最短で当日の掲載・マッチングが可能です。
短期雇用契約を戦略的に活用したい企業にとって、『スポットバイトル』は実に有効なツールになると考えます。
▶【公式】スキマ時間のスポット募集ならスポットバイトル|求人掲載はこちら
短期雇用契約のメリットを享受するには正しい理解が必須!

短期雇用契約は、費用面も含めて効率よく人材を確保できるメリットがある一方で、法規制や注意点を蔑ろにしてしまうと、トラブルを招く羽目になります。
というわけで、あらためておさらいしましょう。
まず、改正労働契約法で定められたルールの遵守は必須です。無期雇用への転換、雇止め法理の法定化、不合理な労働条件の禁止……等々、労働者の権利を保護するために設けられているこれらのルールを把握したうえで適切に対応することは、法的リスクの回避、ひいては労働者との良好な関係維持に寄与します。
また、雇用契約書の作成にも細心の注意を払いましょう。契約期間、労働条件、業務内容、社会保険の加入状況など、必須事項は不備なく記載すること。そこに加えて、試用期間や服務規律などの任意事項も含めれば、より実務に即した契約書になるはずです。コツとしては労働者目線で考えられると、内容に合点がいきやすくスムーズに事を運べるでしょう。
短期雇用を採用ノウハウの一つとして機能させるためにも、契約に対する理解を疎かにするわけにはいきません。短期雇用を検討する際はぜひ、拙稿を参考資料、あるいは安心材料としてお使いいただければ幸いです。
求人掲載・採用業務のサポートや料金についてなど、ぜひ気軽にお問い合わせください。
また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談も無料で承っております!
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【公式】スキマ時間のスポットワーカー募集ならスポットバイトル
┗スキマ時間で「働きたい」と「働いてほしい」をつなぐ求人マッチングサービス。求人は無料で掲載できます。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。
▶【公式】面接コボット – 応募者対応の自動化で面接管理が楽に!
┗求人サイトからの応募対応を自動化できるサービス。チャットボットを通じ、日程調整まで効率よく進めてくれます。
▶【公式】採用ページコボット – 費用・実績も紹介!採用サイト制作サービス
┗採用ページ作成サービス。求人まとめサイトとの自動連携や求人検索エンジンへの対応により外部集客を強化します。
【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所
代表 荒武 慎一
同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。

