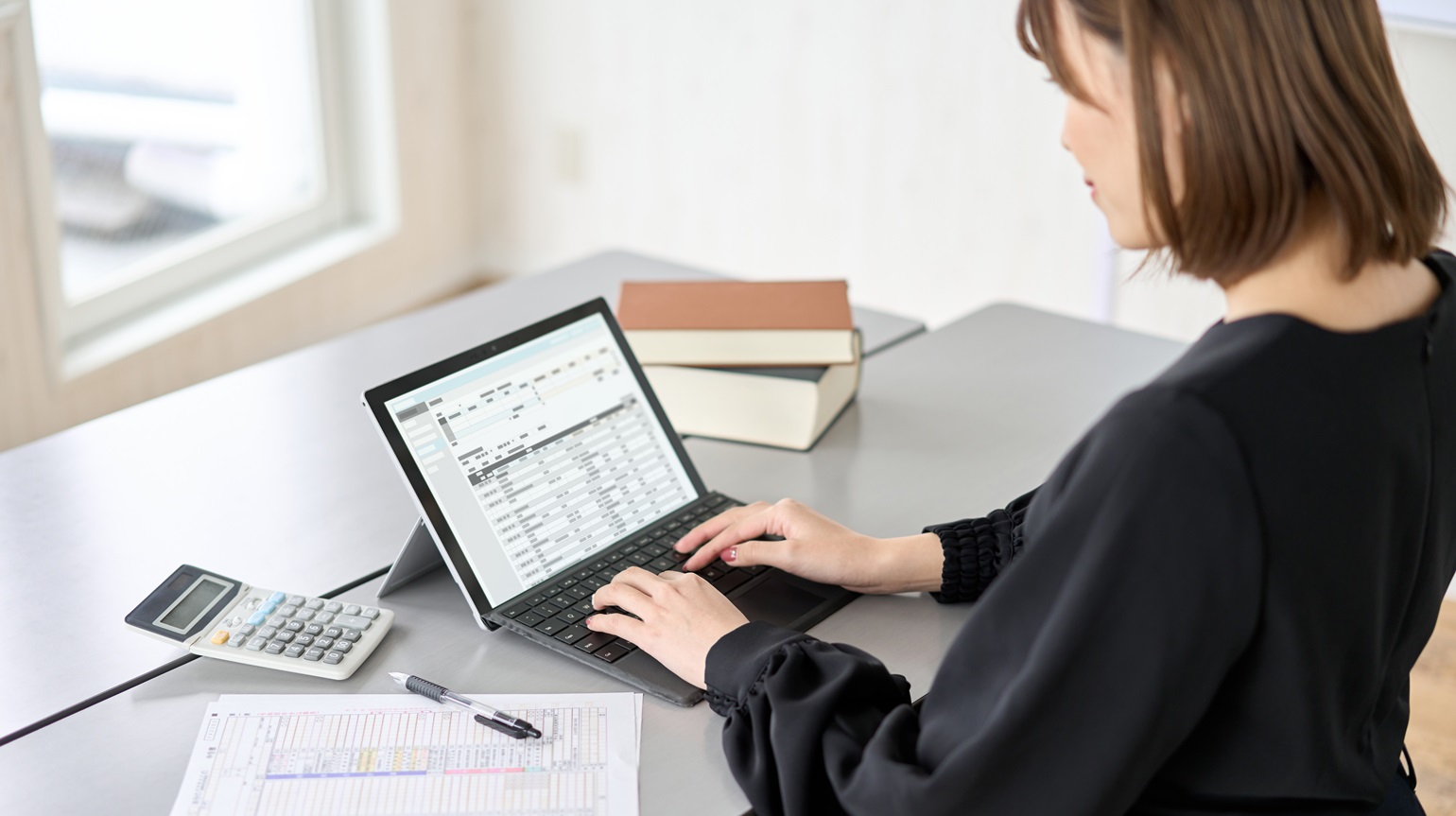企業の副業禁止は違法なのか?

企業が副業を禁止することについて、たびたび話題に上るのがその違法性です。おそらく人事担当者のなかにも実は曖昧な方がいらっしゃるのではないでしょうか。
以下、明確にお伝えします。
原則、副業は自由に行える!
労働者は企業に雇用されると、就業時間中は業務命令に従う必要があります。というのも企業は雇用契約により業務命令権を持っているからです。したがって、従業員の行いが業務命令違反に当たる場合、解雇することもできます。
しかしながら、従業員が副業を行うことについては、法律上、ルールは定められていません。就業時間外はプライベートな時間であるため、それぞれ自由に活動して問題ないというのが原則なのです。それは、就業時間外にほかの仕事に取り組みことも含まれます。つまり副業を行うか否かは、基本、各労働者の意思次第です。これは憲法において「職業選択の自由」が保証されていることからもわかります。
禁止することもできる!
前項と矛盾するようですが、無条件に副業は許可すべきものなのかと問われれば、実際のところそれはまた別の話です。そう、副業は禁止することもできます。本業に多大なる支障をきたす場合は、禁止の対象となり得るのです。
たとえば、終業時刻後に長時間副業を行い疲労を溜め、本業に集中できなくなってしまった場合、これは契約上の労務を十分に実行できていないことを意味します。このように、明らかにパフォーマンス低下の原因が従業員の副業にあるのなら、企業側がそれを禁止するのも無理はないでしょう。むしろ、きわめて妥当な判断だといえます。
就業規則で明確化することが大事!
法律には「副業」という言葉はなく、本業以外の仕事で労働者が収入を得ることを禁止する規律もありません。したがって、副業自体に違法性はないのです。が、就業規則を設けるとなると話は変わります。就業規則は企業が独自に制定するルールであり、労働者と使用者の双方が守るべき契約です。つまり、企業が就業規則のなかで副業を禁止すれば、その行為に及んだ従業員は契約違反に当たります。その逆もしかり。従業員の副業を推奨するならば、企業側が就業規則のなかではっきりと認めてあげればよいわけです。いずれにせよ、副業に関してのルールは、可否はもちろん細かい条件まで含めて就業規則内での明確化が必要だといえます。
副業を禁止できる範囲
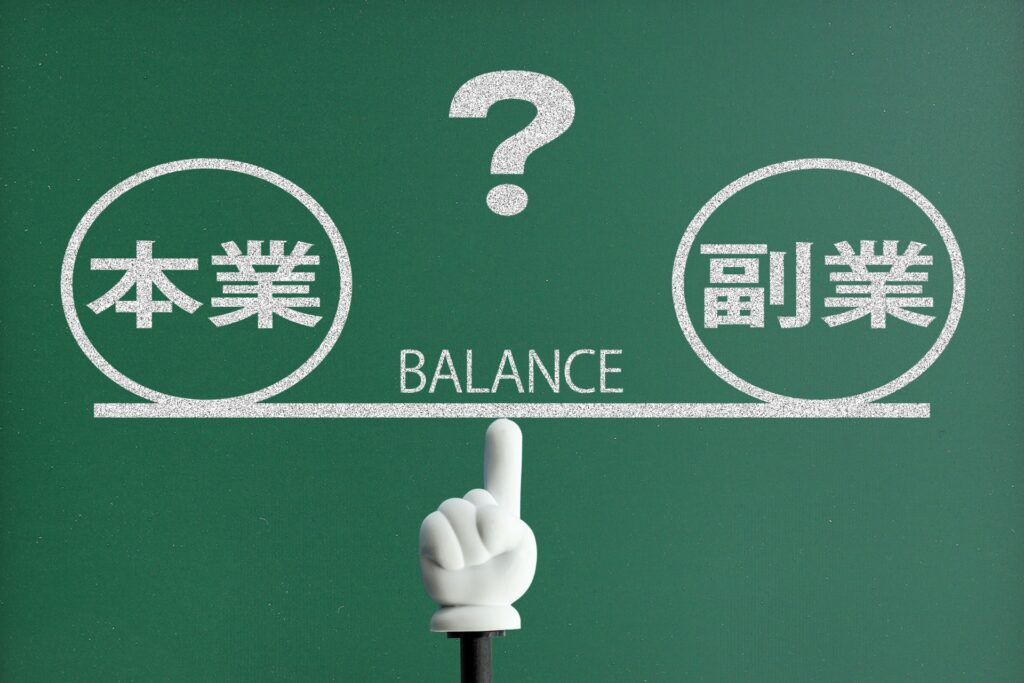
前述のとおり、副業は決して禁止が不可能なわけではありません。ただし、範囲はある程度限られます。
「どこまでが副業を禁止にできる範囲なのか?」 「なぜ企業は副業を禁止にするのか?」
本章にてくわしく紐解きます。
副業禁止に及ぶ範囲
副業は自由とはいえ、企業側からするとできれば本業に力を入れてほしいと考えるのも何ら当然のことでしょう。繰り返しお伝えしますが、副業は禁止行為に定めることが可能です。具体的には、株、FX、家賃収入などの投資や利殖ではなく、競合会社でのアルバイトあるいは副業での長時間労働の場合、会社の業務に悪影響を及ぼすことが十分に考えられます。これらは、副業禁止の規則に組み入れてもおかしくない範囲です。
この辺りの境界線を引くのが曖昧であれば、いっそのこと副業全般を禁止するのも一つの対策といえるでしょう。10人以上の社員が従事する職場では、管轄の労働基準監督署に就業規則を届け出ることが義務づけられていますが、そこで副業禁止を謳い、適切な申請手順を踏み認可が下りれば、禁止事項として成立します。
そのうえで、仮に従業員が副業禁止規定に抵触した場合、(懲戒委員会の開催や弁明の機会を与えるなどの手続きを行う必要こそありますが)正当に何らかの処分を下すことも可能です。
企業が副業を禁止する理由
企業が副業を禁止にするのはさまざまな理由が考えられます。後述するデメリットとも重なりますが、たとえば情報漏洩のリスクです。ノウハウ、技術、取引先の顧客情報などは、企業にとって重要な秘密事項だといえます。裏を返せば、それらは副業を禁止にしてまで守る必要があるものです。前項でも触れましたが、競合他社で企業秘密をそのまま流用されてしまってはたまったものではありません。
同じく、従業員に対するケアが難しくなるのも不都合です。労働契約法では、企業側に従業員の労働時間や健康状態の管理が義務づけられています。副業に割く時間が増え過労による体調不良が生じたとき、本来のパフォーマンスを損ねることになるでしょう。企業にとっても痛手です。
また、人材流出も危惧するポイントに挙げられます。副業での成果が本業を超えた結果、自社を辞められてしまうケースは決して珍しくありません。
上記踏まえて、半ばやむを得ず副業禁止にいたる企業も少なくないのです。
副業は企業にとってデメリットが多い?

前項でも触れたように、つまるところ懸念事項がある限り、「副業はそうたやすく解禁できるものではない」というのが企業側の大方の見解だといえるでしょう。以下、あらためてデメリットを確認します。
生産性が低下する恐れ
副業によって本業が疎かになるのではないかと不安視する向きは少なくありません。とりわけ繁忙期には、どっちつかずになってしまう方もよく見受けられます。また、十分な休養が取れず疲れが蓄積されれば、本業の生産性にも響くはずです。仮に副業を解禁するのであれば、やはりこれらの懸念を払しょくできる材料が必要でしょう。
離職者増加につながる恐れ
当初はお小遣い稼ぎ程度のつもりで始めた副業でも、気づけば本業を凌ぐほどの価値に飛躍するケースがあります。副業で儲かれば、そこにのめり込むのも当然です。しまいには、勤務する会社を辞める方もいらっしゃいます。
このように副業をきっかけに従業員が離れてしまうことは仕方ないのでしょうか。筆者はそこに対してやや懐疑的です。無論、デメリットに思える側面はありますが、それらを嘆く前に防止策を打つこともまた、一つのやり方だと考えます。まずは、自社で働く意義すなわちメリットを普段からしっかり認識してもらう努力が必要でしょう。
情報が漏洩する恐れ
情報漏洩は、図らずも起きてしまうものです。たとえ従業員に悪気はなくても、所属する会社で知り得たノウハウや情報を、副業先で知らず知らずのうちに伝えてしまう可能性は確かに考えられます。そうはいってもやはり、打ち手がないわけではありません。それはたとえば「秘密保持義務」や「競業避止義務」を明確に打ち立て共有することです。リスクがいかに大きいものか一人ひとりに対して意識を植え付けることも求められます。アルバイト・パート含めた全社員に浸透させられるよう、積極的かつ愚直なまでの呼びかけ、働きかけが必要でしょう。
労働時間や保険の管理を誤認する恐れ
副業を認める企業は、従業員の労働時間を(厳密には)より細かく管理する必要があります。なぜなら、法定労働時間が本業と副業を通算したものに変わるからです(例外も存在します)。一方で労災保険や雇用保険などの扱いについては通算されません。
こうした法の理解についてしっかり把握しておかなければ、トラブルを招く可能性があります。それゆえ、副業を解禁することによって人事担当者は業務が複雑に感じられるかもしれません。が、そもそも正しく認識しておかなければならない内容です。副業の禁止云々抜きに業務をスムーズに対応していくには、人事や労務に関しての広い知識が必要でしょう。
副業を解禁する企業は増えている

まさしく「副業解禁元年」とも呼ばれる2018年以降、副業を解禁する企業が増加傾向にあります。とりわけ厚生労働省が作成している「モデル就業規則」のなかで副業や兼業を認めるガイドラインが記述されたのは、この流れに大きく寄与したといえるでしょう。
こうした動きをもとに本章では、副業を解禁する理由やメリットについて述べ、そのうえで注意点も挙げていきます。
企業が副業を解禁する理由とメリット
同じ会社に長く勤め続ける風潮がなくなりつつある現代において、もはや転職は当たり前です。組織に対して不安または不満要素が生まれればたちまちアクションを起こされる、つまり離職につながるケースは少なからず散見されます。副業の禁止がそうした事態を生む要因として直接該当するかはさておき、他所の会社と比較したときに“違い”として認識されることは十分あり得るでしょう。そして、優秀な従業員、社員、スタッフほど世相に敏感な傾向にあります。しからば、やはり副業を解禁した方が人材流出を防ぐ可能性は高まるものと思われ、ゆえに解禁している企業もあるはずです。と同時にそれは採用活動において自社をアピールするポイントにもなり得ます。
ライフイベントに合わせて自由な働き方を選択できることはいまやトレンドいっても過言ではありません。外から見て魅力的な企業に映ることもあれば、働く側の幸福度や意欲を維持・向上させるためにも、副業の選択肢を与えることは大事なのです。
そして実際に副業を通してさまざまな知識や経験を習得し、還元してもらうことは成果はもちろん、自社に新たな刺激を与え、職場の活性化に寄与する期待が持てます。
一見、中途採用の方に求める要素とそれは似ていますが、(自社で活躍している方の場合)すでに自社のカルチャーになじんでいる分、アドバンテージは前者の方が大きいといえるでしょう。本人のスキルやモチベーションアップにつながれば、結果的に会社の業績にも影響するはずです。このように、副業解禁によって組織・仕事上での好循環を生み出そうと目論んでいる企業も少なくないと考えます。いうなれば、もたらすメリットを理由に解禁に踏み切っているわけです。
副業を解禁する場合の注意点
いざ従業員の副業を公に認める際は、リスクに対処できる環境づくりが求められます。具体的には以下の2点です。
安全配所の義務
企業は従業員の副業・兼業といった働き方や職務内容について把握し、各人の健康状態もしっかり管理しておかなければなりません。仮に問題が認められた場合、副業・兼業を速やかに禁止あるいは制限できるよう体制構築が必要です。くれぐれも働く側の安全・安心面を脅かすことがないよう注意しましょう。
秘密保持義務の徹底管理
再三お伝えしているとおり、業務上の秘密や情報漏洩のリスクが存在する限り、副業の解禁は決して安易に行えるものではありません。そうした前提を踏まえたうえで副業を認める場合、結局は各々の良心や意識に依存することになりますが、注意喚起の徹底だけでなく就業規則のなかで厳格なルールを設けた方がよいでしょう。
副業禁止の違法性だけでなく解禁のメリット・デメリットまで把握しよう

副業を禁止することは違法性こそないにせよ、企業内外からの評価やイメージが変わってくるため、可能な限り慎重に判断したいところです。副業制度は活用次第で企業と従業員の双方にメリットをもたらしてくれる一方、デメリットが生じるケースも念頭に置く必要があります。いずれにせよ禁止も解禁も安易に打ち出すことがないよう拙稿で伝えたポイントを整理したうえで決断できると望ましいでしょう。
さて、組織の活性化にはアルバイトの存在も有効です。なかには副業を考えている優秀な人材もいらっしゃるかもしれません。そうした方々との接点機会創出をバリエーション豊富なディップのサービスがお手伝いします。気になる方はまず、内容についてご確認ください。
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。
【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所
代表 荒武 慎一
同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。