子会社化とは
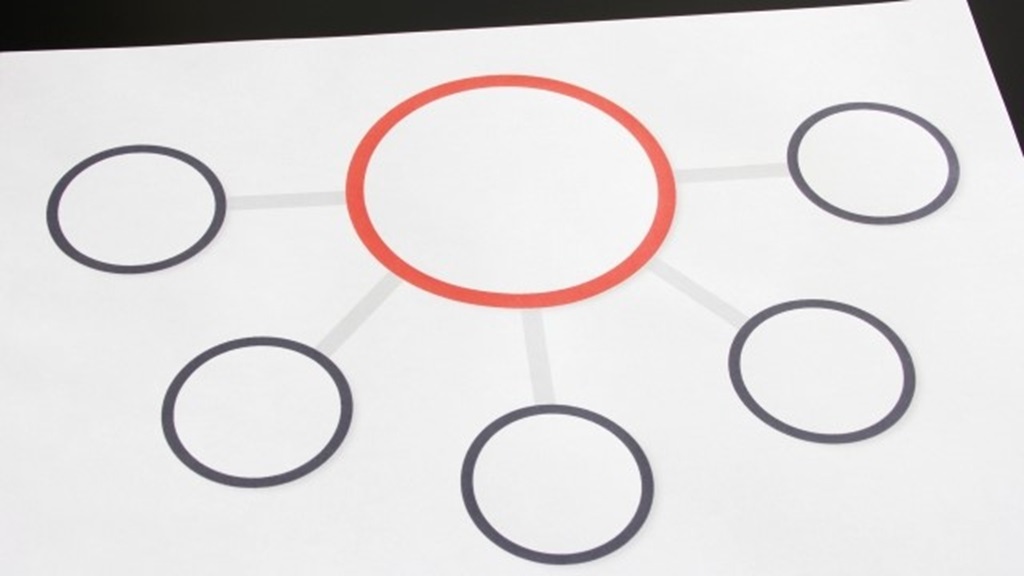
子会社化とは、企業がほかの企業の株式を取得し、その企業を支配下に置きながら法人としての独立性を維持し、(親会社の戦略に沿った)運営を行う形態です。本章ではまず、子会社化の種類と、混同されやすい分社化との違いを説明します。
子会社化の種類
子会社化には、主に完全子会社、連結子会社、非連結子会社の3つがあります。
完全子会社とは、親会社が子会社化する会社の株式を100%保有している状態です。親会社は子会社の経営に対して全面的な支配権を持ち、意思決定が迅速に行えます。
連結子会社とは、親会社が会社の株式の過半数を保有している子会社です。親会社は、その子会社の経営において実質的な支配力を持っています。連結決算もその象徴です。子会社の業績を統合し、グループ全体の財務状況を明確に把握できます。
非連結子会社は、親会社が株式を保有しているものの、連結対象からは外れている子会社です。連結してもしなくてもグループ全体の財務状況にほとんど変化がない場合などに、そう判断されます。
分社化との違い
分社化とは、子会社化と違って、企業が自社の事業の一部を切り離し、独立法人として設立することです。両者は、目指すゴールも異なります。子会社化は、ざっくりいうと、他社を取り込むことで企業の資産基盤を強化し、技術力や顧客基盤の共有、新規市場への参入など、互いの強みを生かして企業全体の成長を促すことが狙いです。他方、分社化は、特定の事業を独立させることで事業の専門性を高めていきます(部分最適を目的とした効率重視といえるでしょう)。
子会社化のメリット
子会社化のメリットはざっと次のとおりです。
- 迅速な意思決定
- 節税対策が可能
- リスクの分散
- 組織の活性化
以下、それぞれ説明します。
迅速な意思決定
子会社化すると親会社が経営方針や戦略を一元的に決定できるため、市場の変化や競争環境にタイムリーに対応しやすくなります。特に、親会社と子会社が緊密に連携している場合、意思決定のプロセスが簡素化され、新製品の投入や価格戦略の見直し、大規模な投資判断といった経営上の重要な施策を迅速に下すことが可能です。
節税対策が可能
親会社と子会社の間では、グループ通算制度など特定の制度を利用している場合、所得の通算が可能です。それゆえグループ全体の納税額を最適化し、節税へとつなげることができます。たとえば、子会社が赤字を出した場合も、その損失を親会社の利益と通算すれば、課税される所得を減らせるわけです。
リスクの分散
子会社化すると、親会社が直接関与することなく、子会社を通じて異なる市場や産業に進出できます。そのため、特定の事業や市場に依存することもありません。経済環境や業界内の変化によるリスクを軽減できる点は大きなメリットの一つです。
組織の活性化
子会社化は、既存の事業体に新しい風を吹き込むことになるため、組織の活性化が促進されます。異なる企業文化や経営スタイルを取り入れることは、多様性を伴い、新たな視点やアイデアの獲得にもつながるでしょう。
子会社化のデメリット
子会社化にはデメリットも存在します。ざっと次のとおりです。
- 管理コストの増加
- ガバナンスの複雑化
- のれん代や減損リスクの発生
- 従業員のモチベーション低下
以下、それぞれ説明します。
管理コストの増加
子会社の設立や運営を行う際、財務管理や法務、コンプライアンスの強化が求められます。そのため、これらの業務、役割を担える人材が必要です。結果、採用や育成も含めて、コストが嵩むことになるでしょう。
ガバナンスの複雑化
親会社と子会社、それぞれの経営方針や運営体制が異なる場合、意思決定プロセスが複雑化し、迅速な対応が難しくなることも考えられます。特に、親会社が複数の子会社を持つ場合は、各子会社の状況に応じてガバナンスの実施が欠かせません。これらを踏まえて、管理体制を整える必要が出てきます。
減損リスクの発生
子会社化するにあたって、取得した企業のブランド価値や顧客基盤など、目に見えない資産への対価として、のれん代が計上されます。のれん代は、自社の収益状況や市場の変動により価値が変わるため、定期的に償却または、減損処理が必要です。業績を圧迫するリスクも当然、考えられます。
従業員のモチベーション低下
組織風土の融合は、決してプラスにのみ作用する話ではありません。既存のカルチャーを居心地よく思っていた従業員からすると、ストレスにもなり得ます。役割分担や責任の所在も同様です。変化によって不安が生まれれば、それが仕事への意欲低下につながる可能性もあります。
子会社化の方法
子会社化には、いくつか方法が存在します。具体的には次のとおりです。
- 事業譲渡
- 会社分割
- 株式取得
以下、それぞれ説明します。
事業譲渡
事業譲渡は、企業が特定の事業をほかの会社に移転することです。その際、譲渡対象となる資産や負債、契約、従業員の移転に伴う条件を明確にする必要があります。譲渡先として新会社を設立することで、子会社化が可能です。この方法によって、買い手は譲渡された事業の実質的な運営権を獲得し、売り手は特定の事業からの撤退や資金調達に動きます。
会社分割
会社分割とは、企業が特定の事業部門や資産を切り離して別会社に分割する手法です。主に吸収分割と新設分割の2種類があります。
吸収分割
吸収分割は、分割元の事業部門をほかの既存会社に移す方法です。具体的には、親会社が保有する資産や負債、契約関係を、子会社が包括的に引き継ぎます。
新設分割
新設分割は、分割元の事業を新たに設立する会社に移す方法です。株式は親会社が保有し、子会社(新たに設立される会社)が事業を展開します。
株式取得
株式取得とは、ある企業がほかの企業の株式を購入することによって、その企業の経営権や支配権を獲得する手法です。主に株式交換、株式譲渡、株式移転の3つの方法があります。
株式交換
株式交換は、既存の株主が所有する株式を親会社の株式と交換することです。親会社は子会社の経営権を取得し、株主は親会社の株式を所有します。
株式譲渡
株式譲渡は、既存の株主が保有する株式を特定の買い手に売却することです。迅速な経営権の移転を可能とし、買い手は直接的に子会社の株主となります。
株式移転
株式移転は、複数の企業が共同で新たに持株会社を設立し、その持株会社が各企業の株式を保有する形態です。この結果、各企業は持株会社の完全子会社となり、統合された経営体制が構築されます。
子会社化する一連の流れ(一例)
メリット・デメリット、そしていくつかの手段も踏まえて、いざ子会社化を進める場合、一例として次の流れが考えられます。
- 基本方針の決定
- スキームの選定
- デューデリジェンス
- 契約書の締結
- 登記手続き等の実務対応
- 関係者への説明・調整
- 子会社としての運営開始
以下、それぞれ説明します。
基本方針の決定
まずは基本方針を決めましょう。子会社化の必要性を社内でしっかりと検討したうえで、具体的に解決したい経営課題(例:事業の選択と集中、人材の最適配置、新規市場への参入)を洗い出していければ、自ずと定まってくるはずです。経営陣や関係部署間での共通理解を前提に、長期的な成長戦略における子会社化の貢献度合いをどう指標に落とし込めるかがカギを握るでしょう。
スキームの選定
続いてスキームの選定です。子会社を新たに設立するか、既存会社を買収するか、会社分割を行うか……等々、前項で定めた基本方針に沿って選べるとよいでしょう。選択事業のスケールや市場環境、資金調達の計画もセットで考えられると、最適解を導き出せるはずです。
デューデリジェンス
デューデリジェンス(Due Diligence)とは、企業が子会社化や買収を行う際に、対象企業の財務状況、法的リスク、ビジネスモデルなどを詳細に調査・分析するプロセスを指します。そこで浮き彫りになるリスクや問題点を把握し、意思決定や条件交渉に役立てることが目的です。たとえば、帳簿に記載されていない負債がないか、訴訟リスクが潜んでいないか、収益構造に無理がないか、といった点を専門家が精査します。子会社化に安心して踏み切るためには、どうしても欠かせないと考えます。
契約書の締結
次に契約書の締結です。ここには、譲渡価格や支払い方法、株式の譲渡条件、事業運営の方針、役員構成などが具体的に記載されます。交渉事ゆえに弁護士や公認会計士のサポートを仰ぐことも大事です。
登記手続き等の実務対応
新たな子会社としての法人格を法的に確立するためには、商業登記簿に必要な変更を行わなければなりません。その際、会社の目的や商号、代表者の変更、資本金の増減など、各種情報の届け出が必要です。さらに、許認可が必要な業種の場合、新たな許認可の取得や既存許認可の名義変更も併せて行います。
関係者への説明・調整
従業員に対しては、子会社化の目的やその背景、具体的な影響などを明確に説明し、不安を和らげることも欠かせません。また、従業員のモチベーション低下を防ぐためにも、今後のキャリアパスや待遇についても丁寧に説明しましょう。
取引先に対しては、取引条件や契約内容に変更がないことを確認し、業務の継続や業務手順、連絡体制をなるべく細かく共有することが大事です。顧客に対しても同様。品質、納期、サポート範囲……等々、不安を生じさせないよう十分な配慮が必要です。
子会社の運営開始
子会社化には、自立して業務を運営できる環境の構築が必要です。たとえば、子会社の経営陣には、中長期的な目標を掲げ、その実現に向けて具体的な事業計画を策定・推進できるリーダーシップが求められます。加えて、業務プロセスや情報管理の徹底も重要です。会社間のコミュニケーションを円滑に保つには、双方の経営方針がブレない体制を整えることが欠かせません。手続きを終えてもなお、子会社化にはこうした細かな意識がひたすらつき纏います。
子会社化で失敗しないためのコツ
どれだけ入念にステップを踏んでもなお、うまくいかないことは出てきます。特に、ただ漠然と進めてしまうのは注意が必要です。本章では少しでもそのケースを減らすべく、いくつか子会社化のコツを紹介します。
移行業務の優先順位を明確にする
子会社化に際して課される業務については、それぞれの重要度と緊急度を見定める必要があります。契約関係、システム対応などを後回しにしてしまっては大きなトラブルになりかねません。てんやわんやにならぬよう、優先順位を明確にすることは非常に大事です。
社内外で良好な関係構築に注力する
親会社と子会社の間で信頼関係が築けていなければ、経営方針がすれ違い、事業運営に支障をきたす恐れがあります。また、既存社員の不安や反発を放置すれば、モチベーションの低下や人材流出も考えられるでしょう。同様に、再編により影響を受ける取引先に対しても、最初の内は特に状況の説明が求められます。
総じて、子会社化は周囲との関係をどう整えるかが肝です。制度理解やスムーズな手続き以上に成否を左右するといっても、決して過言ではありません。
意思決定と現場裁量の線引きを早めに行う
どこまでを親会社が判断し、どこから先を子会社に委ねるのかは早い段階ではっきりと線引きしておきましょう。責任の所在がわからなくなることもさることながら、何より事業を前進させられないことが大きな問題だと考えます。仮にこれが明瞭であれば、親会社は全体戦略に集中でき、子会社も自律的な運営に専念できるはずです。
立ち上げ期の人材確保に求人サービスを活用する
子会社化の立ち上げ期には少なからず人材確保が必要です。なおかつ、スムーズに募集するならやはり求人サービスは活用しておきたいところでしょう。なお、dipの場合は、さまざまなニーズに特化したラインナップが特長です。
たとえば、『スポットバイトル』は、スポットワーカーをターゲットにしているため、一時的であれ、即日、人員補充が見込めます。
また、長期的に活躍する人材なら社員採用に強い『バイトルNEXT』がおすすめです。
さらに、『バイトルPRO』ならスキル、経験が十分な即戦力人材と接点が図れます。 子会社化にあたり、人手不足に困ったなら、このようにバリエーション豊富なdipの求人サービスをぜひ、ご利用ください。
子会社化のポイントまとめ
子会社化には、迅速な意思決定やリスク分散などが期待できる一方で、管理コストやガバナンスの複雑化といった課題にも向き合わなければなりません。また、制度や手続きに対する理解だけでなく、関わる方との信頼構築も大切です。加えて、人材確保にも目を向けましょう。適切なサービス選定もまた、子会社化を進めるうえで大事なアクションです。
つまるところ、子会社化は場当たり的でなく、全体を見据えることが求められます。視野を広げた分、描ける未来もきっと変わってくるはずです。
求人掲載・採用業務のサポートや料金についてなど、ぜひ気軽にお問い合わせください。
また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談も無料で承っております!
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【公式】空いた時間のスポットワーカー募集ならスポットバイトル
┗空いた時間で「働きたい」と「働いてほしい」をつなぐ求人マッチングサービス。求人は無料で掲載できます。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。
▶【公式】面接コボット – 応募者対応の自動化で面接管理が楽に!
┗求人サイトからの応募対応を自動化できるサービス。チャットボットを通じ、日程調整まで効率よく進めてくれます。
▶【公式】採用ページコボット – 費用・実績も紹介!採用サイト制作サービス
┗採用ページ作成サービス。求人まとめサイトとの自動連携や求人検索エンジンへの対応により外部集客を強化します。
【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所
代表 荒武 慎一
同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。

