労働者名簿とは?
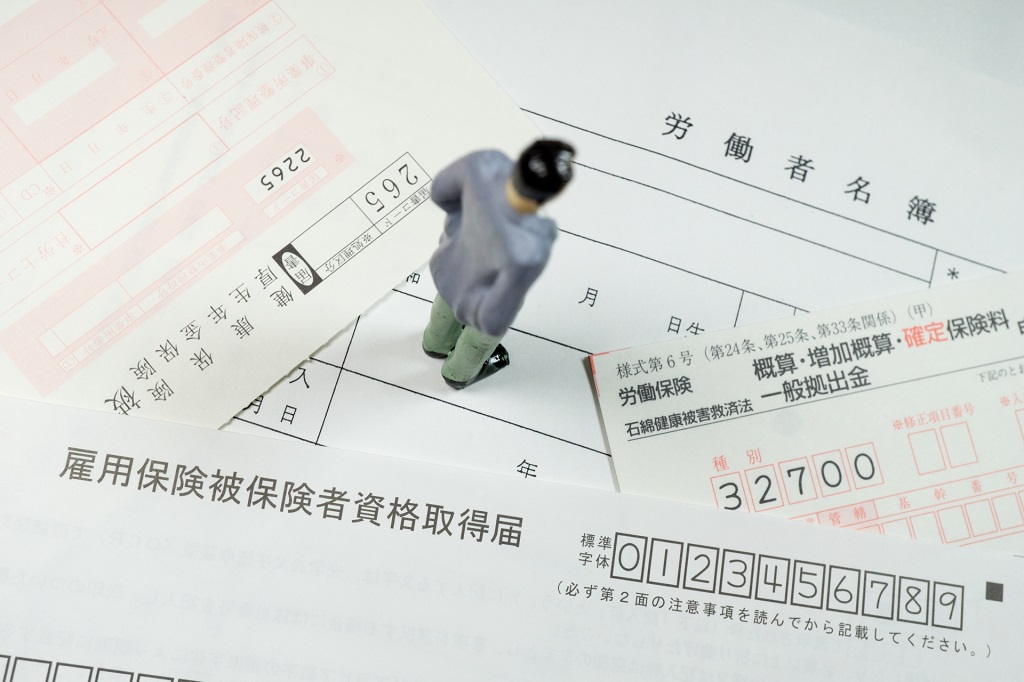
そもそも労働者名簿とは何でしょうか? まずは基本概要をお伝えします。
法定三帳簿の一つ
冒頭でもお伝えしたとおり、労働者名簿とは、労働基準法で定められた法定三帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)の1つです。労働基準監督署の臨検時には、速やかな提出が求められます。企業側が労務管理を正しく行っていることを証明する大事な書類です。
各事業所ごとに、労働者一人ひとりの分が作成され、情報の変更があれば随時調整が入ります。
また、従業員にもしものことがあった場合にも重要です。たとえば、業務の一環で事故や病気に見舞われたとき、労災にあたるかどうかを調べるうえでも使われます。
労働者名簿の対象者
労働者名簿の記載対象は、日雇い労働者を除く、正社員、契約社員、アルバイト、パートタイムの方々です。
他方、派遣社員は、賃金管理など派遣元の会社が行うため、派遣先では労働者名簿の記載は必要ありません。
誤解されやすいのが代表者と役員に関してです。労働基準法の定義上、労働者ではないため、労働基準監督署の調査においては対象外に当たるのですが、社会保険事務所からは被保険者がゆえに調査対象に含まれます。したがって、労働者名簿や賃金台帳の作成が必要です。
また、労働者名簿の作成は、雇用形態による免除がありません。そのため、一日だけの短期アルバイトを採用した場合も、(労働者名簿を)作成・保管の義務が発生します。
労働者名簿の書き方、更新・変更について
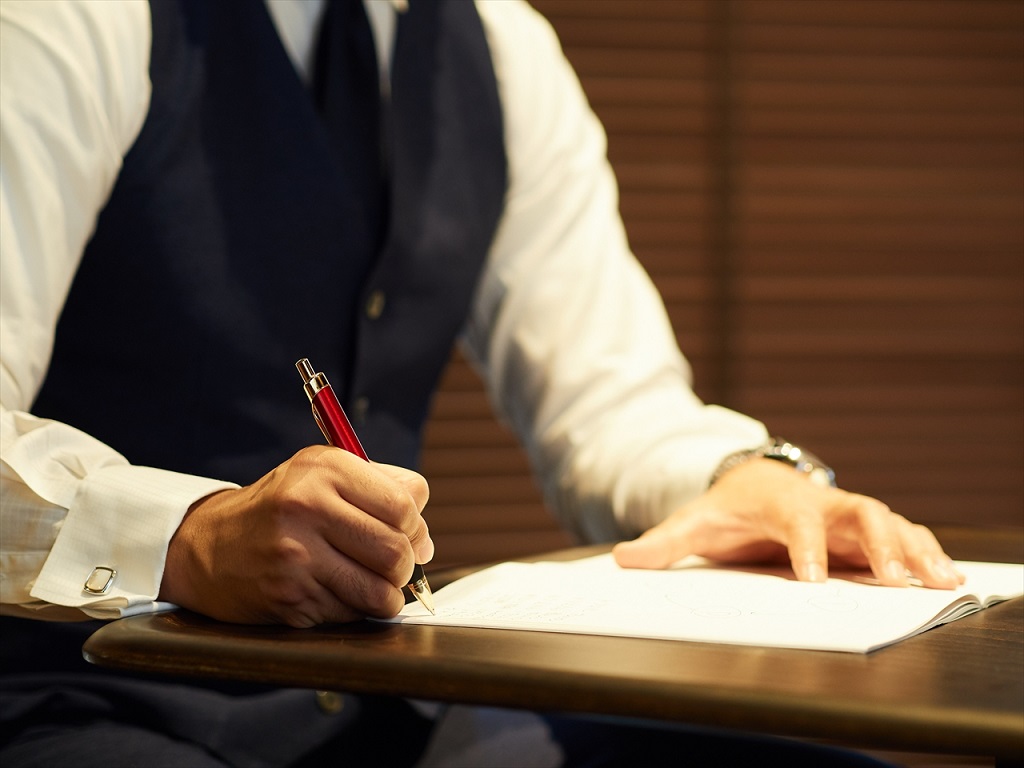
本章では、労働者名簿の書き方と更新・変更方法について解説します。
労働者名簿への記載について
労働者名簿に最低限、記載すべき項目は下記の8つです。
- 労働者の氏名
- 生年月日
- 履歴
- 性別
- 住所
- 従事する業務の種類
- 雇入れの年月日
- 退職した年月日およびその事由(解雇の場合はその理由)
従業員数が30人未満の組織は「従事する業務の種類」の記載を省略できます(労働基準法施行規則 53条2項)。
労働者名簿の記載項目には法令の定めがありますが、書式は問いません。記載内容に漏れがなければ、独自の様式を用いることが可能です。
また、紙であれデータであれ問題なく使用できます。とはいえ、安全に管理しやすいタイプのものを選ぶとよいでしょう。
なお、書面は厚生労働省のサイトからもPDFで入手できます 。
労働者名簿の内容更新・変更
労働者名簿は労働基準法により、従業員の退職や解雇、死亡の日を起点として5年間の保存が義務づけられています。そして、そのなかで適切に運用・管理することが求められています。というのも、労働基準法第107条第2項に「記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。」と書かれているからです。企業側はすぐに労働者名簿を修正し、内容を最新の状態にしておく必要があります。
なお、労働者名簿を紙で保管している場合は、変更した箇所に二重線を引き、訂正印を押してから新たな情報を記載するようにします。アルバイトやパートが多い企業だと特に慌ただしくなりがちです。タイムリーに対応すべく、細心の注意を払いましょう。
労働者名簿の保存期間と保管方法

続いて労働者名簿の保存期間や保管方法について説明します。組織体制あるいは時代が進むにつれてやり方が変わってくるのも当然です。自社の環境と照らし合わせつつ参考にしてみてください。
労働者名簿の保存期間
労働者名簿は、決して常に公的機関への提出が義務づけられているわけではありませんが、労働基準監督署の調査が入り必要になるケースは十分に考えられます。いうまでもなく、適切に管理しておくことは必須です。
前述のとおり、労働基準法では従業員の退職や解雇、死亡の日を起点として5年間の保存が義務づけられているわけですが(改正前は3年間でした)、この期間に対して思いのほか長いといった声を聞くこともあります。このように管理に神経を使う担当者が少なからずいらっしゃる事実。在職中の従業員の名簿との混同など、確かに煩わしい側面は容易に想像できます。そうした面倒を避けるためにも、従業員の退職や解雇の際には別のファイルを作り、そこで保管するとよいでしょう。
労働者名簿の保管方法
前項に加え、人事担当者が保管に手を焼く理由としては、労働者名簿が事業所ごとの作成を義務づけられている点も挙げられます。
そうした背景を踏まえ、労働者名簿の保管方法について以下2つの観点からお伝えします。
支店や事業所が複数ある場合の保管方法
繰り返し述べますが、複数の事業所を持つ企業の場合、労働者名簿は各拠点分を作成することが労働基準法によって義務づけられています(本社で一括作成したものを事業所に配布するやり方でも構いません)。
無論、このとき気を付けたいのが保管です。一括管理とは違って事業所の数だけリスクが生じます。セキュリティ面の強化は至上命題です。したがって、会社全体で教育や指導の機会が必要でしょう。
電子データで作成した場合の保管方法
保管方法は、企業によってさまざまです。
そのなかで近年は、電子データでの取り扱いが主流だといえます。管理のしやすさ、安全性を考慮すれば、必然かもしれません。
ただし、労働者名簿を電子化するにあたっては、以下の条件を満たす必要があります。
| <労働者名簿の電子化条件> ・労働者名簿に記載すべき事項が書かれており、事業所ごとにそれぞれの労働者名簿を画面に表示し、印字するための装置を備えておくこと ・労働基準監督署の立ち入り調査などで労働者名簿の閲覧・提出を求められた場合に、即座に必要事項が明らかになっている写しを提示できるシステムになっていること |
労働者名簿の取り扱いの注意点

ただ漠然と労働者名簿を取り扱ってしまってはトラブルを招く恐れがあります。そうならないためにも、本章にて注意点をお伝えします。
個人情報・プライバシーの取り扱い
労働者名簿に記載されている内容は、個人情報に当たります。記載情報を活用する担当者がすぐにアクセスできる環境は確かに理想的ですが、誰でも簡単に閲覧できる状態はさすがに問題です。そのため、労働者名簿へのアクセス権限を調整する必要があります。たとえば、アクセスできるユーザーを特定の社員に限定したり、彼・彼女らに対しても権限範囲を閲覧あるいは編集作業までにとどめたりと、細かく設定すると安心です。
印刷できる環境も必要
電子データで保管するのが一般的だといえるなか、ときに印刷できる環境が欠かせないケースに出くわすことがあります。というのは、労働基準監督署の立ち入り調査が入った際に、紙での提出を求められることがあるからです。電子データで管理している場合は、紙でも提出できるよう印刷環境を整備しておきましょう。
労働者名簿の書き方や管理について正しく把握しよう
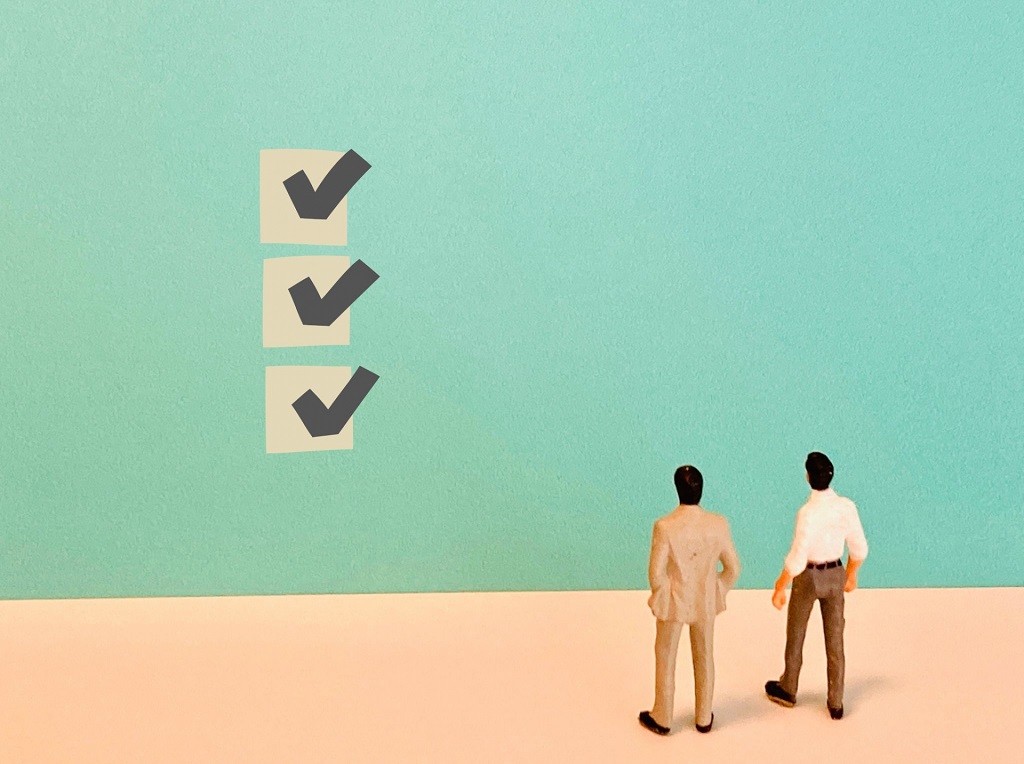
ここまで色々と述べてきましたが、つまるところ、労働者名簿は、企業が適切な労務管理を行うためのものです。いうなれば、正しく作成しているかどうかで、企業に対する労務管理の評価にもつながります。
更新のタイミングや保存期間、保管方法、リスクヘッジ……諸々、曖昧な感覚で対応しないよう気を付けましょう。
さて、労働者名簿の取り扱いはもちろん大事ですが、そのほか従業員の管理や採用に課題を感じる企業の担当者も少なくない印象です。打ち手を探している方はぜひ、ディップの求人広告サービスをおすすめします。目的やターゲットとする求職者によって使い分けも可能です。各サービスサイトをくまなくご確認のうえ、検討ください。なお、お問い合わせは無料です。
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。

