労働条件の明示義務とは

労働条件の明示義務とは、使用者が労働者に対して、賃金や勤務時間などを明らかにしなければならないことです。これは、労働基準法15条に記載されています。法的規制が設けられている以上、明示義務を果たすことは必須です。違反すれば当然、ペナルティが科されます。まず本章では、労働条件の明示義務について確実におさえておくべき内容にフォーカス。義務化されている理由や応じない場合の罰則に加えて、絶対的、相対的に分類される各明示事項にも言及します。
明示の義務化が必要な理由
企業側が条件を明示しなければ、従業員とのあいだに認識のずれが生じることは容易に想像できます。そうなるとやはり、労働者からは不満の声が上がり、トラブル勃発は避けられません。しかもこの場合、雇用する側とされる側の関係上(両者のパワーバランスを加味すると)、後者が不利益を被る可能性が高いと思われます。そうならないためにも、業務内容や待遇などを明らかにすることは必然です。従業員も安心して働けるでしょう。
労働基準法での明示義務に関する内容と罰則
繰り返しますが、労働条件の明示は遵守が絶対です。違反に対する危機意識も含めてその認識が希薄なままでいると、痛い目に遭いかねません。したがって、労働基準法で記されていることや罰則はしっかり念頭におく必要があります。以下、労働条件の明示が該当する労働基準法15条の内容です。
労働基準法15条(労働条件の明示)
1.使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2.前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3.前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法はすべての従業員に適用されます。したがって、労働条件の明示義務も、正社員やアルバイト・パートなど雇用形態を問いません。
▶関連記事:雇用契約書とは?アルバイトにも無いと駄目?記載事項や注意点も解説
仮に労働条件を明示しなければ、労働基準監督署から指導や是正勧告を受けます。それでも改善が見られない企業に対しては、30万円以下の罰金が処される規定です(労働基準法120条)。
もちろん、内容が事実と反してはいけません。相違する場合、2項で書かれているとおり、労働者は契約をすぐに解除できるようになります。
明示する労働条件の種類
明示する労働条件は大きく2つに分かれます。それは、絶対的明示事項と相対的明示事項です。前者が明示必須の項目であるのに対して、後者は社内制度などに応じて(明示が)求められます。
※(2023年現在)労働基準法施行規則5条では、使用者が明示すべき具体的な労働条件について次のように記載されています。
労働基準法施行規則5条
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七 安全及び衛生に関する事項
八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十 表彰及び制裁に関する事項
十一 休職に関する事項
絶対的明示事項
絶対的明示事項は、原則、(昇給に関することを除いて)書面で交付しなければなりません(労働者が希望した場合は、書面として出力できるものに限りFAXやWebメールサービスなどで明示することもできます)。
具体的には次のとおりです。
- 契約期間に関すること
- 期間の定めがある契約を更新する場合の基準に関すること
- 就業場所、従事する業務に関すること
- 始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること
- 賃⾦の決定⽅法、⽀払時期などに関すること
- 退職に関すること(解雇の事由を含む)
- 昇給に関すること
なお、パートタイム労働法によって、短時間勤務のアルバイトや期間の定めを取り交わしている有期労働契約者に対しては、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「雇用管理の改善などに関する相談窓口」も明示する必要があります。
▶関連記事:パートタイム労働者、パートタイム労働法とは?【パート雇用の前提知識】
相対的明示事項
定めを設けた場合に明示しなければならないのが相対的明示事項です。ずばり以下の項目が該当します。
- 退職手当に関すること
- 賞与などに関すること
- 食費、作業用品などの負担に関すること
- 安全衛生に関すること
- 職業訓練に関すること
- 災害補償などに関すること
- 表彰や制裁に関すること
- 休職に関すること
相対的明示事項については、口頭で明示することも許されていますが、できる限り書面での交付が望ましいと考えます。
2024年4月、労働条件明示のルールが改正!

冒頭でも述べましたが、2024年4月より労働条件明示のルールが変わります。これは前述した労働基準法施行規則5条の改正によるものです。労働者と使用者のあいだで認識に齟齬が生じないよう、また、有期雇用者の無期転換をめぐってトラブルが起きないよう、明示事項に新たに4項目が追加されます。いうまでもなく、事業主そして人事・労務担当者の方々は、このルール変更についてあらかじめ内容を把握しておかなければなりません。以下、背景と目的を伝えたうえで、新しく追加される明示事項の詳細、施行日までの対応について説明します。
ルール改正の背景・目的
労働条件明示のルール改正は、厚生労働省による「多様化する労働契約のルールに関する検討会」のなかで約1年のあいだ議論されてきたものです。そもそもの目的は、端を発した2021年3月に議題として挙げられています。それはずばり、有期契約労働者の無期転換ルールの見直しと、多様な正社員の雇用ルールの明確化です。
有期契約労働者の無期転換ルールの見直し
無期転換ルールとは、同一企業(使用者)がアルバイト・パート、契約社員といった有期契約労働者の方を、通算5年を超えて雇用(有期契約)した場合に、労働者側の希望に応じて、文字どおり無期契約へと転換することを指します。
これまでも改正労働契約法にて、有期労働契約で働く人たちの雇い止めに対する不安の解消、処遇の改善が図られていましたが、この制度の理解促進や認知度向上につなげるべく、ルールの見直し検討に至ったというわけです。
関連記事:無期雇用派遣とは?メリット・デメリットや戦略、注意点を解説
多様な正社員の雇用ルールの明確化
2019年に閣議決定された規制改革実施計画では、勤務地限定正社員や職務限定正社員といった「多様な正社員」の雇用ルールを明確化することが含まれていました。無期転換ルールによって無期雇用に変わる社員の重要な受け皿の1つとしても期待されるなか、実態調査などを経て、上述した検討会において議論が交わされることになります。
追加される4つの労働条件明示事項
厚生労働省が、労働条件の明示を義務付ける4つの項目は次のとおりです。
- 就業場所・業務の変更の範囲
- 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
- 無期転換申込機会
- 無期転換後の労働条件
以下、それぞれ詳細を説明します。
就業場所・業務の変更の範囲
すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新時には、雇い入れ直後の就業場所及び従事すべき業務内容に加え、“変更の範囲”まで明示が必要になります。これは、将来的に配置転換の可能性がある就業場所・業務を指します。検討会の報告書にあるように、企業なら、勤務地や勤務時間などに制約のある優秀な人材の確保・定着につながり、他方、労働者からすると、ワーク・ライフ・バランスの実現や希望のキャリア形成を図れる点などは、やはりメリットです。さらには、労使が労働条件を確認し合う契機になり、紛争の未然防止効果も期待できると考えられています。
更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
更新上限については、設定が違法ではなくとも、いくつか課題が挙げられてきたのも事実です。たとえば、更新上限の有無が不明確であれば、契約更新や無期転換の期待を抱く労働者が出てくるのは容易に頷けます。そうなると、仮に認識のずれがあった場合はトラブルに発展しかねません。また、更新上限を最初の契約締結より後で新たに設定することも、紛争の火種になり得ます。少なからず更新を期待する労働者からしてみれば、寝耳に水。不利益を被ったと捉えるのも無理はないという指摘です。
というわけで、有期労働契約の締結と契約更新において更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。
これは、いわば先に挙げた課題の解消策です。そして気を付けたいのは、明示するタイミングです。最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、それ以前にその理由を労働者に説明しなければなりません。契約更新時の条件設定によって、労働者が同意を余儀なくされるケースへの懸念も、このルール改正にはつながっています。
実際に無期転換ルールに関する論点についてまとめられた報告書では、過去の司法判断をもとに「使用者が更新上限の有無及び内容の明示をしたことや労働者が更新上限条項に異議を唱えず契約更新に応じたことのみでは、更新上限について有効な合意が成立したとは認められず、更新の合理的期待は必ずしも消滅しない」ことが言及されています。
無期転換申込機会
厚生労働省が公表している「令和3年有期労働契約に関する実態調査(個人調査)」では、有期契約労働者のうち、労働契約法における無期転換ルールに関する知識について、その内容(“契約社員やパート、アルバイト、再雇用者など呼称を問わず、すべての労働者に適用される”“契約期間を通算して5年を超えても、労働者から「申込み」を行わなければ無期転換されない”“無期転換ル-ルが適用されるのは、平成25年4月1日以降に開始(更新)された、有期労働契約である“など)を1つでも知っていると回答した割合は38.5%と記されています。これを受けて「無期転換ルールの認知度が低いゆえに、無期転換申込権を行使しない労働者が高い割合で存在しているのではないか」との指摘もありました。
今回の改正によって、企業は「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)を明示しなければならなくなります。その目的は、上記を踏まえても察せるとおり、個々の労働者が自社の無期転換制度を理解したうえで、無期転換申込権の行使(するか否か)を主体的に判断しやすくすることです。と同時に、紛争の未然防止につなげる狙いもあります。
無期転換後の労働条件
無期転換後の労働条件が曖昧なことを理由に、無期転換するかどうかをためらう労働者も少なくないでしょう。今回のルール改正では、労働者が適切に権利を行使できるよう、使用者は「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を明示することが義務付けられています。加えて、労働契約法第3条第2項に規定されている内容(労働契約の原則)を踏まえ、就業の実態に応じ、ほかの従業員ら(いわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者)との均衡を考慮した事項(“業務の内容”“責任の程度”“異動の有無・範囲”など)について説明するよう努めなければなりません。不合理な待遇差を設けることを禁止する意味では、同一労働同一賃金の明確化につながるルールともいえそうです。
労働条件明示の新ルール施行までに必要な対応
先述したとおり、絶対的明示事項については書面での交付が義務づけられています。今回の改正にあたり、この書面も部分的には変更が必要です。とはいえ、厚生労働省はすでに、改正後の労働条件通知書のサンプルを公表しています。自社で作成する必要がなければ、そのまま活用してもよいでしょう。いずれにせよ、早いうちに適応した書式を準備しておくことが肝要です。
労働条件通知書の変更箇所
厚生労働省が公表している新たな労働条件通知書ですが、労働者全般と有期契約労働者に関する項目がそれぞれ追加されています。前者に該当するのは、先述した就業場所・業務の変更の範囲です。1枚目に“雇入れ直後”と“変更の範囲”の枠が設けられているのに加え、2枚目の下部でも記入箇所( “以上のほかは、当社就業規則による。就業規則を確認できる場所や方法” )がご用意されています。他方、有期契約労働者向けに足されたのが、“契約期間のなかにある更新上限の有無”の枠です。
くわしくは、こちらのテンプレートをご参照ください。
▶2024年4月以降の労働条件通知書(一般雇用型 常用 有期)
労働条件の明示義務を理解し、改正に備えよう
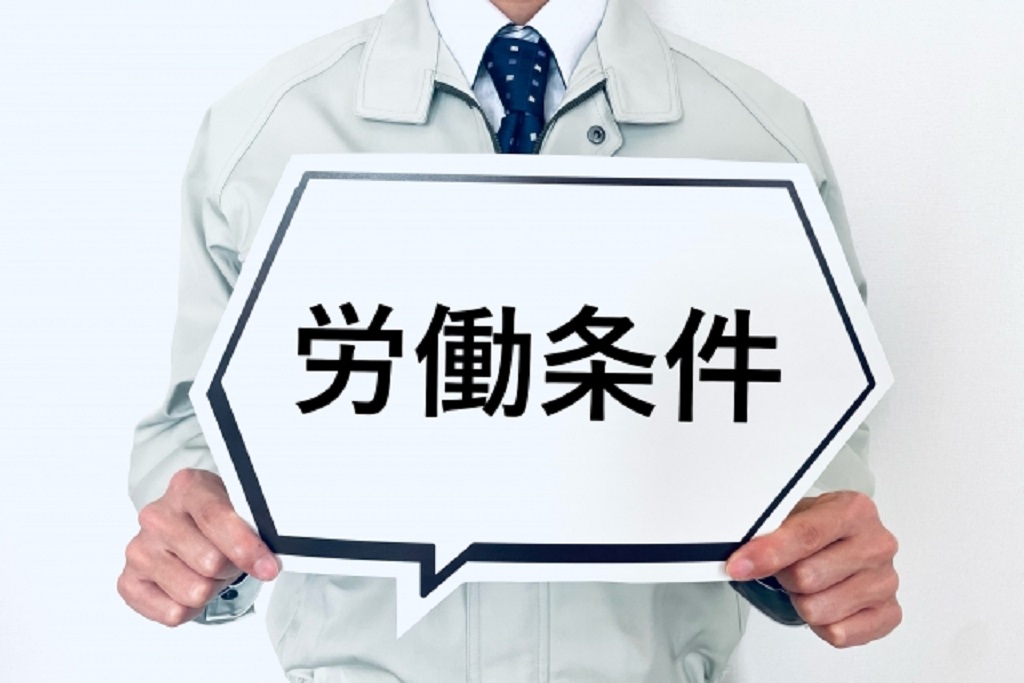
労働条件の明示は使用者の義務です。2024年4月から追加される新たな項目についても抜け洩れが無いよう事前に情報を把握しておく必要があります。一方で漠然とした理解では、トラブルに巻き込まれることも懸念されます。どのような経緯や意図があって改正されるのか、一連の流れもしっかりおさえておきましょう。
そのうえで、今一度、自社の雇用形態別に労働条件を見直すことが大切です。
なお、今回の法改正については、厚生労働省のパンフレット「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」で網羅的に整理されています。そのほか、「令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A」も資料として役立てられるはずです。曖昧さや不安な部分を解消すべく、併せてご覧ください。
さて、労働条件を巡って慌ただしくなるなか、採用業務の効率化・簡素化に向けた動きも、遅かれ早かれ必要に迫られることになるでしょう。新たな明示義務を遵守し、適切に対応すべく、計画的に準備を進めていくことが求められます。
dip(ディップ)では、求人サービスを通した人材採用の支援やDXサービスによる業務自動化など、労働市場における諸課題の解決に向けて取り組んでいます。興味・関心いただけましたら、まずは気軽にお問い合わせください。
【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所
代表 荒武 慎一
同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。

