企業が高齢者雇用に注力する背景と現況

高齢者雇用の重要性が増している背景には、労働力人口の減少や政府の施策、そして高齢者自身の就労意欲の高まりがあります。本章ではまず、それらについて言及。データが導き出す具体的な数字も参考にしながら、現況の把握にお役立てください。
高齢化社会は加速する一方
統計局の「高齢者の人口」の調査では、2022年9月15日の時点で高齢者人口(65歳以上)は3627万人に達しています。このとき、総人口に占める割合は29.1%でした(過去最高を記録)。この傾向が加速するのは、もはや免れません。国立社会保障・人口問題研究所の推計(「日本の将来推計人口」)によると、2060年には総人口の約4割が65歳以上になると予想されています。しからば、生産年齢人口(15~64歳)の大幅な減少も当然見込まれているわけです。東京都主税局(「全国の将来推計人口」)の見立ては、2030年に6,773万人まで減少するだろうとのこと。2015年は7,682万人でした。わずか15年で約1,000万人減ってしまうとなると、いうまでもなく労働市場に大きな影響をもたらすでしょう。
企業における定年制の状況
高年齢者雇用安定法の改正により、企業は65歳までの高年齢者雇用確保措置を講じることが義務付けられています。なお、厚生労働省が公表している「高年齢者雇用状況等報告」では、令和5年は定年を65歳以上に定めている(定年制の廃止も含む)企業が30.8%まで伸びている模様。多くの企業で高齢者雇用に対するスタンスが変わり、取り組みが見直されていることがわかります。
| 区分 | 割合 |
|---|---|
| 定年制を廃止している企業 | 3.9% |
| 定年を60歳とする企業 | 66.4% |
| 定年を61~64歳とする企業 | 2.7% |
| 定年を65歳とする企業 | 23.5% |
| 定年を66~69歳とする企業 | 1.1% |
| 定年を70歳以上とする企業 | 2.3% |
高年齢常用労働者の状況
高年齢者の就業状況も変わってきています。厚生労働省が公表している「高年齢者雇用状況等報告」によると、60歳以上の常用労働者数は約486万人でした。全常用労働者の13.8%を占めています。さらに細かく紐解くと(年齢階級別に見ると)、60~64歳が約262万人、65~69歳が約130万人、70歳以上が約93万人といった具合です。
そのほか、31人以上規模企業における60歳以上の常用労働者数が、2014年と比較して約170万人(59.0%)増加している点も無視できません。これは高齢者の就労意欲の高まりや企業側の受け入れ態勢の整備が進んでいることを示唆しています。
高年齢雇用の価値あるメリット

高齢者雇用は、さまざまな面で企業に価値をもたらします。主なメリットは次のとおりです。
- 人手不足の解消
- ダイバーシティの実現
- 経験・スキル、人脈活用による組織力アップ
- 国からの助成金支援
以下、それぞれ詳述します。
人手不足の解消
労働力人口の減少が進むなか、高齢者雇用は人手不足を解消する有効な手段になり得ます。昨今、65歳以上の就業者数及び就業率は上昇傾向にあり、特に65歳以上(の就業者数)は20年連続で前年を上回っている状況です(参照:内閣府「令和6年版 高齢社会白書(全文)」)。人材確保に苦戦しているのであれば、働く意欲十分の彼・彼女らをターゲットに定めるのも一つの策でしょう。
ダイバーシティの実現
高齢者雇用は、職場の多様性を高めるうえで重要な役割を果たします。世代の異なる仲間の視点やアイデア、知識は、組織が直面する課題解決に一役も二役も買うはずです。いわゆるダイバーシティが実現できれば、企業ブランドとしての価値も高まるでしょう。
また、高齢者の活躍する姿は若い世代の従業員にとってのロールモデルにもなり得ます。入って間もない方々も含めて、皆がおのずと長期的なキャリアビジョンを描いてくれるかもしれません。すなわち人材定着にも寄与する期待が持てます。
▶関連記事:ダイバーシティ採用とは?企業の取り組み事例やアンケート調査の結果も交えて解説
経験・スキル、人脈活用による組織力アップ
高齢者の方々の経験は非常に貴重です。たとえば、顧客折衝においては、長年培われたコミュニケーションスキルで以て軽やかに対応してくれるものと考えます。また、予期せぬ事態にも、適切な解決策を提示してくれるでしょう。それらは当然、ノウハウとしても機能します。若手に伝承できれば、組織全体の成長につながるはずです。さらには、人脈にも期待できます。豊富なそれをうまく活用できれば、業界における立ち位置も変わってくるかもしれません。
国からの助成金支援
高齢者雇用を推進する企業に対しては、国からの支援制度があります。たとえば「65歳超雇用推進助成金」は、65歳以上への定年引上げや高齢者の雇用管理制度を整備する企業に支給されるものです。
また、「70歳雇用推進プランナー」や「高年齢者雇用アドバイザー」による相談サービスも無料で受けられます。高齢者雇用に不安であれば、ぜひ利用してみてください。
高年齢雇用の問題点に当たるデメリット
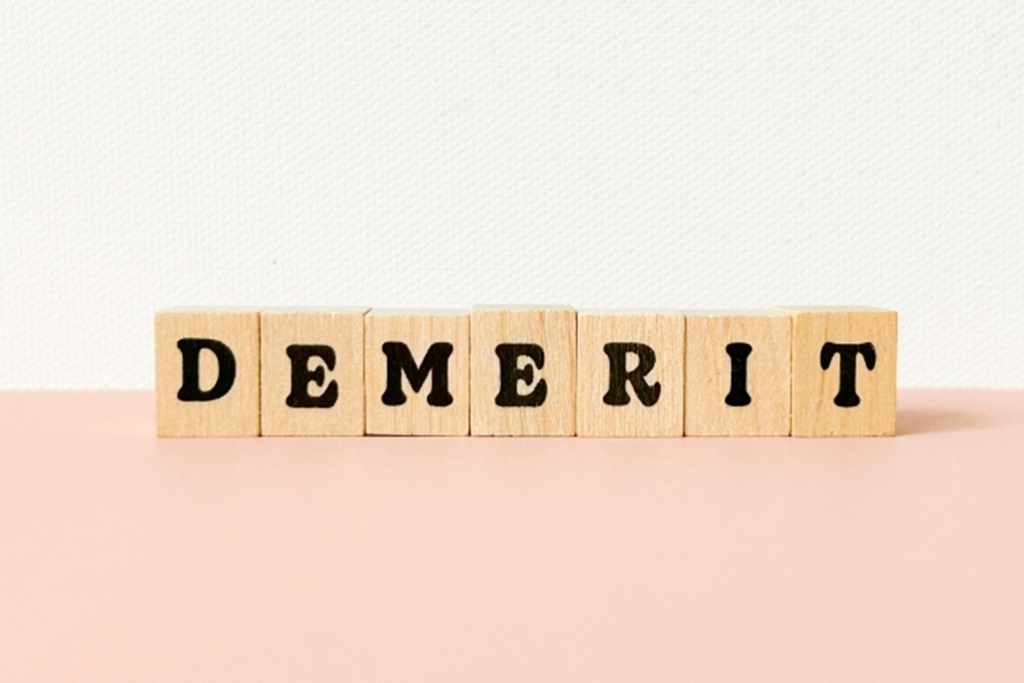
メリットがある一方、高齢者雇用にはいくつか問題点も露見されます。主なデメリットは次のとおりです。
- 体力・体調面の不安
- IT リテラシーに対する懸念
- チーム内コミュニケーションのギャップ
以下、それぞれ詳述します。
体力・体調面の不安
年齢を重ねるにつれ、身体機能の低下は避けられない現実です。高齢者の場合、長時間労働も含めて肉体に負担がかかる仕事は難しいかもしれません。事故につながる危ない場面でも、反射神経の鈍化から最悪の事態を招く恐れがあります。そのリスク、可能性は若年層と比べて明らかに高いでしょう。慢性的に疾患を抱える方についても、欠勤が続くなど、安定しないシフトになることは容易に想像できます。このような状況では、業務効率や職場全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼすことは避けられないでしょう。
ITリテラシーに対する懸念
デジタル技術が急速に発展する現代社会において、高齢者のITリテラシーの問題は無視できません。皆が一様に、苦手にしているわけではありませんが、その割合は年齢が上がるにつれて高くなるものと思われます。たとえば、最新のソフトウェアやデジタルツールの習得に時間がかかるなど懸念されることは多いでしょう。新しいテクノロジーに疎ければ、当然、業務進捗も悪くなるはずです。研修コストも含めて、悩ましい部分だと考えます。
チーム内コミュニケーションのギャップ
世代間の価値観や経験が異なることで、チーム内に軋轢を生むこともないとは言い切れません。経験に対して自負があるからこそ、必要以上に指導的な立場をとる高齢者の方は思いのほか多くいらっしゃいます。そうなると、面白くないと感じるメンバーが出てきてもおかしくないでしょう。また、年齢差による心理的な距離感が、オープンなコミュニケーションを妨げる可能性もあります。これらが職場の雰囲気を悪くさせ、結果、チーム全体のパフォーマンス低下につながるケースは、決して珍しくないのです。
高齢者雇用のデメリットをカバーするために必要な課題

高齢者雇用に伴うデメリットを最小限に抑えるためには、やはり企業側が適切な対応をとっていかなければなりません。まさにそれは、高齢者雇用における課題だといえます。主に挙げられるのは次のとおりです。
- 高齢者が働きやすい環境づくり
- 高齢者のモチベーションを下げない職務分掌
- 高齢者に対する誤解なき理解
以下、それぞれ詳述します。
高齢者が働きやすい環境づくり
高齢者が安全かつ快適に働けるよう、当然ながら、環境の整備は必須です。下表では、「身体的負担の軽減」「安全対策の強化」「健康管理サポート」それぞれについて、具体的な内容をまとめています(これらは、厚生労働省が策定した「エイジフレンドリーガイドライン」に基づき、実施が推奨されている取り組みです)。
| 取り組み | 内容 |
|---|---|
| 身体的負担の軽減 | エルゴノミクスに配慮した作業台や椅子の導入 重量物の取り扱いを減らすための機器の導入 適切な照明や空調の整備 |
| 安全対策の強化 | 滑りにくい床材の使用 手すりの設置 定期的な安全講習の実施 |
| 健康管理サポート | 定期的な健康診断の実施 柔軟な勤務時間の設定(短時間勤務や隔日勤務など) 休憩スペースの充実 |
高齢者のモチベーションを下げない職務分掌
高齢者の経験とスキル、そして意欲に応じて適切な役割を与えることもまた大切です。いわゆる職務分掌をしっかりと行う必要があります。
▶関連記事:職務分掌とは?規程作成に至る手順までわかりやすく解説
シニア採用によって組織の成長を図るのであれば、やはり(高齢者の)生かし方が肝要です。下表では、「スキルと経験の活用」「柔軟な職務設計」「継続的な能力開発」それぞれについて、具体的な内容をまとめています。
| 取り組み | 内容 |
|---|---|
| スキルと経験の活用 | メンター制度の導入(若手従業員の指導役として) 専門的なアドバイザー役の設置 プロジェクトリーダーとしての起用 |
| 柔軟な職務設計 | 個々の体力や健康状態に応じた業務内容の調整 パートタイムや在宅勤務といった働き方の提案 職務の細分化による負担の分散 |
| 継続的な能力開発 | IT研修など、新しいスキル習得の機会提供 自己啓発支援制度の導入 定期的なスキルアセスメントと適切なフィードバック |
高齢者に対する誤解なき理解
高齢者に対して、先入観で接することは危険です。固定観念や偏見に縛られてしまっては、採用活動の段階から事を思うように運べないでしょう。
dipの調査によると、定年後も働きたいと考える55~79歳の男女は約6割に上り、そのなかでも半数以上が同じ業種・職種での就労を希望されています。また、勤務時間の要望については、8時間以上が半数以上いたというから驚きです。
前述したデメリットも、案外、杞憂かもしれません。訴求ポイントも含めて、高齢者のインサイトをしっかり見極めることが大切です。
高齢者雇用に不安な企業のよくある質問

高齢者雇用を検討する企業からは、様々な疑問や懸念が寄せられます。以下、よくある質問とその回答例を紹介します。
改正高年齢者雇用安定法について
Q: 改正高年齢者雇用安定法の主な内容は何ですか?
A: 令和3年4月1日に施行された改正高年齢者雇用安定法の主なポイントは次のとおりです。
- 65歳までの雇用確保措置(義務)
- 定年制の廃止
- 定年年齢の引き上げ
- 継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※継続雇用制度の適用者は原則として「希望者全員」です。平成25年3月31日までに労使協定により制度適用対象者の基準を定めていた場合は、その基準を適用できる年齢を令和7年3月31日までに段階的に引き上げなければなりません(平成24年改正法の経過措置)。
- 70歳までの就業機会の確保(努力義務)
- 70歳までの定年引き上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
参照:厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」
年齢を含む歓迎表現や制限について
Q: 求人広告で「60歳以上歓迎」と記載してもよいですか?
A: 「60歳以上歓迎」の表現は問題ありません。ただし、年齢の上限を設けることは禁止されています。たとえば、“60歳以上65歳未満”と表現することは避けるべきです。
高年齢者就業確保措置を講じる必要性について
Q: 65歳に達する労働者がいない場合でも、高年齢者就業確保措置を講じる必要がありますか?
A: はい、必要があります。高年齢者就業確保措置は全ての企業に対して一律に適用される努力義務です。現時点で65歳以上の従業員がいなくても、将来的に65歳以上の従業員が出てくる可能性を見据えて、措置を講じるよう努めなければなりません。
ただし、これはあくまで努力義務であり、措置を講じなかった場合に直ちに罰則が適用されるわけではありません。しかしながら、講じなかった場合に行政指導を受けることは考えられます。将来的な労働力確保や企業の社会的責任の観点から、可能な限り対応するのが望ましいでしょう。
高年齢雇用継続給付金の支給について
Q: 高年齢雇用継続給付金の支給は縮小・廃止されるのですか?
高年齢雇用継続給付金は、労働者側にも企業側にもメリットがある制度でしたが、2020年度の通常国会で、段階的に縮小し、最終的には廃止されることが決まりました。給付率が減っていく具体的な時期は、ずばり2025年4月からです。
▶関連記事:高年齢雇用継続給付金が廃止へ!いつから?なぜ?申請、計算方法も紹介
高齢者を雇用するメリット・デメリットの把握がシニア採用には不可欠!
労働力人口がどうしても減り続けるなか、シニア採用に希望を見出す企業は増えています。これは、多様性を重視する世相からも、至極当然の流れでしょう。とはいえ、ただ何とはなしに求人を出しても、思うような結果に至らないかもしれません。そこは、しっかりメリット・デメリットを把握し、うまく調整を図ることが大事です。たとえ採用につながっても、実際に働いてもらったときに何かしらトラブルを引き起こす可能性もあります。いずれにしても高齢者を雇う際は慎重に、かつきめ細かな対応を心がけましょう。
▶関連記事:シニア採用完全ガイド:シニア雇用促進のポイントを徹底解説!
求人掲載・採用業務のサポートや料金についてなど、ぜひ気軽にお問い合わせください。
また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談も無料で承っております!
▶【公式】スキマ時間のスポットワーカー募集ならスポットバイトル
┗スキマ時間で「働きたい」と「働いてほしい」をつなぐ求人マッチングサービス。求人は無料で掲載できます。
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。
▶【公式】面接コボット – 応募者対応の自動化で面接管理が楽に!
┗求人サイトからの応募対応を自動化できるサービス。チャットボットを通じ、日程調整まで効率よく進めてくれます。
▶【公式】採用ページコボット – 費用・実績も紹介!採用サイト制作サービス
┗採用ページ作成サービス。求人まとめサイトとの自動連携や求人検索エンジンへの対応により外部集客を強化します。

