バイトテロとは?
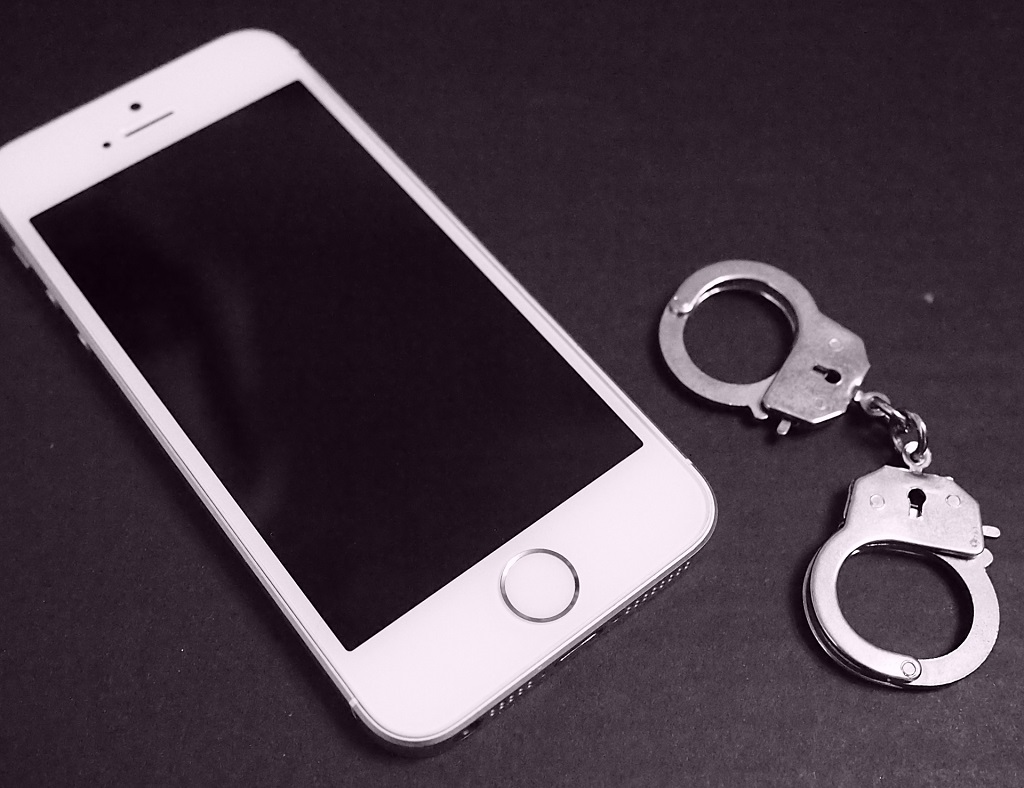
バイトテロとは、アルバイト従業員がふざけて行った不適切な行為が世間に知れ渡り、大きく信頼を落とすなど企業のイメージ悪化につながることです。主にSNS上に投稿された動画や画像によって拡散されて炎上し、世間からバッシングを受けることになります。
非常識なアルバイト従業員による行動が発端となって起こるケースが多く、Twitterを利用したバイトテロは「バカッター」などとも揶揄されています。
一度SNS上に掲載されると、スクリーンショットなどを通じて他のメディアにも転載され、TwitterやInstagram、YouTubeなどあらゆるSNSに拡散されがちです。そうなると、どうしても収集はつかなくなります。また、このような動画や画像は、不適切な行動に至ったアルバイト従業員による投稿に限りません。LINEなどの仲間内だけでやり取りするコミュニティで共有されたものが、気づいたらオープンな場所(まさにTwitterをはじめとした上述のSNS上)でも露わにされていたなど、本人以外が投稿するケースも存在します。
無論、バイトテロのような行為はアルバイト従業員だけでなく、正社員によって引き起こされることもあるため、企業やお店側は広く監視する必要があります。炎上の内容によっては廃業に追い込まれる可能性も否めません。だからこそ、従業員への指導を徹底し、バイトテロを未然に防ぐことは非常に重要なのです。
バイトテロの歴史

バイトテロの最初の事例を示すのは難しいですが、社会的に大きな話題となってから少なくとも10年以上の歴史があります。とりわけTwitterが普及したことによってバイトテロは顕著に増加。先述のとおり2013年には「バカッター」という名称でマスメディアにも取り上げられ、世間に広く知られるようになりました(最近では、Twitterに限らずInstagramでの不適切動画の投稿も行われ、その行為は「バカスタグラム」と呼ばれています )。
投稿の内容は、顧客に提供する食品を使ったり、商品を保管する冷蔵庫に従業員が入ったりと、軽率な悪ふざけがほとんどです。そして、たとえ匿名で行われても(大抵は匿名ですが)、人物や店舗が特定されることは少なくありません。プロフィールや過去投稿、画像から読み取れる情報などから、いとも簡単に見つかってしまうのです。アルバイト従業員による不適切な行為は、おそらく昔からあったと思われます。しかし、スマートフォンなどのデジタルデバイスや4Gなどの通信技術の発達が皮肉にも、各地でバイトテロを生んだのでしょう。いうまでもなく、SNSの登場も無視できません。インターネット社会で可視化された由々しき実態に、私たちは直面したわけです。
さて、こうしたバイトテロを無くすためにも、問題を起こしそうな人を雇わないよう気を付けたいところですが、採用時に完全に見抜くのはなかなか難しいのではないでしょうか。ゆえに、従業員をAIロボットに代替するといったことも近い将来、十分考えられます。
とはいえ、今すぐロボットに頼る体制に変えるわけにもいかないでしょう。したがって、現在アルバイト従業員を雇っている企業・お店は、バイトテロに該当する何かしらの問題に対して、常に警戒の意識を持っておく必要があります。
バイトテロが起こる理由
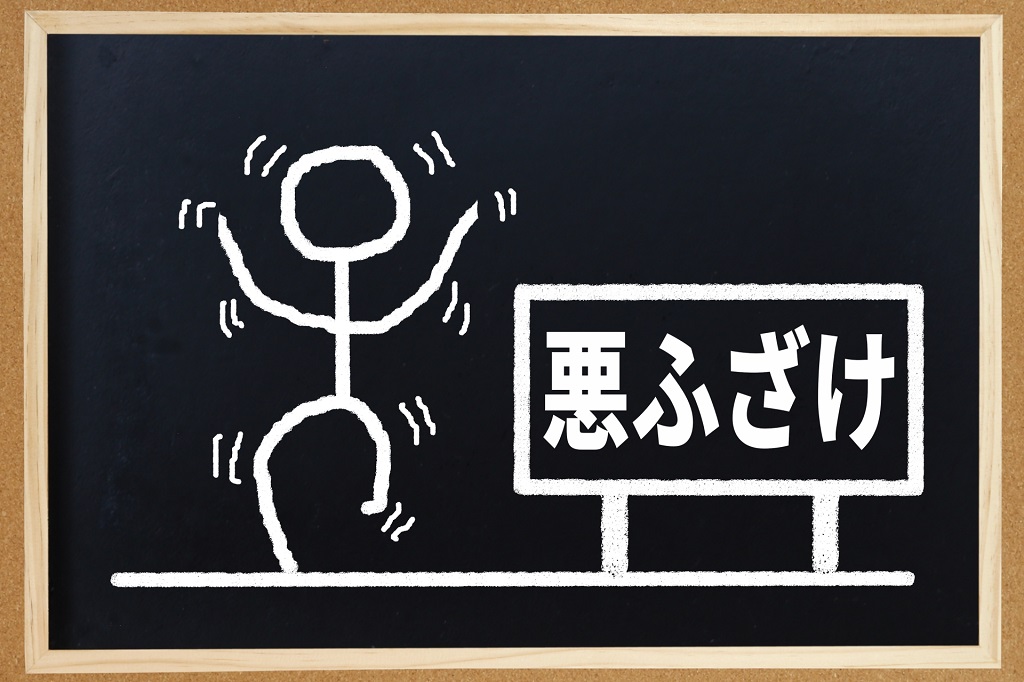
バイトテロはなぜ起こってしまうのか。つまるところ悪ふざけがほとんどだと前項ではお伝えしましたが、そのメカニズムを知らなければ対応は困難を極めるでしょう。というわけで以下、その理由に挙げられる要素について言及します。
アルバイトの安易な欲望
理由の一つとして、アルバイト従業員の承認欲求が挙げられます。SNS上で「目立ちたい」「面白いと思ってもらいたい」といった欲望を満たすために、多くの人が反応すると思われる不適切な動画を投稿してしまうのです。
自分の承認欲求を満たすことだけに意識が向けられるとどうしても他者への思いやりは欠如します。その投稿に対して「面白いと思う人もいれば不快感を抱く人だって当然いるはずだ」と冷静に推察できれば(できる人が多ければ)、起こらずに済んだバイトテロも多数あったことでしょう。
時代性
バイトテロを起こすのは、比較的若い世代のアルバイト従業員が多い傾向にあります。もちろん、軽い気持ちでやってしまうのは、若気の至りといわれればそうなのでしょう。と同時にその背景には、誰でも気軽にSNSに投稿できること、すなわち時代性も相まって起きていると考えられます。SNSに対する個人の危機意識が低下しているのは、そうした現代の特性も無関係とはいえないはずです。そして、承認欲求にブレーキをかける判断力もまた、希薄にさせているのはこの“時代”なのかもしれません。
SNSの拡散性
SNSの拡散性の高さも、結果的にバイトテロを助長したといえるでしょう。実際にバイトテロを起こしてしまう従業員の多くは、同僚や友人など仲間内で共有したいがための行動だといいます。が、シェアの輪が広がればたちまち不特定多数の人らに拡散されてしまうのがSNSです。そして、投稿が一度拡散されてしまうと、そのデータをインターネット上から完全に削除することはできません。むしろ、Web上の情報を削除したり隠蔽しようとすると、かえって拡散されてしまう、インターネット特有のストライサンド効果の現象にもつながりかねません。特にネガティブな情報は瞬く間に広がる傾向にあります。
バイトテロによる拡散方法の変化

前項でSNSの拡散性について触れましたが、実際、その方法やプロセスは時代とともに変化を見せています。たとえば以前は、Twitterで投稿された写真に対して、ユーザーが反応しリツイートなどのアクションによって炎上していく流れが一般的でした。そこからインターネットの掲示板でスレッドが立ち上がり、本人特定につながることもあれば、テレビをはじめマスメディアが後を追うように一連の出来事を社会問題として報じるケースなどもしばしば見受けられる光景だったと考えます。そうやって、まさにバイトテロとして俎上に載せられていくわけです。
一方、最近ではInstagramの鍵付きアカウントを利用し、24時間で消える「ストーリー」に投稿され、その動画がTwitterに転載されて拡散する流れも散見されます。つまり、あらゆるタッチポイントでバイトテロが浮き彫りになってしまうのです。単純に考えて、ソーシャルメディアが増える分、拡散性も高まることでしょう。しからば、今後はより一層、バイトテロ対策を強化する必要があると考えます。
バイトテロが及ぼす影響

ここまでバイトテロの歴史やその理由あるいはメカニズムについて述べてきました。
では、実際にバイトテロが起きたときには、どのような影響が考えられるのでしょうか。
バイトテロをくらった企業への影響
バイトテロによって企業が被る最も大きな影響は、ブランドイメージの低下や風評被害です。たとえば飲食店の場合、「環境が不衛生」「食材を適切に管理できていない」などの印象を持たれてしまうと、たちまち信頼度は下がり来客数は減ってしまう恐れがあります。場合によっては、経営が一気に傾くことさえ考えられるでしょう。いまの時代、個人経営の店舗であっても、容易にSNS上で特定されてしまいます。そして見つかれば、上述した災難が待っています。たとえ従業員自身に悪気のなかったこと、そしてたった一度の過失であっても、企業には重くのしかかる出来事になるリスクは十分にはらんでいるのです。
また、バイトテロの内容によっては顧客からクレームが殺到することもあります。来る日も来る日も顧客に対する謝罪に追われてしまうと、おそらく担当者は本来取り組むべき仕事に手を付けられなくなるでしょう。謝罪以外にも損害賠償請求や再発防止策の検討など、バイトテロに付随する業務に時間を取られれば、どうしたって通常業務は滞るはずです。結果、憔悴しきってしまう姿は容易く想像できます。
さらには、採用活動にも支障をきたします。事件を起こす職場には少なからずネガティブな思いを覚えるものです。教育体制も整っていないと思われるかもしれません。いずれにせよ、まともではない労働環境だと烙印を押されてしまう可能性は大いにあります。
バイトテロに関わった従業員への影響
個人情報を公にしてなくても本人特定されるのがバイトテロの怖いところです。インターネットで名前や住所、電話番号などの個人情報が晒されてしまえば、いたずら電話などリアルの世界にわたって嫌がらせを受ける可能性もあります。何より、バイトテロを起こした人物としてデジタル空間に掲載され続けることは悲痛でしょう。いくら反省したとしても従業員のこの先の人生に大きく影を落とすことを考えれば、惨い仕打ちです。仮に学生の場合、停学や退学になることも考えられます。
企業側からすると、先に述べたダメージに加え、これまで一緒に働いた仲間と望まない形で決別することも少なからず辛いはずです。場合によっては、やむを得ず解雇通知や損害賠償を請求する局面も出てくるでしょう。実際に、バイトテロの被害に遭った飲食店が、該当するアルバイト従業員4名に対して約1,300万円もの賠償請求に至った事例もあります(最終的には和解して200万円の支払いで決着)。
バイトテロは、従業員自身にとっても大きなリスクを伴う行為です。そして、彼・彼女たちにそうした人生を歩ませないよう、やはり企業側も細心の注意を払わなければならないと切に感じます。
バイトテロの主な事例

一口にバイトテロといってもさまざまなケースが存在します。本章では、過去に起きたバイトテロをいくつか紹介。事例を多く知ることで、より身近なものに感じられるかもしれません。そう、バイトテロは決して他人事ではなく、いつ自社が見舞われてもおかしくないものです。ぜひ、それぞれ自分事として確認し、危機管理へとつなげてください。
コンビニで起きたバイトテロ
大手コンビニチェーンの店舗で発生したとあるバイトテロ。アルバイト従業員らは、仕事中、店舗のバックヤードに置かれたモニターを凝視する自分たちの姿を撮影し、TikTokに投稿します。そしてその内容は、従業員らがレジで精算をする若い女性客の胸部を盗み見ていたという卑劣なものでした。動画のアカウントはすぐに削除されましたが、「安心してコンビニへ行けない」などの声がネット上に相次ぎ大きな話題に。この騒動によって、企業はイメージの悪化、信頼の低下を余儀なくされます。
牛丼屋で起きたバイトテロ
大手牛丼チェーンの店舗に勤務していたアルバイト従業員の高校生が、業務中に調理器具を股間に当てた動画を撮影し、SNS上に投稿。動画はすぐに拡散され炎上し、本人だけでなく、企業側も管理体制の問題を問われることになります。
企業はアルバイト従業員を解雇しましたが、顧客の信頼はそうすぐに回復することはなかったようです。
カレー屋で起きたバイトテロ
大手カレーチェーンのお店でアルバイト従業員が、休憩室でカレーの上に自身の体毛を振りかけた動画をInstagramに投稿。その後、動画はTwitterにも転載され炎上します。このとき、事態がそこまで長引かなかったことは少なくとも企業にとっては不幸中の幸いだったかもしれません。というのも運営企業は 、すぐに該当店舗の営業を停止し、再発防止に向けた指導や衛生管理の確認などを行うなど迅速なアクションをみせたといいます。とはいえ、やはり事件が起きてしまう前に、対策を図れなかったのは後悔してもしきれない痛手だったでしょう。明日は我が身。どの企業も(素早い対処も含めて)胸に刻んでおきたい事例です。
蕎麦屋で起きたバイトテロ
ご存じの方も多いかもしれません。2013年、都内の蕎麦屋で起きたバイトテロ事件では、アルバイト従業員が食洗機に入り、寝そべる姿や上半身の服を脱ぎ胸部にお茶碗をあてるといった行為をTwitterで投稿。お店側は、猛批判を浴び、その結果、3ヶ月後に閉店に追い込まれます。負債の額、なんと3,000万円以上。当事者であったアルバイト従業員に対して、お店側は合計1,385万円の損害賠償を求める裁判を起こしますが、結局は約200万円で和解するに至ります(週刊誌による報道)。
寿司屋で起きたバイトテロ
(2023年1月)某寿司屋で起きたあの騒動はアルバイト従業員が起こした不祥事ではありませんが、バイトテロ防止を訴えかけるには、図らずもよい機会になってしまったと考えます。それほど、あまりに悪質な行為でした。具体的には「備えつけの醤油の差し口や未使用の湯呑みを舐めまわしてから戻す」「回転レーン上の寿司に唾液をつけた指を何度も擦りつける」といったもの。活字にするにも悍ましいその卑劣さを前に、もはや唖然とするしかないなか、SNSで拡散され、大きく問題視されました。
そして実際のところ、寿司屋では過去に広く報道されたバイトテロも起きています。これまた活字にするには気が引ける悪質な行為でした。端的に述べると、アルバイト従業員がハマチの切り身をゴミ箱に捨てた後、再度まな板の上に載せたのです。その動画を撮影しTwitterに投稿すると、当然ながら炎上。店舗への抗議の電話は、相当だったようです。この件、深刻な問題ととらえたお店側は、当事者2人に退職処分を下します。そのうえで、刑事と民事、両面から厳正に対処するとの意思を高らかに宣言します(2人はその後、偽計業務妨害容疑と偽計業務妨害幇助容疑で書類送検されます)。
こうした行き過ぎたアルバイト従業員の不適切行為(動画投稿)は、無論、いたずらではすみません。ただ本人たちは、軽い気持ちだったのでしょう。そうやって簡単に起きてしまうからこそ、普段から教育を徹底させることの必要性(もはや必然性)がわかります。
バイトテロを回避するための企業側の対策

繰り返しお伝えしますが、バイトテロに対しては未然に防ぐべく対策を講じる必要があります。では具体的に、どのようなやり方が有効なのでしょうか。以下、解説します。
バイトテロがもたらすリスク研修
バイトテロをしでかすアルバイト従業員のほとんどが、問題の大きさを理解しないあるいは自分だけは大丈夫と考えて投稿してしまいます。だからこそ、アルバイト従業員には普段から当事者意識を植え付けることが大事です。具体的には、バイトテロがもたらすリスクについて理解を深める研修の実施をおすすめします。バイトテロが与える企業側と個人への悪影響についてしっかりわかってもらえるよう、実際に起きたケースを交えながら、説き続けることが大事です。
SNS上でのルール設定
バイトテロが悪いことだと分かっていても、今日我々はSNSを日常的に使っているため、意図せず悲劇が起きる可能性もあります。ゆえにSNSを使用する際のルールを社内で明確に決めておくことも有効な対策です。近年では多くの企業が、SNSの運用ルールをソーシャルメディアポリシーやSNSガイドラインといった形で定めています。
たとえば「職場にスマートフォンを持ち込まない」「店内や社内では写真や動画の撮影禁止」「顧客の個人情報は業務担当者以外は扱わない」など、基本的なルールでかまいません。大事なのは、採用時から周知を徹底することです。これだけでも、何も規定を設けないよりは、バイトテロの発生防止につながるものと考えます。
SNSのモニタリング
ルールを定めた先に行いたいことの一つが、SNSのモニタリングです。前項で述べたルール設定は少なからず効果的とはいえ、やはり従業員個人の行動をコントロールすべく、監視体制もあるに越したことはないでしょう。不適切な投稿を早期に検知し、被害を最小限に抑えるためには、SNS上の自社に関する投稿を常にチェックしておくことが大切です。そうした体制づくりに努めるべく、可能であれば、投稿監視ツールや専門業者を頼ることもおすすめします。
防犯カメラの設置
店内や社内に防犯カメラを設置することも有効です。防犯カメラは、本来、店舗やオフィスを狙う犯罪の抑止力になるものですが、バイトテロ防止にも一役買います。SNSに投稿する以前に、勤務中の従業員の様子をしっかり把握することも当然ながら大事です。
採用基準の見直し
人手不足が課題の企業では、採用基準を下げて人材を集めようとしがちですが、バイトテロが発生すれば、人手不足以上の問題に発展する可能性があります。リスク回避のため、従業員の採用基準に問題がないか見直すことも、重要なバイトテロ対策です。
バイトテロ発生後の対応

前述した対策を講じても、バイトテロが起きてしまう可能性はゼロではありません。万が一に備えた対策も必要です。たとえば、被害を最小限に留めるべく、謝罪やクレーム対応など誰がどのように行うか事前にマニュアル化しておけるとよいでしょう。加えて、随時ブラッシュアップできると、なお望ましいと考えます。
いずれにせよ、バイトテロ発生後の対応についても企業側はしっかり向き合わなければなりません。以下、具体的なアクションについて述べていきます。
一連の流れ
バイトテロの被害を最小限に抑えられるかどうかは、発生後の対応スピードにかかっています。ゆえに、先述のとおり、マニュアル化が必須です。 あらかじめバイトテロが発生した場合を想定し、行うべき対応をまとめておかなければ、いざ起きたときには迅速に動けないでしょう(あるいは慌ててしまい対処を間違うことも大いに考えられます)。
一連の流れは次のとおりです。
まず、誰がどこで何をしたのか、事実確認を行います。間違いなくバイトテロが起きていたと判断できれば、すぐに上司へ報告しましょう。
次に、概要の公表です。気を付けてほしいのは、速やかに行わなければ隠蔽したと非難されることがあります。信用が低下しないよう、公式サイトに謝罪文を掲載するなど、世間に対して事の一部始終、そして反省する姿勢を真摯に伝えてください。また、クレームが殺到することも考えられます。必要に応じて対応窓口の設置も検討しましょう。
最後に、再発防止策の策定です。これも謝罪同様、公式サイトやメディアなどを通じて対外的に示す必要があります。もちろん、有言実行なくして意味を成しませんが、同じ過ちを繰り返さない姿勢をみせることも非常に大事です。適切な対応として、明確に伝えるようにしてください。
デジタルタトゥーへの対応
デジタルタトゥーとは、インターネット上に公開された画像やコメントなど、一度拡散された情報を完全に削除するのが困難なことを、タトゥー(完全には消せない)に例えた表現です。仮にバイトテロによる騒ぎ自体は、ほとぼりが冷めたとしても、インターネットで検索すれば事件は記録されたままのため、最悪、いつでも蒸し返されてしまうことも懸念されます。これを対処するには、弁護士に相談するなど何かしら手を打つ必要があるでしょう。
そうはいってもやはり、完全に取り除くのは難しいのが現実です。ゆえに、どうしても消せない傷に固執するよりは、イメージ回復に向けた取り組みを展開する方向へ舵を切った方がよいかもしれません。具体的には、社会に対して何ができるか考え、粘り強く発信していくことです。こうした黒歴史すなわちデジタルタトゥーを上書きするやり方も、一つの立派な手段だと考えます。
バイトテロの法的責任について

バイトテロを行った従業員には、刑事責任もしくは民事責任が生じる可能性があります。企業側はそれらについても知っておいた方がよいでしょう。以下、それぞれ説明します。
刑事責任
投稿内容が企業の名誉や信用を棄損していると判断された場合、名誉棄損罪や侮辱罪に当たる可能性も出てきます。投稿の内容次第では、威力業務妨害罪が成立するケースも珍しくありません。事案があまりに悪質で企業の被害が大きければ、刑事告訴の検討もやむを得ないでしょう。
民事責任
企業はバイトテロを起こした従業員に対し、受けた損害を賠償請求できます。具体的には、商品や備品の廃棄費用、清掃費用、バイトテロ後の対応費用などが請求可能です。また、取引停止や休業などにより、本来得られたはずの営業利益も、損害として立証できれば、同様に対象に含まれます。
ただし、バイトテロを行った従業員の経済事情によっては、希望額の回収は難しいかもしれません。
バイトテロに備えたうえで優秀な人材を確保しよう
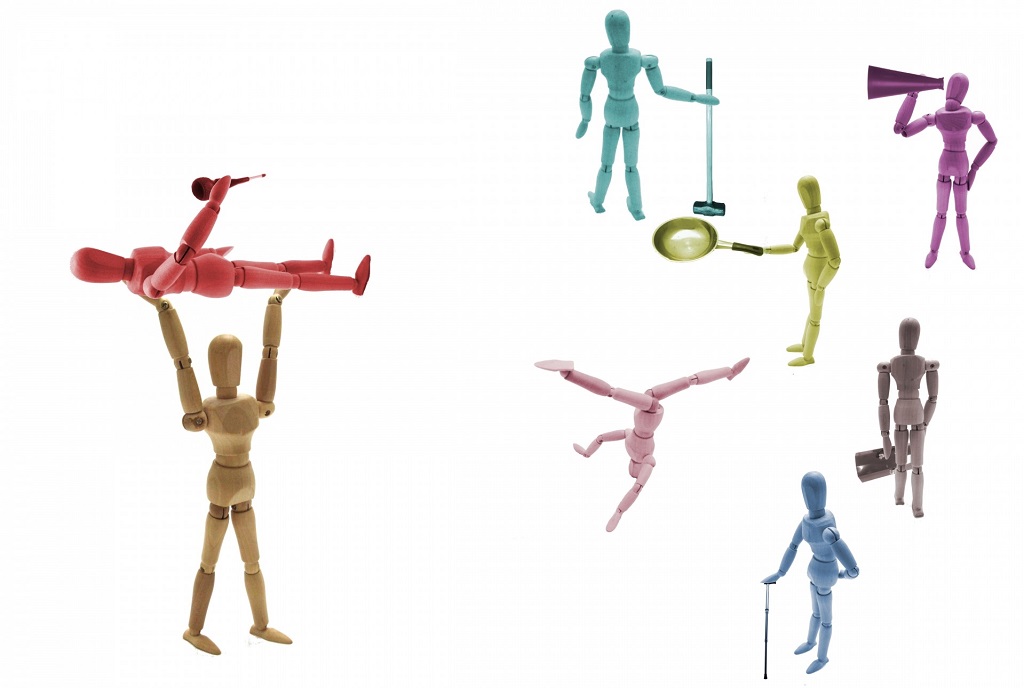
軽はずみな気持ちでSNSに投稿されたものが、不適切な行為だった場合、瞬く間に世間を騒がせることは、いまの時代、当たり前に考えられます。そのため、アルバイト従業員を雇用している企業やお店は、バイトテロが起こる可能性を想定したうえで、十分にケアしていかなければなりません。もちろん、アルバイト・パート以外の方に対しても、起こり得るものとして、対処しましょう。具体的には、既述のとおり、リスク研修の実施やSNSを利用するにあたってのルール設定などをおすすめします。
なお、dipでは企業の求人ニーズに合わせたターゲティングがスムーズに行えるサービスを提供しています。バイトテロ対策につながる最適な人材を採用すべく、ぜひ、導入をご検討ください。
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。

