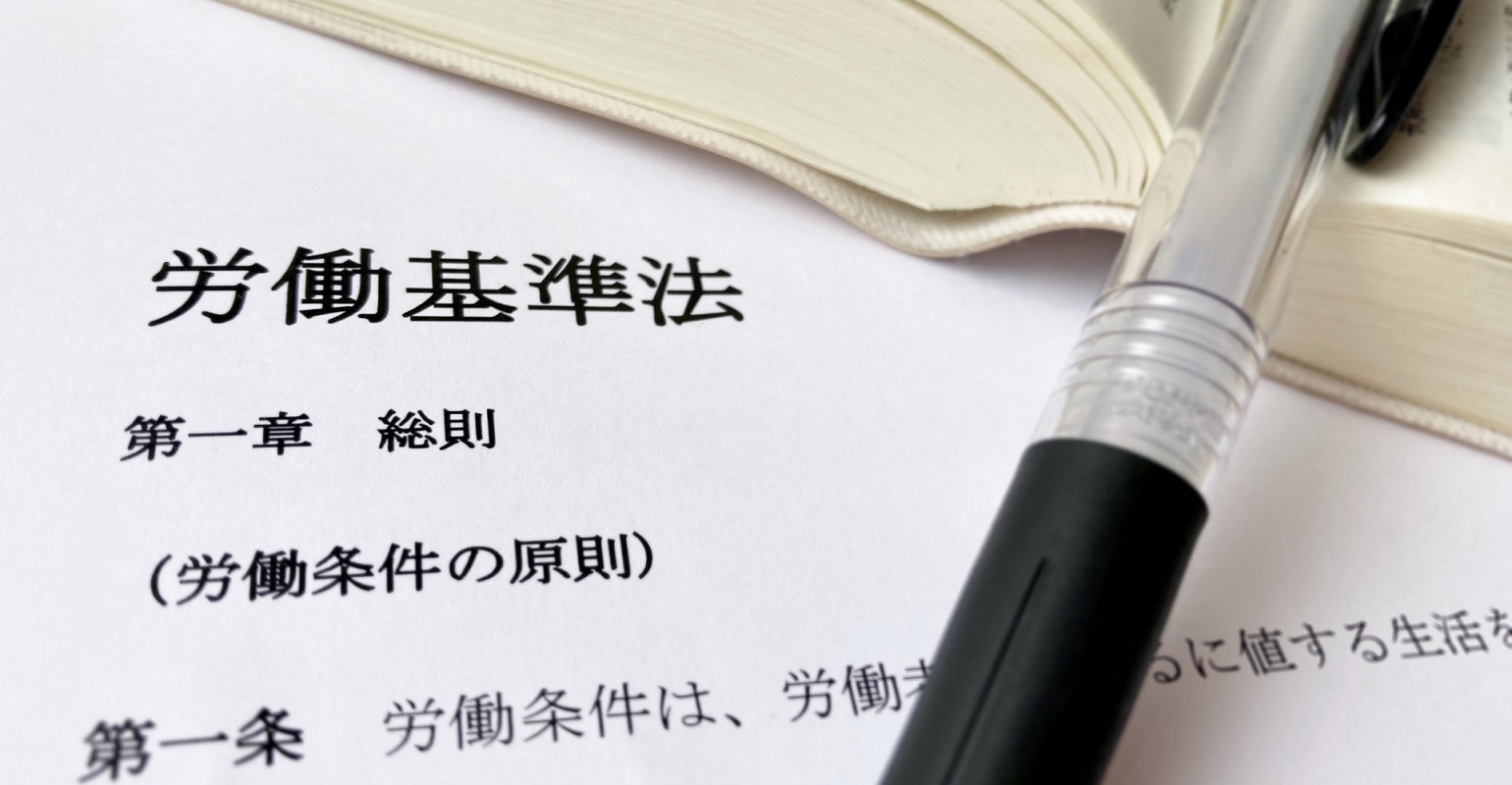労働三法とは
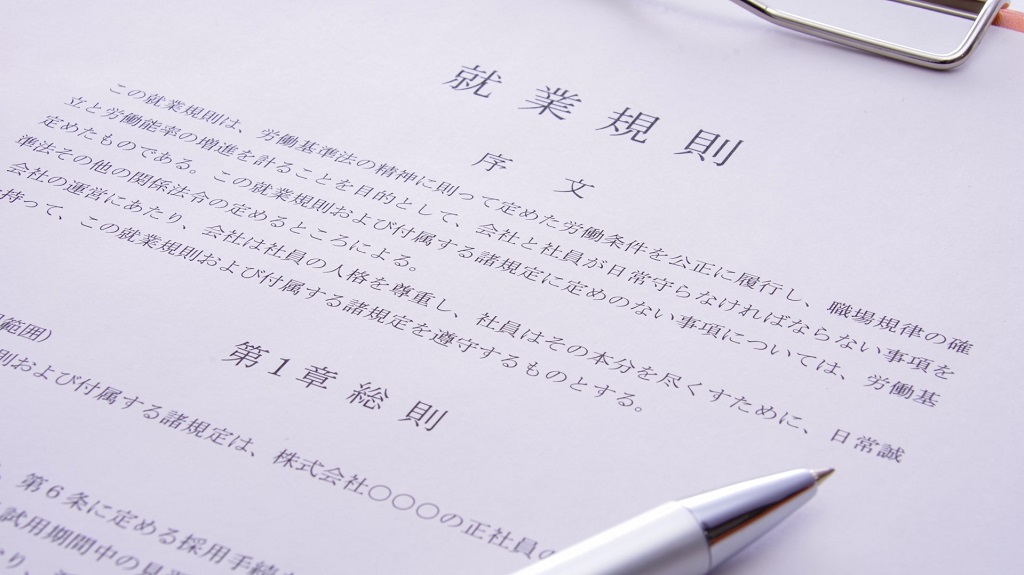
労働三法とは何か、まずは大まかにとらえてみましょう。加えて、冒頭でも触れたとおり、同じものとして扱われやすい労働三権についても、明確に違いが分かるよう定義します。
労働三法の基本概要
繰り返しお伝えしますが、労働三法は、労働者を守るために定められた次の3つの法律を指す総称です。
- 労働基準法:労働時間や休日、賃金など、労働に関する最低限の基準を定めた法律
- 労働組合法:労働組合を組織し、企業と交渉や話し合いができることを保障した法律
- 労働関係調整法:使用者と労働者の間で争いが生じた際、二者間での解決ができない時は間に外部組織が入って解決することを定めた法律
労働に関する法律は時代とともに移り変わりが激しく、制定されてから何度も改正が行われてきました。しかし。これら3つは、第二次世界大戦後から現在まで変わらずに残されています。まさしく労働法に相応しい(労働法の基盤となる)法律です。
労働三権とは
労働三権とは、日本国憲法第28条に制定された、労働者の下記3つの権利をまとめたものです。
- 団結権:使用者側と対等の立場で話し合いができるように、労働者が組織を作ったり加入したりできる権利
- 団体交渉権:使用者と組織が労働条件などを交渉し、決定事項を文書で定めることができる権利
- 団体行動権:労働条件改善などを求める際に、労働者がいわゆるストライキなどを集団で行使できる権利
労働三権は、文字どおり権利を指します。定義上、法律として括られる労働三法とは異なりますが、労働者を守るために存在している点は、両者共通項といえるでしょう。
労働三法に含まれる労働基準法とは

ここからは労働三法に含まれる法律一つひとつを紹介します。
まずは、労働基準法についてです。
労働基準法の基本概要
労働基準法には、労働条件の最低基準が記されています。遡ること1947年、日本国憲法第27条の「労働権」に基づき制定されました。日本国民はもちろん、国籍や身分を問わず、すべての労働者の適切な雇用を守るための法律です(ただし、一部の国家公務員、船員などは除外されます)。
労働基準法で取り上げられている項目は、労働時間、休暇、休憩時間、賃金、安全や衛生、年少者や妊産婦の扱い、就業規則などです。労働基準法の第1条で高らかに宣言される“労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない”の一節だけでも、この法律があくまで最低限のルールを設定していることが分かります。
では、守らなければどうなるでしょう?
たとえば、第5条で定められているように、強制労働をさせていた場合は1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金に処されます。そのほか、違法な解雇を行えば、第20条に該当する6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。このように、労働基準法に違反すると、それぞれの条項にしたがって罰則が与えられます。
労働条件について
労働基準法では、労働者を雇用する際に、条件を明示しなければなりません(労働基準法第15条第1項、労働基準法施行規則第5条)。具体的には次の項目に対してです。
- 契約期間
- 契約の更新基準
- 従事する業務と、就業する場所
- 勤務時間(始業および終業時間)、休日、休憩時間など
- 賃金、支払い日など
- 退職・解雇など
- 昇給
▶関連記事:労働条件の明示義務について、ルールの改正とあわせて解説
常時10人以上の労働者がいる場合は、これらを記載した就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署へ提出します。
なお、時間外および休日の労働について定める場合には、いわゆる36(サブロク)協定と呼ばれる労使協定の締結が必要です。36協定を結んだ際も、労働基準監督署への提出は義務付けられています。
また、「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の3つの書類、そう、法定三帳簿の作成も必須です。
さらには、契約期間の上限も細かく規定されています。仮に有期労働契約を結ぶ場合、原則として上限は3年です。ただし、専門的な知識がある方や、満60歳以上になると上限は5年に引き伸ばされます。
そのほか年少者や妊産婦に関する規定も、人事担当者は確実におさえておきたい内容です。まずは前者。たとえば第56条には、“使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない”と記載されています。つまり、中学校の義務教育を終えない者を雇用してはいけないわけです。が、例外もあります。「映画や演劇、お芝居の舞台に出演する子役」「新聞配達など非工業的事業に関わる仕事」は15歳未満でも、就労させてかまいません。
そして、後者。
労働基準法の第65条には、“使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない”や、“使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない(ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない)”といった規定が並びます。産前6週間(双子以上は14週間)、産後8週間は産休・育休を取ってもらい、生後満1年に達しない生児を育てる女性に1日2回、、各々少なくとも30分の育児休業を与えることは、もはや義務なのです。そして、これらに違反すると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。
労働時間・法定休日に関する細かな規定
労働基準法では、労働時間や法定休日を、次のように規定しています。
労働時間
法定労働時間として「1日8時間・週40時間」までと決められています。仮にその範疇を超過して労働させる場合には、別途36協定の締結が必要です。が、36協定を結んでもなお、時間外労働の上限は「年360時間・月45時間」と定められています。と、これもまた特別な事情がある場合に限っては特別条項の制定で凌げるのですが、行きつく先の「年720時間・休日労働+時間外労働で100時間未満」の条件には必ずしたがわなければなりません。
休憩時間
勤務時間中には、労働者に休憩時間を与えることが義務付けられています。1日の労働が6時間以上なら45分以上、8時間以上であれば1時間以上の休憩の付与が必要です。なお、この休憩時間は、分割して取ってもらってもかまいません。
法定休日
法定休日は労働基準法第35条によって規定されています。雇用主は労働者に対して、最低週に1日、4週のうち4日の休日を与えることが義務です。なお、曜日の縛りはありません。
▶関連記事:法定休日とは?所定休日(法定外休日)との違いや法改正による変更点など解説
有給休暇
有給休暇とは、賃金が発生する休暇のことです。原則、6ヶ月以上の継続勤務と、8割以上出勤している従業員に対しては、正社員もパートもアルバイトも関係なく、有給休暇を付与しなければなりません。
なお、企業側は有給休暇の取得日を、事業の正常な運営を妨げる場合においてのみ「時季変更権」で変更させることができます。
▶関連記事:パートの有給休暇取得の条件、付与する日数、賃金の計算方法など解説
賃金
雇用主は労働者に対して、毎月1回、指定の方法で賃金を支払わなければなりません。この当たり前の規定もまた、労働基準法で定められています。
支払い方法
第24条では、賃金の支払い方について、次の5原則が明記されています。
直接払い
労働者本人に直接支払います。従業員が指定しても、代理人に支払うことはできません。また、未成年であっても同様です。そのため、両親などへの支払いも禁止されています。
毎月一回払い
最低でも月1回の頻度で支払いを行います。年俸制であっても、1年分の報酬をまとめて支払うことはできず、12分割して毎月支給しなければなりません。
通貨払い
日本で流通する通貨、すなわち日本円で支払います。合意を条件に銀行振り込みが可能です。なお、現物支給は不可とされています。
一定期日払い
支払期日は周期的に定められ、たとえば「月末締めの翌20日払い」などが当てはまります。なお、この期日に賞与は含まれません。
全額払い
賃金は全額を支払います。条件を満たせば控除も可能です。ただし、労働協定や所得税法令などで定められたものは除きます。
男女同一賃金
労働基準法の第4条では、“使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。”と定められています。つまり、性別を理由に賃金の格差を設けてはならない決まりです。
最低賃金
労働基準法の第28条では“賃金の最低基準に関しては、最低賃金法の定めるところによる。”と記されています。いうまでもなく、支払う賃金が最低賃金法で定められた額を下回ってはいけません(最低賃金法第4条)。
▶関連記事:2022年10月から最低賃金の引き上げが決定!アップ額に加え、理由やメリット・デメリットも解説
割増賃金
法定労働時間を超えた時間外労働や、深夜労働(22時から5時)、法定休日での労働に対しては、割増賃金を支払わなければなりません。
割増賃金に関する主な適用例は次のとおりです。
- 法定時間外労働、深夜労働…割増率25%以上
- 法定休日での労働…割増率35%以上
- 1ヶ月60時間を超える時間外労働…割増率50%以上(中小企業の適用は2023年3月末まで猶予あり)
減給
労働者に対して減給の制裁をする際、1回の賃金支払い額の10分の1を下回ることがあってはいけません(91条)。
金品の請求
退職または労働者の死亡により、本人または権利者から請求があった場合には、7日以内の賃金の支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません(第23条)。
解雇通告について
解雇については、主に次のような決まりがあります。
まず、労働者を解雇する場合、30日以上前からの予告または30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません(第20条)。また、産前産後や業務上の病床を理由とする休業期間や、その後の30日間は解雇することができません(第19条)。
▶関連記事:アルバイトを解雇するには?妥当な理由、方法、流れについて解説
▶関連記事:解雇予告手当とは?計算方法や支払日、源泉徴収についてなど徹底解説
労働三法に含まれる労働組合法とは

続いては、労働組合法です。この法律によって、労働者は使用者と対等に交渉を行える労働組合を作ることができます。以下、おさえておきたいポイントを中心にまとめました。
労働組合法の基本概要
労働組合法は、いわば労働三権の「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」を保証するための法律です。
労働組合法の第1条には、このように記されています。
この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。
労働組合法の第1条
“この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。”
すなわち、企業は労働組合に対して不当な扱いをしてはならないわけです。同時に、労働者が意欲的に働くためにも、結果、企業がより良い職場環境作りを実現するためにも欠かせない組織であることが分かります。双方にとって貴重な存在です。
労働組合の種類
労働組合は、大きく分けると4種類あります。個人で加入できるものできないものありますが、それゆえ一般的には前者を認識する向きが多いでしょう。下記リストだと、下段2つが該当します。
- ナショナルセンター(全国中央組織)…労働組合の代表となる組織。個人では加入できない。
- 産業別・職業別組合…企業ごとの組合やユニオンを統括する組織。個人では加入できない。
- 企業別組合(単位組合)…同じ企業の労働者により結成。入社と同時に加入する人が多い。
- 合同労働組合(ユニオン)…複数の企業の労働者により結成。各々が適合組織を探して加入する。
労働組合の役割、目的
労働組合の役割や目的は、そのまま定義にも結びついているわけですが、企業、そして従業員にとって、生来的にはどのように機能すべきか、曖昧な方もいらっしゃるかもしれません。以下、あらためて整理します。
| ◆企業への役割、目的 【役割】労働組合を通して、企業の問題点を知る機会を作る 【役割】労働組合を通して、労働者の生の声を知る機会を作る 【目的】企業と労働者の信頼関係を築く ◆従業員への役割、目的 【役割】解雇や左遷など、労働者が不当な扱いを受けたときに企業と交渉する 【役割】労働者の相談窓口になる 【目的】企業と労働者の信頼関係を築く |
つまるところ、目的は共通。そこに至るまでの過程で労働組合が奮闘します。
不当労働行為
労働組合法では、労働組合に対しての不当労働行為を禁止しています。仮に起きてしまった場合、組合側は損害賠償や慰謝料の請求、「労働委員会」への救済申し立てが可能です。
なお、主な不当労働行為には、次のようなものがあります。
- 労働組合からの団体交渉の申し入れを拒否
- 労働組合の結成や加入に対する減給、解雇、嫌がらせ
- 組合員と非組合員での待遇差別
- 労働組合が不当労働行為の申し立てを行ったことを理由にした、労働組合に対する不利益な扱い
- (企業が)労働組合の運営に対する介入や支配
組合費
労働組合に加入すると、組合費が発生します。過去の調査では、1人あたりの平均月間費用が、たとえば平成30年度は3,707円、平成28年度は3,574円でした。なお、階級別でみると、「4,000円以上5,000円未満」の層の割合が最も多い傾向にあります。
労働三法に含まれる労働関係調整法とは

最後に労働関係調整法についてです。この法律は、企業と労働者間でのいざこざ、トラブル、問題に対して解決を図るべく規定されています。その他詳細は、以下のとおりです。
労働関係調整法の基本概要
あらためて、労働関係調整法とは、企業と労働者の争議を防止したり、労働委員会が間に入って解決したりといった、労働関係の調整について定められた法律です。
労働関係調整法の第1条には、このように記されています。
この法律は、労働組合法と相まって、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする。
労働関係調整法の第1条
争議行為とは、同盟罷業(ストライキ)、怠業(サボタージュ)、作業所閉鎖(ロックアウト)などといった、労働者が主張を貫徹するために行う団体行動のことです。争議行為が発生すると、企業または労働組合は、労働委員会もしくは都道府県知事への届け出が義務付けられています。その後、労働委員会が間に入り、各所への調整が開始されます。
労働関係調整法の主な手続き
争議行為が発生すると、労働関係調整法により、以下の調停手続きが行われます。
斡旋
企業・労働組合からの申し立てにより行われる調整方法です。
労働委員会(の会長)が指名する斡旋員が関係当事者間に入り、双方の主張の要点を確かめて事件解決に努めます。斡旋員の提案に拘束力はありません。また、提案を受け入れるか拒否するかの決裁者は当事者です。ほかの手続きよりも比較的簡単に行えることもあり、大半の争議調整が斡旋によって解決されています。
仲裁
労働委員会の公益委員から選定された仲裁委員会が、争いの解決を行う調整方法です。
仲裁委員会が労働争議の実情を調査し、争議解決の条件を定める裁定を行います。書面で作成された仲裁裁定は労働協約と同一の効力を有し、関係当事者を法的に拘束するものです。提案の拒否はできません。関係当事者の双方、もしくは一方の申請に基づいて行われます。
調停
労働委員会から選出された調停委員会が、関係者の意見を聴いたうえで争いの解決を行う調整方法です。
調停委員会は調停案を作成して、これを関係者に提示し、受託の勧告を行います。調停案に拘束力はなく、また提案を受け入れるか拒否するか決めるのは当事者です。
関係当事者の双方、もしくは一方の申請に基づいて行われますが、公益事業に関する事件の調停は例外に当たります。この場合、関係当事者の一方の申請または職権に基づいて行われます。
緊急調整
大規模なストライキや労働紛争が起こった際に、内閣総理大臣が行使できる調整方法です。国民の経済や生活を著しく危うくする恐れがある際、内閣総理大臣は中央労働委員会の意見を聴いて、これを決定します。
緊急調整制度は極めて例外的で、実際のところ、これまで発動されたのは、1952年の炭労ストライキの際のみです。
労働三法の理解を深め、人材確保につなげよう
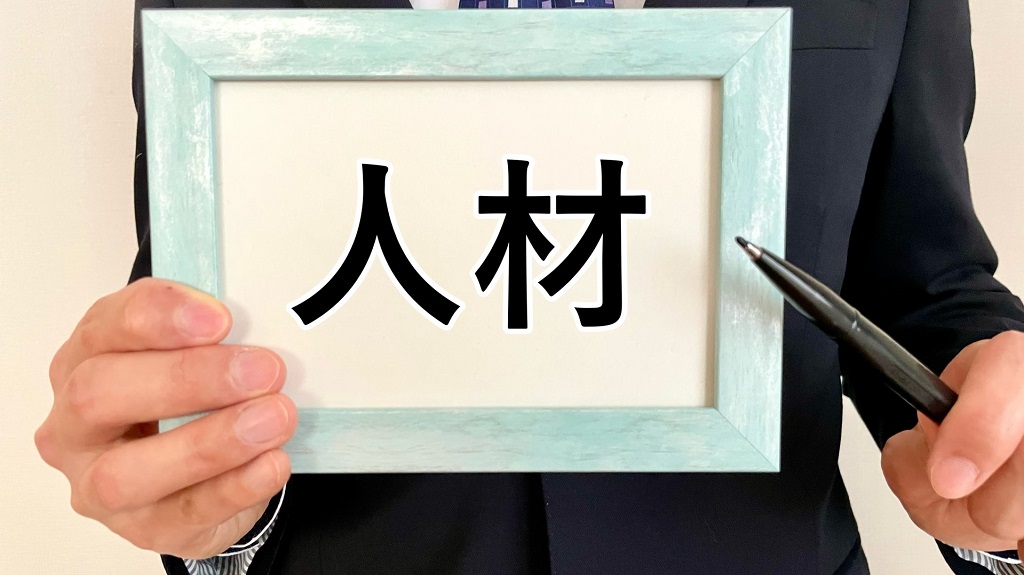
「労働三法」は、労働者が安心して社会で働くための基本的な法律です。正しく理解することが、労働者との関係構築にもつながります。そのうえで、採用活動が重要です。心機一転、労働にまつわる法律を高い水準で把握したとき、求職者へのアプローチはおのずと変わってくるかもしれません。ひいてはその結果、応募してくる層やタイプも従来より潜在的に求めていた方々が増える期待さえ持てます。まさにパラダイムシフト。
そうしたなかで企業の人事担当者様におすすめしたいのが「はたらこねっと」です。dipにはさまざまなサービスがありますが、はたらこねっとの幅広さは訴求する際も、多様な引出しでマッチングの確率アップに一役買ってくれるものと考えております。派遣やパート・アルバイトなど、正社員以外の働き方を検討している方は決して少なくありません。まずはサービス内容をチェックし、気になる方は無料のお問い合わせ登録もご利用ください。
▶【公式】はたらこねっと – 派遣、直接雇用案件の掲載可能!料金プランも豊富
【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所
代表 荒武 慎一
同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。