休憩時間ってそもそも何?パートと正社員で変わる?
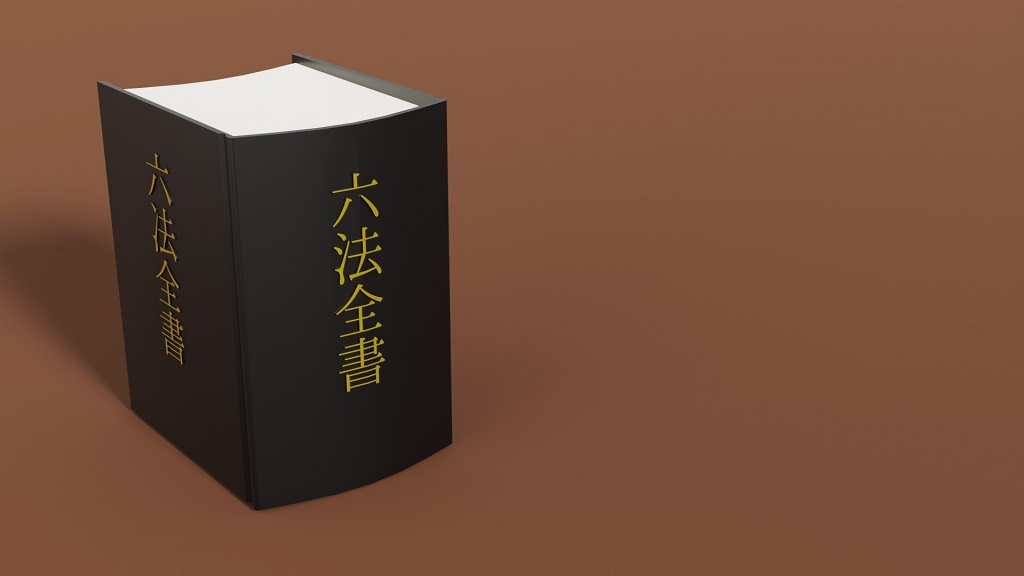
「休憩時間とは何かと問われても、休憩時間は休憩時間。それ以上でも以下でもないはず」と多くの方は思うかもしれません。確かにそう。しかし、意外と深掘りできる題材なのです。とりわけ管理するとなると、簡単には侮れません。
企業にとって、従業員に休憩時間を与えることは大切な義務です。だからこそトラブルの温床にもなり得ます。「仕事が忙しくて休憩が取れない」「休憩時間に仕事をしたのに給料が出ない」といった声が頻繁にあがる組織では特に要注意です。これを放置しておくとたちまち大きな問題につながります。
まずは、休憩時間とは何か。法律上の定義やルールを中心に紐解きましょう。
労働基準法で定められている
企業は従業員を雇用する際、労働基準法を守り人材を適切に管理することが義務づけられています。労働基準法とは、従業員が働くうえでの最低限の決めごとを定めた法律です。裏を返せば、雇用契約のなかで労働基準法に満たない雇用条件があった場合、その部分は無効化されます。
さて、それでは休憩時間に関する具体的なルールの紹介です。
労働基準法第34条において、次のように定められています。
- 労働時間が6時間以上の場合、45分の休憩を与える
- 労働時間が8時間以上の場合、1時間以上の休憩を与える
上記は、6時間以下の労働に関して休憩時間を与える必要がないことも示しています。
また、分割して与えることも可能です。たとえば、9時から18時までの勤務で1時間の休憩を与える場合、11時台に15分、13時台に30分、15時台に15分といった具合に配分できます。
休憩時間の3原則
労働基準法では、休憩時間について、次の3原則が定められています。
- 一斉付与の原則
- 途中付与の原則
- 自由利用の原則
いわゆる「休憩時間の3原則」です。それぞれ言及しましょう。
一斉付与の原則
一斉付与の原則とは、社内で働く従業員に対して、皆一斉に休憩を与えることです。 正社員に限らず、アルバイトやパート、派遣社員も含みます。
ただし、運送関連や販売、金融保険や保育者などの業種や、同一空間で同時に休憩をとるのが困難な職種(職場)に関しては対象外です。
また、シフト勤務や従業員の人数制限を設けていることから、休憩時間を交代制にせざるを得ない企業の場合、労働協定での合意のもと、休憩を一斉に与えなくてもかまいません。
途中付与の原則
休憩時間は、勤務が始まる前あるいは終了時間後に設けてはいけません。つまり、勤務時間の途中で設ける必要があります。これが、途中付与の原則です。
出社前や業務後に休憩時間を設定してしまっては、従業員の心身の疲労回復など到底見込めず、本来の目的に反します。当たり前とはいえ、非常に大事なルールです。
自由利用の原則
休憩時間の付与は、いわば従業員を労働から解放してあげることです。そのため、企業側がその時間の使い方に制限を掛けるような真似をしてはいけません。 よくあるのが、来客や電話対応です。これらは立派な業務であり、その間を休憩時間に数えることは、自由利用の原則に反します。すなわち、この場合、休憩中とはみなされません。
ただし、仕事内容、職種、環境、他者への干渉など、さまざまな観点で自由利用の原則が適用外とされるケースもあります。具体的には次のとおりです。
- 児童養護施設、乳児院、障害児入居施設など、児童に関する仕事に従事する場合
- 警察官、消防団員(常勤)など
- 事業所内に飲食可能施設や休憩施設を備えている場合の外出制限
- 事業の正常な運営や他の従業員の自由利用を妨害する行動
- 坑内労働者
パートにも正社員にも必ず与える
いうまでもなく、正社員はもちろんパート・アルバイトであっても雇用契約の締結は必要です。そのなかで休憩時間を与えることも雇用形態を問わず、義務化されています。
ただし管理職以上の立場の方に関しては、経営者と一体的な立場にある者とみなされるため、休憩時間を含む労働時間に関する法律が厳密にいうと適用外です。そうはいっても(労働者の安全と健康を確保すべく)、休憩時間自体をなくすことはできません。
▶関連記事:アルバイトの休憩時間の決め方って?法律に沿って解説
放置は罰則につながる
仮に休憩時間を与えることができなかった場合はどうなるのでしょうか。
くわしくは「休憩時間が取れないよくあるケース」の章でも後述しますが、人員不足やトラブルが原因で休憩時間を与えられない事態に陥ることは決して珍しくありません。雇用契約を結んだ際、企業は従業員に所定労働時間を明示しています。そのため、8時間勤務のなかで、1時間の休憩を取ってもらえなければ、額面では労働基準法違反です。無論、対処法はあります。「当日のうちに別の休憩時間を用意する」「休憩時間に働いた分の賃金を支払う」などです(こちらに関しては「休憩時間が取れなかった従業員への適切な対処」の章で詳しく解説します)。逆にいうと、何も対処せず放置してしまうと、労働基準法に違反します。その場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性が出てきます。加えて、社会的信用の低下も考えられ、企業へのダメージはおそらく思いのほか大きいものとなるでしょう。
従業員側の都合で休憩時間が取れなかった場合は?
では、従業員が自らすすんで休憩を取らずに働いたなら、どのように扱われるのでしょうか。ずばりこのケースでも、企業側がしっかり管理しなければなりません。仮に黙認したのであれば、給与の支払いは必須です。また、代わりの時間帯に休憩することを要求された場合、きちんと応じる義務があります。
こうした状況に見舞われないためには、休憩時間の労働を上司の承認制にするといった決まりを就業規則に明示するとよいでしょう。それであれば、休憩時間に従業員が許可なく働き、その分の賃金の支払いを求められた場合でも、拒否が可能です。
休憩時間が取れないよくあるケース

従業員が休憩時間を取らずに困っているのであれば、まずその原因を突き止めましょう。ここで紹介するのは、典型的な休憩時間が取れないケースです。つい休憩時間と捉えられがちでも実際は労働時間であるシチュエーションも多く、図らずもそれらを社内全体で間違って認識されていることは往々にしてあります。そうした落とし穴に気付くためにも、以下ご参照ください。
多忙を極める過酷な環境
「午前中、急なトラブルが発生し、どう考えても休憩時間を取っている場合ではなかった」「同僚の離職や欠勤が相次ぎ、人手不足のなか休まずに働くしかなかった」「とにかく忙しい」……等々、珍しい話ではありません。とてもじゃないけれども正常な環境とはいえないなかで仕事をする場合、正常ではないからこそ決められた時間どおりに休憩を取るのは困難です。
来客や電話対応
急な来客や電話がかかってきた場合、その対応は休憩時間にも及ぶことがあります。なかには、先方の都合や意向を汲んで、あえて休憩時間を利用するケースも珍しくありません。労働と休憩は法律上でこそ区分けられていますが、曖昧にしている企業も少なからず見受けられます。
ミーティングや勉強会への強制参加
ミーティングあるいは勉強会を休憩時間に設ける企業があります。従業員に強制する場合は、前述した「自由利用の原則」に反するものです。当然、休憩としては扱われません。ただし、従業員の任意で出欠が判断でき、欠席しても問題がないのであれば話は変わります。加えて、業務に直接関係がなく、希望参加で開催される講習なども同様です。これらは、休憩時間に含まれます。
仮眠時間、待機時間
企業からすると休憩の一部だと信じ込んでいた時間が、実際には労働時間として換算されるものだったケースは、まだまだあります。たとえば仮眠時間。警備員や看護師の方々は仕事の合間によく仮眠を取ることがありますが、これもまた立派な労働時間の一部なのです。また、上述した来客対応だけでなく、お客様が自社に訪れるまでに待った時間もれっきとした労働時間に該当します。
休憩時間が取れなかった従業員への適切な対処
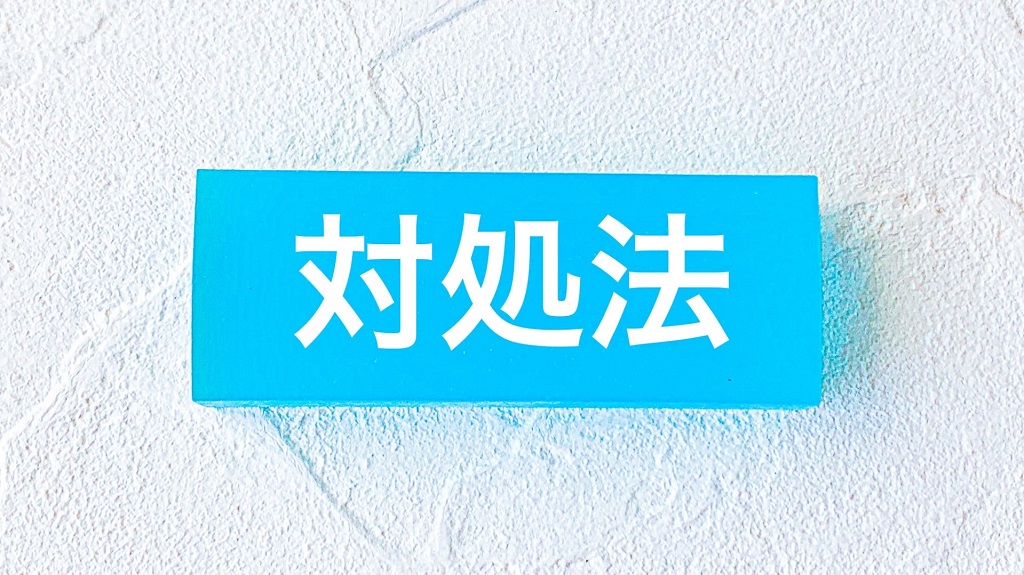
原因を突き止め、従業員がなるべく労働時間外に働かないよう用意周到に動ていもなお、業務が指定の休憩時間に及ぶことはあります。だからこそ、その後の対処が重要です。以下、具体的に説明します。
時間帯をずらす
急なトラブルや顧客対応などにより、決められた時間で休憩を取れなかった場合は、その日のうちに別の時間帯へとずらしてもらえれば問題ありません。そう、あくまで当日です。というのも休憩時間は、翌日以降に繰り越すことができません。
どうしても当日中に休憩時間を取らせることができなかった場合は、その分の賃金を支払う義務が生じます。
給与に加算する
休憩時間に働いた従業員にはその分、給与に加算しなければなりません。その際、支払う金額は、労働時間の種類によって異なります。それは、ずばり所定労働時間と法定労働時間による違いです。
所定労働時間とは、労働契約や、就業規則によって定められた労働時間を指します。法定労働時間とは、労働基準法が定めた労働可能な時間の上限です。具体的には、1日8時間、週40時間と定められています。
休憩時間も働いていた場合、法定労働時間を超えて働いたとみなされます。この場合、割増で賃金を支払わなければなりません。それでもなお、休憩時間を与えられなかったことは、労働基準法に違反している状態を意味します。くれぐれも賃金さえ支払えばよいといった考えに堕することないよう、企業は管理意識を高く持つようにしましょう。
▶関連記事:アルバイトの労働時間について、上限など労働基準法に則り解説
休憩時間に対する理解を深めることが大事!
労働基準法のもと、企業は休憩時間をきちんと与えなければなりません。また、取れなかった場合にも備えておく必要があります。そのうえで、もっとも手っ取り早くなおかつ有効な方法が、休憩時間自体に対する理解を深めることです。漠然としたままでは、気付かないところで法に抵触したり、企業イメージを落としたりといった災難に見舞われるかもしれません。法への理解、休憩時間への意識が、結果的に従業員を大切にすることにもつながります。その辺りのアピールがうまくいけば採用活動にもよい影響を及ぼすでしょう。バイトルシリーズやはたらこねっとなどdipが提供する求人広告の掲載サービスでもそれは十分に活用できます。自社の働き方を丁寧に記すだけでも訴求しやすい、伝わりやすい求人広告が生まれるはずです。すぐに導入とまではいかなくとも、気になる方は、ひとまず無料のお問い合わせ登録もおすすめします。
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。
【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所
代表 荒武 慎一
同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。

