アルバイトに対する減給とは?

アルバイトに対する減給については、しばしば賃金カットと混同されがちです。また、最低賃金法が適用されるかどうかも案外、曖昧な方がいらっしゃるかもしれません。本章では、アルバイトに対する減給が何を指すのか明確にすべく、これらの基本知識について説明します。
賃金カットとの違い
アルバイトに対する減給は、労働者が業務上の規律違反や職務怠慢などの問題行為を行った場合に、その個人への懲戒処分として賃金を一時的または継続的に減額するものです。これは労働基準法に基づき、(減給の制限や手続きが)定められています。一方、賃金カットは、企業の経営状況の悪化や業績不振などの理由で、全従業員または特定のグループに対して労働条件を変更し、賃金を全体的に減額する措置です。賃金カットを行う場合、労働契約の変更となるため、労働者の同意が必要であり、就業規則や労使協定の改定が求められます。つまり、減給は個人の行為に対する懲戒であり、賃金カットは経営上の理由による組織的な賃金削減というわけです。この点が大きな違いだといえます。
最低賃金法第四条は適用される?
アルバイトに対する減給においても、最低賃金法第四条は適用されます。同法第四条は、使用者が労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払う義務を定めており、これはすべての労働者が対象です。したがって、懲戒処分であっても減給後に最低賃金を下回ることは許されません。
参照:最低賃金法第四条
アルバイトに対する減給の違法性

労働契約法に基づき、企業側の一方的な決定による給与の減額は、労働条件の不利益変更として認められていません。そう、労働者の同意なしに労働条件を不利に変更することは違法なのです。これは、アルバイトを含むすべての労働者が該当します。
くわしくは次章でもお伝えしますが、減給には合理的な理由があるうえで個別の同意や十分な説明が必要です。労働者からすると、理不尽な処置に対しては、自身の権利を守るために労働基準監督署や労働組合に相談することができます。また、未払い賃金の請求や損害賠償を求めることも可能です。いずれにしても、企業は法令を遵守し、公正な労働環境を維持する責任があります。
参照:労働契約法第九条
アルバイトに対する減給が認められるケース

前述のとおり、アルバイトに対して減給することは原則、合理的な理由がない限りできません。しかしながら、懲戒処分として、かつ従業員側との合意に至った場合は例外的に認められます。本章では、これら特定の条件をピックアップ。減給を検討する際は、こうしたケースに当てはまるか確認する必要があります。
懲戒処分を下す場合
アルバイトが職務上の義務違反や不適切な行動をとった場合には、懲戒処分として減給を行えます。ただし、労働契約や社内規定に基づいた正当な理由がなければなりません。また、なぜ違反なのかをきちんと説明し、反論の機会を設けることも求められます。こうした条件を満たし、後述するように従業員側と合意形成できてはじめて減給が認められます。
従業員側との合意に至った場合
労働条件の変更には労働者の同意が必要です。これは、労働契約法第八条で定められています。たとえば、企業が経営上の理由や業績の悪化により賃金を減額したい場合でも、事前に労働者に十分な説明を行い、納得を得るまでは認められないわけです。なお、合意形成は口頭ではなく、書面で明確に残しましょう。客観的な証拠がなければ後々、トラブルになりかねません。あくまで従業員との信頼関係を保ちつつ、法的な手続きを踏むことが求められます。
参照:労働契約法第八条
アルバイトへの減給の理由として不適切なケース

アルバイトへの減給には正当な理由が必要です。一方で、そうでない理由とは具体的に何でしょう。本章で次のケースを挙げます。
- 妊娠や出産
- 育児休業や介護休業
いずれも、これを理由に言及することは許されません。以下、くわしく説明します。
妊娠や出産
妊娠や出産を控えるアルバイトに減給の措置を取ることは男女雇用機会均等法によって禁じられています。妊娠や出産は、労働者の基本的人権に関わる重要な事柄です。ゆえに、それを理由に賃金を減額することは性差別にも当たります。企業は労働者の権利を尊重し、公平な労働環境を提供しなければなりません。妊娠や出産を理由に減給することは、その義務に相反します。
育児休業や介護休業
育児・介護休業法では、労働者が育児休業や介護休業を取得する権利が保障されています。したがって、それを理由に減給することはできません。むしろ企業側は、従業員が仕事と家庭を両立できるよう、積極的に支援するべきでしょう。(育児休業や介護休業を理由にした減給が)不利益な取り扱いとみなされるのも当然です。
アルバイトの減給に際しての注意点

アルバイトの減給が可能か否かばかりに気を取られていると、思わぬ落とし穴にハマってしまうことも考えられます。具体的には次の注意点を念頭におく必要があります。
- 金額や期間には上限がある
- 懲戒処分が有効になるには条件がある
- 二重処罰は原則禁止
以下、それぞれ詳述します。
金額や期間には上限がある
アルバイトの給与を減額する際、その金額や期間には法定の上限が設けられています。労働基準法第九十一条によると、減給の額は一回の違反につき平均賃金の半日分を超えてはいけません。また、減給の総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えるのもご法度です。と、期間についても無制限に設定することはできず、就業規則や労使協定で明確に規定する必要があります。
仮にこれらを違反した場合、労働基準監督署からの是正勧告や罰則扱いとなる可能性が出てきます。
参照:労働基準法第九十一条
懲戒処分が有効になるには条件がある
懲戒処分としての減給を行うためには、労働契約法第十五条に基づく必要があります。ここで定められているのは次のとおりです。
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
安易に懲戒処分を下せないことは、すでにお伝えした内容と重なりますが、つまるところ客観的な証拠が求められるわけです。そのうえで(懲戒処分の対象者には)弁解の余地を与えなければなりません(違反行為についてきちんと説明したのち、彼・彼女らの言い分を聞く「聴取の機会」を設けることが義務付けられています)。処分の厳しさ(減給のレンジ)が果たして適切かどうかも、慎重に見定めていくことが重要です。
参照:労働契約法第十五条
二重処罰は原則禁止
一つの違反行為に対して複数の懲戒処分を科すことは認められません。そう、二重処罰は原則、禁止です。これは、労働者に対して過剰な制裁を防ぎ、公平な処遇を確保するために定められています。たとえば、減給と出勤停止を同時に科すといった行為は過度な処罰とみなされるわけです。そうなると、労働基準監督署への通報や法的な争いを招く恐れも出てきます。(こうしたリスクも念頭におきながら)企業側は処分を下すにせよ、くれぐれも慎重に進めるようにしましょう。
アルバイトの管理上、罰則を設けて減給できる?

アルバイトに手を焼く職場では、何かしら罰則を設けなければ状況が改善されないといった考えに至ることもあるかもしれません。ミスや遅刻が頻発する方、無断欠勤が続く方などに対しては、罰則に乗じ、減給を敢行したいのはやまやまでしょう。が、法律がそれを許すかどうかはまた別の話です。本章では減給可能か否か、雇用主の方々のよくある質問に対して回答します。
アルバイトのミスで生じた損害を給料から天引きできる?
損害額を給料から差し引くこと(勝手に罰金などを天引きすること)は、労働基準法第二十四条に違反する行為です。この規定は、労働者が不慮のミスから自由であることを保障し、過度な財務的負担から保護することを目的としています。そのため、たとえばアルバイトが対応した飲食店のレジの計算に誤差があったとしても、原則、その分を給料から天引きすることはできません。
ただし、明らかな故意や重大な過失がある場合は例外です。が、そのような状況でも雇用主は法的手続きに従って対応する必要があります。
アルバイトのミスに対して前もって弁償額を設定できる?
飲食店で働くアルバイトが誤って高価な食器を破損したとしましょう。この場合、お店側はアルバイトに弁償請求できるのでしょうか。これは、不慮のミスに当たるため、上述のケース同様で請求はできません。では、もしも前もって「お皿1枚の破損につき○○円の罰金」といったルールを設けていたらどうでしょう?
結論、これも請求することは禁止されています。なぜなら、労働基準法第16条(賠償予定の禁止)で、契約の不履行による違約金や損害に対する賠償金の規定は労使間で定めてはならないと決められているからです。就業規則に弁償額を設定しても、その規定は無効と見なされることでしょう。それでもなお、会社が一方的に設定した弁償額を強制すれば、法に抵触することになります。
遅刻や欠勤が続くアルバイトに対して減給できる?
遅刻や欠勤に手を焼くアルバイトに対しても、客観的合理性を欠き、社会的相当性がない場合は減給処分が困難でしょう。しかしながら、減給が認められる余地がないわけではありません。遅刻や欠勤が続くようなら懲戒の理由として妥当と判断されることも、適切な手順を踏めば、可能性が出てきます。
就業規則に明記のうえ、日々の勤務状況を管理し、かつ対象のアルバイトにフィードバックし、説明(弁明)の機会を設けたうえで問題行為とみなせるならば、懲戒処分として減給を行うことが可能です。
なお、懲戒処分であれ制約はあります。労働基準法第九十一条に基づき、減給の総額は月給平均(一賃金支払期ごとの賃金)の10分の1以下でおさえなければなりません。
参照:労働基準法第九十一条
アルバイトの減給を行う手順

ここまでお伝えしてきた内容を踏まえて、実際にアルバイトに対して減給を行う場合、どのような手順で進めればよいのでしょうか。ざっとステップを伝えると次のとおりです。
- 就業規則や労働契約書の確認
- 減給の妥当性を確認
- 従業員への説明
以下、それぞれ詳述します。
就業規則や労働契約書の確認
アルバイトの減給にあたってまずは、就業規則や労働契約書を確認しましょう。それらの文書には減給の条件や手続きの流れが定められているはずです。法的な規定、基準も然り。これによって、減給が労働者の権利を不当に侵害していないかを今一度見直すことができます。
減給の妥当性を確認
書類チェックのあとは、減給の理由に対する精査です。このフェーズでは、減給の妥当性をより細かく吟味していきます。その際、減給が従業員に過度な影響を与えないよう、適切な処置であるかまで検討することが必要です。
従業員への説明
減給を行う前には、対象のアルバイトに対してその理由を明確に説明しなければなりません。決して理不尽なことではなく、客観的にみて妥当か否かを、彼・彼女らにあらためて確かめてもらうフェーズです。そのうえで弁明、反論の機会も提供します。双方がなるべく納得できるように取り計らうことが肝要です。
アルバイトが減給を拒否した場合に取るべき対応
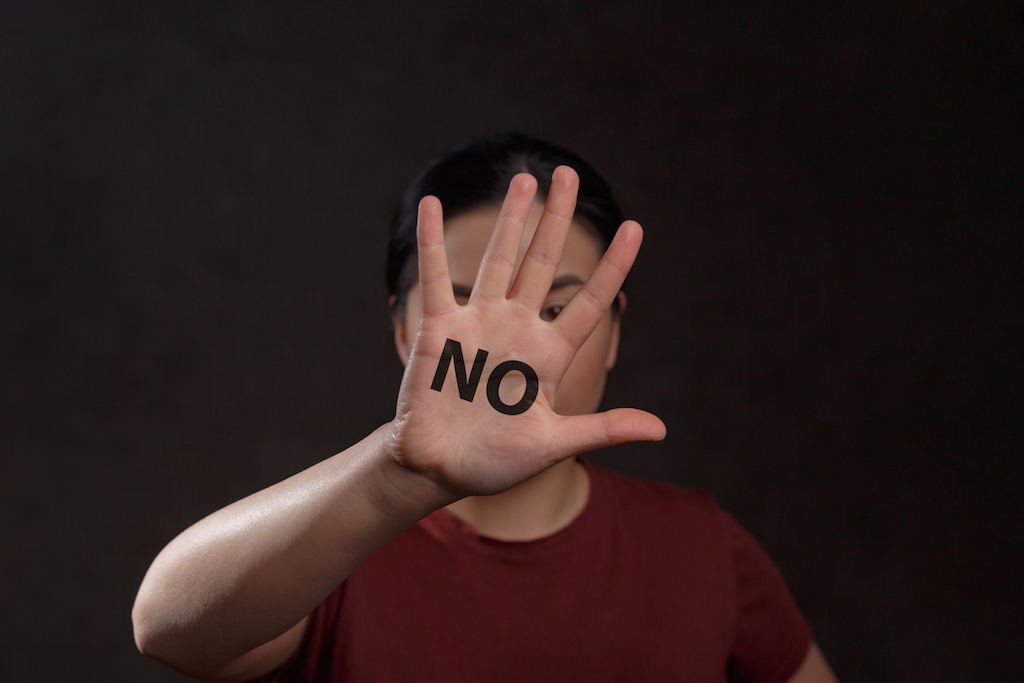
先の説明や反論する機会を与えた結果、思いがけず、アルバイトが減給を拒否することもあるでしょう。ここからは根気が必要です。従業員の懸念を払拭するための対話を進めつつ、それでも合意に至らない場合は、専門家に相談することも考えた方がよいかもしれません。あるいは勤務条件の調整やその他のインセンティブを提供するなど、金銭以外の解決策も考えられます。どの対応を選択するにしても、従業員との信頼関係を保ちながら、企業のポリシーと法的枠組みの中で対応することが求められます。
アルバイトの減給には法律の理解や慎重な手続きが必要!

アルバイトに対して減給したくとも、どうしても法律による制約は免れません。労働基準法や労働契約法は、懲戒処分を行う際の条件や手続きを厳格に定めており、適用には慎重さが求められます。特に、二重処罰の禁止や最低賃金法の遵守、労働者との合意形成など、企業は減給に至るまでに十分な配慮をしなければなりません。法的な手続きを怠ると、不当労働行為としてトラブルに発展する可能性があるため、就業規則の整備や減給の根拠を明確にすることが重要です。労働者の権利を尊重し、法律を理解したうえで適正な手続きを踏むことが、企業の信頼を守るカギとなります。
さらには、長期的な視点で労働環境を整えることで、企業は従業員の安心感を育み、健全な職場づくりが行えるでしょう。減給(懲戒処分)に頼るだけではなく、日常的な対話やフォローを通じて職場の調和を保つことが、結果として自組織の成長にもつながります。
求人掲載・採用業務のサポートや料金についてなど、ぜひ気軽にお問い合わせください。
また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談も無料で承っております!
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。
▶【公式】面接コボット – 応募者対応の自動化で面接管理が楽に!
┗求人サイトからの応募対応を自動化できるサービス。チャットボットを通じ、日程調整まで効率よく進めてくれます。
▶【公式】採用ページコボット – 費用・実績も紹介!採用サイト制作サービス
┗採用ページ作成サービス。求人まとめサイトとの自動連携や求人検索エンジンへの対応により外部集客を強化します。

