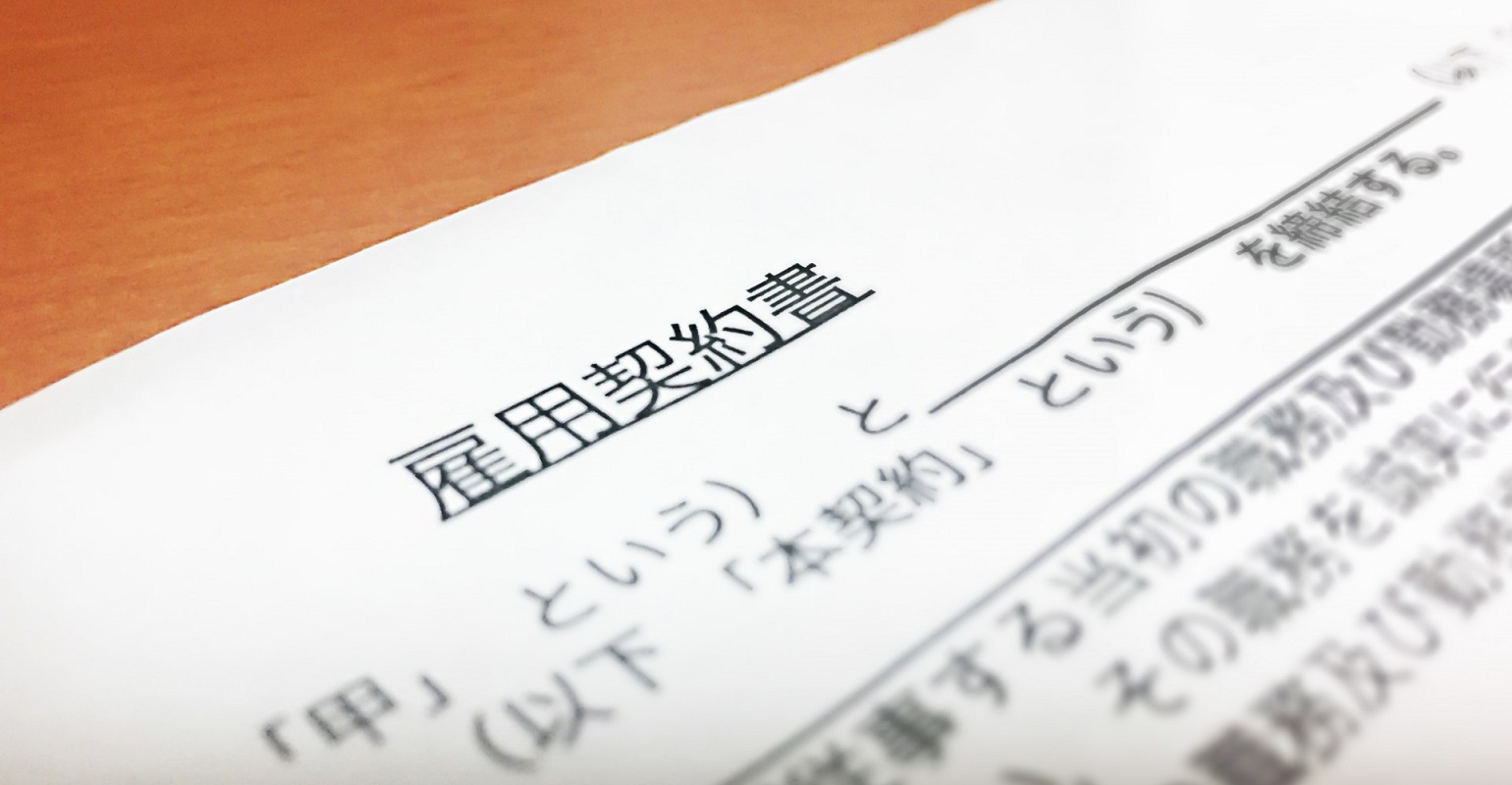個人事業主でも従業員の雇用を検討すべし!

まず、法人化していない個人事業主であっても、従業員を雇うことは可能です。外部業者への発注だけに依存せず、アルバイトを筆頭に自社・自店舗の一員をしっかり雇用することは、もはや当たり前に必要だと考えます。
というのも、いわゆる「外注」と「雇用」では、やはり異なるポイントによって品質や精度、コスト面に差が生じてしまうからです。前者はコミュニケーションで一苦労することも少なくありません。要望やルール、マニュアルを共有したところで正しく認識しないまま納品時に齟齬が発覚するケースも多々あります。そもそもスキルも厳密には未知数で測りづらく、仮に教育を要する場合でも、本人がプロジェクトや業務、発注先(つまりはその個人事業主)に対して少なからずモチベーションを見出さない限り、そこから成長を促すのはなかなか困難でしょう。
他方、雇用に舵を切った場合、従業員(として働いてくれる方)のみならず事業自体を、将来的に大きくしてくれる期待が持てます。もちろん、ミスマッチは付き物です。だからこそ、採用活動を行う際は、専門のサービスに任せることをおすすめします。
▶サービスのご案内:【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
個人事業主が従業員を雇用する際に必要な手続き

個人事業主が従業員を雇用するために必要な手続きは、大きく分けて次の5つのステップで構成されます。
- 労働条件の提示
- 労働保険・社会保険の加入
- 源泉徴収に対する準備
- 給与支払いを約束する書類の提出
- 法定三帳簿の作成と管理
それぞれ以下に解説。手続きの全体像、そして詳細についてもしっかりと把握してください。
労働条件の提示

従業員を雇用する際は、労働基準法により、賃金や労働時間等の労働条件を「労働条件通知書」として作成し、通知する義務があります。特に決まった書式はありませんが、厚生労働省が公開しているテンプレートを活用すると、項目にもれが出ず安心でしょう。以下、記入例含めて詳細をお伝えします。
労働条件通知書について
労働条件通知書とは、賃金や契約期間、休暇などの労働条件を従業員に提示するための書面です。労働基準法第15条により作成・通知が義務付けられているため、違反すると30万円の罰金など、ペナルティを科される可能性があります。
従業員側から希望があった場合に限り、FAXやメールでの交付も可能です。役所へ提出する必要こそありませんが、従業員退職後3年間は保管しておかなければなりません。
さて、記載項目は次の通りです。
- 契約期間
- 業務内容
- 就業場所
- 始業・終業時間
- 休憩時間
- 賃金の支払い方法
- 賃金の決定・計算方法
- 賃金の締日・支払日
- 昇給について
- 休日と休暇について
- 所定労働時間を超える可能性の有無
- 労働契約更新の基準(有期雇用労働者の場合)
- 就業時転換について(従業員を2組に分けて労働させる場合)
- 退職、解雇条件
上記は必須項目です。対して、下記項目は任意のものとして扱われています。が、労使トラブル防止の観点からも、しっかり書面を通じ交付することが望ましいでしょう。
- 職業訓練について
- 退職手当
- 臨時に支払われる賃金(賞与など)
- その他、従業員に通知が必要と思われる事項
なお、必須、任意問わずこれらに対しては情報管理を考慮する意味でも、NDA(秘密保持契約)や誓約書(就業規則を定めることが前提)の取り交わしをおすすめします。
テンプレートと記入例
労働条件通知書は、全体の統率を図る就業規則と比較すると、従業員一人ひとりのためのものだといえます。
具体的には上述した項目に対する内容を記入すればよいわけですが、手軽に気軽に着手するなら厚生労働省が公開しているテンプレートの活用をおすすめします。なお、2024年4月からは労働条件の明示ルールが変わるため注意が必要です。
(2023年現在)労働条件通知書 – 厚生労働省
▶関連記事:労働条件の明示義務について、ルールの改正とあわせて解説
と、これらを踏まえて各項目の記入例を紹介します。
契約期間
労働契約期間に定めがある場合、有期契約なら「2022年4月1日~2023年3月31日」といった具合に記載します。その際、試用期間があればその旨も加えてください。さらには、契約更新の有無やその判断基準も明示が必要です。
就業場所
就業場所に関しては、雇入れ直後の場所で問題ありません。勤務地が複数ある場合は、そのすべてを記載し、将来的な就業場所を網羅的に示すことも差し支えないとされています。
業務内容
就業場所と同様、雇入れ直後の業務内容を記載します。「営業」「販売」「経理」などそれぞれはっきりわかるように記載してください。
始業・終業時刻
「始業時刻9:00、終業時刻17:30」のように明示しましょう。と、労働時間に関して、始業時刻前の朝礼やミーティングに参加した分もしっかりとカウントしてください。
賃金
賃金の欄には「基本給:月給250,000円 通勤手当:5,000円/月」など、項目と金額を具体的に記載します。出来高制の場合は、最低賃金を下回らないよう注意してください。
休日・休暇
所定休日を記載します。「毎週土曜日・日曜日、国民の祝日」といった具合です。休暇については、年次有給休暇を付与する条件(6ヶ月間勤務し、出勤率が8割以上)とその日数を明示してください。
賃金の締日・支払日
賃金の締日・支払日は、「毎月25日」のように具体的に記載してください。残業が発生する可能性がある場合には、有りである旨や1ヶ月間で想定しうる時間を伝えます。
退職、解雇
退職や解雇に関しても伝えなければなりません。自己都合退職の場合も含めて、それぞれの事由および手続きについて記載します。
労働保険・社会保険の加入

「労働保険」は労災保険と雇用保険の総称を指し、「社会保険」は健康保険と厚生年金保険の総称を指します。業種や規模にかかわらず一人でも従業員を雇用した場合は、「労働保険」の加入手続きを行い(雇用保険は適用条件あり)、労働保険料を負担しなければなりません。一方、「社会保険」の加入に関しては、個人事業主が雇っている従業員数が5人未満であれば任意で行うことになります。裏を返せば、5人以上だと加入は必須です。
労働保険の手続き方法
まず、雇用保険は、所定労働時間と雇用見込みによって適用対象が異なります。
具体的には次のとおりです。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上雇用される見込みがある
そして労災保険は、事業主が1人でも従業員を雇用すると加入が必要です
上記を踏まえて、保険料の申告・納付には2通りあります。
一つは、雇用保険・労災保険の両保険を一本化するパターンです。いわゆる一元適用事業に対するもので、この場合の労働保険の手続きは、次のステップで行います。
| 1.「保険関係成立届」を、保険関係が成立した日の翌日から10日以内に管轄内の労働基準監督署に提出 2.「概算保険料申告書」を、保険関係が成立した日の翌日から50日以内に日本銀行または管轄内の労働基準監督署、都道府県労働局のいずれかに提出 3.「雇用保険適用事業所設置届」を、設置日の翌日から10日以内に管轄内の公共職業安定所(ハローワーク)に提出 4.「雇用保険被保険者資格取得届」を、資格習得の事実があった日から翌月10日までに管轄内の公共職業安定所(ハローワーク)に提出 |
保険関係成立届と雇用保険適用事業所設置届は、初めて従業員を雇用する時に提出し、概算保険料申告書と雇用保険被保険者資格取得届は従業員を雇用するたびに提出します。
次に、保険料の申告・納付のもう一つのパターン、二元適用事業での手続き方法です。これは、建築業や農林漁業などが該当し、先の一本化に対して雇用保険と労災保険が区別されます。
まずは、労災保険に係る手続きです。
| 1.「保険関係成立届」を、保険関係が成立した日の翌日から10日以内に、管轄内の労働基準監督署に提出 2.「概算保険料申告書」を保険関係が成立した日の翌日から50日以内に、日本銀行または管轄内の労働基準監督署、都道府県労働局のいずれかに提出 |
雇用保険に係る手続きは次のとおりです。
| 1.「保険関係成立届」を、保険関係が成立した日の翌日から10日以内に公共職業安定所(ハローワーク)に提出 2.「概算保険料申告書」を、保険関係が成立した日の翌日から50日以内に日本銀行または管轄内の都道府県労働局のいずれかに提出 3.「雇用保険適用事業所設置届」を、設置日の翌日から10日以内に管轄内の公共職業安定所(ハローワーク)に提出 4.「雇用保険被保険者資格取得届」を、資格習得の事実があった日から翌月10日までに管轄内の公共職業安定所(ハローワーク)に提出 |
保険関係成立届の書き方
保険関係成立届にある主な項目を取り上げ、それぞれ何を記せばよいのか、以下にまとめます。
参照元:保険関係成立届の記入見本
| 冒頭部 | 初めて従業員を雇用する場合は「保険関係成立届(有期)」と「任意加入申請書(事務処理委託届)」は関係ないため、二重線で消しましょう。提出先は、最寄りの労働基準監督署を記入し「届けます」を丸で囲んでください。 |
| 事業所の住所・名称・氏名 | 事業所(事務所や店舗など)の所在地・屋号・氏名を記入します。 |
| 事業 | 屋号と代表者名を記入します。 |
| 事業の概要 | 製造工程や作業内容、商品名など、具体的に事業内容が分かるように記入します。 (例) ・食料品や日用品などの販売(コンビニ) ・ウェブサイトの製作代行 ・金属製品の加工業 |
| 事業の種類 | 業種を記入します。 (例) ・小売業 ・飲食業 ・貨物取扱事業 |
| 賃金総額の見込額 | 保険関係成立届の提出日から、その年度の末日(次の3月末)までの間に従業員に支払う賃金総額(給与・賞与・残業代・手当)の見込額を記入します。 |
| 加入済みの労働保険 | 加入済みの労働保険があれば該当するものを丸で囲みます。 初めて従業員を採用する場合は、記入不要です。 |
| 保険関係成立年月日 | 労災保険と雇用保険それぞれに対して適用事業所となった日(対象従業員を初めて雇用した日)を記入します。 |
| 雇用保険被保険者数 | 雇用保険の対象に当たる従業員数を記入します。 |
| 常時使用者労働数 | 保険加入する年度の1日の想定平均従業員数を記入します。 |
| 免除対象高年齢労働者数 | 従業員のうち、4月1日時点で高年齢労働者(64歳以上)に当たる人数を記入します。 |
概算保険料申告書の書き方
続いて、概算保険料申告書にある主な項目を取り上げ、それぞれ何を記せばよいのか、以下にまとめます。
参照元:概算保険料申告書の記入見本
| 冒頭部 | 「概算」を丸で囲みます。 |
| 労働保険番号 | 保険関係成立届を提出した際に付与された「労働保険番号」を記入します。 |
| 雇用保険被保険者数 | 雇用保険の対象に当たる従業員数を記入します。 |
| 常時使用労働者数 | 保険加入する年度の1日の想定平均従業員数を記入します。 |
| 免除対象高年齢労働者数 | 従業員のうち、4月1日時点で高年齢労働者(64歳以上)に当たる人数を記入します。 |
| 概算・増加概算保険料算定内訳 | 算定期間内で従業員に支払う賃金の想定総額を記入します。 |
| 保険料率 | 労災保険と雇用保険の保険料率を記入します。 |
| 概算・増加概算保険料額 | 労災保険料額と雇用保険料額の合計額を記入します。 |
| 延納の申請 | 概算保険料が40万円以上(労災保険または雇用保険のみ成立している場合は20万円以上)であれば、延納(分割納付)が可能です。延納を希望する場合は、納付回数を記入します。 |
| 納付額 | 労災保険料額と雇用保険料額の合計額を記入します。 |
雇用保険適用事業所設置届の書き方
雇用保険適用事業所設置届にある主な項目を取り上げ、記入の仕方を以下にまとめます。
参照元:雇用保険適用事業所設置届の記入見本
| 事業所の概要 | 事業所の名称、所在地、電話番号を記入します。 |
| 設置年月日 | 雇用保険の適用事業になった年月日(雇用保険の被保険者となる従業員を初めて雇った日)を記入します。 |
| 労働保険番号 | 保険関係成立届の提出後に付与された14桁の番号を記入します。 |
| 事業主 | 事業主の住所、名称、氏名を記入します。 |
| 事業の概要 | 具体的な事業内容を記入します。 (例) ・木製品製造業 ・食料品の販売 ・清掃業 |
| 事業の開始年月日 | 事業の開始年月日を記入します。 |
| 常時使用労働者数 | 想定される1日の平均従業員数を記入します。 |
| 雇用保険被保険者数 | 雇用保険の対象従業員数を記入します。 |
| 賃金支払関係 | 賃金の締日と支払日を記入します。 |
| 社会保険加入状況 | 加入している社会保険を丸で囲みます。 |
雇用保険被保険者資格取得届の書き方
雇用保険被保険者資格取得届にある主な項目を取り上げ、記入の仕方を以下にまとめます。
参照元:雇用保険被保険者資格取得届の記入見本
| 個人番号 | マイナンバーを記入します。 |
| 被保険者番号 | 被保険者証を持っている場合はその番号を転記します。初めて被保険者となる場合は空欄にしてください。 |
| 取得区分 | 初めて被保険者となる場合は「新規」、被保険者番号を持っている場合は「 再取得」を選択します。 |
| 被保険者(氏名・性別・生年月日) | 被保険者の指名・性別・生年月日を記入します。 |
| 被保険者となったことの原因 | 以下のなかから該当する区分を選択します。 1.新規雇用(新卒・学卒) 2.新規雇用(その他) 3.日雇からの切替 4.その他 5.出向元への復帰等 (65歳以上) |
| 賃金 | 資格取得年月日での支払いについて、態様(「月給」「週給」「日給」「時間給」「その他」)を選択および賃金の月額を記入します。 |
| 1週間の所定労働時間 | 従業員の1週間の所定労働時間を記入します。 |
| 契約期間の定め | 契約期間の定めについて選択するだけでなく、契約更新条項の有無も記入します。 |
| 事業主 | 住所、会社名、代表名、電話番号を記入します。 |
社会保険の手続き方法
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入基準を満たす従業員を新たに採用した際、資格取得日(入社日)から5日以内に、申請書類を事業所の所在地を所轄する年金事務所に提出する必要があります。加入手続きに必要な主な提出書類は次のとおりです。
- 被保険者資格取得届(健康保険・厚生年金保険)
- 新規適用届(健康保険・厚生年金保険)
- 事業主の世帯全員分の住民票の原本…90日以内に発行したもの
被保険者資格取得届の書き方
被保険者資格取得届にある主な項目を取り上げ、記入の仕方を以下にまとめます。
参照元:被保険者資格取得届の記入見本
| 事業所整理記号・事業所番号 | 事業所整理記号は、社会保険に新規加入した際に「決定通知書」で事業所ごとに付与される番号のことです。数字とカタカナで構成されます。 事業所番号は新規適用時に年金事務所で付与された5桁の番号です。 |
| 種別 | 厚生年金基金に加入しているか否かにも気を付けて選択してください。 |
| 取得区分 | 厚生年金保険加入の有無、共済組合から一般企業へ出向した職員、船員保険の任意継続被保険者などで区分されるなかから選択します。 |
| 個人番号(基礎年金番号) | 個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号を記入します。 |
| 取得(該当)年月日 | 社会保険の適用開始日、すなわち入社年月日を記入します。 |
| 被扶養者 | 新たに採用する従業員に被扶養者がいるか否かを選択します。 |
| 報酬月額 | 報酬月額は、通貨と現物に分けて記入します。 前者は月額給与(基本給や手当等)の総額が該当します。 |
新規適用届の書き方
新規適用届にある主な項目を取り上げ、記入の仕方を以下にまとめます。
参照元:新規適用届の記入見本
| 事業主記入欄 | 事業所の所在地、名称、電話番号を記入します。 |
| 事業の種類 | 具体的な事業内容を記入します。 |
| 個人・法人等 区分 | (個人事業主の場合)個人事業所を選択します。 |
| 厚生年金基金番号 | 厚生年金基金へ加入している場合は、基金番号および基金の名称を記入します。 |
| 昇給月、賞与支払い予定月 | 該当月を記入します。 |
| 給与形態・諸手当の種類・現物給与の種類 | 該当するものをすべて丸で囲みます。 |
| 従業員情報 | 従業員と社会保険への加入者数を記入します。 加入しない従業員がいる場合も、その人数と勤務形態を書く必要があります。 |
源泉徴収に対する準備
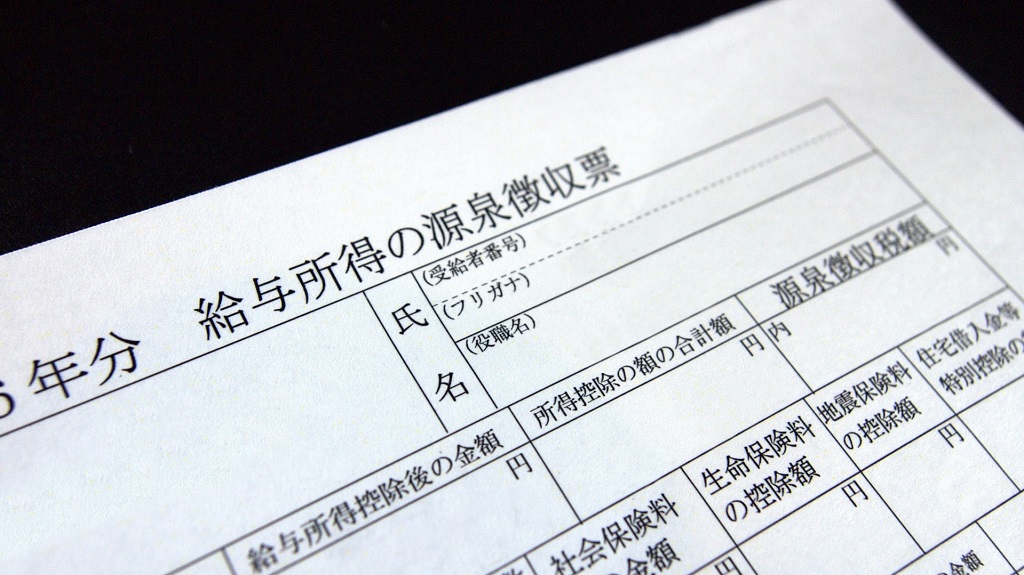
従業員を雇用して給与を支払う事業主は、給与に応じた納税額をあらかじめ差し引き、源泉徴収を行わなければなりません。その際、従業員の家族構成などによって適用税額が異なる点にも注意が必要です。正確に対応すべく「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は確実に提出してもらえるようにしましょう。
毎月行う源泉徴収
源泉徴収は毎月の給与支払い時に発生します。具体的には、総支給額(基本給・残業代・各種手当など)から社会保険料や非課税の交通費を差し引いて、手取り額を確定させ行います。控除対象については細かいところまで把握しておきましょう。たとえば、団体生命保険料や労使協定による財形貯蓄も控除対象です。また、退職金が発生した場合も、別途、源泉徴収が必要になります。
▶関連記事:源泉徴収票はアルバイトにも必要!発行時期や書き方について徹底解説
年末調整
年末調整は、毎月の源泉徴収と年間の合計所得との差異を解消するためのものです。年末調整で算出された「年調年税額」(所得税および復興特別所得税の額)と比較して、徴収が少なければ課税し、多ければ返金します。
また、年末調整を行うにあたり、従業員に適用される控除によっては以下の提出書類が必要です。
- 給与所得者の基礎控除申告書
- 所得金額調整控除申告書
- 配偶者控除等申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
なお、よくある誤解の一つとして「通勤手当(交通費)が源泉徴収の対象内か対象外か」を一概に認識される方がいらっしゃいます。厳密には一定額までは非課税(源泉徴収の対象外)です。
▶関連記事:交通費支給の際に知っておきたい非課税の基準
給与支払いを約束する書類の提出

初めて従業員を雇う際、税務署には「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。これは「従業員に給与を払います」と宣言する(知らせる)ものです。従業員を初めて雇用した日から1ヶ月以内に、所轄の税務署へ提出してください。
給与支払事務所等の開設届出書について
前述のとおり、「給与支払事務所等の開設届出書」は雇用した従業員に給与の支払いが必要な場合に税務署へ提出しなければならない書類ですが、個人事業主であれば、開業届(「個人事業の開業・廃業等届出書」)で事足りることもあります。というのは、後者の方にも給与の支払い状況について記入する欄が存在するからです。そうはいってもやはり提出のために準備しておくのが無難でしょう。
給与支払事務所等の開設届出書の書き方
給与支払事務所等の開設届出書にある主な項目を取り上げ、記入の仕方を以下にまとめます。
参照元:給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
| 日付 | 税務署に提出する日付を記入します。 |
| 税務署名 | 納税地を管轄する税務署の名称を記入します。 |
| 個人番号又は法人番号 | 個人事業主の方は12桁のマイナンバーを記入します。 |
| 開設・移転・廃止年月日 | 「開設」を丸で囲み、オフィスの開設日を記入します。 |
| 給与支払を開始する年月日 | 従業員に給与を支払う最初の日を記入します。 |
| 届出の内容および理由 | 会社を設立した場合は、「開業又は法人の設立」にチェックを入れます。 |
| 従業員数 | 給与を支払う従業員の人数を記入します。 |
提出方法
1部作成した後、所在地が管轄する税務署に持参または郵送します。
前者の場合は、本人確認できるものが必要です。個人番号と身元確認証(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)はあらかじめ準備しておきましょう。
法定三帳簿の作成と管理
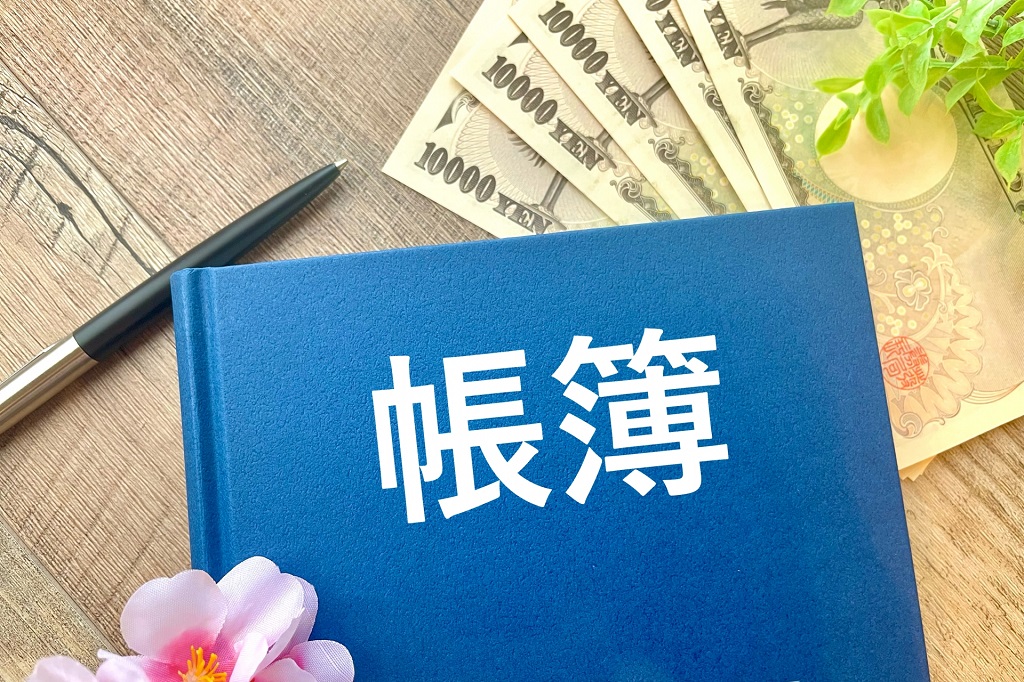
事業規模にかかわらず労働者の雇い入れを行った場合、「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の3つからなる「法定三帳簿」の作成が義務付けられています。これらは、労働基準法のもと、一定期間、保管しておかなければなりません。罰則もあるため、必ず対応しましょう。
法定三帳簿について
法定三帳簿は、企業側が労務管理を適切に行っていることを証明する大事な書類です。一方で法定三帳簿の作成・管理を怠った場合は30万円以下の罰金を科せられる可能性があります。労働基準監督署の臨検時に提出が求められるなど、問題ないかチェックされる場面は、往々にして予期せぬタイミングで訪れるものです。いつでも対応できるようしっかり保管しておいてください。
なお、法定三帳簿の保存期間はいずれも5年間ですが、起算日はそれぞれ異なります。こちらについても、正しく把握しておきましょう。
| 労働者名簿…従業員の退職・解雇・死亡日から起算 賃金台帳…従業員の賃金について最後の記入を行った日から起算 出勤簿…従業員の最後の出勤日から起算 |
労働者名簿の記入について
法定三帳簿の一つ、労働者名簿は労働者ごとに事業場単位で作成するものです。また、記載事項に変更があれば遅滞なく訂正しなければなりません。
記入事項は、次のとおりです。
- 労働者情報(氏名・性別・生年月日・住所)
- 履歴
- 業務の種類(従業員が常時30人未満でない場合)
- 雇用した年月日
- 退職、解雇理由と年月日
- 死亡した場合、その原因と年月日
上記以外では、電話番号をはじめ連絡先や社会保険に関連する内容など、任意で設けることも可能です。
▶関連記事:労働者名簿とは?書き方や保存期間・保管方法について解説
賃金台帳の記入について
賃金台帳もまた事業場単位で作成します。主な内容は従業員の勤務時間および支払われた賃金の詳細です。
記入事項は、次のとおりです。
- 労働者の情報(氏名・性別)
- 労働日数と労働時間
- 時間外・休日・深夜労働の時間
- 基本給や各種手当の額
- 賃金計算期間
- 賃金控除項目と控除額
賃金台帳は、雇用形態にかかわらず、従業員全員の内容を記載する必要がありますが、日雇い労働者に関して述べると賃金計算期間の記載は不要です。また、始業時刻や休憩時間も書く必要はありません。
なお、給与明細で事足りるのではないかといった向きもありますが、実際のところ、賃金台帳の代わりにはなりません。これは、(給与明細が)法が定める記入事項を網羅していないことが多いためです。
出勤簿の記入について
出勤簿は、従業員の出勤時刻や退勤時刻などの記録です。 労働者名簿や賃金台帳と異なり、労働基準法上で明文化された規定はありませんが、給料計算の基礎となるため、作成・管理自体は決して疎かにしてはいけません。
なお、労働者名簿や賃金台帳と同様に、事業場単位で作成する必要があります。
記入事項は、次のとおりです。
- 出勤日と労働日数
- 日別の労働時間
- 始終業の時刻と休憩時間
- 時間外労働、休日労働、深夜労働を行った日付と時刻と時間
出勤簿には定められた形式がありません。また、場合によっては(出勤したか否か、定刻どおり勤務したか)客観的な証明が難しいことも考えられます。こうした条件下では、やむを得ず自己申告で管理するのも可能です。ただし、そうした体制については、十分な説明が求められることも想定しておきましょう。
個人事業主がいざ従業員を雇用する際に意識すべきポイント

個人事業主が従業員を雇用するにあたっては、書類の提出や管理体制の構築など、色々とやるべきことが出てきます。そうはいってもやはり、“外注”にはない魅力やメリットがあるのも確かです。自社あるいは自店舗のメンバーだからこそ、組織の成長が期待できます。雇用によって加わる仲間は、そのための貴重な戦力になり得る存在です。
もちろん、ただ何とはなしに求人活動を行っては、ミスマッチも含めてうまくいかないことが多いでしょう。ターゲットやゴールの設定は不可欠だといえます。たとえば「任せたい業務は何か」「求めるスキルは何か」などです。加えて、本記事で述べた「雇用に必要な手続きや書類」を整理しながら、いざ採用の準備を進めることをおすすめします。
なお、採用活動を行ううえで個人事業主の方に紹介したいサービスの一つが「コボット」です。煩わしい応募対応を自動化するシステムで以て効率化を図ります。普段の業務でお忙しい方でも、採用活動との両立が可能です。ぜひ、この機会に導入をご検討ください。
▶採用活動を楽にしてくれるサービスページのご案内:【公式】人事業務を自動化・効率化!AI・RPA導入ならコボット
【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所
代表 荒武 慎一
同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。