介護業界は課題を抱えている

日本の総人口は2008年をピークに減少局面に入り、少子高齢化はさらに加速しています。2022年の高齢化率は28.9%に達し、今後も上昇し続けることが確実視されています。それに伴い、介護を必要とする高齢者の数も増加しており、介護サービスの需要は高まる一方です。
※参照元:高齢化の現状と将来像|令和4年版高齢社会白書(全体版) – 内閣府
それに対して、介護現場の人手不足は深刻化しており、サービスの質の維持・向上が大きな課題となっています。加えて、介護報酬の引き下げや人件費の高騰などにより、事業者の経営環境は厳しさを増しています。
このように、拡大する需要に応えながら、質の高いサービスを安定的に提供し続けるには、あらゆる困難を乗り越えていかなければなりません。しからば今日の介護業界は、「転換期」ともいえる岐路に立たされているのです。
介護業界の課題につながる社会問題

介護業界の課題を論じるうえで、まずは日本社会が抱える構造的問題を理解することが必要です。
ここでは以下5つのトピックスについて解説します。
- 2025年問題
- 生産年齢人口の地域格差
- 老老介護
- 認認介護
- 社会保障の財源不足
2025年問題
いわゆる「2025年問題」とは、団塊の世代がすべて75歳以上となる2025年に向けて、医療・介護需要の急増が見込まれている問題のことです。厚生労働省の推計によると、2025年には65歳以上の高齢者が3,677万人に達し、総人口の30%を超えると予測されています。介護サービスのニーズは今後ますます高まることが確実視されている状況です。
生産年齢人口の地域格差
少子高齢化の進行に伴い、総務省の推計によると、日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年の8,716万人をピークに減少し続けています。2030年代半ばには7,000万人を割り込む予測です。介護の担い手となる若年層の減少は、人材確保を困難にする一因となっています。
加えて、生産年齢人口の減少幅には地域差があります。総務省統計局によると、東京都では66.1%であるのに対し、もっとも低い秋田県では52.4%です(2021年時点)。地方の介護事業者にとって人材不足は、さらに切実な問題となっています。
老老介護
「老老介護」とは、高齢者が同じく高齢者(同居人など)の介護を担うことです。「2025年問題」が指摘されるなか、介護サービスを利用できない状況に追い込まれるケースが増加しつつあります。そのため、自身も介護が必要の身でありながら、親やパートナーの介護を行わなければならなくなるわけです。然るべき社会福祉が整わない(間に合わない)がゆえに引き起こされる由々しき問題だといえます。
認認介護
「認認介護」とは、認知症の人同士による介護を指します。厚生労働省によると、2012年時点で462万人だった認知症患者数は2025年には約700万人前後になると見込まれています。「老老介護」と同様、介護する側(そしてされる側)の肉体的・精神的負担は計り知れません。適切な介護サービスの提供が急務の問題です。
社会保障の財源不足
日本の社会保障給付費は年々増加しています。今後も、(少子高齢化の進行により)年金・医療・介護などに要する費用は増大していくことが明らかです。一方で、(生産年齢人口の減少により)社会保険料収入の伸びは鈍化していくと見込まれます。したがって、社会保障の持続可能性には常に不安がつきまとうでしょう。
介護業界が直面している主な課題
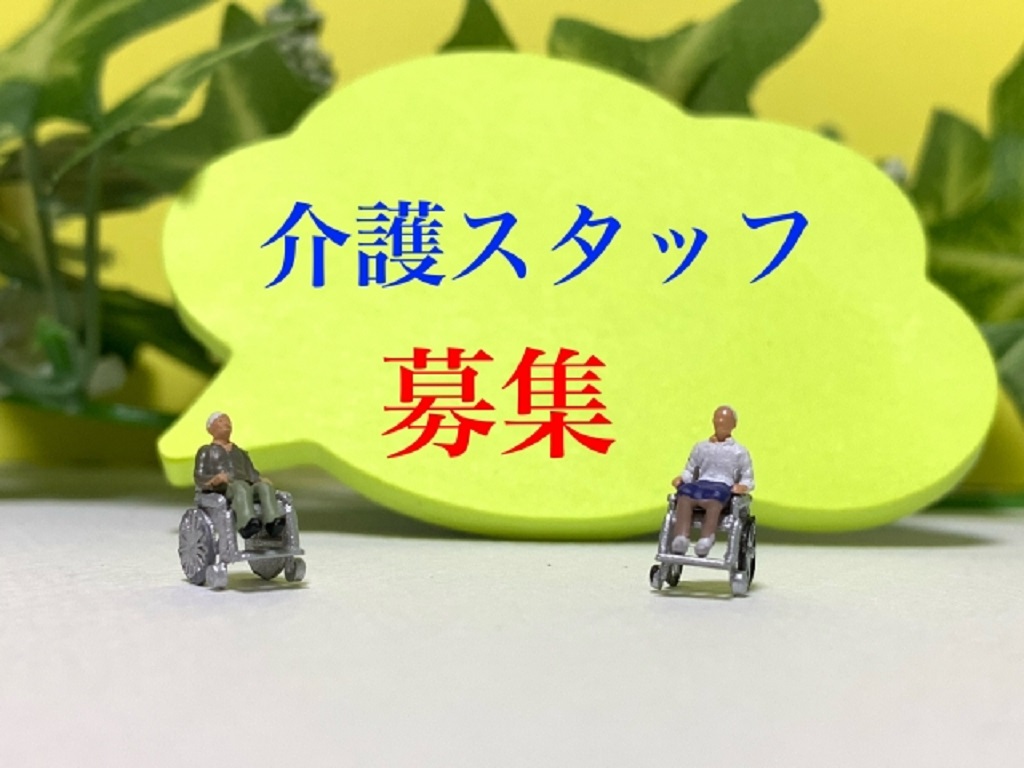
介護業界が抱える課題のなかで特に重要なのが次の4つです。
- 求める人材の獲得
- 離職防止
- 経営難からの脱却
- 介護業務の効率化
以下、それぞれ詳述します。
求める人材の獲得
繰り返しお伝えしているとおり、介護人材の確保は急務の課題です。が、介護職員が数少なくなれば、当然、人材獲得競争は激化します。経験者にこだわらず主婦層やシニア層へと採用ターゲットの範囲を広げる施設も見受けられますが、それでも苦戦されているところがほとんどです。これは、雇用形態問わず職種別にみた有効求人倍率の高さからもうかがえます。
▶関連記事:最新!アルバイト・パートの有効求人倍率(エリア・職種別あり)
▶関連記事:最新!社員の有効求人倍率(エリア・職種別あり)
離職防止
介護業界で人が足りない要因は離職率の高さも挙げられます。ではなぜ人材が定着しないでしょう。一概にはいえなくとも、パブリックイメージでも浸透しているように、過酷な労働環境、そこに対して割に合わない報酬、融通の利かない勤務形態……等々が蔓延っているのかもしれません。実際これらが当てはまっている場合、精神的・肉体的な負担の大きさから離職につながるのは至極、当然です。
貴重な人材を確保しても、すぐに辞められてしまっては現場が回りません。離職防止のための職場環境の整備は不可欠です。
経営難からの脱却
介護報酬の引き下げや人件費の高騰などにより、介護事業者の経営環境は厳しさを増しています。赤字の施設だけでなく、たとえ黒字でも今後の運営に対して「先行きが不透明」と感じている事業者は多くいるのが現況です。外部環境の変化にも柔軟に応じるべく、これまでのやり方を見直し、効率的な運営体制の構築を進めていく必要があります。
介護業務の効率化
介護の現場では、煩わしい事務作業に追われてしまい、肝心の利用者への対応が疎かになるケースも問題視されています。限られた人員で効果的にサービスを提供するには、業務の効率化を進めることが不可欠です。適正な管理体制を構築し、職員の負担を減らしつつ、利用者の安全と満足度の向上につなげていく必要があります。
介護業界の課題が生まれる原因

そもそも前述した課題が生じる原因はどこにあるのかもしっかりと把握しておく必要があります。人材確保だけでなく定着の視点も忘れてはいけません。具体的には次のとおりです。
- 待遇面に対する期待度、満足度が高くない
- 労働環境に対するイメージがよくない
- 経営コストと介護報酬がアンバランス
- 業務システムがアップデートできていない
以下、それぞれ詳述します。
待遇面に対する期待度、満足度が高くない
介護職は「きつい、汚い、危険」といったイメージが未だ根強い傾向にあります。にもかかわらず賃金水準は、厚生労働省が公表している賃金構造基本統計調査(令和5年度版)をみると、依然低いことがわかります。
求職者の立場からすると、「やりがいを感じられる仕事」とはいえ、生活を支える賃金水準でなければ、選択肢から外れてしまうでしょう。また、現役の介護職員にとっても、努力が正当に評価されず、将来への希望を見出せない環境では、意欲を保ち続けることは難しいはずです。
求める人材を呼び込み、定着してもらうために、介護事業者には賃金をはじめとした大幅な待遇改善が求められています。
労働環境に対するイメージがよくない
未経験者の多くは、介護の仕事に対して肉体的にも精神的にもハードなイメージを抱きがちです。たとえば、夜勤を含めた不規則な勤務、入浴介助などは身体的負担の観点で敬遠される要素のひとつに挙げられます。他方、利用者やその家族からの過度な要求、クレーム、はたまた職場の人間関係といったメンタル面で苦労することへの懸念を示す求職者も少なくありません。
経営コストと介護報酬がアンバランス
介護事業者の収入の大半は介護報酬ですが、その水準は必ずしも十分とはいえません。基本報酬は据え置かれたまま、加算項目が細分化されるなど、算定要件は年々厳格化しています。とはいえ、人件費を上げていくことは至難の業です。物価水準が年々上がっているため、コストは増大し続けています。結果として、収支のバランスが崩れ、運営に窮するケースも出てくるわけです。こうした背景から、待遇改善の原資を捻出できない事業者は、決して少なくありません。
業務システムがアップデートできていない
介護業界では未だに、アナログな業務が色濃く残っているのが実状です。日々の業務記録の作成や情報共有に多くの時間を費やしているケースはそこかしこで見受けられます。にもかかわらずテクノロジーの導入に二の足を踏むため、業務の非効率性はなかなか改善できないわけです。
介護職員の負担軽減は定着率アップのカギを握ります。また、時代の流れに乗れずにいれば、上述した介護業界のイメージは一向に改善しないでしょう。これは、これからの人材獲得にも影響する大きな問題です。
介護業界の課題に自分たちの施設はどう取り組めばよいか?

では、施設の方々は介護業界の課題に対して具体的にどのような策を講じればよいのでしょうか。いくつか列挙すると次のとおりです。
- 多様な人材にアプローチする
- 給与・福利厚生を整備する
- 職場環境を見直す
- 資格取得支援制度を導入する
- 採用業務を効率化する
無論、一朝一夕で解決できるものではありませんが、一つひとつ着実に取り組んでいくことが重要です。以下、それぞれ詳述します。
多様な人材にアプローチする
深刻化する人手不足を踏まえ、これまでの採用ターゲットを広げていくことが求められます。具体的には、次のような層へのアプローチを検討してみましょう。従来の枠組みにとらわれず、柔軟な発想で採用に取り組むことが重要です。
主婦層
ブランクがあっても丁寧な研修で専門性は十分に身につけられます。子育て中の女性を中心に、ワークライフバランスが取りやすい職場環境をアピールするとよいでしょう。
シニア層
定年退職後の高齢者の雇用も選択肢の一つです。豊富な社会経験やコミュニケーション力を武器に、若手職員の良き相談相手となってもらえる可能性があります。短時間勤務など柔軟な働き方を提案するのも有効です。
外国人
EPA(経済連携協定)に基づく介護福祉士候補者の受け入れのほか、在留資格「特定技能」での採用も選択肢に入ります。言語面や生活習慣の違いなど、受け入れ態勢の整備には一定の負担がかかりますが、幅広い人材獲得の点では検討に値するでしょう。
給与・福利厚生を整備する
介護人材を惹きつけ、定着してもらうには、給与・福利厚生制度の見直し、再整備も大事です。
とはいえ給与を大幅に上げるのは難しいかもしれません。が、福利厚生の面では、少なくとも下記の対応は(未整備なら)前向きに検討していきたいところです。とにもかくにも、従業員のニーズを適切に把握し、働きがいを実感できる職場づくりが求められます。
社会保険の完備
雇用保険、健康保険、厚生年金保険などは、従業員の安心につながる基本的な制度です。
有給休暇の取得促進
年次有給休暇の計画的付与を進め、ワークライフバランスの実現を支援しましょう。
産休育休制度の整備
子育て中の従業員が安心して働き続けられるよう、法定を上回る手厚い制度設計を心がけましょう。
資格取得支援制度
介護福祉士などの資格取得を支援する助成金制度などを用意し、キャリアアップを後押ししましょう。
メンタルヘルス対策
ストレスチェックの実施やカウンセリング体制の整備など、従業員の心身の健康をサポートする取り組みも重要です。
職場環境を見直す
職場環境も多くの介護施設で改善の余地があります。一人ひとりが意欲的に働くには、ちょっとしたことでも変えられるところは変えていく姿勢が大切です。職員たちの声に積極的に耳を傾けるなど、意識次第で見直せることは多くあると考えます。
業務フローの見直し
施設利用者のニーズを満たしたうえで、現場での業務フローの効率化を図りましょう。無駄な負担を減らすことが人材定着にもつながります。
労働時間の適正管理
長時間労働の常態化は避けるべきです。シフト管理を徹底し、時間外労働の削減に努めましょう。
コミュニケーションの活性化
職員間の風通しの良い関係づくりを心がけましょう。定期的な面談の実施やレクリエーションの企画など、コミュニケーションの機会を増やすことが有効です。
ハラスメント防止
パワーハラスメントやセクシャルハラスメントは、そもそもあってはならないことです。当然、職場の士気にもかかわります。研修など を通じて意識啓発を図るとともに、適切な相談・対応体制を整えましょう。
資格取得支援制度を導入する
介護福祉士などの国家資格の取得を支援することは、キャリアアップを図る意欲的な従業員の背中を押すのにもってこいです。もちろん、求職者に対しても有効に作用します。自己研鑽を励みながら、専門性を高められる職場であることを対外的にアピールできれば、有望な人材の確保につながるはずです。
採用業務を効率化する
人材獲得競争においては採用業務の効率化も肝になります。というのも煩雑な事務作業に追われ、肝心の採用活動が疎かになってしまっては本末転倒です。応募者管理に漏れが生まれ、貴重な人材が他社に流れる恐れもあります。そうならないよう、採用プロセスに対しても手を打たなければなりません。
なお、dipが提供する『面接コボット』を利用すると、応募者対応を24時間365日自動化できます。面接日程調整も管理画面またはメールで届く応募者がWEB上で選択した希望日を承認するだけで完了。採用担当者の工数を大幅に削減できます。また、複数の求人媒体の応募情報を一元管理できるため、情報の見える化にも寄与。採用業務に費やす時間とコストを最小限に抑えつつ、採用成功に集中できる環境整備が実現可能です。
▶面接コボット:【公式】面接コボット – 応募者対応の自動化で面接管理が楽に!
まずは介護業界の課題を把握し、できることから改善を図ろう!

介護業界を取り巻く環境は厳しさを増していますが、社会を支える重要な役割を担っていることに変わりはありません。目の前の課題に臆することなく、着実に打開策を講じていく姿勢が何より大切です。
人材面の対策としては、これまでの発想を転換し、多様な人材へのアプローチを図ることが求められます。あわせて、働きがいを実感できる職場環境の整備や、キャリア形成の後押しにも力を入れていくことが大事でしょう。
加えて、業務の効率化や経営基盤の強化など、息の長い取り組みも欠かせません。
他社や市場の変化にも目配りしつつ、一歩ずつ前に進んでいきましょう。
▶関連記事:介護業界の人手不足がやばい!?原因や解決策を交えて解説
▶関連記事:介護職採用のコツとは?介護人材を獲得するために必要なこと
▶関連記事:介護業界は人手不足なのに採用難、定着難。その原因と対策を解説
▶サービス:介護業界の求人掲載なら、プロ人材が集まるサイト『バイトルPRO』
人員不足は、決して一朝一夕で解消できるものではありません。が、いくら難題でも、変化を恐れず立ち向かうことで道は開けるはずです。拙稿で述べた対策や、取り上げた事例がそれを伝えています。とにもかくにも人員不足という逆境を、組織を変革するチャンスと捉え、前向きに取り組んでいきましょう。
求人掲載・採用業務のサポートや料金についてなど、ぜひ気軽にお問い合わせください。
また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談も無料で承っております!

