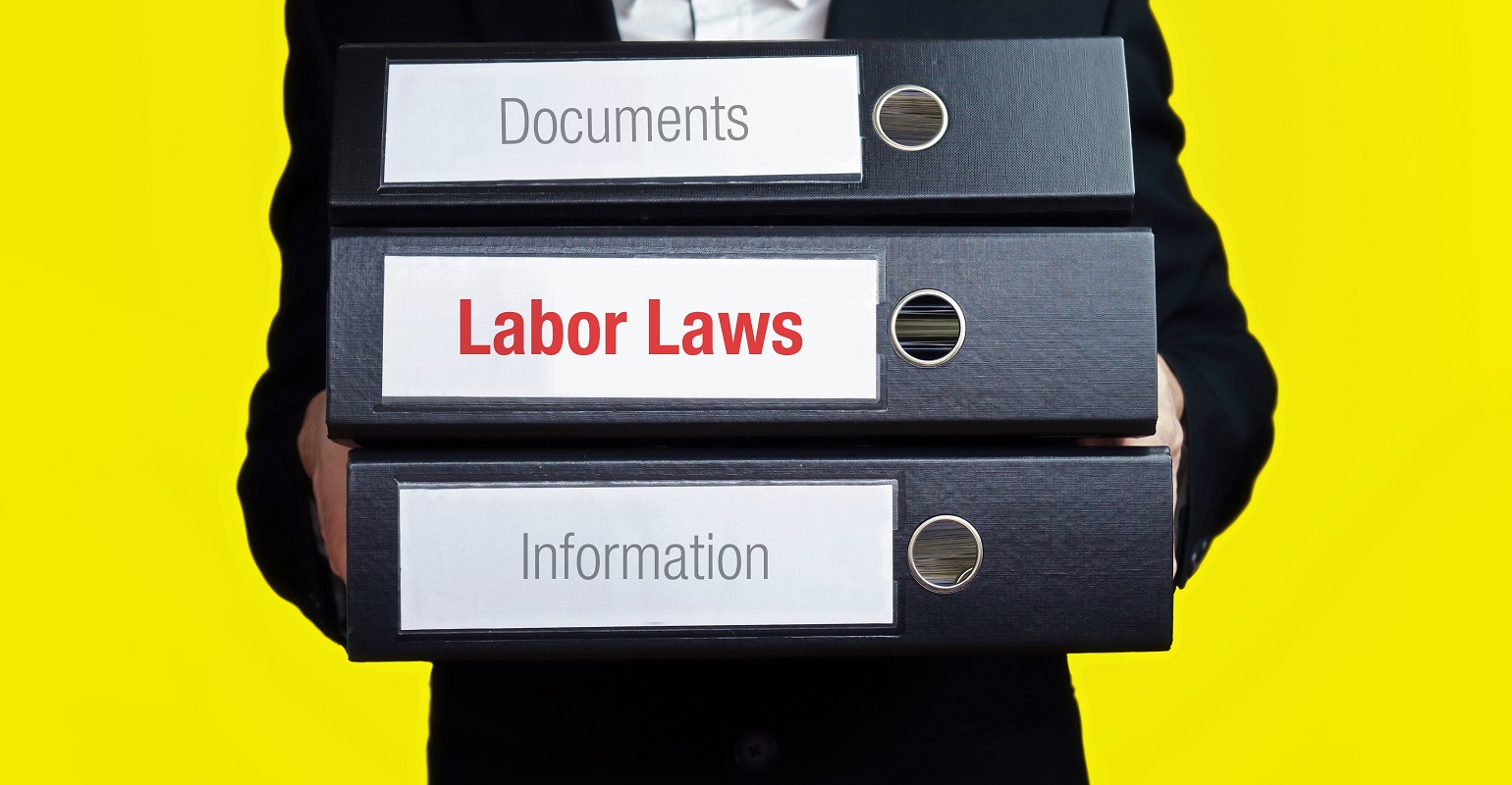パートタイム労働者について

一口にパートタイム労働者といっても、実際にどのような定義に沿ってその方々を指すのでしょうか。以下、“そもそもパートタイムとは何か”を補足し、“アルバイト”との呼称の使い分けについても言及しながら、基本概要を説明します。
パートタイムとは?
パートタイムとは、端的に述べると企業が指定する労働時間よりも短い勤務時間を指します。パートタイムで働く方々は文字どおり、パートタイム労働者です。もしくはパートタイマーと呼ばれることも少なくありません。なお、(くわしくは次章にて後述しますが)パートタイム・有期雇用労働法では、パートタイム労働者を「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と定義しています。ここでいう「通常の労働者」とは、同一の事業主に雇用される正社員(無期雇用フルタイム労働者)や正職員です。“通常”の判断は業務の種類ごとに行い、賃金体系・雇用体系などを総合的に見て判断されます。事業所に同種の業務に従事する正規労働者がいない場合は、フルタイムで働いている従業員がそれに該当。他方、その時間に満たない方々がパートタイム労働者です。
パートタイム労働者とアルバイトの違い
パートタイム労働者と“アルバイト”は法律上で特に区別はありませんが、あえてパブリックイメージだけで分類するならば、前者は平日の昼間に働く主婦(主夫)、後者は学生やフリーターの印象が強いかもしれません。また、求人広告などで企業側が独自に書き分けていることも多いように思われます。
▶関連記事:パートとアルバイトに違いはあるの?社会保険や扶養の観点からも解説
| サービスのご案内についてはこちら▼ 料金表付き!求人掲載サービス「バイトル」 サービスの導入事例をピックアップ▼ 2、3件だった応募数が一気に30件! |
パートタイム労働法について

パートタイム労働法は、正式には「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の名のもと、1993年12月に施行されました。パートタイム労働者が能力を有効に発揮できる環境および能力に応じた公正な待遇を受けられる環境の整備を目的として制定された法律です。その後、パートタイム労働者の雇用環境をより良くしようと、頻繁に改正が行われています。結果、2020年4月に更新されたのが現行の『パートタイム・有期雇用労働法』です。以下、詳細を解説します。
パートタイム・有期雇用労働法とは?
パートタイム労働者の待遇は、多くの企業において、その働きぶりや貢献度との乖離がみられ、正社員とも顕著に格差が生じてしまうといった問題が見受けられました(ます)。そうした不合理をなくすことが、パートタイム・有期雇用労働法の目的です。もちろん、これは従来のパートタイム労働法でも目指していました。が、対象範囲を有期雇用労働者も含めたことや、事業所ではなく企業単位にまで広げた点は明白な違いといえます。
▶関連記事:同一労働同一賃金とは?パートタイム・有期雇用労働法の解説交えて言及!
こうした経緯を踏まえて、パートタイム・有期雇用労働法にはどのような特徴があるのか、いくつかの観点から紹介します。
労働条件
パートタイム労働者を雇用する際は、労働条件を文書で明示することが義務付けられています。口頭で説明していたとしても、後になって「それは聞いていない」などトラブルになりかねないため、やはり雇用契約書や労働条件通知書の作成は必須です。その際、次の項目は確実に盛り込むようにしてください。
- 賃金
- 契約期間
- 更新の基準(有期契約の場合)
- 就業場所
- 労働時間
- 業務内容
- 退職に関する事項
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与の有無
- 相談窓口
▶関連記事:労働条件の明示義務について、ルールの改正とあわせて解説
就業規則
パートタイム労働者を含め常時10人以上の労働者を使用する雇用主は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。その際、便宜を図る意味でも正社員向けとパートタイム労働者用に分けて作成しておくとよいでしょう。
なお、労働条件の明示もそうですが、就業規則の提出も義務事項に当たります。違反した場合、30万円以下の罰金が科せられる可能性があるため必ず作成・対応しましょう。
賃金
パートタイム労働者に支払う賃金は、職務内容・成果・能力・意欲などに基づき、通常の労働者との均衡を考えた額にしましょう。そのうえで最低賃金や割増賃金にも注意が必要です。とりわけ後者は、時間外労働や深夜労働、休日出勤など細かく規定されています。
福利厚生
福利厚生もまたパートタイム・有期雇用労働法において、パートタイム労働者と正社員に格差が生まれないよう是正が図られています。たとえば、社会保険や労働保険、医療関連、住宅関連、そのほか各種手当をはじめとしたライフサポート全般、両者に不合理な違いがあってはいけません。教育研修の実施、休憩室・更衣室・給食施設の利用なども同様です。
説明義務
事業主は、雇用管理の改善事項などパートタイム労働者からの相談に応じるべく、措置内容の説明を行う必要があります。たとえば「給与が低い」「手当が出ない」などの不満はまさしく不合理な待遇差に結びつきやすい要素です。このときパートタイム労働者から理由を求められた場合、事業主はロジカルに説得しなければなりません。 なお、パートタイム労働者の要求に対して、不利益をもたらすように取扱うことは法律により禁止されています。
苦情対応
パートタイム労働者からの苦情には「相談窓口」を設置することが義務付けられています。事業主は、パートタイム労働者からの苦情の申し出を受けた場合、自主的な解決を図らなければならないのです。事業所内の苦情処理機関を活用するほか、人事担当者が自らクレームを担当するなど努力が必須です。
なお、事業主またはパートタイム労働者の一方または双方の申し出があれば、都道府県労働局のもと、無料かつ非公開で紛争解決の手続きが行えます。パートタイム労働者との間で発生したトラブルがどうしても平行線をたどる場合は、利用を検討してもよいでしょう。
パートタイム労働者と通常の労働者の均衡待遇推進について
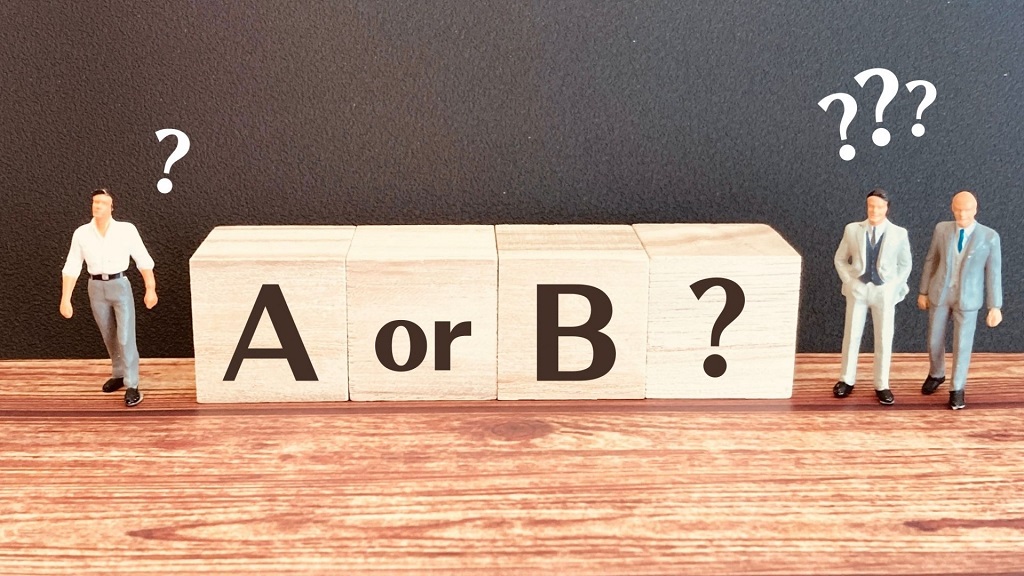
待遇面でパートタイム労働者と通常の労働者の間に不合理な差を設けてはならないことは、ここまで述べてきたとおりです。では、両者の均衡を図るためには、どのようなアプローチが有効なのでしょうか。以下、説明します。
均衡待遇とは
そもそも、均衡待遇とは何を意味しているのでしょう。これは、同じ職務を担う従業員に対して、同じ賃金・待遇を与えることを指します。性別・国籍・年齢などの個人的な要因によらず同じ報酬を与えることが原則です。無論、パートタイム労働者と通常の労働者においても同様。逆にいうと、業務内容に違いがある場合は、それぞれに応じた賃金を支払う必要があります。
一つの職務に対して雇用形態はじめ属性による差を生むことのない相応の報酬を与えられれば、公正な労働環境の提供につながるため、従業員のモチベーションや生産性の向上が期待できます。
業務内容の比較
均衡待遇を推進する以前に、まずは両者の差の有無を知る必要があります。そうなると当然、業務内容の把握も必須です。そのうえでそれぞれの中核的業務を抽出し、実質的に同等か否かを判断しなければなりません。ざっくり述べると「与えられた職務を行う際に不可欠な業務」「成果が事業所の業績や評価に大きな影響を与える業務」「労働者の職務全体に占める時間や頻度の割合が大きな業務」などが判断材料として該当します。また、権限範囲やトラブル時の役割、ノルマ達成に対する責任の度合いも重要項目に置いてよいでしょう。
人事異動の有無や範囲の比較
パートタイム労働者と通常の労働者に対して、それぞれ昇進や配置転換を行う場合、その範囲も比較しましょう。ある労働者はエリア限定の転勤、もう一人は全国転勤といったケースであれば、もちろん同等とはいえません。
自社状況の見直し
前項を踏まえて、待遇差を判断する術は、待遇項目(基本給、賞与、各種手当、休暇、福利厚生、教育訓練)と内容(業務、配置の変更範囲、職務の成果、経験、能力事業主と労働組合との交渉経緯、合理的な労使の慣行)の掛け合わせだといえます。
一方で厚生労働省が発表している「同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)」もまた、わかりやすい物差しでしょう。
ガイドライン自体はあくまで基本的な考え方を示すもので、法的に拘束力が働くわけではありませんが、大いに参考になるはずです。
パートタイム労働者を雇うメリット・デメリット
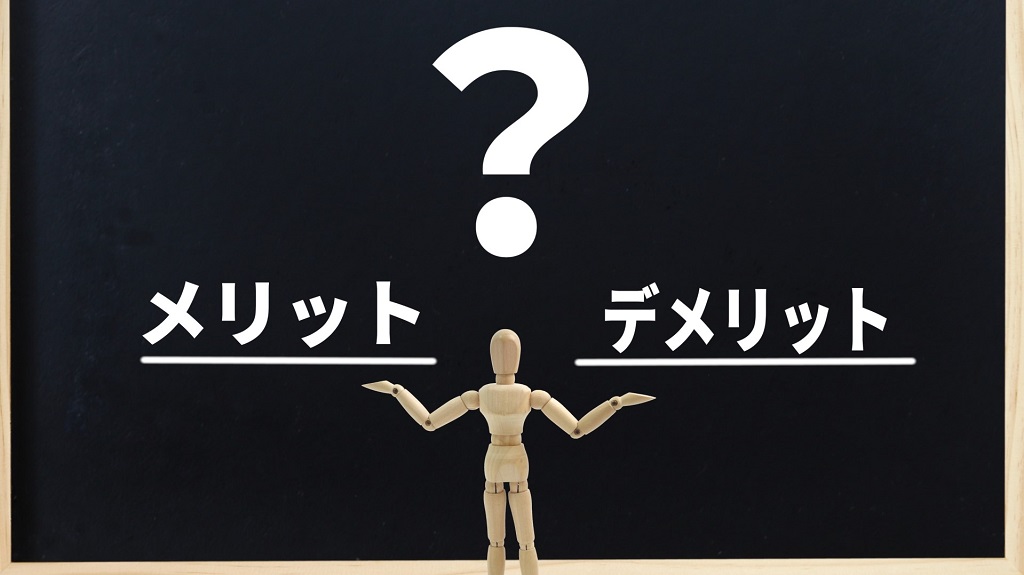
冒頭でも述べたとおり、パートタイム労働者の価値がより高まっていく気運のなか、いざ雇用するにあたっては当然、メリットもデメリットも両方理解しておくことが大事です。そういうわけで、以下それぞれピックアップします。
メリットその1:人員調整しやすい
一つめのメリットに挙げるのが、人員調整のしやすさです。繁忙期や、昼間、土日など人が足りない時に働いてもらえる点だけでも重宝したくなるのはうなずけます。柔軟なシフト調整は、決して働く側だけでなく、雇用する側にとってもありがたいことなのです。
メリットその2:人員コストを抑えられる
パートタイム労働者が担う業務は、一般的に正社員と比較してマニュアル化しやすいものが多く、仕事の難易度はそう高くない傾向にあります。そのため、支払う賃金を相応に抑えることが可能です。ただし、あくまでもそれはパートタイム・有期雇用労働法に違反しないことが前提にあります。再三お伝えしているとおり、通常の労働者と同じ業務内容にもかかわらずパートタイム労働者だからという理由で給与(待遇)に差をつけてはいけません。
メリットその3:将来的には正社員人材としても見込める
パートタイム労働者にゆくゆくは正社員になってもらいたい事業者も少なくないでしょう。優秀な人材ならなおさらです。仮にそうした人物を正社員登用した場合、業務はもとより環境にも十分馴染んでいるため、より責任のある仕事を担当してもらったところでそうミスマッチは起きにくいと考えられます。このように、将来に向けた人事の基盤体制を構築する意味でも、パートタイム労働者を雇うことは有効なのです。
デメリットその1:本業が優先される
パートタイム労働者のほとんどが主婦(主夫)や学生であることを考えると、どうしても子育てや学業など、彼・彼女らにとっての本業が優先されるのは致し方ありません。繁忙期や人手不足の際に頼りになるパートタイム労働者ですが、一方で本業ではない分、急な欠勤や、休みが長期に及ぶことも多々出てくることは、あらかじめ認識しておいた方がよいでしょう。
デメリットその2:長期的に働く人が少ない
パートタイム労働者は長期的に働くことを前提にしていない方が多く、離職へのハードルは低い傾向にあります。そのため、従業員の頻繁な入れ替わりが発生する企業はそこかしこで見られます。本来であれば人材育成にも注力したいところですが、特に何も手を打っていなければ、人手不足の問題を根本から解消するのはなかなか困難かもしれません。他方、裏を返せば、中長期的な視野で採用活動に取り組むことで、こうしたデメリットを払拭できる可能性は十分にあるでしょう。
パートタイム労働者の雇用にパートタイム労働法の理解は必須!

パートタイム労働者を雇用するのにパートタイム・有期雇用労働法の理解は欠かせません。安易に設定した給与体系が、通常の労働者との不合理な待遇差を生み、違反行為で罰則を受ける可能性もあります。それとは別に、パートタイム労働者を重用することが昨今の人手不足問題を食い止める糸口になるケースもあるでしょう。そもそも雇うこと自体、人員調整やコスト削減、将来を見据えた戦力確保につながる期待が持てます。いずれにせよ、(社内の競争力を高めるためにも)パートタイム労働者が活躍できる環境を整えることは、企業の命題です。ぜひ柔軟に対応してほしいと思います。
求人掲載・採用業務のサポートや料金についてなど、ぜひ気軽にお問い合わせください。
また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談も無料で承っております!
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。
【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所
代表 荒武 慎一
同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。