人手不足の問題を放置してはいけない理由

人手不足の問題を抱えつつ、何も手を打たなければ、状況はどんどんと悪化していきます。具体的には「サービスの質低下」であったり、「連鎖退職」であったり、それこそ「人手不足倒産」のリスクも高くなる一方です。まさにこうした事態を避けるべく、放置しないよう気を付けなければなりません。以下、くわしく解説します。
サービスの質低下
人手不足は、顧客への価値提供に直接作用するといっても過言ではありません。十分に人員が揃わなければ従業員一人あたりの業務負担は増加し、本来なら丁寧に対応できる業務も手短にまとめることを余儀なくされます。結果、サービスに対して満足度の低下を招き、クレーム増加や顧客離れを起こしてしまうわけです。特に中小企業では限られた人員で多様な業務をこなす傾向にあるため、一人の欠員が及ぼす影響は思いのほか大きくなります。
連鎖退職
ただでさえ人手不足なのにもかかわらず、そこからまた一人と抜ければ、残された従業員の業務負担はさらに嵩むことになります。その状況に耐えられず辞めてしまう方が出てくるのも想像に難くないでしょう。こうなるともう悪循環です。従業員が次々と離職しても何らおかしくありません。特に中堅社員の離職は、単なる人数の減少以上に現場のナレッジ喪失という形で大きな打撃です。退職者が出るたびに採用・育成コストが発生し、さらに人材不足が加速することで企業の成長戦略そのものが頓挫する可能性も十分に考えられます。
人手不足倒産
繰り返しお伝えしているように、昨今は人手不足による倒産が顕著です。帝国データバンクの調査によれば、2024年の人手不足倒産は累計342件に達し、前年比で約1.3倍に増えています。(調査を開始した2013年以降の)過去最多を2年連続で大幅に更新。特に建設業界や物流業界で目立ち、全体の約4割を占めています。
物価高も深刻ななか、人件費に多くを割けない中小企業はどうしてもこのような危機に直面しがちです。待遇改善や設備投資が困難な場合、採用にも響くでしょう。人が足りないのに人を集められない。人手不足倒産は、いわば構造上の問題ともいえます。これを放置せず一刻も早く解決策を講じていくのは、もはや必須の命題です。
人手不足感が強い業界

労働市場の需給バランスを客観的に把握するため、厚生労働省は「労働者過不足判断D.I.」という指標を公表しています。これは、「不足」と回答した事業所から「過剰」と回答した事業所の割合を差し引いて算出されるものです。つまり、数値が大きいほど人手不足だと感じていることを示します。本章では、業界にフォーカス。どの産業、分野が人手不足感を強く抱いているのか、正社員等労働者とパートタイム労働者に分けてお伝えします。
正社員等労働者に対して
正社員等労働者では、運輸業や建設業、医療・福祉分野で特に人手不足感が顕著です。具体的には下表にまとめています。(単位:%、ポイント)
| 産業 | 不足 | 過剰 | 労働者過不足判断D.I. |
|---|---|---|---|
| 医療・福祉 | 64 | 1 | +63 |
| 運輸業・郵便業 | 58 | 1 | +57 |
| 建設業 | 58 | 1 | +57 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 58 | 2 | +56 |
| 情報通信業 | 55 | 1 | +54 |
少子高齢化や技術者不足が如実にあらわれた結果のようにも見て取れます。たとえば、運輸業・郵便業は物流の需要増加や2024年問題なども影響しているのでしょう。長期前提で正社員を採用したからには、定着につながる対策が早急に求められます。
パートタイム労働者に対して
パートタイム労働者では、とりわけ宿泊業・飲食サービス業の人手不足感が目立ちます。具体的には下表のとおりです。
| 産業 | 不足 | 過剰 | 労働者過不足判断D.I. |
|---|---|---|---|
| 宿泊業・飲食サービス業 | 55 | 1 | +54 |
| 卸売業・小売業 | 40 | 2 | +38 |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 41 | 5 | +36 |
| 運輸業・郵便業 | 35 | 0 | +35 |
| 医療・福祉 | 40 | 5 | +35 |
低賃金や不安定な労働環境が人材定着を妨げている一方で、繁忙期に対応すべくアルバイト・パートを柔軟に雇いたくとも、なかなかうまくいかないのが実状のようです。そのため、求人での訴求やサービス選定にも意識的に取り組む必要があると考えます。
人手不足に陥る要因

人手不足の解決策を検討する前に、まず把握すべきは根本的な原因です。これが曖昧な場合、たとえ対策を打ったところでうまくかみ合わなければ課題解消には至りません。そしてそれを続けても埒が明かない可能性があります。
とはいえ人手不足の問題は、大体が組織風土と採用戦略の2つに集約されるケースがほとんどです。以下、それぞれくわしく解説します。
組織風土の問題
過度な業務負担や長時間労働、上司との信頼関係の欠如、成長機会の乏しさなどは、従業員の離職を招く大きな要因です。こうした環境が改善されないままでは、一人ひとりのモチベーションは下がり、次々と辞められてしまうのも無理はありません。そしてこのネガティブな状況が悪い評判として外部に広まると、たちまち採用活動にも悪影響を及ぼします。欠員を補充したくとも求職者から敬遠されてしまえば、一向に人手不足は解消されないでしょう。
採用戦略の問題
採用活動は試行錯誤がつきものです。それゆえ従来のやり方に固執してしまっては、状況を打破するのが難しいと考えます。そもそも戦略がきちんと打ち立てられていないケースも珍しくありません。人材要件、採用基準、注力する時期、取り入れる手法、利用する媒体、サービス……等々、人手不足に陥っている企業こそ調整を図り指針を定める余地が多く残っているはずです。また、競合他社の情報や市況の動向についてもリサーチが欠かせません。そのうえでどう自社の魅力を伝えていくかが問われます。いずれにせよ、採用戦略を疎かにした場合、人材確保に苦戦するのは至極当然だといえます。
人手不足の解決策

前述した要因を踏まえてどのような施策が人手不足には有効なのでしょうか。定着につながる手を打てばよいのか、はたまた採用面のテコ入れが大事なのか。
結論はずばり、両軸で取り組むことです。そう、人手不足の問題解決を図るにはどちらか一方に偏るのではなく、どちらにも注力することが求められます。
上記の観点で、以下、具体的な解決策を紹介します。
ノー残業デーの設定
長時間労働は多くの職場で問題視されています。フィジカルだけの話ではなくメンタルの面でも疲労は蓄積していくものです。これが辛く辞めることを検討している従業員もいれば、無自覚なまま頑張ってしまい倒れる方もいらっしゃいます。やはりこのような状況は避けなければなりません。そしてメリハリをつける意味でも、残業させない日を作ることは重要です。いわゆるノー残業デーの制度を設けることは、業務の見直しや効率化を促進する仕組みとしても機能します(もちろん、ノー残業デーに限らず、こうした取り組みは日常的に行えるとよいでしょう)。特に管理職が率先して定時退社することで、組織全体の意識改革につながります。「残業=熱心」という旧来的な価値観からの脱却は、少なからず働きやすさを生み、人材の定着や確保に寄与するはずです。
テクノロジーの活用
テクノロジーの活用でいくつかの業務を自動化できると、一人当たりの負担軽減につながり、効率的な労働環境が作り出せます。とはいえ、企業規模によってはなかなかコストをひねり出すのが難しいでしょう。しかしながら最近は、費用をそこまでかけずとも導入できるクラウドサービスが多く出てきています。なお、dipが提供する『面接コボット』もその一つです。
テレワークの推進
テレワークの導入は従業員の働きやすさに加え、採用ターゲットの幅を広げる点でも有効です。たとえば前者は、通勤時間の削減によるタイムパフォーマンスの向上やワークライフバランスの改善などが該当します。後者については、遠く離れた地に住む人たちや、育児や介護との両立を図りたい方々にもアプローチできることがメリットです。まさに定着面、採用面の両方から人手不足を回避できます。
融通が利く勤務時間の設定
多様な人材ニーズに応えるには、勤務時間も柔軟さが必要です。最たる例ではフレックスタイム制などが挙げられるでしょう。これによって育児・介護世代やシニア層も安心して応募できるはずです。結果、幅広く母集団形成が図れます。
特に人材不足が顕著に出ている小売・サービス業では、従業員の希望を反映した勤務体系が定着率向上につながるでしょう。
▶関連記事:固定就労と変則就労の違いとは?メリット・デメリットも併せて解説
▶関連記事:固定シフトとは?メリット・デメリットや自由・完全シフトとの違いも解説
サバティカル休暇の導入
サバティカル休暇とは、一定期間勤続した従業員に対して、比較的長期の有給休暇を付与する制度です(一般的には、5年や10年といった節目の年に、数週間から長くてひと月以上の休暇が与えられます)。この制度によって心身のリフレッシュや自己成長につながれば、従業員のモチベーションも上がり、安易に離職されることも減るでしょう。
▶関連記事:サバティカル休暇とは?福利厚生制度の一つとして企業向けに紹介
給与体系の見直し
優秀な人材の確保と定着のためには、どうしても給与を上げざるを得ない側面があるのも否めません。とはいえ、いたずらに賃上げしたところで企業にとっては財務負担が嵩み、それはそれで困窮する羽目になる恐れがあります。そのため、状況に応じてインセンティブや特別賞与など(できる範囲で)段階的かつ慎重に対応することも大事でしょう。が、業界平均と比較して著しく低いようなら、結局は自社の給与体系にはっきりとメスを入れなければならないとも考えます。
教育体制の見直し
新入社員、はたまた求職者からしても、教育体制が整っていない環境に対して不安に駆られるのは当然です。だからこそ、これを見直し、安心して業務に取り掛かれる環境を作っていくことが求められます。「教える人がいない」「教え方が属人的」などはもってのほか。ただマニュアルを渡したり、形式的な研修を行ったりするのも避けましょう。きちんと成長していく過程を管理できる仕組みのもと、レクチャー(マネジメント)することが大事です。可能であればコーチングのスキルを持ったメンターを付けるのも望ましいでしょう。
スキルアップ機会の拡充
スキルアップを図りたい従業員の希望に応えられる環境でなければ、辞められてしまう、または応募が来ない状況に陥っても仕方ないでしょう。裏を返せば、人手不足を解消するためにもそうした機会をどんどん作っていくことが大事です。具体的には、資格取得支援や外部セミナー参加への補助など積極的におこなっていけるのが望ましいと考えます。それらは、いわば付加価値です。特に中小企業の場合は採用競争に勝つためには必須といってもよいかもしれません。もちろん、今いる従業員のモチベーションアップを図る意味でも効果的です。
副業・兼業の許可
昨今は、かつてのように一社で出世していくサクセスストーリーを願う向きが減り、管理職、重役へと上りつめずとも副業・兼業で収入アップを図る労働者が増えてきている時代です。実際、一つの世界に閉じこもるのが嫌で離職する方も多いなかで、副業・兼業を解禁することは大なり小なり魅力的な制度だといえます。こうしたトレンドや変化を敏感に察知し、柔軟に許容することが人手不足に悩む状況を打開する第一歩かもしれません(そもそもそういった企業は人手不足に陥ることも少ない)。
ダイバーシティ採用
人手不足の解消には採用ターゲットの幅を広げることも一つの手です。年齢、性別、国籍……等々にとらわれることなく多様な人材にアプローチできれば、それだけ接点が増え、人員を確保できる期待もぐっと高まります。実際、こうしたいわゆるダイバーシティ採用によって、優秀な仲間が増えたといった声も少なくありません。企業イメージもポジティブに昇華され、エンゲージメント向上にもつながるケースはしばしば見受けられます。
▶関連記事:ダイバーシティ採用とは?企業の取り組み事例やアンケート調査の結果も交えて解説
ダイレクトソーシング
ダイレクトソーシングとは、企業が直接、求職者にアプローチする採用方法です。今の時代、人材紹介会社に頼らずとも、自社に合いそうな方とコンタクトを取ることはできます。求人サイトの機能として備わっているものも少なくありません。つまるところ、応募がこなければこちらから仕掛けていくというわけです。人手不足を食い止めるにはそういった姿勢が何より大事だと考えます。
▶関連記事:ダイレクトソーシングとは?メリット・デメリットや事例も交えて解説
採用特化サイトの作成
自社で採用に特化したサイトを持つことで、特長や魅力がより伝えやすくなるでしょう。求人サイトなどのプラットフォームとは違って、載せられる情報は格段に広がります。仕事内容一つをとっても、解像度をぐんと上げられるはずです。知名度がそう高くない企業ならなおさらでしょう。ユニークなコンテンツがひょんなことから拡散され話題になれば、まさに採用ブランディングとして機能することになります。自社の資産として継続的に運用できる点もメリットです。軌道に乗ったときには安定して人材を確保できているかもしれません。
参考:【公式】採用ページコボット – 費用・実績も紹介!採用サイト制作サービス
スポットワーカーの活用
空いた時間に働くいわゆるスポットワーカーの存在は、近年ますます注目を集めています。必要な時にシフトを埋めてくれるため、重用する企業も少なくありません。繁忙期をはじめイベント業務など一時的な人員増強には特にうってつけ。彼・彼女らがまさに人手不足を解決してくれます。
▶関連記事:スポットワーカーとは?採用するメリットや懸念点、平均時給などくわしく解説
そして求人市場においては、スポットワーカーの採用に特化したサービスも増えています。dipが提供する『スポットバイトル』もその一つです。最短で即日マッチングが可能。掲載費用をかけずに済むため費用対効果の向上に期待が持てます。加えて、「Good Job ボーナス」の機能も無視できません。モチベーションを担保する仕組みゆえにリピート応募が見込めます。こうした特長からも、安心して募集できるでしょう。
参考:【公式】空いた時間のスポット募集ならスポットバイトル|求人掲載はこちら
人手不足の解決を図った中小企業・小規模事業者の事例
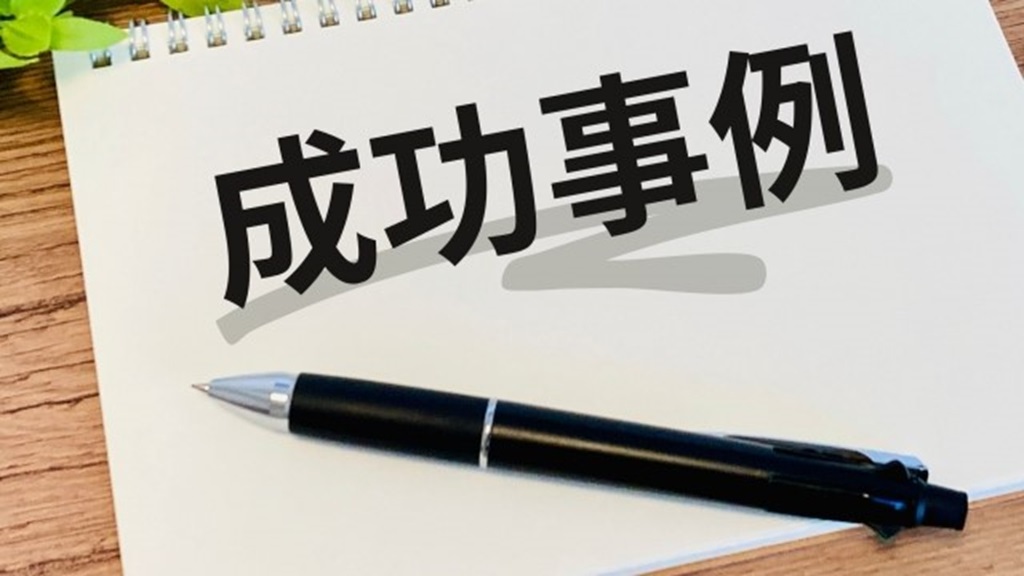
前述した解決策だけでなく、実際にどのようにして困難を乗り越えたのかがわかるエピソードや事例も、人手不足の問題に対峙するうえでは大いにヒントになり得ます。本章にてピックアップする話は、中小企業庁によって公表済みの「地域中小企業人材確保支援等事業(中小企業・小規模事業者における優良事例調査等事業/地域ネットワーク実証事業)」で作成された事例集を基にしたものです。ぜひ、参考にしてみてください。
参考:中小企業・小規模事業者の人手不足への対応事例(令和2年2月 中小企業庁)
部署別採算表の活用により、社員の士気が向上
株式会社英田エンジニアリングでは、有給休暇の取得が進まない、利益率の低い業務に工数が割かれるといった問題を抱えるなかで業務の見直しと効率化を図る必要がありました。残業時間の削減、何より社員のモチベーション維持は必須の命題だったわけですが、部署別に採算表を導入したことが一つの転機となります。具体的には部署ごとの収支を可視化。その結果、目標管理はもちろん、社員一人ひとりが利益や生産性を意識するように変わります。業務改善の提案など自発的なアクションも増えた模様。採算管理の工夫が、働き方に対する当事者意識の醸成、社員の士気、ひいては職場全体の活力向上へとつながった好例です。
周囲がサポートできる体制を構築
株式会社一ノ蔵では、長年にわたり残業が常態化し、社員の有給休暇取得もままならない状況でした。そこで、業務負担の集中を防ぐべくいくつか対策を講じます。たとえば生産現場では多能工化を推進、事務職の部署ではジョブローテーションによって業務を共有できる体制づくりに注力します。そして、全社一斉の有給取得日の導入です。これにより、(有給取得に対する)心理的なハードルが下がり、狙いどおり取得率が向上したといいます。ただ、これらの取り組みは社員同士で業務を補完できる環境が整ったからこそできることです。「一人で抱え込まない」仕組みが、人員が欠けてしまってもうまく対応できているのだと考えます。
柔軟な働き方により採用・定着が促進
有限会社WILLPLANTは、不規則な稼働が常態化していたことを問題視し、社員が働き続けたいと思える会社作りに舵を切ることにします。具体的に取り入れたのは、始業・終業時間を社員自身が調整できる自由な勤務体系への変更です。また、副業についても認めることに。すると、業務で身につけた技能やノウハウを活用して、専門学校でトレーナーとしても働く社員が出てくるようになったといいます。これらの取り組みによって、「この会社で働きたい」という人材が増加。定着にもつながっています。
新卒社員の離職率も低下
馬野建設株式会社では、例にもれず建設業界全体が抱える採用難に直面し、かつ新卒社員の早期離職にも頭を悩ましていました。そこで手を打ったのは、働き方や福利厚生に対する改革です。トップダウンで見直しを図ります。具体的には、残業時間を削減する社内ルールの構築や有給休暇の取得推進など。新卒採用者向けの教育プログラムも確立します。こうした取り組みを続けていった結果、コンスタントに採用もでき、かつ新卒社員の離職率の低下にもつなげられたようです。
イベントの実施が職場の雰囲気を改善
岡田パッケージ株式会社では、女性が働きやすい職場づくりに取り組むものの制度が機能していなかったり、社員同士が各人の家庭状況に合わせて協力するといった雰囲気がなかったりと問題を抱えていました。これらは人手不足を招く温床です。そして社員同士が活き活きと長く働き続けることができる“素敵な会社”を目指すなかではやはり、抜本的な対策を講じる必要がありました。そこで行ったのが、「次世代育成支援金制度」や「ファミリーデー」などの取り組みです。前者は、出産から高校卒業までの節目に、こども一人当たり総額51万円を支給します。そして後者は、夏休みを利用して、年に1回、社員の家族を会社に招いて交流するイベントです。そのほか、社員同士で良い所を褒め合い、感謝をカードに書いて伝える「いいねぇいいねぇ活動」も実施。こうして職場の雰囲気は改善された模様。人手不足の回避策にもなったと考えます。
経営難を乗り越え、社員が幸せになれる会社へ
株式会社オーザックでは、新卒採用で若い人材が入社しても、労働環境が未整備であったため定着せずに流出が続いていたといいます。現場の疲弊もあり、そうした状況は経営難にも少なからず影響を及ぼしていました。そこで目指したのが「社員が幸せになれる会社づくり」でした。主に、時間やコストに対する意識改革と週休二日制の導入に踏み切ります。前者では、各工程に目標時間と予定原価を設定。目標時間内に終わらない作業は各部署が話し合って原因の精査・改善を行い、一日における一人あたりの仕事量を見える化し、業務の偏りを減らしていったようです。後者については、導入にあたり、稼働日が減っても生産高を維持するため、休憩時間の交代制や多能工化も推進。結果、入社5年の定着率は97%と高い水準を達成し、加えて、入社希望の学生増加にもつながったといいます。
採用面にも好影響を及ぼした就労環境の改善
大手企業の受託システム開発を行っている株式会社グランドデザインでは、若い人材が一人前になったタイミングで他社へ転職するケースが繰り返されていました。3年以内の離職率はなんと40%。引き継ぎを行うコストの増加と、残った従業員の負荷が膨大に嵩む状況は、顧客への責任あるサービス提供ができなくなる点も含めて大きな問題でした。そこで取ったアクションは業務プロセスの見直しでした。具体的には、開発体制を一元化し、属人的ではなく複数名で案件を対応するようにします。結果、個々の残業時間は減り、離職率は低下(なんと4%台!)。採用面でも新卒応募が500名を超えるなど、良い循環が生まれています。
一部の社員に負荷が掛からないように
株式会社米五では、小規模な会社かつ繁閑の差が大きいがゆえに特定の社員に業務負担の偏りが見られました。これを無くすために行ったことはまず残業時間の見える化です。具体的には、グラフで見せて、社員それぞれが自身の残業時間を把握し、業務効率を意識できるようにしたといいます。また、パート社員の担当業務を明確にしたことも大きかったようです。正社員の業務を補完的にサポートできるようになり、業務量の平準化につながります。こうした取り組みにより、社員1人あたりの残業時間は前年比で3割以上減少。属人化の防止、すなわちチーム全体で支える体制づくりがうまくいったといえます。
働きやすい環境づくりで社員(全員女性)の定着率が向上
有限会社栄工業では、全社員が女性。結婚・出産・育児・介護等々のライフイベントによって継続勤務が難しく、実際、離職される方も少なくありませんでした。そこで取り組んだのがまず多能工化の推進です。これによって社員が互いに業務をカバーできるようになったといいます。また、産休・育休制度の整備等の有給休暇の充実、テレワークの導入、地域の製造業よりも多い年間休日(約120日)等も無視できません。このように働きやすい職場へと変わったことが、結果的に社員の定着にもつながっています。
給与体系の変更を実施でモチベーションアップ
自然免疫応用技研株式会社では、長時間労働や有給休暇取得率の低さといった労働環境の改善、さらには人材確保のためにも、給与体系や定年年齢なども、時代に応じた制度・運用へと変えなければならないと課題意識を持っていたようです。特に給与面にはテコ入れの必要性を感じ、年齢給、勤続年数給の上昇率を下げ、能力・努力・貢献度に応じた制度へと再設計します。また、定年を60歳から65歳にし、希望があれば70歳まで再雇用するように変更。実際、60歳と67歳の社員が活躍しているといいます。
シニア人材の活躍や女性の定着率が向上する組織へと変化
聖徳ゼロテック株式会社では、長年培ってきた技術の継承とともに、女性社員の定着率向上も課題とされていました。そこで、まず多能工化を推進。高齢の技術者それぞれが持っているノウハウを複数の若手技術者に伝承してもらうことで、1人が複数の工程を遂行できるようにしています。また、定年後も引き続き雇用を継続することで、教育役だけでなくプレイヤーとしても活躍してもらっているようです。
一方、子育て世代の女性社員に対しては、育児休業後の復帰を支える体制を整備し、部門内で業務をカバーし合えるように人員配置も調整。子育てと両立しながらも定着する女性社員が増えているといいます。
人手不足の解決策がうまくハマった主なdipのお客様事例
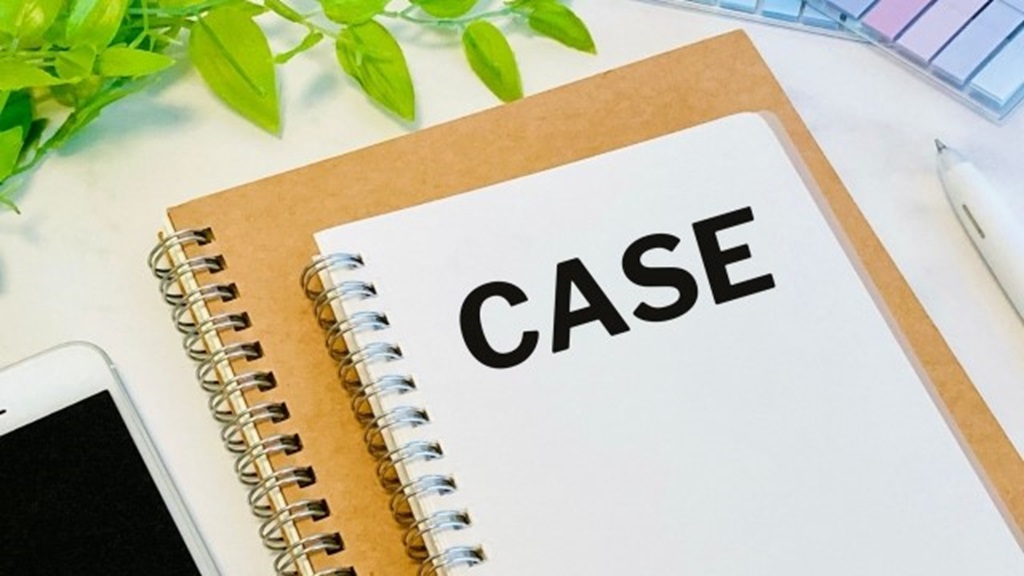
続けて、dipのサービスを活用して人手不足が解消されたお客様の事例も紹介します。これらからもまた、採用戦略のヒントや具体的な施策を学ぶことができるはずです。
なお、dipのサービスで課題解決につながったそのほかの事例も確認したい方は、ぜひこちらをご確認ください。
原稿作成の工夫で幅広い年齢層から応募が集まるように!
株式会社伊藤祐次商店様は、求人原稿の作成に不安を持っていたものの、dipのサービス(『バイトルNEXT』や『バイトルPRO』)を使い、担当者からの提案により職種ごとに訴求内容を変えたところ、幅広い年齢層の応募を獲得できたといいます。具体的には「葬儀屋」のイメージを明るく変えられるよう「お客様に寄り添う仕事」という切り口で打ち出したことが効果的だったようです。なかには、「ここしかない」と強く共感し入社された方もいたのだとか。応募の層が幅広いだけでなく、欲しい人材ともしっかりマッチングできています。
▶参考事例:「会社が好き」とはっきり言える人材に出会えた!葬儀社としての魅力をとらえなおした原稿作成
掲載期間の調整でミスマッチが減るように!
銀座という採用激戦区で苦戦していたBen’s Cookies様は、応募が来ない焦りが引き起こす悪循環に陥っていました。その要因は2〜3週間の短期掲載だったようです。十分な応募が集まらず、そのせいか焦って採用することも多かったようです。ミスマッチが起きていたのも容易にうなずけます。そこで思い切って長期掲載へ。すると『バイトル』、そして『バイトルNEXT』でも応募の増加が見られたといいます。「Ben’s Cookiesで働きたい」という志望度の高い方も出てくるようになったそうです。そうやって候補者を見極める時間的な余裕も生まれた結果、定着率向上と安定的な人員確保が実現します。
▶参考事例:短期掲載で焦って採用」から長期掲載で応募数&定着率アップ!
時給アップや資格支援制度の導入で採用効果がアップ!
特別養護老人ホームのサニーヒル板橋様は、これまで広告費をかける割には応募数が1、2件と少なく、満足のいく求人ができていませんでした。が、『バイトルNEXT』や『バイトルPRO』を中心に採用を展開し、ターゲットに合わせた原稿作成(動画や写真をできるだけ多く掲載したのもポイント)のほか、時給アップや資格支援制度導入を実施したところ、目に見えて効果があったようです。
▶参考事例:広告費94%削減&応募者10倍増加 費用対効果を劇的に改善させたdipの提案
採用DXで優秀な人材の確保と定着に成功!
大京警備保障株式会社様は、電話対応メインの採用プロセスに限界を感じていました。応募から面接設定まで3〜4日を要し、その間に他社へ人材が流れてしまう問題に直面していたのです。そこで導入したのが『面接コボット』。応募者が自身の希望に合わせて面接日程を即時選択できるシステムを構築したことで、面接設定率は従来の2倍以上に向上したといいます。タイムリーな選考が求職者の印象も良くしたのでしょう。優秀な人材を取りこぼさず採用までこぎ着けます。
▶参考事例:採用工数を削減しながら就業意欲の高い求職者の採用に成功
人手不足の解決策を講じるうえでよくある質問
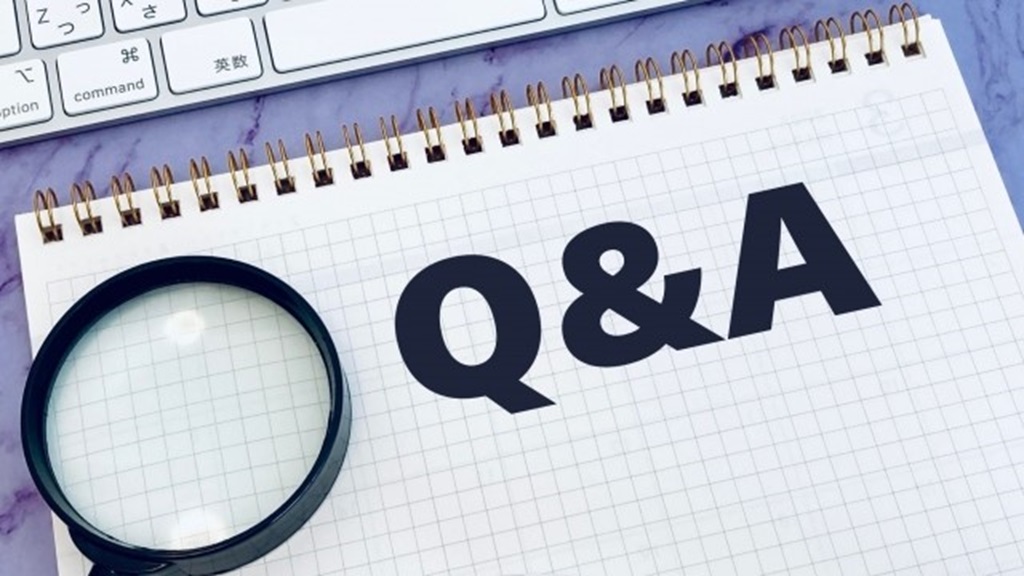
ここでは企業担当者から寄せられる質問をいくつか紹介します。
優秀なスポットワーカーを確保していくには?
優秀なスポットワーカーを安定して確保するには、単発的な募集ではなく継続的な関係構築が肝要です。前述した『スポットバイトル』はその本質を大事にしています。搭載されている独自の機能「Good Job ボーナス」はまさにそれ。高いパフォーマンスを発揮した人材に追加報酬を提供する仕組み(dipが負担)によって、モチベーションが担保されリピートにつながる期待が持てます。
ダイバーシティ採用で気を付けることは?
ダイバーシティ採用によって多様な人材を受け入れることは、ポジティブな面も多い一方で、大なり小なり組織に軋轢を生むリスクも伴います。異なる背景を持つからこそ、既存のメンバーとの間でコミュニケーションの食い違いが起きる可能性は当然ながらゼロではありません。したがって、定期的に相互理解を促進する場を作ることが大切です。
コストをかけずに魅力的な働き方を提示するには?
魅力的な働き方を提示する方法は限られた予算内でも可能です。それは近年の傾向を見てもわかります。ずばり述べると、自由なスタイルで働ける環境だと伝えることです。節度を保つことは当然として、服装や外見に縛られない働き方ができることを訴求ポイントとして打ち出せば、一定数の方には(特に若年層やクリエイター志望の方)刺さりやすいと思われます。これは、多様な価値観を受け入れる姿勢も示せるため、採用ブランディングとしても有効です。
人手不足に対して解決策を講じるとともに企業が問われる姿勢とは?

冒頭でもお伝えしたように、日本企業が直面する人手不足の問題は実に深刻です。仮に放置したままだと、もはや企業存続すら危ぶまれます。人手不足倒産の件数が増加している現状がまさにこのリスクを物語っています。だからこそ、積極的に解対策を講じていくことが必要です。加えて大事なのは、「今までのやり方」に固執せず、企業文化そのものを問い直し、働く人の価値観や多様性に応えられる組織へと進化していく姿勢です。テクノロジー導入や柔軟な働き方、多様な人材への門戸を広げるなど、時代の流れを受け入れ、実行していくこと。その先にこそ、人が集まり、定着し、成長し続ける理想像があります。人材に対する捉え方も同様です。リソースという概念ではなく「一緒に成長していける存在」として向き合うことが、これからの企業にとって本当に大切だと考えます。
求人掲載・採用業務のサポートや料金についてなど、ぜひ気軽にお問い合わせください。
また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談も無料で承っております!
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【公式】空いた時間のスポットワーカー募集ならスポットバイトル
┗空いた時間で「働きたい」と「働いてほしい」をつなぐ求人マッチングサービス。求人は無料で掲載できます。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。
▶【公式】面接コボット – 応募者対応の自動化で面接管理が楽に!
┗求人サイトからの応募対応を自動化できるサービス。チャットボットを通じ、日程調整まで効率よく進めてくれます。
▶【公式】採用ページコボット – 費用・実績も紹介!採用サイト制作サービス
┗採用ページ作成サービス。求人まとめサイトとの自動連携や求人検索エンジンへの対応により外部集客を強化します。

