オウンドメディアリクルーティングとは

まずは、基本的な内容からお伝えします。そもそもオウンドメディアとは何なのか、そして求人情報サイトとの違いはどこにあるのか。これらを明確にしつつ、オウンドメディアリクルーティングとは何かを定義付けます。
そもそもオウンドメディアって何?
オウンドメディアは、自社で保有し運営するメディアチャネルです。広報誌やWebサイト、SNSなど自社が発信するコンテンツの媒体すべてが含まれます。製品情報や業界の洞察、ユーザーガイド等々、切り口は自社でコントロールできるゆえにさまざまです。ブランドの価値や企業文化を伝えるのにも役立ちます。
求人情報サイトとは何が違う?
オウンドメディアを使った求人と、一般的な求人情報サイトの違いはやはり、運用の自由度でしょう。後者は多くの企業求人を一つのプラットフォームで扱うため、レイアウトやデザインなどテイストに制約が生まれます。他方、自社のメディアであれば、求人情報をより柔軟に伝えることが可能です。オリジナリティを前面に打ち出せるため、ブランドイメージの統一あるいは強化にもうってつけだと考えます。
つまり、オウンドメディアリクルーティングとは?
つまるところ、オウンドメディアリクルーティングとは、自社で保有し運営するWebサイトなどを軸に、採用ターゲットに対して主体的、能動的にアプローチできる(人材獲得を図れる)リクルーティング手法です。自社独自の発信を通じて求職者のエンゲージメントを高められる期待が持てます。
オウンドメディアリクルーティングが浸透する背景

オウンドメディアリクルーティングが浸透してきた背景には、労働市場の変化が大きく関わっています。人口動態や行動様式が影響した結果、訴求の仕方も変えざるを得ない状況なのは確かです。そうなるとおのずと手法も変わってくる(選択肢が増える)のは、容易に頷けます。以下、これらの状況についてくわしく説明します。
労働力人口の減少
労働力人口の減少は、いうまでもなく少子高齢化が影響しています。限られたリソースから欲しい人材を獲得していくのは、そう容易いことではありません。実際に人手不足に陥る企業もそこかしこで見られます。だからこそ、自分たちでメディアを持ち、従来の採用媒体と差別化を図っていくことは、もはや必至といっても過言ではないでしょう。
訴求ポイントの多様化
人手不足の問題が深刻化するなかで、求人が横並びの打ち出し方では、苦戦するのも無理はないでしょう。求職者側からすると、応募の決め手が欲しいはずです。しからば、情報量や内容の充実さがカギを握ります。結果、訴求ポイントが多様化していくわけです。これと親和性が高いオウンドメディアが活用されるのは、至って自然な流れだと考えます。
求職者の行動にみられる変化
いまや、お仕事情報をオンラインで収集するのは当たり前です。求職者の行動特性としても、求人を自ら能動的に探しています。その際、あらかじめプラットフォームを決めるというよりは、最初から条件を絞って検索される方も多い状況です。そうやって行き着く先に現れるのが企業のオウンドメディアであることも多く、接点はどんどん生まれれています。採用要件に合った内容を求職者自らが検索し、結果、自社メディアに訪問してくれるのであれば、注力しない手はないと考える企業が増えるのも当然です。
オウンドメディアリクルーティングのメリット

オウンドメディアリクルーティングが浸透する背景とは別に、いくつかのメリットがあることもまた、多くの企業が実施している理由だと考えます。(メリットは)具体的には次のとおりです。
- 広告費を抑えられる
- 潜在層にリーチしやすい
- ほかのプラットフォームとの親和性が高い
- 自社について理解してもらいやすい
- 自社のブランディングに使える
以下、それぞれ詳述します。
広告費を抑えられる
オウンドメディアリクルーティングでは、外部の求人広告サービスやエージェンシーに頼る必要がないため、その分のコストは抑えられます。もちろん、メディア制作にあたってかかる費用こそありますが、中長期的にみたとき、費用対効果の向上につなげられる期待が持てるでしょう。
潜在層にリーチしやすい
オウンドメディアリクルーティングには、自社の求人情報を求職者のなかの潜在層に届けやすいという側面があります。これは、求人検索エンジンやソーシャルメディア全般、自然検索等々、チャネルを横断して接点を持つことができるからです。先述したように、求職者はインターネット上で自ら条件を絞って検索する方が多い傾向にあります。その内容とマッチするコンテンツを発信しているのであれば、リーチする機会は増えてくるはずです。
ほかのプラットフォームとの親和性が高い
オウンドメディアは、前述のとおりほかのプラットフォームと連携を図れます。Web上のスポンサー枠の掲載だけでなく、求人検索エンジンにピックアップされることやSNSで拡散される可能性を考えると、相乗的に効果が期待できる手法といえるでしょう。
自社について理解してもらいやすい
オウンドメディアをうまく使えば、自社のミッション、ビジョン、職場の雰囲気、社員の声などを詳細に伝えることができます。また、リアルタイムでのコンテンツ更新を通じて最新の動向やニュースを共有することも可能です。これらによって、大なり小なり、企業理解の促進につなげられます。
自社のブランディングに使える
オウンドメディアリクルーティングは自社ブランドを築くのに有効な手法です。ユニークな取り組みはそのまま企業の個性や強みにつながります。また、メッセージに一貫性があれば、それも同様に企業イメージを醸成する要素になり得ます。
オウンドメディアリクルーティングの注意点

オウンドメディアリクルーティングに対してメリットだけをみて安易に飛びつくのは考えものです。実際のところ、いくつか注意点が存在します。具体的には次のとおりです。
- 制作コストはかかる
- 社内全体で取り組んだ方がよい
- 運用ノウハウが必要
- 継続できるリソースが必要
以下、それぞれ詳述します。
制作コストはかかる
オウンドメディアの制作には初期投資が必要です。特に品質にこだわるのであれば、それなりに費用がかかります。デザイン、コンテンツ、技術的なサポート……等々、あらかじめビジョンを明確化し、予算と照らし合わせておくことが大切です。
社内全体で取り組んだ方がよい
オウンドメディアの運用を一部署に委ねてしまうと、どうしても近視眼的で偏ったコンテンツばかりになることが懸念されます。幅広い層に訴求するにはやはり、多角的な切り口が必要です。そうなると社内全体を巻き込むことが求められます。できることなら、バラエティに富んだ内容でユニーク性を湛えたメディアにしていきましょう。
運用ノウハウが必要
オウンドメディアの効果的な運用には少なからずノウハウが必要です。コンテンツマーケティング、SEO対策、アクセス解析……等々、デジタルメディアに精通する方がいないなかで、何となく運用してみても思ったような効果は生まれないかもしれません。これを避けるには、メディア運用のプロフェッショナルがサポートしてくれるサービスを利用することが無難でしょう。
継続できるリソースが必要
オウンドメディアは継続的な更新が大事です。が、リソースが足りなければ、当然対応は難しくなります。古い情報のまま放置されているメディアも時折、目にすることがありますが、これでは逆に信頼性が下がり、マイナスのイメージを持たれてしまうでしょう。
オウンドメディアリクルーティングに必要な情報、コンテンツ

オウンドメディアリクルーティングは、(オウンドメディアに)掲載する内容が鍵を握ります。本章で取り上げる情報、そしてコンテンツはいずれも確実におさえておきたいものです。以下、詳述します。
ジョブディスクリプション
一つはジョブディスクリプションです。これは、職務内容、必要なスキル、期待される成果などオウンドメディアに掲載する基本的な内容を指します。求職者のニーズに応えるべく、なるべく詳細に記載することが大事です。
シェアードバリューコンテンツ
続いて、シェアードバリューコンテンツです。これは、自社で働くことの社会的意義や社会貢献度を伝えるものを指し、そこから共感を喚起していきます。大きく分けると次の2つです。
- パーパスコンテンツ
- カルチャーコンテンツ
それぞれ、説明します。
パーパスコンテンツ
パーパスコンテンツは、企業の使命や目的を明確に伝えるコンテンツです。企業がなぜ存在するのか、どのような価値を社会に提供しようとしているのかを具体的に示します。こうした企業理念や長期的なビジョンに対する理解を促進したうえで、同じ価値観を持つ人材を引き寄せることが狙いです。
カルチャーコンテンツ
カルチャーコンテンツは、組織風土や雰囲気を表現するものです。従業員の声、オフィスの日常、チームビルディングの様子、社内イベントの紹介などを通じて、自社のあれこれをリアルに伝えていきます。ただ漠然と描写するのではなく、あくまで求職者に自身が働く姿を重ねてもらえるよう意識し、発信していくことが大事です。
オウンドメディアリクルーティングの流れ
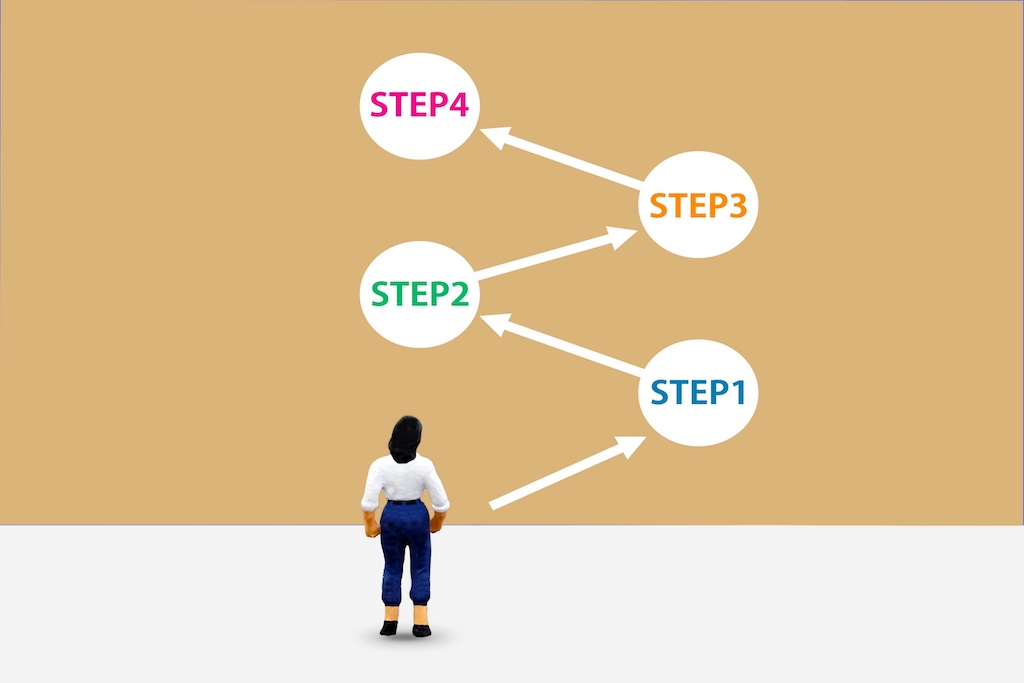
定義、メリット、注意点、必要な情報やコンテンツは、あくまで前提知識です。いざオウンドメディアリクルーティングを始めるなら、当然、一連の流れも把握しておかなければなりません。以下、プロジェクトの始動から運用までの具体的なステップについて説明します。
プロジェクトメンバーを選定する
まずは、プロジェクトメンバーの選定です。オウンドメディアリクルーティングを中心となって進める方々は誰が相応しいのかをしっかりと吟味し選んでいきます。この際、あらためて目的も明確にしておきましょう。
スケジュールを立てる
メンバーが集まったなら、早速スケジュールを立てていきましょう。これには、各タスクの開始日と終了日、重要なマイルストーンの設定、およびプロジェクトの期限が含まれます。いうまでもなく、皆の認識がブレないよう慎重に取り進めることが大事です。
採用要件を設計する
求める職位に必要なスキル、経験、資格などを採用要件の定義もはっきりさせておく必要があります。訴求の仕方やコンテンツの方向性などにも関わってくる大事なフェーズです。
▶関連記事:人材要件とは?定義の仕方やフレームワークに具体例も交えて解説
自社の魅力を抽出する
オウンドメディアのなかで発信する自社の魅力も事前に抽出しておけるとよいでしょう。職場環境、研修体制、明確なキャリアパス……等々、ターゲットのニーズに合った強みを洗い出し、コンテンツに昇華していくイメージをこの段階で持てると、後々の運用もスムーズでしょう。
他社動向を調査する
せっかくのオウンドメディアが他社と変わらない内容になってしまうのは、ともすれば、ありきたりなコンテンツや打ち出しを意味します。一方で、自社の発想やアングルからは出てこなかった切り口で他社が訴求していることも考えられます。これらをケアすべく、競合他社のメディアを調査することは必要不可欠です。当然、自社の戦略調整にも生かせます。
コンセプトを設定する
採用キャンペーンのコンセプトを設定する際には、企業のブランドアイデンティティと求職者との接点を考慮し、魅力的で一貫性のあるメッセージが有効です。そうやって確立したコンセプトは、自社が進めるオウンドメディアリクルーティングの基盤となります。ゆえに、(方向性を見失ったときなど)局面によって立ち返り見つめ直すものとして必要です。
コンテンツを策定する
コンセプトまで定まったなら、オウンドメディアに掲載するコンテンツを策定していきましょう。方針に沿ったトピックやテーマを並べ、どのような見せ方にするかまで検討できると望ましいでしょう。
「内製か外注か」を決定する
要件やコンセプト、コンテンツの方向性があらかじめ定まっていれば内製に固執せず、外部の業者に頼むのも一つのやり方です。これを決める際は、プロジェクトの規模、予算、社内リソース等々を考慮する必要があります。
オウンドメディアを形にする
ここまでの決定事項を踏まえて、オウンドメディアに落とし込むフェーズでは、ブログ特化型にせよ採用ホームページにせよ、ユーザーにとって使いやすい仕様を突き詰めていくことが大事です。あわせて、運用面でも管理システムはなるべくシンプルなものがなものがよいでしょう。いわゆるUI/UXを、自社・求職者両方の観点で意識することが必要です。
オウンドメディアを運用する
あまねく求人媒体にいえることですが、オウンドメディアもまた作って終わりではありません。定期的な情報更新や状況に応じてメンテナンスが必要です。また、効果検証もしっかり行わなければ、それは“運用”と呼べません。オウンドメディアリクルーティングは、いうなれば、常に改善を図っていくことを前提に取り組んでいくものです。なお、運用方法については次章でくわしく解説します。
オウンドメディアリクルーティングで大切な運用について

オウンドメディアの運用がままならなければ、オウンドメディアリクルーティングは成り立ちません。本章ではオウンドメディアリクルーティングの進め方、すなわちオウンドメディアの具体的な運用方法について解説します。
タイムリーに情報を更新する
オウンドメディアに載せる情報は常に最新の状態に保つことが望ましく、ここが更新されていないと、せっかく接点が生まれた求職者を簡単に手放してしまいます。なお、更新するニュースがない場合は、次項の継続的にコンテンツを発信することももちろん大事ですが、求人情報がまだ有効である旨を定期的に明示してしてあげられるとよいでしょう。
継続的にコンテンツを発信する
訪れる度に新鮮なコンテンツが提供されていれば、求職者のエンゲージメントは向上し、応募につながるチャンスがぐっと広がるでしょう。上述したタイムリーな更新もそうですが、オウンドメディアが動いていることを伝えられる工夫が必要です。
適宜、戦略を見直す
市場の変化や現況に対して柔軟に取り組んでいくためにも、定期的に戦略を見直すことは不可欠です。継続的にコンテンツを発信しても、流入が一向に伸びないなら、当然やり方を変える必要があります。オウンドメディアリクルーティングは、うまくいくケースも当然ありますが、絶対視しないことが肝要です。期待が過剰になってしまわないよう気を付けましょう。
PDCAサイクルを構築し円滑に回す
オウンドメディアを運用する以上、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Act)のサイクルを構築し円滑に回すことは必須です。先述のとおり、オウンドメディアは作って終わりでなければ、絶対的なものでもありません。そう、オウンドメディアリクルーティングは、育成ありきの手法です。大前提、その認識で運用しましょう。
オウンドメディアリクルーティングを採用のプロにお任せするなら

いまや決して特別ではない手法ゆえに、市場ではオウンドメディアリクルーティングに適したさまざまなサービスが見られます。したがって、採用のプロにお任せするのも当然、一つの手段です。そうしたなかdipでは、いちメディアとして採用サイトを制作するサービス『採用ページコボット』がラインナップされています。以下、その内容について紹介します。
『採用ページコボット』について
採用ページコボットは、オウンドメディアとして使える採用サイトの制作が可能です。プロによる求人原稿の作成や応募レポート機能などサポートが充実している点、プランによっては取材・撮影を含めたテンプレートを用いない完全オリジナル仕様のものを提供できるなど、いくつもの特長が挙げられます。
求人情報は、複数の大手求人検索エンジンと自動連携。広範囲に露出が増えるため、応募者の増加が期待できます。
▶【公式】採用ページコボット – 費用・実績も紹介!採用サイト制作サービス
『面接コボット』のセット利用で応募対応の負担が軽減!
採用ページコボットを利用したオウンドメディアを運用する場合、面接コボットとセットで使うことをおすすめします。応募が集まることを想定した場合、次に懸念されるのが滞りなく(応募者への)対応ができるかどうかです。面接コボットは、就業条件の確認や面接日時の設定などをチャットボットのシステムで行います。これによって自動対応が可能です。しかもタイムリー。応募者とのやり取りに手間をかけずに済むだけでなく、連絡漏れなども防げます。応募が来ても他社に流れてしまう(取りこぼしてしまう)ことにお悩みならぜひ、採用ページコボットでオウンドメディアを作成し、面接コボットで採用業務の効率化を図るとよいでしょう。
▶【公式】面接コボット – 応募者対応の自動化で面接管理が楽に!
オウンドメディアリクルーティングの成功事例

オウンドメディアリクルーティングが実際にどのような効果をもたらしているのか。本章では、前述の採用ページコボットを活用しうまくいった事例をいくつか紹介します。
『株式会社吉野家』の取り組み
株式会社吉野家様は、店舗業務の負担軽減のために『採用ページコボット』を導入。その発端は、世の中の変化に合わせてアルバイト採用のあり方も変えていかないといけないといった意識改革からでした。オウンドメディアを持つこともまた同様。結果、当初の目的どおり負担軽減に成功します。引き続き、労働力人口の減少に対応すべく、求職者のニーズに応える採用に取り組んでいくとのことです。
▶事例詳細:コボットの導入により、採用効率の向上を目指す。 求職者に選ばれ続ける企業になるための、 吉野家の取り組みとは?
『株式会社トミダ』の取り組み
株式会社トミダ様は、メインの採用活動のために『採用ページコボット』を導入。アルバイト・パート採用に強い『バイトル』との併用で応募数は一気に増えたといいます。掲載内容の修正・更新のスピードにも満足しているご様子。総じて、費用対効果の高さを実感されています。
▶事例詳細:採用ページコボットの活用で、年間477件の応募を獲得!
『株式会社佐藤クリーニング』の取り組み
株式会社佐藤クリーニング様は、採用コストの増加と従業員の高齢化に対応するため、媒体を「採用ページコボット」に切り替えたところ、如実に問題が解消。応募者情報の部署間共有で、余計な工数がかからなくなり、応募の取りこぼしも防げるようになったといいます。また、採用ページコボットで作ったオウンドメディアだからこそターゲットに適した訴求ができたとのことで、結果、欲しい層の人材確保を実現されています。
▶事例詳細:採用ページコボットで採用コストの圧縮に成功。データの見える化で応募者からのアプローチを取りこぼさない体制を構築。
オウンドメディアリクルーティングが採用の手札に加わると安心!

オウンドメディアリクルーティングは、いまや当たり前のように採用手法の一つとして数えられています。複数のプラットフォームと連携を図りやすい特性上、広い範囲で応募者にアプローチできる点など、メリットが多いことも確かです。一方で運用ノウハウがないと効果を生みにくいといった注意点もあります。これらに加え、セオリーとして掲載すべき情報やコンテンツ、一連の流れも、実施するならしっかり把握しておかなければなりません。拙稿で紹介した『採用ページコボット』なら、その辺りのフォロー、ケアはできますが、当然、費用もかかるため、予算内に収まるかは要チェックです(問い合わせは無料です)。
いずれにしても、うまく活用できればオウンドメディアリクルーティングによる成果も期待できるでしょう。現況に停滞感を覚えるなら、ぜひ、手札の一つに加えてみてください。
求人掲載・採用業務のサポートや料金についてなど、ぜひ気軽にお問い合わせください。
また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談も無料で承っております!
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。
▶【公式】面接コボット – 応募者対応の自動化で面接管理が楽に!
┗求人サイトからの応募対応を自動化できるサービス。チャットボットを通じ、日程調整まで効率よく進めてくれます。
▶【公式】採用ページコボット – 費用・実績も紹介!採用サイト制作サービス
┗採用ページ作成サービス。求人まとめサイトとの自動連携や求人検索エンジンへの対応により外部集客を強化します。

