多くの職場で人手・欲しい人材が足りていない!

人手不足は現代の職場において深刻な問題です。業務の効率低下や従業員の負担増加を引き起こし、長期化すれば企業の成長や競争力の低下につながる恐れがあります。有効求人倍率を見ても、特に介護や運輸、飲食サービスなどの業界で人材確保が難しい状況が見て取れます。一方、優秀な人材は自己成長の機会や働きがいを求めて行動する傾向にあるといえるでしょう。
いま、人手不足によって生じている問題
人手不足は職場にさまざまな問題をもたらします。上述のとおり、業務効率が悪化し、残業の増加や有給休暇の取得困難など、従業員の負担が増加します。
これにより、モチベーションや満足度の低下を招き、さらなる離職を引き起こす悪循環をも生みかねません。また、人が足りず適材適所への人員配置が難しくなれば、顧客に対するサービスの質も下がっていくことになるでしょう。
将来的に懸念される人手不足が及ぼす影響
人手不足が長期化することで、企業の成長力や競争力の低下が懸念されます。そうなると、新たな事業展開や市場開拓の機会を逸してしまうかもしれません。たとえビジョンを高く掲げても、イノベーションの創出は困難を極めるでしょう。
優秀な人材の流出は単に技術が失われるだけでなく、組織の行く末にも影響します。すなわち、企業の存続を脅かす事態に陥るわけです。そうならないよう早い段階で食い止める必要があります。
有効求人倍率で見る人手不足が悩ましい職種
職種別の有効求人倍率を見ると、人手不足が特に深刻な業界が浮かび上がります。※以下は、2024年3月時のデータです。

▲職種別有効求人倍率(常用的パート)

▲職種別有効求人倍率(パート除く常用)
介護サービスの職業ではアルバイト・パートの有効求人倍率が前年に比べてアップ。自動車運転や商品販売も同様。前年比でプラスに推移しているこれらの職種は、おそらく今年も求人に苦戦されているように思います。
特に介護業界は、高齢化の進展に伴い人材需要が高まる一方で、労働環境の厳しさから敬遠されがちです。このため、処遇の改善や社会的評価の向上に向けた取り組みが求められています。
一方、パートを除く場合、前月比では全体的に微減しています。前年比で見ると、「商品販売」「自動車運転」「介護サービス」の職業で大きく上昇。アルバイト・パートと同じ動きであることがわかります。
▶関連記事:【最新版】アルバイト・パートの有効求人倍率はコチラ
▶関連記事:【最新版】社員の有効求人倍率はコチラ
※参照:厚生労働省『一般職業紹介状況』
欲しい人材はどこにいる?
「欲しい人材がなかなか見つからない」
こうした悩みを抱える企業は従来のやり方に固執している可能性があります。たとえば、リモートワークの普及に伴い昨今は、全国、あるいは海外からも採用が可能です。また、門外漢だからといって端から採用対象から外してしまうことも、もしかしたら短絡的な判断かもしれません。異業種や異文化にいる方々の経験やアイデアが組織を活性化させることは往々にしてあります。そう考えると、一気に視界が開けるはずです。
加えて、優秀な人材の思考・行動特性も念頭におけるとよいでしょう。彼・彼女らは、自身のキャリアアップと働きがいを重視する傾向にあり、スキルアップのための研修制度や、チャレンジングな仕事に挑戦できる機会の有無などを見極めようとします。求人広告では、そうしたインサイトに訴求できると応募につながりやすくなるでしょう。
職場で人手不足が起きる理由

人手不足にはさまざまな理由が考えられます。具体的には、少子高齢化、求職者ニーズとのズレ、ミスマッチ採用、コストに対する見誤りなどです。以下、これらについて一つずつ紐解きます。
少子高齢化
人手不足は、少子高齢化による人口構成の変化が引き起こしているともいえます。労働力人口の減少は、どうしたって大きな痛手です。特に地方では顕著。また、先述したように介護や医療、福祉業界の場合、高齢者層が増えれば増える分、対応する人間も必要になってきます。したがって、人手不足を食い止めることが日に日に困難な状況です。
求職者のニーズ(トレンド)からずれた求人
求職者のニーズと求人内容のミスマッチも、人手不足の原因として考えられます。ターゲットによって重視する項目が変わるなか、ただ漠然と求人情報を記載していては大なり小なり齟齬も生まれるでしょう。求職者のニーズ、特性を安易に捉えず、トレンドも含めてしっかり目配りしていく必要があります。
採用した人材とのミスマッチ
せっかく採用まで至っても、すぐに辞められてしまえば意味がありません。「いざ入社してみたら思っていた職場と違った」などというケースは星の数ほど見聞きしてきました。他方、企業側の誤算も多々見受けられます。新入社員が、面接での印象と実際の働きぶりにギャップがある場合や、企業文化・風土への適応が難しければ、遅かれ早かれ離職につながることがほとんどです。
採用予算を適切に設定できていない
なるべく採用コストを抑えたい気持ちはわかります。しかし、必要以上に渋ってしまうと、今度は十分に採用活動ができません。これだと本末転倒です。市場価値の高い人材を確保するためには、ある程度のコストは仕方ないでしょう。もちろんコストをかけすぎるのも問題です。そのため、適切な予算を設定するには慎重に吟味していく必要があります。
職場で優秀な人材が定着しない原因

人手不足は、採用面だけでなく既存の従業員をケアできていない点も問題です。特に優秀な人材ほど、早々に見切りをつける傾向にあります。彼・彼女らが定着しない背景にあるのは、評価制度の不透明さ、ワークライフバランスの崩れ、キャリアパスの不明確さ、他社との待遇差など、さまざまです。これらについて以下、詳述します。
自身への評価に対して釈然としない
評価制度の不透明さは、従業員の不満や不安につながります。客観的に見て評価の仕方に納得感が生まれなければ、いくら頑張っても正当に評価されないと考えるようになり、そのままモチベーションも下がっていくに違いありません。結果、離職されてしまうのも無理はないでしょう。
私生活に支障をきたす働き方を余儀なくされる
残業が多い、有給休暇をとる暇がない、休日出勤が多いなど、長時間労働や休みが取りづらい環境は、従業員を心身ともに疲弊させます。離職するのは時間の問題です。業界を含めて職場によってはなかなか改善が難しいところもあるでしょう。しかしながら、柔軟な勤務形態の導入やテレワークの推進など、世の中の働き方を参照すれば、多少なりともできることが見つかるはずです。いずれにしても、優秀な人材の定着には、従業員のウェルビーイングを大切にする職場環境づくりが欠かせません。
キャリアアップの機会が見えない
従業員がキャリアの行き詰まりを感じることも、離職の原因です。自身のスキルアップや将来のキャリアパスが見通せない状況では、モチベーションを維持することは難しいでしょう。社内の教育研修制度を充実させたり、メンター制度を導入したりと、従業員の成長をサポートする取り組みが求められます。また、社内公募制度などを通じて、チャレンジングな仕事に挑戦する機会を提供することも効果的です。従業員一人ひとりのキャリアビジョンを尊重し、その実現を支援する姿勢は企業の成長につながる意味でも大切だと考えます。
他社の待遇が魅力的に映る
他社との待遇差も、優秀な人材の流出につながります。報酬水準や福利厚生の内容が競合他社に劣っていれば、そちらに目移りするのも無理はありません。そうならないためにも、市場も含めた他社の動向を定期的に調査することが大切です。そのうえで臨機応変に待遇面の見直しを図るようにしましょう。
他社の労働環境が魅力的に映る
労働環境の良し悪しもまた、従業員の定着に大きく影響します。職場の人間関係や上司のマネジメントスタイル、社内のコミュニケーション不足などは、離職リスクを高める大きな要因です。一方、オープンで柔軟な組織文化を持つ企業は、従業員の満足度が高い傾向にあります。他社に対して風通しのよさを感じた従業員が続々といなくなる、しかも競合に流れていくとなれば、市場での形勢は一気に不利になってしまいます。
他社の企業風土が魅力的に映る
イノベーティブで挑戦を奨励する風土、多様性を尊重するカルチャー、社会貢献を重視する価値観などは、従業員の共感を得られやすく、そういった部分に惹かれて他社に転職する向きも決して少なくありません。逆にいうと、企業体質が変わらない、もしくはこれといったビジョンもなければ一体感もない組織には、いつまでもお世話になる理由がないでしょう。
職場での人手・人材不足を解消するには?

人手・人材不足を解消していくにあたっては、多角的なアプローチが必要です。具体的には、採用基準や採用手法、時期の見直しに加え、待遇・福利厚生の改善、勤務形態の柔軟化、職務内容の明確化、求人広告の最適化等々を図っていけるとよいでしょう。これらについて以下、詳述します。
採用基準を見直していく
従来の採用基準にとらわれず、なるべく多様なバックグラウンドを持つ方々を受け入れることで人材確保につながります。特に、年齢や性別、国籍など、一昔前の価値観では敬遠しがちだった属性もシームレスに扱えると望ましいでしょう。
また、学歴や経験だけでなく、ポテンシャルや人物面も十分評価の対象になり得ます。いずれにしても、柔軟な採用を行うことが人手・人材不足解消には肝要です。
採用手法を見直していく
これまで取り組んでこなかった採用手法に挑戦してみることも打開策の一つといえます。SNSを活用し、気軽にフォロワーに対してアプローチしてみたり、自社の従業員に紹介を募ってみたりと、手法の数だけ可能性はあるはずです。もちろん、現在利用している求人媒体を変えるだけでも成果につながる期待は持てます。そのほか、プラン変更やサービスの組み合わせ利用などもおすすめです。
採用時期を見直していく
求職者の動向や求人の状況をあらためて精査し、タイミングを図って採用活動を行うことも重要です。一般的に、求職者が多い時期に採用活動を行えば、より多くの応募を集めることができます。しかし、求職者が少ない時期でも、競合他社の求人が少なければ、優位に採用を進められるかもしれません。自社の採用ニーズや業界の特性を踏まえ、戦略的に取り組むことが大事です。
待遇・福利厚生を魅力的にする
待遇や福利厚生が魅力的(業界水準以上)であれば人を惹きつけやすいでしょう。これらは、当然、求職者のみならず既存従業員のモチベーション向上にもつながります。たとえば待遇面では、住宅手当や家族手当、資格取得支援など、ライフステージに合わせた手厚い支援制度を用意すると、他社との差別化が図りやすいかもしれません。また、福利厚生においても、社員旅行や懇親会など、従業員同士の交流を深める機会を設けることで、一体感のある組織文化を醸成でき、エンゲージメントへと寄与していく期待が持てます。さらには、いまの時代、伸び伸び無駄なく働ける環境も求められています。タイムリーに価値観をアップデートし、新たな仲間を迎え入れるようにしましょう。
▶関連記事:待遇や福利厚生の改善を図ろう!採用・定着のカギは価値観の更新
昇給や賞与制度を魅力的にする
求職者は入社時に提示される額面上の給与も重視しますが、頑張りによってどれだけ昇給できるかも、長期的に働くうえで大切にされる方がほとんどです。また、賞与制度も魅力的かつ成果に結びつけることで、(給与に対する)不平・不満による離職を抑制してくれるでしょう。
▶関連記事:アルバイト・パートの昇給について時給アップの事例も交えて解説
勤務地やシフトの柔軟化を図る
フレックスタイムやテレワークなど、柔軟な勤務形態を導入することで、多様な人材が活躍できる環境を整備できます。特に、育児や介護との両立を余儀なくされる方にとっては、勤務時間や勤務場所が選べるのであればそれは実に大きなメリットです。また、副業解禁や(勤続期間によって与えられる)長期の休暇制度なども積極的に取り入れることで、優秀な人材の獲得や定着につながる期待が持てます。
業務の詳細や領域を明確にする
職務分掌を見直し、業務の効率化と専門性の向上を図ることも重要です。職務分掌とは、担当者の行うべき職務を整理・配分し、責任の所在と業務の詳細や領域を明確にすることを指します。
各部門の役割や責任範囲がはっきりしていることで、従業員一人ひとりの業務内容の最適化が可能です。これにより、専門性の高い人材が育つ期待が持てます。ひいては、このような適材適所の配置が、組織全体のパフォーマンス向上にもつながっていきます。
▶関連記事:職務分掌とは?規程作成に至る手順までわかりやすく解説
部門間交流を促進する
自分の業務にしか目を向けられなかったため、自社が合わないと感じ離職される方がいます。これを未然に防ぐためには、部門間交流が有効です。他部署の業務や雰囲気を知ってもらうことで、他社に流れず、自社内で適性ある仕事に気づけるかもしれません。こうした機会を提供することは、(その従業員にとって)不明瞭だったキャリアパスの解像度を上げることにもつながります。
メンタル管理もしっかり行う
ハラスメント防止やメンタルヘルス対策にも力を入れていることも大事です。心身ともに従業員の健康をサポートしていくことは、企業の一番の命題といっても過言ではありません。
求人広告にしっかりと落とし込む
上述した人手・人材不足の解消案を求人情報のなかで落とし込めれば、訴求力が高い広告になるはずです。また、見せ方にも工夫を凝らすとなおよいでしょう。特に動画で表現できると職場の様子をリアルに伝えられるため、求職者は自身が働く姿をイメージしやすくなります。コンテンツとしても他社との差別化が図れるため有効です。
職場での人手・人材不足を解決する具体策は?

前項で挙げた人手・人材不足解消への足掛かりとなるアプローチのいくつかをはじめ、より具体的なアクションへと昇華したのが次の取り組みです。
- ダイバーシティ採用
- 障がい者雇用
- リファラル採用
- 社内公募制度
- 出戻り採用
- 採用アウトソーシング(RPO)
- 適性検査
- トライアル雇用
- 皆勤手当
- ハイブリッドワーク(勤務)
- サバティカル休暇
- 正社員登用制度
以下、それぞれ詳述します。
ダイバーシティ採用
ダイバーシティ採用を推進し、多様な価値観や経験を持つ方々を積極的に受け入れることで、優秀な人材の獲得機会を広げることができます。性別や年齢、国籍などにとらわれず柔軟な組織文化を醸成できれば、従業員のエンゲージメントさながら、定着率アップにもつながるでしょう。
▶関連記事:ダイバーシティ採用とは?企業の取り組み事例やアンケート調査の結果も交えて解説
障がい者雇用
障がい者雇用に注力することで、まず人手を補えます。加えて、スキルフルな人材の獲得も可能です。一般雇用と同じ要件で採用できるケースも多く、また、ブランドイメージの向上や税制優遇、助成金の受給といったメリットもあるため、法的義務だけで取り組むのは勿体ないといえます。
▶関連記事:障がい者雇用とは?メリット・デメリット、助成金の話など
リファラル採用
リファラル採用とは、従業員から自社に見合った人材を紹介してもらう採用手法です。従業員のネットワーク次第で、効率よく自社にマッチする人材を獲得できます。そのほかメリットとして、採用コストの削減や定着率の向上につながりやすい側面もあります。
▶関連記事:リファラル採用とは?報酬の決め方や違法性、トラブル回避策など解説
社内公募制度
社内公募制度では、人材を必要とする部署が社内で募集をかけ、それに呼応する形で従業員が自主的に応募します。つまり、人手・人材不足を外からではなく内から補っていくわけです。この制度は、従業員のキャリア形成と意欲向上にもつなげることができます。
▶関連記事:社内公募制度とは?流れや面接方法、メリット・デメリットなど解説
出戻り採用
優秀な人材に辞められたからといって、取り戻すチャンスが無くなったわけではありません。そう、出戻り採用の実施です。実際に、一度離れていった従業員を再雇用する企業は一定数存在します。いわゆる円満退社の方を対象にするならば、一つの選択肢に含めてもよいかもしれません。自社の文化や仕事の進め方を理解している分、即戦力として活躍してくれる可能性も高いでしょう。
▶関連記事:出戻り採用、出戻り社員とは?メリット・デメリット、事例交えて解説
採用アウトソーシング(RPO)
企業が人材採用プロセスの一部またはすべてを外部の専門家に委託する「採用アウトソーシング」のサービスを活用してみてはどうでしょう。自社あるいはいつも利用する求人サービスではなかなか採用に至らず、人手・人材不足に困窮しているのであれば、ノウハウが豊富な業者にお願いするのも一つの手です。
▶関連記事:採用アウトソーシング(RPO)とは?気になる採用代行サービスの話
適性検査
応募者の能力や適性を客観的に評価する適性検査を選考プロセスの中に組み込むことで、採用におけるミスマッチを減らせる期待が持てます。また、適性検査のデータからは応募者の傾向を抽出していくことが可能です。そのため、一連の人材募集に対して、欲しい層、ターゲットを集められているかどうかの効果検証にも使えます。
▶関連記事:適性検査とは?種類やテスト方式、導入の目的、実施方法など解説
トライアル雇用
入社してもらった後の早期離職を避けるために、一旦トライアルの期間を設けることも一つのやり方としてあります。文字どおり、トライアル雇用です。応募者の見極め、長期契約に対するリスクヘッジ、助成金の支給など、企業にとってはメリットも感じられやすいでしょう。
▶関連記事:トライアル雇用とは?メリット・デメリットや助成金の話などくわしく解説
ハイブリッドワーク(勤務)
オフィス勤務とリモートワークを組み合わせたハイブリッドワークの導入も検討に値します。柔軟な働き方を実現することで、多様な人材の活躍を後押しできるでしょう。オフィスにいればスペースを効率よく使え、他方、外で作業できれば交通機関の乱れも特段気にする必要がないわけです。ちょっとしたことでもストレスの軽減につながれば、生産性アップにも期待が持てます。
▶関連記事:ハイブリッドワーク(勤務)とは?デメリットや課題についても解説
サバティカル休暇
サバティカル休暇とは、従業員が一定の勤続期間を経た後に与えられる長期休暇です。実際のところ、条件や内容は企業によって異なりますが、この期間は、資格取得やリスキリングといった学びの時間を推奨する傾向にあります。いずれにしても従業員のリフレッシュと自己研鑽を支援することは、スキル以上に従業員のエンゲージメントを高めるはずです。結果、定着率向上にもつながると考えます。
▶関連記事:サバティカル休暇とは?福利厚生制度の一つとして企業向けに紹介
正社員登用制度
アルバイトで頑張ってくれる人に対して本人の希望を尊重し正社員へ登用する機会を与えることは、早期離職の抑止策にもなれば、自社への定着促進ひいては将来に向けた育成にもつながります。実際に、雇用形態問わず優秀な方は多く存在します。正社員の人手が足りない場合は、正社員登用制度を整備し、積極的に昇進させるのもよいかもしれません。キャリアパスを明確化させる意味でも、人手不足の解消、人材の定着を図るのに有効な対策だと考えます。
▶関連記事:正社員登用制度とは?企業が導入するメリットや注意点などを解説
職場での人手・人材不足を救った事例
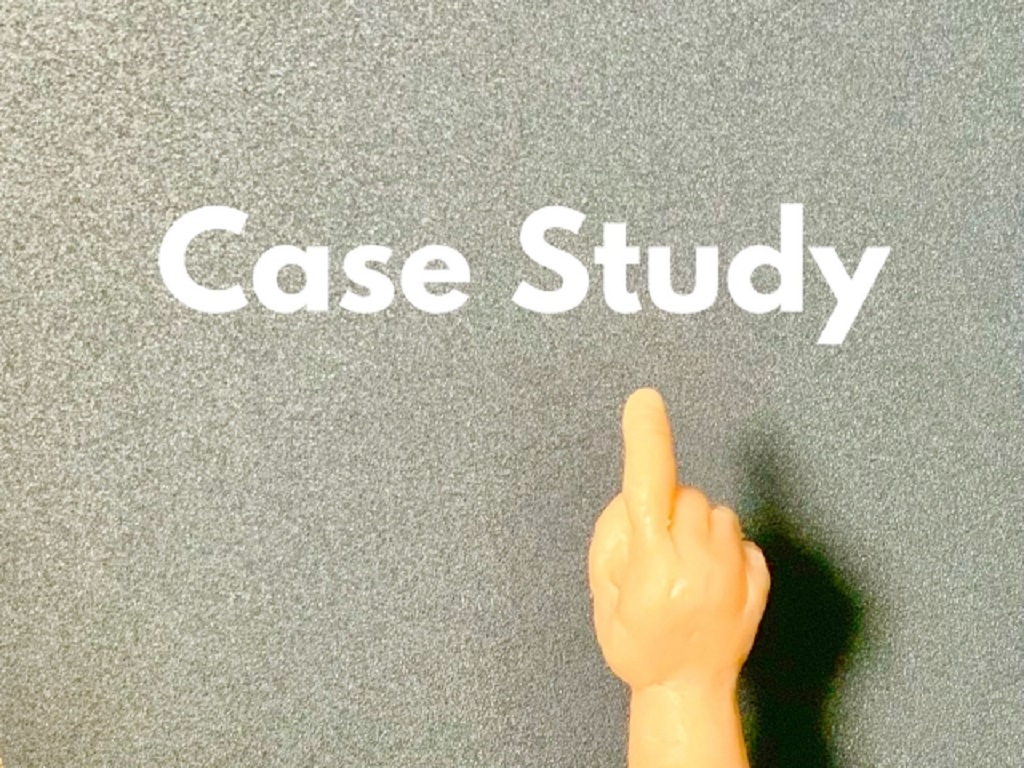
人手・人材不足に悩む企業は確かに年々増えています。その一方で解消につながった企業も少なくありません。下記にいくつか事例をピックアップ。貴社の課題と重なる部分があれば、ぜひ参考にしてみてください。
オンライン面接の見直しでミスマッチ減少!
労働者派遣事業を行っている株式会社グランド様は、ミスマッチ採用が続き人手・人材不足に直面していたため、ターゲットの拡大を遂行。そのうえで応募者の多様化に伴い、採用プロセスの改善に取り組むことに。そのなかでオンライン面接について見直しを図ります。具体的には応募者データのフォーマットを緻密に管理し、必要な情報を事前にインプット。これにより効率よく面接を実施できたといいます。結果、ミスマッチが減少。一方で応募の取りこぼしも問題だったため、タイムリーに面接日時設定できるツールを導入。応募者対応の自動化により生まれた時間を他の業務に振り分けられたことも収穫だったようです。
▶関連サービス:【公式】面接コボット – 応募者対応の自動化で面接管理が楽に!
長期掲載で応募数&定着率アップ!
クッキー販売のBen’s Cookies株式会社様は、以前の短期掲載では応募数がなかなか伸びず、定着率も芳しくなかったといいます。が、長期掲載に変えたことで、状況が一変。わかりやすく成果が出るようになります。なかでも志望理由に驚かれたようで、「Ben’s Cookiesで働きたいから」と明確に自社への愛着心を語る方が増えた模様。以降、採用基準も、長期的な視点に変え、原稿作成はdipに一任。「バイトル」「バイトルNEXT」それぞれのサービスを利用されています。
▶バイトル:【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
▶バイトルNEXT:【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
▶Ben’s Cookies Japan株式会社様の成功事例をもっとくわしく読む
多様な人材が活躍できる環境を整備!
株式会社物語コーポレーション様は、外食事業の直営による経営とフランチャイズチェーンを展開している会社です。経営戦略の中核にダイバーシティ&インクルージョンを掲げ、グローバル人材やセクシャルマイノリティ、障がい者雇用などに積極注力。年齢や立場にかかわらずチャレンジできる環境づくりに取り組んでいます。たとえば、アルバイト・パートでも主任や店長といった重要なポジションを任せる「役職パートナー制度」や、できたこと(スキルや業務)に対して評価としての“星”を与える「星制度」などのユニークな取り組みは、まさに象徴的です。こうした背景もあり、今日は、不足していたシニアや外国人など多様な人材が集まっています(シニアスタッフは約400名、インターナショナルスタッフは約600名)。とはいえ、まだまだ満足せず、さらに強化を図っていくといいます。
▶株式会社物語コーポレーションの成功事例をもっとくわしく読む
職場での人手・人材不足は丁寧に取り組むことが大事!

人手・人材不足の解消は、多くの企業が直面する喫緊の課題です。拙稿でも取り上げたとおり、その原因は採用面、定着面それぞれ多岐にわたります。止まらない少子高齢化、日々移り行く求職者ニーズ、他社との環境比較……等々、これらにどう対応していくかが、結局のところ解決の糸口です。たとえば、採用基準や採用手法の見直しが必要かもしれません。また、待遇・福利厚生も改善の余地があれば前向きに検討した方がよいでしょう。勤務形態を整備していくことも、急務でないにせよ考える局面にはいずれ出くわす可能性があります。さらには、抜本的な対策も戦略・戦術のなかに組み込めると安心でしょう。ダイバーシティ採用や障がい者雇用、リファラル採用、社内公募制度など、引き出しが増えればいざというときに頼りになります。もちろん、闇雲に手を出すことのリスクもケアしなければなりません。まずは求人のプロに相談してみることをおすすめします。あるいは他社の成功事例からも学べることは多いでしょう。自社の状況に合わせて応用していければ、なお望ましいと考えます。
いずれにしても、人手・人材不足の問題に対して真摯に向き合うことが肝要です。上述した内容をあらためておさらいしたうえで、活力あふれる組織づくりに邁進していきましょう。
▶関連記事:人、労働力が不足する原因と対策を業界の状況交えて解説
▶関連記事:人材・人手不足の解消方法とは?成功例と併せて具体的に解説
▶関連記事:人手不足の解決策を事例もヒントに解説!企業ができる取り組みとは?
求人掲載・採用業務のサポートや料金についてなど、ぜひ気軽にお問い合わせください。
また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談も無料で承っております!

