人員不足とは?
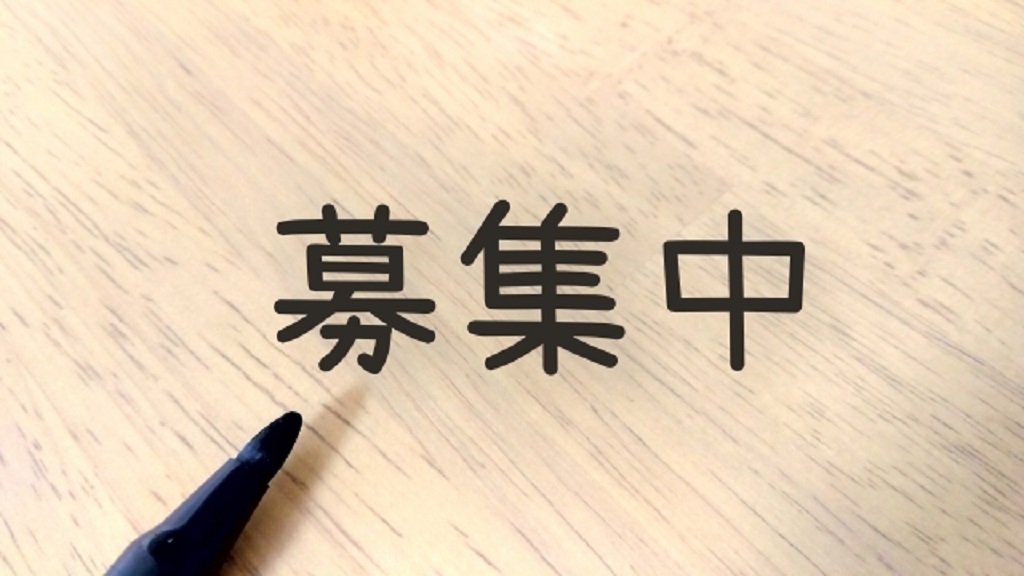
人員不足とは、業務を円滑に回すのに十分な従業員・スタッフの数を確保できない状態を指します。企業だけでなく、教育、医療、公共サービスなど、あらゆる組織や業界で見られる問題です。そもそも働ける人がいないため、その深刻さは後述する人材不足以上だといえます。一時的なものから長期的なものまで、その状況や度合いは区々です。
人材不足よりも深刻な人員不足
仮に人は足りても、スキルや経験が不十分であれば、なかなか戦力として数えるのは難しいかもしれません。この場合、いわゆる人材不足が起きています。これは「スキルギャップ」とも呼ばれ、特定の技術や知識を持つ人材が市場に存在しない、または求職者と求人者のマッチングがうまくいかないことが原因です。対して人員不足は、人数も確保できていない状況を指します。一人当たりの業務負担も大きいため、当然、パフォーマンスにも影響するはずです。組織全体が疲弊する悪循環を引き起こすことは、容易に想像できます。
人員不足に悩む企業は多い
冒頭でもお伝えしたように、人員不足に悩む企業は少なくありません。特に中小企業やスタートアップでは、そこかしこで悩み、嘆きの声を見聞きします。予算の制約が厳しかったり、ブランド認知がまだまだ低かったりすると、優秀な人材はおろか、不特定多数の人員さえ引きつけることが困難でしょう。もちろん、大企業でも組織の拡大や新規事業の立ち上げなど急に人が必要なケースはあります。その際、知名度が高いからといって、無策で募集をかけると痛い目に遭うでしょう。業界や職種によっては、企業規模問わず、(労働力人口の減少もあり)人員不足が常態化しているようにも見受けられます。
人員不足によって生じる問題
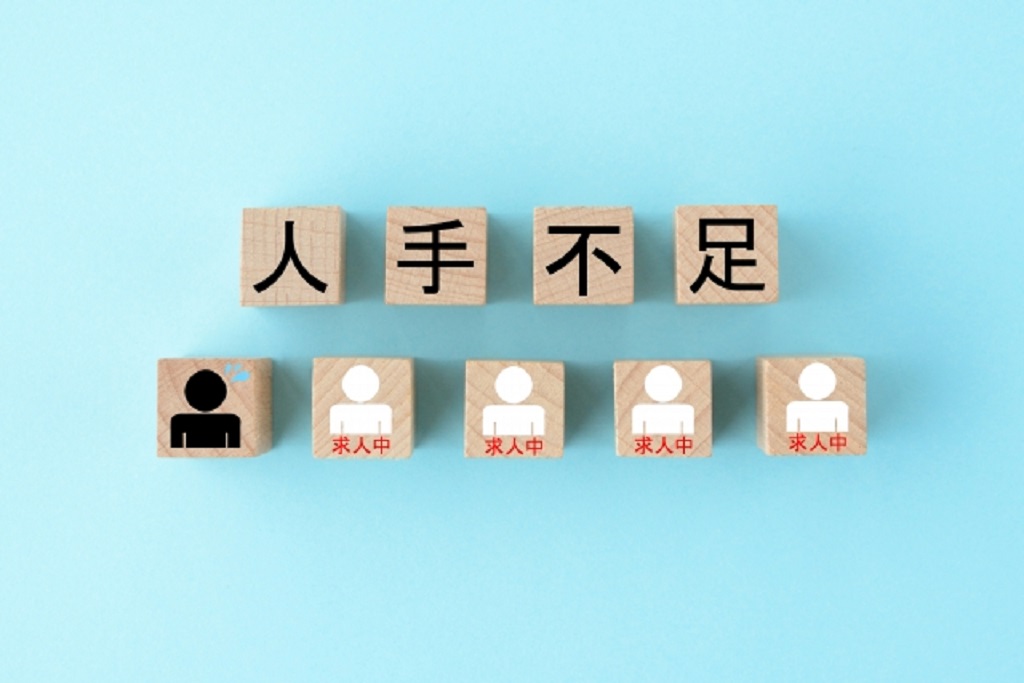
人員不足は、企業や組織にさまざまな問題をもたらします。具体的には次のとおりです。
- 生産性の低下
- サービスのクオリティ低下
- 従業員のモチベーション低下
- 採用コストの上昇
- 人手不足倒産
以下、それぞれ詳述します。
生産性の低下
人員不足が加速し続ければ、当然、一人当たりの業務負担も嵩みます。疲労も相まってパフォーマンスが下がることはいわずもがなです。人員配置を見直すにも、その場しのぎにしかならず、組織としての機能は望めないケースがほとんどだと考えます。結果、生産性の低下は免れないでしょう。
サービスのクオリティ低下
人員不足は、上述した一人にかかる負担や無理な配置転換などによってパフォーマンスに悪影響を及ぼす恐れがあります。それは、サポート対応や提供する商品・サービスの質にも関わることです。顧客満足度が下がるだけでなく、大きなミスやトラブルにも発展しかねません。その結果、企業イメージの悪化にもつながります。
従業員のモチベーション低下
人員不足による業務負担は、従業員のモチベーション低下にもつながります。過重労働やストレスで心身に支障をきたせば、なおさら大問題です。
採用コストの上昇
人員不足を解消しようと闇雲に採用活動を続けてしまっては、採用コストが増えるだけです。停滞する状況を打破するにはやはり、媒体選定や求人広告の書き方など、おさえておくべきセオリーやコツを適切なやり方で進める必要があります。
人手不足倒産
深刻な人員不足は、最悪の場合、廃業・倒産を招く恐れがあります。いわゆる人手不足倒産です。帝国データバンクの調査記事からも増加傾向は一目瞭然。決して、一部の企業だけの話ではなく、どこでも起き得る問題だと考えます。
人員不足に直面する組織の課題

人員不足に直面する組織は、さまざまな課題に取り組む必要があります。具体的には次のとおりです。
- 事業の継続
- 組織デザインの更新
- 採用プロセスの効率化
以下、それぞれ詳述します。
事業の継続
人員不足により、「納期が遅れる」「品質が低下する」「受注に対応できない」など、事業運営に支障をきたせば、企業の存続自体が危ぶまれます。特に、専門性や技術力が問われる現場では一人抜けるだけでも痛手になりやすく、連鎖退職が起きればたちまち人員不足になりかねません。こうしたケースも考慮しつつ、組織が崩壊しないよういかに事業を継続させていくかは、常日頃、課題あるいは戦略として持っておく必要があります。
組織デザインの更新
組織デザインとは、チーム体制、役割、責任、プロセス、報酬システムなどを、(組織が掲げる)目標の達成につなげるために再整備することです。このフレームワークがうまくはまれば、従業員の能力最大化、あるいは満足度向上につながります。しからば人員不足に堕する事態を招かずに済むかもしれません。そう考えると、組織デザインの更新は、紛うことなく企業が向き合うべき課題だといえます。
▶関連記事:組織デザインとは?人事担当者が押さえるべきポイントを解説
採用プロセスの効率化
採用プロセスの効率化もまた、人員不足に陥らないための課題として不可欠です。状況に応じて、媒体選定やプラン設定から見直す必要もあるでしょう。応募管理、内定者フォローも、ほかの業務との兼ね合いで疎かにならないよう気を付けなければなりません。
人員不足が深刻な業界

人員不足は業界によってその度合いは異なります。では、実際に深刻化している業界はどこなのでしょう。以下、アルバイト・パートと正社員で分けて説明します。
アルバイト・パートの人員不足に悩む業界
飲食業界、コンビニやスーパーなどの小売系業界、介護業界などでは、アルバイト・パート採用の有効求人倍率が高いことからも人員不足の深刻さがうかがえます。特に繁忙期がはっきりしていると、書き入れ時にもかかわらず不安が背中合わせでついてきます。というのも、スタッフが足りないばっかりにイベントの開催やお店の営業を断念せざるを得ない事態になる恐れがあるからです。そうならないよう、どうしたって人手は確保しておかなければなりません。また、上記に挙げた業界はどうしても深夜や早朝勤務も多く、なかなか今の時代の働き方に合っているとは言い難い部分もあります。学生、フリーターなどタイムパフォーマンスを重視する向きが多い昨今、業界全体で見直していかなければ、シフトの融通が利かないイメージを理由に、応募から遠ざかる求職者は増え続けることになるでしょう。
▶関連記事:最新!アルバイト・パートの有効求人倍率(エリア・職種別あり)
正社員の人員不足に悩む業界
たとえば、建設、製造、介護などの業界は専門性や経験値の高さを必要とすることが多いため、正社員採用の成否が二極化しているように思います。これは、採用要件の設定も含めてプロフェッショナル人材を確保する難しさを物語っています。教師・医師を含めた士業も同様です。これらの業界で人員不足を解消していくには、やはり媒体選定から自社の業界に特化したサービスを見極めていくことが求められます。たとえば軽作業・物流業界なら「バイトルNEXT」、有資格者を集めたいなら「バイトルPRO」といった具合です。
▶関連記事:最新!社員の有効求人倍率(エリア・職種別あり)
人員不足の業界にみられる傾向
人員不足の業界にはいくつかの共通した傾向が見られます。少子高齢化の進行に伴い労働力人口が減少し、新たな労働者の確保が難しくなるのはどの業界も抱えている問題ですが、そのなかでも介護や医療、建設業などの現場では特に顕著です。スキルや経験を要する仕事だけあって、ただでさえ要件を満たす人材は限られます。そこに世相が加わるわけです。実際、若年層の就業者が減少し、高齢の労働者に依存するケースは増えています。さらにこれらの業界では、給与や労働条件が他業種に比べて厳しいことが多く(あるいはイメージが強く)、なかなか人が集まりません。たとえうまく採用できたとしても、今度は早期離職の問題が浮上してきます。これでは慢性的な人員不足は解消されません。つまるところ、プロフェショナル人材が求められ、イメージ改善や働きやすい環境作りが急務な業界ほど、人員不足に陥りやすいといえそうです。
なぜ、人員不足が起きるのか?
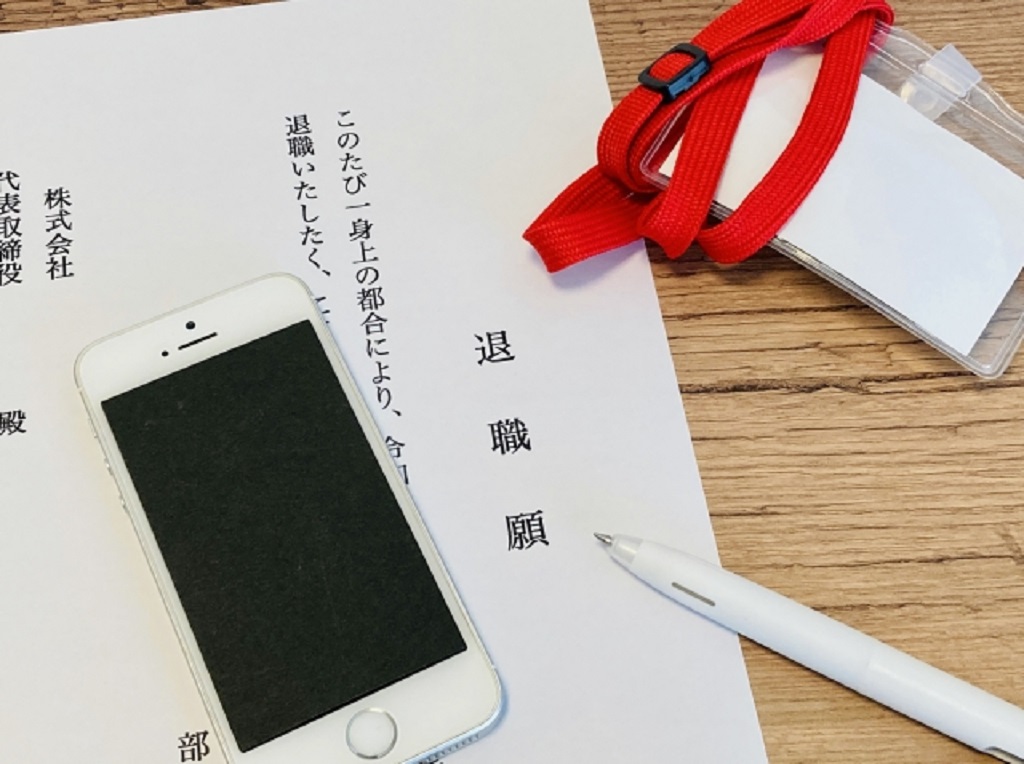
人員不足が起きる原因は、大きく分けて3つあります。具体的には次のとおりです。
- 採用がうまくいかない
- 採用しても定着しない
- 他社と比較されている
さらにはこれらも一つずつ紐解くと、要因は複雑に絡んでいることがわかります。以下、それぞれ詳述します。
採用がうまくいかない
採用がうまくいかなければ人員は揃いません。そもそも応募自体、集まっていないケースも人員不足に悩む企業ではしばしば見受けられます。ではなぜ、うまくいかないのか。一つは前述した「労働力人口が減っている」が挙げられます。加えて、「求人広告で訴求できていない」ことも起因しているでしょう。
労働力人口が減っている
総務省の調査によると少子高齢化の進行により、日国の生産年齢人口(15~64歳)は1995年を境に減少しています。この傾向は加速し続け、2050年には5,275万人(2021年から29.2%減)になる見込みです。
労働力人口が減ると、求人(売り手)と求職者(買い手)のバランスは崩れていきます。採用市況での影響は明らかです。
求人広告で訴求できていない
採用がうまくいかない場合は、求人広告にも目を向けましょう。採用ターゲットのニーズに合った魅力的な求人広告を作成できれば、そうでない場合と比べて、大なり小なり、(求職者の)興味・関心を引けるかもしれません。逆にいうと、ここを疎かにし訴求力の低い求人広告を出してしまうと、応募者数はなかなか伸びてこないでしょう。
採用しても定着しない
早期離職も人員不足を招く大きな原因の一つです。これは、そもそもミスマッチ人材を採用してしまったり、あるいは人材育成の環境が整備されていなかったりと、雇う側のスタンスや体制に問題があります。コストの増大だけでなく、既存従業員のモチベーション低下や企業イメージの悪化にもつながりかねません。そう、採用後こそ肝心なのです。
ミスマッチ人材を採用している
慌てて採用してしまうと、企業が求めるスキルや要件にズレが生じることは往々にしてあります。ミスマッチは採用された側にとっても不幸です。結果、早期離職につながるケースがほとんどといってもよいでしょう。定着率が低ければ、どれだけ採用しても人員不足の穴は埋められません。
人材育成の環境が整備されていない
教育体制やスキルアップの機会が設けられていなければ、新入社員の成長が望めず、組織としてのパフォーマンスも低調になってしまうかもしれません。それ以前に従業員自身、キャリアパスの道筋が見えずにやる気を失い離職に至る可能性が大いに出てきます。人材育成の失敗は、とりもなおさず人材流出のリスクを生むといっても過言ではないでしょう。
他社と比較されている
人員不足が起きている背景には、他社と比べられていることもあるでしょう。「待遇」「福利厚生」「労働環境」「職場の雰囲気」など、求職者はさまざまな観点で他社と比較しています。以下、それらを深堀りします。
他社の待遇・福利厚生が魅力的
求職者のほとんどは、とりあえず複数の企業に応募しています。選考を進めていくなかで絞り込んでいくわけですが、そこでポイントになるのが待遇や福利厚生です。他社と比較し、魅力的に映ればそちらに流れるのが自然でしょう。なお、これは既存の従業員に対してもいえます。今いるメンバーで正当に評価されないと感じている方が、他社からよい条件のオファーをもらえば、そちらになびくのはやはり当然の因果でしょう。
他社の労働環境が魅力的
他社と比較されるのは、給与や福利厚生だけに留まりません。労働環境を重視される方も多くいらっしゃいます。たとえば、リモートワークやフレキシブルな勤務形態など、要望に応じてもらえるかどうかは、人によっては待遇以上に大事なことかもしれません。
他社の雰囲気が魅力的
職場の雰囲気にすぐに慣れるかどうかも、求職者が気にするポイントです。にもかかわらず、自社の求人広告で職場の様子をうまく伝えていないケースもしばしば目にします。他方、動画コンテンツなどを駆使し、リアルな現場の魅力を明確に表現している企業が存在するのも確かです。両者を比較したとき、後者に軍配が上がることは容易に想像できます。
人員不足を打開する策はあるのか?

ここまで人員不足に陥るいわばメカニズムをお伝えしてきましたが、この悪しき事態を打ち破る方法は果たしてあるのでしょうか。
確かに一つの策に固執してもなかなかすぐに結果は出ないかもしれません。が、さまざまな取り組みを適材適所で試すことで、状況が一変する可能性は大いにあります。本章で取り上げるいくつかの対策も同様です。その期待に沿うだけのポテンシャルは十分にあると考えます。というわけで、人員不足の主な打開策は次のとおりです。
- ハイブリッドワーク(勤務)への切り替え
- ダイバーシティ採用に注力
- 求人広告の書き方や見せ方を工夫
- 社内公募制度の導入
- カルチャーフィットを重視した採用
- スキルアッププログラムの提供
- メンタリングの実施
- 給与体系の再構築
- オフィス環境の改善
- ワークライフバランスの促進
- 企業風土の改革
- 求人・採用サービス、プランの見直し
以下、それぞれ詳述します。
ハイブリッドワーク(勤務)への切り替え
リモートワークとオフィス出勤を組み合わせた勤務形態がハイブリッドワークです。これを導入することで、従業員の働き方に柔軟さが生まれます。勤務場所が会社内外のどちらかに縛られないことで、彼・彼女らの心の余裕にもつながるはずです。結果、定着率向上が期待できるかもしれません。
▶関連記事:ハイブリッドワーク(勤務)とは?デメリットや課題についても解説
ダイバーシティ採用に注力
シニア、外国人、高校生など、一昔前なら採用に躊躇していただろう属性に対してもシームレスに求人の間口を広げることで、人員不足を免れるかもしれません。と同時に、多様性ゆえに多角的な視点、価値観が自社内に浸透し、組織の活性化にもつながる期待が持てます。
▶関連記事:ダイバーシティ採用とは?企業の取り組み事例やアンケート調査の結果も交えて解説
求人広告の書き方や見せ方を工夫
求人広告の書き方や見せ方をちょっと工夫するだけで応募数が劇的に変わるかもしれません。というのも、セオリーに沿っていなかったり、求職者の視点を蔑ろにしていたりと、基本ができていない求人は思いのほか多く見受けられます。改善の余地が多ければ、その分、成果を生む可能性も広がります。いずれにしても、どうすれば訴求力が高い求人広告を作成できるのか。そこに真摯に向き合うことが、人員不足を食い止めるためには肝要です。
▶関連記事:求人広告の書き方を例・テンプレートを交えて解説。応募を集める求人とは?
社内公募制度の導入
既存従業員に目を向け、希望を募り配置転換を行うことも、人員不足の解消に使える一つの手です。そう、いわゆる社内公募制度の導入がそれに当たります。従業員のモチベーション向上はもちろん、組織パフォーマンスの最大化も期待できます。
▶関連記事:社内公募制度とは?流れや面接方法、メリット・デメリットなど解説
カルチャーフィットを重視した採用
企業文化や価値観に合う人物を採用することで、定着率の向上が図れます。カルチャーフィットは、近年ますます重視されている概念です。スキルを要する仕事内容ではなかなか決断が難しいかもしれませんが、育成も踏まえた長期的な視点で考えたとき、目の前の人員不足を解消する以上の意味があるかもしれません。
スキルアッププログラムの提供
定着率を上げるには、従業員のスキルアップや成長は積極的にサポートしたいところです。具体的なプログラムとしては、外部遠征も含めた定期的な研修の実施や資格取得の支援などが該当します。
メンタリングの実施
入社したばかりの従業員は慣れない時期は不安な気持ちで過ごす方がほとんどです。扱いを間違えるとたちまち早期離職につながります。その前提を踏まえて、メンター制度の導入が必要です。これは、豊富な知識と経験を有した社内の先輩(メンター)が、後輩(メンティ) に対して行います。キャリアを形成するうえで必要なサポートだけでなく、メンティが自発的に悩みを相談してくれる関係構築も大事です。
給与体系の再構築
給与体系に不満を覚え離職、あるいは魅力が感じられないことを理由に応募に至らないケースはそこかしこで見受けられます。ここを再構築できるかどうかは、求職者や従業員の目線では、もっともインパクトがある施策かもしれません。とはいえ、ただ闇雲に上げるのは悪手です。他社や業界水準を考慮し、慎重に見直しを図りましょう。
▶関連記事:アルバイト・パートの昇給について時給アップの事例も交えて解説
オフィス環境の改善
快適で働きやすいオフィス環境を整備することは、従業員の満足度と生産性の向上につながります。その様子や状況が拡散されれば、認知度にも影響するかもしれません。そうなると採用に寄与する期待も持てるでしょう。人間工学に基づいたオフィス設計やコミュニケーションスペースの設置など、改善の余地があれば、前向きに検討することをおすすめします。
ワークライフバランスの促進
仕事と生活の両立が難しいことを理由に離職される方も少なくありません。彼・彼女らのそうした悩みを解決すべく、ワークライフバランスの実現に向けた制度や取り組みが必要です。具体的には、フレックスタイム制や休暇取得の促進などが挙げられます。
企業風土の改革
人員不足を解消するには、何かを変えなければなりません。企業風土もまたその対象の一つです。そもそも確立できていない企業も多く見受けられます。経営理念の浸透、社内コミュニケーションの活性化、従業員の自律性に対する尊重……等々、共通の価値観で求職者に訴求できるカラー、カルチャーを形成することは、(人を惹きつけて離さない)エンゲージメントを高めていくのに少なからず役立つはずです。
求人・採用サービス、プランの見直し
いま利用しているサービスやプランを変えることで求人・採用がうまくいくことがあります。そもそも、採用目的やターゲットから見直さなければならないかもしれません。そのうえでどのサービスが適切か。状況によっては、一つのサービスに固執しているがゆえの停滞も考えられます。この場合、複数のサービスを組み合わせて使うことも選択肢に入れられるとよいでしょう。
以下、dipが提供する求人・採用サービスです。
▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能
┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。
▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら
┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。
▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!
┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。
▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!
┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。
▶【公式】コボット – 人事業務を手軽に効率化!採用DXサービス
┗応募獲得、応募者管理に悩む企業に向けて開発された採用DXサービスです。『面接コボット』と『採用ページコボット』がラインナップされています。
料金表付きの資料も用意しています。無料でダウンロード可能です。
不足する人員を獲得できた成功事例

人員不足を解消するには前述した施策の実施に加えて、他社の成功体験を参考にすることも大切です。以下、dipのお客様の事例をいくつか紹介します。それぞれの取り組み、サービス活用例のなかには、多くのヒントがあるはずです。
初めての有料媒体で満足度の高い結果に!
有限会社エーティーアーク様は、社員採用に強い『バイトルNEXT』と、自社で保有する採用メディアの作成が可能な『採用ページコボット』を導入。成果は早々に生まれます。利用開始後数ヶ月で複数名を採用。サービスの特性もさることながら、業界未経験の方でも応募しやすい原稿づくりや、作業中の写真・動画を積極的に掲載するなど、随所に工夫を凝らしたことが結果につながったといいます。
苦戦していた欠員補充がスピーディーに実現!
おそばの樹なり様は、2023年3月に柏市でお店をオープン。欠員補充のために最初は他社媒体で求人を出していたようですが反応がなく思い切ってサービス変更に踏み切ります。導入したのは『バイトル』です。すると導入後3週間で60件もの応募を獲得。そのままスピーディーかつスムーズに採用までこぎ着けたといいます。
採用だけでなく定着率も改善!
南州環境開発株式会社様は、これまでは業界経験者のみを採用していましたが、定着率の低さが大きな問題でした。が、人員不足に悩むなか、いよいよ未経験者もターゲットに含めることに。そこで使ったサービスが『バイトルNEXT』です。一方で必要な免許を持った方に向けては『バイトルPRO』を利用します。このようにサービスを使い分けたことが功を奏したのか、応募は増え、人員獲得も成功。懸念していた業界未経験者の採用については、教育体制を整備するよい機会になったといい、結果、定着率も向上したようです。
人員不足とどう向き合っていくべきか?

人員不足は、多くの企業が直面する普遍的な問題です。少子高齢化が進むなか、労働力人口の減少はどうしたって避けられません。たとえ今は人員不足に悩んでいなくても、いずれは向き合わざるを得ない状況と化す可能性は大いにあります。
と、重要なのはやはり、人員不足を自社の問題として真摯に受け止め、持続的な解決方法を模索することです。組織全体で課題意識を共有し、採用、育成、定着、組織風土など、さまざまな観点から打開策を検討する必要があります。そしてこれは、いわば業界全体のミッションです。同業他社との連携や、行政との協働など、オープンイノベーションの視点も不可欠だといえます。
人員不足は、決して一朝一夕で解消できるものではありません。が、いくら難題でも、変化を恐れず立ち向かうことで道は開けるはずです。拙稿で述べた対策や、取り上げた事例がそれを伝えています。とにもかくにも人員不足という逆境を、組織を変革するチャンスと捉え、前向きに取り組んでいきましょう。
求人掲載・採用業務のサポートや料金についてなど、ぜひ気軽にお問い合わせください。
また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談も無料で承っております!

